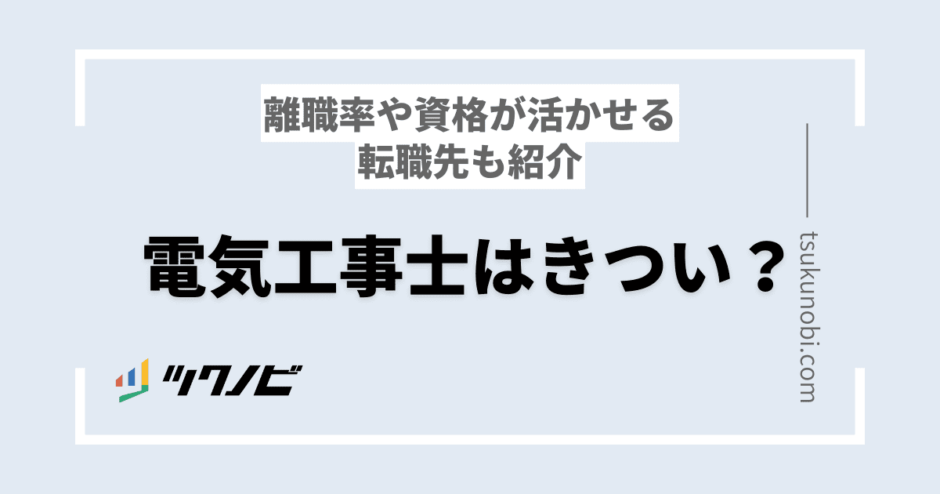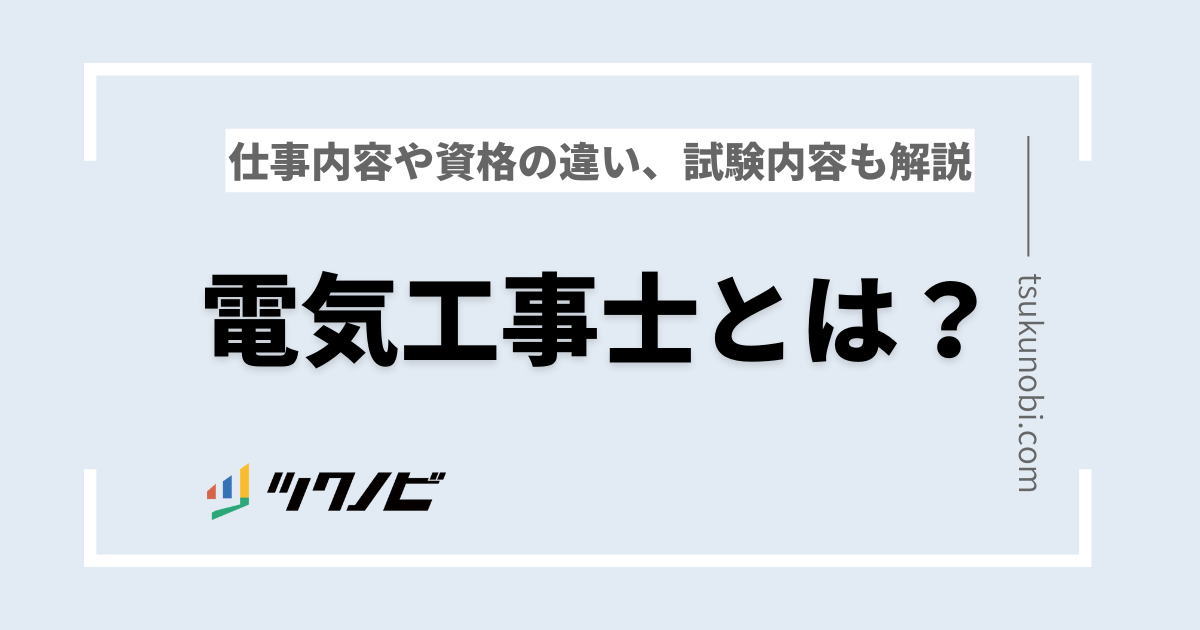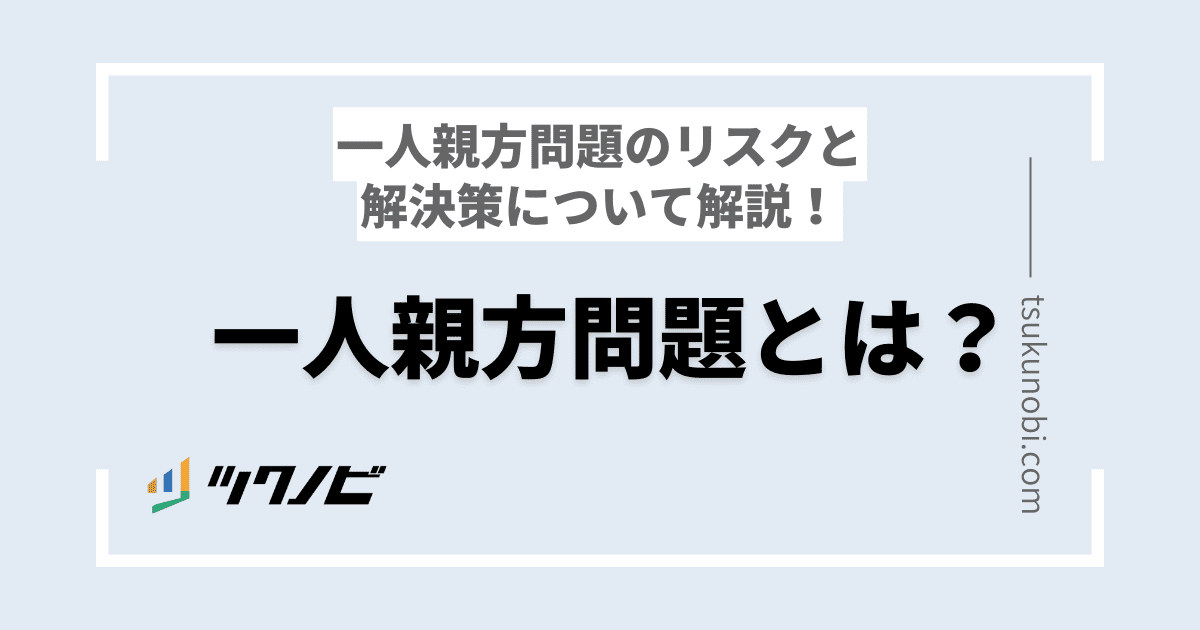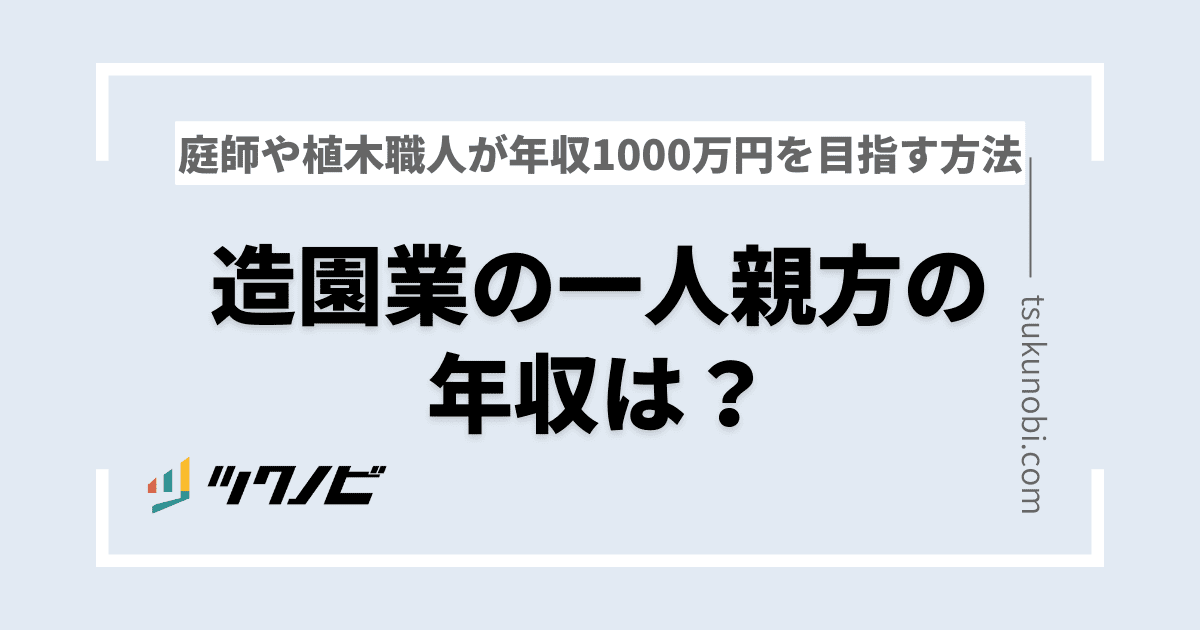※記事内に広告を含みます
電気工事士の仕事は精神的・体力的に厳しいと考える人が多いでしょう。
しかし、これから電気工事士として就職・転職を考えている方は、「本当にしんどいのか?」と疑問を持っているかもしれません。
電気工事士は今は辛くても、乗り越えられます。
この記事では、電気工事士の仕事がなぜやめとけと言われるのか、電気工事士の資格を取得するメリットやその資格を活かせる仕事について説明し、電気工事士に合っている人と合わない人についても紹介します。
電気工事士がやめとけと言われる4つの理由
電気工事士は、「仕事がしんどいからやめとけ」と言われています。つまり、働き方がブラックで仕事内容や人間関係、金銭的にしんどい仕事とされています。
電気工事の業界に、ブラック企業がないとは言い切れません。
しかし、ブラック企業が多いわけではなく、電気工事士という職業自体がしんどい仕事です。
電気工事士という仕事がしんどいからやめとけと言われる理由は、次の3つです。
- 勤務時間が不規則
- 肉体労働なため体力的にきつい
- 一人前になるまでは年収が低い
- 資格取得が難しい
勤務時間が不規則
電気工事士は、現場に出向いて仕事をすることが多い職業です。
現場への移動には時間がかかり、現場の状況によって仕事が遅くなることも珍しくありません。休日にも仕事が入ることがあり、見習い期間には、不規則な勤務時間を理由にやめる人が多いです。
働き方改革や残業時間の規制により、10年前よりも働く環境は良くなりましたが、個人の電気店や中小企業で、なかなか労働時間について改善されていないことがあります。
電気工事士として働く方は、就職の際は勤務形態について事前に調べておきましょう。
参考:電気工事士の残業や勤務時間は?求人をチェックする際のポイントも解説|工事士.com
肉体労働なため体力的にきつい
電気工事士は屋外作業が多く、夏と冬は厳しい暑さと寒さの中で仕事をする必要があります。
また、荷物の運搬や高所作業など、力仕事だけでなく体力が必要な場面もあります。
電気工事士は電気を扱うために危険が伴いますが、肉体労働による怪我があるのも、やめとけと言われる理由の一つです。
加えて、休憩時間は設けられていますが、長時間立ちっぱなしで仕事をしないといけません。
したがって、体力や力仕事に自信がない方は向いていないでしょう。
一人前になるまでは年収が低い
電気工事士には2〜3年の見習い期間があり、その間の給料が低いことがやめとけといわれる理由の一つです。見習い期間の年収は300万円ほどとされています。
しかし、資格取得や経験を積んで独立するなどの方法を取ることで年収を上げることができます。
具体的には、ボイラー技士電験三種、第一種電気工事士などの資格を取得して経験を積んで独立するなどがあります。
これらの方法によって資格手当やキャリアアップを実現し、年収アップが可能です。
電気工事士が年収をアップさせる方法は、こちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
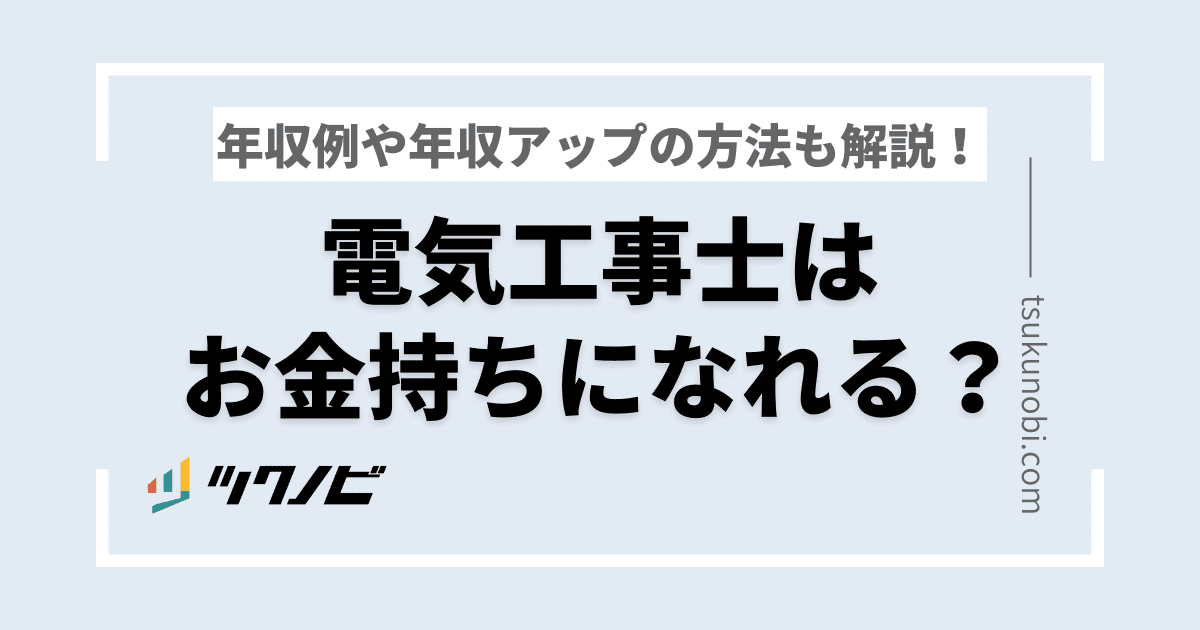 電気工事士はお金持ちになれる?年収例や年収アップの方法も解説
電気工事士はお金持ちになれる?年収例や年収アップの方法も解説
資格取得が難しい
電気工事士は資格の取得が必要です。そして、こちらの資格取得が難しいことも、電気工事士はやめとけと言われる理由の一つです。
一般社団法人電気技術者試験センターの発表によると、令和3年から令和5年の第一種電気工事士上期学科試験および上期技能試験の合格率は以下表の通りです。
令和3年から令和5年の第一種電気工事士上期学科試験・上期技能試験の合格率の推移
| 上期学科試験の合格率 | 上期技能試験の合格率 | |
| 令和3年全国合計 | 53.5% | 67.0% |
| 令和4年全国合計 | 58.2% | 62.7% |
| 令和5年全国合計 | 61.6% | 60.6% |
参照:「一般財団法人 電気技術者試験センター」の「令和5年度第一種電気工事士学科試験の結果について」および「令和5年度第一種電気工事士技能試験の結果について」
令和3年から令和5年の第二種電気工事士上期学科試験・上期技能試験の合格率の推移
| 上期学科試験の合格率 | 上期技能試験の合格率 | |
| 令和3年全国合計 | 60.4% | 74.2% |
| 令和4年全国合計 | 58.2% | 74.3% |
| 令和5年全国合計 | 59.9% | 73.2% |
参照:「一般財団法人 電気技術者試験センター」の「令和5年度第二種電気工事士上期学科試験の結果について」および「令和5年度第二種電気工事士上期技能試験の結果について」
ご覧のように第一種電気工事士・第二種電気工事士どちらも学科試験の合格率は50〜60%です。望みの薄い数値とは言えませんが、約半数が落ちていると考えると油断できません。
また、電気工事士資格の取得には、技能試験に合格する必要もあります。合格率を見ても、第一種電気工事士資格試験の方が難易度は高いと言えます。
電気工事士になることのメリット
電気工事士は働き方や金銭状況などからやめとけと言われる職業ですが、しんどい面だけでもありません。
電気工事士は、不安定な雇用に怯える必要もなくキャリアを積み上げられるといった、メリットもあります。
電気工事士として働く主なメリットは、次の3つです。
- 仕事に困ることが無い
- 社会的信用度が高い
- 資格手当がつく場合がある
仕事に困ることが無い
電気工事士の仕事は、人間の生活に欠かせません。そのため、需要も無くならないと考えられています。将来性もある職業です。
また、電気工事士は慢性的な人材不足の傾向もあるため、安定して働きたい人にとって、メリットとなります。さらに、電気工事士は建築や産業プロジェクトなど、様々な分野で活躍することも可能です。
社会的信用度が高い
電気工事士には、資格を持っていることで扱える独占業務が存在します。そのため、電気工事は資格を持っている人のみ扱える仕事と言えます。
さらに、電気工事士の資格は国家資格なので、社会的信用度が高い点もメリットです。
また、資格を持っていることは、知識や技術があることの証明にもなります。転職や独立時は有利に働きます。
資格手当がつく場合がある
勤める企業によっては、電気工事士の資格を持っていることで、資格手当を受けられる場合もあります。手当の金額は企業により異なりますが、収入アップに繋がることは間違いありません。
また、第二種電気工事士より第一種電気工事士の方が、手当も上がりやすいです。求人票に資格手当が記載されている場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
電気工事士の離職率はどのくらい?
電気工事業界に入った新人のうち、3年以内に離職する割合が高く、全業界でやや高めの40%と報告されています。離職の理由としては、OJT(実地研修)の不足や休暇日数の少なさ、劣悪な勤務環境などが挙げられています。
現在の電気工事業界では、工業高校卒業生がほぼ50%を占めており、中途採用や他業種からの採用はほとんど行われていません。
工業高校生の数が減少していく中、長期的には電気工事士の数も減少することが予想されています。
それに加えて、離職率が高いため電気工事士が不足すると、残っている人たちの業務量が増え、更に離職率が高くなるという悪循環が起こり、電気工事士の不足は加速するでしょう。
電気工事士の人手不足については、こちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
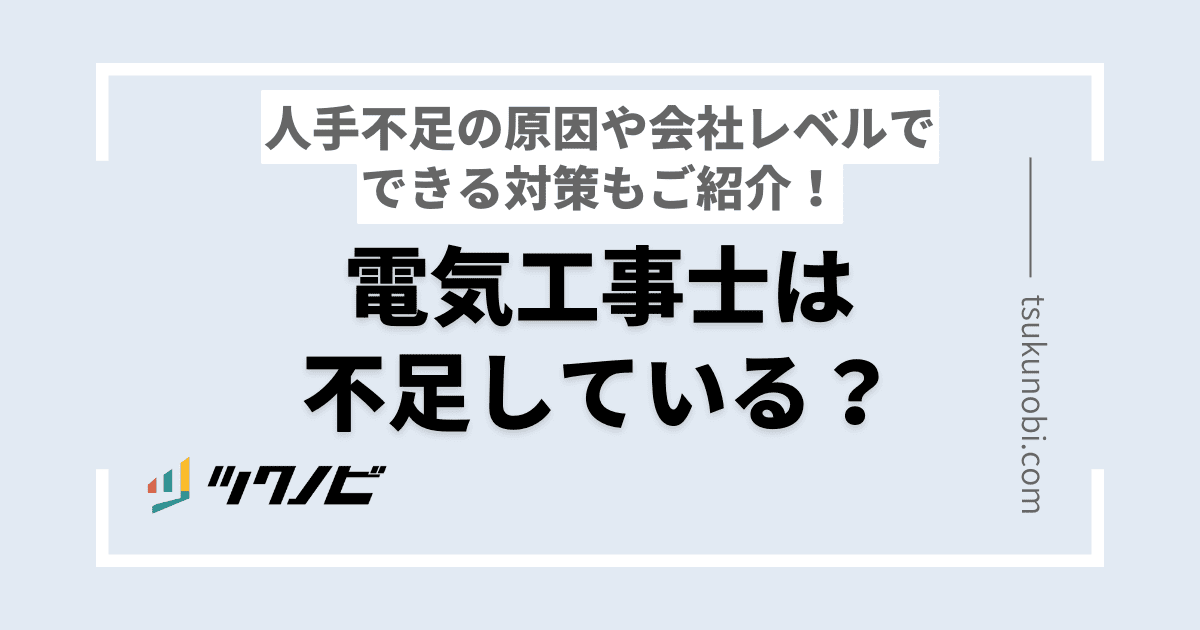 電気工事士の人手不足の原因は?対処法もご紹介!
電気工事士の人手不足の原因は?対処法もご紹介!
電気工事士が向いている人の特徴
見習いの期間は年収が少ないうえに、体力仕事や力仕事が多い職業なので、辛く感じる人も多いでしょう。
一方で電気工事士という仕事自体がしんどいと言われていますが、そのうえで楽しく仕事を続けられる人もいます。
電気工事士の仕事に向いている人の特徴は、次の3つです。
- モノ作りが得意
- コツコツと継続ができる人
- 体を動かして仕事をしたい人
電気工事士を目指している人は、自分と照らし合わせて確認してみてください。
こちらの記事では、電気工事士とは何かについて解説しています。
モノ作りが得意
電気工事士はモノ作りが得意・好きな人に向いている職業です。
というのも、何かを作る人は物を作る過程や完成する瞬間に、達成感を感じる傾向があるからです。たとえば、とくにDIYや建築などの施工が好きな人は電気工事士に向いているでしょう。
他にも、施工に関わらずモノ作り自体が好きな人にも向いています。何かを作り上げることに魅力を感じる人にとって、電気工事士はおすすめの職業です。
モノ作りにおいて手が器用でないと電気工事士になれないわけではなく、現場の立ち回りでカバーできる場合が多いので、器用さは重要ではありません。
コツコツと継続ができる人
電気工事士の仕事には、一日中地味な作業を繰り返すものもあります。とくに見習い期間は、地道な作業を繰り返すことが多いです。
それでも必要不可欠な仕事として、責任感を持って地道にコツコツと取り組まないといけません。コミュニケーション能力も重要ですが、一人で作業することも多いので一人で黙々と細かい作業に没頭できる人に適しているといえるでしょう。
一方で、飽きっぽい性格の人や、より刺激的な仕事を求める人には向いていません。
体を動かして仕事をしたい人
地道な作業を繰り返すこともありますが、基本的には身体を使う肉体労働です。そのため、体を動かすことが好きな人にとっては理想的な仕事でしょう。
机に向かって一日中仕事をするよりも、体を動かす仕事が好きな人にはおすすめです。
また、学生時代にスポーツに打ち込んだ人は体力的にも向いているといえます。しかし、体力に自信がない人でも、仕事をしていれば慣れるので必ず体力がいるわけではありません。あくまで、向いているというだけです。
電気工事士が向いていない人の特徴
コツコツと仕事を継続して行える忍耐強さや力仕事、体力仕事が得意な人に向いています。他にも、モノ作りが好きな人も向いていると言えるでしょう。
一方で、電気工事士が向いていない人もいます。電気工事士が向いていない人の特徴は、次の3つです。
- 継続することが苦手
- 指示通りに遂行するのが苦手
- 人とのコミュニケーションが苦手
電気工事士はきつい仕事で、入社後に「想像していたのと違った」と後悔しないためにも、目指している人は事前に確認してみましょう。
継続することが苦手
電気工事士になるためには、努力が必要であることは間違いありません。この職業には、経験と技術を身につけるために失敗や経験が不可欠です。
失敗を重ねながらも、成長していくことができる人は向いていますが、努力が苦手な人は電気工事士として働くことの、現実と理想のギャップに落ち込んでしまう可能性があります。
失敗を繰り返しながら成長することができない人や、指導を受けることが苦手な人は、電気工事士に向いていないといえるでしょう。
指示通りに遂行するのが苦手
電気工事士には、指示に従って正確に作業を行う能力が求められます。
自己判断で作業を進めてしまうと、施工不良になる可能性があるため、図面や指示書をよく読み込み、正確に作業を行う必要があります。
見習いの時期は仕事に慣れていないため、指示通りに仕事を遂行しないと危険が伴います。
周囲との信頼関係も重要であり、自己判断で作業を行うと周囲から不信感を抱かれることがあるため、指示通りに作業を進める能力は必要でしょう。
人とのコミュニケーションが苦手
電気工事士は、人間関係が重要であり、仕事の中でのコミュニケーションや協調性が求められます。また、肉体労働が中心であり、高所作業や屋外作業が必要な場合もあります。
つまり、電気工事士の仕事は、体力や力仕事にくわえてコミュニケーション能力と協調性が求められます。
そのため、仕事の正確性を気にせず仕事をしたい人やコミュニケーションをとって協調性を出すのが苦手な人には向いていません。しかし、コミュニケーション能力や協調性は仕事をしていくなかで学べるので、今ないからといって諦める必要はないでしょう。
電気工事士の資格が活かせる仕事
電気工事士の資格を使ってできる仕事は、次の3つです。
・ビルメンテナンス
・電気主任技術者
・サービスエンジニア
ビル内の電気設備や水道設備、エレベーター、ボイラーなどの点検や管理、医療・セキュリティ機器等の専門的な機械の修理など、電気工事士の資格はさまざまな分野で活かすことが可能です。
しかし、それぞれで必要な電気工事士の資格が異なります。ここでは、それぞれの仕事について必要な資格と仕事内容の概要を解説します。
ビルメンテナンス
ビルメンテナンスは通称「ビルメン」と呼ばれており、ビルや建物の設備・管理を行う仕事です。
電気設備や水道設備、エレベーター、ボイラー等の点検・管理を担当します。そのため、電気工事士以外の資格も必要となります。
例えば、ボイラー技士や危険物取扱者、第三種冷凍機械責任者の資格が必要です。消防設備の点検については、消防設備士の資格を取得した方がよいでしょう。
ビルメンテナンス業務は、設備の点検やトラブル解決などで、日々新しい問題に直面することが多いため、多くの資格を持っていると融通が利きます。
電気主任技術者
電気工事士の資格は、電気主任技術者の仕事でも役立ちますが、点検作業には電験三種以上の資格が必要です。電気主任技術者は、保安・管理を中心に行う資格で、電気工事には携われません。
しかし、点検時に電気設備の不良箇所を発見して、修理する場合には電気工事士の資格が要ります。
電気工事士の資格を取得することで、電気主任技術者として直接働くことはできませんが、2つ資格を取得することで、より幅広い仕事に携わることができます。
サービスエンジニア
サービスエンジニアは、専門的な機械や機器について故障が生じた際に修理やメンテナンスを担当する技術者のことです。例えば、医療機器、セキュリティ機器、コンピューターハードウェア、通信機器等が該当します。このような機械や機器は、一般的な家庭用品と異なり、専門的な知識が必要です。
したがって、サービスエンジニアになるためには第二種電気工事士の資格が必要になります。第二種電気工事士は、主に住宅・ビルなどで行われる簡単な電気工事ができる資格です。
建設業に強い求人サイトはこちらの記事で紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。
 建設業に強い求人サイト18選!種類や効果的に活用するポイントを解説
建設業に強い求人サイト18選!種類や効果的に活用するポイントを解説
建設業で働き方を見直すならツクノビワークがおすすめ
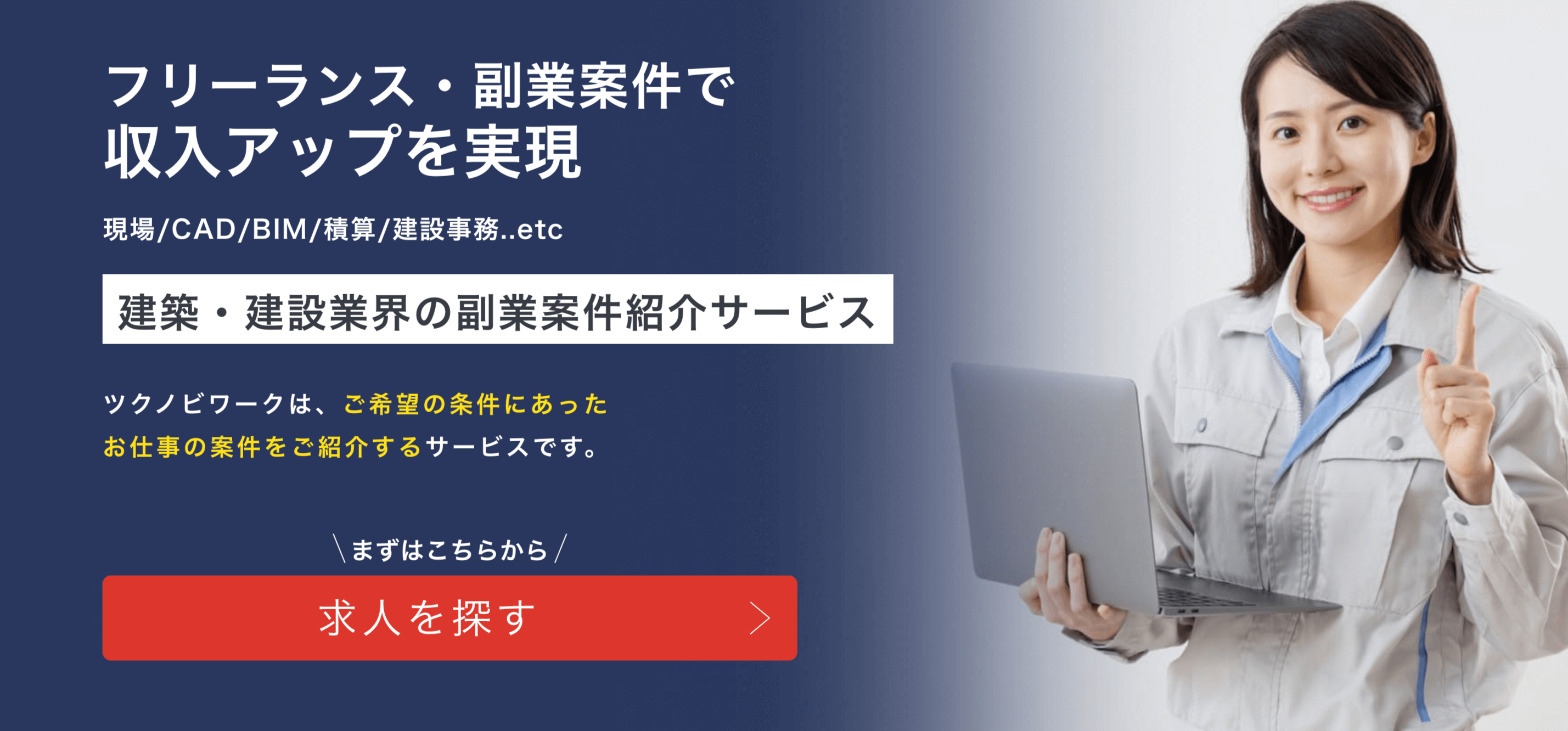
建設業で働き方を見直したい方には、建設業特化のフリーランス・副業案件マッチングサービス「ツクノビワーク」の活用がおすすめです。
週1~5日で勤務できる案件やリモートワークで勤務できる案件など、幅広い案件の中からご希望の案件をマッチング可能です。働く方々に寄り添い、ワークライフバランス改善やスキル向上、年収UPなど、様々なご要望に沿うフリーランス・副業案件をご紹介いたします。
スキマ時間で稼ぎたい方や働き方を見直したい方はぜひこちらから詳細をご確認ください。
【まとめ】自分に合った最適な職業を見つけよう
電気工事士の見習い期間は、しんどいので誰でも辛いです。
他にも、単調な作業が多かったり、時には体力勝負の仕事をする場合もあります。
見習い期間は給料も低く辛いと感じるかも知れませんが、見習い期間の辛さは電気工事士に関わらず、どのような仕事でも言えることでしょう。
大切なのは、自分に合った選択をするということ。というのも、楽しく仕事をするなら、自分に合っている職業を選ぶことが大切だからです。自分が選んで進んだ選択肢であれば、後悔せずに努力できるでしょう。
※弊社の営業代行サービスツクノビセールスは、
【効果が出なければ全額返金プラン】を新たにスタートさせました!

※詳しくは👆👆👆のバナーをクリック!!