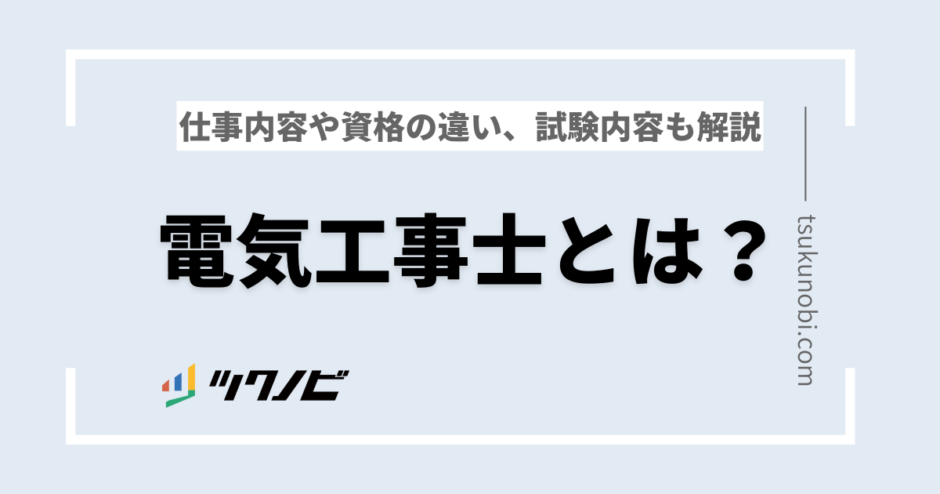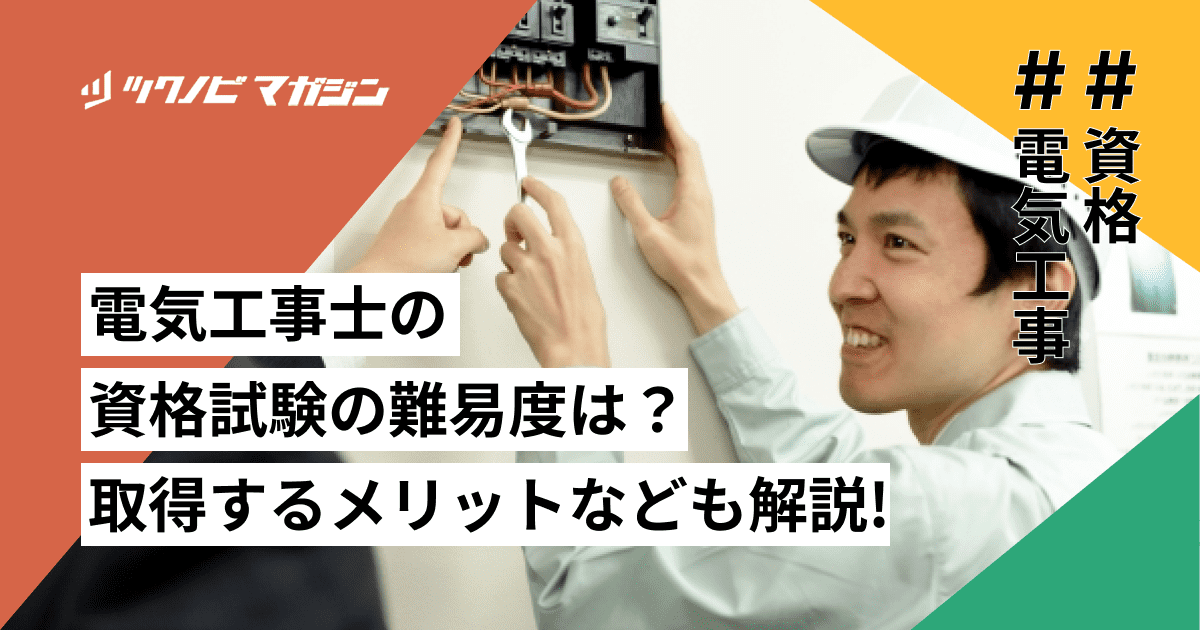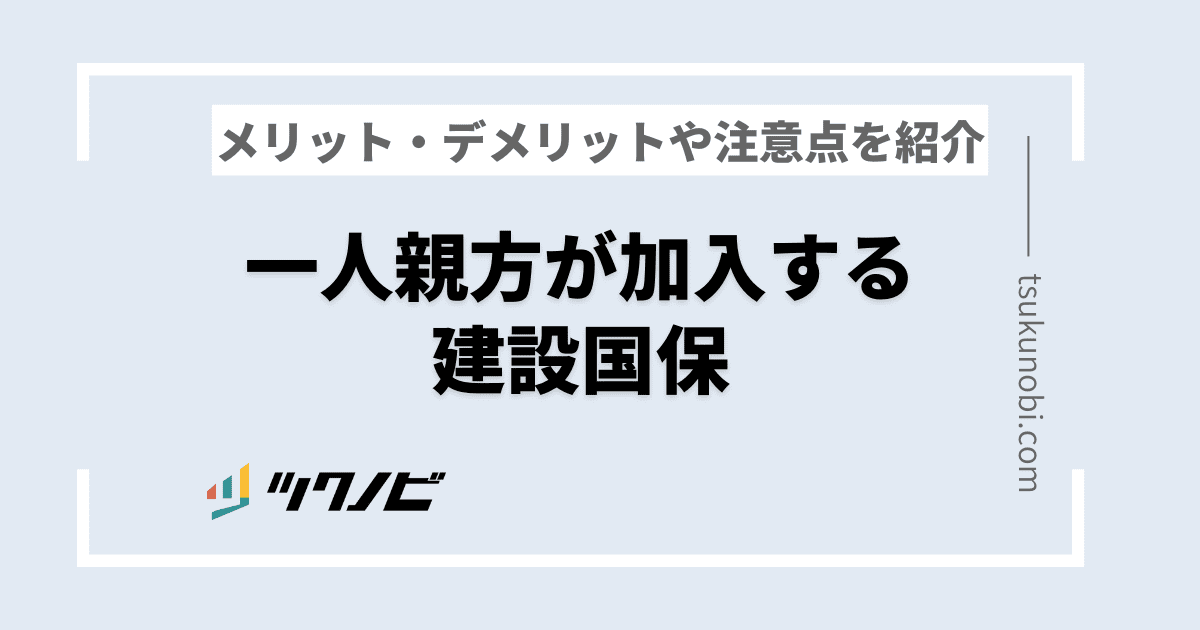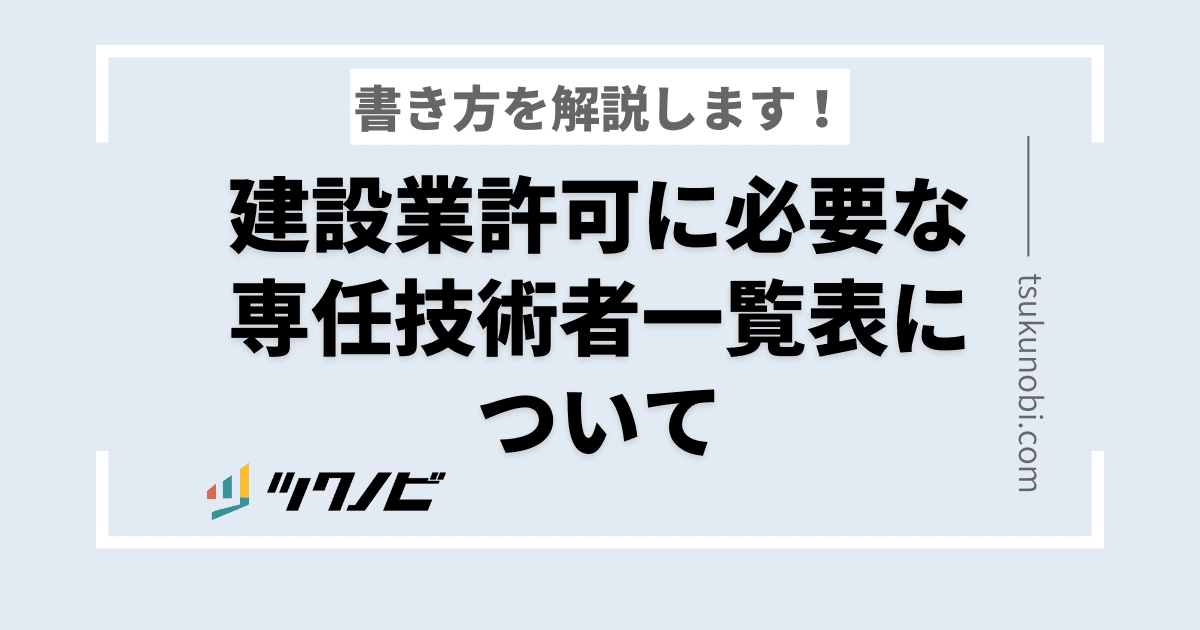※記事内に広告を含みます
「電気」に関する設備の安全を保つのは電気工事士の仕事です。なかには
- 電気工事士とはどんな仕事をするの?
- 電気工事士になるにはどんな資格が必要?
- 第一種電気工事士と第二種電気工事士の違いはなに?
など疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、電気工事士の仕事内容や電気工事士の仕事に必須な資格、第一種電気工事士と第二種電気工事士の違いについて解説します。
電気工事士とは?
電気工事士とは一般住宅からビル、鉄道などあらゆる建物・乗り物にある電気設備の工事や取り扱いを行うための国家資格のことです。電気設備の安全を守るため、電気工事を行うにはこの資格が必要となります。
主な業務内容は様々な建物の電気設備工事に携わる「建設電気工事」と鉄道に関する電気設備工事に携わる「鉄道電気工事」の2つがあります。
また、資格についても、600V(ボルト)以下の一般用電気工作物の作業ができる第二種電気工事士と500kW(キロワット)未満の自家用電気工作物の作業ができる第一種電気工事士の主に2つがあります。
設備工事についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
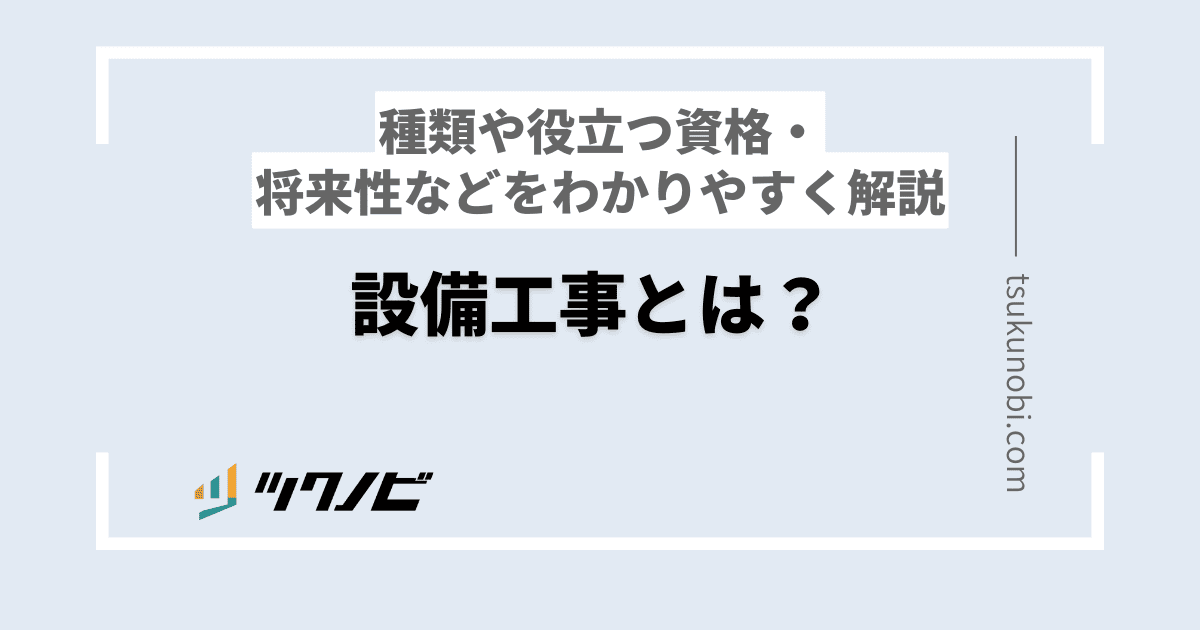 設備工事とは?種類や役立つ資格・将来性などをわかりやすく解説
設備工事とは?種類や役立つ資格・将来性などをわかりやすく解説
電気工事士の仕事内容
電気工事士の仕事内容は、一般の家庭や学校、ビルなどといった電気設備に携わることです。電気工事士の仕事は、大まかに下記の2種類に分かれています。
- 建築電気工事
- 鉄道電気工事
ここからはこの2種類の仕事内容について詳しく解説していきます。
建設電気工事の仕事内容
「建設電気工事」は、一般住宅から公共建造物、ビルなどさまざまな建造物に必要な室内外の電気設備の施工管理に携わっています。
受変電設備の配線や大型機械の制御回路の修理など大規模なものから、照明の設置といった小規模なものまであらゆる電気に関わる作業を行います。
建設電気工事は、電気工事以外の異なる建設作業と並行して作業をすることもあり、色んな業種の方と一緒の現場で仕事をすることも多くあります。
業務を行うことができる現場は多方面にあり、需要が高いのも特徴です。
鉄道電気工事の仕事内容
「鉄道電気工事」は、鉄道に関する電気設備の業務を行う仕事です。鉄道には電車に電気を届ける架設や安心安全に操縦ができるように保つ信号システム、駅の照明・通信設備、電気を供給する発電所や変電所に届くまで、多種多様な電気設備があります。これらを安全に使えるよう設置したりメンテナンスを行ったりします。
鉄道電気工事を行うためには、各種要件をクリアしなければいけません。そのため、鉄道電気工事に携わることができる業者は限られます。
電気工事士に求められる資格
電気工事士の仕事に就くには、まずは資格取得をする必要があります。
電気工事士の資格には、大きく第二種電気工事士と第一種電気工事士の2種類があります。
2つの資格にはそれぞれ作業できる幅が異なるため、自分にマッチする資格の取得が必須になってきます。
ここからは、この2種類の資格に関しての詳しい内容について見ていきましょう。
第二種電気工事士
第二種電気工事士の資格は電気工事士の仕事において取得しておくことがほぼ必須となる資格です。
第二種電気工事士の資格が無ければ、インターホンや豆電球などの小型変圧器しか扱うことができません。「軽微な工事」以外の工事を行うと電気工事士法に違反してしまい罰則を受けることとなってしまいます。
第二種電気工事士の受験資格
第二種電気工事士の受験資格はとくにないため誰でも受けることができます。そのため、年齢や学歴、実務経験なども考慮する必要はありません。
ただ、試験問題を解いて合格するにはある程度の数学や物理の知識も必要です。学科試験は四肢択一ではありますが、高校1~2年生までの数学・物理の知識はしっかりと頭に入れておく必要があります。
技能試験では持参した作業用工具をつかって配線図通りに配線などの作業を行います。
第二種電気工事士を取得するとできること
第二種電気工事士の資格を取得することで一般の家庭や商店、小規模なオフィスなどの600V(ボルト)以下の低電圧で受電するところの配線や電気設備を担当することができます。
また、資格を取得することで現場代理人になることも可能です。現場代理人とは、電気工事の現場を管理する人のことです。現場管理人は電気工事を円滑に進めるために必要な存在であり、現場の安全を守ってくれます。
また仕事面以外でも、自宅のリフォームやDIYも専門的に行うことができるようになるでしょう。資格を持っていることで電気にまつわる知識や技術が身に付くというメリットもあります。
第一種電気工事士
第一種電気工事士は第二種電気工事士よりも難易度も高く、その分より広範囲での工事ができるようになる国家資格です。第一種電気工事士の資格を取得することで大規模な現場の高圧配線工事もできるようになります。取得することで転職する際などもより有利になるでしょう。
第一種電気工事士の受験資格
第一種電気工事士の受験資格は第二種電気工事士と同様にとくにありません。そのため誰でも試験自体は受けることができます。
しかし、試験合格後、申請・取得できる免状の交付には3年の実務経験が必要となります。免状とは資格を取得したことの証明となるもので、実質これがなければ第一種電気工事士になることはできません。
実務経験年数のカウントは試験の受験前・受験後どちらでも大丈夫です。そのため、第二種電気工事士を取得し、3年の実務経験を積んでから第一種電気工事士の試験に合格できると免状をスムーズに取得することができます。
実務経験として認められる内容は以下の通りです。
- 一般用電気工作物の電気工事(第二種電気工事士の資格が必要)
- 500kW未満の自家用電気工作物の低圧部分の電気工事(認定電気工事従事者の資格が必要)
- 500kW 以上の自家用電気工作物に係る電気工事
- 第二種電気工事士養成施設において教員として行う実習
電気工事士法施行令で定められている「軽微な工事」やネオン工事は実務経験の対象にはならないので注意しましょう。
第一種電気工事士を取得するとできること
第一種電気工事士の資格を取得することで一般用電気工作物のほか、最大電力500kW(キロワット)未満の自家用電気工作物の電気工事ができるようになります。ただしネオン工事や非常用予備発電装置工事はできません。
第一種電気工事士の資格を持っていると第二種電気工事士よりも工事の幅が広がるので、昇進や給料が上がることも期待できます。
第二種電気工事士と第一種電気工事士の違い
次に第二種電気工事士と第一種電気工事士の違いについてより詳しく見ていきましょう。
作業できる範囲の違い
それぞれの資格で作業できる範囲は以下の通りです。
| 資格 | 工事可能範囲 | 主な施工場所 |
|---|---|---|
| 第二種電気工事士 | 600V以下の一般用電気工作物 | 一般住宅や小規模店舗など |
| 第一種電気工事士 | 一般用電気工作物等の電気工事最大電力500 キロワット未満の自家用電気工作物の工事 | 上記のほか工場やビル、工事現場など |
第二電気工事士が活躍できる場は一般的な住宅や小さい店舗などに限られます。一方で、第一種電気工事士の場合はより大きな規模の電気工事もできるようになります。そのため、ビルや工場、工事現場などでも業務を担当できます。
試験の合格難易度の違い
第二種電気工事士と第一種電気工事士の令和5年度の合格率は以下の通りです。
| 資格 | 学科試験 | 技能試験 |
|---|---|---|
| 第二種電気工事士 | 59.9% | 73.2% |
| 第一種電気工事士 | 61.6% | 60.5% |
参照元:一般財団法人 電気技術者試験センター
「令和5年度第二種電気工事士上期学科試験の結果について」「令和5年度第二種電気工事士上期技能試験の結果について」「試験実施状況の推移(第一種電気工事士試験)」
どちらも学科試験では60%前後と大きな違いはないものの、技能試験では第一種電気工事士のほうが10%以上も合格率が落ちていることが分かります。また全体的に見て合格率はそれほど低くないため、国家資格のなかではそこまで難易度は高くないでしょう。
定期更新の必要性の違い
第二種電気工事士と第一種電気工事士では定期更新についても条件が異なります。第一種電気工事士は定期更新が必要ですが、第二種電気工事士は更新は不要です。
第一種電気工事士の場合、免状の交付を受けた日もしくは前回の講習日から5年以内に講習を受けなくてはいけません。講習を受けずにいると、都道府県から免状返納通告を受けることがあります。そのため忘れずに更新できるようにしましょう。
待遇の違い
第二種電気工事士と第一種電気工事士では年収などの給与面で待遇も異なります。
例えば第二種電気工事士の場合、月給30.2万円、年収換算で362.4万円です。
一方で第一種電気工事士の場合、月給35.3万円、年収換算で423.6万円となります。
年収アップを考えるのであれば、第一種電気工事士の取得を目指すと良いでしょう。また、経験を積むことで年収も上がるので、スキルアップを目指して経験を積み上げていくことも大切です。
参照元:求人ボックス「電気工事士-第2種の仕事」「電気工事士-第1種の仕事」
資格試験の詳細
ここからは実際に第二種電気工事士と第一種電気工事士の試験を受けたいという方のために、それぞれの試験内容、難易度、合格率などを紹介していきます。
第二種電気工事士
まずは第二種電気工事士の試験内容や難易度・合格率、日程を詳しくみていきましょう。
試験内容
試験は学科試験50問と技能試験に分かれています。
学科試験は7科目あり、それぞれの内容は以下の通りです。
- 電気に関する基礎理論
- 配電理論及び配線設計
- 電気機器、配線器具並びに電気工事用の材料及び工具
- 電気工事の施工方法
- 一般用電気工作物等の検査方法
- 配線図
- 一般用電気工作物等の保安に関する法令
技能試験では用意された材料をもとに配線図通りに配線作業を行うことが求められます。工具は持参しますが、電動工具を使うことは禁止されています。
難易度・合格率
第二種電気工事士の令和5年度の合格率は以下の通りです。
| 資格 | 学科試験 | 技能試験 |
|---|---|---|
| 第二種電気工事士 | 59.9% | 73.2% |
合格率は50%を超えているため、国家資格の中では難易度はそれほど高いものではないでしょう。そのため、独学で1~3ヶ月ほど勉強すれば、十分に合格を目指せます。高校レベルの電気物理、数学の基礎知識を身につけておくとよいでしょう。
日程
令和6年度の第二種電気工事士の試験は年に2回行われます。それぞれの試験日程は以下の通りです。
CBT(Computer Based Testing)方式とは、パソコンを使用して学科試験を受験する方法のことです。
| 学科試験 |
技能試験
|
||
| CBT方式 | 筆記方式 | ||
| 上期試験 | 4 月 22 日(月) ~5 月 9 日(木) |
5 月 26 日(日) | 7 月 20 日(土) 又は 7 月 21 日(日) |
| 下期試験 | 9 月 20 日(金) ~10 月 7 日(月) |
10 月 27 日(日) | 12 月 14 日(土) 又は 12 月 15 日(日) |
試験時間について学科試験は120分間、技能試験は40分間となります。
第一種電気工事士
つぎに第一種電気工事士の試験内容や難易度・合格率、日程を詳しくみていきましょう。
試験内容
第一種電気工事士の試験も学科試験と技能試験があります。
学科試験は9科目あり、それぞれの内容は以下の通りです。
- 電気に関する基礎理論
- 配電理論及び配線設計
- 電気応用
- 電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備
- 電気工事の施工方法
- 自家用電気工作物の検査方法
- 配線図
- 発電施設、送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性
- 一般用電気工作物等及び自家用電気工作物の保安に関する法令
技能試験では、配布される材料をつかって配線図通りに接続や電線の圧着などを行います。
難易度・合格率
第一種電気工事士の合格率は以下の通りです。
| 資格 | 学科試験 | 技能試験 |
|---|---|---|
| 第一種電気工事士 | 61.6% | 60.50% |
合格ラインは毎年変動しますが、6割以上と言われています。国家資格の中では難易度は中程度といえるでしょう。第二種電気工事士よりは難易度もあがるのでより入念な対策が求められます。
日程
令和6年度の第一種電気工事士の試験は年に2回行われます。それぞれの試験日程は以下の通りです。
また上期の学科試験では筆記方式での受験はできないので気をつけましょう。
| 学科試験 |
技能試験
|
||
| CBT方式 | 筆記方式 | ||
| 上期試験 | 4 月 1 日(月) ~5 月 9 日(木) |
CBT 方式のみ実施 | 7 月 6 日(土) |
| 下期試験 | 9 月 2 日(月) ~9 月 19 日(木) |
10 月 6 日(日) | 11 月 24 日(日) |
試験時間について、学科試験は140分間、技能試験は60分間となります。
電気工事に関する他の資格
電気工事士にまつわる資格は前述で紹介した2種類以外にもおすすめの資格があります。
- 電気通信の工事担任者
電気通信の工事担任者とは、電気通信回線・端末の保守点検や工事業務などの施行や監督を行うことができる国家資格です。電気通信の工事担任者の資格は、受験資格に条件がありませんので誰でも受けることができます。 - 第三種電気主任技術者
2つ目におすすめの資格が第三種電気主任技術者という通称「電験三種」と言われている資格です。「電験三種」は、工場施設やオフィスビルなどの電気設備の安全管理や監督を行うことができます。対象となる業務は、電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物になります。(出力5000kW以上の発電所は除く)
上記の資格を取得することで更なる給料アップを目指すことができますのでぜひ資格取得に挑戦してみてください。
電気工事士の仕事に関するQ&A
最後に電気工事士の仕事でよくある質問をまとめました。電気工事士の給与ややりがいなどについて質問形式で紹介していきます。
平均給与はどのくらい?
電気工事従事者の平均年収は、厚生労働省の「令和4年賃金構造基本統計調査」によると459.6万円になります。
また、年収は年齢や会社の大きさ、地域などによっても変動があります。例えば年齢では50~54歳が最も高くなり、平均年収が592万円となります。また、会社の規模では1,000人以上で最も平均年収が高く528.1万円となります。
企業によっては、資格を取得することによって年収アップや資格手当をもらえる事もあります。
参照元:厚生労働省「令和4年賃金構造基本統計調査」
所定内給与額1年分と「年間賞与その他特別給与額」を合計した額から算出
試験合格のためには独学かスクーリングのどちらが良い?
未経験の方は、試験に向けて独学で勉強することに不安を感じるかもしれません。
しかし、電気工事士の資格は独学でも取得することができます。独学で勉強する際には過去問に取り組むのがおすすめです。
また一人ではなかなかモチベーションが上がらない方はスクーリング(通信大学)も利用すると良いでしょう。独学よりもお金がかかるといったことはありますがスクーリング(通信大学)に通うことで着実に最短で試験に合格することができるでしょう。
電気工事士の仕事のやりがいとは?
電気工事士の仕事内容や職場環境は大変な事も多いですが、やりがいももちろんあります。
私たちの生活では電気がないと生きていけません。地震や災害を経験されてる方は特に身に染みて感じるでしょう。
今こうしてWebページが見れているのも電気が通っていてパソコンやスマホを充電できるおかげです。
電気がある事で救われる命もあります。こういったことから、電気工事士はとても社会に貢献できるやりがいがある仕事といえます。
電気工事士の仕事の大変なところは?
電気工事士は働き方改革などといった時代の変化で職場環境は以前に比べてとても良くなりました。
ですが、現実はそう甘くはありません。会社にもよりますが、仕事のやり方を上司が教えてくれることは少ないかもしれません。
現場で見て自分で仕事のやり方を覚えないといけない点も多々あり、最初はとても苦労するかもしれません。
仕事で使う重い工具や機械を運ぶこともあり、体力を使うため自分の体力がないときつい仕事でもあります。
【まとめ】多岐に渡る電気工事士の仕事内容!自分のキャリアプランに合わせて資格を取得しよう
今回は、電気工事士の仕事内容について解説しました。電気工事士の仕事内容は、お店やビル、一般家庭などといった電気設備に携わることができ、とても多方面に活躍することができます。電気工事士は資格がないとできない業務も多くあります。まずは、資格取得を優先しましょう。
資格の種類によってできることも変わってきますので自分の携わりたい仕事に合った資格の取得をすることが大切です。
電気工事士の年収についてはこちらの記事でより詳しく解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
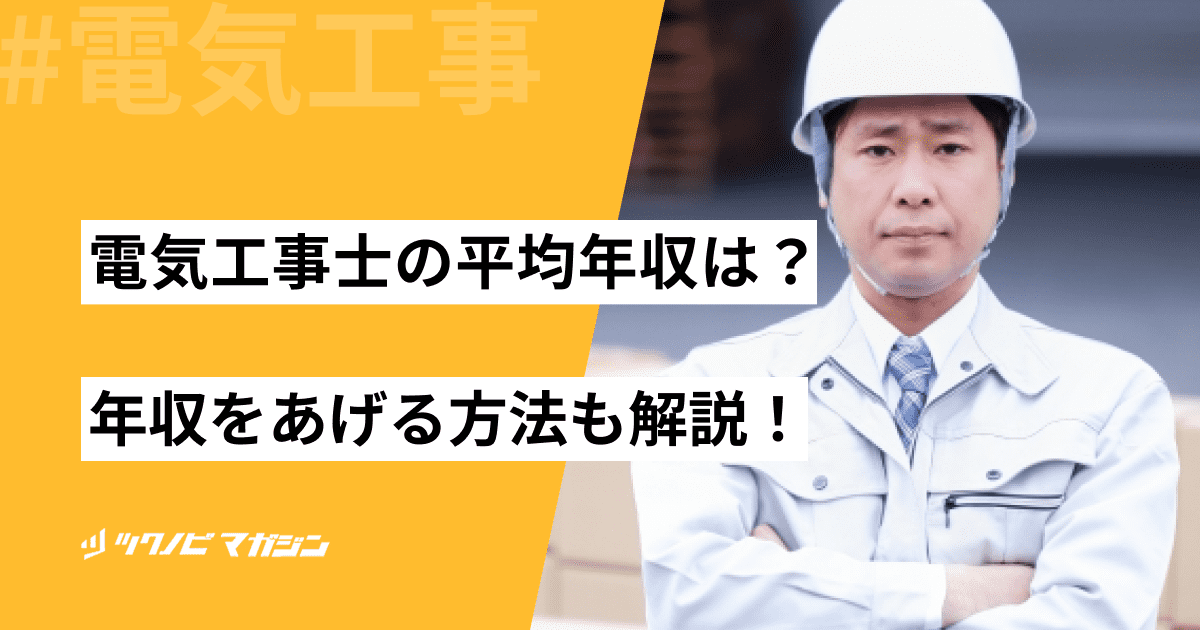 電気工事士の平均年収は?年収をあげる方法も徹底解説!
電気工事士の平均年収は?年収をあげる方法も徹底解説!
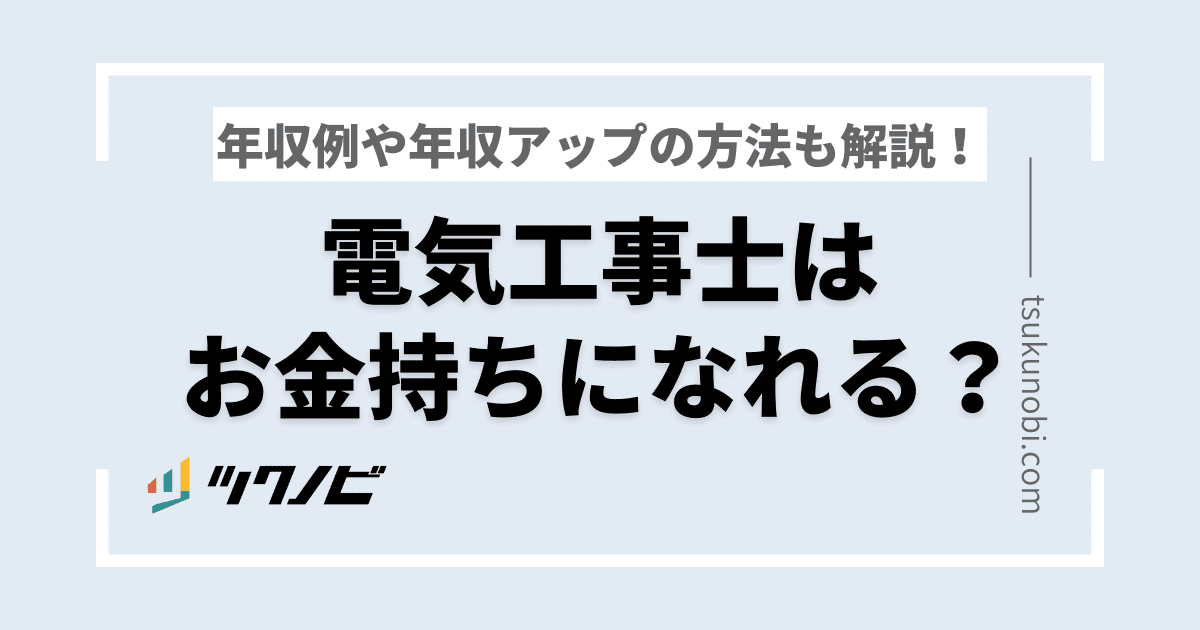 電気工事士はお金持ちになれる?年収例や年収アップの方法も解説
電気工事士はお金持ちになれる?年収例や年収アップの方法も解説
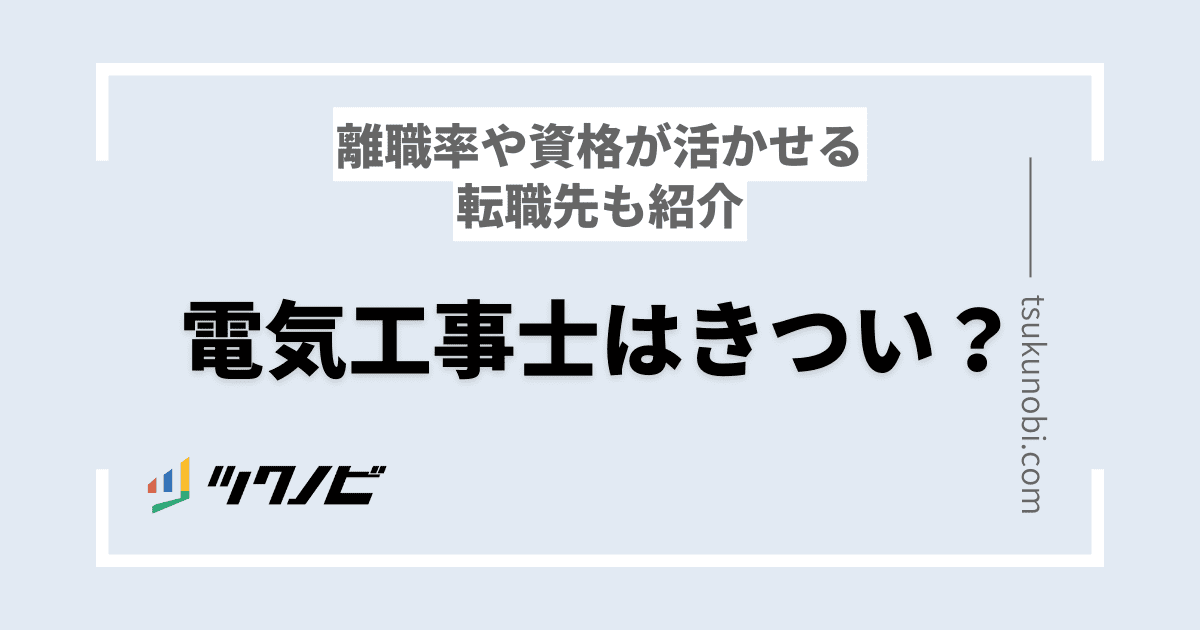 電気工事士がやめとけと言われる理由|離職率や資格が活かせる転職先を紹介
電気工事士がやめとけと言われる理由|離職率や資格が活かせる転職先を紹介
電験三種で独立するのに必要な条件やメリットについてはこちらの記事でより詳しく解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
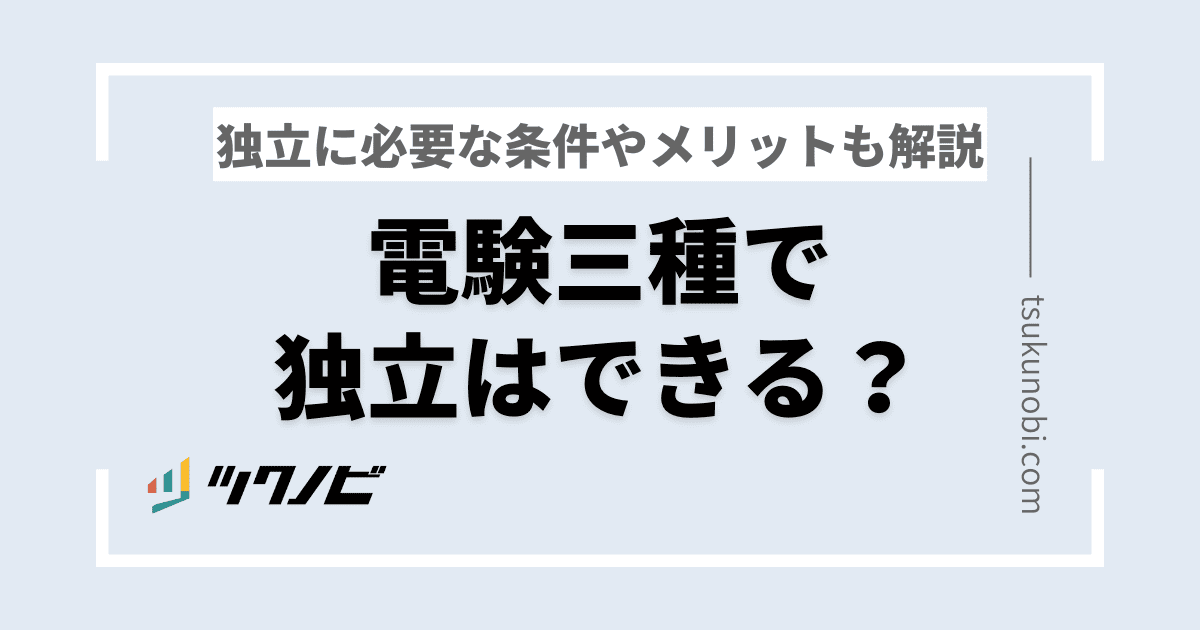 電験三種で独立できる?独立に必要な条件やメリットを解説
電験三種で独立できる?独立に必要な条件やメリットを解説
※弊社の営業代行サービスであるツクノビセールスでは、
【効果が出なければ全額返金プラン】を新たにスタートさせました!

※詳しくは👆👆👆のバナーをクリック!!