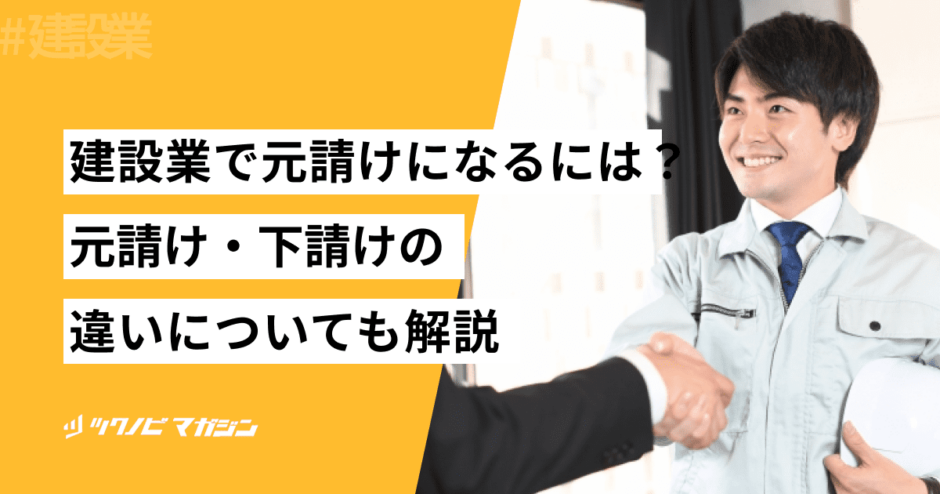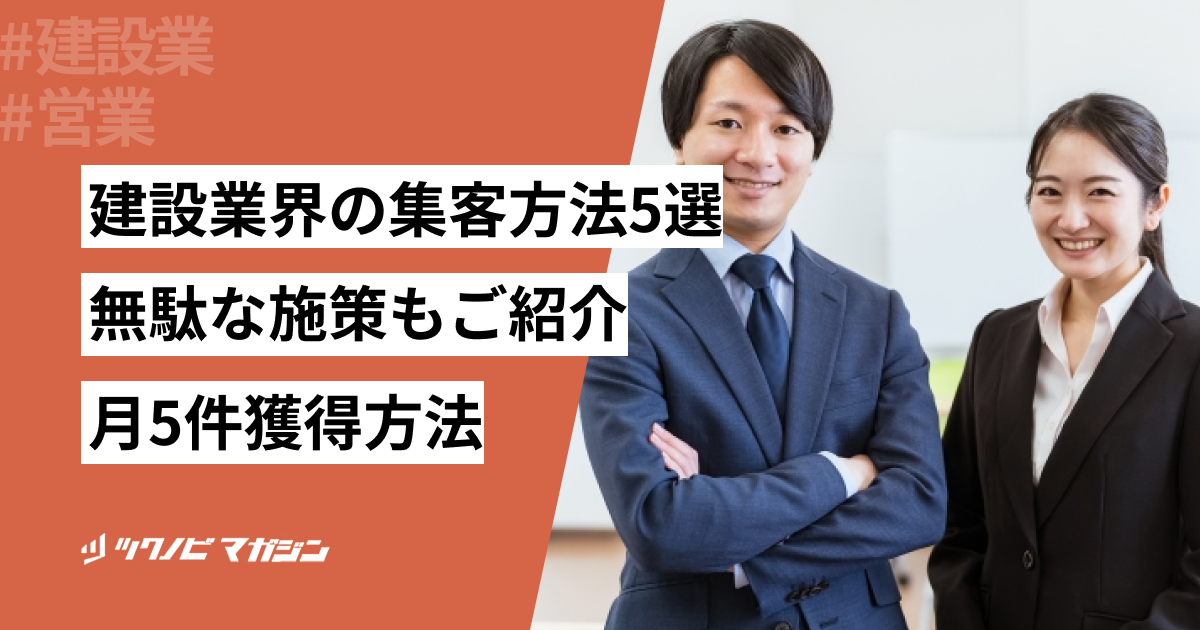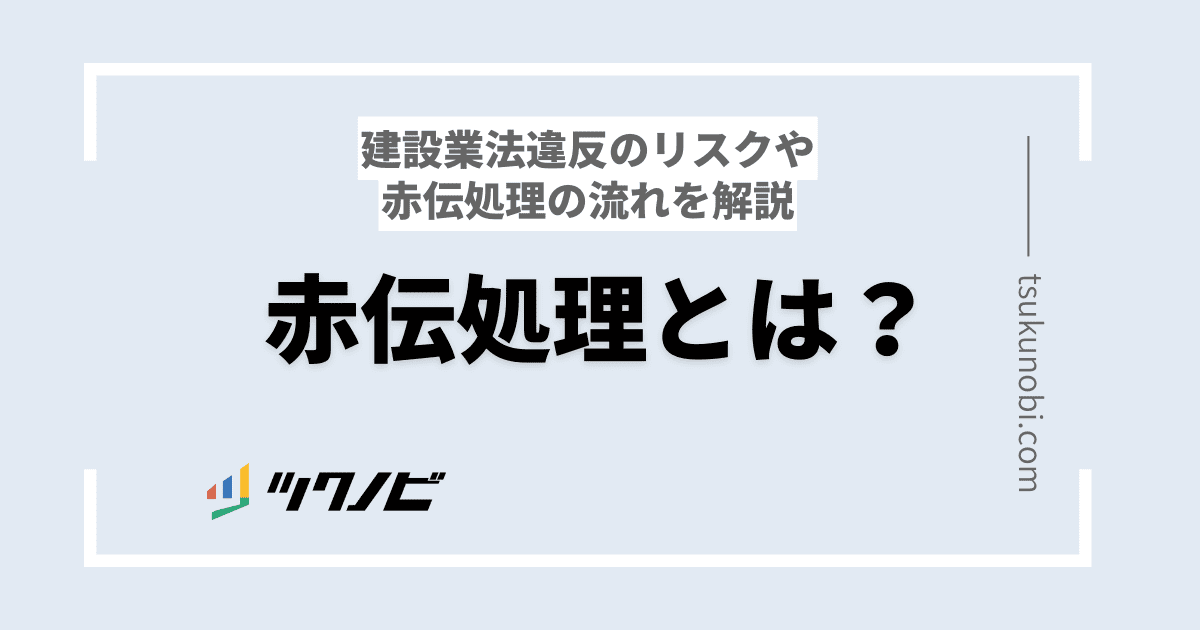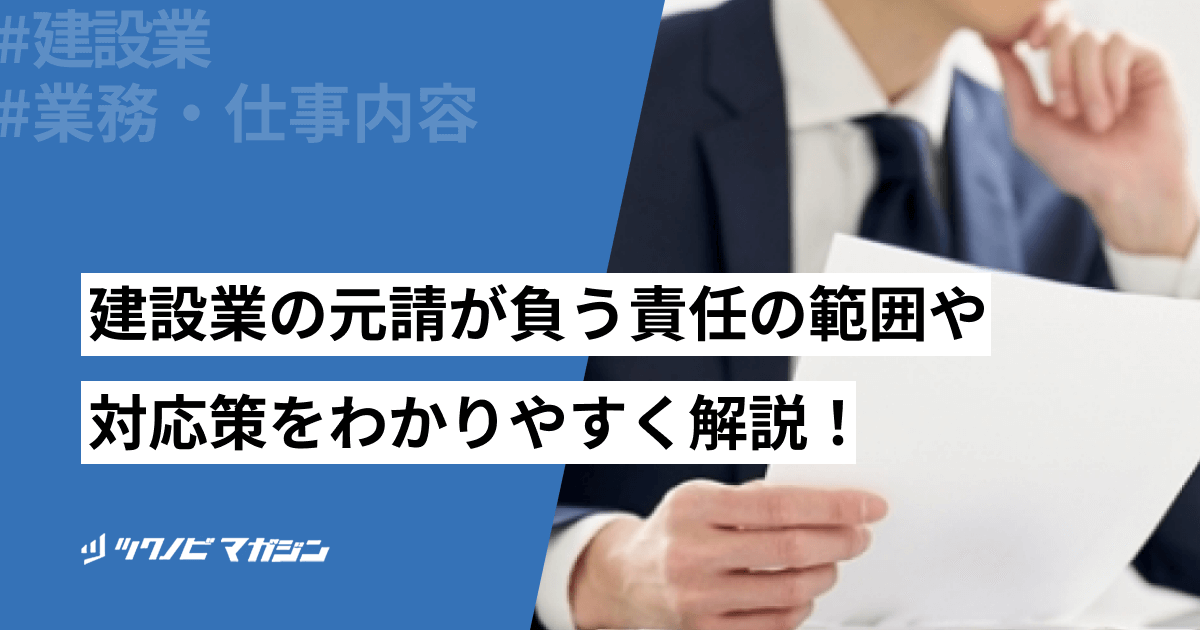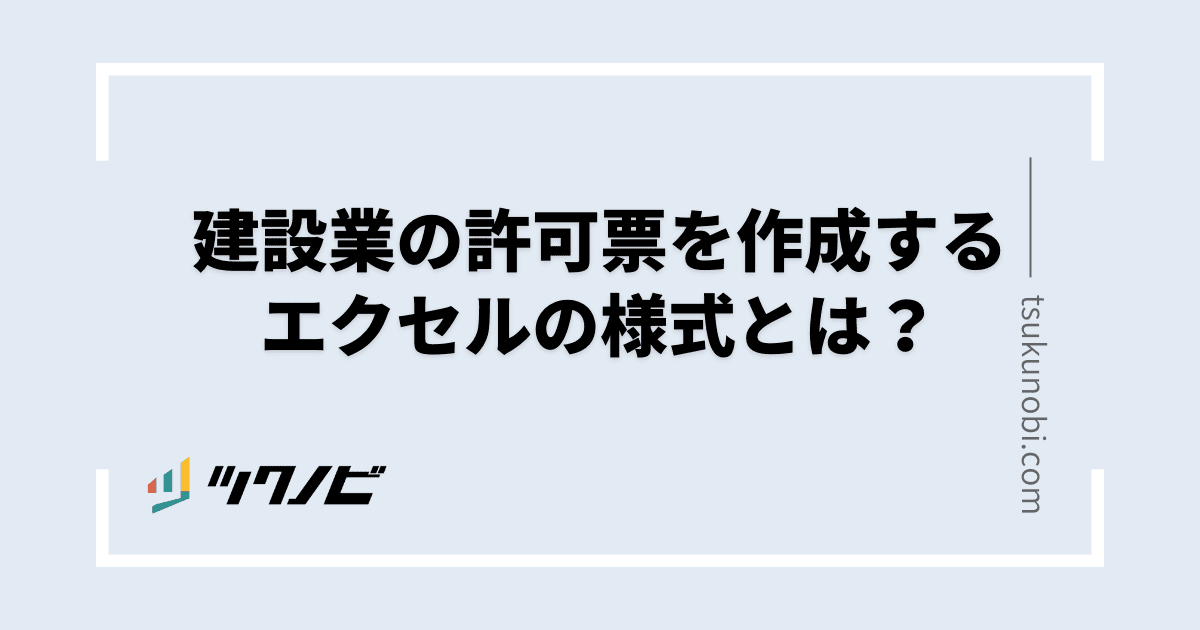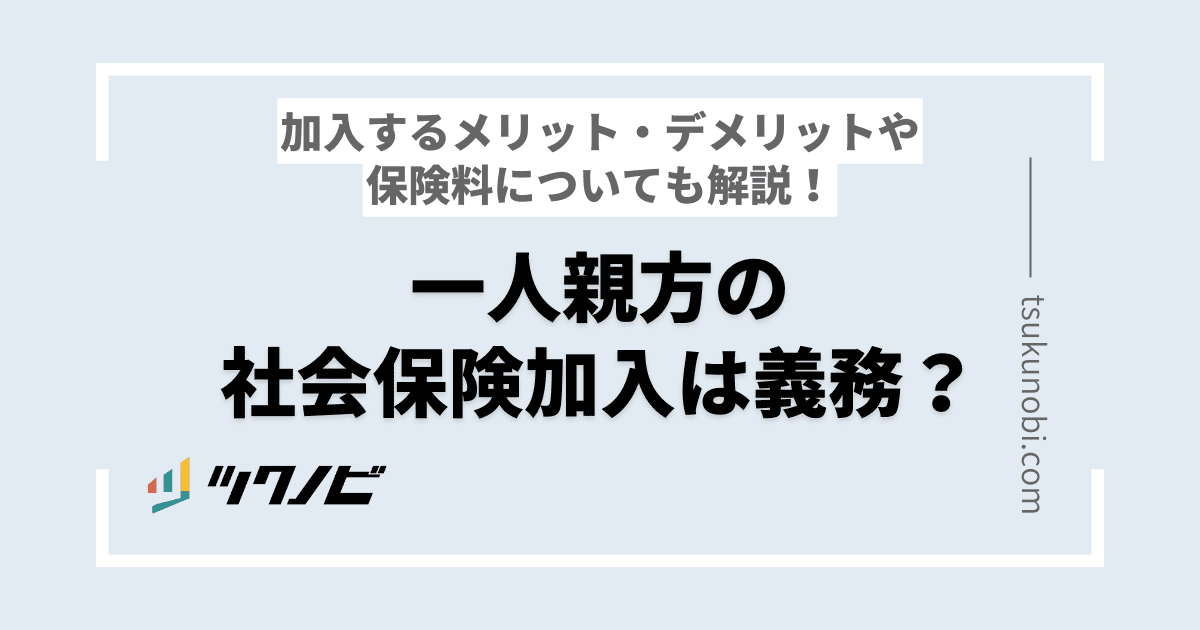建設業を語るうえで、「元請」「下請」の構造は、避けては通れないといっても過言ではありません。工事の分業化を図るうえで、多くの現場は下請が何層にもある重層下請構造で成り立っています。そのようななかで
- 元請けになるにはどうすればいいのだろう
- 下請けから元請けになるのは可能なのだろうか
といった疑問や悩みをお持ちの方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は建設業において、下請けから元請けになる方法や、元請け・下請けのメリット・デメリットまで含めて紹介します。
ツクノビセールスは、建設業に特化した営業代行サービスです。御社の代わりに月間2,000社に営業を実施し、【効果が出なければ全額返金プラン】もご用意しております。累計で4000万円の受注ができた事例もあります。
建設業での元請けと下請けとは
建設業では、元請けと下請けといった2つの主要な立場が存在します。そして、下請けはさらに細かく「一次請け」「孫請け」に分かれています。元請けや下請けは、よく耳にする言葉ですが、両者は具体的にどのような特徴を持っているのでしょうか。
ここでは、元請けと下請け、それぞれの特徴について解説します。
元請けとは
建設業における元請けとは、発注者から直接受注を受ける業者を指します。それに対して下請けは、その元請業者の仕事の一部を請け負う業者を意味します。両者の違いは「誰から依頼を受けて仕事するか」です。
元請けの依頼人は発注者、下請けの依頼人は元請業者となります。例えば、ゼネコンから直接依頼を受ける建設業者を元請け、その業務の一部を委託される小規模な建築会社や一人親方などは下請けとなります。
下請け構造の下層に行けば行くほど、受注価格は安くなる傾向にあります。
一次請けとは
一次請けとは元請けから直接受注を受ける業者や一人親方のことを指します。「一次」という言葉から発注者から受注する元請けと混同する人も見受けられます。しかし元請→一次請けという構造なので間違わないようにしましょう。
元請けは基本的に1社ですが、一次請けは複数の企業で担当する場合もあります。例えば、建設工事、内装工事、外構工事などの各工事を専門性の高い業者にそれぞれ委託するケースは珍しくありません。
ただし、資材の販売業者や地盤調査業務、警備や運送業者などの直接関わらない業者は、元請けと直接契約しても下請けとは定義されません。
孫請けとは
孫請けとは、一次請けの事業者から受注を受けて業務を行う業者や一人親方を指します。二次請けや二次下請けと称することもあり、比較的小規模で元請けから直接契約を受注できない業者が目立ちます。
この場合であっても、工事の責任は一次請けではなく元請けが追うことになります。そのため、下請けは孫請けに業務のすべてを丸投げはすることは許されません。一次請けは、再下請負通知書を元請けに提出して、業務の一部を孫請けに委託したという報告をしなくてはいけません。
元請けと下請けの違い
建設業界では、元請けが請け負った仕事を下請け企業に発注する形式が主流です。そして、元請けと下請けでは、様々な違いが存在します。具体的には以下のような違いです。
- 発注者の違い
- 指示系統の違い
- 請負金額の違い
ここでは元請けと下請けの違いについて、1つずつ解説します。
発注者の違い
元請けと下請けの根本的な違いは「発注者」です。元請けが仕事を請け負い、受注契約を結ぶ相手は国や民間企業などの「発注者」です。しかし、下請けが仕事を請け負い、契約を結ぶ相手は元請けです。
そのため、下請けが「発注者」と関わることはほぼありません。下請は、あくまでも現場での作業担当です。一方、元請けは工事や業務全体の責任を負い、納期・品質管理などを担当します。
指示系統の違い
元請けは、工事など業務範囲を決定し、下請けに具体的な指示を出す立場です。一方、下請けは、元請けから具体的な作業やタスクの指示を受け、作業を進める立場です。そして、元請けは下請けが行う作業内容の監督や品質管理を行います。
また「外部」の業者に発注することを「外注」と言います。ただし「一人親方」など、下請けで作業をするものの、外注は元請けから具体的な指示を受けません。自ら考え作業を行うため「下請け」とは違う立場となります。
請負金額の違い
元請けは発注者から仕事を請け負い、下請けは元請けから仕事を請け負います。ただし、請負金額は両者で違います。下請けの請負金額は、元請けよりも少ないです。
下請は、元請けが発注者から請け負った一部の工事や業務を担当し、その対価として報酬を受け取ります。しかし、下請けの請負金額は元請けが発注先から請け負った金額から算出されます。そのため、重層下請構造の下位に位置するほど請負金額は少なくなるのです。
建設業で元請けになるための3つのステップ
建設業で元請けになるには以下の3つのステップをふむ必要があります。
- 実績を積む
- 組織を増やす
- 営業や集客をする
それでは詳しくみていきましょう。
実績を積む
仕事を受注するにあたって、相手からもっとも重要視されるポイントは、今までの実績です。真面目に仕事に取り組んでくれるか、また自分がイメージする内容に近いか…などを判断するために、実績をアピールする点はとても重要なポイントとなります。
実績を積むためには仕事を請け負い、実際に現場で形として残すことがもっとも効果的です。また、仕事を依頼してもらう前の段階であれば、まずはスキルを身につけ資格を取得する、競合との差別化を図るといった点も重視してみるのも良いでしょう。
組織を増やす
物作りは人育てにも近い部分があるため、人材育成を踏まえたしっかりとした組織作りも大変重要になります。建設業界に関わらず社員の入れ替わりが激しい会社は、質の高い物作りが難しくなります。人手が足りないと一人一人の負担が重くなり、ひとつの作業に十分な時間や手を掛ける余裕がなくなってしまうためです。そして、新たな人材の確保はとても重要ですが、育成だけでなく、社員が辞めない組織づくりも大切です。
社員がすぐやめてしまうような労働環境では、発注者からの信頼も落ちてしまうでしょう。そのため、社員にとって仕事をしやすい組織作りを行うことも元請けには求められます。
営業や集客をする
元請けとして案件を受注するためには、営業を行い、集客することが欠かせません。営業方法は法人向けに行うか、個人向けに行うかによっても変わってきます。具体的な詳しい営業・集客方法については以下のページをご参照ください。
法人向けの工事をしている場合はこちら!
個人向けの工事をしている場合はこちら!
弊社では建設業における法人営業や競合調査等で活用できる全国の業者リストをご提供しております。
詳しくはこちらからお気軽にお問い合わせください。
案件を獲得するためには営業代行サービスもおすすめ
元請けとして案件を獲得できる営業の体制やノウハウがない場合は、営業代行サービスの活用もおすすめです。
建設業に特化した営業代行サービスであれば、プロの営業担当が業界全体の動向やニーズを把握したうえで営業活動が行うので、効果的なアプローチが可能となります。
また、コスト面でも、営業人材を正社員として採用・維持するよりも低コストで営業活動ができます。
弊社サービスである建築建設特化の営業代行「ツクノビセールス」は、月に2000社もの企業に御社の営業としてアタックし、かつ成果が出なかったら返金保証もしています。
まずは話だけでも聞いてみたい!という方には無料で営業戦略のご提案も致しておりますので、こちらからお気軽にご相談ください。
建設業における元請けのメリット・デメリット
このように建設現場の多くは、発注者→元請→一次請け→二次請け→三次請け…と重層化層構造で成り立っています。工事の内容が高度化したことから、専門化や分業化が進み、さらに機器や工法の多様化への対応するためこのような構造が生まれました。
合理的な仕組みのように見えますが、元請け、下請けそれぞれで抱えるメリットやデメリットがそれぞれに発生し、工事が複雑化し様々な弊害が生まれていることも事実です。
まずは元請業者でいるメリットについて、3つに分けて解説していきましょう。
元請けのメリット
元請けのメリットとして、以下の3つが挙げられます。
- 自社で捌ききれない工事も請けられる
- 利益率が高い
- 請求金額を決められる
元請けのメリットについて、詳しくみていきましょう。
自社で捌ききれない工事も請けられる
元請となるメリットの1つに工事の一部を下請に発注できるため、自社だけでは難しい専門性の高い工事や規模の大きな現場などの、幅広い業務を受注できることが挙げられます。逆に、得意とする分野の小規模工事は自社で対応し、大規模な工事は下請けに回すことも可能です。
このようにすれば、大規模工事を受注する際も委託、複数の建設企業でジョイント・ベンチャーを設立する必要もありません。
元請になれば自社だけでは対応できない案件も、下請に一部業務を委託することで受注できるようになります。
利益率が高い
元請になれば、利益率の高い仕事ができます。先述したように建設業界の重層下請構造では、二次請け、三次請けと下層になるほどに中間マージンが差し引かれるため利益率の低い仕事になります。
発注者から直接受注できる元請になれば、仕事を請けた分、自社の利益となるのは非常に大きなメリットです。また、一部の業務を下請けに委託すれば、機材や人件費などの固定費も大幅にカットできます。
このようにコストカットができる点も、元請けの利益率を高くしている要因といえるでしょう。
請求金額を決められる
発注者から受注する際、価格は元請の言い値で決まることが多いため、自由に価格を設定することができるのも元請となるメリットの1つです。工事の価格だけではなく、工期、工事のスケジュールなども発注者と直接コミュニケーションをとりながら決められます。
そのため、互いのニーズに沿った受注ができるのは元請ならではの醍醐味と言えます。さらに、工事は元請の実績として記録されるので、今後の企業のアピールにも活かせるでしょう。下請けへの発注価格を、元請けが決定できるのは非常に大きな利点です。
元請のデメリット
元請けは利益を生みやすくなるなど、メリットが豊富です。しかし、元請けにもデメリットはあります。元請けのデメリットは以下の2つです。
- 責任が大きくなる
- 出張や転勤が発生する可能性がある
それでは、詳しくみていきましょう。
責任が大きくなる
元請けでいることのデメリットは、責任の大きさです。二次請け以下のすべての下請けの事故やミスの責任の所在はすべて元請けになります。そのため、下請けの労災保険は元請けの負担の下で加入されることになるのです。
業務の一部を丸投げするのではなく、下請けと業務の連絡を取り合い発注者の意図に沿った工事であることを監督し、安全の確保にも配慮しなければなりません。工事が終わるまで何社もの下請けの業務を管理することは、時に大きなリスクも伴います。
出張や転勤が発生する可能性がある
元請けは大規模なプロジェクトや業務を担当することが多いです。そして、業務の実施地域によっては、現地での作業や調整が必要となる場合もあります。
そのため、出張や転勤が発生する可能性もないとは言えません。ただし、出張や転勤は、個人の価値観や状況によってデメリットに感じない場合もあります。転勤や出張が、新たな成長に繋がる場合もあるためです。
建設業における下請けのメリット・デメリット
これまでは元請けのメリット・デメリットを解説してきました。逆に、下請けであることのメリットやデメリットはどのようなものなのでしょうか。ここでは、下請けのメリット・デメリットを解説していきます。
下請けのメリット
元請けには様々なメリットがありますが、そんな元請と同様に下請業者にも、メリットはあります。元請けから業務を委託する下請業者になることで得られるメリットを、まずは以下で2つ紹介していきます。
営業の必要がない
営業活動をしなくても良いことは、下請けになる最大のメリットといえるでしょう。営業活動には、営業の人件費と広告費などの費用と時間がかかります。しかし、元請から受注するルートを確立していればその時間と労力をすべて実務に費やせるのです。
また、工事に伴う書類作成や取引条件の交渉などもすべて元請が負担してくれます。さらに、自社だけでは受注できないような大きな案件も下請けとして一部を受注することも可能であるため、実績を積みながら、スキルも磨くこともできます。
業務量を一定数確保できる
下請になれば安定した業務量を確保できるのも大きなメリットです。元請は利益率が高い仕事ができますが、仕事を受注するために大きな労力を費やしています。先述したような営業活動も必須ですし、競合他社の研究をして戦略を得る必要もあります。
しかし、下請けとして一定の規模を誇る元請と関係を構築していれば、何もせずとも業務が下りてくるようになります。そのため独立する際は、下請けからキャリアをスタートする一人親方が多いのです。
下請けのデメリット
下請となれば、営業活動や開発に費用や時間を割かなくても、元請から業務を委託できます。もちろん、工事に伴う事務手続きも殆どは元請が請け負うので、事務手続きなどをやらず実務に集中したいという職人気質の方には向いている働き方と言えるでしょう。
しかし、当然のことながら下請けとなるデメリットもあります。下請となるとどうしても金銭や工事の進行に関しては不自由さを感じる機会が増えてくるのです。
下請けになることで発生するデメリットを、以下で2つに分けてより詳しく解説していきましょう。
請負価格の自社決定権がない
元請とは異なり、請負価格の自社決定権がないことは下請になる最大のデメリットです。元請は自分の利益率を上げるために、少しでも安く請け負ってくれる業者を探しています。
そうすると下請け業者の中で価格競争が発生し、元請にかなり安価な金額で買い叩かれてしまうケースが非常に多いのです。その中から中間マージンも抜かれるため、工事が終わったら赤字だったというケースもあります。
このように、下請け業者は請負価格を自由に決められず、思うように利益を上げられないという一面があります。
元請のいいなりになってしまう
自社の都合ではなく元請けの条件の下で働かなければならないのもデメリットの1つです。例えば、何らかの理由で工事が難航したとしても、一度元請けから提示された価格や取引条件の変更は難しいケースもあります。
さらに、元請の業績が悪化すればその影響をダイレクトに受けるため、業務量が減らされたり、最悪の場合契約を打ち切られることも考えられるのです。
実際に元請けの強い立場を利用した、支払いを渋る、契約外の業務をさせる、無理な工期を要求するなどの「下請いじめ」は珍しいものではありません。これは、建設業界の悪しき習慣として認知されています。
下請契約で気を付けるべき建設業法とは
国土交通省が提示している「建設業法令遵守ガイドライン」により、元請負人と下請負人との請負契約では守らなくてはいけない点が定められています。
これは、元請負人と下請負人が対等な立場として取引を行うことを目的として作成されました。
【守らなくてはいけない項目】
・見積条件の提示
・書面による契約締結(当初契約、追加工事等に伴う追加・変更契約、後期変更に伴う変更契約)
・不当に低い発注金額
・指値発注
・不当な使用資材等の購入強制
・やり直し工事
・赤伝処理
・工期
・支払保留
・長期手形
・帳簿の備付け・保存及び営業に関する図書の保存
・関係法令(独占禁止法との関係、社会保険・労働保険)
・労働災害防止対策について
これらの項目に違反すると、基本的にはまず行政からの助言・勧告といった指導から入ります。それでも改善されない場合、指示、営業停止、許可取消…というように徐々に処分は重くなります。
実際の処分については、違反行為の内容や程度を鑑みつつ、社会的影響や情状などを考慮し、総合的に勘案されます。
赤伝処理の詳細と注意点についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認くださいね。
元請けが下請け会社を選ぶ時の注意点
元請けになると下請けによるトラブルで被害を被ることもあります。先述したように下請けのミスやトラブルはすべて元請けの責任になるため、下請け次第では元請けの評判も落としかねません。そこで今回は良質な下請け業者を選ぶための注意点について、以下で説明していきます。
無理のない金額設定
元請け、下請け双方にとって無理のない金額設定で契約できる業者を選びましょう。自社の利益を確保しようと下請けに低い金額を設定すると、人材や資材が不足し結果として満足いく業務が行えずトラブルになるケースが見受けられます。
資材や経費も下請けの負担となるため、それを差し引いても下請けが十分な利益を確保できる金額を設定すればそのようなリスクは回避できます。また、支払期日下請けの材料費の支払い日なども考慮して設定しましょう。お互いが納得できる金額で契約することが大切です。
労働条件を明確に決定する
労働条件を明確に提示している下請けを選びましょう。受注した工事の責任は元請けが負うので、労働条件が曖昧な下請け業者を選んでしまうと互いの中で認識のずれが生じている可能性があり、後にトラブルとなる恐れがあります。
特に社会保険未加入問題は問題視されているので、加入しているかはしっかり確認しましょう。作業員の名簿など安全書類の作成業務などの雑務を滞りなく行える環境が整っているかも、下請け業者を選定する際にチェックしたいポイントの1つです。
作業員と技術者の人数確保
工事に必要な作業員と技術者の人数を揃えらえる業者であるかを確認してください。建設業法で請負金額にかかわらず、工事現場には主任技術者又は監理技術者を配置しなければならないと定められています。
また、工事に必要な人員が確保できないと、工期内に安全で制度の高い工事を進めることは不可能でしょう。請負金額を重視して安価な業者を選定すると、人数が足らずに求められるレベルの工事が行えない可能性があるので、下請けの人員確保能力も重視して選定しましょう。
コストをかけず手軽にWeb集客をするならゼヒトモがおすすめ
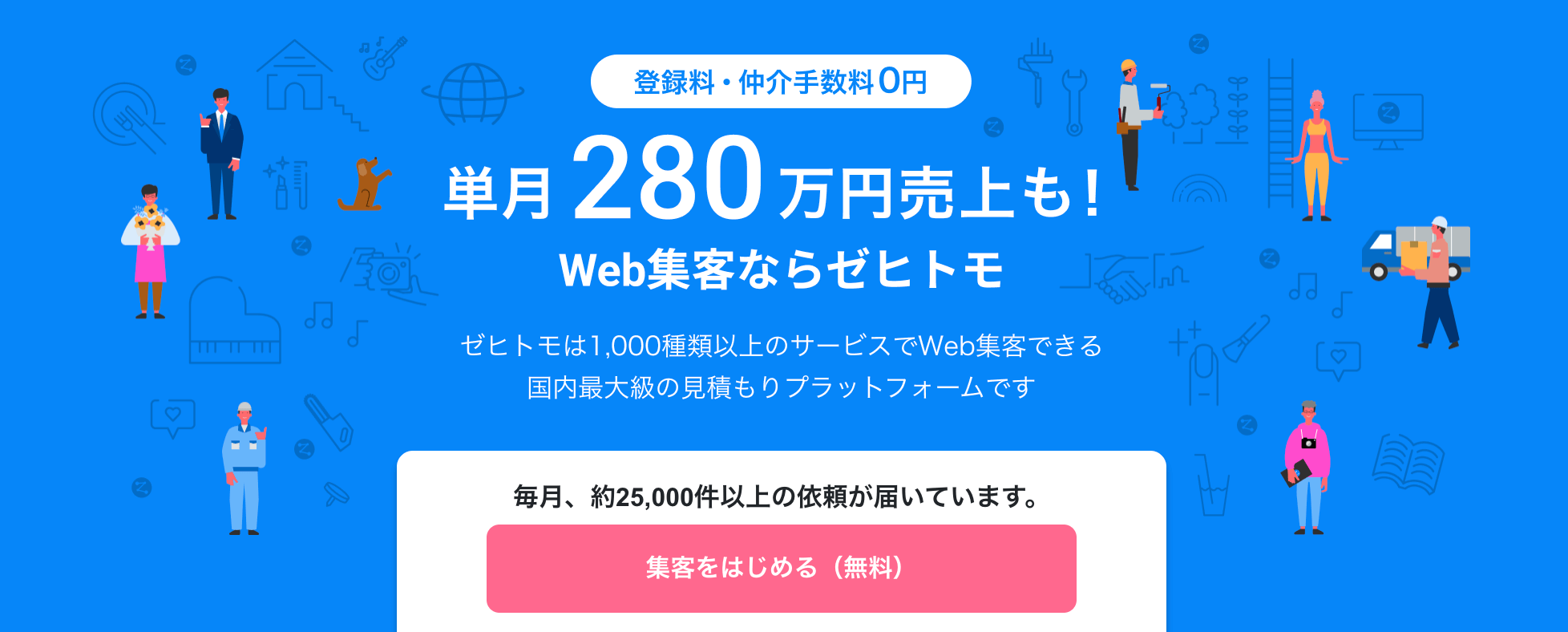
手数料0円でWeb集客をしたいならゼヒトモがおすすめです。ゼヒトモには検討意欲の高いリフォーム・内装・外装・外構工事などの案件が毎月25,000件以上集まっています。かかるのは初回メッセージ送信料のみなので、なるべくコストをかけずに効率よく集客ができます。
元請けと下請けの違いを理解し、自社に適した立場で建設現場に関わろう!
元請けは高い利益率を確保できる一方で責任が大きな立場になります。下請けは営業などにかける時間を短縮できますが、利益率を確保できるかどうかが課題となります。
またこうした重層下請け構造のなかでは施工責任の所在が曖昧になり、品質や安全性が低下するという問題が発生する可能性もあります。元請け・下請けどちらがいいのかは自分の働き方に合わせて決めるとよいでしょう。
そして、金銭トラブルやパワハラといったトラブルが起こることもあります。今回紹介した内容を参考にトラブルに巻き込まれないよう注意しましょう。トラブルのない安全な現場を目指しましょう。
塗装の下請け業者・協力会社を募集する方法6選や建設業の元請が負う責任の範囲についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
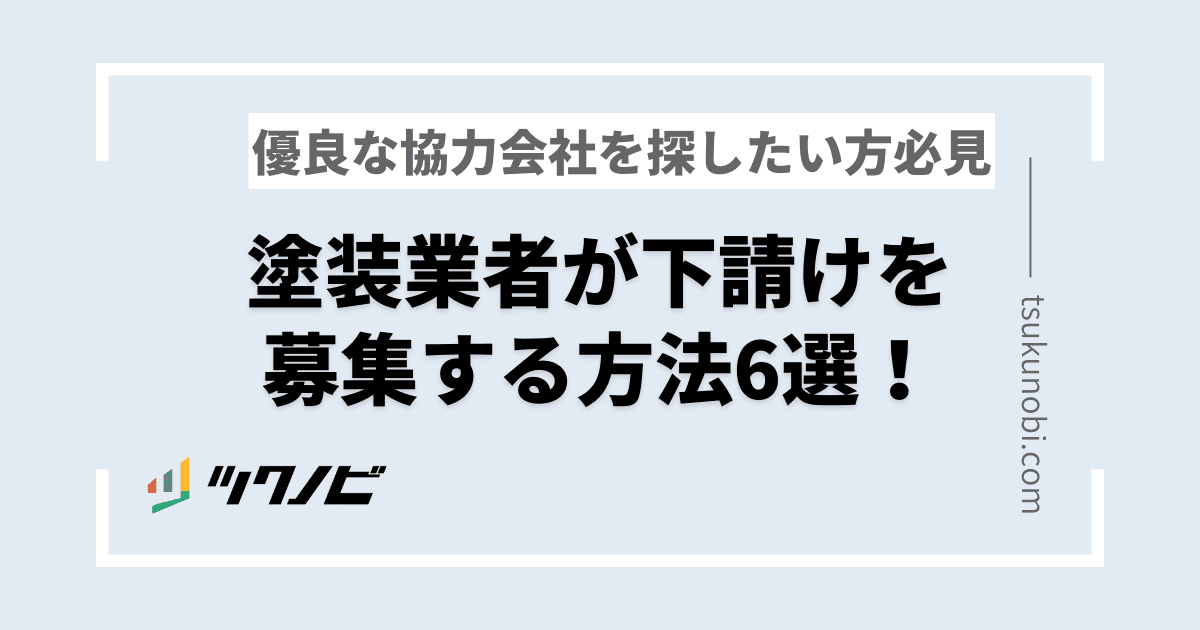 塗装の下請け業者・協力会社を募集する方法6選!優良な協力会社の探し方
塗装の下請け業者・協力会社を募集する方法6選!優良な協力会社の探し方
※弊社の営業代行サービスであるツクノビセールスでは、
【効果が出なければ全額返金プラン】を新たにスタートさせました!

※詳しくは👆👆👆のバナーをクリック!!