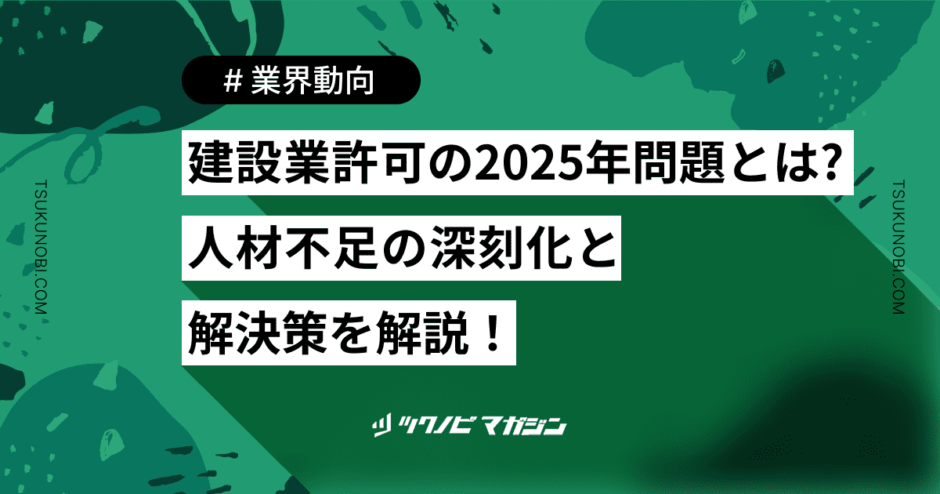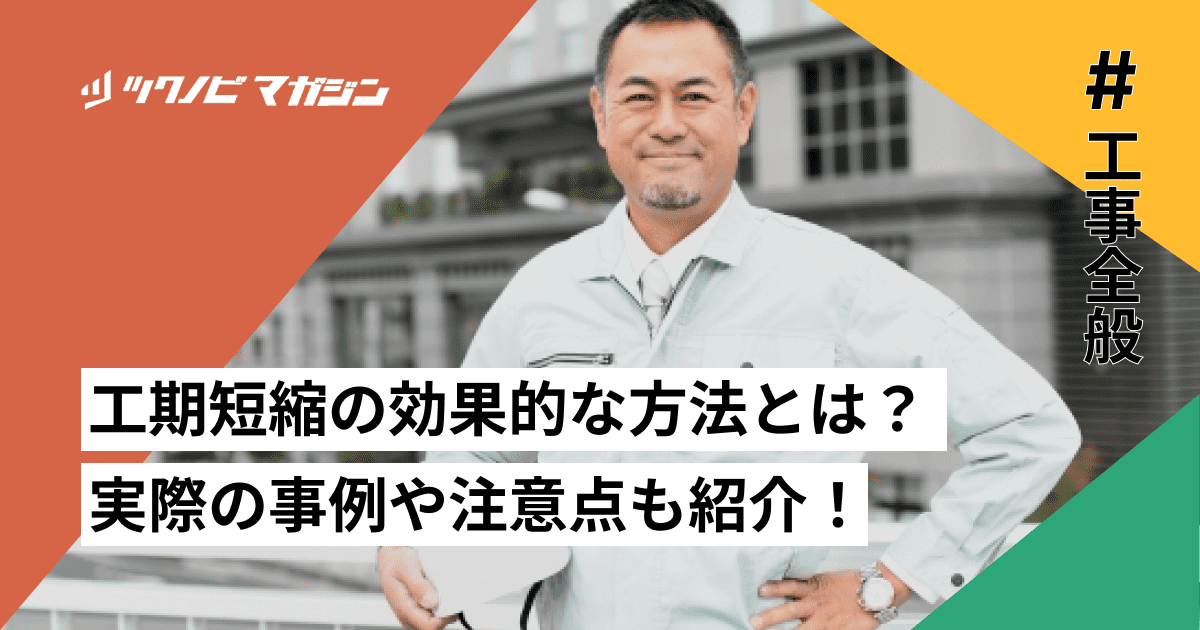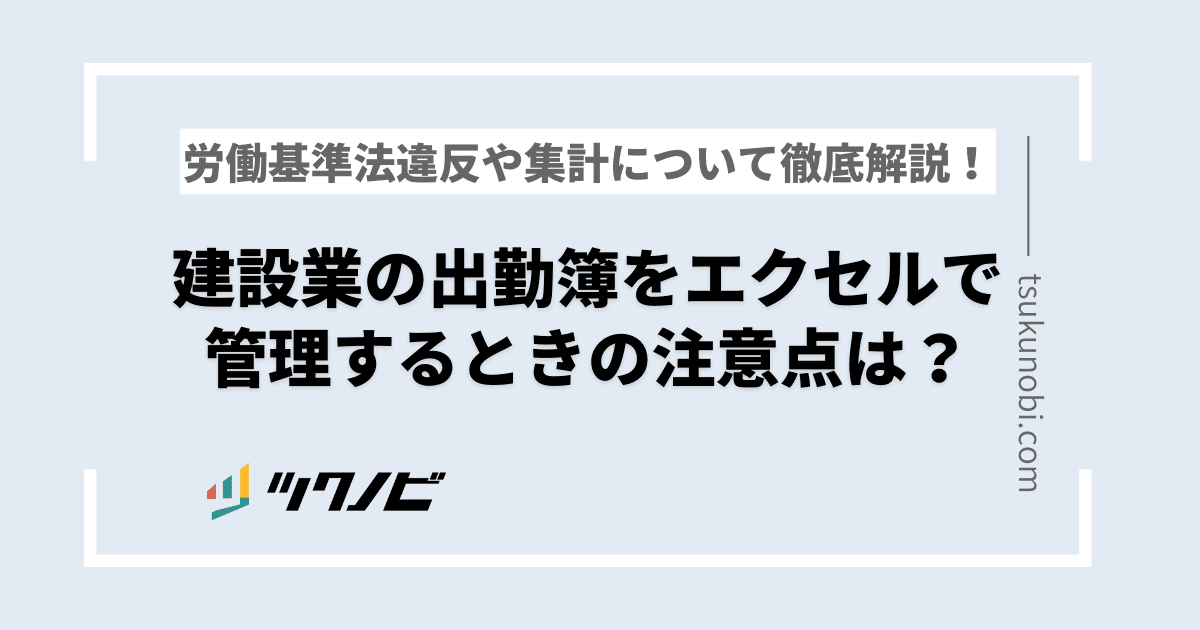※記事内に広告を含みます
皆さんは「2025年問題」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?近年では建設業における人手不足が問題となっていますが、2025年以降にはいっそう深刻な人手不足が予想されています。
そこで今回は建設業における2025年問題と人材不足の解決方法について詳しくご紹介していきます。
ツクノビBPOは、時間のかかる建設業業務を低コストで代行する建設業特化のアウトソーシングサービスです。
CADを活用した工事図面作成や事務作業、書類作成、積算、経理労務などまで幅広い業務に対応しています。詳細はぜひこちらからご確認ください。
2025年問題とはなにか
まずそもそも「2025年問題」とは何でしょうか?
2025年問題は1947年から1949年に生まれたいわゆる団塊の世代が後期高齢者となる境目の年に付随して起こる問題を総称したものです。75歳以上の後期高齢者が2180万人に達することで超高齢化社会が到来し、それに伴って医療費や介護費用の大幅な増加が見込まれます。75歳未満と75歳以上との間の一年間の一人当たりの医療費は約4倍ほどの差があり、現役世代の負担の大幅な増加も予想されます。
建設業における2025年問題とは?
それではこの「2025年問題」は建設業にどのような影響を与えるのでしょうか?
建設業も他の産業と同じく今後10年以内に熟練労働者の退職による深刻な人材不足が予想されます。建設業に従事する労働者の数は年々減少しており、2022年時点で約479万人ほどです。約20年前と比較すると100万人以上も減少しており、人材不足への対策は急務です。
参考:日本建設業連合会
建設業界の現状
建設業では2025年を迎える前の現在でも深刻な人出不足に悩まされています。
続いて建設業界の現状を整理して、現在行われている労働環境改善の施策を幾つかご紹介していきます。
深刻な人手不足
建設業は現状でも深刻な人手不足です。
この背景にはもちろん日本社会の少子高齢化もありますが、建設業が長年抱えている「3K(きつい・汚い・危険)」イメージもまた大きな影響を与えています。企業努力に反して、このイメージがなかなか払拭されないため、若い労働力が業界に流入しにくい現状を抱えています。
データによれば建設業に従事する労働者のうち55歳以上が約36%を占めるのに対して、29歳以下の割合が約12%程と、他の産業と比較して極端に若年層が少ない産業であることがわかっています。
参考:日本建設業連合会
建設キャリアアップシステムの普及
建設業界には建設キャリアアップシステム(CCUS)というものがあり、徐々に普及しつつあります。
建設キャリアアップシステムは国土交通省が推進しているシステムで、就業者の保有資格や経歴をデータとして蓄積する仕組みです。
このデータを個人用のカードにデータとして記録することで、個人の経験やスキルを客観的に評価可能となり、適正な評価、賃金を得ることができます。建設キャリアアップシステムの申請は技能者登録と事業者登録の二種があり、それぞれインターネット上での申請と窓口での申請が可能です。
時間外労働の上限規制
建設業では労働基準法の改正に伴って労働環境が変化しています。
労働基準法の定める現在の労働時間は1日8時間・1週40時間が原則です。この労働時間を超過して労働をさせる場合は36協定という労使協定を結ぶ必要があります。労働基準法第36条に則った協定の締結並びに管轄労働基準監督署への届け出が義務付けられていますが、この36協定によって法定労働時間を超過して月45時間並びに年360時間まで時間外労働をさせることができます。
この時間外労働に関しては2019年の法改正において労働時間の上限が定められましたが、建設業はこの法の適用外業種として猶予が与えられています。
これは建設業という業種が工事に長期の期間を要すること、そして工事が天候などによって左右されやすいことによります。このような猶予を与えられていた建設業界ですが、2024年4月から労働時間の上限規制が適用されます。上限規制が適用されると時間外労働は36協定の通り月45時間、年360時間までとなります。また月45時間を超過する時間外労働の上限は年に6回までとなります。更に年間を通しての時間外労働時間の総時間は720時間までとなります。
建設業では、2024年問題とよばれる課題があります。こちらの記事では、2024年問題について解説しています。
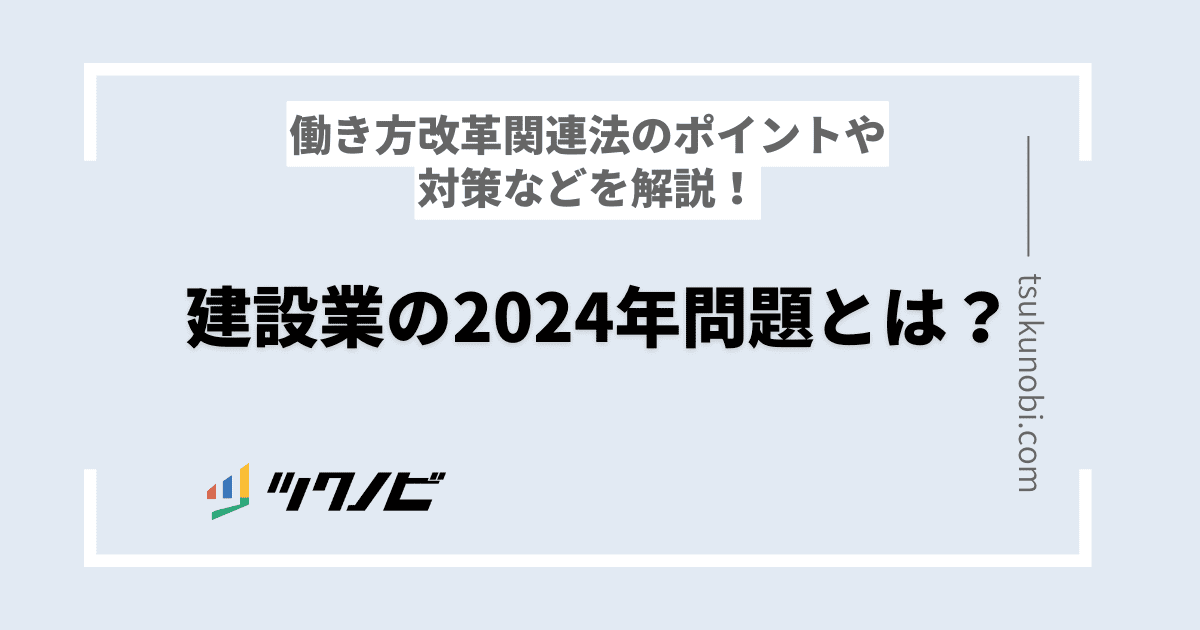 建設業の2024年問題とは?ポイントや対策をわかりやすく解説!
建設業の2024年問題とは?ポイントや対策をわかりやすく解説!
建設業における深刻な人手不足の原因
建設業が慢性的な人材不足であり、そしてこれから一層人材不足になるであろうことには複合的な要因があります。
続いて建設業界の人材不足の代表的な原因について幾つかご紹介していきます。
労働環境の厳しさ
建設業における人手不足の原因には厳しい労働環境があります。
一般的に建設業には昔から「3K」と言われる「きつい・汚い・危険」というイメージがついています。
そして多くの企業が労働環境改善や業界イメージの改善に取り組んでいるものの依然として労働環境の改善が追い付いていない側面もあります。
このような厳しい労働環境も相まって若者が参入しづらい現状があるのです。
高齢化と若手離れ
「労働環境の厳しさ」でご紹介した若者離れに加えて、建設業界は労働人口の高齢化という問題も抱えています。
日本建設業連合会が公開しているデータによれば、建設業界の55歳以降の割合は約36%で、全産業の平均年齢より5%ほど高くなっています。
この労働年齢の高齢化問題は若者離れの問題と密接に関係しています。若者の新規雇用が進まず、若手の離職率が高いことで、結果的に中高年層が辞められずに長く働き続ける現状が続いているのです。
現在の労働の担い手達も今後10年でどんどんと辞めていく年齢に達し、2025年の時点で最大93万人もの技能労働者が不足するとの見通しもあります。若者の新規雇用を促進するためには何よりもまず建設業のイメージを若者が積極的に働きたいと思えるようなものへと変えていく必要があります。
この記事では、建設業で若者離れが当たり前とされている理由について解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
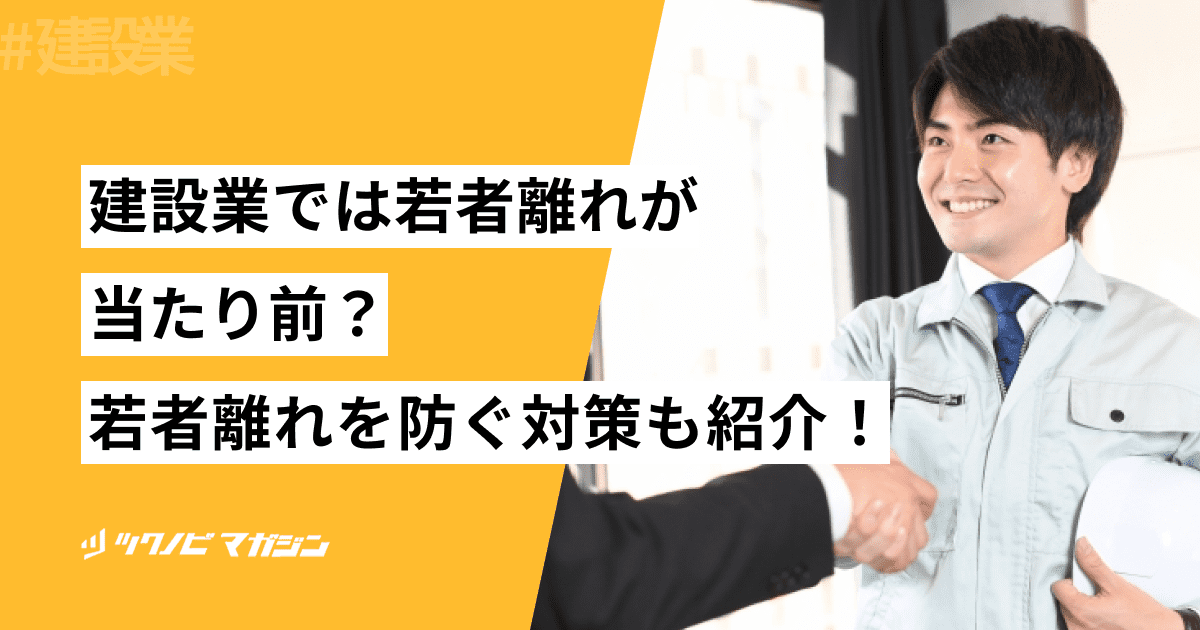 建設業では若者離れが当たり前?理由や人手不足の現状・対策を解説
建設業では若者離れが当たり前?理由や人手不足の現状・対策を解説
建設業の需要拡大
建設業界が人材不足に陥っている背景には、建設業そのものへの需要が拡大していることも一因です。
東京オリンピック、パラリンピックが終わり建設バブルは一段落したものの、依然として建設業には一定の需要があります。
建設業は戸建ての建築以外にもインフラなどの公共工事、災害復興事業など常に需要がある産業です。
建設業における2025年問題の解決策
ここまでは建設業界の人手不足の現状とその原因をご紹介してきました。
続いて2025年以降に生じる人材不足の具体的な解決策をご紹介していきます。
建設業に対するイメージの向上
人材不足を解決するためには建設業そのもののイメージ向上が不可欠です。業界イメージがクリーンなものへと改善されなければ将来の労働力の担い手である若者は業界に参入してこないでしょう。建設業界のイメージ改善のためには官民双方の取り組みが必要です。
以前には国土交通省が主導した建設業イメージアップ戦略実践プロジェクトチーム(CIU)が業界のイメージアップに取り組みました。また大手企業などを中心としてSDGsへの取り組みを通して企業イメージアップや市民見学会などの開催を通して地域交流を図るなど様々な取り組みが見られます。
イメージアップにはSNSの活用がおすすめ
建設業ではとくに若い年齢層の人手不足が深刻です。そうした層へ、建設業に対するポジティブなイメージを持ってもらうにはSNSを活用するのがおすすめです。とくにtiktokは自社の雰囲気や実際に働いている様子などを伝えやすく、求人採用媒体として高い効果が見込めます。
「tiktokの運用方法が分からない」「採用に力をいれたい」という場合は採用に特化したサービスを利用するのもおすすめです。バズステップ採用は、tiktok採用に特化したサービスで、2か月で10人の採用に至ったという実績もあります。
IT・ICT・DXの利用
新しい人材を取り込むだけではなく、作業効率を上げて既存の人数でも十分に回せる現場体制を構築することも重要です。
人材不足を埋めるために近年注目されているものはIT(情報技術)やICT(情報通信技術)・DX(デジタルトランスフォーメーション)といったツールです。例えばドローンなどを測量に導入することで人力で行うよりも作業効率を飛躍的に高めることができます。
それ以外にはICT建機と呼ばれる情報通信技術を搭載した建機の活用などがこれにあたります。ICT建機は操縦などを測量したデータなどをもとに自動で行うことが可能なため、一部の熟練した職人のみが可能であった重機のコントロールを誰でも行えるようになります。こうした建設現場におけるICTの活用に関しては、国土交通省が「i-Construction」という形で後援しています。
参考: 国土交通省
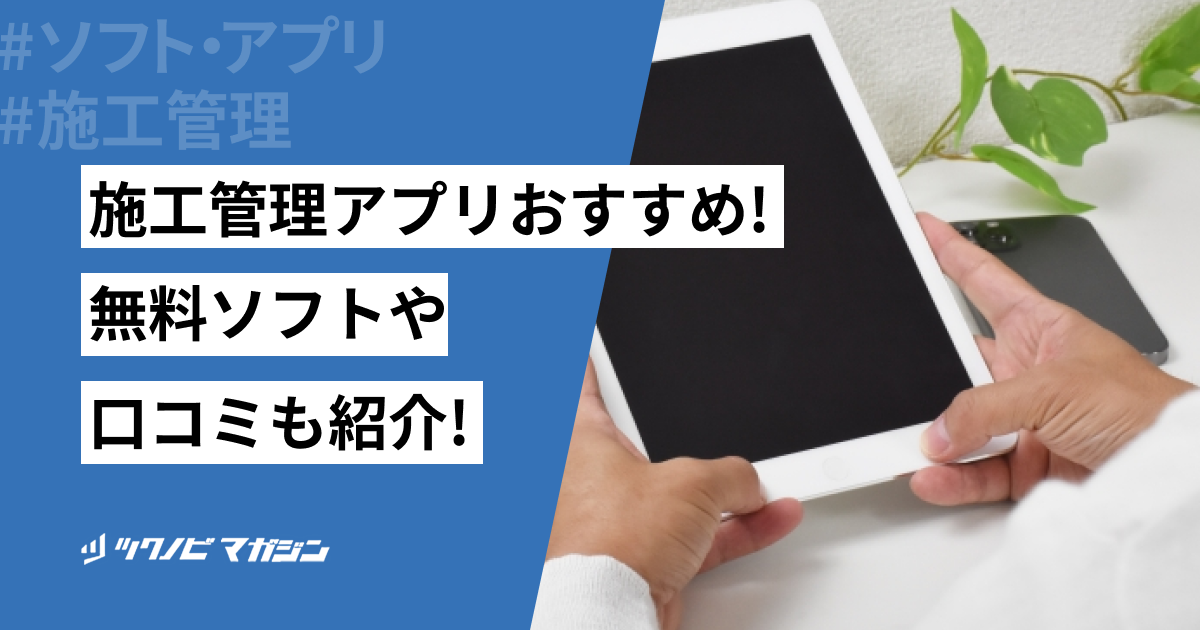 施工管理アプリおすすめ13選!導入するメリットや選び方も解説
施工管理アプリおすすめ13選!導入するメリットや選び方も解説
熟練職人の育成
若手の新規人材を受け入れるためには、若者にとって魅力的なキャリアパスを提示することが重要です。せっかく若手が入社しても賃金や労働環境の問題ですぐに辞めてしまっては労働人口の問題は解決しません。しっかりと若手が定着できるような労働環境を整備して、熟練工へと成長できるようなキャリアパスを提供することが重要です。
現在では多くの事業者が建設キャリアアップシステム(Construction Career Up System)の導入を開始しています。技能に対して正当な賃金が支払われればおのずと人材定着率が上昇するでしょう。
人材の育成には動画システムの活用がおすすめ
人材の育成を行う際には動画を活用するのがおすすめです。動画は場所を問わず研修を実施でき、一度作れば何度でも繰り返し使えます。
「いまいちどうやって動画を活用した社内教育を進めていけばいいのか分からない」という方には、動画システム構築・サポートを行っているnecfru(ネクフル)の利用がおすすめです。
働き方改善
近年では「働き方改革」という言葉に代表されるようにワークライフバランスを重視した働き方が注目を集めています。
現場作業が多くなる都合、リモートワークとはいかないかもしれませんが生産性や効率を高めるなど労働股間を短縮する施策を打って、労働環境の改善していくことが重要です。
助成金を活用する
建設業界で人材を確保するためには、助成金を活用することも視野にいれましょう。
厚生労働省が支援する建設業に関する助成金は主に
- トライアル雇用助成金
- 人材確保等支援助成金
- 人材開発支援助成金
の3つから構成されており、さらに細かく12のコースが設定されています。
トライアル雇用助成金は若年者や女性の積極的な雇用に関する助成金です。
人材確保等支援助成金は、技能労働者の育成を通して、建設業の雇用の安定化を助成するための制度です。
人材開発支援助成金には令和4年から新たに建設キャリアアップシステム普及促進コースが新設されました。キャリアシステムを活用する事業者も助成を受けられます。
助成金はコースごとに助成を受ける事業者の条件が異なるため、希望する助成金の要件の確認が重要です。また、助成金によっては人材雇用の一定の取り組みを実施後に申請を行う場合もあります。申請と審査をスムーズに行うには社労士などの専門家に相談するのがおすすめです。
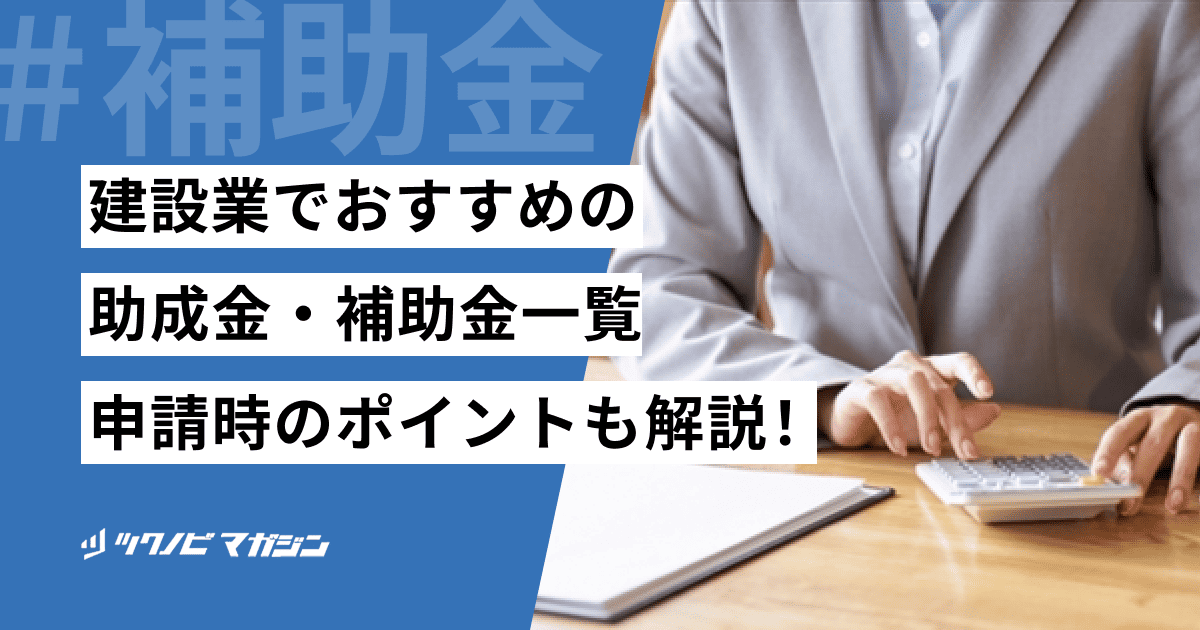 【2024年】建設業でおすすめの助成金・補助金一覧!申請時のポイントについても徹底解説!
【2024年】建設業でおすすめの助成金・補助金一覧!申請時のポイントについても徹底解説!
外国人の採用
不足する人材を補うために外国人労働者を登用することも手段の一つです。
国土交通省が公開しているデータによれば、2021年度の建設分野における外国人労働者は約11万人と全産業の6%ほどを占めています。特定技能外国人制度に関しては2019年に運用が開始され、年々受け入れ人数が増加しています。
参考:国土交通省
メリット
外国人労働者を受け入れる一番のメリットは、何よりも不足している人材を埋められる点です。また労働意欲が高く、勤勉であるため労働環境に馴染み適応しやすいという特徴もあります。さらに、特定技能外国人の採用に特化した支援サービスもあるため、どの企業でも外国人労働者の雇用がしやすい環境になりつつあります。
注意点
続いて外国人労働者を雇用する際の注意点をご紹介します。
外国人労働者を雇用する際には、雇用者が正式な在留資格を得ているかどうかの確認が重要です。仮に雇用した外国人労働者が不法就労であった際には、事業者が意図しない場合でも不法就労助長罪に問われて、3年以下の懲役か300万円以下の罰金刑が科される可能性があります。
このような外国人労働者に特有のトラブルを避けるためには、外国人労働者に特化した人材派遣サービスを活用することがおすすめです。こうしたサービスでは在留資格や外国人雇用状況の届出に関するサポートを行ってくれるため、スムーズな人材雇用が可能です。
特定技能外国人に特化した採用・支援サービス
リフト株式会社では特定技能外国人に特化した採用・支援サービスを行っています。最短2週間で候補者の案内が可能で、定着率が90%以上と高いのが特徴です。特定技能の10個の義務的支援もしっかりサポートしているため、初めて特定技能外国人を採用したい、という企業にもおすすめです。
建設業に未来はない?建設業の今後
今回ご紹介してきた人材不足の問題なども相まって、建設業界の今後について不安を抱かれている事業者の方も多いかと思います。人材問題の解決方法や、建設業界の今後の展望についてはこちらの記事で詳しくご紹介していますので是非参考にしてみて下さい。
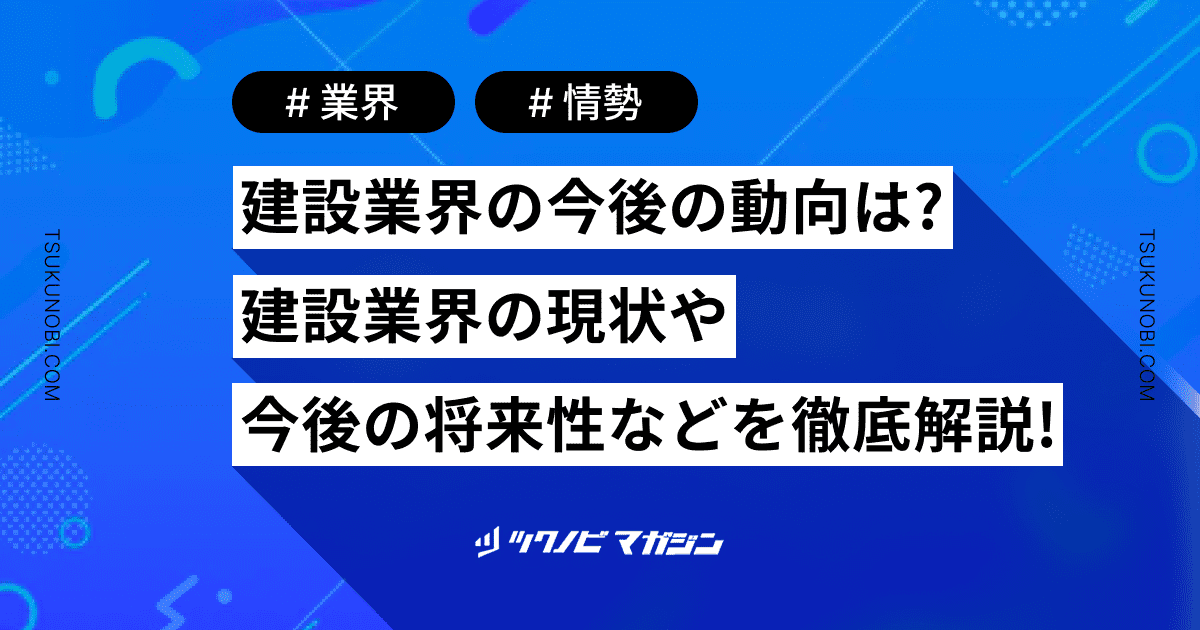 【2024】建設業界の今後の動向は?建設業界の現状や今後の将来性などを徹底解説!
【2024】建設業界の今後の動向は?建設業界の現状や今後の将来性などを徹底解説!
建設業の人手不足解消ならツクノビBPOがおすすめ
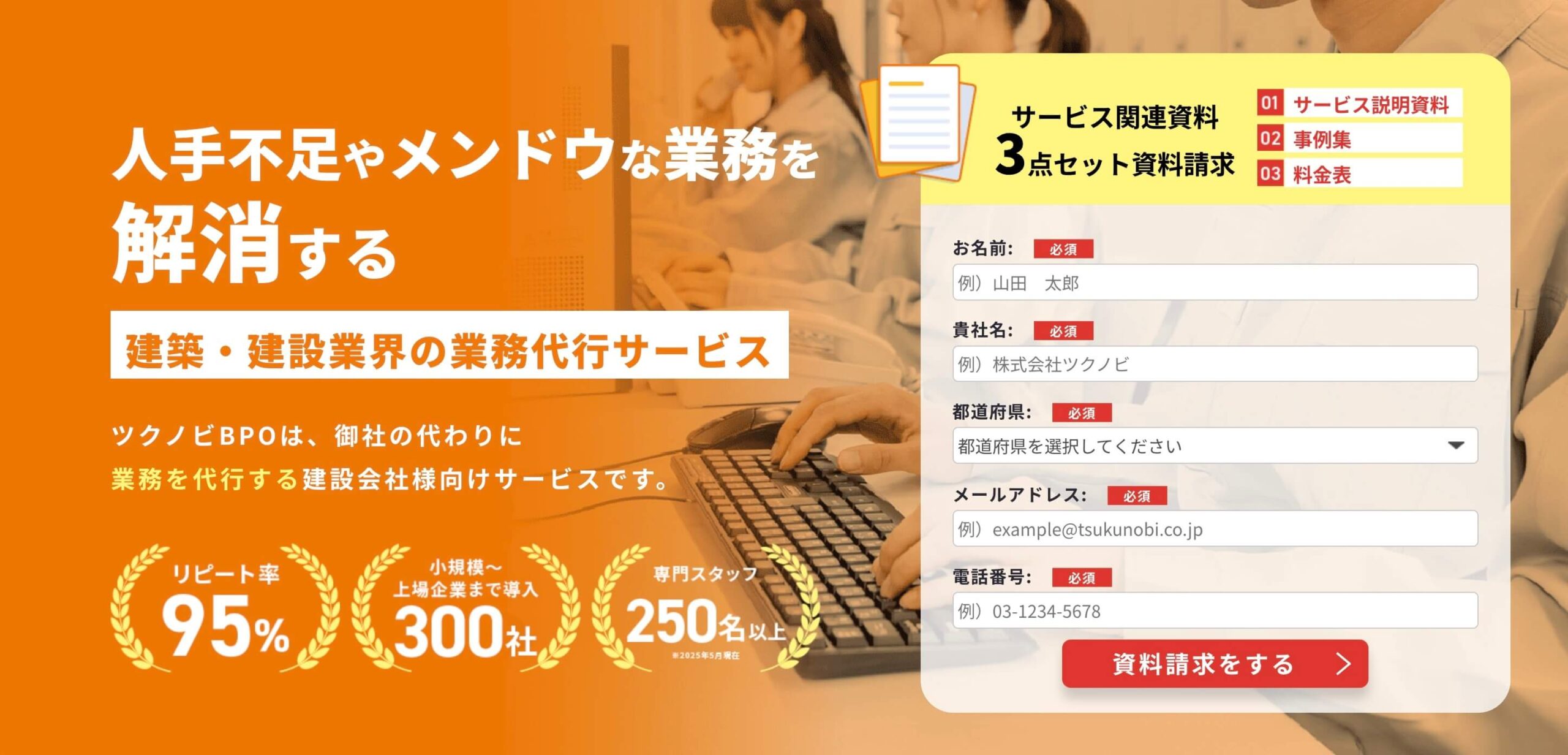
建設業の人手不足を解消するためには、アウトソーシングサービスの利用もおすすめです。
従業員のリソースがひっ迫している場合や、業務に対応できる人材が不足している場合などは、アウトソーシングサービスを活用すると、少ない工数で業務を実行できます。BPOサービスでは、専門的な知識を持っているスタッフが対応するため、さまざまな業務をスムーズに進められます。
弊社では、建設業の業務に対応している建設業特化のBPOサービス「ツクノビBPO」を提供しています。書類作成や図面の作成、積算業務など、幅広い業務を代行できます。ツクノビBPOでは、倍率200倍の選りすぐりの専任スタッフが対応いたします。
リソース不足を解消したい方は、ぜひこちらからお問い合わせください。
【まとめ】業務効率化や人材育成を積極的に行って2025年問題を解決しよう!
ここまで建設業界における人材不足の現状とその解決方法についてご紹介してきました。建設業界に限らず人材不足はどの業界も抱えている問題ではありますが、とりわけ建設業では特に若者の新規雇用数を増やすことが喫緊の課題となっています。業界イメージの改善やIT・ICT・DXの活用による労働環境改善を通して、若者が積極的に働きたいと思えるような環境を整備していきましょう。
建設業に未来はないと思われている理由と将来性についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
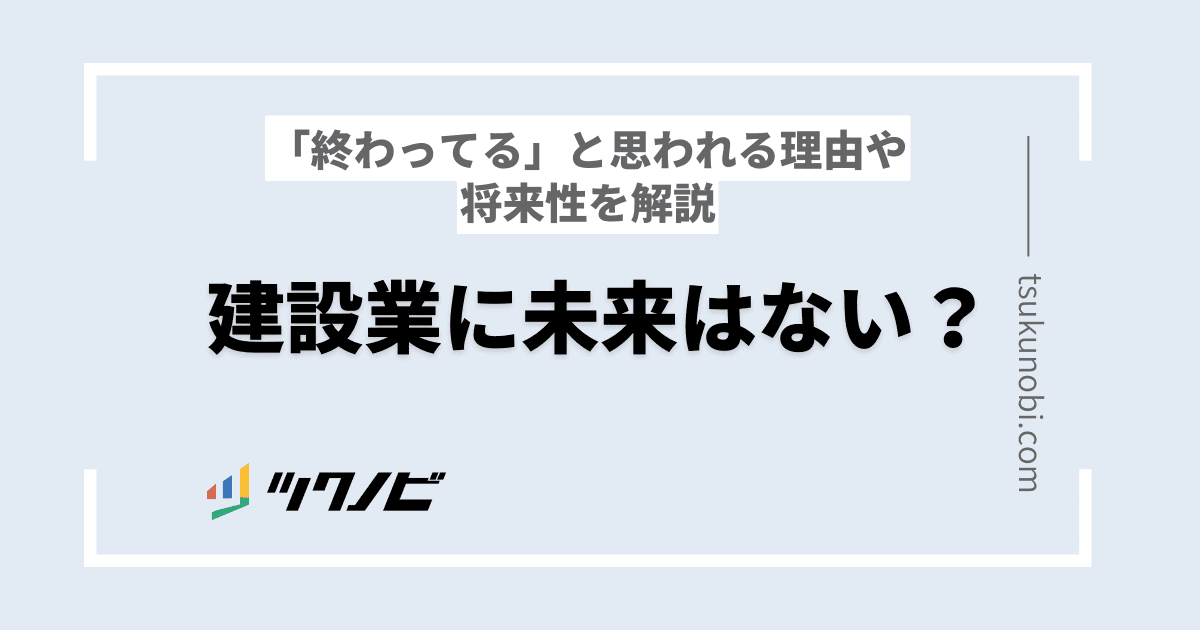 建設業に未来はない?「終わってる」と思われる理由や将来性を解説
建設業に未来はない?「終わってる」と思われる理由や将来性を解説
※弊社の営業代行サービスツクノビセールスは、
【効果が出なければ全額返金プラン】を新たにスタートさせました!  ※詳しくは👆👆👆のバナーをクリック!!
※詳しくは👆👆👆のバナーをクリック!!