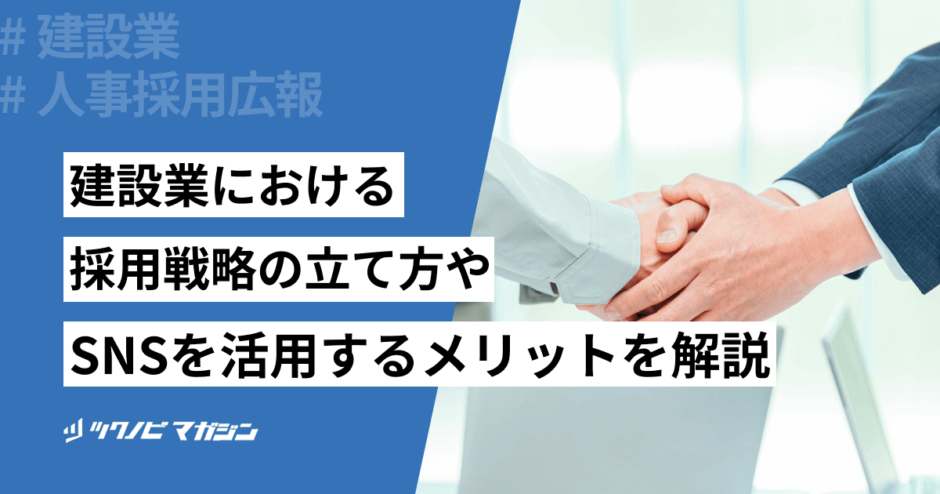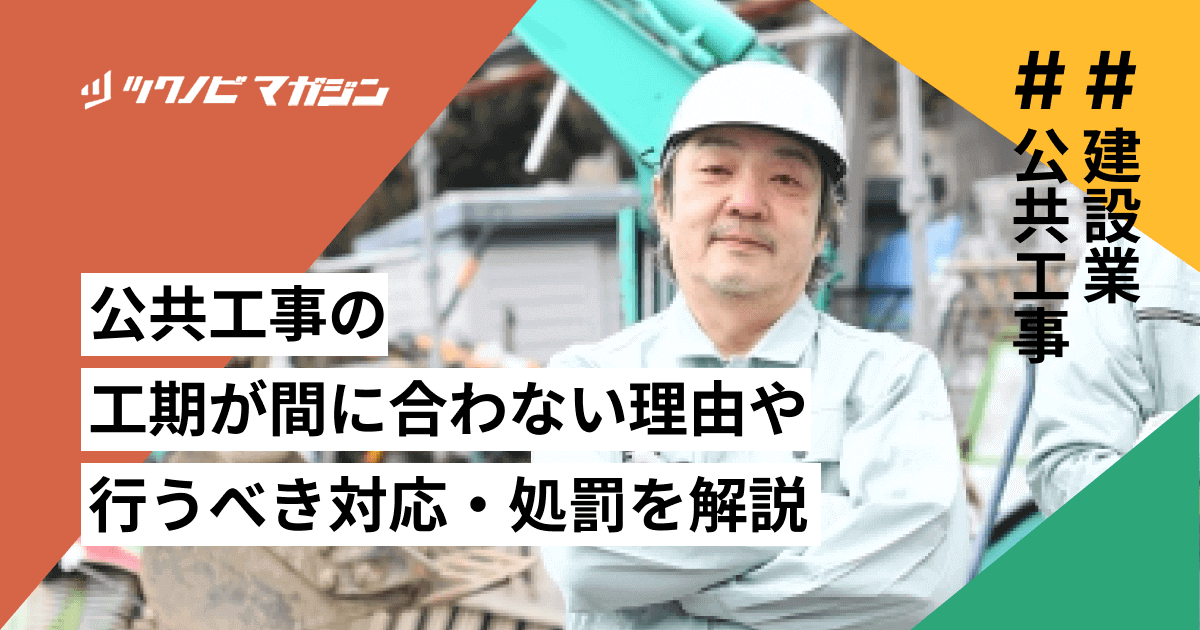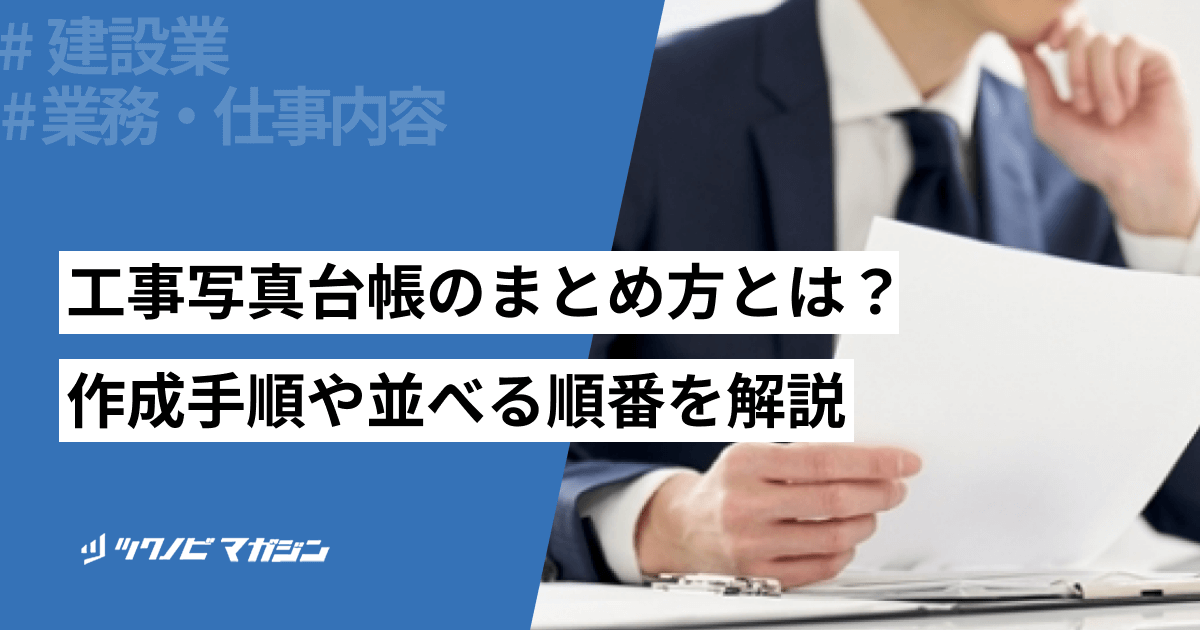※記事内に広告を含みます
建設業界では深刻な人手不足により、必要な人材の確保(採用)が経営上の大きな課題となっています。とくに、若年層の減少や高齢化で現場の担い手不足が一層深刻です。従来型の採用活動だけでは人材獲得が難しい中、今回は効果的な採用戦略の立て方とその実践方法を、SNS活用など新しいアプローチも含めて紹介します。
建設業界の現状
建設業の有効求人倍率は2024年時点で約4.15倍に達し、求人に対し求職者が圧倒的に不足しています。
また、労働人口も長期的に減少しています。建設業就業者数は1997年の約685万人をピークに減少が続き、2022年には約479万人とピーク時の約7割程度にまで落ち込みました。
年齢構成を見ると、29歳以下が11.7%なのに対し、60歳以上は25.7%です。
このように、若手不足と高齢化が進んでおり、今後さらに人手不足が深刻化すると懸念されています。
参照:厚生労働省「職業別<中分類>常用計 有効求人・求職・求人倍率 (令和6年12月)」/国土交通省「建設業を巡る現状と課題」
【建設業必見】求人に応募が来ない理由についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
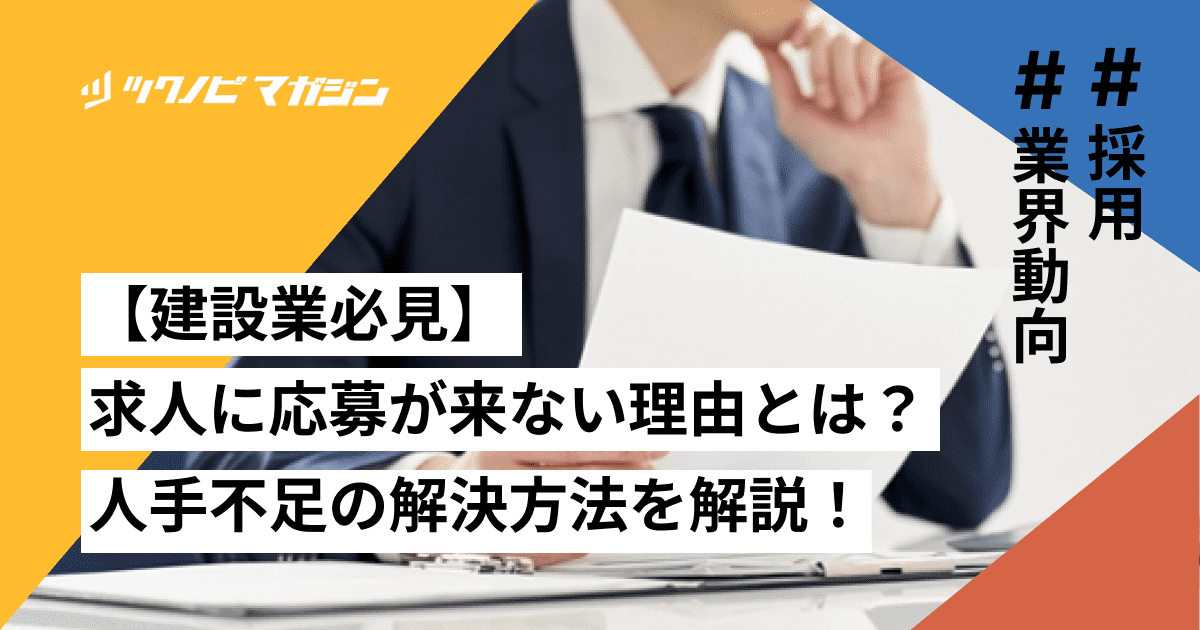 【建設業必見】求人に応募が来ない理由とは?人手不足の解決方法を徹底解説
【建設業必見】求人に応募が来ない理由とは?人手不足の解決方法を徹底解説
建設業が行うべき採用戦略
建設業が行うべき採用戦略は以下のとおりです。
- SNSを活用する
- 求人サイトを活用する
- フリーペーパーを活用する
- アウトソーシングサービスを活用する
- 女性の採用を積極的に行う
- 人材を紹介してもらう
複数の採用戦略を組み合わせることで、より効果的な採用活動を実現できるでしょう。それぞれの採用戦略を下記で詳しく解説します。
SNSを活用する
建設業界でもSNSを活用した採用が広がっています。X(Twitter)やInstagram、TikTok、YouTubeなどの企業アカウントで自社の現場や社員の様子を発信し、社風や魅力を直接アピールできます。
とくに、若い世代へのアプローチに有効です。
たとえば、ある建設会社では、それまでの求人サイト頼みの採用からSNS中心に転換した結果、5年間で14名の新入社員を採用できました。
また、SNSによって遠方の人材にも自社を知ってもらえるため、地元以外からの応募が期待できる点も魅力です。
このように、コストをかけず新しい層にリーチできるSNSは、建設業の採用戦略において積極的に活用すべき手法です。
参照:株式会社江口組
求人サイトを活用する
Indeedやマイナビ転職など大手の求人サイトは、多くの求職者が利用するため応募を集めやすい手段です。
建設業向けに特化した求人サイト(GATEN職、建設転職ナビ)を活用すれば、よりターゲット層に絞った募集も可能です。求人サイトは掲載料や成功報酬など費用がかかりますが、その分、広範囲から人材を募ることができます。
魅力的な求人内容を掲載すれば短期間で複数の応募が期待でき、新たな人材との出会いの機会が広がります。
ただし、他社の求人も多数掲載されるため、求職者の目に留まるような工夫が必要です。
建設業に強い求人サイト18選についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
 建設業に強い求人サイト18選!種類や効果的に活用するポイントを解説
建設業に強い求人サイト18選!種類や効果的に活用するポイントを解説
フリーペーパーを活用する
フリーペーパーを活用すると、地域に密着した採用活動ができるためおすすめです。
コンビニエンスストアや駅など人が多く訪れる場所で配布され、地域の求職者へダイレクトに情報を届けられます。
また、インターネットをあまり使わない層にも手軽に情報を届けられることもメリットです。
建設業に馴染みが薄い人々の目に触れやすく、潜在的な人材を発掘できる可能性も高まります。地域への貢献や職場の雰囲気、福利厚生の手厚さなどを具体的に伝えることで、求職者が「ここで働きたい」と感じるような工夫が必要です。
ただし、ターゲットの年齢層や住んでいる地域に合った場所をしっかりと選び、どのエリアに配るのか、どの媒体が効果的かをしっかりと決める必要があります。
アウトソーシングサービスを活用する
アウトソーシングサービスを利用すると、採用活動がスムーズになり、人材確保もしやすくなります。
専門業者に業務の一部を委託すれば、自社スタッフは採用戦略の企画立案や面接実施などの重要業務に集中できます。また、専門企業が持つ豊富なノウハウを生かし、応募者管理や面接調整などを的確に進めることが可能です。
専任の採用スタッフを持てない中小企業にとっては、採用の質向上や業務負担軽減の大きなメリットが得られます。
ただし、委託先企業との密なコミュニケーションや連携体制を構築し、業務内容や進捗管理のズレを防ぐことが重要です。
女性の採用を積極的に行う
建設業界では、女性採用の積極的な推進が必要です。
従来、建設業は男性主体の職場環境でしたが、近年ではDXや機械化が進み、女性が活躍できる職種や業務が増えました。女性が持つきめ細かな作業やコミュニケーション力、協調性は、現場管理や顧客対応など幅広い業務で発揮されます。
女性を積極的に採用すると、職場環境の改善につながり、業界全体のイメージアップにもつながります。
さらに、育児休暇や時短勤務制度などの働きやすい環境整備を進めれば、女性が長く働き続けられる職場として、定着率の向上にも効果的です。
建設企業が女性の活躍推進を単なる採用目的で終わらせるのではなく、長く会社が成長していくための重要な柱として考えることが大切です。
人材を紹介してもらう
自社の従業員や取引先などから人材を紹介してもらう方法もおすすめです。
社内でリファラル採用(社員紹介制度)を整備し、知人や元同僚で適任者がいれば推薦してもらうと、企業文化に馴染みやすくミスマッチの少ない人材を確保しやすくなります。実際に、建設業界では信頼できる仲間の紹介で採用に至るケースも多々あります。
また、人材紹介会社(転職エージェント)を利用すると、専門のコンサルタントが候補者を見極めて紹介してくれるため、採用ニーズに合った人材に出会える可能性が高まります。
ただし、紹介手数料として採用者の年収の20〜30%程度といった成功報酬が発生するため、コストとのバランスを考慮しましょう。
建設業が採用に苦戦する理由
建設業が採用に苦戦する理由には、業界特有の労働環境や、若年層との求人媒体のミスマッチなどがあります。さらに、昨今の働き方の多様化や少子高齢化の進行も、採用を困難にする大きな要因です。
また、業界イメージの悪さも影響しており、求職者の建設業離れが加速しています。こうした課題をそのままにしていると、建設業界の人手不足はますます深刻になってしまうでしょう。
ここでは、建設業が採用に苦戦する理由について、詳しく解説します。
労働環境に過酷なイメージがあるため
建設業は屋外作業が多く、身体的な負担が大きい業務が中心です。そのため、「過酷」「危険」といったイメージが強く、求職者の敬遠材料になっています。
また、メディアによる現場事故の報道もネガティブな印象を助長しており、業界全体の魅力を損なっています。
実際、多くの企業で安全対策や作業環境改善が進んでいますが、一般への認知度は低く、古いイメージが払拭されていません。
このような現状を変えるためには、現場の安全性向上や働きやすさへの取り組みを広くアピールする必要があります。そのため、積極的に情報を発信し、マイナスイメージを少しずつでも改善していくことが大切です。
求人媒体がマッチしていないため
求人媒体がマッチしていないと、思うように応募が集まりません。
例えば、若年層を採用ターゲットとした場合、新聞や雑誌の紙媒体はほとんど効果はありません。反対に、SNSやオンライン求人サイトを使えば、より多くの人に関心を持ってもらいやすくなります。
自社のターゲット層がどのようなメディアを利用しているかを詳細に分析し、それに合わせた媒体選択が重要です。
また、複数の媒体をうまく組み合わせて使い、いろいろな求職者の目に留まるような工夫も大切です。
働き方が多様化しているため
近年は働き方が多様になってきていることも、建設業界で採用が難しくなっている理由のひとつです。
とくに、リモートワークやフレックス制など、自由度の高い働き方を望む人が増えています。
これに対し、建設業は現場作業が中心で、勤務時間や場所の制約が大きい業種です。その結果、働き方を重視する人材にとっては、建設業界への魅力が薄れてしまいます。
これからの時代、建設業もフレキシブルな勤務形態や現場作業以外の業務のリモート化など、柔軟な働き方の導入を検討すべきです。時代に合わせた働き方改革が、求職者の興味を引き、採用力向上につながります。
若者離れと高齢化が進んでいるため
少子高齢化に伴う若者離れと業界の高齢化が、建設業の採用を困難にしています。現在、建設業界では高齢の技術者の退職が目立つようになってきており、若い世代の新規入職者は徐々に減ってきています。
若者が少ないため、若年層は同年代の仲間が少ない職場環境に不安を感じ、就業を避ける傾向があるのです。
このような問題に対応するためには、若手の採用を前提とした職場環境整備や積極的な若者向けのPR活動が必要です。業界内で若い世代が活躍している様子を積極的に伝え、若者にとって魅力的な職場環境を作っていく必要があります。
建設業が採用戦略を立案する手順
建設業における採用戦略の立て方は、以下の4つです。
- 採用計画の方向性を決定する
- 採用したいターゲットを明確にする
- 採用方法を選定する
- 採用活動を開始する
それぞれの立て方を下記で詳しく解説します。
1.採用計画の方向性を決定する
採用計画の方向性を決めるにあたっては、経営方針や事業計画を踏まえ、何のためにどの部署に何人の人材が必要かを洗い出します。
人手を増やすという漠然としたものではなく、新規事業への対応や現場の世代交代など明確な採用目的を設定しましょう。その上で、必要な人員数や採用時期、採用にかけられる予算などを検討します。
また、活用する採用チャネル(ハローワーク、求人サイト、紹介会社)もこの段階で決めておきましょう。さらに、できれば現場責任者や従業員から人手に関する意見をヒアリングし、計画に反映させましょう。
採用の全体像を事前に描いておけば、無計画な採用による予算超過や人員過剰を防げます。
2.採用したいターゲットを明確にする
採用計画が定まったら、次に求める人物像(ターゲット)を具体的に定義しましょう。「責任感がある」「真面目」など抽象的な表現ではなく、保有資格や経験年数、仕事に対する価値観、性格面などをできるだけ明確に言語化しましょう。
たとえば、「未経験でも建設業に興味と体力がある20代前半の人材」や「職人経験があり高齢の先輩とも円滑にコミュニケーションできる人」、「施工管理経験5年以上で現場を任せられる即戦力」など、採用したい人材像をイメージしてください。
また、自社の社風や現場の雰囲気に合った人かどうかもポイントです。ターゲットを具体化すると、採用方法の選定や採用後のミスマッチ防止に役立ちます。
3.採用方法を選定する
ターゲット像が固まったら、人材に届く採用手法を検討しましょう。従来からあるハローワークへの求人申込、合同企業説明会への参加、求人広告の掲載に加え、近年ではインターネットやSNSの活用も必須です。
若年層を狙うならInstagramやTikTok、経験者なら専門の求人サイトや転職エージェントなど、ターゲット層に合ったチャネルを選びましょう。
建設業に特化した求人サイトや、Wantedlyのように企業文化を訴求できるサービスの活用もおすすめです。必要に応じて人材紹介会社(転職エージェント)や派遣会社の利用も検討しましょう。
複数の手法を組み合わせると、幅広い人材を獲得できます。
4.採用活動を開始する
採用計画と方針が固まったら、いよいよ採用活動の開始です。
作成した求人情報を各種媒体に掲載したり、SNSで発信したりして、理想の人材に出会えるまで粘り強く取り組みましょう。
また、求人票ではターゲットに響く自社の強みを十分に伝えることも意識しましょう。すぐに応募が来る場合もあれば、なかなか集まらない場合もあります。
採用には時間がかかる可能性があるため、長期戦も見据えて、通常業務との両立を図りながら計画的に進めることが大切です。
一定期間試して応募が集まらない場合は、求人内容や手法に見直すべき点がないか検証しましょう。必要に応じて戦略を修正し、採用成功に向けて随時対応しましょう。
建設業が採用戦略を成功させる方法
採用戦略は、立案して実行すれば必ず成果が出るというものではありません。建設業が採用戦略を成功させるためには、いくつか重要なポイントを押さえる必要があります。ここでは、建設業が採用戦略を成功させる方法について解説します。
働き方を改善する
建設業の年間労働時間が全産業平均より360時間以上長く、完全週休二日制を導入していないという指摘があります。
そのため、働き方改革の推進による労働環境の改善が求められています。
週休二日制の導入や残業時間の削減、安全管理の徹底など、労働環境の向上に取り組みましょう。職場の待遇や働きやすさが向上すれば、求人への応募意欲も高まり、定着率の向上にもつながります。
参照:厚生労働省「建設業における時間外労働の上限規制について」
自社の魅力が伝わる求人票を作成する
自社の魅力がしっかり伝わる求人票を作ることは、建設業で人材を確保するためにとても重要です。
建設業は職場環境や仕事内容にネガティブなイメージが持たれることが多く、求職者が敬遠しやすい業界です。そこで、求人票には仕事内容の具体的な説明を詳しく記載し、明確な業務内容や役割分担を伝えます。
また、充実した福利厚生や資格取得支援制度、キャリアアップの道筋など、自社の強みもわかりやすく提示しましょう。
さらに、実際に働いている社員のインタビューや現場写真などを掲載すると、求職者が企業の雰囲気を具体的にイメージでき、安心感を与えられます。
自社ならではの特徴や良さを具体的にわかりやすく伝えれば、求人票を見る人が増え、応募につながりやすくなります。求人票はただの募集要項ではなく、自社の魅力を伝える重要な広報ツールと捉え、工夫を凝らしましょう。
オンラインの採用活動を導入する
オンラインの採用活動を導入すると、求職者への訴求力が大幅に高まります。
近年の求職者はスマートフォンやパソコンを中心に求人情報を収集し、応募検討を進めています。そのため、オンライン面接やウェブ説明会などを活用すれば、時間や場所の制約を超え、幅広い層に効率よく情報を届けることが可能です。
また、企業の現場風景や社員インタビュー動画を公開するなど、視覚的に職場環境を伝える工夫も効果的です。
オンラインツールを活用した応募書類の一元管理や選考プロセスの効率化も可能となり、採用担当者の負担を軽減し、質の高い選考を行えます。
オンラインを効果的に活用した採用活動は、求職者との接点を増やし、企業の採用競争力を飛躍的に向上させます。
このように、建設業界も積極的にオンラインを活用し、採用環境を改善しましょう。
建設業の人手不足解消ならツクノビBPOがおすすめ
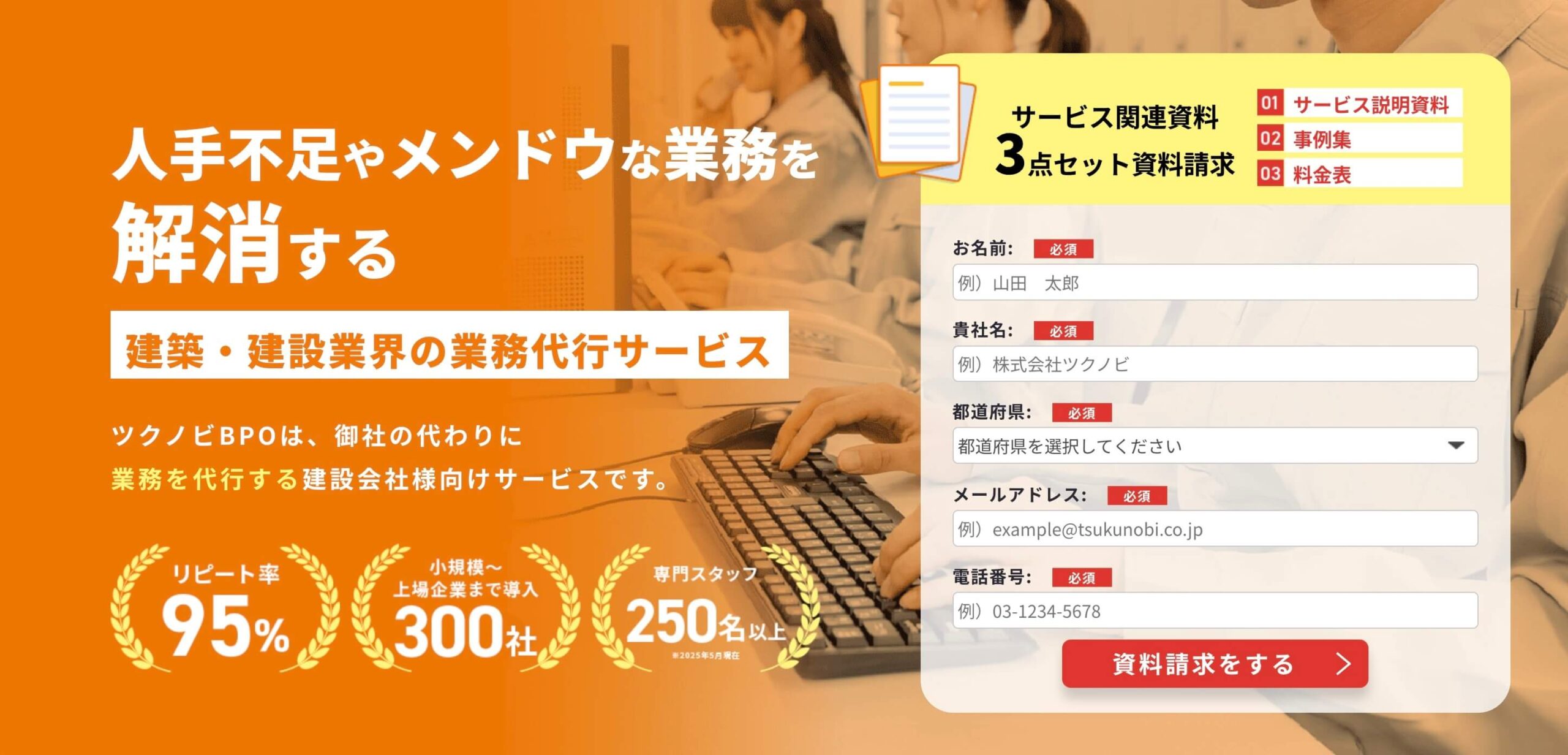
建設業の人手不足を解消するためには、アウトソーシングサービスの利用もおすすめです。
従業員のリソースがひっ迫している場合や、業務に対応できる人材が不足している場合などは、アウトソーシングサービスを活用すると、少ない工数で業務を実行できます。BPOサービスでは、専門的な知識を持っているスタッフが対応するため、さまざまな業務をスムーズに進められます。
弊社では、建設業の業務に対応している建設業特化のBPOサービス「ツクノビBPO」を提供しています。書類作成や図面の作成、積算業務など、幅広い業務を代行できます。ツクノビBPOでは、倍率200倍の選りすぐりの専任スタッフが対応いたします。
リソース不足を解消したい方は、ぜひこちらからお問い合わせください。
【まとめ】建設業の採用戦略は自社の強みや魅力を理解し適切な方法で行おう!
建設業界の人手不足に対し、計画的な採用戦略を立てて実行してください。
採用計画の策定からターゲット設定、手法の選定・実施までを戦略的に進め、ハローワークや求人サイト、SNSなど複数のチャネルを駆使しましょう。
また、働き方改革による職場環境の改善や採用活動のPDCAによる継続的な改善も、採用成功につながります。自社に合った採用戦略を構築し、将来を担う人材を着実に確保していきましょう。
建設業の採用が厳しい理由や建設業での人材採用のコツなどについてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
 建設業の採用が厳しい理由や増やすための対策・採用方法を解説!
建設業の採用が厳しい理由や増やすための対策・採用方法を解説!
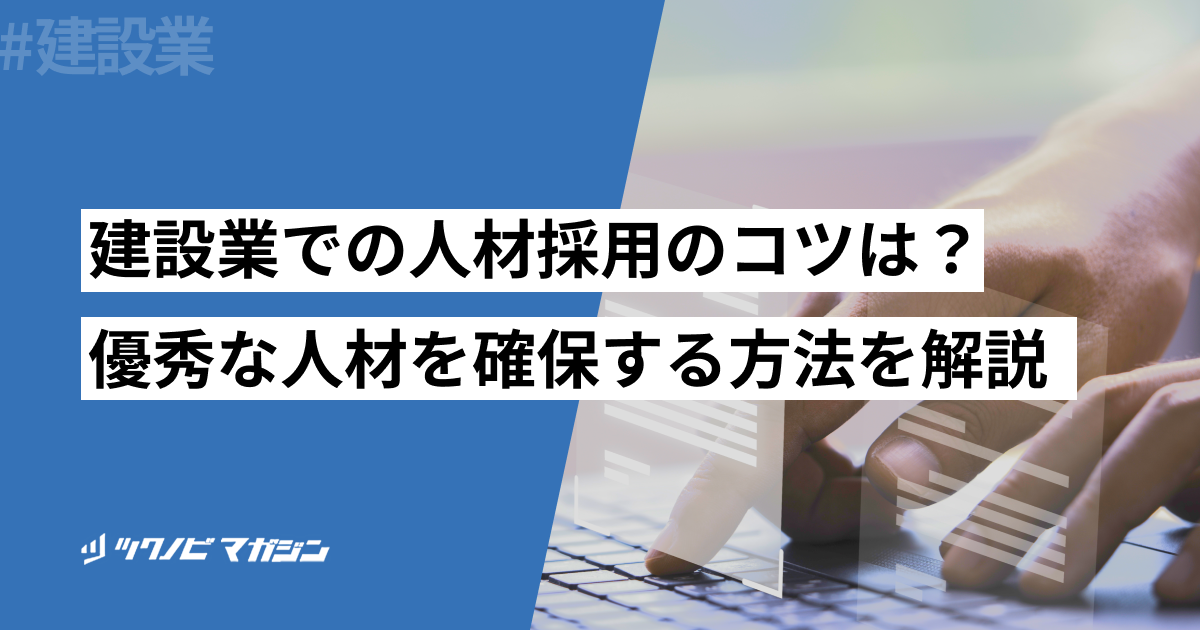 建設業での人材採用のコツは?優秀な人材を確保する方法を解説
建設業での人材採用のコツは?優秀な人材を確保する方法を解説