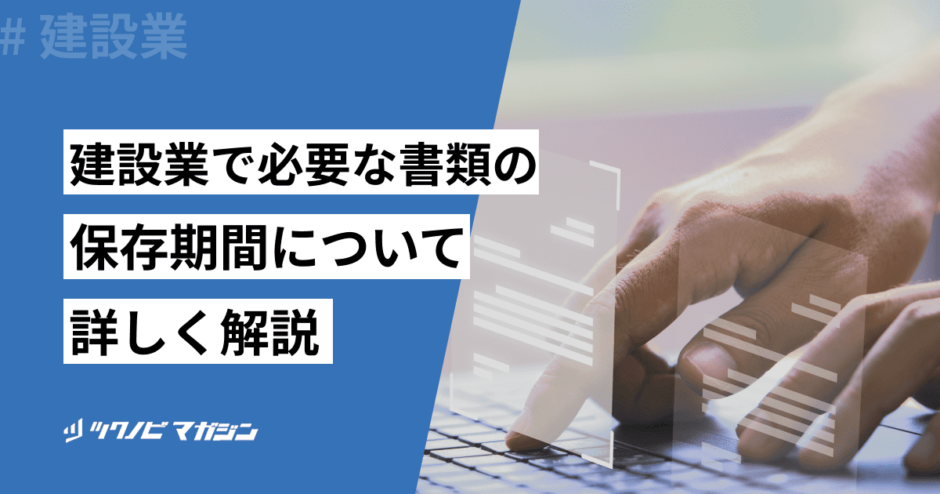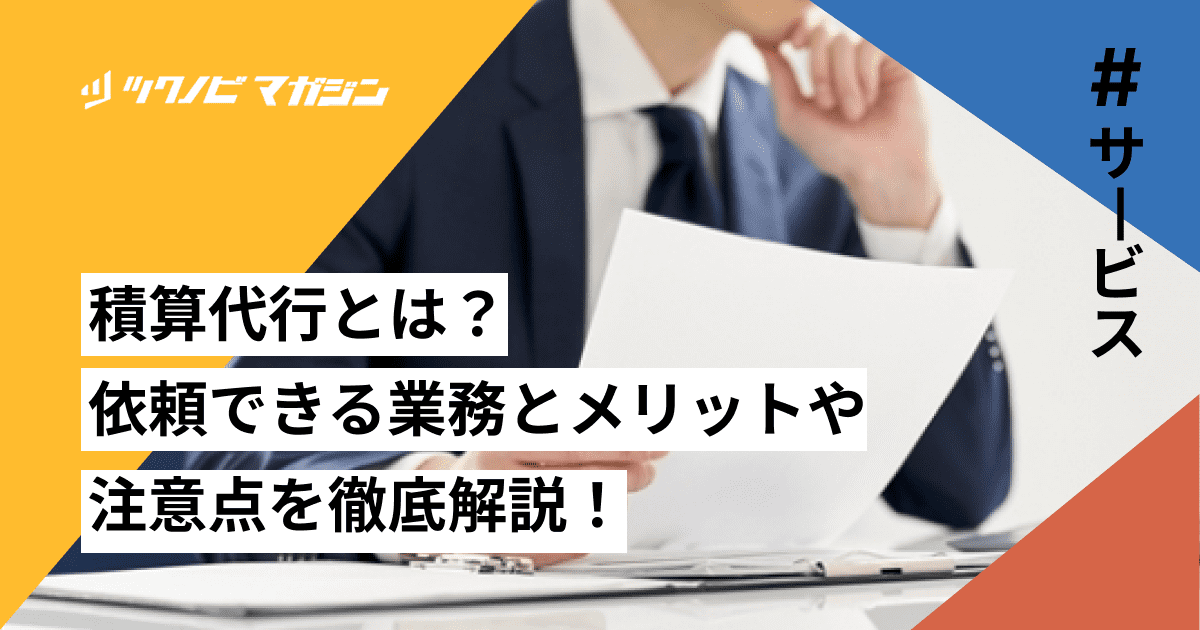※記事内に広告を含みます
建設業では多くの書類を扱いますが、なかには保存が義務付けられている書類があります。
これらの書類は数も多く、書類ごとに保存期間もまちまちであるため、建設業者の方のなかには保存が必要な書類の種類や保存期間についてお悩みの方もいることでしょう。
そこで今回は建設業で必要な書類の保存期間について詳しく解説します。
建設業では書類の保存義務がある
建設業における書類の保存義務は建設業法で定められています。規定に沿って保存されていなければ罰則を受けることもあるため注意が必要です。
書類によって保存期間は異なるため、誤って処分しないよう正しく把握しておきましょう。また、書類の管理は営業所ごとに行う必要があり、本社でまとめて管理することはできません。
建設業法による書類の保存義務
建設業で書類を保存しなければならない理由の1つは建設業法による規定です。建設業法の第55条では帳簿に関する保存の義務が規定されています。
帳簿を保存せず、必要に応じて提示できない事業者は10万円以下の過料を払わなくてはいけません。罰則を受けないためにも必要書類を整理して保存することが重要です。
建設業法の目的や違反したときの罰則についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
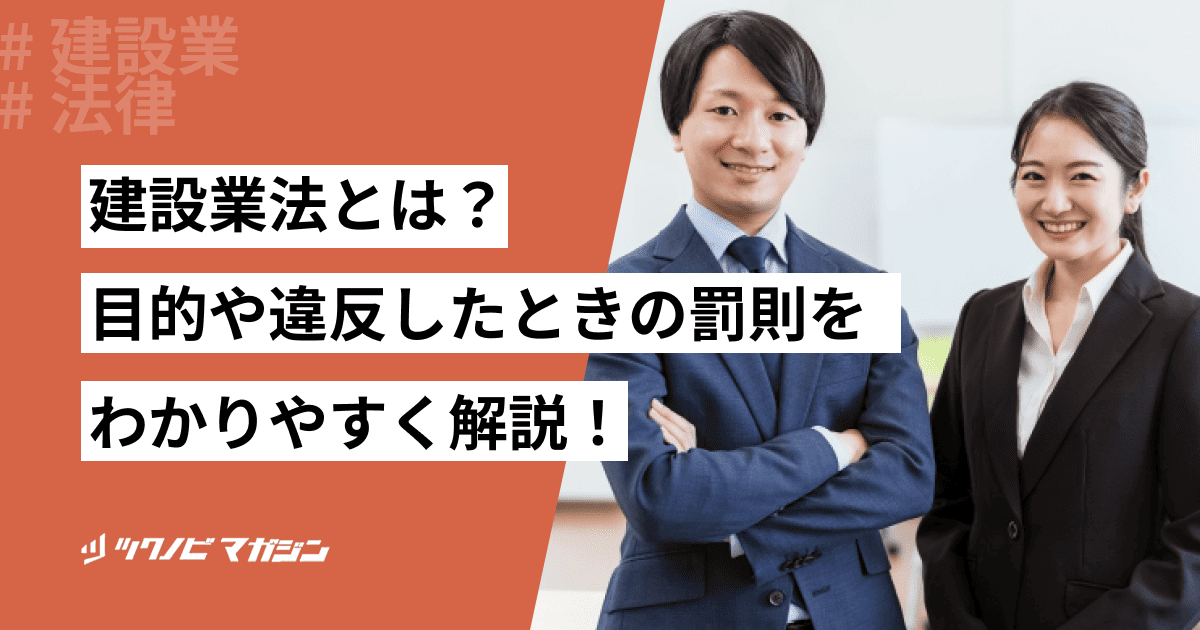 建設業法とは?目的や違反したときの罰則をわかりやすく解説!
建設業法とは?目的や違反したときの罰則をわかりやすく解説!
書類の保存が必要な理由
建設業ではなぜ書類を保存する必要があるのでしょうか。続いて建設業において書類を保存する理由を紹介します。
トラブル防止
建設業で書類を保存するふたつ目の理由はトラブル防止です。建設業では施主と契約を交わして施工を行うため、契約内用に関してトラブルが生じることもあります。
金銭面や施工の内容に関するトラブルに際して、取り決めた内容を記載した書類が手元にあることで、条件の確認がスムーズに行えます。トラブルの悪化防止のためにも書類の保存が重要です。
労災の証明
労働災害の認定に関しても書類の保存が役立ちます。労災は必ずしも事故があったその時点で生じるとは限りません。
場合によっては時間を置いてから労災の症状が出ることもあるため、作業員の契約状況をを記した帳簿などは保存が必須です。
建設業法で定められている書類の保存期間
建設業法で規定されている書類を保存すべき期間は以下の通りです。
- 帳簿:5年間
- 帳簿の添付書類:5年間
- 営業に関する図書:10年間
詳しくは後述しますが、建設業法で作成が求められている帳簿は、会計帳簿とは別のもので、建設工事に関する情報を記載した帳簿を指します。会計帳簿と同じだと勘違いしているケースも多いため、注意しましょう。また、添付書類も忘れず保存する必要があります。
営業に関する図書は注文者と協議した議事録や竣工図のことです。完成した建築物を引き渡した日が1日目としてカウントされます。これらの書類は紙だけではなく、データ保存も認められています。
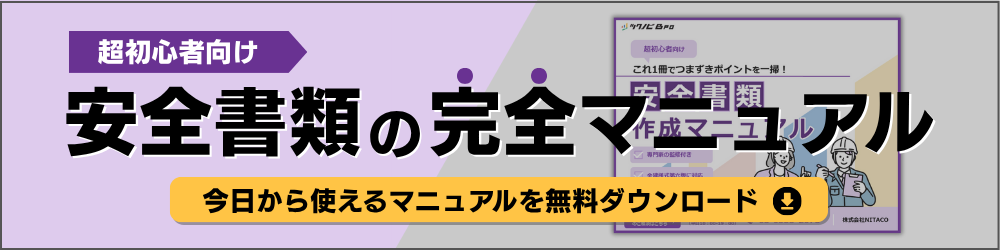
保存が必要な書類の種類と保存期間
建設業では様々な書類を作成します。帳簿や営業に関わる図書など作成する書類は多岐に渡りますが、それぞれの書類ごとに保存期間が異なります。
続いて保存が必要な書類の種類と保存期間について解説します。また、保存書類は工事を請け負った営業所で保管することが義務づけられています。
本部や一部の営業所にまとめて保存することは、建設業法で禁止されています。建設業における書類は紙媒体、電子データでの保存が許可されています。保存が必要な書類は以下の3種類です。
それぞれの保存年数とともにご紹介します。
- 帳簿
- 営業に関する図書
- その他の書類
帳簿
建設業において帳簿は5年の保存が義務付けられています。帳簿に記載する項目は主に以下の4点です。
- 代表者氏名並びに代表者となった年月日
- 受注した工事の請負契約情報
受注した建設工事の名称、工事現場の場所
請負契約締結日
注文者の情報
受注した工事の完了確認検査の日付
引き渡し年月日 - 住宅の新築工事の請負契約情報
住宅の床面積
建物瑕疵の負担割合
住宅瑕疵担保責任保険法人 - 下請契約に関する情報
下請負人に請け負わせた建設工事の名称、工事現場の場所
下請負人との契約締結日
下請負人の情報
下請工事の完了確認検査の日付
下請業者からの引き渡し年月日 - 注意事項:特定建設業の許可を受けているものが注文者(元請工事とは限らない)となって一般建設業者(資本金が4,000万円以上の法人企業を除く)に建設工事を下請けした場合は以下の記載も必要
支払った下請代金の額、支払った年月日及び支払手段
支払手形を交付した際は、手形の金額、交付年月日、手形の満期
一部支払済の場合は、支払残高
遅延利息の額・支払日(下請負人からの引き渡しの申し出から50日を経過した場合に発生する遅延利息(14.6%/年)の支払いにかかるもの)
帳簿に添付する書類
建設業において帳簿に添付する書類は以下の通りです。
- 契約書
すべての請負った工事で添付が必要です。 - 下請代金の額、支払いした年月日、支払い手段を証明する書類の写し
特定建設業者が注文者として資本金4,000万円未満の下請け契約を結んだ場合 - 施工体制台帳の特定部分の添付
事業者自身が直接下請け契約を結んだ公共工事、または下請けの請負額が4,000万円
以上の公共工事を除く工事
営業に関する図書
建設業において営業に関する図書は原則として10年間の保存が義務付けられています。営業に関する図書とは工事内容に関する議事録や、施工体系図などを指します。
営業に関する図書は発注者から直接工事を請け負った元請けに保存義務があります。必要書類の詳細を下記で詳しく解説します。
営業に関する図書に必要な書類が必要な場合は以下の通りです。
- 注文者と受注者が相互に交付する工事内容に関する打ち合わせ議事録
すべての工事で添付が必要です - 完成図
事業者自身が作成した場合、または注文者から受領した場合添付が必要です - 施工体系図
下請け契約を結んだ公共工事、または総額4,000万円以上の公共工事を除く工事
その他の書類
続いて上記の書類以外で保存が必要な書類をご紹介します。建設業で保存が必要な書類は以下の通りです。
| 保存期間 | 書類の種類 |
|---|---|
| 3年間 |
|
| 5年間 |
|
| 7年間 |
|
| 10年間 |
|
| 30年間 |
|
| 保存期間なし |
|
建設業の書類作成代行サービスについてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
 建設業の書類作成代行サービスを紹介!メリットや活用事例も解説
建設業の書類作成代行サービスを紹介!メリットや活用事例も解説
建設業書類を管理する方法
建設業では保存が必要な書類が多くあるため、日頃からの書類整理が重要です。建設業で保存が必要な書類の管理方法について紹介します。
案件別に整理する
建設業の書類は作成した日付順ではなく、まずは案件ごとにまとめて保存しましょう。同一案件の書類が散逸してしまうと、あとから収集、整理する手間がかかります。できるだけ作成した時点で、案件ごとにファイリングする習慣をつけましょう。
保存期間別に整理する
案件ごとにファイリングしたあとに、上記で挙げた保存期間ごとにまとめましょう。保存期間ごとにまとめておくことで、保存期間が過ぎた後の書類破棄などが楽になるほか、必要に応じた書類の確認がしやすいというメリットがあります。
その他に分類した方がよい書類
建設業書類では上記以外の方法で整理・保存した方がよい書類もあります。特に、営業所に配置する経営業務の管理責任者の経歴証明に使う書類は別途保存しましょう。経営業務の管理責任者の経歴証明には、過去の工事の注文書などを使用します。
これらの経歴証明書類は保管せずに破棄してしまうと再度復元することが難しい書類です。破棄することなくしっかりと保管しておきましょう。
電子帳簿保存法とは?保存期間や保存方法を徹底解説!の記事はこちら
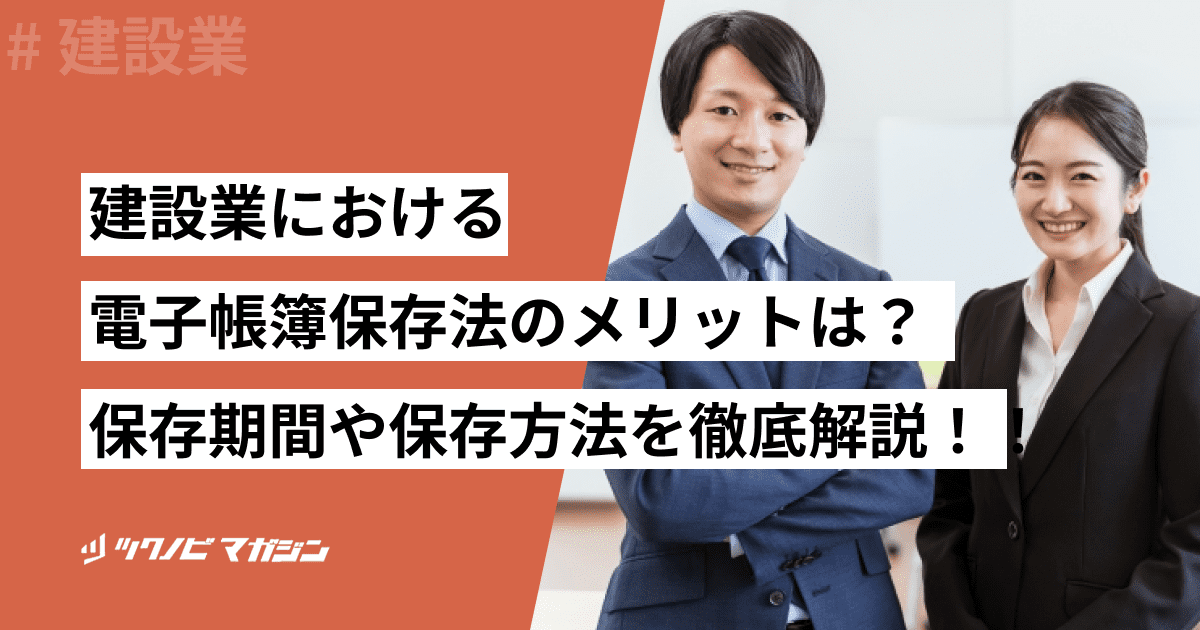 建設業における電子帳簿保存法のメリットは?保存期間や保存方法を徹底解説!
建設業における電子帳簿保存法のメリットは?保存期間や保存方法を徹底解説!
建設業法で備付けが必要な帳簿とは? 保存義務の概要、帳簿の記載事項など分かりやすく解説の記事はこちら
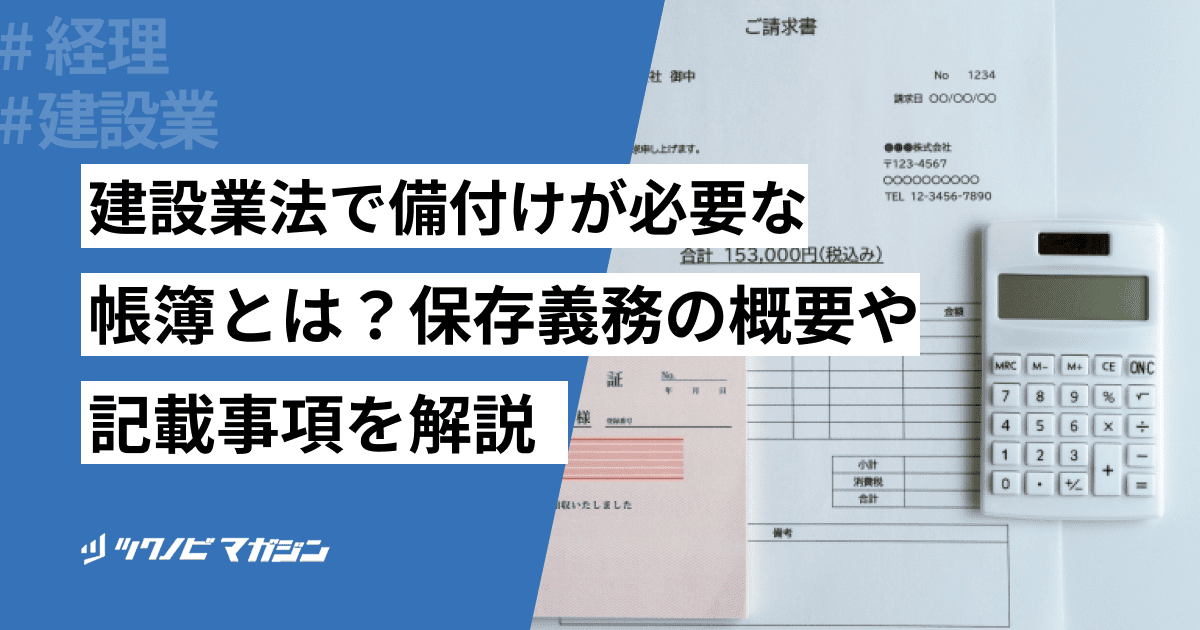 建設業法で備付けが必要な帳簿とは?保存義務の概要や記載事項を解説
建設業法で備付けが必要な帳簿とは?保存義務の概要や記載事項を解説
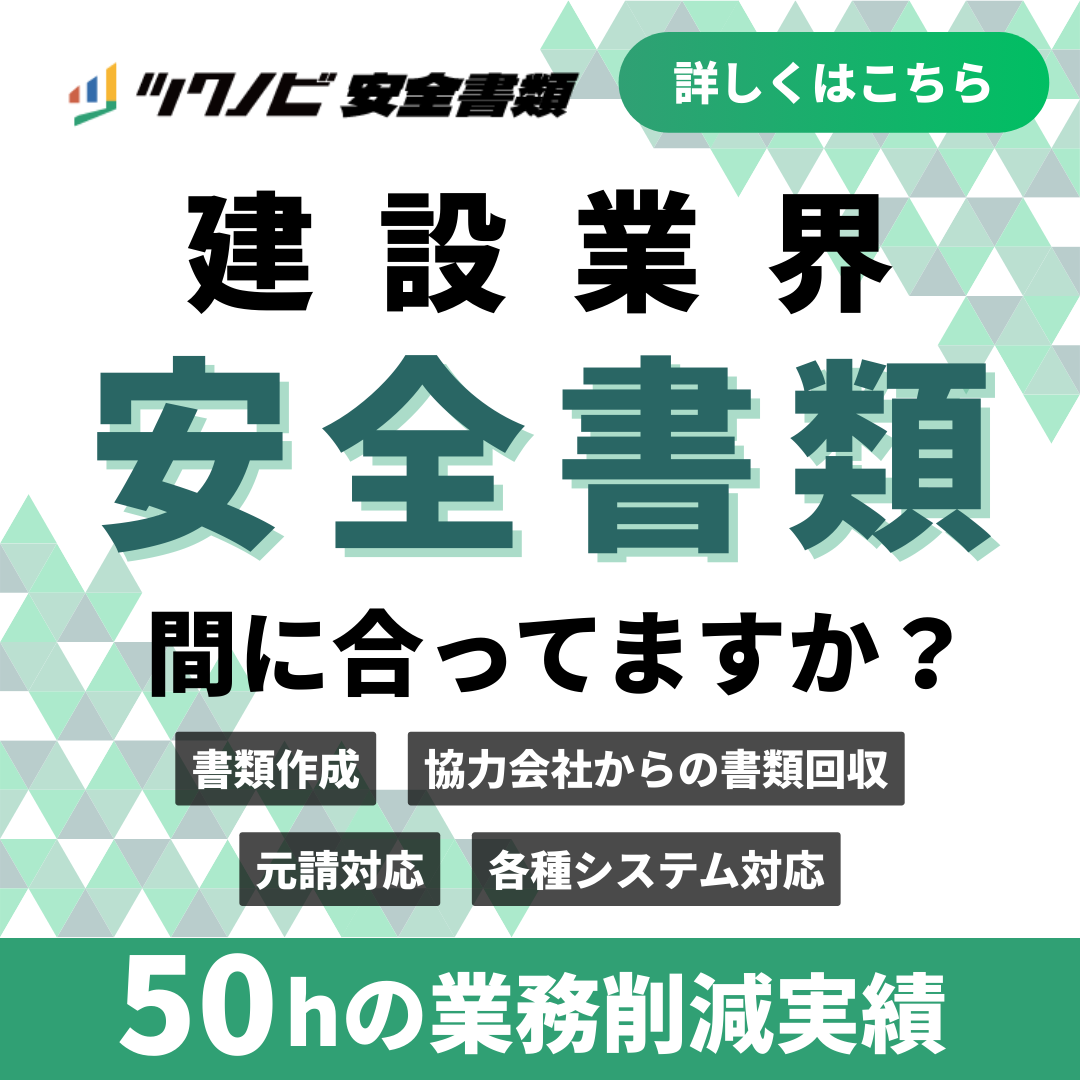
建設業用の書類管理システムを導入するメリット
建設業では、様々な種類の書類を保管する必要があります。書類の保管に困っている場合は、建設業用の書類管理システムの導入がおすすめです。
建設業用の書類管理システムを導入することで、効率的に書類を保管できます。ここでは、建設業用の書類管理システムを導入するメリットを解説します。
業務効率化
書類管理システムを導入すれば、業務の効率化につながります。書類をデータ化することで、パソコンやスマホ、タブレットなど、様々な端末ですぐに書類を閲覧できるためです。
紙で書類を保管している場合、書類を閲覧する際は保管場所まで行き、手作業で探し出す必要があるでしょう。しかし、書類をデータ化しておけば、必要な書類をすぐに確認できます。保管場所へ移動する手間や書類を探す時間を短縮できるなど無駄を省けるため、業務を効率的に行えるでしょう。
経費削減
書類管理システムを導入し書類をデータ管理することで、様々な経費削減につながります。まず、紙の書類で保管する際に必要な印刷代や郵送代を削減できます。
さらに、書類を保管するスペースも必要ありません。空いたスペースを活用することで、オフィスを広く使用できるでしょう。
また、書類を管理する部署に、ほかの業務を任せる時間も確保できます。
リスク管理
書類管理システムは、リスク管理の面でもメリットがあります。紙の書類では、失くしたり破けたりするリスクがあります。しかし、書類管理システムにより、データ化した書類はバックアップしておくことで、失くしたり破けたりするリスクを低減できます。
また、長い年月による黄ばみや退色などの経年劣化も防止できるでしょう。さらに、書類管理システムによる書類管理は、情報漏洩対策にもつながります。紙で書類を保管している場合、保管場所がわかれば誰でも閲覧できるリスクがあります。
しかし、書類管理システムでは閲覧者を限定するためのパスワード設定が可能です。パスワードを設定すれば、関係者以外は書類を閲覧できません。情報漏洩のリスクを下げられるでしょう。
安全書類の作成/管理業務はアウトソーシングもおすすめ
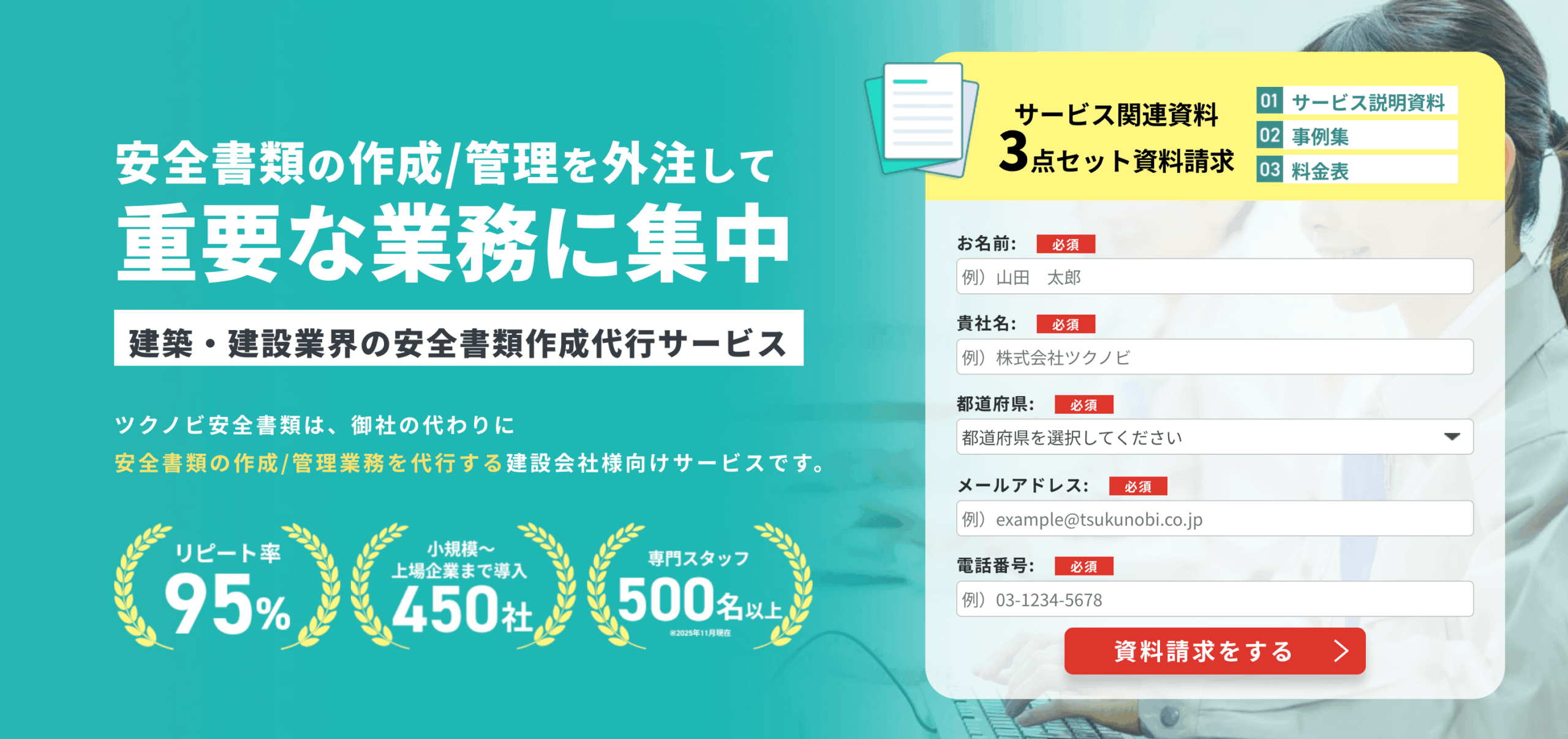
安全書類の作成/管理業務は、アウトソーシングサービスの利用もおすすめです。
従業員のリソースがひっ迫している場合や、書類の作成に対応できる人材が不足している場合などは、アウトソーシングサービスを活用すると、少ない工数で業務に必要な書類を作成できます。専門的な知識を持っているスタッフが対応するため、業務を進めるために効果的な書類を作成できます。
弊社では、建設工事に必要な業務書類の作成に対応している建設業特化のBPOサービス「ツクノビ安全書類」を提供しています。安全書類の作成はもちろん、安全書類ソフトの登録や入力、建設キャリアアップシステムの連携など、幅広い業務を対応いたします。
そして、協力会社からの安全書類の回収や元請け会社への提出も代行可能です。各関係者とのやりとりを代行するため、コミュニケーションコストの削減や心理的なストレス軽減にもつながるでしょう。
安全書類の作成や建設業事務を効率化したい方は、ぜひこちらからお問い合わせください。
【まとめ】建設業の書類は分類・整理して保存しよう
今回は建設業で保存が必要な書類について、種類と保存期間をご紹介しました。建設業では、建設業法によって帳簿や営業の図書書類をはじめ様々な書類の保存が義務付けられています。
建設業の書類は契約の上のトラブル防止や労災の認定など様々な目的に使われるため、しっかりと整理・保存することが重要です。ぜひ今回の記事を参考にして書類の整理・保存に取り組んでみてください。
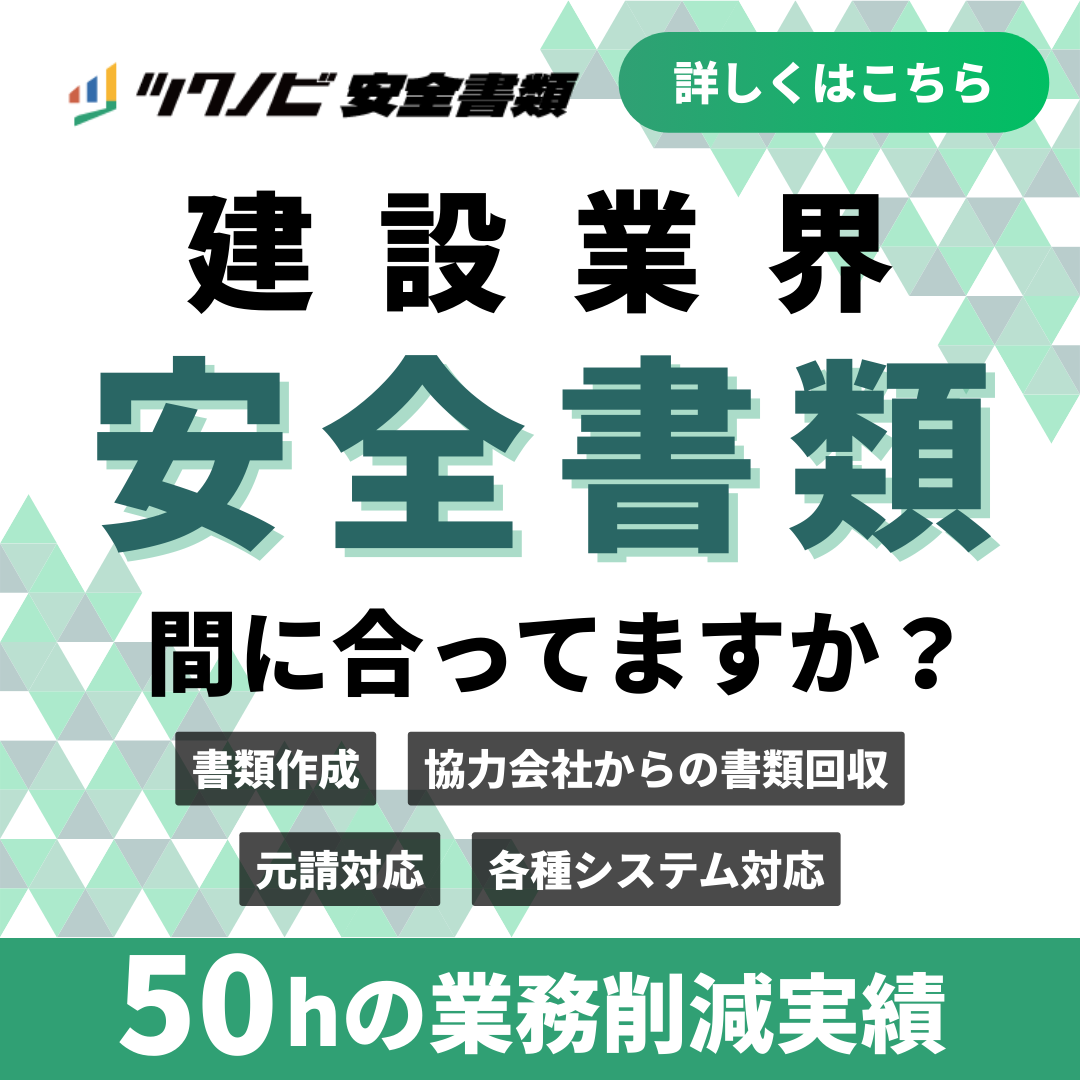
※弊社の営業代行サービスツクノビセールスは、
【効果が出なければ全額返金プラン】を新たにスタートさせました!  ※詳しくは👆👆👆のバナーをクリック!!
※詳しくは👆👆👆のバナーをクリック!!