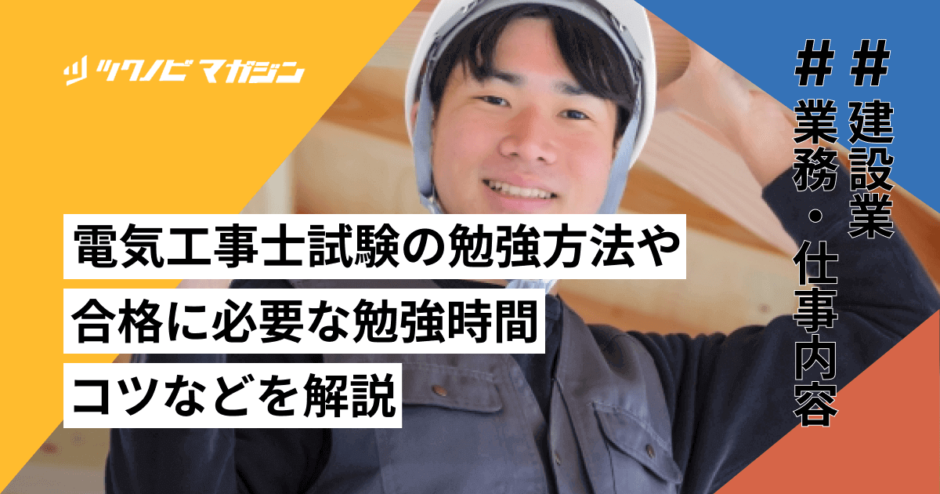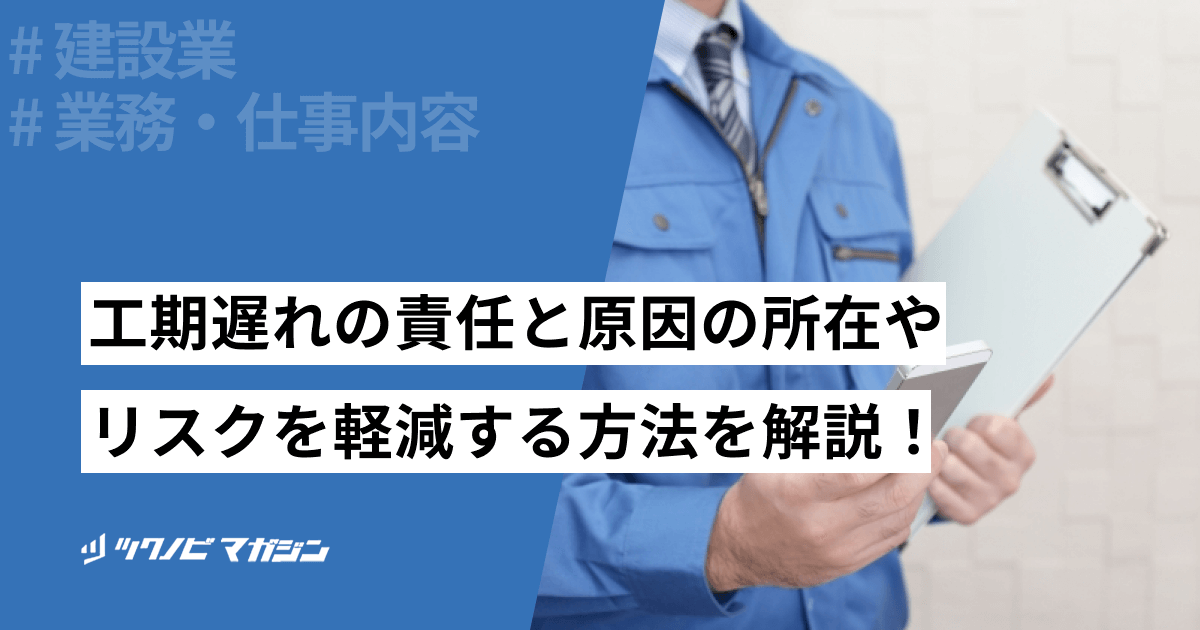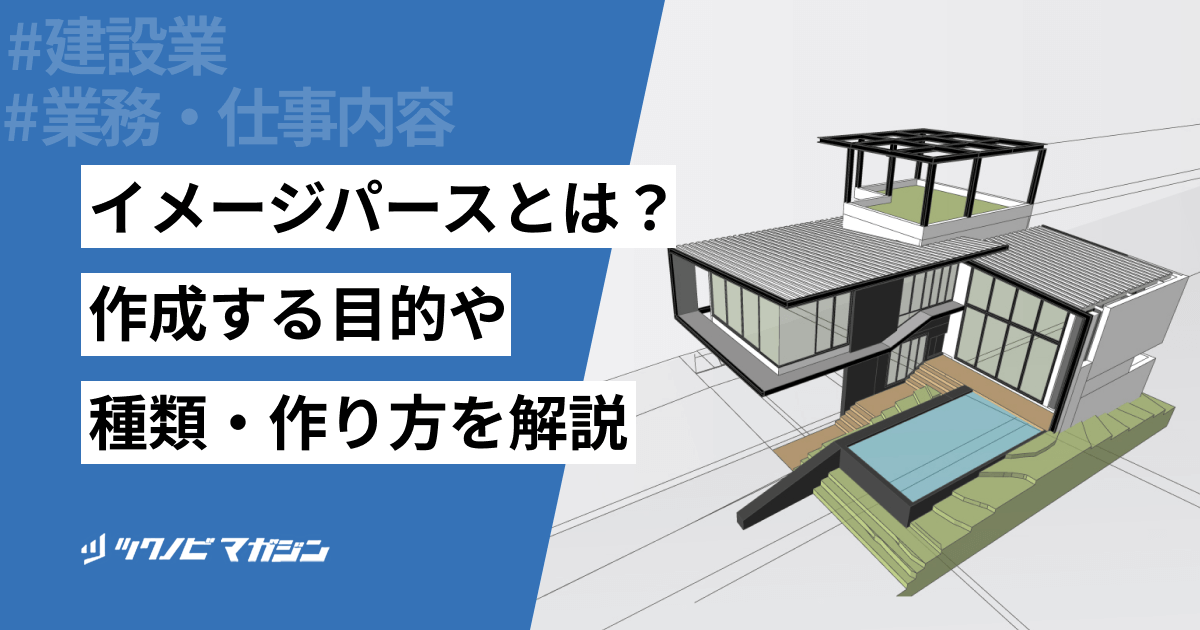※記事内に広告を含みます
電気工事士は、電気工事を実施するために必要な国家資格です。電気工事の欠陥による災害を防ぐという社会的な役割があります。
電気工事士の資格を取得するためには、一般財団法人電気技術者試験センターが開催している電気工事士試験に合格しなければなりません。適切な方法でコツコツと勉強することが大切です。
本記事では、電気工事士試験の内容、勉強方法、必要な勉強時間、勉強のコツなどを解説します。電気工事士の資格取得を目指している人は、ぜひ本記事を参考にしてください。
電気工事士試験の概要
電気工事士試験には第一種と第二種があります。
それぞれの電気工事士試験の内容を解説します。
第一種電気工事士試験
第一種電気工事士試験には学科試験と技能試験があります。学科試験に合格すると、技能試験を受けられます。
学科試験と技能試験の内容は以下のとおりです。
【学科試験】
- 試験方式:マークシート方式(四肢択一)
- 出題数:全50問
- 配点:1問につき2点
- 試験時間:140分
- 電気に関する基礎理論
- 配電理論及び配線設計
- 電気応用
- 電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備
- 電気工事の施工方法
- 自家用電気工作物の検査方法
- 配線図
- 発電施設、送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性
- 一般用電気工作物等及び自家用電気工作物の保安に関する法令
【技能試験】
- 試験方式:持参した作業用工具を用いて、出題された配線図を施工する
- 出題数:1問
- 試験時間:60分
- 電線の接続
- 配線工事
- 電気機器、蓄電池及び配線器具の設置
- 電気機器、蓄電池、配線器具並びに電気工事用の材料及び工具の使用方法
- コード及びキャブタイヤケーブルの取付け
- 接地工事
- 電流、電圧、電力及び電気抵抗の測定
- 自家用電気工作物の検査
- 自家用電気工作物の操作及び故障箇所の修理
参照:一般財団法人電気技術者試験センター「第一種電気工事士の試験概要」
第二種電気工事士試験
第二種電気工事士試験も、第一種と同様に学科試験と技能試験があります。
学科試験と技能試験の内容は以下のとおりです。
【学科試験】
- 試験方式:マークシート方式(四肢択一)
- 出題数:全50問
- 配点:1問につき2点
- 試験時間:120分
- 電気に関する基礎理論
- 配電理論及び配線設計
- 電気機器・配線器具並びに電気工事用の材料及び工具
- 電気工事の施工方法
- 一般用電気工作物の検査方法
- 配線図
- 一般用電気工作物の保安に関する法令
【技能試験】
- 試験方式:持参した作業用工具を用いて、出題された配線図を施工する
- 出題数:1問
- 試験時間:40分
- 電線の接続
- 配線工事
- 電気機器及び配線器具の設置
- 電気機器、配線器具並びに電気工事用の材料及び工具の使用方法
- コード及びキャブタイヤケーブルの取付け
- 接地工事
- 電流、電圧、電力及び電気抵抗の測定
- 一般用電気工作物等の検査
- 一般用電気工作物等の故障箇所の修理
参照:一般財団法人電気技術者試験センター「第二種電気工事士の試験概要」
第二種電気工事士試験の出題傾向
第二種電気工事士試験の問題は、計算問題と知識問題の2つに大別できます。第二種電気工事士試験の出題傾向を以下の項目に分けて解説します。
- 計算問題
- 知識問題
- 各項目の問題数
計算問題
第二種電気工事士試験の計算問題の題材は、主に以下のとおりです。
- 直流・交流回路
- 三相交流回路
- 電力損失
- 電圧降下
- 許容電流
提示された回路や電線などにおける電流値、電圧値、抵抗値、力率などを算出します。
電卓や計算尺の持ち込みは禁止されており、複雑な計算問題は出題されません。四則演算を理解していれば十分に計算可能です。しかし、回路図や数式を理解していないと解けないので、時間をかけて勉強する必要があります。
知識問題
第二種電気工事士試験では、知識を問われる問題も出題されます。
出題される問題は、正誤を問われる問題、図やイラストなどの名称や使用方法を問われる問題、示された記号の意味を問われる問題などです。。暗記していれば簡単に解ける問題だけでなく、知識を組み合わせて導き出さないと解けない問題も出題されます。
工事の手法や法律などの細かな違いも覚えなければなりません。必要な知識が多いため、暗記するためにやはり時間がかかります。
各項目の問題数
受験日によって異なりますが、「配電理論及び配線設計」、「電気機器・配線器具並びに電気工事用の材料及び工具」、「電気工事の施工方法」、「配線図」の分野の問題が多く出題される傾向にあります。
一方で、「一般用電気工作物の保安に関する法令」に関する問題は少なめです。
様々な分野の知識をまんべんなく身に付けることが大切ですが、時間がない場合は出題される可能性が高い分野を重点的に勉強しましょう。
電気工事士試験の勉強方法
電気工事士試験の勉強方法は主に以下の3つです。
- 参考書を活用する
- 動画を活用する
- 専門学校に通う
それぞれの内容を解説します。
参考書を活用する
電気工事士試験の勉強方法の1つに、独学で参考書を活用する方法が挙げられます。
近年、電気工事士試験の参考書が多く市販されており、書店やネット通販などで簡単に入手可能です。必要な参考書を数千円で揃えられ、後述する専門学校への通学よりも安価に勉強を始められます。
ただし、自分でスケジュールを立ててコツコツと根気よく勉強しなければなりません。すきま時間を活用して効率よく勉強を継続することが大切です。
動画を活用する
動画教材を活用して電気工事士試験の勉強をする方法も有効です。
近年、電気工事士試験向けの動画教材が多くあります。有料の動画教材以外にも、YouTubeのような動画配信サイトで無料で視聴できる教材もあります。
スマホやPCでどこでも簡単に視聴できることがメリットです。優れた動画教材であれば、専門講師が難解な法律や数式などをわかりやすく解説してくれるので、効率よく理解を深められるでしょう。
ただし、視聴しただけで満足するのではなく、十分に知識を身に付けることが大切です。
専門学校に通う
専門学校に通って電気工事士試験対策を学ぶ方法もあります。
電気工事士試験に精通した講師の指導を直接受けられることが利点です。わからないことがあっても、質問をしてすぐに理解を深められるでしょう。
ただし、定められたスケジュールで学校に通わなければならないため、忙しい社会人は受講が難しいかもしれません。忙しい人向けに、いつでも見直せるオンラインストリーミングの授業もあります。自分に合った専門学校を見つけましょう。
電気工事士試験に合格するために必要な勉強時間
およそ30~40時間勉強して第二種電気工事士試験に合格している人もいます。試験日の1~2か月前から勉強すれば、十分に間に合うでしょう。
ある専門学校での第二種電気試験工事士試験講座には、学科試験対策が2日間、技能試験対策が3日間あります。
電気工事士試験に合格するための時間は人それぞれ異なります。1つの教材を十分に理解できるまでコツコツ勉強しましょう。
忙しい社会人は、まとまった勉強時間がなかなか取れないでしょう。通退勤や休憩時間といったすきま時間を活用して勉強することが大切です。
電気工事士試験の勉強方法のコツ
電気工事士試験の勉強のコツがいくつかあります。
- 参考書に一通り目を通し概要を掴む
- 暗記部分は好きな分野から取り組む
- 計算問題が苦手な場合は取捨選択する
- 過去問を繰り返し解く
それぞれの内容を解説します。
参考書に一通り目を通し概要を掴む
電気工事士試験の勉強をする際には、はじめに参考書にひととおり目を通して、概要を把握することが大切です。
参考書全体に目を通し、簡単そうな箇所と難しそうな箇所、得意そうな箇所と苦手そうな箇所の目星を付けましょう。概要を把握することで、適切な勉強のスケジュールを立てられます。
テキストの順番どおりに進めなくても構いません。難しそうな箇所や苦手そうな箇所の勉強時間を十分に確保しましょう。
暗記部分は好きな分野から取り組む
電気工事士試験の勉強をする際、好きな分野から暗記することをおすすめします。
電気工事士試験で出題される分野は多岐に渡ります。情報量が多いため、参考書に目を通しただけで気が滅入ってしまうかもしれません。
好きな分野から暗記を始めれば、スムーズに勉強に取り組めるでしょう。好きな分野ほど集中して取り組めるので、効率よく暗記できます。
ただし、苦手な分野にも十分に時間をかけて取り組むように注意しましょう。
配線器具や工具
電気工事試験の学科試験では、配線器具や工具などに関する問題が多く出題されます。配線器具や工具などを暗記する際には、外観や名称だけでなく、用途も一緒に覚えましょう。
配線図
電気工事試験の学科試験において、配線図の問題が占める割合も大きい傾向にあります。覚えなければならない図記号が多くありますが、似たような図記号をまとめながら十分に暗記しましょう。
計算問題が苦手な場合は取捨選択する
どうしても計算が苦手な人は、計算問題を取捨選択して勉強しましょう。
計算問題で扱う範囲は広いため、すべての解法を理解するには時間がかかります。計算に苦手意識がある人は、なかなか勉強が進まないかもしれません。
電気工事士の学科試験で出題される計算問題自体は、四則演算がわかっていれば十分に計算できます。解ける問題を少しずつ増やすことが大切です。焦らずに一つひとつの計算問題を勉強しましょう。
過去問を繰り返し解く
電気工事士試験の勉強のコツに、過去問を繰り返し解くことも挙げられます。
過去問を繰り返し解くことで、試験の雰囲気を体感できます。過去問に慣れれば、どの問題にどの程度の時間をかけるべきかを把握できるでしょう。時間を測定しながら、本番と同じシチュエーションで解くことが大切です。
一般財団法人電気技術者試験センター公式サイト「第一種電気工事士試験の問題と解答」、「第二種電気工事士試験の問題と解答」に過去問が掲載されています。無料で利用できるので、繰り返し解きましょう。
電気工事士試験の勉強方法の注意点
電気工事士試験の技能試験に備えて以下の点に注意しましょう。
- 工具を準備しておく
- 実技の練習を怠らない
それぞれの内容を解説します。
工具を準備しておく
電気工事士試験の技能試験に備えて、工具を準備しておきましょう。
技能試験では、持参した工具を用いて課題を実施します。受験者同士の工具の貸し借りは不可です。工具に不足があったり故障があったりすると、十分に課題に対応できません。
一般財団法人電気技術者試験センターは、以下の7つの工具を必ず持参するように指定しています。
- ペンチ
- ドライバー(プラス・マイナス)
- 電工ナイフ
- スケール
- ウォーターポンププライヤー
- リングスリーブ用圧着工具 (JIS C 9711:1982・1990・1997 適合品)
さらに、VVFストリッパーがあると、スムーズに施工できます。
実技の練習を怠らない
電気工事士試験の技能試験のために、実技の練習を怠らないように注意しましょう。
日頃から現場で作業をしていれば問題なく技能試験をクリアできるかもしれません。しかし、慣れない実技の問題が出題される恐れもあります。
一般財団法人電気技術者試験センター公式サイト「第一種電気工事士試験の問題と解答」、「第二種電気工事士試験の問題と解答」に技能試験の過去問も載っています。一度は目を通しておきましょう。
また、実技の練習は独学では難しいため、事前に周囲の電気工事士取得者にアドバイスをもらいましょう。技能試験の練習だけ外部講習を利用することもおすすめします。
建設業で働き方を見直すならツクノビワークがおすすめ
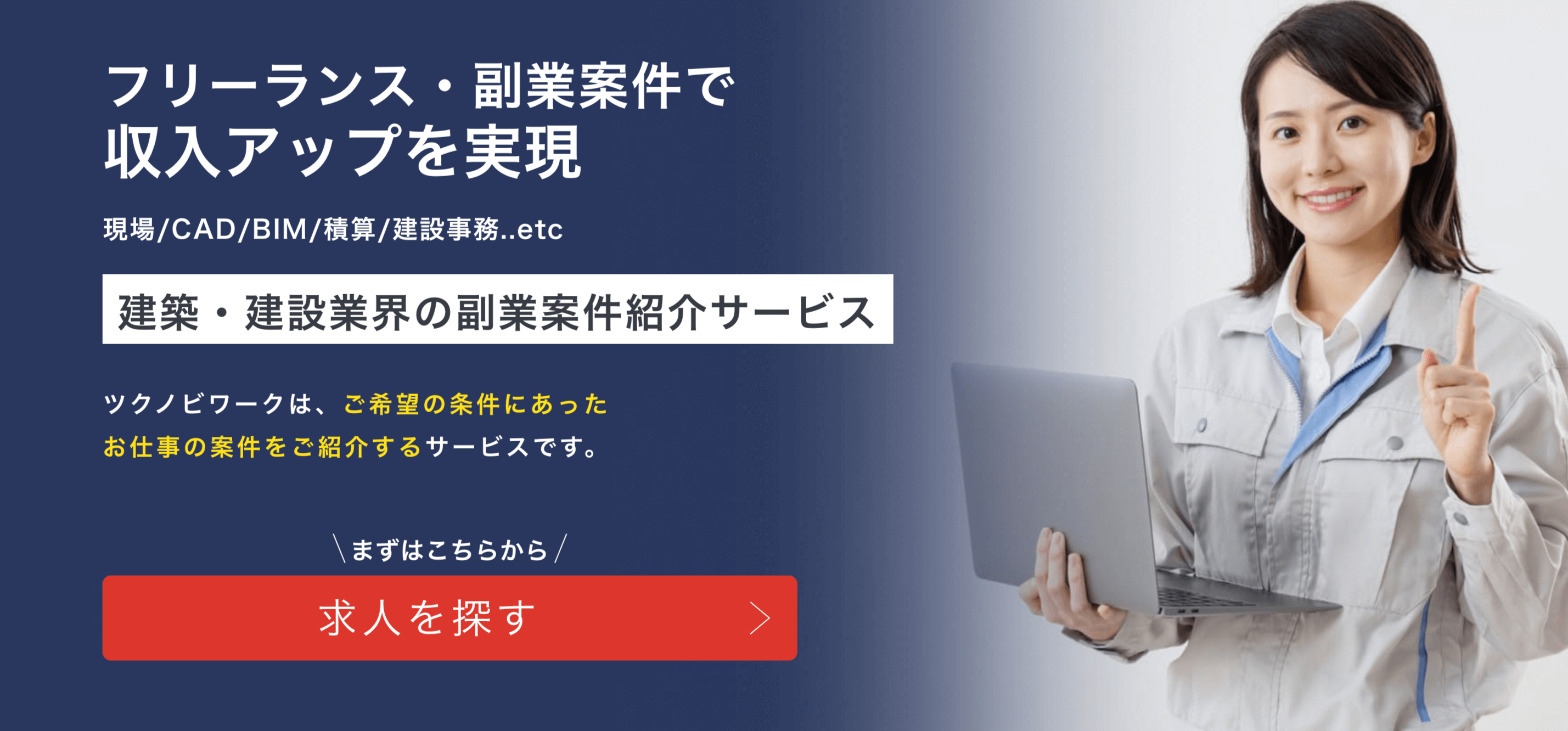
建設業で働き方を見直したい方には、建設業特化のフリーランス・副業案件マッチングサービス「ツクノビワーク」の活用がおすすめです。
週1~5日で勤務できる案件やリモートワークで勤務できる案件など、幅広い案件の中からご希望の案件をマッチング可能です。働く方々に寄り添い、ワークライフバランス改善やスキル向上、年収UPなど、様々なご要望に沿うフリーランス・副業案件をご紹介いたします。
スキマ時間で稼ぎたい方や働き方を見直したい方はぜひこちらから詳細をご確認ください。
【まとめ】電気工事士試験の勉強方法は自分に合う方法から選ぼう!
電気工事士試験の内容、勉強方法、必要な勉強時間、勉強のコツなどを解説しました。
電気工事士試験には、第一種と第二種のどちらにも学科試験と技能試験があります。学科試験には計算問題があるので、法則や数式を十分に覚えなければなりません。
参考書や過去問を繰り返し解いて、理解を深めることが大切です。忙しくて時間が取れない人は、動画教材や専門学校を活用しましょう。
ぜひ本記事を参考に、電気工事士試験合格を実現させましょう。
電気工事士が副業に適している理由や電気工事士の将来性・電気工事士の資格試験の難易度についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
 電気工事士が副業に適している理由やおすすめの仕事内容を解説!
電気工事士が副業に適している理由やおすすめの仕事内容を解説!
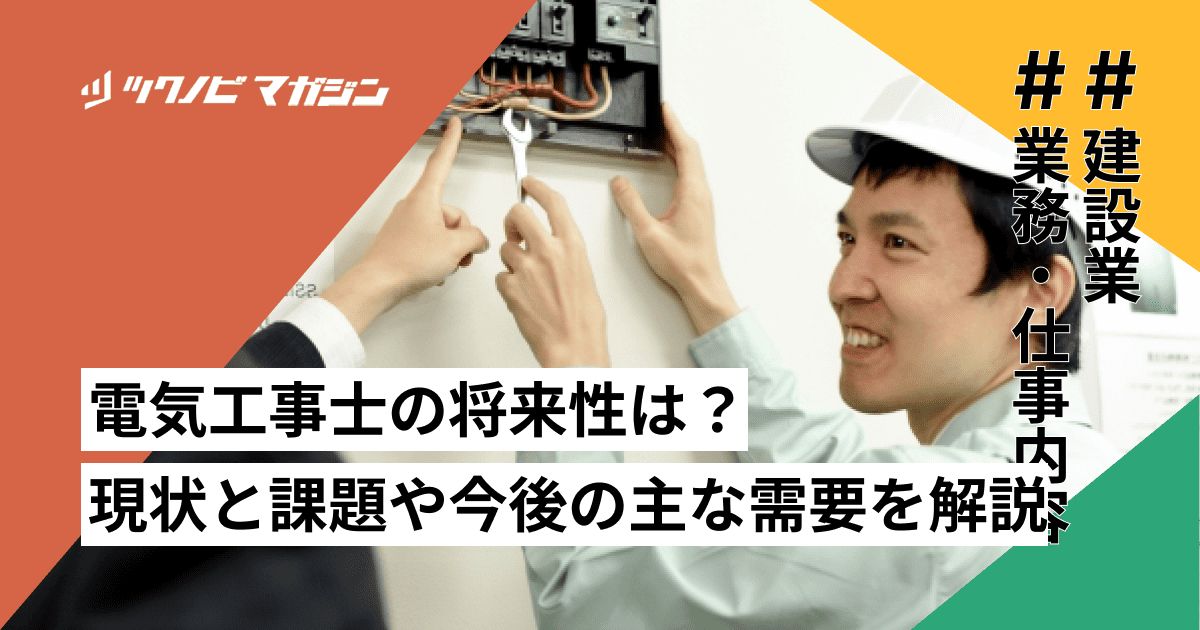 電気工事士の将来性は?現状と課題や今後の主な需要などを解説
電気工事士の将来性は?現状と課題や今後の主な需要などを解説
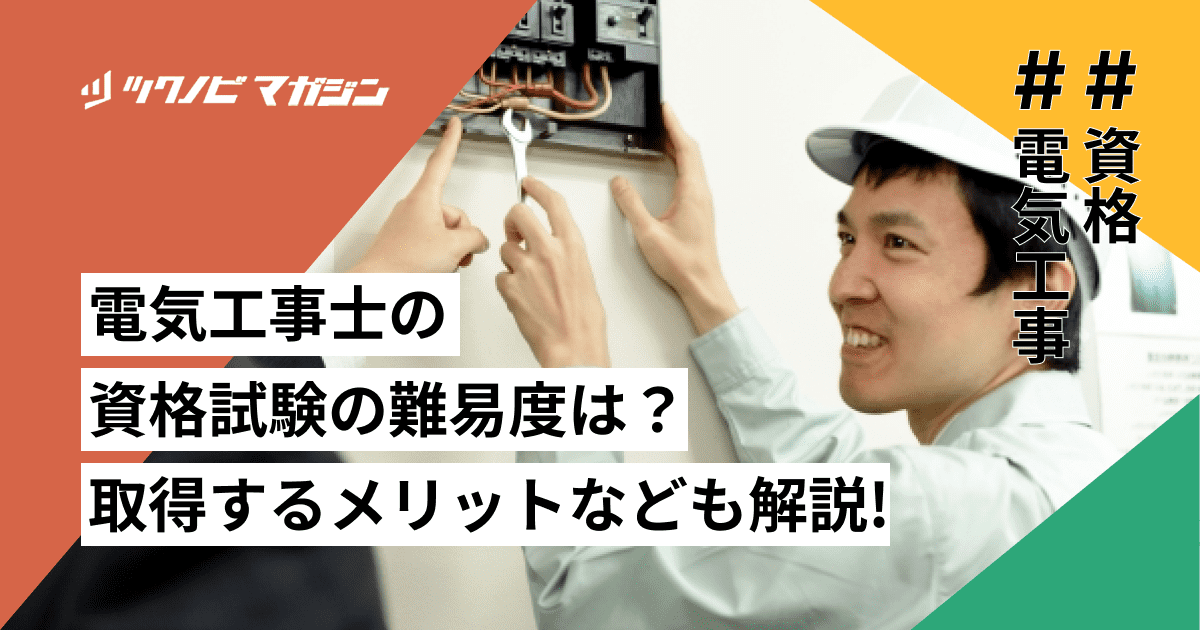 電気工事士の資格試験の難易度は?取得するメリットなども解説
電気工事士の資格試験の難易度は?取得するメリットなども解説