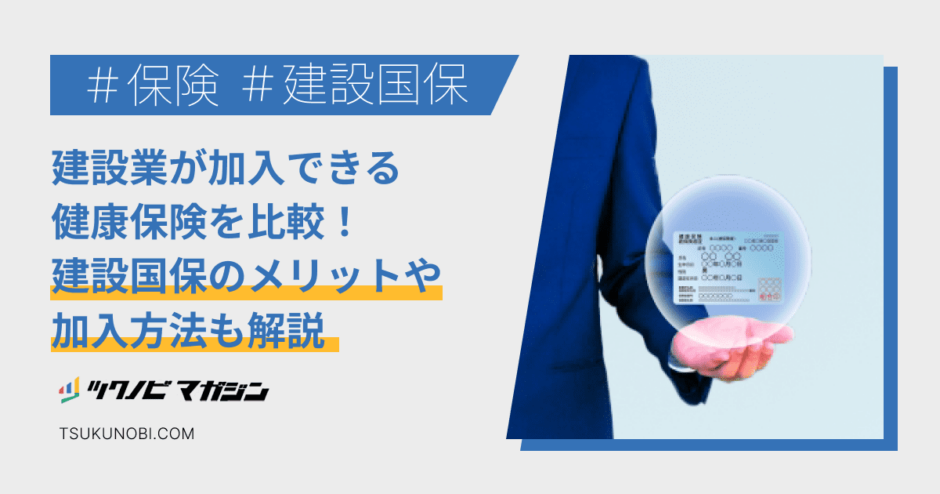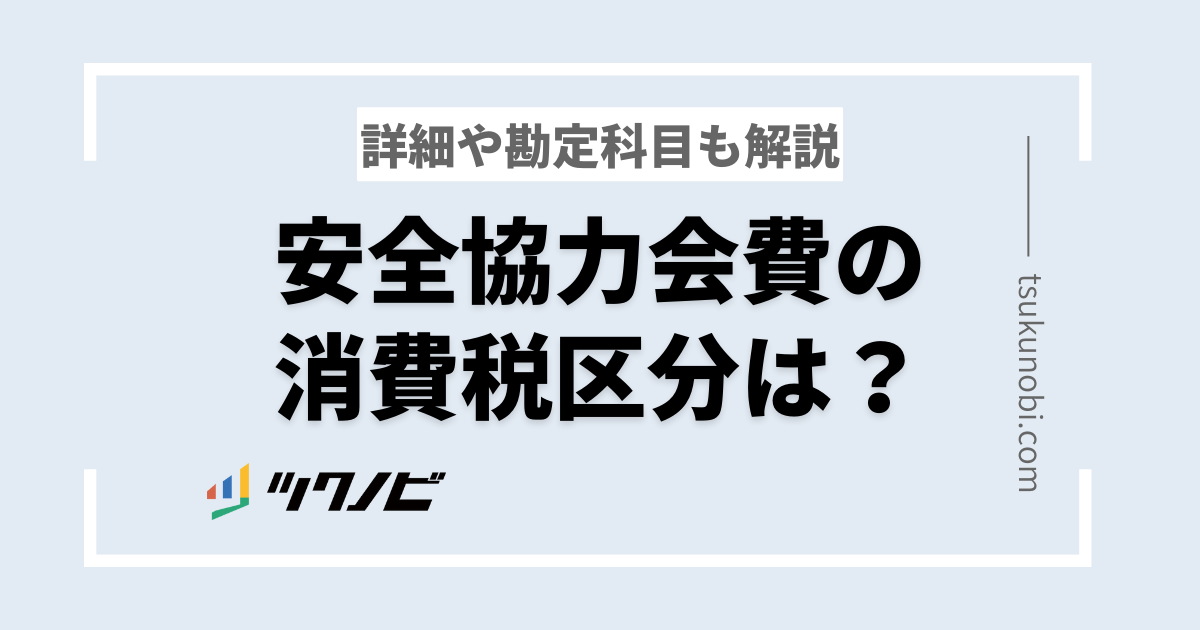※記事内に広告を含みます
建設国保は、建設業が加入できる健康保険です。建設国保に加入することで、毎月の保険料が安くなる場合があります。
ただ、建設業を営む人の健康保険は、建設保険だけでなく、他にも国民健康保険、健康保険(協会けんぽ)の選択肢があります。自身に合った健康保険を選ばないと保険料が高くなってしまう可能性もあります。
自身の場合、健康保険はどれが良いのかが分からないという方も多いのではないでしょうか。今回の記事で紹介する建設保険のメリットとデメリット、他の保険の内容などを把握し、自分にぴったりの保険を選びましょう。
ツクノビBPOは、面倒な事務業務を低コストで代行する建設業特化のアウトソーシングサービスです。
書類作成や事務作業、図面作成など、建設業に必要な幅広い業務に対応可能です。サービスの詳細はぜひこちらからご確認ください。
建設国保とは
建設国保とは、建設業に従事する方とその家族のための医療保険で、様々な組合によって運営されているものがあります。今回はそのなかでも「全国建設工事業国民健康保険組合」に焦点を当てて紹介します。全国建設工事業国民健康保険組合は建設業の中でも従業員の人数が5名未満の個人事業所の従業員とその家族、一人親方が加入できます。
建設国保は国民健康保険や協会けんぽとは異なる点があるため、自分に合った健康保険を選ぶことが重要です。
建設業が加入できる健康保険比較
建設業が加入できるおすすめの保険は、主に3種類あります。協会けんぽ・建設国保・国民健康保険、それぞれの特徴を把握して自分に合った保険を選びましょう。
健康保険と一口にいっても、それぞれ特徴や保険料率や保険料は異なっています。建設業の健康保険の種類と内容を正しく理解し、自身に合った選択をしましょう。
| 運営母体 | 加入条件 | 保険料率または保険料 | |
|---|---|---|---|
| 建設国保 | 全国建設工事業国民健康保険組合 | ・建設工事業に携わっていること ・個人事業所、または一人親方の方であること ・株式会社などの法人事業所や常時5人以上の従業員を雇用している個人事業所ではないこと |
年齢と就業実態、加入する家族の人数によって変動 |
| 国民健康保険 | 地方自治体 | ・他の医療保険(健康保険)に加入していないこと ・他の医療保険(健康保険)の被扶養者ではないこと ・生活保護を受けていないこと ・後期高齢者医療制度に加入していないこと ・短期滞在在留外国人ではないこと |
居住する自治体と前年の所得金額によって変動 |
| 協会けんぽ | 全国健康保険協会 | ・協会けんぽに加入している事業所に常時雇用されていること(事業所が法人の場合は、法人の役員も加入) ・週の所定労働時間が常時雇用されている従業員の4分の3以上かつ1ヵ月の所定労働日数が常時雇用されている従業員の4分の3以上である者 |
・事業所が所在する都道府県と給与または報酬金額によって変動 ・扶養している家族の保険料は無料 |
建設国保
建設国保は、建設業に特化した健康保険です。代表的なものに『全国建設工事業国民健康保険組合』があげられます。
経営者や一人親方の場合はとても便利な反面、常時5人未満の従業員を雇用している個人事業所の従業員の場合は全額保険料を払わなければならないので痛い出費になるかもしれません。保険料は決して手軽な金額ではないので、そのことも把握しておきましょう。
補償内容はほかの保険と異なる点があるので、家族構成などを考慮し、建設国保に加入するかを見極める必要があります。
建設国保の加入条件
建設国保に加入するには以下の条件があります。
- 建設工事業に携わっていること
- 個人事業所、または一人親方の方であること
- 株式会社などの法人事業所や常時5人以上の従業員を雇用している個人事業所ではないこと
ただし、すでに加入していている方が、法人または常時5人以上の従業員がいる事業所を新たに設立した場合、所定の手続きをおこなえば引き続き建設国保に加入できます。
参照:資格・適用のご案内(加入資格) | 保険の手続き | 全国建設工事業国民健康保険組合
建設国保の保険料額
建設国保の保険料額は、年齢と就業実態、加入する家族の人数によって変動します。そのため、収入金額による保険料の変動はありません。また、保険料は労使折半ではなく、被保険者の全額負担です。※事業所の福利厚生によっては、折半負担をするケースもあります。
例えば、B区分(20歳以上30歳未満)の一人親方の保険料は14,600円となり、加入家族が増えるにつれて6,600円ずつ加算されていきます。※加入家族が40歳の到達月(誕生日の前日の属する月)から、65歳の到達月(誕生日の前日の属する月)に該当する場合は、さらに3,500円が加算されます。
自身の保険料がいくらになるかは公式HPでシミュレーションができるので、ぜひ一度確認してみてください。
国民健康保険
国民健康保険は、主に個人事業主の方が加入する健康保険です。国民健康保険は地方自治体が運営しています。
もし一人親方として業務を行っている場合は、建設国保か国民健康保険のどちらかを選択することになるでしょう。国民健康保険の場合も本人の全額負担となります。
国民健康保険の加入条件
国民健康保険に加入するには以下の条件があります。
- 他の医療保険(健康保険)に加入していないこと
- 他の医療保険(健康保険)の被扶養者ではないこと
- 生活保護を受けていないこと
- 後期高齢者医療制度に加入していないこと
- 短期滞在在留外国人ではないこと
国民健康保険の保険料率
国民健康保険の保険料額は、居住する自治体と前年の所得金額によって変動します。そのため、保険料額が毎年変動します。
例えば、東京都大田区に在住の40歳未満の方の場合、所得金額が400万円の方の保険料は33,539円となります。自身の保険料のシミュレーションは居住している自治体のHPでできます。実際に確認してみましょう。
協会けんぽ
協会けんぽは、主に企業の従業員が加入する健康保険です。『全国健康保険協会』が運営しています。
法人や、従業員が5名以上の個人事業主の事業所が加盟しなければならない社会保険です。こちらは保険料を会社が半額負担するので、経営者の負担は少し大きめです。しかし、従業員の負担が軽くなるので、従業員からの信頼を得られやすいのが特徴です。
協会けんぽの加入条件
協会けんぽに加入するには以下の条件があります。正社員として雇用される方はもちろん、パートやアルバイトの方でも条件を満たせば加入対象となります。
- 協会けんぽに加入している事業所に常時雇用されていること
- 週の所定労働時間が常時雇用されている従業員の4分の3以上かつ1ヵ月の所定労働日数が常時雇用されている従業員の4分の3以上である者※1
※1 被保険者数が101人以上(令和6年10月からは51人以上)の事業所は、次のパート、アルバイトも加入します。
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が継続して2か月を超えて使用される見込みであること
・賃金の月額が8万8,000円以上であること
・学生でないこと
協会けんぽの保険料率
協会けんぽの保険料率は、事業所が所在する都道府県と加入する被保険者の賃金・報酬によって変動します。そのため、加入する被保険者の賃金・報酬金額が大きい方ほど保険料は上がります。保険料は労使折半です。
例えば、東京都にある事業所の従業員で月給40万円の方(40歳未満)の保険料は20,500円となります。(令和5年の場合)また、その中の本人負担額は、半分の10,250円となります。自身の保険料シミュレーションはこちらのHPからできます。
※40歳以上65歳未満の被保険者は、別途介護保険料の負担があります。こちらも労使折半の負担です。
また、協会けんぽは被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族も加入できます。被扶養者と認定されれば、保険料を負担しなくても保険給付を受けられます。そのため、基本的には加入する家族が増えても保険料は増えません。
建設業の健康保険を選ぶポイント
仕事を続けていくうえで、建設国保と協会けんぽ、国民健康保険のどれがよいのかを判断し、加入する必要があります。それぞれの健康保険は、保険内容が若干異なるだけでなく、保険料の支払い金額にも違いがあるのです。
特に、一人親方の場合は自身で建設国保と国民健康保険のどちらかを選ぶ必要があります。自身が支払うことになる保険料をシミュレーションしたうえで判断するとよいでしょう。
個人経営者の場合は、建設国保に加入するか、協会けんぽに加入するかを判断することになるかもしれません。従業員数が5名以下であれば建設国保にすれば会社負担がないのでコストカットにつながります。ただし、協会けんぽと違って、保険料は事業所と折半負担ではないので、被保険者が全額保険料を負担するため、従業員からの印象はダウンしやすくなるので注意しましょう。なお、法人の場合は、協会けんぽに加入します。
建設業で建設国保に加入するメリット
建設国保を国民健康保険と比較したときに見えてくるメリットは、どのようなものが挙げられるのでしょうか。健康保険はなんとなく選んで加入してしまうと、後悔することもあります。以下で紹介する建設国保に加入するメリットをチェックしたうえで判断しましょう。
メリット1:低所得者は保険料が安くなる
国民健康保険は、前年の所得額によって保険料が変動します。そのため、比較的所得が低い人であれば非常に魅力的な健康保険です。
しかし、所得額が多くなると、その分高い金額の保険料になります。保険料は高くなっても、保険の内容は変わりません。ある程度の高所得額である場合は、建設国保の加入がおすすめです。
建設国保は、所得額に関係なく一律の保険料を支払う保険です。所得額が多い人にとっては、国民健康保険より安くなることもしばしばあります。所得額が増えた人は、保険料の計算を行い、どちらが安いのかを見比べてみましょう。
メリット2:補償内容が充実している
建設国保の金額は一律なので、高所得者にとっては保険料が安くなることがあります。安い保険料だと、手当てがしっかり出るのか不安に感じる人もいるかもしれません。
建設国保は、国民健康保険と同じ補償を受けられます。それだけでなく、建設国保では入院給付金や出産手当金も出ます。国民健康保険には出ない補償で、入院給付金は建設業で現場に出ている人であればあって損はない補償といえます。葬祭費も、国民健康保険よりも多い金額が支給されることが多いです。
メリット3:収支が安定する
建設国保は、収入額に関係なく一律の保険料を支払う健康保険です。ある程度の収入がある人にとっては、支出額の変動がないのは非常にありがたい制度です。
また、建設国保に加入している人は、現在現役で働いている人が大半です。安定した収入があるため、収支のバランスが取りやすくなる面もメリットといえます。
保険料が一律となると、他の部分での収支のバランスが取りやすくなるので、それも嬉しい点です。一律の保険料なので、個人経営者で確定申告を行うときなども計算がスムーズに行えます。
メリット4:保険料の事業者負担がない
先ほども少し触れましたが、建設国保は被保険者が全額負担する健康保険です。そのため、会社の経費削減にもつながります。経営者としては、非常に便利な健康保険なのです。
一人親方など、自分一人で仕事をしていて、ある程度の収入を安定して稼げるのであれば、建設国保はおすすめの健康保険といえます。
しかし、従業員がいる場合は、保険料が従業員負担となってしまうので、保険料を全額支払ってもらう分、給与を少し増やすなどの対策が必要です。あえて、建設国保の保険料を、福利厚生の一環で、事業主と折半負担するケースもあります。
建設業で建設国保に加入するデメリット
建設国保には、メリットがある反面デメリットも存在しています。どのようなデメリットがあるのかを把握し、メリットと併せて確認しておきましょう。自分や雇っている従業員に対してどの健康保険を会社で採用すべきなのかを見極め、みんなが納得する結果を導き出すことは、経営者として見過ごすわけにはいかない部分といえます。
一人親方として活躍している人も、建設国保のデメリットを把握しておいて損はありません。メリットとデメリット双方を確認し、健康保険を選びましょう。
デメリット1:従業員負担が大きい
建設国保は、協会けんぽなどよりも保険料が、被保険者の年齢、扶養する家族構成によっては高く設定されています。高い保険料を、従業員が全額負担するとなると、従業員の給与が保険料の分減ってしまいます。
会社で保険料を折半するわけではないので、全額の支払いとなると、月に数万円という決して安くない額の金額を従業員自身が払うことになります。
給与そのものがあまり高くない場合は、従業員の負担が大きい建設国保を採用してしまうと会社の印象が悪くなってしまうので注意すべきです。
デメリット2:小規模な事業所しか加入できない
建設国保は、5名未満の個人事業所や一人親方などの少数の会社しか加入できません。一人親方であっても、法人化してしまったら建設国保に加入できない仕組みになっています。法人化していなくても、従業員数が5名以上の場合は加入不可なので、その点は絶対に注意しておきましょう。
条件に当てはまらず、加入できない場合は、国民健康保険などほかの健康保険に加入しなければならなくなります。建設国保に加入を検討している人は、自分が加入できる条件であるかを確認しておくと安心です。
※建設国保に加入後、条件に当てはまらなくなっても、所定の手続きをおこなえば、引き続き建設国保に加入できます。
デメリット3:家族分は全て組合員の負担になる
建設国保は、家族の人数分組合員がお金を負担することになっています。保険料は所得のみならず住んでいる地域も含めて一定金額ですが、家族の人数によって、地域によっては少し保険料が割高になってしまうことがあります。
健康保険を選ぶときは、自分一人だけではなく、養う家族がいる人は家族の人数や就業状態などもチェックしておく必要があるのです。綿密な計算をして、どの保険が自分と家族にとってぴったりなのかを見極めましょう。
建設国保の加入がおすすめの人
これまで、建設国保のメリット、デメリットについて解説してきました。それぞれを考えた上で建設国保に加入することがおすすめの人はどのような人なのでしょうか。ここでは、建設国保に加入することがおすすめの人とその理由について解説していきます。
一定以上の収入がある一人親方
建設国保は一定以上の収入がある一人親方におすすめです。国民健康保険は所得が上がれば上がるほど保険料が上がりますが、建設国保は所得が上がっても保険料は一定だからです。
例えば、令和5年、東京都大田区在住で所得500万円、28歳の一人親方の場合、それぞれの保険料は以下となります。
| 建設国保 | 国民健康保険 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 保険料(月額) | 14,600円 | 41,530円 | 26,930円 |
| 保険料(年額) | 175,200円 | 498,363円 | 323,163円 |
選択する健康保険が違うだけで年額30万円以上の差が生まれます。選択する健康保険を誤ってしまうと、それだけのお金を支払うことになるので、慎重に選択することが重要です。
一定収入以上の収入がある一人親方は建設国保への加入がおすすめです。
家族分も含めて国保よりも保険料が安くなる人
建設国保に家族も加入する場合、家族分の保険料も負担する必要があります。加入者本人が全額を負担するため、家族単位で考えた場合、国民健康保険の方が保険料が安くなる場合もあります。
例えば、令和5年、東京都大田区在住で所得500万円、45歳で家族3名が加入する場合の保険料は以下となります。
| 建設国保 | 国民健康保険 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 保険料(月額) | 46,700円 | 41,530円 | -5,170円 |
| 保険料(年額) | 560,400円 | 498,363円 | -62,037円 |
家族も含めて考えた際に建設国保が安くなる方は建設国保への加入がおすすめです。選択する際は家族全体での負担額と自身での負担額を考えて選択するとよいでしょう。
建設業が建設国保に加入する方法
建設国保に加入するときには、今まで説明した従業員人数や法人化していないという条件を満たしておかなければなりません。条件を満たしている人は、手続きをすれば建設国保に加入できます。
被保険者本人と家族としての建設国保への加入方法、加入時に必ずそろえておかなければならない書類と、シチュエーション別の必須書類の情報をまとめました。
建設国保への加入を検討している人は、ぜひ参考にしてみてください。必要な書類は複数あるので、早めに準備しておくことをおすすめします。
被保険者本人の加入方法
建設国保に加入する条件が整っている人は、被保険者になるための手続きを進めましょう。まず調べたいのが、建設国保の支部や出張所です。ホームページを検索すれば、住んでいる地域のものがすぐにヒットするので、とっても簡単です。
支部や出張所に出向き、「加入申請書」と「重要事項説明同意書」をもらって記入します。そのほかにも必要な書類は複数あるのでチェックしておきましょう。支部や出張所に行く前に資料をそろえておくと、スムーズに建設国保に加入できます。
必要書類
建設国保に加入する際、上記で紹介した2種類の書類とは別にそろえておくべき資料があります。
まずは、世帯人数分の住民票です。これは、証明日より3か月以内のものをそろえる必要があります。住民票は市役所やコンビニで取得可能です。
次に、保険加入者と一緒に住んでいる世帯の人の被保険証の写しを用意しましょう。こちらはコピーを取ればよいので、コンビニや自宅のプリンターを使います。
最後に、現在の業種や業態が確認できるものを用意します。先ほどの資料と併せて、5種類の書類を用意しておきましょう。
その他必要書類
その他に必要な書類は、現在の会社の状態や家族の状況によって変わってきます。
現在5人以上の従業員を雇っていたり、法人事業所の従業員である場合は、健康保険証被保険者適用除外承認証が必要です。従業員人数が規定人数以内の個人事業所に勤務している場合は、雇用保険資格確認通知証か雇用証明書が必要になります。
住民票には一緒に記載されているけれど、建設国保に加入していない人がいる場合は、該当する人の被保険者証のコピーを持参しましょう。
離れた場所で勉学に励む家族がいる場合は、該当する人の在学証明書が必要です。
家族として加入する
建設国保の組合員の同居家族も、建設国保に加入できます。75歳未満であることと、上記で紹介した書類を集めて提出することが加入条件です。
同居ではなく、進学で別居している子どもも加入可能です。その場合は、上記で紹介したように在学証明書が必要になります。そろえなければならない書類は、同居家族であれば特別なものはありません。
コンビニでそろえられるものが中心で、在学証明書は常に持っているはずなので、加入の際は手際よく資料を集めておきましょう。
参照:資格・適用のご案内(加入手続き) | 保険の手続き | 全国建設工事業国民健康保険組合
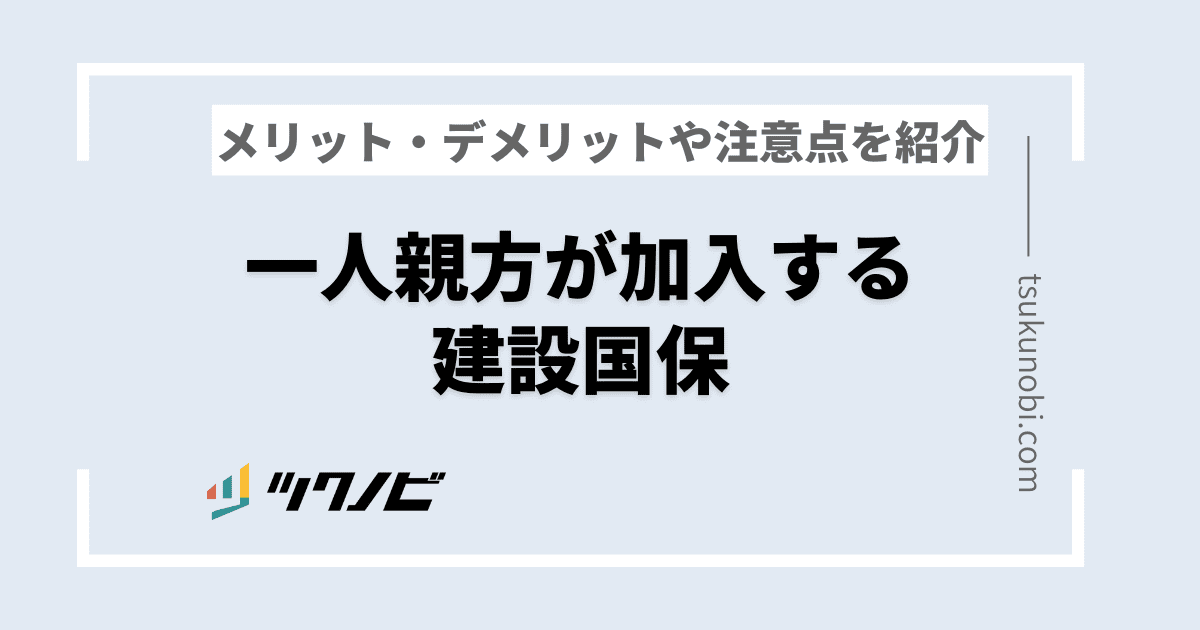 建設国保に一人親方が加入するメリット・デメリットや注意点を紹介
建設国保に一人親方が加入するメリット・デメリットや注意点を紹介
健康保険についてプロに無料相談するなら「社会保険労務士法人TSC」がおすすめ
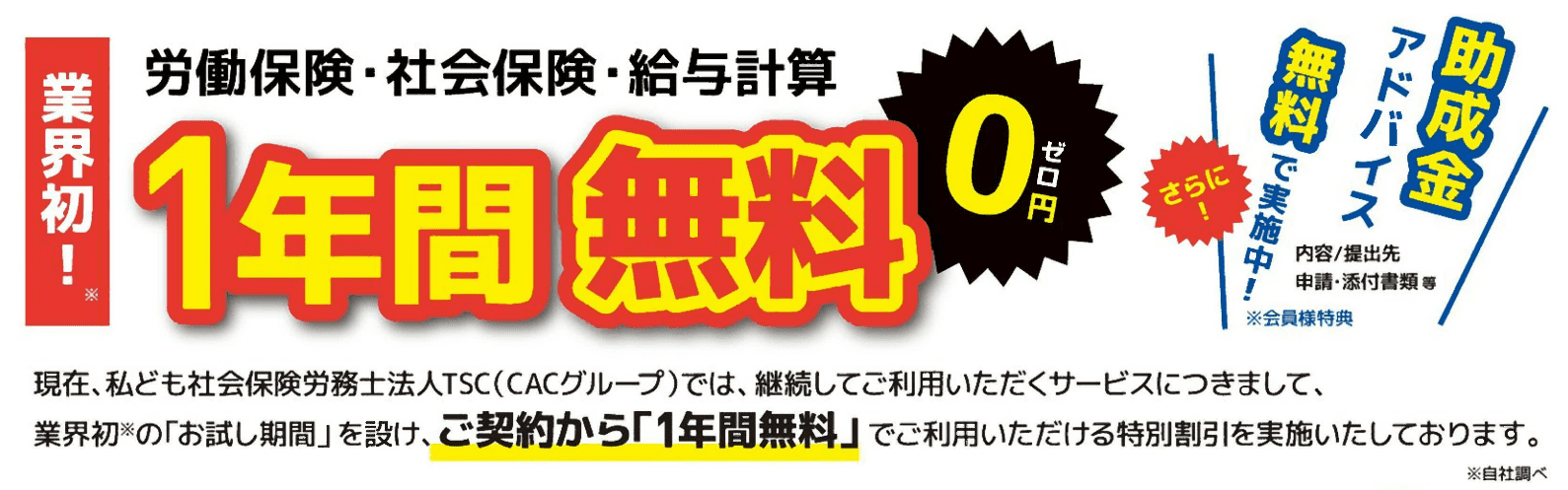
社会保険労務士法人TSCは1年間無料でサービス利用できる社労士です。そのため「お試しで社労士に依頼したい」という方にもおすすめです。社会保険や労務関係の業務を丸ごと委託できるだけでなく、個人事業主が法人化する場合の社会保険の手続きなどもサポートしてくれます。
 【一人親方必見】おすすめの労災保険ランキング!人気の保険を8つ紹介します
【一人親方必見】おすすめの労災保険ランキング!人気の保険を8つ紹介します
建設業のプロ人材を採用したいならツクノビBPOがおすすめ
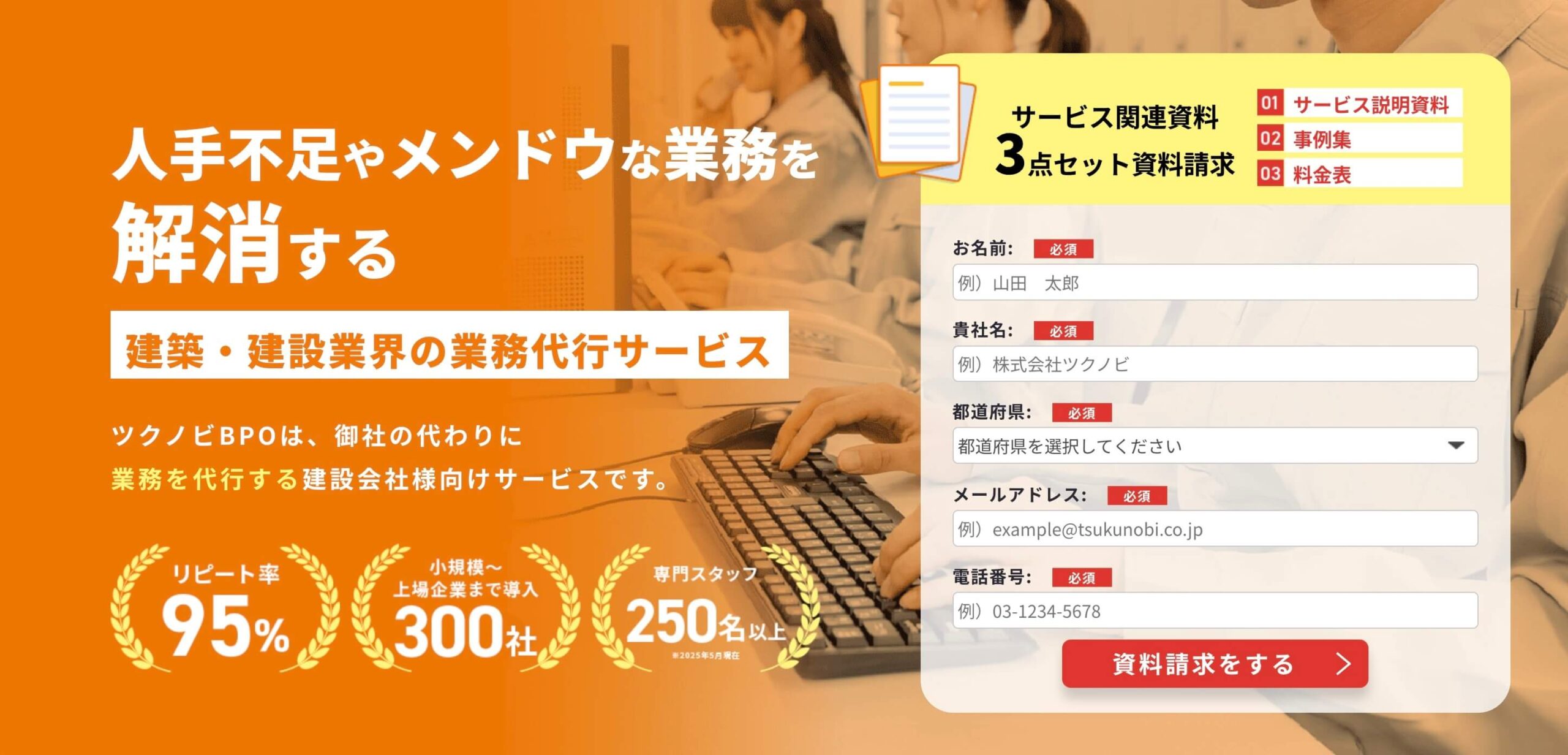
対応したことのない業務が発生した場合や業務に対応できる人材が不足している場合は建設業のプロ人材を活用することがおすすめです。
建設業特化の業務代行サービス「ツクノビBPO」は、建設業の経験が豊富なプロ人材が御社の業務を代行するサービスです。採用倍率200倍を乗り越えた選りすぐりのプロ人材を採用しているため、安心して業務を依頼できるでしょう。
対応可能な業務は施工管理や建設業事務、書類作成、各種申請業務、CAD図面作成、積算など多岐にわたります。業務をただ代行するだけでなく、作業効率が高い方法のご提案や業務マニュアル作成などで御社の作業効率の向上に貢献いたします。
業務の品質を上げたい方やこれまで対応できなかった業務にも対応していきたい方、作業効率を上げたい方などはぜひこちらから詳細をご確認ください。
【まとめ】建設業におすすめの健康保険は建設国保!協会けんぽや国民健康保険とも比較して加入を検討しましょう
建設業の中でも、少人数の事業所や一人親方で仕事をしていて高収入の人には、建設国保加入がおすすめです。自分が条件に当てはまっているかをチェックし、少しでも保険料を安く、よいサービスの保険に加入するよう保険を選びましょう。
建設国保だけではなく、協会けんぽや国民健康保険も、保険内容はしっかりと把握しておくべきです。一か月でかかる保険料や内容を比較して、保険に加入しておくことで、万が一のとき家族と自分を守ることにもつながります。
一人親方が法人化するメリット・デメリットについてはこちらでより詳しく解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
 一人親方が法人化するメリットは?デメリットやタイミング、会社設立の流れも紹介
一人親方が法人化するメリットは?デメリットやタイミング、会社設立の流れも紹介
工事保険おすすめ6社!工事中に発生するリスクや選び方などを解説の記事はこちら
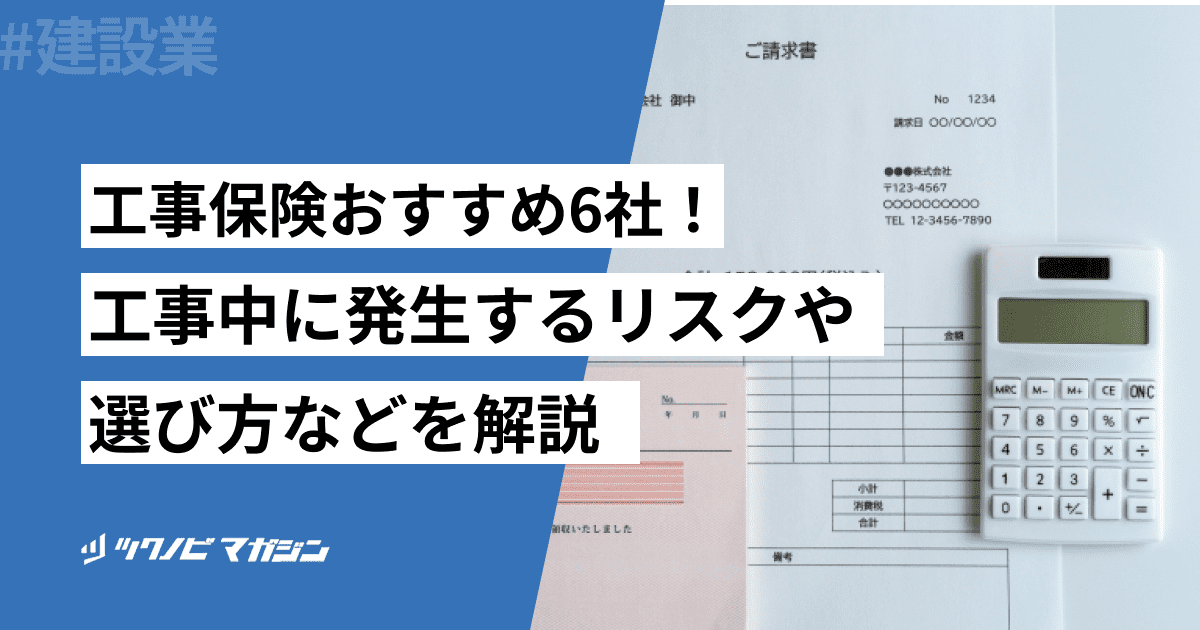 工事保険おすすめ6社!工事中に発生するリスクや選び方などを解説
工事保険おすすめ6社!工事中に発生するリスクや選び方などを解説
※ちなみに弊社では、建築建設業界特化の
無料ホームページ制作代行を新たにスタートさせました! 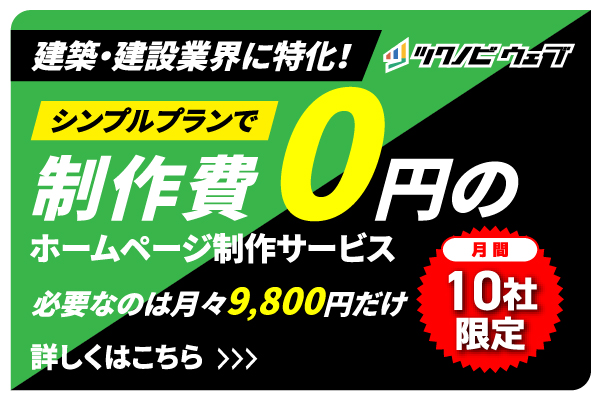 ※詳しくは👆👆👆のバナーをクリック!!
※詳しくは👆👆👆のバナーをクリック!!