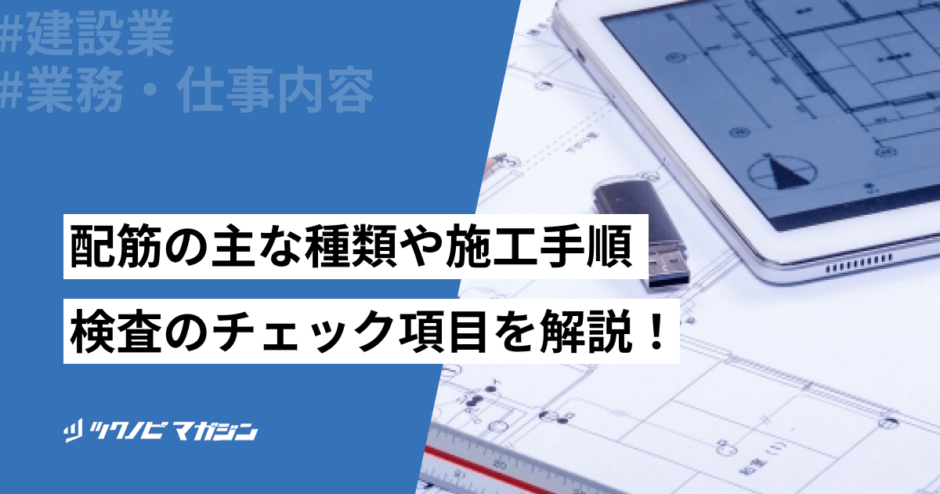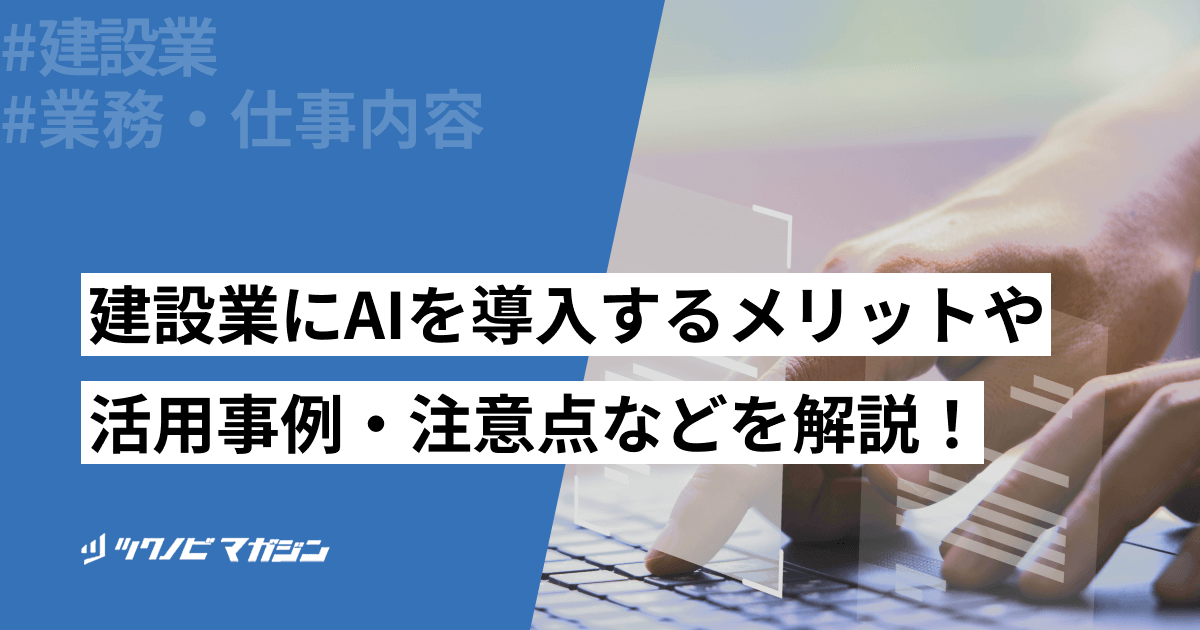※記事内に広告を含みます
配筋は、丈夫な建物を建造するために重要な要素の1つです。配筋には、箇所や用途によって様々な種類があります。種類ごとにいくつもの呼び名があることも特徴です。対応を間違えないように、種類と名称を覚える必要があります。
配筋の種類や名称を知り、手順を守って施工することが大切です。また、配筋後、適切に配筋検査をすることが求められます。
本記事では、配筋の主な種類、施工手順、配筋検査のチェック項目などを解説します。配筋について知りたいと思っていた人は、ぜひ本記事を参考にしてください。
配筋とは
鉄筋を適正な数量・位置で配置することを「配筋」と呼びます。配筋に使用される鉄筋の種類、鉄筋以外の材料を以下で解説します。
配筋に使用される鉄筋の種類
配筋に使用される鉄筋の種類に、SR(Steel Round:丸鋼)とSD(Steel De-formed:異形棒鋼)の2つが挙げられます。
SRは、表面に突起のない、円柱形の鋼材です。SDは、リブや節と呼ばれる突起が表面に設けられた棒状の鋼材です。
SRはコンクリートに付着しにくい一方で、SDは表面の突起によってコンクリートに対する付着性が高められています。現在は、コンクリートに付着しやすいSDが主に鉄筋として利用されています。
鉄筋以外の材料
鉄筋以外の材料に、結束線とスペーサーが挙げられます。
結束線は、鉄筋同士を結束して固定するために使う針金です。ハッカーと呼ばれる専用工具を用いて、鉄筋と鉄筋を結束線で固定します。
スペーサーは、配置した鉄筋が動かないように固定しつつ、かぶり厚さを保つために設置される材料です。かぶり厚さは、鉄筋とコンクリート表面の間の距離を指します。かぶり厚さが足りないと、コンクリートが経年劣化によりひび割れた際に、侵入した雨水によって鉄筋が錆びてしまうかもしれません。
スペーサーを設置して適切なかぶり厚さを保つことで、コンクリート内の鉄筋を保護できます。
配筋の主な種類
配筋の種類は主に以下のとおりです。
- 主筋
- 帯筋
- あばら筋
- シングル配筋
- ダブル配筋
- はかま筋
- 千鳥配筋
それぞれの特徴を解説します。
主筋
主筋(しゅきん)は、柱や梁などを構成する主要な配筋です。軸方向に配置されることから、軸方向筋とも呼ばれます。柱であれば上下を貫く太い鉄筋、梁であれば上部と下部に水平に配置される太い鉄筋が主筋です。
主筋は、柱、梁、基礎などの荷重を支えなければなりません。十分に荷重を負担できるよう、構造計算によって主筋の太さや本数などが算出されます。
また、主筋を補強するために、後述する帯筋やあばら筋が設けられます。
帯筋
帯筋(おびきん)は、柱に対して垂直に、外周部を囲むように設けられる配筋です。フープと呼ばれることもあります。
主筋がばらばらになることを防ぐことが帯筋の役割です。
また、帯筋を設けることで、「せん断力」への抵抗力を高められます。
せん断力は、ものをずらそうとする力であり、建物の耐久性を高めるために考慮しなければならない重要な要素です。地震の際に、建物の部材に大きなせん断力が加わります。大きなせん断力が加わったとき、コンクリートだけでは耐えられないため、柱に帯筋を設けます。
あばら筋
あばら筋は、梁に対して垂直に、外周部を囲むように設けられる配筋です。柱に設けられる配筋が帯筋、梁に設けられる配筋があばら筋です。馬具の一種である鐙(あぶみ)に見た目が似ていることから、スターラップ(stirrup)とも呼ばれます。
あばら筋には、帯筋と同様に、主筋がばらばらになることを防ぎ、せん断力への抵抗力を高める役割があります。
あばら筋の種類は主に、梁の主筋の上端と下端を囲む閉鎖型と、フック部を上端に引っかけるU字型の2つです。
シングル配筋
シングル配筋は、壁やスラブなどで鉄筋を1列に配置する工法です。
後述するダブル配筋よりも配置する鉄骨が少なく済むことがメリットです。鉄筋が交錯する箇所でも、シングル配筋によって整然と鉄筋を配置できます。
ただし、鉄筋の数量が少なく済む分だけ、部材の耐力が低いことが欠点です。耐力が低いことから、コンクリートにひび割れが発生しやすいこともデメリットに挙げられます。
現在は、後述するダブル配筋が主流です。
ダブル配筋
ダブル配筋も工法の1つです。シングル配筋が2列に鉄骨を並べるのに対し、ダブル配筋では鉄筋を2列に配置します。
鉄筋の数量が多いため、耐力が高めです。シングル配筋よりも高い耐力により、大きな荷重や振動に耐えられます。
ただし、鉄筋の数量が多い分、コストが高いことがデメリットです。また、建材に一定以上の厚さがないと、ダブル配筋を採用できません。
丈夫であることから、現在はダブル配筋が普及しています。
はかま筋
はかま筋は、基礎スラブの上部・側面に籠のように設けられる配筋です。下部・側面に設けられるベース筋ごと覆うように配置されます。はかま筋と呼ばれる理由は、下部が開いており、基礎スラブを覆うように設けられている姿が袴に似ているためです。
はかま筋には、コンクリートのひび割れを防ぐ役割があります。
直接基礎の場合、計算上、はかま筋は必要ありません。ただし、ひび割れ防止のためにはかま筋を設けることが一般的です。
杭基礎の場合、計算上はかま筋が必要です。
千鳥配筋
千鳥配筋は、定められたピッチの半分ごとに、左右交互にずらしながら鉄筋を配置する、ダブル配筋の1種です。千鳥の足跡のように左右交互に鉄筋が設けられることが、千鳥配筋という名前の由来です。
通常のダブル配筋やシングル配筋よりも鉄筋を密に配置して強度を高められることから、千鳥配筋は薄い壁で採用されることが多くあります。
特に鉄筋を配置する位置に注意しなければならず、正確な施工が求められます。
配筋施工の手順
配筋の施工は、以下の手順で実施します。
- 施工計画書を作成する
- 施工図・鉄筋加工図を作成する
- 鉄筋を図面通りに作り上げる
- 鉄筋を工事現場へ搬入する
- 基礎部分の配筋作業を行う
それぞれの項目を解説します。
施工計画書を作成する
設計図をふまえて施工計画書を作成します。
請負代金が500万円(税込)以上である場合、建設業法により、施工計画書の作成・提出が義務付けられています。請負代金が500万円以下であっても、発注者から求められた場合は施工計画書を作成・提出しなければなりません。
施工計画書には、工事のスケジュールだけでなく、施工の進め方、安全管理、使用する材料や機械なども具体的に記載します。適切な施工計画書を作成・提出することで、未然にトラブルを防ぎ、円滑に施工を進められるでしょう。
施工図・鉄筋加工図を作成する
施工計画書を基にして、施工図と鉄筋加工図を作成します。
施工図には、部材の寸法、形状、型式などを具体的に記載します。特に、設計図だけではわかりにくいような箇所について詳細に記載しましょう。後述する配筋検査の際に施工図が必要なので、変更がある都度、修正してください。
鉄筋加工時には、使う材料、加工寸法、本数などを明記します。誰が見ても必要な材料や構成がわかるように、丁寧に作成しましょう。
鉄筋を図面通りに作り上げる
作成した施工図や鉄筋加工図などを確認して、図面どおりに鉄筋を作り上げます。
鉄筋の加工は、現場ではなく加工業者の工場で実施されます。工場で実施することで、現場よりも正確な加工が可能です。
切断加工、曲げ加工だけでなく、ある程度組み立てておくユニット化も実施されることがあります。ユニット化することで、現場で円滑に組み立て作業を進められ、工期を短縮できるでしょう。
鉄筋材料は、元請により材料メーカーに発注され、加工業者の工場に納入されます。
鉄筋を工事現場へ搬入する
加工した鉄筋を工事現場に搬入します。
鉄筋の搬入は大規模になるケースも多いため、円滑な現場作業と安全確保のために、計画的に搬入作業を実施することが求められるでしょう。
搬入が完了したら、その場で検収することが大切です。鉄筋が図面どおりに加工されているか、数が足りているかを確認します。確認せずに組み立て作業を始めると、トラブルにつながるかもしれません。十分に検査し、写真を残しておきましょう。
基礎部分の配筋作業を行う
搬入された鉄筋に問題ないことを確認したら、基礎部分の配筋作業を実施します。
基礎部分の一般的な配筋手順は以下のとおりです。
- 主筋を配筋する
- 配力筋(主筋に直行する鉄筋)を配筋する
- 鉄筋を結束する
- スぺ一サーを配置する
- 柱筋、地中梁筋、はかま筋を配筋する
配筋時には、鉄筋の上下関係、配置間隔、数量などを十分に確認することが重要です。また、ジョイント部分は、偏りがないように千鳥状につなげましょう。
配筋検査とは
配筋作業の完了後、図面どおりに配筋が実施されているかを検査しなければなりません。
配筋検査に合格したら、コンクリートを打設します。コンクリートを打設したら配筋の状況は見えなくなるので、写真や書面を適切に残すことが重要です。
配筋検査に関する3つの項目について以下で解説します。
- 第三者機関によって行われる配筋検査
- 配筋検査を実施するタイミング
- 配筋検査のチェック項目
第三者機関によって行われる配筋検査
配筋検査は、第三者機関によって実施されます。
検査を担当するのは、住宅性能評価機関や住宅瑕疵担保責任保険法人といった専門機関です。建築業者が委託した機関でなく、施主が委託した住宅検査会社(ホームインスペクター)が検査するケースもあります。
また、図面と巻尺があれば、施主も配筋を確認できます。専門の人だけに任せるのではなく、自分でも図面を見ながら配筋が正しく実施されているか確認してみましょう。
配筋検査を実施するタイミング
配筋検査を実施するタイミングは、コンクリートの打設前です。コンクリートを打設してしまうと、配筋は見えなくなり、検査できません。スムーズにコンクリートの打設に移れるように、あらかじめスケジュールを定めましょう。
また、基礎工事の検査自体には、主に以下のように6回の機会があります。
- 掘り方(遣り方)工事
- 基礎部分の配筋
- 基礎部分のコンクリート打設
- 基礎立上り部分の配筋
- 基礎立上り部分のコンクリート打設
- コンクリート打設後の基礎の仕上がり
配筋検査のチェック項目
配筋検査時に、主に以下の項目を確認します。
- 鉄筋の配置
- かぶり厚さ
- 鉄筋の波打ち
- 鉄筋の定着(2つの鉄筋をつなぎ合わせた際に重なった箇所)の長さ
- 鉄筋の径
- 防水・防湿シートの状態
- ホールダウン金物(柱と土台をつなぐ補強金物)の位置、本数、状態
- アンカーボルトの位置、本数、状態
施工後のトラブルを避けるために、写真や書面で検査項目と検査結果を十分に残すことが大切です。検査の記録は、大切に保管してください。
建設業のプロ人材を採用したいならツクノビBPOがおすすめ
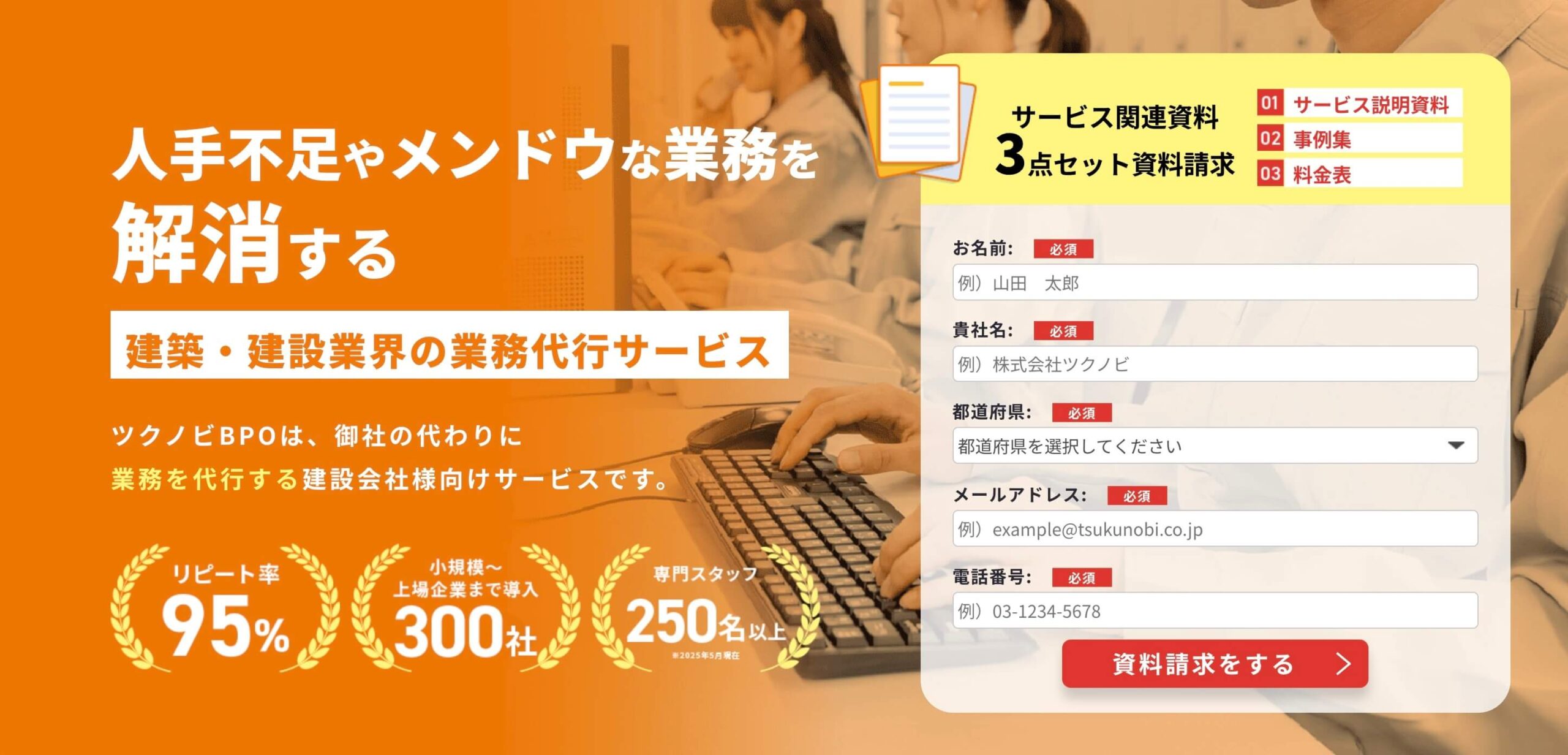
対応したことのない業務が発生した場合や業務に対応できる人材が不足している場合は建設業のプロ人材を活用することがおすすめです。
建設業特化の業務代行サービス「ツクノビBPO」は、建設業の経験が豊富なプロ人材が御社の業務を代行するサービスです。採用倍率200倍を乗り越えた選りすぐりのプロ人材を採用しているため、安心して業務を依頼できるでしょう。
対応可能な業務は施工管理や建設業事務、書類作成、各種申請業務、CAD図面作成、積算など多岐にわたります。業務をただ代行するだけでなく、作業効率が高い方法のご提案や業務マニュアル作成などで御社の作業効率の向上に貢献いたします。
業務の品質を上げたい方やこれまで対応できなかった業務にも対応していきたい方、作業効率を上げたい方などはぜひこちらから詳細をご確認ください。
【まとめ】配筋は建物の安全性に関わる構造部材!よく理解して適切に行おう
配筋の主な種類、施工手順、配筋検査のチェック項目などを解説しました。
配筋には、主筋や帯筋などの様々な種類があり、それぞれ用途や役割が異なります。適切に配筋しないと、地震のような大きな衝撃があった際に、建物が破損してしまうかもしれません。
施工前に、適切な施工計画書や施工図を作成することが大切です。施工後、適切なタイミングで配筋検査を実施して、鉄筋の配置やかぶり厚さなどを十分に確認することも重要です。
ぜひ本記事を参考に、適切に配筋を実施しましょう。
配筋検査や伏図・鉄筋の積算ソフトおすすめ4選についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
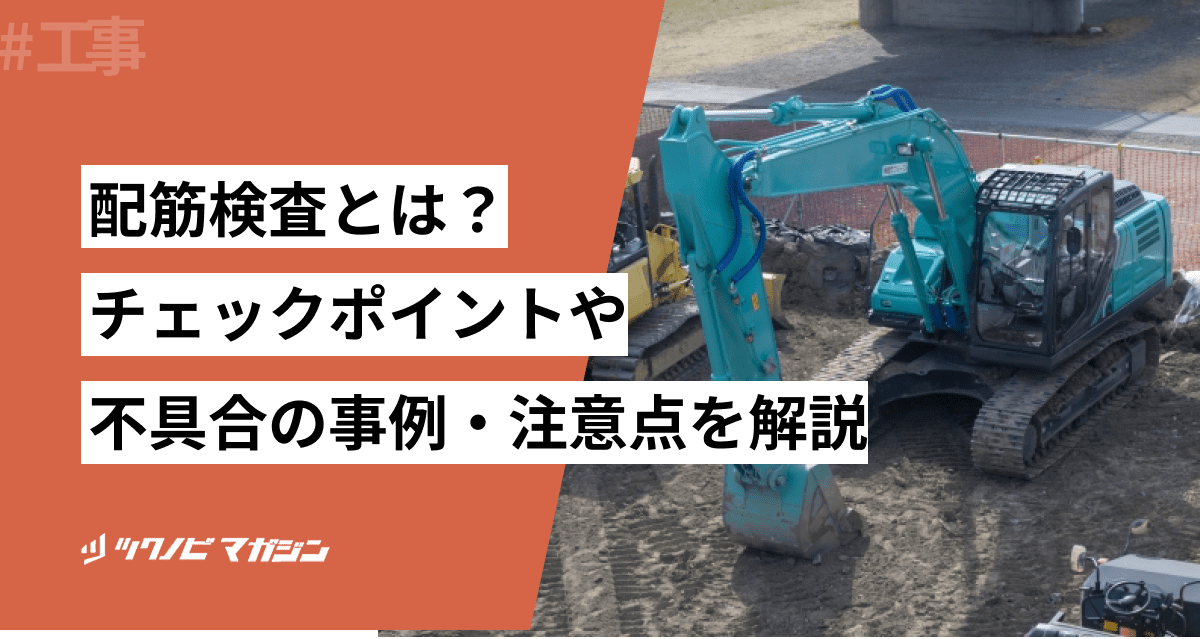 配筋検査とは?チェックポイントや不具合の事例・注意点を解説
配筋検査とは?チェックポイントや不具合の事例・注意点を解説
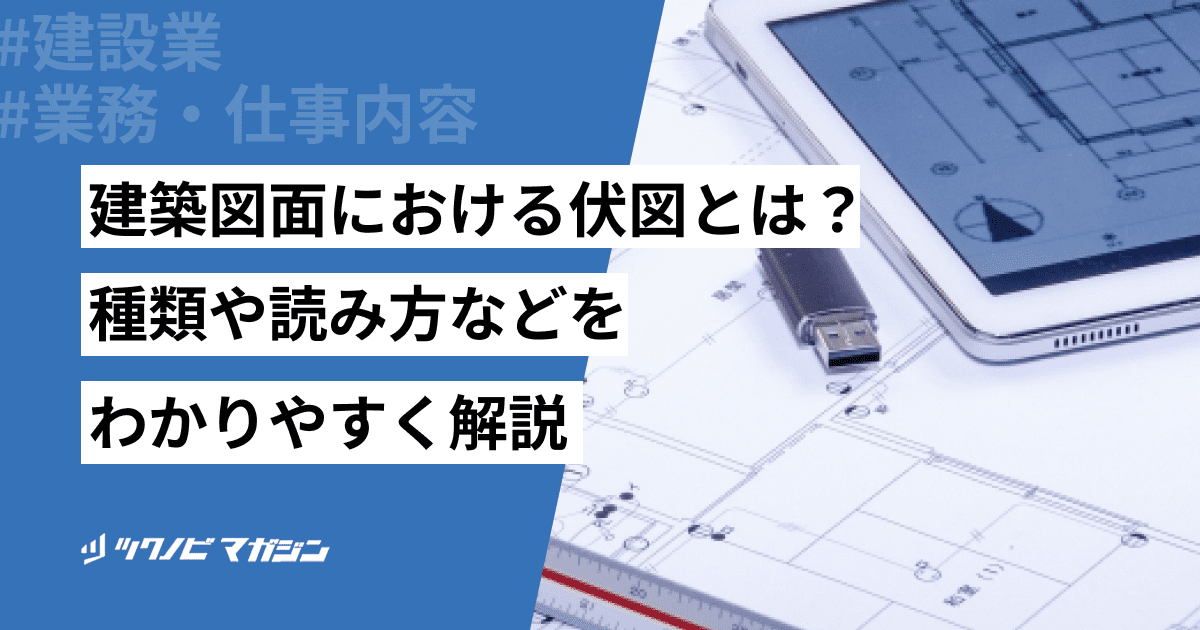 建築図面における伏図とは?種類や読み方などをわかりやすく解説
建築図面における伏図とは?種類や読み方などをわかりやすく解説
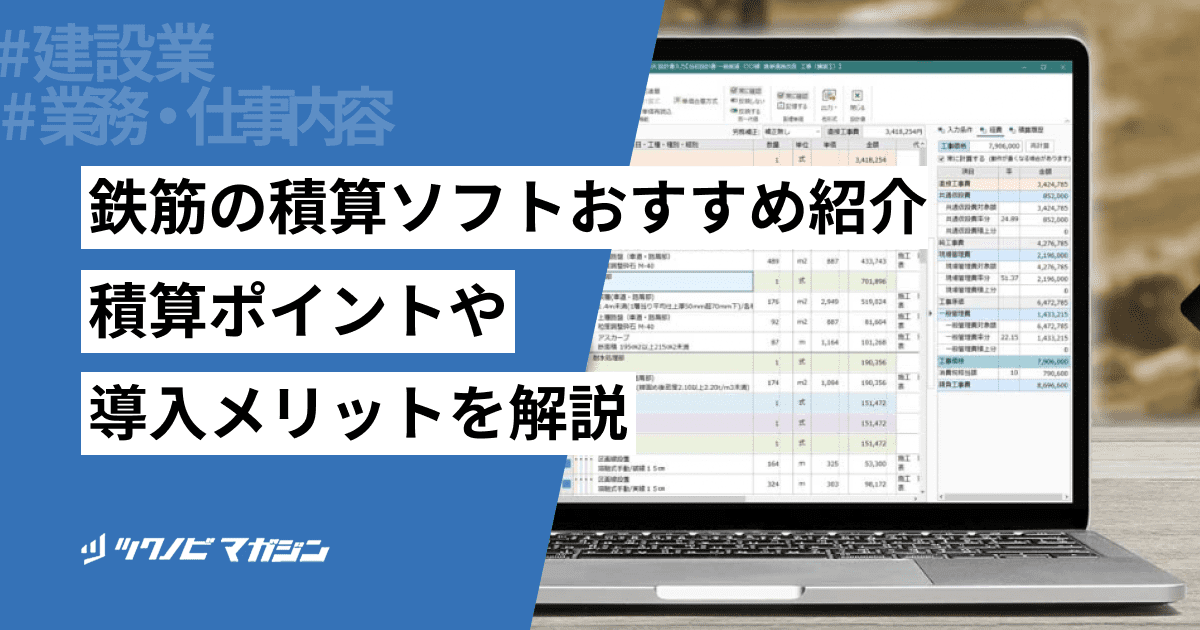 鉄筋の積算方法とは?数量拾いや効率化するポイントなどを解説
鉄筋の積算方法とは?数量拾いや効率化するポイントなどを解説