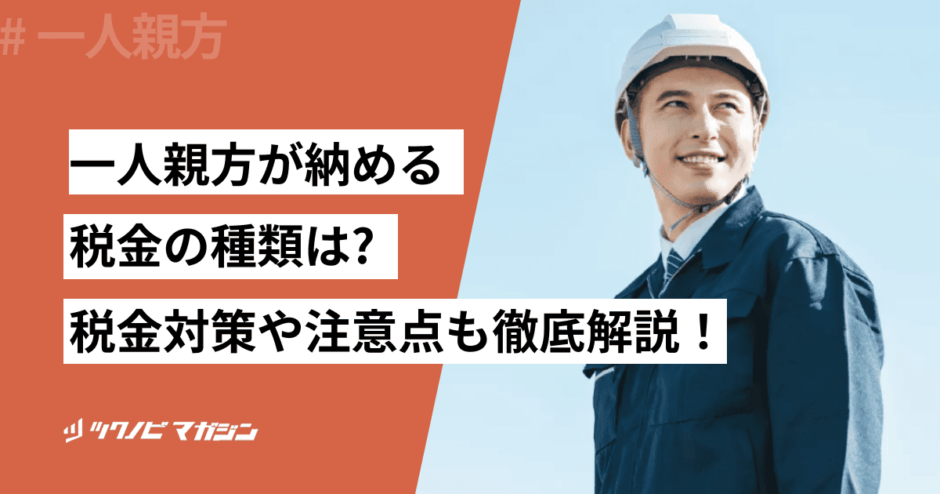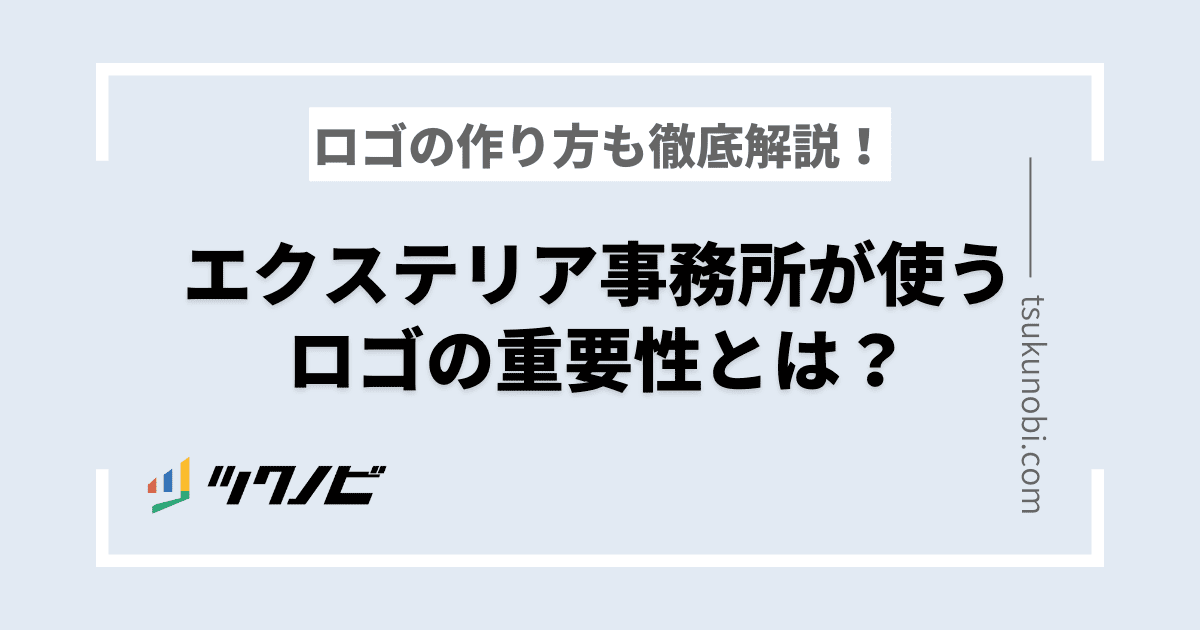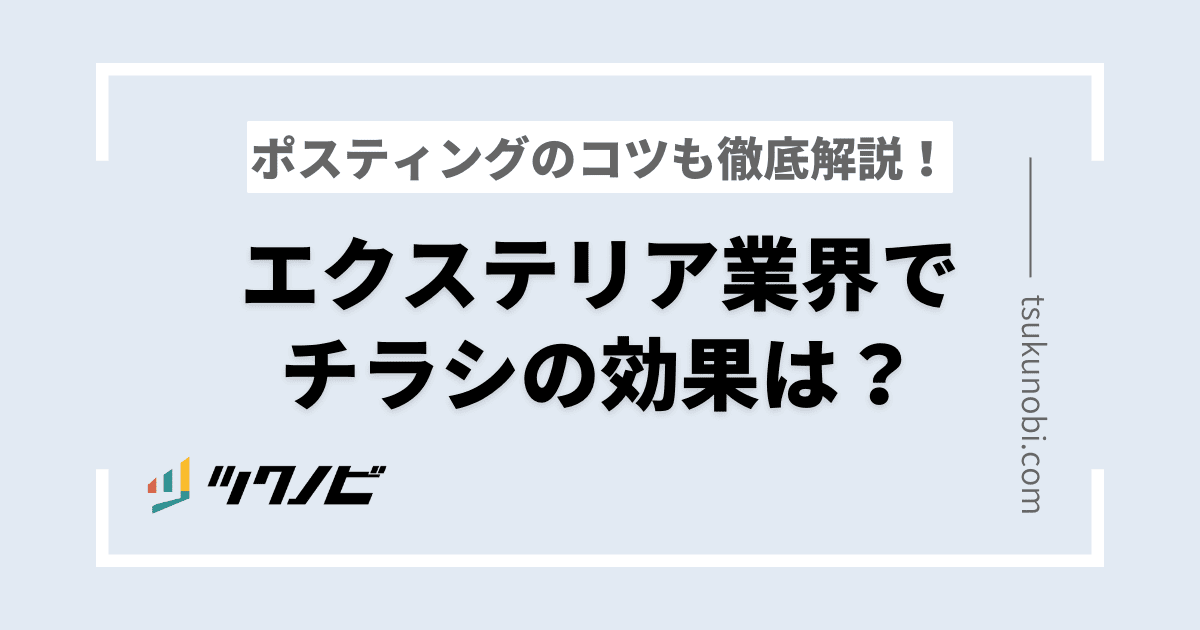※記事内に広告を含みます
一人親方は会社員とは違い、自分で税金の申告と支払いをしなくてはなりません。支払いのためには確定申告の書類を用意し、手続きを行う必要があります。
そのためには、支払う税金の種類や支払い方の知識が必要です。また、節税対策には経費や控除についても知っておかなくてはなりません。
今回は、一人親方に発生する税金の種類や対策方法、税金の支払いなどで注意すべきポイントを解説します。
一人親方が納めるべき税金とは?
一人親方は、個人事業主に該当するため、確定申告を行って税金を納める必要があります。そして、一人親方が納める税金にはいくつかの種類があります。
また、一人親方は確定申告を行うことと自身で税金の支払いを行うことが必要となります。税金の申告と支払いを自身で行う点が会社員との違いです。
確定申告では、毎年1月1日から12月31日までの期間に生じた所得を申告します。確定申告の期間は2月16日から3月15日までです。
一人親方が確定申告を行う方法
確定申告を行う際には、「青色申告」と「白色申告」という2つの申告方法から申告方法を選ぶ必要があります。それぞれの方法によって、メリットとデメリットがそれぞれあります。
ここからは、確定申告の方法について解説していきます。
青色申告
青色申告は、日々の取引を記録した内容に基づき確定申告を行う方法です。青色申告を行う際は、収入金額や経費に関する日々の状況を記録した帳簿が必要となります。
青色申告の大きなメリットは、最大で65万円の控除を受けられる点です。条件によって控除額は異なり、「10万円」「55万円」「65万円」の3種類があります。「55万円」か「65万円」の控除を受けるためには、複式簿記で記帳する必要があります。
青色申告は帳簿付けが必要になるため、面倒に感じるかもしれませんが、会計ソフトを活用すると簡単に対応できます。青色申告を選択する場合は、自身に合った会計ソフトを探してみるとよいでしょう。
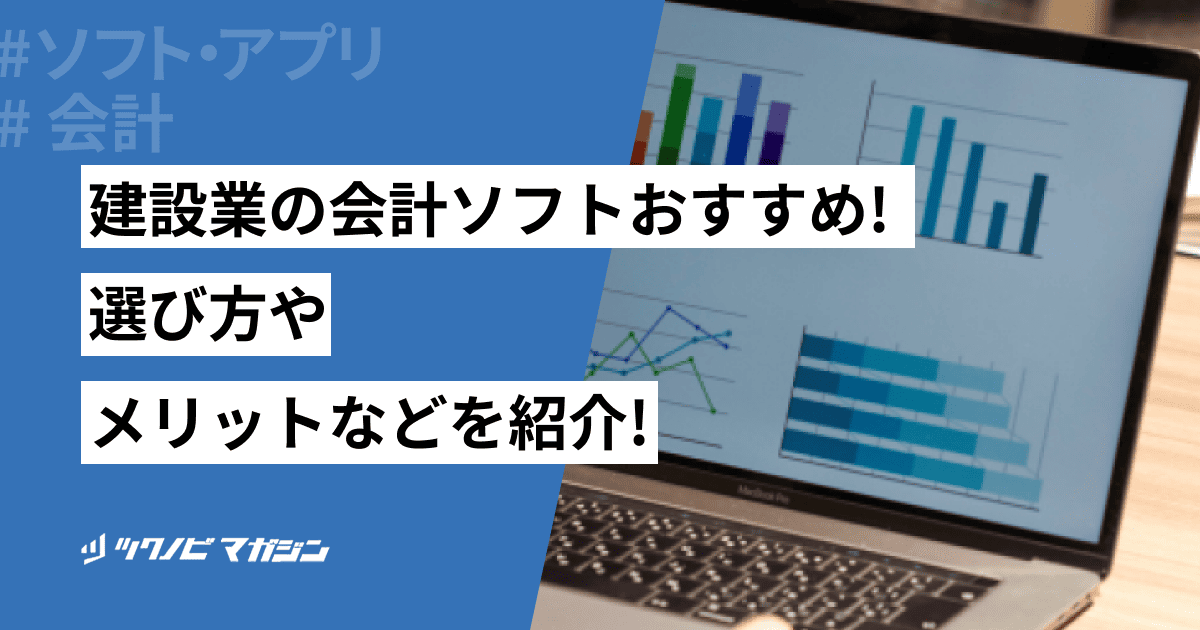 建設業界で活用できる会計ソフトおすすめ7選!選び方やメリットも解説
建設業界で活用できる会計ソフトおすすめ7選!選び方やメリットも解説
白色申告
白色申告は、青色申告よりも簡単な申告方法です。白色申告で確定申告を行う際には、収支内訳書、確定申告書が必要となります。青色申告とは異なり、貸借対照表と損益計算書が必要ありません。
白色申告のメリットは、青色申告よりも簡単に確定申告をできる点でしょう。所得金額を正確に計算できる限りは、個々の取引を記載する必要はありません。
ただ、最大65万円の控除を受けられない点は大きなデメリットとなるため、注意が必要です。確定申告は税理士に依頼もできるため、依頼したい場合は税理士ドットコム![]() などを使って税理士を探してみてもよいでしょう。
などを使って税理士を探してみてもよいでしょう。
建設業におすすめの税理士についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
 建設業に強い税理士おすすめ15選!選び方や依頼するメリットも紹介!
建設業に強い税理士おすすめ15選!選び方や依頼するメリットも紹介!
一人親方が納めるべき4つの税金
一人親方が支払う税金は、全部で4つです。
- 所得税
- 住民税
- 消費税
- 個人事業税
それぞれ内容が異なるため、まずは支払わなくてはならない税金について学びましょう。
4つの税金について解説します。
「帳簿付けが面倒、、」「税金の計算が大変、、」という方におすすめなのが、アプリが自動的に帳簿付けをしてくれて、確定申告もパッと終わるアプリのTaxnap(タックスナップ)です!
無料で利用ができることから、2023年にリリースしてすぐに5万ユーザー突破しました!
所得税
所得税は、1年間で得た所得に対し課せられる税金で、国に納めます。所得税は、以下の流れで計算されます。
収入-必要経費=所得
所得-所得控除=課税所得
課税所得×課税額に応じた税率=所得税の金額
所得とは、収入から必要経費を差し引いたものです。
一人親方の場合、工事にかかった報酬から、施工に必要な建材や現場に行くためにかかったガソリン代などを差し引いた額が該当します。
所得からさらに控除分の金額を引くと、課税される金額が分かります。この金額に応じた倍率をかけて算出した額が、所得税の金額です。
所得税の税率は、課税額が多くなれば多いほど大きくなる仕組みで、この仕組みを「累進課税制度」と呼びます。
所得税の倍率は最低5%・最大45%と、課税額により支払う金額が大幅に変化します。節税対策をする際は、所得税の税率に注目しましょう。
住民税
住民税は、済んでいる地域の社会を守るために徴収される税金で、地方税の一種です。住んでいる土地の都道府県に納めます。住民税は、以下2つの要素で構成されています。
均等割額…都道府県民税:1,500円+市町村民税:3,500円 =5,000円
所得割額…前年の収入に都道府県民税は4%、市町村民税は6%をかけた金額
この2つの金額を掛け合わせたものが、住民税の金額です。住民税を構成する金額は、一部が所得税のように自分の収入により金額が左右されます。計算する際はご注意ください。
消費税
消費税は国税の一種で、商品やサービスの購入金額に対して課されます。個人の買い物でも発生する税金ですが、一人親方が国に納める場合は仕事上の請求金額にも発生します。
課税される条件は決まっており、開業から2年間は全額免除されるため、納付する必要はありません。また、2年を超えても以下の条件を満たす場合も課税対象外です。
- 前々年度の課税売上高が1,000万円以下
- 前年度1~6月の課税売上高もしくは給与支払高が1,000万円以下
- 個人事業主として課税事業者届書を提出していない
なお、前年度の1〜6の売上高と給与支払いの両方が1,000万円を超えると、開業2年目でも納税しなくてはならない可能性があります。
消費税の課税額は、以下の計算式を使って算出します。
課税売上高の10%-課税仕入れなどの10%=消費税
なお、2019年からはこの計算式で算出されていますが、消費税の税率や計算方法が変わる可能性もあります。計算する際は、現在の計算式を確認してから算出してください。
建設業の一人親方が払うべき消費税についてはこちらの記事でも解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
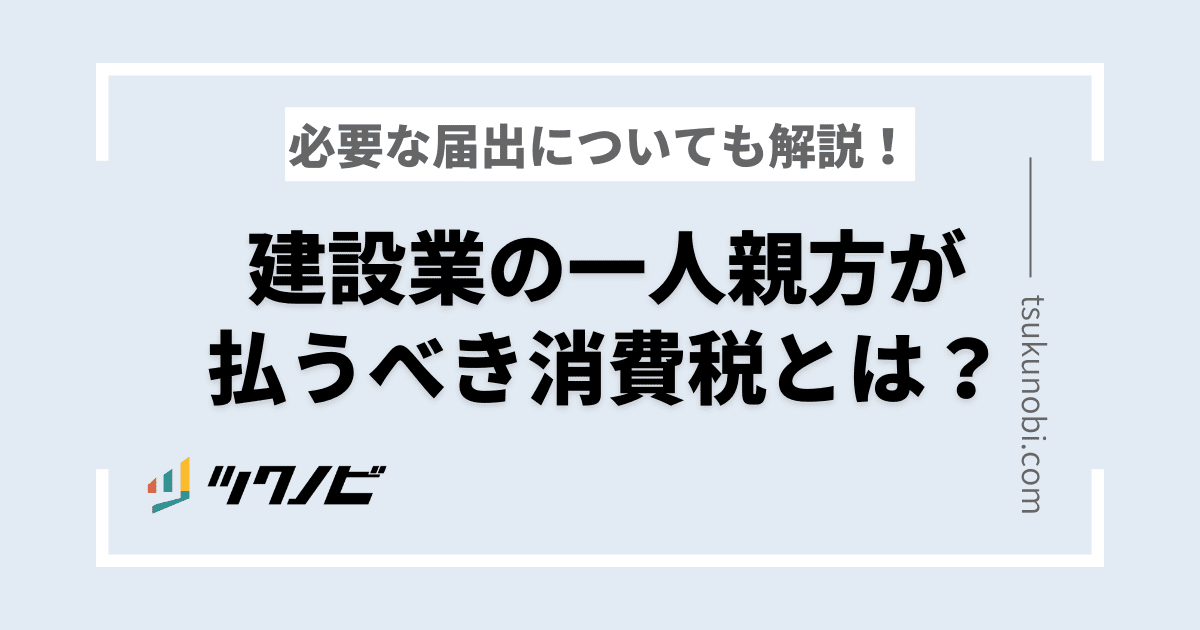 建設業の一人親方が払うべき消費税とは?必要な届出についても解説!
建設業の一人親方が払うべき消費税とは?必要な届出についても解説!
個人事業税
個人事業主は、一人親方などの事業主に課税される税です。住民税と同じく地方税で、あらかじめ290万円分の控除が設けられています。
よって、1年間の所得が290万円以下なら、支払う必要はありません。290万円以上所得があっても、仕事が法定業種に含まれない場合、課税対象から外れます。
上記ののい場合は、以下の計算式を用いて算出した額を支払います。なお、個人事業主は業種ごとに税率が決められており、一人親方が多い建設業は5%です。
計算式をまとめると、以下のようになります。
(所得-各種控除-基礎控除:290万円)×5%=個人事業税の金額
一人親方が税金対策として計上すべき経費10種類
所得税をはじめとした税金の額は、所得により決められています。所得は収入から経費を差し引いた額から求められるため、経費が多ければ多いほど支払う税金の額も少なくなるのです。
税金対策の基本は、計算できる経費を積極的に計上することから始めます。経費を正しく計上するには、経費項目の内容とルールを知っておくことが大切です。次は、一人親方が税金対策として計上すべき経費の中でも、特にかかわりの深い項目を解説します。
消耗品費(材料費)
消耗品費は、仕事上必要な材料を購入した場合に計上できる経費です。一人親方の場合だと、建材や部品、契約に必要な書類や領収書の用紙などが該当します。計上できる費用は、以下の条件を満たしたものです。
- 購入金額が10万円以上である
- 使用可能期間が1年未満である
この条件に合致しないものは、別の費用で計上します。混同しないようご注意ください。
水道光熱費
仕事の際に使用した水道代・ガス代・電気代も計上できます。事務所で電気代や水道代などが発生している場合は、その費用をそのまま経費にできます。
なお、一人親方として仕事をしている方の中には、自宅をそのまま事務所として使っている方もいらっしゃるでしょう。
このような場合は、費用を仕事用とプライベート用に分けて計上します。この考え方は「家事按分」といい、このほかの経費でも発生するため、覚えておきましょう。
家事按分での割合は、実際に仕事に使っている水道光熱費の割合によります。不自然な割合で計上してしまうと、税務署から問い合わせされるかもしれません。
万が一の事態を避け、遭遇してもきちんとした対応をとるためにも、家事按分で水道光熱費を計上する際は、常識的な割合を意識してください。
地代家賃
事務所を借りる際に必要な家賃も、経費として計上できます。事務所だけでなく仕事用の車などのために借りている駐車場も計上できるため、忘れないようにしましょう。
自宅を事務所代わりにしている場合、水道光熱費と同じく家事按分で計算します。地代家賃での計算は、仕事に使用している㎡数に応じて計算してください。
たとえば、自宅の床面積が300㎡で、仕事道具などを置いているスペースが大体30㎡だとします。この場合、地代家賃で計上できるのは、家賃の1割分です。計算方法が水道光熱費とは異なるため、ご注意ください。
通信費
通信費は、仕事上必要な連絡手段にかかる費用を計上するための項目です。「通信」と聞くと、電話やスマートフォンなどのイメージをもつ方もいますが、それ以外の連絡方法も計上できます。
- 仕事用スマートフォンやWi-Fiの料金
- 事務所の固定電話やFAX
- 業務で使った切手やはがき代
- 業務で必要なものを送ったときの配送料
一人親方だと、自宅の固定電話や私物のスマートフォンを仕事に使っている方もいらっしゃるでしょう。この場合も、家事按分で割合を計算した額を計上します。計算方法は水道光熱費と同じです。普段どれだけの割合で使っているかを、ある程度把握しておきましょう。
なお、DMのはがきなどの広告を出すときにかかった費用は、別の項目に計上します。少々判断が難しいですが、仕事で何かしらの連絡をしたときにかかった費用は、通信費で計上できると覚えておきましょう。
車両費
仕事で使っている車を維持・管理するための費用は、車両費で計上します。車両費には、以下の費用が該当します。
- ガソリン代
- ETC料金
- 検査登録費用
- 車庫証明書手続代行費用
これらの費用は必ず車両費に計上しなくてはならないわけではありません。たとえばガソリン代は、旅費交通費や消耗品費としても計上できます。自分が管理しやすい項目で計算しましょう。
仕事で使っている車をプライベートでも使用している場合は、家事按分が必要です。車両費の場合、以下ふたつの方法の内どちらか片方で計算します。
- 走行距離で分ける
- 使った日数により分ける
走行距離で分ける場合、根拠となる資料が必要なため、運転記録などを残しておく必要があります。
日数の場合、業務記録を残しておけばそれが根拠となるため、車両費用に資料を用意する必要がありません。日数で計算する方が簡単なため、こちらを採用している方が多いようです。
支払手数料
仕事上支払う必要があった手数料も、経費の対象です。
- 振込手数料
- 代引き手数料
- 証明書の発行手数料
- 仲介料
上記のような費用が発生したら、支払手数料として計上しましょう。重要度の高い手続きにかかった手数料や、定期的に発生する手数料なら計上できるため、忘れないようにしてください。
交際費
仕事関連の打ち合わせを喫茶店などの飲食店で行った場合、その費用を交際費として計上できます。このほか、供応・慰安・贈答も同様です。
仕事のイベントや付き合いで食べ物などを提供したときは、忘れずに計上しておきましょう。
なお、交際費はプライベートとの区別が難しいことから、税務署の確認が入りやすい費用でもあります。計上したら万が一質問されてもきちんと答えられるよう、プライベートとの線引きをはっきりさせておきましょう。また、金額が大きくなればその分指摘される可能性も高くなります。
交際費を計上するときは、金額にもご注意ください。
減価償却費
減価償却費は、固定資産の購入費用を複数年に分割して費用計上する処理のことです。
消耗品費に該当しない、購入にかかった費用が10万円以上で耐用年数が1年以上ある物は、こちらの項目で計上します。計上方法は定額法と定率法のふたつから選びますが、一人親方をはじめとした個人事業主は、定額法で計算するのが一般的です。
どうしても定率法を使いたい場合は、事前に届出を出さなくてはなりません。計算方法は定額法の方が簡単なため、特別な理由がない限りは定額法で計算・計上しましょう。
専従者給与
事業を生計を共にしている配偶者や15歳以上の親族に手伝ってもらっている場合、給与を支払っているなら専従者給与の項目に計上できます。
青色申告なら、6か月以上事業に従事している配偶者または親族がいる場合、支払った給与をすべて経費にできます。まとまった額を経費に計上できるため、忘れないようにしましょう。
雑費
これまで解説した経費に該当しない費用や、一時的に発生した費用も、雑費として経費に計上できます。雑費はさまざまな費用が計上できますが、具体的な例としては以下のようなものが該当します。
- ごみや不用品の処分費用
- 少額の解約違約金
- 清掃やクリーニング時の手数料
どれも普段定期的に発生していない限りは、費用項目を用意しないものばかりです。計上する科目に該当しないものがあるときは、雑費の項目で計上しましょう。
雑費に関する注意点
雑費を計上する際の注意点として、金額があります。雑費はさまざまなものを計上できるため、分からないものを雑費にすべて放り込んでおくと、内容を把握できず帳簿が分かりにくい状態になります。このような状態だと、税務署から指摘される可能性も高くなるため、ご注意ください。
不安な方は経理アプリの利用がおすすめです。
Taxnap(タックスナップ)は一人親方のための経理代行アプリです。経費を正しく判別して帳簿付けるのはとても大変です。しかし、タックスナップを使えば、勘定科目を自動的に判別してくれ、帳簿付けもしてくれます。確定申告までこれ1つ簡単にでできるようになります。無料で始められるのでまずはお試しで使ってみるのも良いでしょう。
一人親方が税金対策として利用すべき所得控除10種類
節税において、経費だけでなく控除も重要な要素です。控除を受けられる条件を満たせば、課税額や税金そのものの額を減らすことができます。
控除は複数受けられるため、つかえる控除は積極的に活用していきましょう。次は、一人親方が利用できる所得控除について解説します。
基礎控除
基礎控除は、税を納める人の合計所得金額が2,500万円であれば、必ず適用される控除です。控除の金額は合計所得金額により異なります。
- 2,400万円以下…48万円
- 2,400万円超2,450万円以下…32万円
- 2,450万円超2,500万円以下…16万円
- 2,500万円超…0円
一人親方の場合ほとんどの人が48万円の控除を受けられることになります。基礎控除はほかの控除と同時に受けられるため、つかえる控除があれば積極的に活用しましょう。
扶養控除
未成年や高齢者に該当する年齢の家族がいる場合は、扶養控除が利用できます。
扶養控除は、該当する親族により金額が異なります。扶養控除を利用するときは、扶養している人の年齢などが関わるため、ご注意ください。
| 区分 | 控除額 | ||
| 一般の控除対象扶養親族 | 38万円 | ||
| 特定扶養親族 | 63万円 | ||
| 老人扶養親族 | 同居老親以外の者 | 48万円 | |
| 同居老親等 | 58万円 | ||
配偶者控除
扶養控除に加え、配偶者がいる場合は配偶者控除が使えます。配偶者控除は、配偶者の所得が以下の条件を満たしていない場合にのみ使える控除です。
- 配偶者の所得が48万円以下
- 給与所得を得ている場合は最大103万円まで
配偶者の条件が合致していない場合は、48万円までの控除が受けられます。なお、条件に合致しない場合でも、配偶者が給与所得を得ている場合は、別の控除が使えます。配偶者がいる場合は、合致する条件の控除がないか調べておきましょう。
生命保険料控除
以下3つの生命保険に加入している場合、生命保険料控除を利用できます。
| 生命保険の種類 | 内容 |
| 一般生命保険 | 生存または死亡に起因して支払う保険金または給付金 |
| 介護医療保険 | 入院・通院を伴う給付が受けられる保険 |
| 個人年金保険 | 個人年金保険料税制適格特約を付与した個人年金 |
控除の金額は最大12万円です。該当する保険に加入していると、保険会社から特定の時期に保険料を記載した明細書が送付されます。
明細書は控除を受けるのに必要なため、必ず保管しておきましょう。
社会保険料控除
税を納める人やその配偶者・親族が負担する社会保険料を支払ったときに使えるのが、社会保険料控除です。以下の社会保険に支払った保険料などは、控除を計算する際に使えます。
- 国民年金
- 国民健康保険
- 介護保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
- 労災保険
こちらも控除証明書が届いたら、申告するまで大切に取っておきましょう。
損害保険料控除
地震保険に支払った保険料も、控除の対象です。所得税や住民税にかかる控除で、所得税は最大5万円、住民税は最大2万5,000円まで受けられます。こちらも生命保険同様、申告の際に明細書が必要になるため、保険会社から送られてきたら大切に保管しましょう。
医療費控除
1年の内に支払った医療費が、10万円以上となる場合、200万円を最大として医療控除が使えます。医療控除は通院や入院にかかった費用だけでなく、セルフメディケーション税制の対象となる市販薬も含まれます。定期的に通院している、またはこまめに購入している薬があるなら、1年間の合計金額が10万円を超えないか確認しましょう。
なお、健康診断や人間ドックなどは、病気やケガが見つからない限りは対象になりません。
医療費控除は、あくまでも病気やケガを治療したときにかかった費用を控除する目的で設けられているためです。医療費控除の条件を確認するときは、健康診断等にかかった費用を混同しないようにしましょう。
ふるさと納税(寄附金)控除
市町村や特定の団体への寄付や、ふるさと納税を利用した場合、その金額をもとに控除が受けられます。
控除を受けるには、寄付したことを証明する書類が必要です。寄付の手続きを完了したときにもらえる書類などは、大切に保管しておきましょう。
青色申告控除
青色申告を行うと、10万円・55万円・65万円のいずれかの控除を受けられます。10万円の控除は青色申告をすれば受けられますが、55万円および65万円は、以下の条件を満たす必要があります。
- 不動産所得または事業所得がある
- 複式簿記で記帳している
- 貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付している
- e-TAXによる申告または電子帳簿保存を行っている
最大の65万円控除を受けるには、すべての条件を満たさなくてはなりません。55万円控除は、上3つの条件を満たすと受けられます。
雑損控除
震災や火災・盗難などの被害を受けたときには、雑損控除が使えます。
雑損控除は被害額が大きく控除しきれない場合は翌年以降に繰り越しができ、最大3年間は繰り越せるため、覚えておきましょう。なお、別荘や書画・骨董など、ひとつの価値が30万円を超えるものは対象外です。控除を計算する際は、ご注意ください。
控除の計算を楽に行いたい場合は経理アプリの利用がおすすめです。
Taxnap(タックスナップ)は一人親方のための経理代行アプリです。上記で挙げた10種類の控除を正しく計算して申告するのは、手間も時間もかかります。しかし、こうしたアプリを活用すれば、複数ある控除も全て自動計算してくれ、確定申告の際も楽になります。無料で始められるので、まずはお試しで使ってみるのも良いでしょう。
一人親方が税金対策で注意するべき点
ここまで一人親方が税金対策で使える経費や控除について解説しました。これらの経費や控除は、ただ計上すれば使えるものではありません。計上の際には、領収書の保存や確定申告の実施が必要です。次は、それぞれの注意点を解説します。
領収書をしっかり保管しておく
経費や控除を計上するには、領収書などの費用が発生した証拠となる書類が必要です。経費や控除に関わる費用が発生したときは、必ず領収書を保管しておきましょう。
領収書もただ金額を書いてあるだけでは、税務署に怪しまれてしまいます。宛名や発行年月日がきちんと明記されたものを受領してください。
これらの領収書には保管義務があります。もらったものはファイルなどに入れて管理し、申告後も何かあればすぐに取り出せるようにしておきましょう。」
確定申告の実施
一人親方は個人事業主のため、税の申告も自分で行わなくてはなりません。所得税や住民税を納付するには、確定申告をする必要があります。確定申告は忘れずに行いましょう。
確定申告を期限内に終わらせておかないと、無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生します。頑張って経費や控除で節税しても、これでは意味がありません。
確定申告はローンの契約などの所得を証明する際にも必要です。建設業の場合は仕事の受注にもかかわります。一人親方として独立したら、確定申告の準備や作業も忘れず行いましょう。
より効果的に節税をするなら税理士に依頼がおすすめ
「確定申告がめんどくさい」「効果的な節税方法が知りたい」そのように感じる場合は思い切って税理士に依頼するのもおすすめです
税理士は確定申告の書類作成ができるだけでなく、節税方法のアドバイスをくれたり、融資や資金調達の相談などもできます。
自分に合った税理士が分からない場合は自分にあった税理士を見つけてくれる完全無料のサービス税理士ドットコム![]() を使うのがおすすめです。
を使うのがおすすめです。
まずは税理士ドットコムに無料登録して、自分にあった税理士を探してみると良いでしょう。
税理士に依頼するほどではないけど、確定申告をスムーズに行いたい、という場合は会計ソフトの導入を検討しましょう。
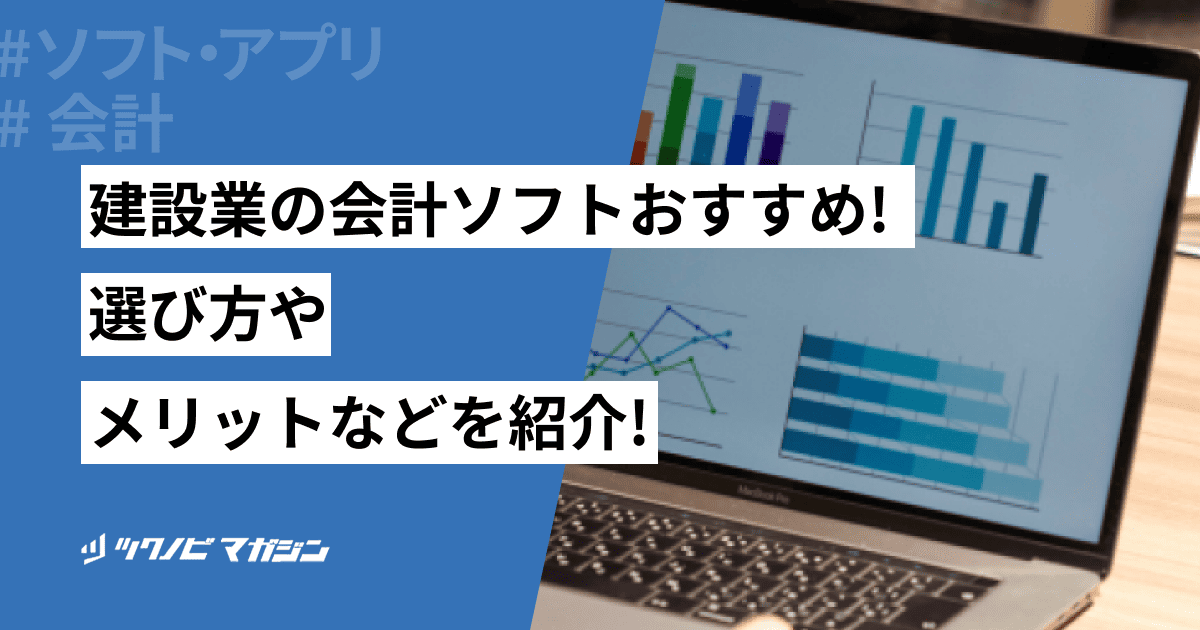 建設業界で活用できる会計ソフトおすすめ7選!選び方やメリットも解説
建設業界で活用できる会計ソフトおすすめ7選!選び方やメリットも解説
一人親方のための税金対策・確定申告アプリはTaxnap(タックスナップ)がおすすめです。
一人親方の税金はどこで支払う?
確定申告を行うと、申告内容に応じた税金を支払わなくてはなりません。所得税と住民税は、大体5〜6月あたりに事務所のある都道府県から振込用紙が送付されます。振込用紙の金額と使用期限に従って支払処理をしてください。
個人事業税は、原則として8月と11月の末日に納付時期が来ますが、所得税の確定申告をしている場合は、単独で申請する必要はありません。所得税や住民税と同じように、用紙などが来たら支払い手続きを行いましょう。消費税も同様です。
なお、納税は口座振替でも実施されています。口座振替を希望している場合は、指定した口座に必要な額の料金を振り込んで置く形で対応します。納税額により引き落とし回数や時期が異なるため、ご注意ください。
建設業で年収を上げるならツクノビワークがおすすめ
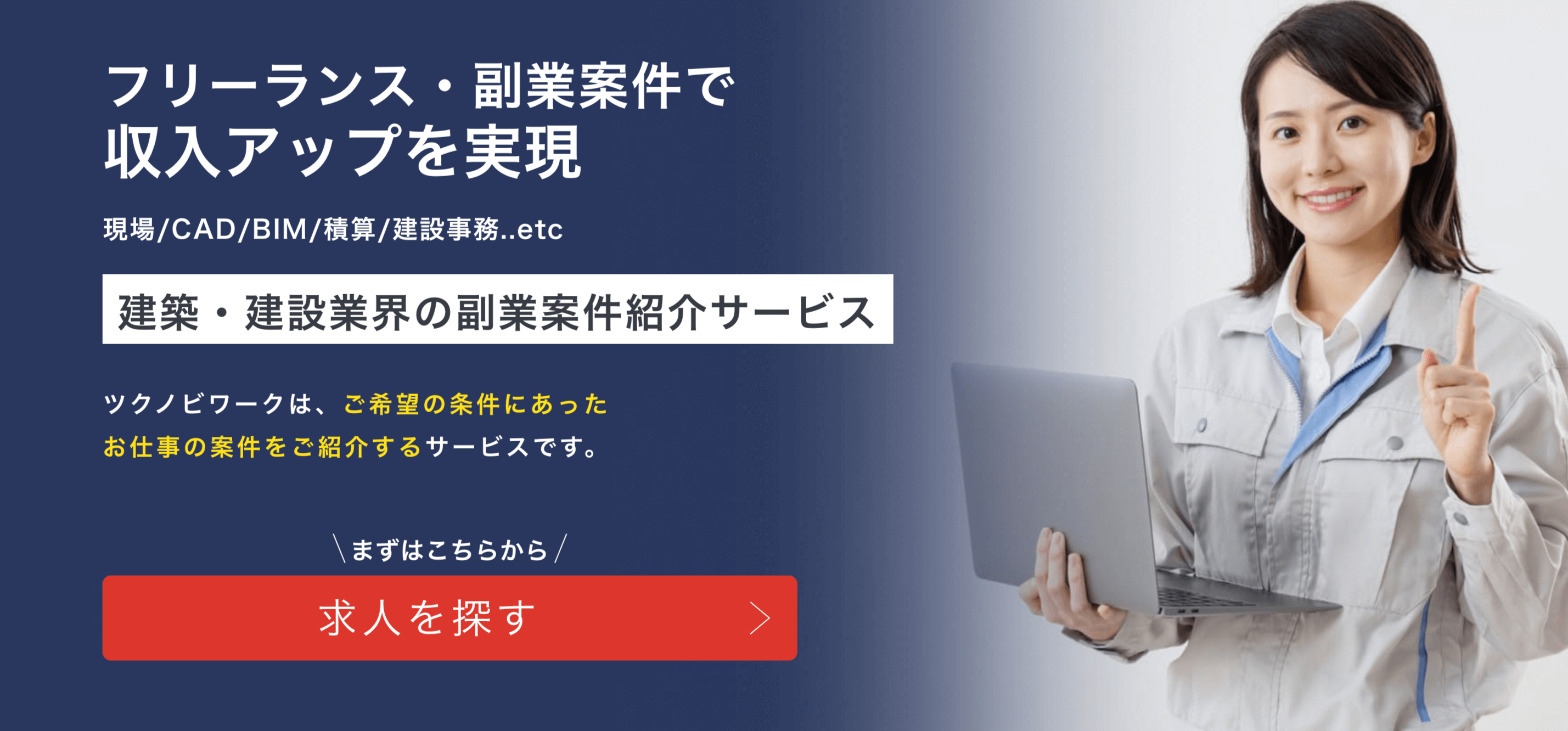
建設業で年収を上げたい方には、建設業特化のフリーランス・副業案件マッチングサービス「ツクノビワーク」の活用がおすすめです。
週1~5日で勤務できる案件やリモートワークで勤務できる案件など、幅広い案件の中からご希望の案件をマッチング可能です。大手企業の案件から、即ご活躍いただける中小の企業まで、さまざまな規模の案件を用意しています。
スキマ時間で稼ぎたい方や年収を上げたい方はぜひこちらから詳細をご確認ください。
一人親方が支払う税金は4種類!経費や所得を日頃から計上して確定申告の準備を整えておこう
一人親方が支払う税金は、申告内容により異なります。
経費や控除をうまく使って納税額や支払う税金の額を小さくできれば、支払いの負担を軽減できます。普段から経費や所得を意識し、こまめに計上して確定申告の準備と、節税対策に取り組んでおきましょう。
一人親方にとっての物損保険とは?加入する必要性や選び方を解説の記事はこちら
 一人親方にとっての物損保険とは?加入する必要性や選び方を解説
一人親方にとっての物損保険とは?加入する必要性や選び方を解説
※ちなみに弊社では、建築建設業界特化の
無料ホームページ制作代行を新たにスタートさせました! 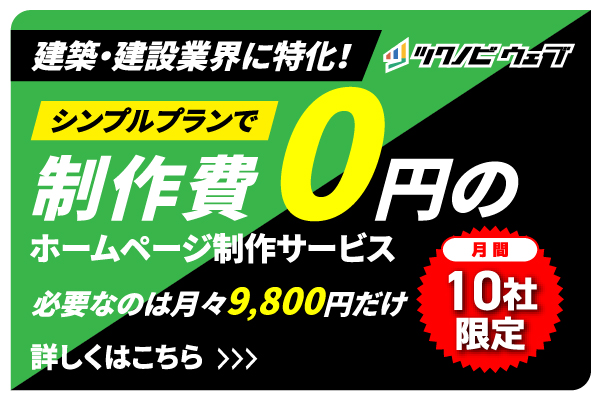 ※詳しくは👆👆👆のバナーをクリック!!
※詳しくは👆👆👆のバナーをクリック!!