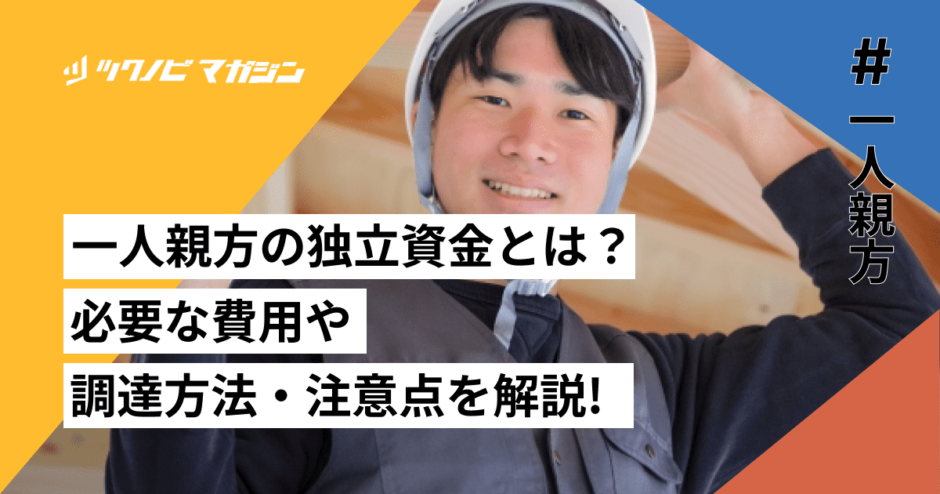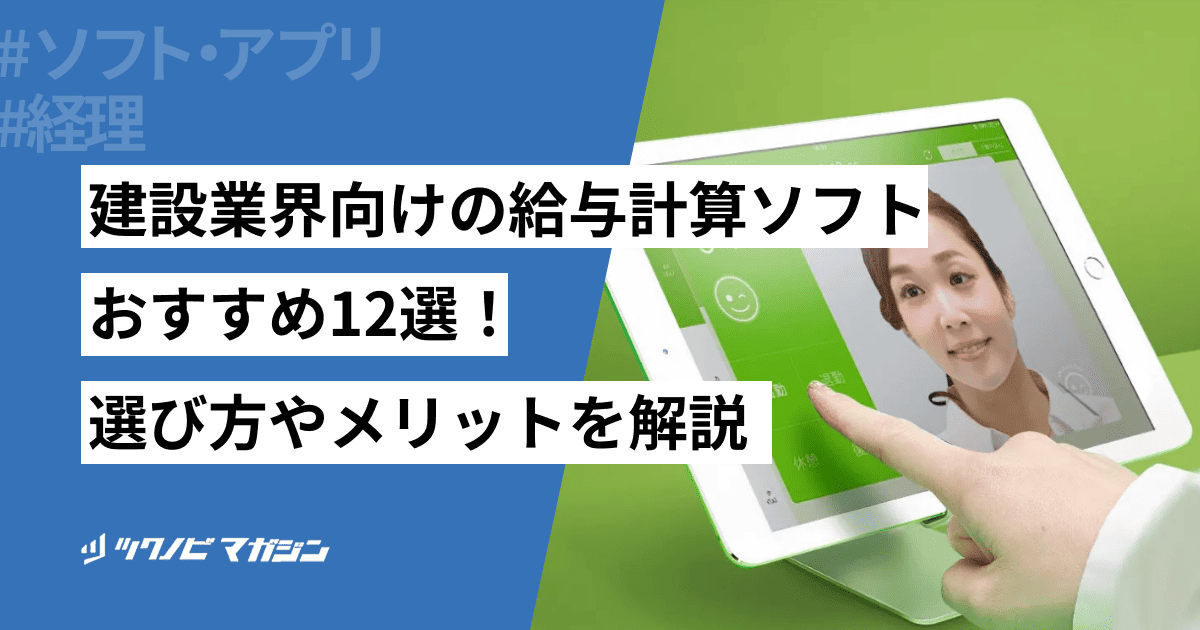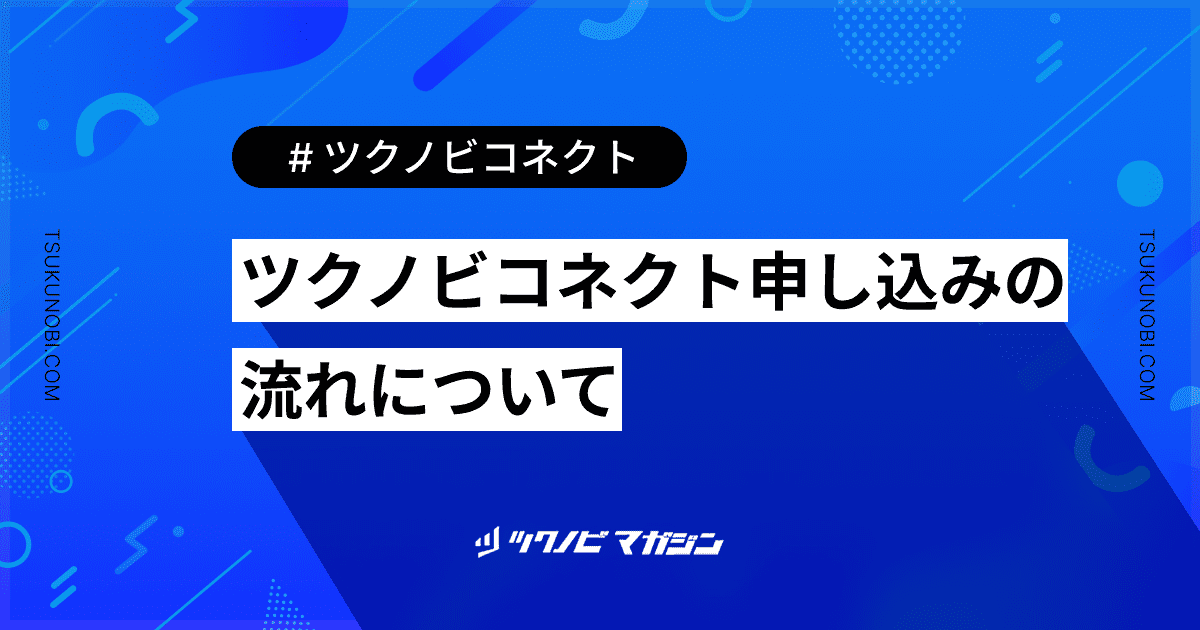※記事内に広告を含みます
建設業で働いていてある程度の実績と経験を積んだ人の中には、将来独立したいと考えている人も多いでしょう。建設業の実態を見ると、まずは一人親方として独立して、目処が立った後に職人を雇う人が多いようです。ただし、独立するためにはまとまった資金を調達しなければなりません。今回は、一人親方として独立する際の必要な資金と調達方法についてまとめました。独立するときの注意点にも触れていますので参考にしてください。
一人親方として独立するときに必要な資金
一人親方として独立するために必要な資金は次の3点です。
- 初期費用 事務所費用や什器備品など
- 運転資金 家賃や燃料などの変動経費、仕入れ費用
- 生活費
以下、順に説明します。細かい内訳にも言及していますので参考にしてください。
初期費用
建設業にかかわらず、独立する際には初期費用を準備しなければなりません。初期費用は独立する事業の種類や規模によって変わってきます。一人親方として独立する場合は基本的に従業員を雇用しないことが主流です。そのため、工夫次第では初期費用を抑えることも可能です。独立する時に必要な初期費用は、事務所費用や運転資金などが挙げられます。
事務所
初期費用として最初に考慮すべき資金は事務所費用です。賃貸で事務所を構える場合には契約に必要な保証金や仲介手数料、前払い家賃を一時金として納める必要があります。一人親方として従業員を雇わない場合は自宅兼事務所の登録でも十分です。自宅を利用すれば初期費用は抑えられます。事務所の開設は、独立後の事業規模や従業員数を考えて慎重に計画しましょう。
什器備品
事務所に揃える什器備品も初期費用として考えましょう。事務所に必要な電話やパソコン、プリンターなどが必要です。最近では固定電話の他に業務用の携帯電話を利用する人も増えています。屋外の現場に出向いていても連絡が取れるため便利です。パソコンと同時にインターネット環境も整備しましょう。スケジュール管理や工程管理など、クラウドを利用したソフトを導入しておけば様々な状況に対応できます。
車両や工具
車両の購入は初期費用として大きな割合を占めるものです。現場への移動や工具の運搬、突発的な資材の購入にも車両を利用します。事業規模にもよりますが、ショベルカーやブルドーザを準備する場合もあるでしょう。便利なリース契約もあります。事業の実態を踏まえて必要な車両を準備しましょう。また、実務に使用する工具類も必要です。初期費用としてどのような工具が必要なのかピックアップして無駄の無いように準備しましょう。
運転資金
初期費用として当面必要な経費や材料費なども運転資金として準備しなければなりません。建設業は資金回収までに時間がかかる業種です。通常は開業して売上げ金が手元に入るまでには3カ月程度のタイムラグがあります。請け負った工事の材料費や経費だけでなく、事務所を維持するための家賃や光熱費、消耗備品の補充など細かいところまでピックアップして準備しましょう。
家賃や重機などの燃料
賃貸で事務所を構えている場合は、当面3カ月程度の家賃は準備しておきましょう。契約時の保証金などと合わせるとかなり大きな金額になるので注意が必要です。電気やガスなどの光熱費やインターネット利用料金、電話料金も含めた通信費もかかります。
社用車や重機などの燃料費も計算して準備しましょう。初回の工事で遠方の現場を請け負う場合は思ったより燃料費がかかるので注意が必要です。
材料の仕入れ
運転資金として当面の材料費も準備しておきましょう。ただし、これから請け負う工事なので正確な金額が予測できません。資金がショートして仕入れができなくなると事業そのものが成り立たなくなります。
そのため、最初は余裕をもった資金確保が必要です。事業に見合った毎月の仕入れ費用を計算して、最低3カ月分は資金確保しておきましょう。
生活費
一人親方として独立開業するときは、自分の生活に必要な資金も初期費用として準備しておきましょう。売上金の入金までに時間がかかることを意識して、最低でも3か月分の生活費を確保します。事業に必要な初期費用と、自分の生活のために自由に使える費用はきちんと区分し明確な使い分けが重要です。特に独立後は、お金の流れを把握するのが難しくなるので無駄な出費を抑えるよう意識しましょう。
一人親方の独立資金を調達する方法
ここまで、一人親方として独立するための初期費用について説明してきました。この項目では、初期費用も含めて独立資金を調達する方法について説明します。資金調達の方法は次の5点です。
- 自己資金(預金)
- 政策金融公庫からの融資
- ビジネスローン
- 銀行からの借り入れ
- 家族や友人からの借り入れ
以下順に詳しく説明します。
貯金
独立資金は、できるだけ借り入れをせずに独立前の預金で賄うことが理想です。自己資金としてできるだけ預金しておくと、不足分の融資を受けるときの審査で有利に働きます。
また、通帳の入出金記録は必ず残しておきましょう。融資を受けるときに通帳の提出が求められ、事業の準備が計画的に行われて来たかが確認されます。副業やクラウドソーシングなど、会社で働きながら自己資金を貯める方法も有効です。
政策金融公庫からの融資
日本政策金融公庫で借入れをする方法もあります。中小企業や小規模事業者に向けた国の融資制度で、通常の借り入れに比べて金利が低いのが特徴です。
新しく事業を始める事業者向けの「新創業融資制度」を利用すると、無担保、無保証人で最大3000万円(運転資金含む)まで借入できます。ただし、資金総額の10分の1以上の自己資金が必要です。また、新事業に対する適正な事業計画と事業計画遂行能力が審査されます。
ビジネスローン
独立資金の調達方法としてビジネスローンも考えられますが金利が高いので注意が必要です。長期の返済計画では利子が自社の利益を圧迫するおそれがあります。短期間で早期に返済できる見込みがあるときに利用しましょう。
また、運転資金が必要なときにビジネスローンを使うのはおすすめできません。運転資金は増えていくので借入金が返せない事態になることも考えられます。ビジネスローンは最後の手段として捉えましょう。
銀行からの借入
銀行からの借入金を独立資金に充当する手段もありますが、銀行融資は新事業創業者にとって難易度が高いと思われます。銀行は、事業の操業状態や入出金の状況を審査します。さらに、ある程度の顧客があって安定的な売上げが計上されていて「利益が確定している」ことが審査時の重要なポイントです。新規創業状態では条件を整えるのが難しいでしょう。
家族や友人からの借金
独立資金として、信頼のおける友人や家族から借入をする方法もあります。事業に理解があり本人の信頼があれば融資してもらえるかもしれません。家族や友人なら金融機関ほど金利が高くないのが利点です。ただし、家族や友人に頼りきってしまわないよう注意しましょう。
あくまでも事業者としての自覚を持つことが大切です。また、金銭の授受は手渡しで行わずに振り込みにしてもらい履歴を残しましょう。
一人親方として独立するときの注意点
建設業では人手不足が慢性化しているので、一人親方として独立すれば需要がありチャンスも掴めるでしょう。ただし、経営がうまくゆかず失敗するケースもあります。この項目では、失敗しないように注意する点について言及します。下記の3点は要注意です。
- 資金繰りが難しい
- 工事内容により許可や資格が必要
- 独立後は社会保険への加入が必要
それぞれについて、詳しく説明します。
資金繰りが難しい
建設業界は売上金で資金回収するまでに時間がかかりやすいので注意が必要です。資金回収が滞ると資金繰りが困難になり、最悪の場合は売上げや利益が出ているのに倒産することもあります。これが「黒字倒産」です。創業時には十分な運転資金を準備しておきましょう。キャッシュフロー計算書で現金の流れを把握し、資材調達や経費なども頭に入れて工事を請け負うように心がけましょう。
請け負う工事内容により許可や資格が必要
請け負う工事内容によっては様々な許可申請が必要になります。特に、請け負う工事の金額や規模によって必要になる「建設業許可」については熟知しておきましょう。1件あたりの請負金額が税込み500万円以上(建築一式工事の場合は税込み1500万円以上)の工事には建設業許可が必要です。建設業許可は工事の種類ごとに取得する必要があり、有効期限(5年)があります。
独立後は社会保険への加入が必要
一人親方として独立した場合は、個人事業主となり労働者の雇用がないため、健康保険や厚生年金、労災保険や雇用保険の適用対象外となります。ただし、労働者として認められる場合には他の労働者と同じように社会保険(国民健康保険、国民年金)へ加入しなければなりません。また、労災保険にも特別加入できます。以下にそれぞれの保険加入について詳しく説明します。
国民健康保険
建設業ではケガをするリスクが高いので健康保険への加入は必須です。一人親方は法人格を持たないので国民健康保険への加入となります。市町村の国民健康保険だけではなく、同業による組合員で組織された「国民健康保険組合」へ加入することもできます。組合員になる必要がありますが、市町村の国民健康保険と比べて保険料が安く給付内容も手厚いのでおすすめです。
国民年金
一人親方として独立した場合でも国民年金には加入する義務があります。国の制度では、20歳以上の国民は全て国民年金に加入しなければなりません。会社に勤めているときは会社が保険金額の1/2を補填してくれますが、独立後は補填がありません。保険金額は増額しますが、老後の生活費の補填も考えて加入するようにしましょう。
労災保険
労災保険への加入は義務ではありません。しかし、ケガや危険と隣り合わせの建設業では一人親方でも特別加入できる仕組みになっています。万が一のために加入しておくと安心です。労災保険は通勤時の災害や就労時のケガ等の治療費の他に、働けなくなった場合の保障も受けられます。加入手続きは一人親方組合などの団体を通じて申請するのが一般的です。申請書を団体に提出すれば労働基準監督署の審査を受けて加入できます。
一人親方向け労災保険で一番おすすめなのは、業界No.1の加入者で実績豊富な一人親方労災保険組合の労災保険です。主な特徴は、以下の通りです。
- 全国の加入組合数は90,000人と業界トップクラス
- 月額組合費が500円と業界最安値
- 組合員様限定の優待サービスが多数
| 入会費 | 1,000円(初回のみ) |
|---|---|
| 組合費 | 500円/月 |
一人親方労災保険組合ではレストランやカラオケ、映画館など全国で20万ヵ所以上の施設のクーポンや割引などが適用される組合員様限定の優待サービスや友達紹介割引もあります。
一人親方になるには?大工や職人から独立する準備を紹介の記事はこちら
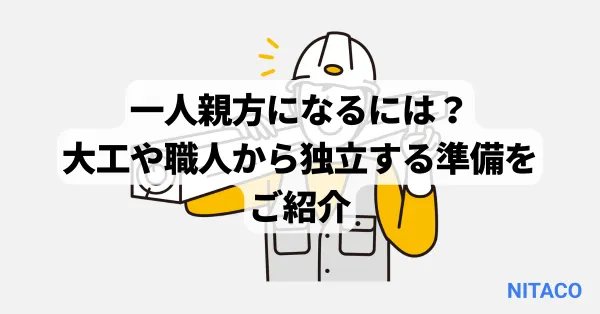 一人親方になるには?大工や職人から独立する準備を紹介
一人親方になるには?大工や職人から独立する準備を紹介
一人親方とは?個人事業主との違いや加入できる労災保険などの解説記事はこちら
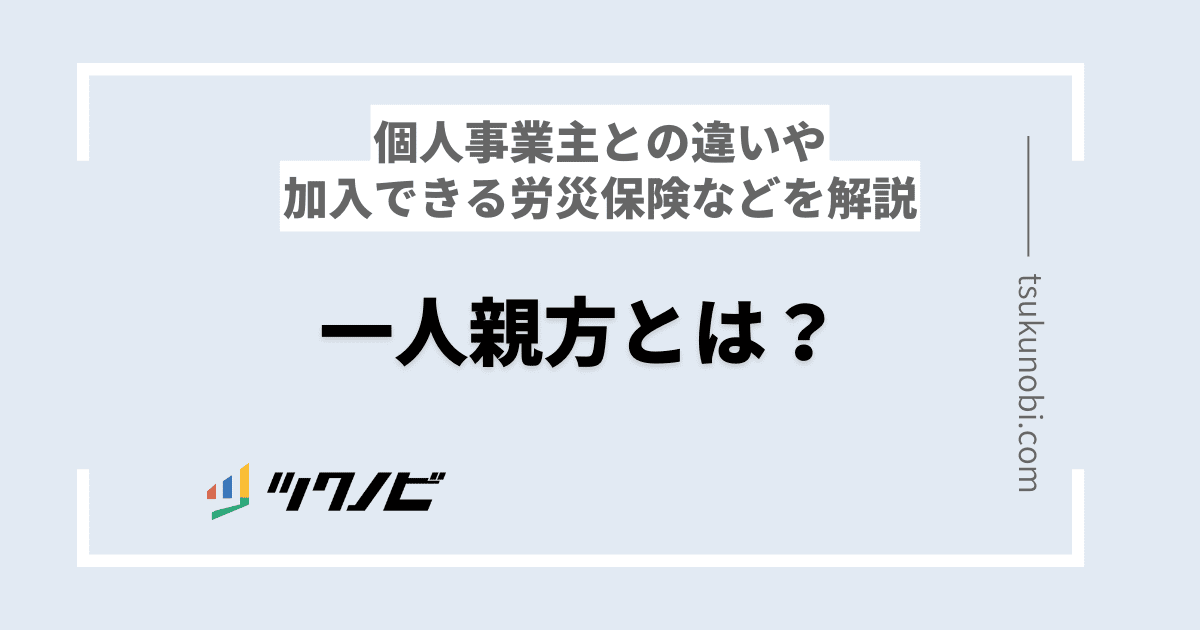 一人親方とは?個人事業主との違いや加入できる労災保険などを解説
一人親方とは?個人事業主との違いや加入できる労災保険などを解説
建設業の人手不足解消ならツクノビBPOがおすすめ
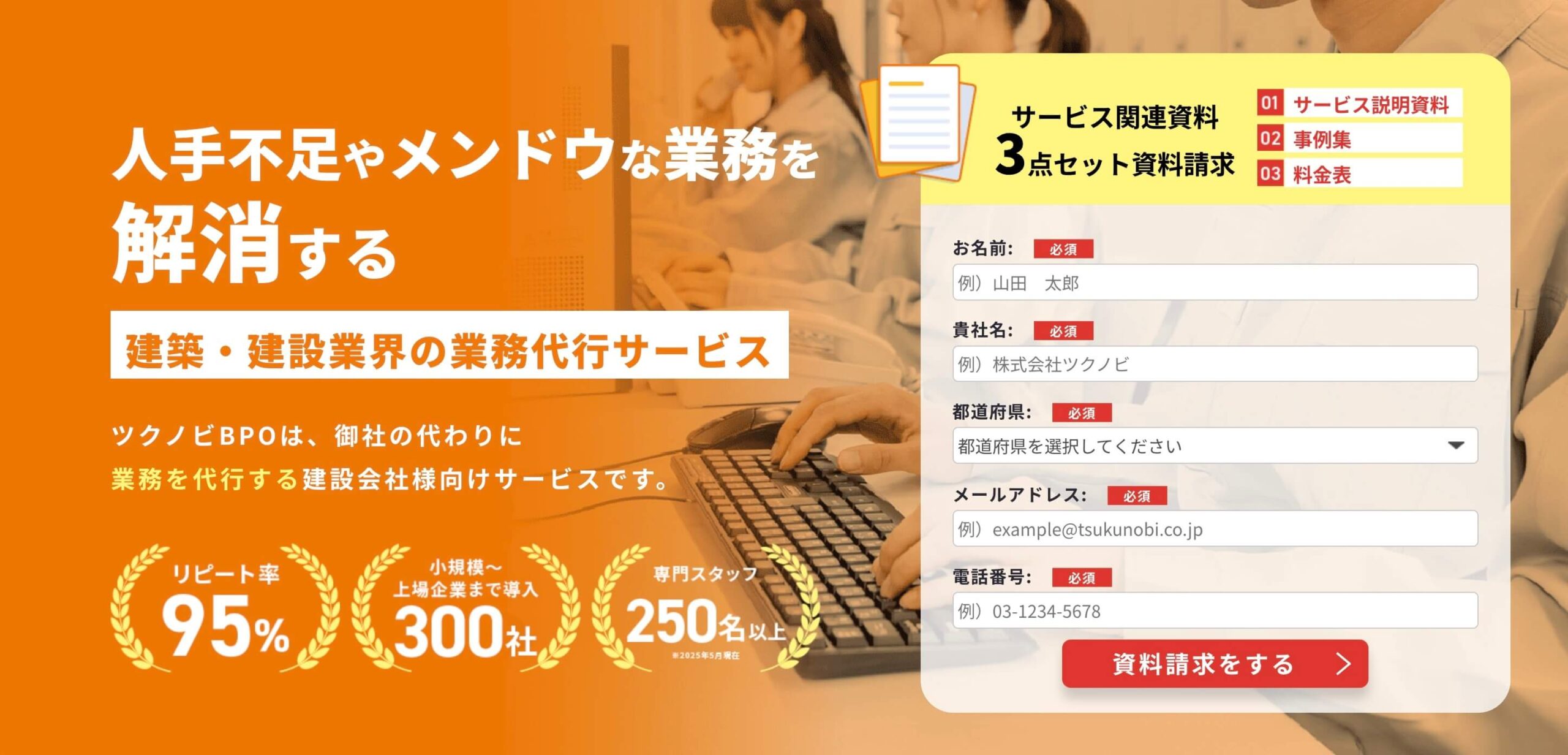
建設業の人手不足を解消するためには、アウトソーシングサービスの利用もおすすめです。
従業員のリソースがひっ迫している場合や、業務に対応できる人材が不足している場合などは、アウトソーシングサービスを活用すると、少ない工数で業務を実行できます。BPOサービスでは、専門的な知識を持っているスタッフが対応するため、さまざまな業務をスムーズに進められます。
弊社では、建設業の業務に対応している建設業特化のBPOサービス「ツクノビBPO」を提供しています。書類作成や図面の作成、積算業務など、幅広い業務を代行できます。ツクノビBPOでは、倍率200倍の選りすぐりの専任スタッフが対応いたします。
リソース不足を解消したい方は、ぜひこちらからお問い合わせください。
【まとめ】一人親方は貯金や融資などを活用し独立資金に余裕を持たせよう!
一人親方として独立する場合は、独立資金として十分な初期費用、運転資金の準備が必要です。資金調達方法は、自己預金を始めとして日本政策金融公庫などからの融資などがありますが、できるだけ預金で賄うようにし不足分を融資で賄いましょう。また、独立後の資金繰りがうまくいかずに黒字倒産してしまうリスクもあります。十分余裕をもって運転資金を準備することや、現金の流れを確実に把握して工事を請け負うよう心がけましょう。
※弊社の営業代行サービスであるツクノビセールスでは、
【効果が出なければ全額返金プラン】を新たにスタートさせました!

※詳しくは👆👆👆のバナーをクリック!!