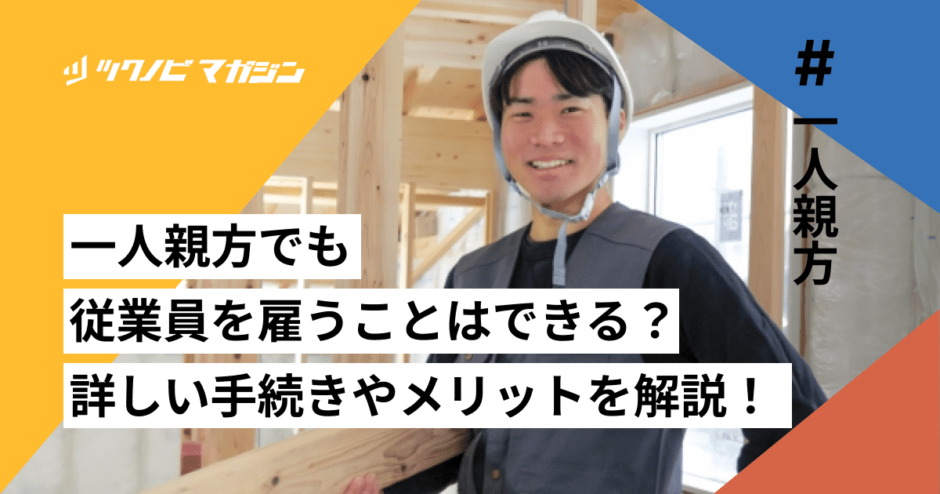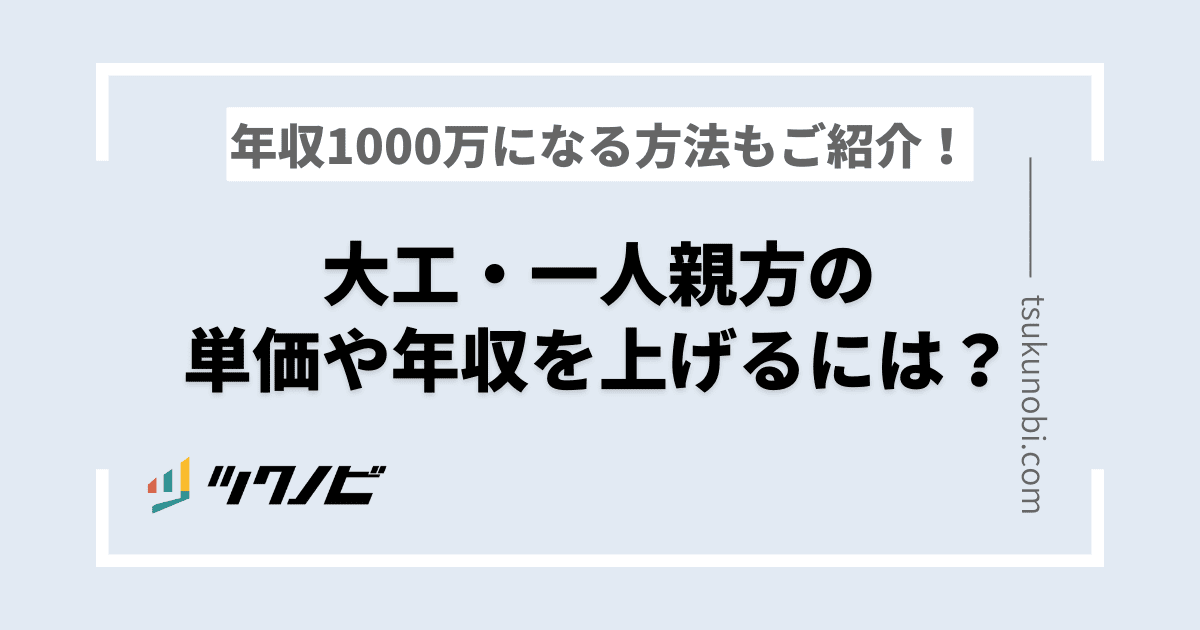※記事内に広告を含みます
親方の元で修行を積んだ職人さんが家族以外の従業員を雇わずに独立開業した場合、「一人親方」になります。
- 依頼案件が増えてきたから、そろそろ人手を増やしたい
- 毎年、確定申告が大変だから今年こそは経理事務員を雇いたい
- 従業員を雇用する際の注意点を知りたい
とお困りではありませんか? そこで今回は、一人親方が従業員を雇うときの詳しい手続きとメリット・デメリットについて解説していきます。
ツクノビワークは、建設業特化の副業案件紹介サービスです。CAD/BIM/積算/業務書類作成/建設事務など、幅広い領域で希望に沿った案件をご紹介します。隙間時間で稼ぎたい方や副業で年収を上げたい方におすすめです。案件を探している方はぜひお気軽にご登録ください。
一人親方でも従業員を雇うことはできるのか?従業員を雇うメリット・デメリットを解説
公的な手続きや条件をクリアすれば、一人親方でも従業員を雇うことができます。 一人親方として一人で働く場合、軌道に乗れば乗るほど、目の回るような忙しさに追われます。一人親方は本業のほか、営業や経理事務、保険や税金など、全ての仕事に対応しなくてはいけないからです。そこでおすすめなのが、従業員を雇うことです。 ここからは、従業員を雇うメリットとデメリットについて解説していきます。
一人親方が従業員を雇うメリットは?
一人親方に限らず、個人事業主そのものが、従業員を雇うことが可能です。どのような雇用形態(正社員、契約社員、パート、アルバイトなど)で雇用するかについても、事業主と従業員が話し合い、自由に決定することが可能です。 もちろん給与の支払いもしなければいけませんし、常時5人以上の従業員を雇用する場合は社会保険の手続きが必要です。しかしその分、従業員を雇うと次にあげる魅力的な2つのメリットを得ることができます。
デスクワークを任せられる
一人親方が従業員を雇うと得られる1つめのメリットは、事務作業をしなくてすむようになることです。
従業員を雇わない場合、本業と並行しながら事務作業も行わなければいけません。取引先とのメールや電話の応対も大変ですし、年があけたら確定申告も待っています。普段から伝票の仕分けが追い付かず、申告時期になってから頭を抱える人も多いのではないでしょうか。 手続きの漏れや、書類のミスがあるとさらに大変です。
そんな方におすすめなのが、経理事務員を雇うことです。 確定申告だけではなく、発注書や請求書などの書類作成、大切な書類や荷物などの管理、電話応対も任せられます。業種によって会計処理(勘定科目など)や必要な書類が異なるので、最初からお任せしたいなら、同じ業種で何年か経理事務をした経験のある方を雇うのがベストです。 事務作業を依頼して自分が本業に集中すれば生産性もあがります。
売上が上がる
一人親方が従業員を雇うと得られる2つめのメリットは、売上アップが狙えることです。受注する件数を増やしたり、「1人では請け負いきれない」とあきらめていた大きな案件にもチャレンジすることができます。売り上げを伸ばし、ひいては事業を拡大することにもつながるでしょう。 また、一人親方の場合、「仕事を休みたいのに休めない」というリスクがつねにつきまといます。従業員を雇用して業務を分散し、しっかりとしたマニュアルを作っておけば、そうした時も安心です。従業員に仕事を任せられるので、いざというときに頼りになります。
一人親方が従業員を雇うデメリットは?
一人親方が従業員を雇うデメリットは以下の2つです。
責任の範囲が広がる
一人親方が従業員を雇うときに発生する1つめのデメリットは、責任を負わなければいけない範囲が広がることです。 今までは自分がミスしないように注意すればこと足りましたが、従業員が仕事で失敗をしてしまった場合も、雇用主であるあなたに責任が降りかかってきます。 従業員がお客様や取引先に迷惑をかけてしまったら、従業員と一緒に謝罪をしなければいけません。設備を破損させてしまったり、事故で相手を怪我させてしまったら、損害賠償を請求される恐れがあります。
従業員がミスを起こさないように、分かりやすい、しっかりとしたマニュアルを作成し、十分に教育を行いましょう。従業員の人数が増えれば増えるほど、ミスが起きる危険も高まりますので要注意です。
手続きが必要
一人親方が従業員を雇うときに発生する2つめのデメリットは、さまざまな公的手続きをしなければいけないことです。多くの書類の準備をして役所などに提出しなくてはいけません。 また、就業規則を作成したり、従業員分の保険料の支払いも発生します。さらに手続きに漏れがあると、あとで業務に支障が出る恐れもあります。
そうしたトラブルを防ぐためには初めから社労士に相談、労務関係の業務を依頼するのがおすすめです。 プロに任せられるので、こちらで書類の準備をする手間も省けるだけでなく何か不安があれば相談することもできます。就業規則の作成も依頼できるので従業員を初めて雇う場合でも安心です。
雇用についてプロに無料相談したい場合は「社会保険労務士法人TSC」がおすすめ
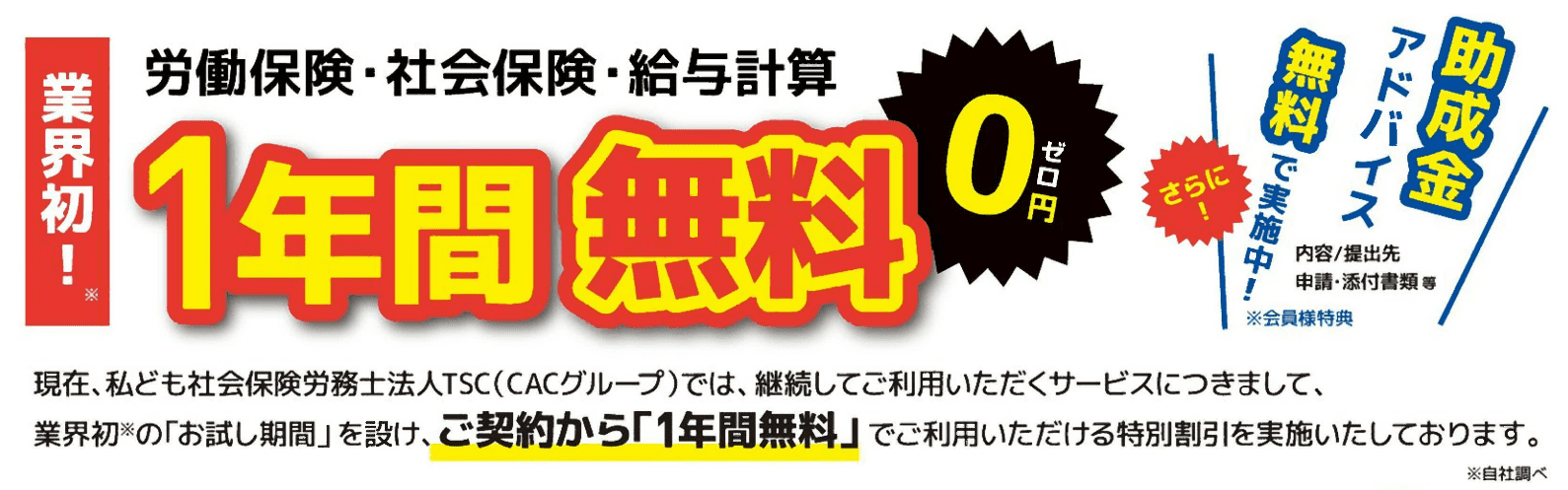 社会保険労務士法人TSCは1年間無料で社会保険や給与計算に関するサービスを利用できます。社会保険関係の事務業務を外部に委託でき、自分は本業に集中できるほか、個人事業主が法人化する場合の社会保険の手続きなどもサポートしてくれるのでおすすめです。
社会保険労務士法人TSCは1年間無料で社会保険や給与計算に関するサービスを利用できます。社会保険関係の事務業務を外部に委託でき、自分は本業に集中できるほか、個人事業主が法人化する場合の社会保険の手続きなどもサポートしてくれるのでおすすめです。
一人親方が一人親方を雇うとどうなる?
一人親方が一人親方である人を雇うとどうなるのでしょうか。まず雇われた側は雇われた先の「従業員」となります。そのため、雇われた先では「従業員」として労災保険などの各種保険に加入することになります。
また、従業員を雇った一人親方も、場合によっては一人親方の労災保険特別加入を中小事業主の特別加入に切り替えなければならないことがあります。従業員が社会保険に加入する場合には、社会保険料の負担が必要になる可能性もあります。
一人親方が従業員を雇う時に必要な手続きを解説
一人親方が従業員を雇うときしなければいけない公的な手続きには、どのようなものがあるでしょうか? 代表的な手続きは、主に3つに分けることができます。
- 各種保険への加入手続き
- 労務関連の(労働基準法の決まりに即した)手続き
- 給料を支払うための手続き
雇用形態(正社員なのか、それとも短期間のバイトなのか)や、雇う人数によって、しなければいけない手続きが変わりますのでご注意ください。 以下、順番に解説していきます。
保険加入の手続き
従業員を病気や失業などのリスクから守るために、各種保険への加入が必要となります。手続きが必要な保険は3つあります。
- 労災保険
- 雇用保険
- 社会保険
それぞれ加入条件が法律で決まっています。全ての一人親方が無条件に加入できるわけではありません。 それぞれの保険の内容や、申告の仕方について説明していきます。
労災保険
「労災保険」は、勤務中や通勤中にケガをしたり、病気になったときに給付金が降りる保険です。加入手続きの対象者は、すべての従業員です。 はじめて従業員を雇うときには、必ず労災保険に加入させなければいけません。雇う側が個人事業主であっても、法人であっても、従業員を一人でも雇用する場合は、原則として労災保険に加入させる義務があります。
また、従業員側が正社員だけではなく、パート従業員やアルバイト、さらに外国人を雇ったときも労災保険に加入する義務が発生しますので注意しましょう。 従業員の労災保険の手続きは、労働保険事務組合を通じて行います。また、以下の場合もすみやかに労働保険組合に連絡してください。
- 職場の名前や所在地が変わった時
- 職場の所在地が変わった時
- 労災保険の内容について変更があったとき
【一人親方必見】おすすめの労災保険ランキングについてはこちらで解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
 【一人親方必見】おすすめの労災保険ランキング!人気の保険を8つ紹介します
【一人親方必見】おすすめの労災保険ランキング!人気の保険を8つ紹介します
雇用保険
「雇用保険」は、従業員が失業するリスクに備えて加入する保険です。失業すると「失業給付」を受給できます。また、従業員が指定の教育訓練を受けたり、育児休業を取った時にも、給付金をもらうことができます。 雇用保険の対象者になるのは、正社員と、次の要件に当てはまるパート従業員です。
- 31日以上雇用する見込みがある従業員
- 1週間に20時間以上労働する従業員
雇用保険の手続きは、ハローワークで行うのが一般的です。 しかし、一人親方が労働保険事務組合で労災保険に加入している場合は、労働保険事務組合で手続きを行うことができます。従業員を雇うとなったら一度労働保険事務組合に問い合わせしてみてください。
社会保険
健康保険と厚生年金を合わせて「社会保険」と呼びます。 「健康保険」は業務外のケガや病気に備える保険です。 「厚生年金」は、被保険者が老齢・障害・死亡した時に備える保険です。
一人親方が常時5人以上の従業員を雇う場合、社会保険に加入する必要があります。 従業員が国民健康保険や国民年金に加入していた場合は、健康保険と厚生年金に切り替える手続きを取りましょう。
建設業の法人の場合は、従業員を雇っていなくても、必ず健康保険と厚生年金へ加入しなければなりません。 社会保険は、所轄の年金事務所で手続きを行います。
書類は、日本年金機構のサイトからダウンロードできます。 書類の提出方法は①年金事務所に直接書類を持っていく②郵送する③電子申請するの3つがありますので、お好きな方法で提出してください。
労務関連の手続き
一人親方が従業員を雇う場合には、労務関連の手続きも忘れず行いましょう。 労務関連の手続きはいずれも、労働基準法に基づいて手続きを行います。 ひとつずつ、順番に説明していきます。
雇用契約の締結
一人親方が従業員を雇用するときは、雇用契約を締結し、雇用契約書を作成しましょう。雇用契約とは「従業員が仕事をする対価として、雇い主が給料を支払う」という契約です。 雇用契約書は、事業主と労働者の双方を保護する目的があり、労働基準法で定められた内容に従って作成する必要があります。
あとで雇用契約の内容について「聞いていた話と違う」と揉めたら大変です。その点、「雇用契約書」を作成しておくと、「事業主と従業員の双方が雇用内容に合意した」ということを証明することができます。
雇用契約書は2部作成します。一部は一人親方の、もう一部は従業員の控えです。 それぞれの書類に、一人親方と従業員が署名・捺印します。
労働条件の通知
一人親方が従業員を雇う際には、雇用保険の締結と合わせて「労働条件の通知」を行います。従事する内容、給料、休日などの労働条件を、従業員にはっきりと提示しなければいけません。
絶対的明示事項(説明する義務がある労働条件)は法律で定められています。
- 労働契約の期間 就業する場所
- 業務内容
- 始業および終業時刻と、残業の有無
- 休憩や休日に関する事項
- 給料の計算方法や、支払時期・退職に関する事項
など
出典:e-gov法令検索「労働基準法施行規則(第5条)」
「労働条件通知書」には、絶対的明示事項のうち、昇給に関する事項以外、すべて記載します。従業員に労働条件を説明したら、「労働条件通知書」を従業員に渡します。
36協定の締結
「時間外労働・休日労働に関する労使協定書」のことを、通称、36(サブロク)協定と呼びます。 従業員に残業させたり、休日労働させる予定があるときは、36協定を結んでおきましょう。 36協定の用紙は、厚生労働省のサイトからダウンロードできます。同じものを2通作成し、それぞれに一人親方と従業員の代表者が署名捺印。所轄の労働基準監督署に提出します。郵送や電子申請でも提出できます。2通のうち1通は、事業所の控えです。 労働基準監督署が受領印を押して返してくれますので、保管しておいてください。
就業規則の届出
従業員を雇ったら、「就業規則」を作成しましょう。就業規則とは労働時間や残業代など、労働者のルールを書面化したものです。就業規則を作っておくと、残業代請求や不当解雇、セクハラなどの労務トラブルを事前に防ぐことができます。就業規則の作成が義務付けられるのは、常時10人以上の従業員を雇用する場合ですが、たとえ従業員が少人数であっても作っておいたほうが安心です。
絶対的必要記載事項(就業規則に必ず記載しなければいけない内容)は、労働基準法で決められています。所轄の労働基準監督署が用意しているフォームを参考に作成してください。
都内で従業員を雇う一人親方の場合は、東京労働局のサイトからダウンロードできます。 「就業規則」を労働基準監督署に提出するときは、「意見書」を添付します。意見書は、従業員から就業規則について意見を聞き取って作成します。 たとえ反対意見が記載されていたとしても、受領してもらうことは可能です。とはいえ、「就業規則」は労務トラブルを事前に防ぐために作成するもの。反対意見が出た場合は、よく話し合っておくことが大切です。
給与支払いのための手続き
従業員に給与を支払うときは、単に時給や月給を計算すればいい、というものではありません。給料から差し引いた所得税や住民税は、税務署や市役所に納付しなければいけないからです。 給与を支払う準備として必要な手続きには、以下のようなものがあります。
- 給与計算の準備
- 給与支払事務所等の開設届出書の提出
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の用意
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出
それぞれ解説していきます。
給与計算の準備
一人親方が自分で給与計算をするときは、いくつか準備しておいたほうがいいことがあります。
- 給与計算ソフトを導入
- 給与計算ソフトへ基本事項を入力
- 給与明細書用紙を購入
- 給与の振込先(口座情報)を確認
はじめて給与ソフトを購入した方は、使い方に慣れるまで一苦労します。給料日目前に一気に作業しようとすると、時間がかかってあたふたしかねません。時間に余裕をもって準備しておきましょう。 忙しくて給与計算の事務処理に時間を取れない方や、PC作業が苦手な方は、社労士に委託する方法もあります。 初めて従業員を雇う方はとくに社労士など専門家への委託を検討した方が良いでしょう。
給与支払事務所等の開設届出書の提出
従業員を雇うことが決まったら、所轄の税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しましょう。 「給与支払事務所等の開設届出書」とは文字通り、「従業員を雇って給与を支払う事務所を開設するための届出書」のことです。
「給与支払事務所等の開設届出書」の用紙は、国税庁のサイトからダウンロードできます。 必要事項を記入して、所轄の税務署に持参しましょう。郵送でも提出できますよ。 提出期限は、給与を支払うことになった日から起算して一か月以内です。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の用意
年末調整に備えて、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を用意しましょう。 年末調整の際、事業主である一人親方は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を見て、所得からいくら控除分を引けるか計算しなくてはいけません。 所得税の額は、従業員の年齢、扶養家族の人数やその年齢、障がいの有無などによって大きく異なります。
申告書のフォームは、国税庁のサイトからダウンロードできます。 入社時に従業員に書類を渡し、その年の分を記入して提出してもらいましょう。また毎年12月に、翌年分を提出してもらいます。
なお、税務署や市区町村長から特に求められないかぎり、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は提出する必要はありません。年末調整で必要となるため、一人親方のほうで大切に保管しておきましょう。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出
従業員が10人未満のときは、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しましょう。 従業員の給料から差し引いた源泉所得税は、原則としては、毎月納付しなければいけません。 しかし給与の支払人数が10人未満のときは、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することによって、特例として、納付を7月と翌年1月の年2回だけにすることができるのです。
事務手続きを減らすことが出来るので、本業に集中しやすくなります。 申請書は税務署に持参するか、郵送で提出します。提出期限は特に定められていませんが、納付の特例が適用されるのは申請書を提出した翌月からになります。
労務業務についてプロに無料相談したい場合は社会保険労務士法人TSCがおすすめ
社会保険労務士法人TSCは1年間無料で社会保険や給与計算に関するサービスを利用できます。社会保険関係の事務業務を外部に委託でき、自分は本業に集中できるほか、個人事業主が法人化する場合の社会保険の手続きなどもサポートしてくれるのでおすすめです。
家族を従業員として雇うことはできる?
一人親方が同居する家族(配偶者やご自身の子ども、兄弟姉妹)を雇う場合、法的に、一般の従業員とは区別して考えられます。労務や保険の面で特殊な扱いをしなければいけません。しっかりと違いをおさえておきましょう。
家族を雇う場合は手続き不要?
同居する家族の場合、「家族従事者」として扱います。考え方は、「一人親方」の場合と同じです。
- 雇用保険には加入できない
- 労災保険へは特別加入できる(中学を卒業した子どもを雇用する場合も、労災保険に特別加入できます)
- 国民健康保険(もしくは、建設国保)に加入
- 国民年金に加入
手続きが必要な場合とは?
ほかにも従業員を雇っていて、かつ以下の条件を全て満たす場合、同居する家族もほかの従業員と同じように扱うことができます。
- ほかの従業員と、勤務時間・給与の支払い形式・休日制度などが同じ
- 雇用主の指揮命令に従って働いている
何をどうすべきか迷ったら、自治体や組合に相談してみましょう。
一人親方の下で働く場合は?注意点3選
ここまでは従業員を雇う一人親方について説明してきました。逆に一人親方に雇用される場合にはどのようなことに注意すれば良いでしょうか。以下の3点に注意する必要があります。
廃業届を提出する
開業届を出して今まで一人親方として働いていた方は、雇用されて個人事業主ではなくなるのであれば、所轄税務署と管轄の都道府県税事務所に廃業等届出書を出す必要があります。また、廃業届を出したとしてもその年分の確定申告は必要となるので注意しましょう。 その他、下記の書類も必要に応じて提出が必要となります。
- 青色申告の取りやめ届出書
- 消費税の事業廃止届出書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書
- 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書
- 個人事業税の事業廃止届出書
給与明細を確認する
従業員として雇用され、社会保険に加入する場合は、国民健康保険や国民年金から健康保険・厚生年金に切り替わります。給与や天引きされている社会保険料を確認するためにも、給与明細を受け取り、内容をしっかりと確認するようにしましょう。
再開する予定がある場合は廃業しない
一度廃業等届出書を出してから、再度事業を再開するとなるとまた様々な手続きが必要となります。そのため、一時的に自分の事業を休業するという場合は、廃業等届出書は出さずに、休業するという方法もあります。休業する場合は基本的に手続きは必要ありません。
一人親方でも従業員を雇うことができる!但し、各種手続きをお忘れなく!
一人親方が従業員を雇うと、仕事の生産性を向上させたり、優遇措置を受けられるメリットがあります。 一方で、従業員の分まで責任が増え、各種手続きをするために時間がかかったりするなどのデメリットも発生します。当然ながら給与を支払わなければいけないので、それ以上の利益を生み出せるように事業プランを立てなければいけません。 従業員を増やして会社を成長させるのか、それとも自分一人で事業を進めていくのか。 将来への目標をビジョンに入れ、働きやすさも考慮しつつ、あなたにぴったりあった道を選択してくださいね。
一人親方が法人化するメリット・デメリットについてはこちらで解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
 一人親方が法人化するメリットは?デメリットやタイミング、会社設立の流れも紹介
一人親方が法人化するメリットは?デメリットやタイミング、会社設立の流れも紹介
※ちなみに弊社では、建築建設業界特化の
無料ホームページ制作代行を新たにスタートさせました! 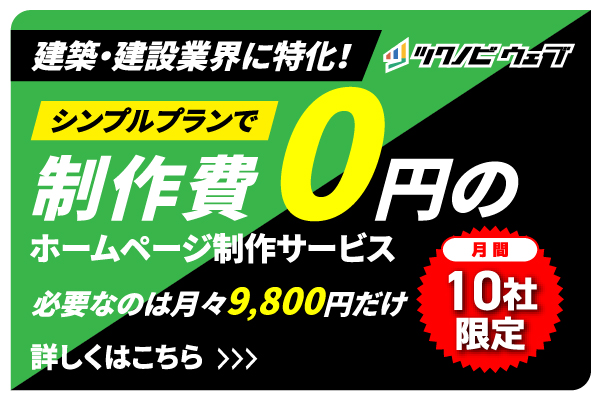 ※詳しくは👆👆👆のバナーをクリック!!
※詳しくは👆👆👆のバナーをクリック!!