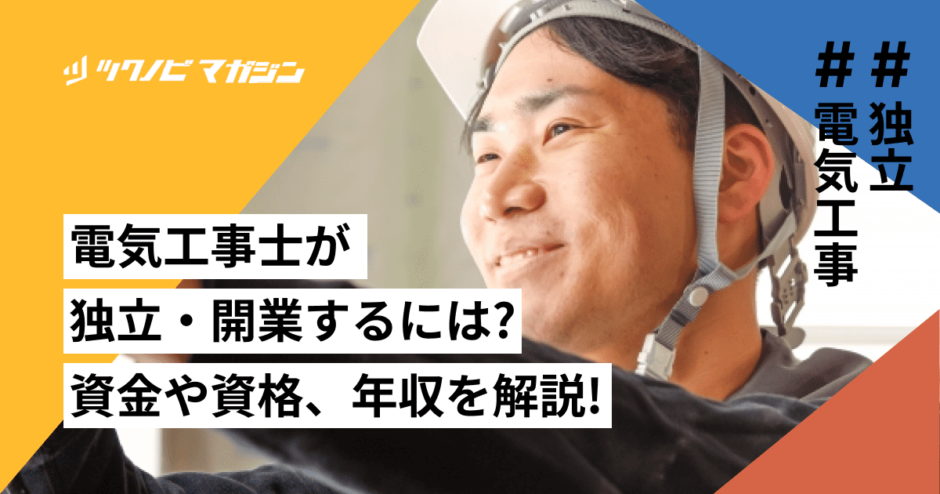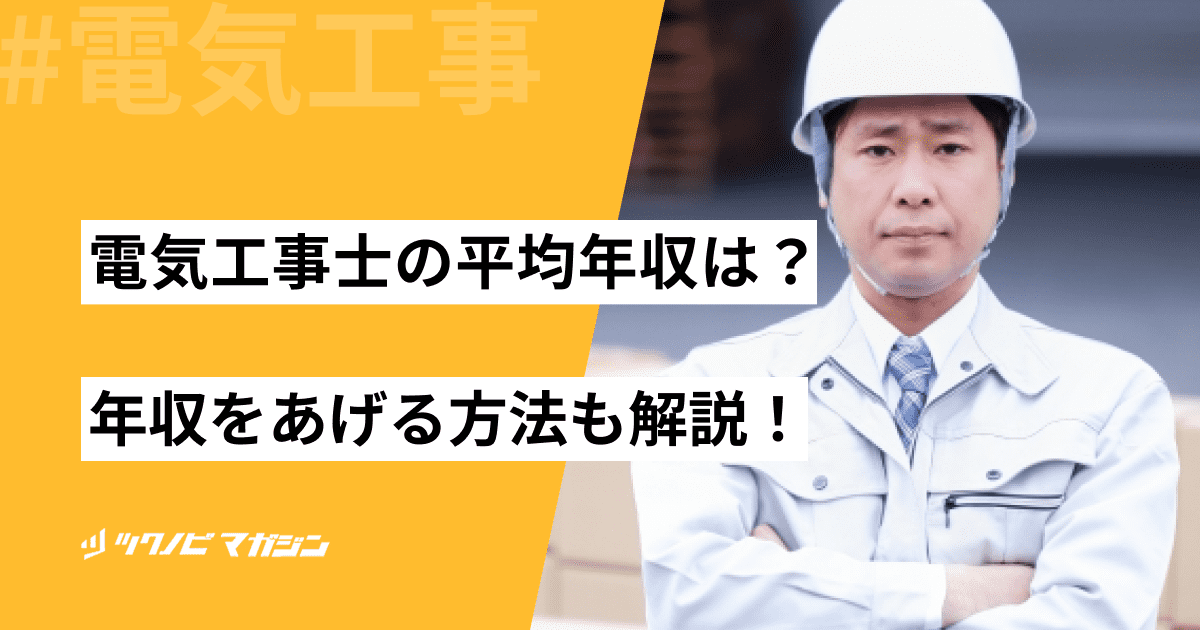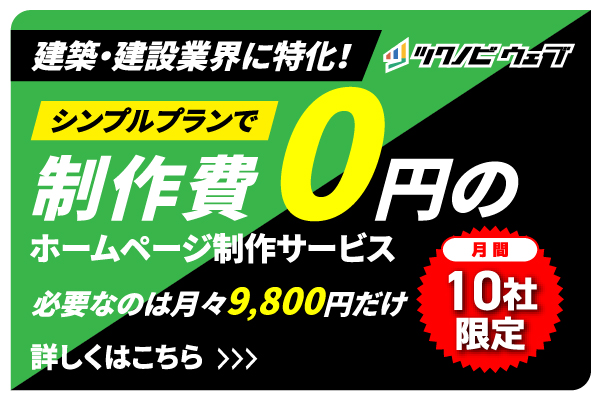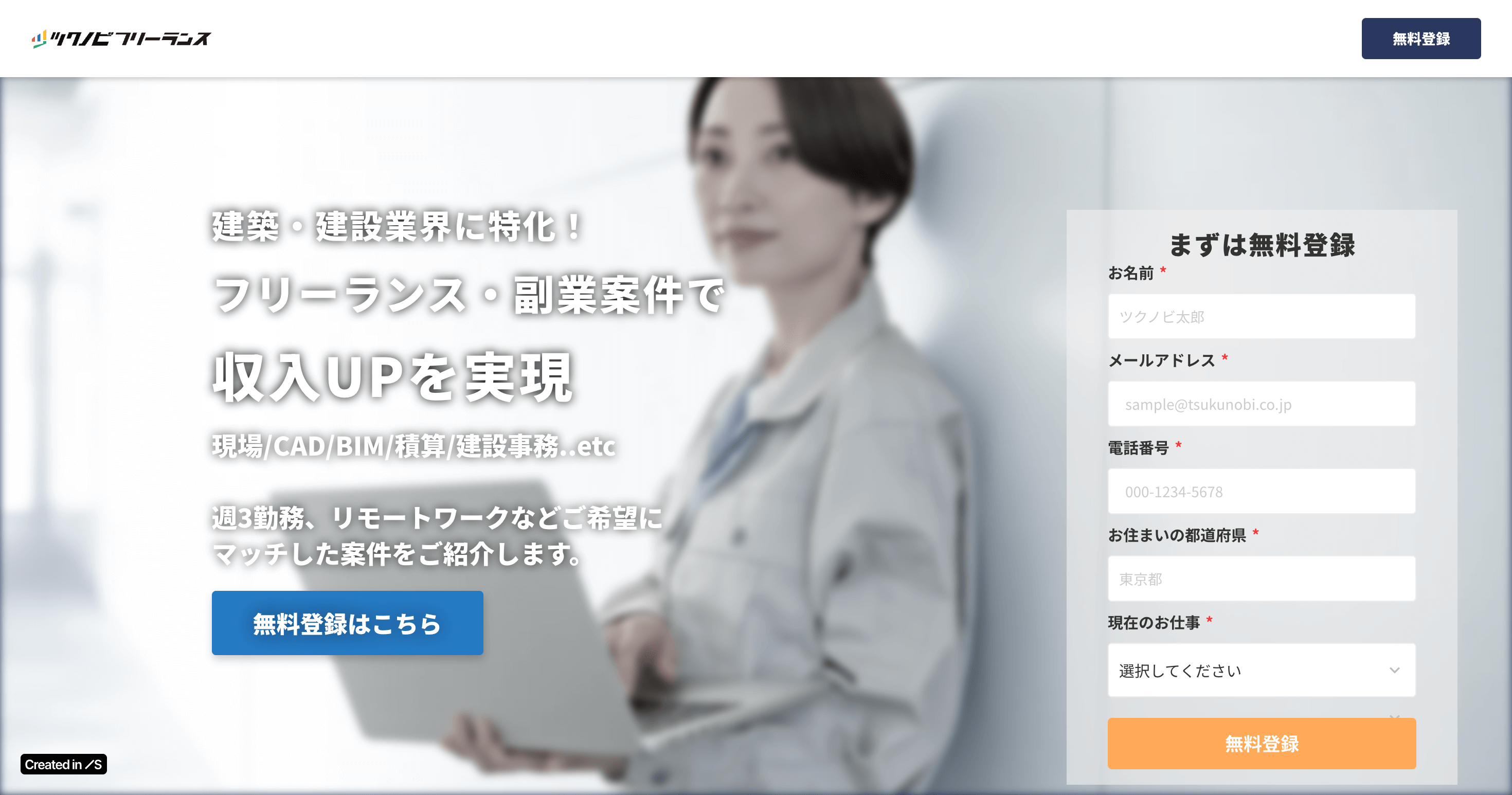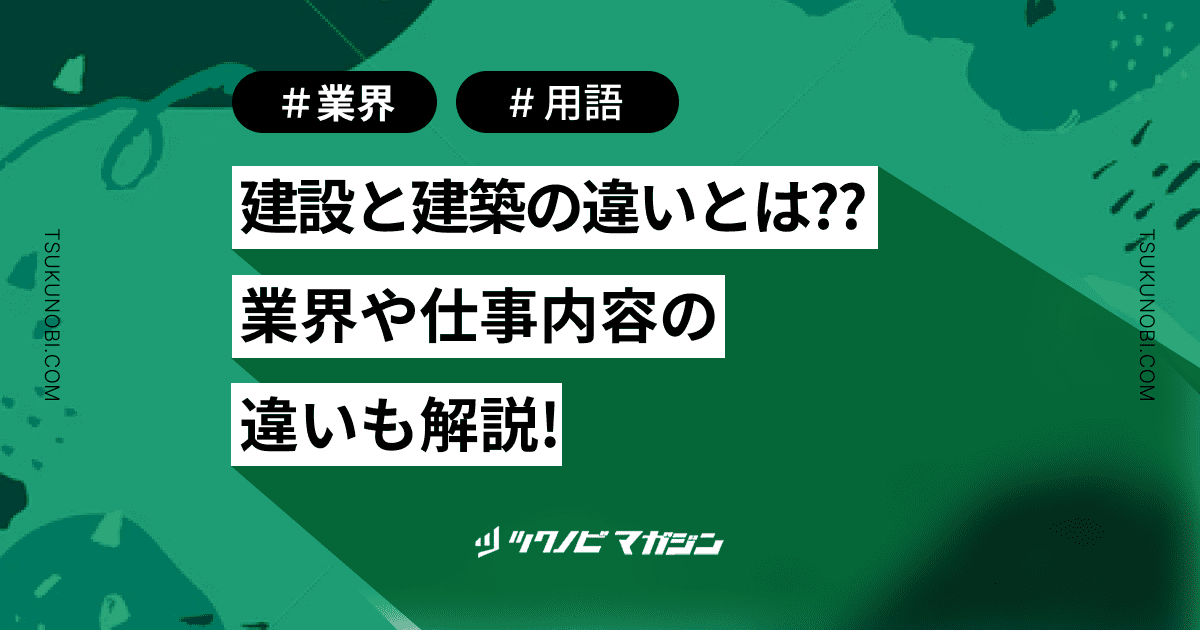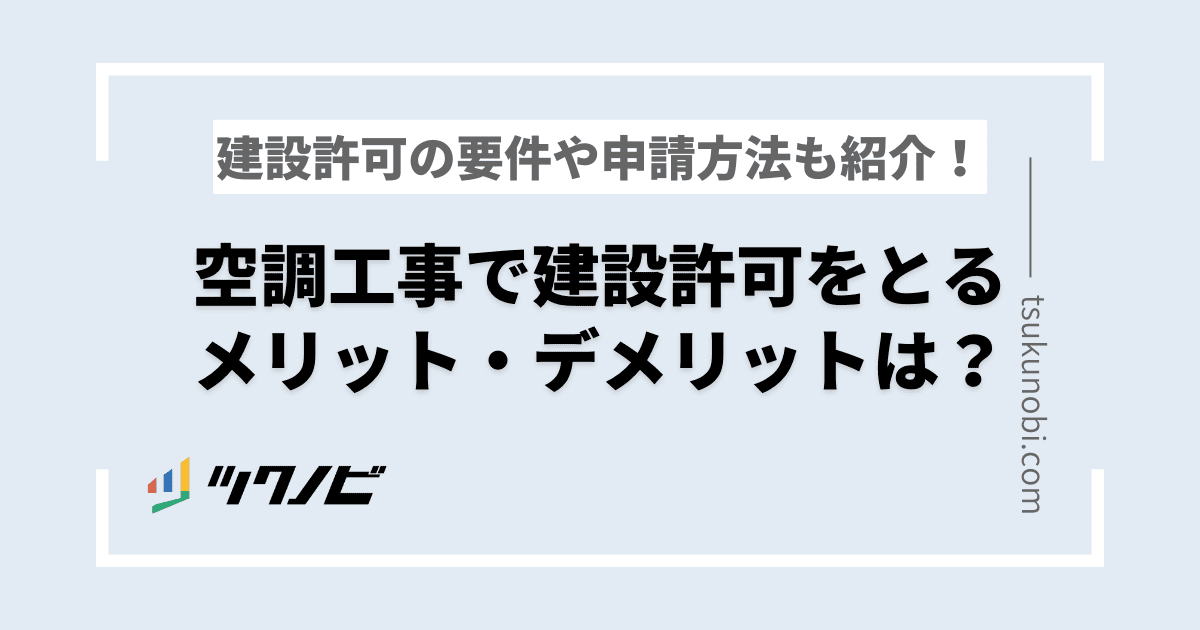※記事内に広告を含みます
電気工事に携わっている方のなかには
- 電気工事士で独立したらどのくらい稼げるのだろう
- 電気工事士が独立するにはどうすればいいのだろう
と疑問に思っている方もいるのかもしれません。そこで今回は電気工事士が独立する方法、独立にかかる費用や必要な資格、独立した場合の年収などをご紹介します。
電気工事士が独立した場合の年収
独立する際に一番気になるのは「独立したらどのくらい稼げるのか」ということでしょう。
ひとくちに電気工事士と言っても一人親方として独立している人や街の電気屋さんで開業している人など、独立の仕方にも様々なものがあり、その形態によって、収入にも差があります。
年収600~700万円
電気工事士が独立した場合で一番多い年収は500万円~600万円の範囲です。月収にすると50万円弱ほどになるでしょう。ただし、ここから業務に関わる必要経費などを引くと手元に残るのはさらに少ない額になります。
また、「営業力がなければ、この年収は難しかった」という方もおり、独立して稼ぐには営業力がなければ難しいこともうかがえます。
年収1000万円
電気工事士で独立した方のなかには、年収1000万円以上稼ぐ方もいます。電気工事は需要が高く、また電気工事士自体の人手不足もあいまって仕事が取りやすい状況にあります。営業をしっかりと行えば、年収1000万円にも手が届くでしょう。
電気工事士の年収についてはこちらの記事でより詳しく解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
電気工事士が独立するための必要な手順
電気工事士が独立するには以下の手順をふみましょう。
- 経験を積み、資格を取得する
- 独立に必要なものや資金を準備する
- 電気工事業者の登録手続きを行い独立する
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
1.経験を積み、資格を取得する
電気工事士として開業するには資格が必要です。まずは第二種電気工事士の資格を取得し、取得後3年以上の実務経験を積みましょう。
実務経験があれば認定講習をしなくても認定工事従事者の資格申請ができます。また、第一種電気工事士の受験資格も得られます。独立前に第二種電気工事士の資格を取得しているのであれば、実務経験の勤務証明書を発行してもらいましょう。
第一種電気工事士・認定工事従事者、どちらの資格でも独立するうえで業務の幅も広がり仕事を受注するにもメリットとなります。
電気工事士の一人親方が収入をアップさせるポイントはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
 電気工事士の一人親方がもらえる日当は?メリットや収入アップのポイントも解説
電気工事士の一人親方がもらえる日当は?メリットや収入アップのポイントも解説
2.独立に必要なものや資金を準備する
独立には設備を準備する資金や営業資金、車両にかかる資金などいろいろな費用にかかる資金が必要です。例えば、電気工事に必要な工具、現場へ行くための車両、営業には名刺や車両などがあります。
インターネットを使った営業となればパソコンやその周辺機器などこまごまとした備品にも費用が掛かります。
少ない資金で独立しても良いのですが、軌道に乗る前に資金が無くなる可能性もあるでしょう。準備する資金の目安として500万円程度が必要と言われています。
3.電気工事業者の登録手続きを行い独立する
独立するのには電気工事業者としての登録手続きが必要です。資格取得後に登録電気工事業者として都道府県知事に登録申請を行ってください。
手続きに必要な提出書類や該当条件などが複雑で都道府県によって細かく異なるため、申請する窓口に問い合わせしてみるのも良いでしょう。また、専門家である行政書士などにお願いして手続きする方も多いです。
登録ができたら独立開業となります。登録してから5年後には更新手続きを行うことになるため注意しましょう。
電気工事で独立するために必要な準備
電気工事で独立するためには、様々な準備が必要です。独立する際準備しておくと良いものを以下具体的に紹介していきます。
電気工事に関わる資格の取得
電気工事業で独立するためには、「電気工事士」(第一種 第二種)の資格が必要です。
最低でも第二種の資格は取りましょう。第二種は実務経験がいりません。しかし独立するのであれば、可能な限り第一種があったほうがいいでしょう。次に第一種と第二種の資格の違いを見てみましょう。
電気工事士(第一種・第二種)
第二種電気工事士は、試験に合格するか専修学校や専門学校、公共職業訓練施設等を卒業すると取得することができます。電圧が600Ⅴ以下の電気工事(配線工事や電気設備工事)を扱うことができます。働く場所は、一般住宅や小規模な店舗・事業所になります。
第一種電気工事士は、電気工事の実務を通算3年以上経験し、第一種電気工事士試験に合格しなければいけません。最大電力が500㎾未満の電気工事(配線工事や電気設備工事)を扱うことができます。働く場所は、ビルや工場・大型店舗と広がります。第一種電気工事士は、5年ごとに「認定講習」がありますので、忘れないように受けましょう。
試験では筆記試験のほか、各自持参した工具を使って配線作業をする技能試験も出題されます。一から工具を揃えるのは難しいので、問題集と必要な工具がセットになっている「技能試験対策セット![]() 」を購入してしまうのがおすすめです。また試験練習の回数は1~3回分から選べます。
」を購入してしまうのがおすすめです。また試験練習の回数は1~3回分から選べます。
認定電気工事従事者
第二種電気工事士が、実務経験3年で申請すると取得できる資格です。試験は特にありません。事業所物件について電気工事をする場合は、この資格が必要となります。
電気工事士の資格だけでは、家庭用の電気工事しかできないのです。独立するなら、取っておきましょう。
登録電気工事業者
第二種電気工事士と認定電気工事従事者の資格がとれたら、登録電気工事業者は確実に申請します。(試験はありません。)
なぜなら、電気工事をするためには都道府県の知事の許可が必要だからです。書類作成が難しい場合は行政書士などに代行申請してもらうこともできます。
建設業許可
結論から言うと、建設業許可は急いで取得する必要はありません。電気工事の場合は「建設業許可(電気工事)」という許可になりますが、この許可が必要な
工事は1件当たりの受注額で決まります。電気工事は「建築一式工事以外」と言って、消費税込みで1件の請負代金が500万を超える工事の場合、建設業許可が必要となります。
独立開業当初は、500万を超える仕事を受注することは少ないでしょう。なので、独立して余裕のある時に取得しましょう。
その他の資格
その他に特殊な資格や関連領域の資格を、載せておきます。
自分の請け負いたい工事の種類や内容に応じて取得を検討しましょう。
〇特殊電気工事資格(ネオン工事)
〇特殊電気工事資格(非常用予備発電設置工事)
〇電気工事施工管理技士(1種、2種)
〇技術士(建設、電気電子、統合技術監理含む)
〇電気主任技術者(1種~3種)
〇登録電気工事基幹技能者
〇建築設備士
〇計装士
工具の準備
独立をするのであれば電気工事に使用する工具も準備しましょう。今までは会社の工具を利用していたため準備する必要はありませんでした。しかし、独立開業するためには工具を揃えなければなりません。
始めから全部揃えるには資金も必要となります。そのため、受注した工事によって必要な工具を揃えるのが良いでしょう。必ず使用する工具や電気工事作業に必要な道具、材料などを挙げていきます。
〇測定器・計器類(絶縁抵抗計、接地抵抗計、テスター)
〇安全装備品(ヘルメット、安全靴、安全帯フルハーネス)
〇電気工事作業工具(腰道具、電動ドリル、脚立、梯子など)
〇材料(VVF電線、CVTケーブル、ビニールパイプ、配線用器具、アース棒など)
資金の準備
電気工事で独立するためには、開業資金と準備品が必要です。まずは、工具備品で30万円はいるでしょう。もちろん今まで使用していたものでも構いません。
移動や工具運搬のための軽トラックか軽バンは、自家用車と別に用意しましょう。100万円~150万円かかるとすると、合計で130万円~180万円は必要です。
さらに後で述べますが、法人の場合は法定設立費用6万円~20万円+資本金が必要です。もし建設業許可を取得する場合は、財産要件500万円が必要ですが、これは資本金と重複可能です。
開業費用は、自己負担が難しい場合、創業融資も視野に入れておくことも考えられます。創業融資は、日本政策金融公庫や自治体の創業窓口に相談してみましょう。
また、「経営サポートプラスアルファ」という、開業と資金調達に強い専門家集団がいますので、相談してみると良いでしょう。
クレジットカードを作成する
独立には資金準備が大変ですが、現金で全部を支払うには限界があるため、備品の購入などに利用できるクレジットカードの作成も必要です。クレジットカードは独立する前、会社に勤めている時に作成するのがよいでしょう。
独立直後だと収入が不安定と判断され、クレジットカードの審査が通らないかもしれません。独立するなら個人とは別で法人用のクレジットカードを用意しておくとよいでしょう。確定申告などの際に会計処理が楽になります。
立地的に必要な場合は車を購入する
現場へ向かうためには工具や備品を積んだ車が必要です。歩いて現場にいければ良いのですが、あちこちに現場があるとなれば車はどうしても必要になります。
値段も高価なものになるため、一括支払いは難しく購入にはローンを使うのが一般的です。しかし、独立した後では収入がなく信用がない状況のため、審査が通らないことがほとんどです。ローンで車を購入するならば、独立後のことを考え
会社勤めをしている間に準備することをおすすめします。
事前にHPを作っておき、独立後すぐに公開できるようにする
独立後は営業や準備に忙しいため、ホームページを独立前に作成しておくことも重要です。最近では自社をアピールする、宣伝する方法としてホームページ開設が主流になっています。
インターネットを利用した集客や営業はどんな業種でも利用しているツールです。独立してすぐに必要となる名刺や会社のロゴなどもホームページに掲載し、独立前に準備しておくと開業後に取引先や営業先から信頼感も得られやすくなります。
ホームページ制作を依頼するには何十万~200万円ほどかかるイメージですが、最近では安価に制作できるサービスもあります。まずは名刺代わりに欲しいという方におすすめです。
弊社では初期費用0円、月額9,800円のホームページ制作サービスを行っています。1からホームページを作成するのが難しい方はぜひ検討してみてください。
電気工事士が独立するメリット
電気工事士で独立すると様々なメリットがあります。ここでは電気工事士として独立する場合の4つのメリットを紹介します。
建設系職人の中でも収入が高め
建設系の工事には様々な種類があります。そのなかでも電気工事の職人は年収が高めになります。
大きな施設から個人の家まで、建物を利用するには電気設備が必要です。電気工事以外の職人は、作業する分野が異なり専門的な知識や資格が必要な電気工事はできません。
建築している建物があれば電気工事の仕事は必ずあります。資格取得が必要な電気工事は感電など危険なリスクを伴っているため、建設系職人の中でも収入は高めとなっています。第一種電気工事士を取得して独立開業すると年収は500万円〜700万円程度になる方が多いです。
需要が多い
電気はライフラインに必要不可欠なものです。住宅や工場、ビルなど、建物があれば電気が必要です。そのため、電気工事は絶対になくならない仕事といえます。
新築の建物以外でも、古くなった建物の点検や電気設備の修理などもあります。最近では自然災害なども多く、ライフラインである電気を復旧するための電気工事も重要です。独立すると自分で仕事を決められるため依頼があるかぎりは仕事がなくなることはないでしょう。
仕事のペースを調整しやすい
会社に勤務していると作業現場や仕事のペースや工期が決められていたため、自由な調整はできませんでした。独立すると工期に合わせて自分のペースで仕事ができます。
決められた工期内に作業が完了していれば良いのです。極端な例ですが、1か月の工期に対して半月で仕上げ、残りの半月は休むといったことも可能になるのです。
また仕事を自分で選ぶこともできるため、仕事のペースを調整しやすくなります。ただし調整しやすいからといって工期を忘れてしまっては信用を失ってしまうため注意が必要です。
うまくいけば会社勤めよりも稼げる
電気工事の資格を取得していても会社勤めをしていると、売上げに関係なく給料というかたちで収入を得ることができます。しかし同じ資格を取得していて独立開業すると、売上げは自分のものになるため収入は上げられます。
また、営業がうまくいって売上げの高い仕事を受注すると収入はもっと上がります。売上げから経費を引いた分が自分の収入となるのです。経費計上もできるため節税対策にもなります。受注次第で会社勤めよりも稼げるようになるでしょう。
電気工事士が独立するデメリット
独立には様々なメリットがありますが、同様にデメリットもあります。次に電気工事士が独立する4つのデメリットを紹介します。
資格や経験を積んでおく必要がある
電気工事で独立するには資格取得や経験が必要です。電気工事は感電など危険を伴う作業になるため資格取得で専門的な知識を得て、経験を積んでおかなければなりません。
周囲から電気工事士としての信頼を得られないと集客できないため、独立が難しくなります。会社勤めをしているうちに開業に必要で有利な資格をなるべく多く取得し、自分のスキルや経験値をあげておきましょう。
独立後にさらに上を目指して資格を取得しても良いですが、現場の作業以外にも事務的なことに時間が取られるため、なかなか取得しにくくなります。独立がスムーズに行えるよう準備しておきましょう。
営業も自分でやらないといけない
会社に勤めていると仕事はありますが、独立後は仕事がすぐにもらえるとは限りません。営業しないと仕事は来ません。
独立して仕事を受注するには自分で営業を行います。会社に勤めているうちに取引先などに独立することを伝え、つながりを持っておくことも重要な営業のひとつです。
営業は複数の会社や個人にも行う必要があります。しかし、独立後、一人で作業しながらの営業はなかなか難しいでしょう。
そんな場合には作業は自分が行って、営業は外部に委託するという方法もおすすめです。営業代行サービスであれば営業のプロが質の高い営業を行い案件獲得してくれます。自分は施工に集中することができるので作業効率もアップします。
ツクノビセールスは、建設業に特化した営業代行サービスです。御社の代わりに月間2,000社に営業を実施し、【効果が出なければ全額返金プラン】もご用意しております。電気工事業のお客様で、2ヵ月で1,200万円の売り上げに繋がった事例もありますので、ぜひ一度詳細をご確認ください。
※弊社の営業代行サービスツクノビセールスは、
【効果が出なければ全額返金プラン】を新たにスタートさせました!

※詳しくは👆👆👆のバナーをクリック!!
経理などの事務仕事もする必要がある
電気工事士としての仕事だけではなく、独立すると事務仕事などもあります。今まで携わっていなかった分野も自分で行わなければなりません。
経理の内容は多岐にわたります。資金繰りから支払いや請求、金融機関とのやり取りなどです。また確定申告なども自分で行う必要があります。
会計ソフトなどを利用して入出金を毎日のように処理すると後で慌てることもないでしょう。作業が忙しいからと後回しにしないように心がけることが大切です。
「現場の合間の事務効率」を上げたい方向け
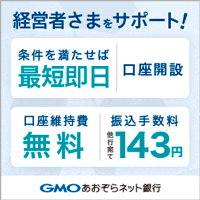
GMOあおぞらネット銀行 法人口座なら銀行へ行く時間がない現場仕事の合間に、スマホ一つで振込完結。
手数料が安いうえに入出金も即座に通知が届くので、忙しい工期中の資金繰り管理がとにかく楽になります。
病気やケガなどで収入が減るリスクもある
独立すると個人事業主となるため、労災に加入できません。仕事でケガをしたり、病気になった場合は保障がないのです。仕事ができないことで収入も減ってしまうリスクもあります。
従業員がいればカバーできますが、一人で独立している個人事業主では難しいでしょう。こういう場合もあるため、民間の保険に加入するなど月々の支払いも考慮しながら、リスクに備えることを検討してみましょう。
建設業で年収を上げるならツクノビフリーランスがおすすめ
建設業で年収を上げたい方には、建設業特化のフリーランス・副業案件マッチングサービス「ツクノビワーク」の活用がおすすめです。
様々な条件の案件を取り揃えているため、週1~5日で勤務できる案件やリモートワークで勤務できる案件など、幅広い案件の中からご希望の案件をマッチング可能です。大手企業の案件から、即ご活躍いただける中小の企業まで、さまざまな規模の案件を用意しています。
スキマ時間で稼ぎたい方や年収を上げたい方はぜひこちらから詳細をご確認ください。
「法人化」で独立する時と「個人事業主」で独立する時の違い
電気工事で独立開業する場合は、法人化(会社設立)と個人事業主という2つの道があります。一人親方として開業される場合は、個人事業主として活動されて問題ありません。まずは第一種電気工事士の資格取得を目指しましょう。
ただ、電気工事で独立の場合、比較的単価が高いので会社設立の検討もおすすめです。ここでは法人化と個人事業主で独立する時の違いを詳しく解説していきます。
経営面での違い
- 法人化の場合は、経営面で以下のメリットがあります。
- 社会的信用がある
- 経費の範囲が広い
- 責任の範囲が有限
- 赤字繰り越しが10年である
- 売り上げが多くなれば、個人事業主よりも税率が下がる
- 最高税率が23.2%と所得税の約半分
税制面での違い
法人化した場合は税制面でも下のようなメリットがあります。
・所得税・・・代表個人の役員報酬を「給与所得」として算出し、その5%~45%
・個人住民税・・・代表個人の役員報酬を「給与所得」として算出し、その約10%
・消費税・・・課税売上1000万円以上の場合支払う。(会社の場合は2年間は支払義務がない特例あり)
ただし法人化の場合、デメリットとして、法人税(15%~23.2%)と、法人住民税がかかります。
法人化には様々なメリットがありますが、ハードルが高いと感じる方もいます。最初は個人事業主として独立し、売上が高くなったら法人化を検討するのもよいでしょう。
電気工事で独立で失敗しないためのポイント
独立したはいいものの、売上がなかなか安定しない、仕事が受注できないと悩む方も少なくありません。ここでは電気工事で独立した際失敗しないポイントを紹介していきます。
資金をしっかり確保しておく
独立する予算があまりない状態で独立してしまうと資金繰りで苦労します。独立後は初月からそれまでの給料分の収入が得られることはまずないでしょう。最低限半年分の生活費は、貯金しておき、仕事が受注できなくてもしのげるようにしておきましょう。
経験を積んでから独立する
電気工事で独立しようと思ったら、資格や実務経験が必須です。スキルも知識も実績もない状態では、電気工事でお金を稼ぐことはできません。会社で働いているうちにスキルや知識をしっかりと身に着けておきましょう。できれば営業や経理などの勉強もしておくのがおすすめです。
営業を行う
電気工事で独立するためには、営業経験が必要です。なかには「今まで営業は全くしたことがない」という方もいるでしょう。しかし、独立したからには営業しないと仕事が取れません。営業するにあたっては、「人脈の多さ」と「新規開拓できること」が必要になってきます。
人脈に関しては独立前に勤めていた会社で扱った案件の関係者との関係を大切にしましょう。以前、扱った仕事の対応や技術が高評価であれば、独立後もあなた個人に引き継いで仕事をお願いする案件が多くなるでしょう。独立する際に「どれだけ人脈を持っているか」非常に大きなカギになります。
「新規開拓」は自分で行動し、必要のある所に電話を掛けたり、足を運んだりして提案しに行く必要があります。このようにして、案件受注が安定してくると、独立が成功したといえるでしょう。
経理事務担当者を配置する
経理事務を誰にどこまで任せるかを独立前に確認し、決めておくことです。独立すると公的機関への届け出から、決算表の作成、税金手続きなどの他に、様々な書類作成や細かい手続きを行う機会が実にたくさん増えます。
営業と工事と同時進行で行うことはかなりのストレスです。経理事務担当者を配置することで工事などの業務に集中できるようになります。
独立支援を活用する
求人情報には「独立支援」という記載が載っている会社があります。従業員の独立を、積極的に推奨している会社です。
そこでは「横のつながり」のために色々な援助を行ったり、案定した案件受注や経営の要素を教えてくれます。こうした支援も積極的に活用していきましょう。
営業代行サービスに相談して営業戦略の提案を受ける
営業代行サービスに相談して営業戦略の提案を受けるという方法もあります。営業代行には獲得のプロがいますので、外部に頼ってみるのもおすすめです。
例えば弊社サービスである建築建設特化の営業代行「ツクノビセールス」は、月に2000社もの企業に御社の営業としてアタックし、かつ成果が出なかったら返金保証もしています。一人親方向けのミニマムプランももちろんご用意しております。
まずは話だけでも聞いてみたい!という方には無料でどのように営業していくべきか営業戦略のご提案も致しておりますので、お気軽にご相談ください。
オンラインにて30分程度でお打ち合わせ可能ですので、明日30分だけ空いている!という方でも気軽にご相談いただけます。
無料相談はこちらから↓↓↓
建設業の人手不足解消ならツクノビBPOがおすすめ
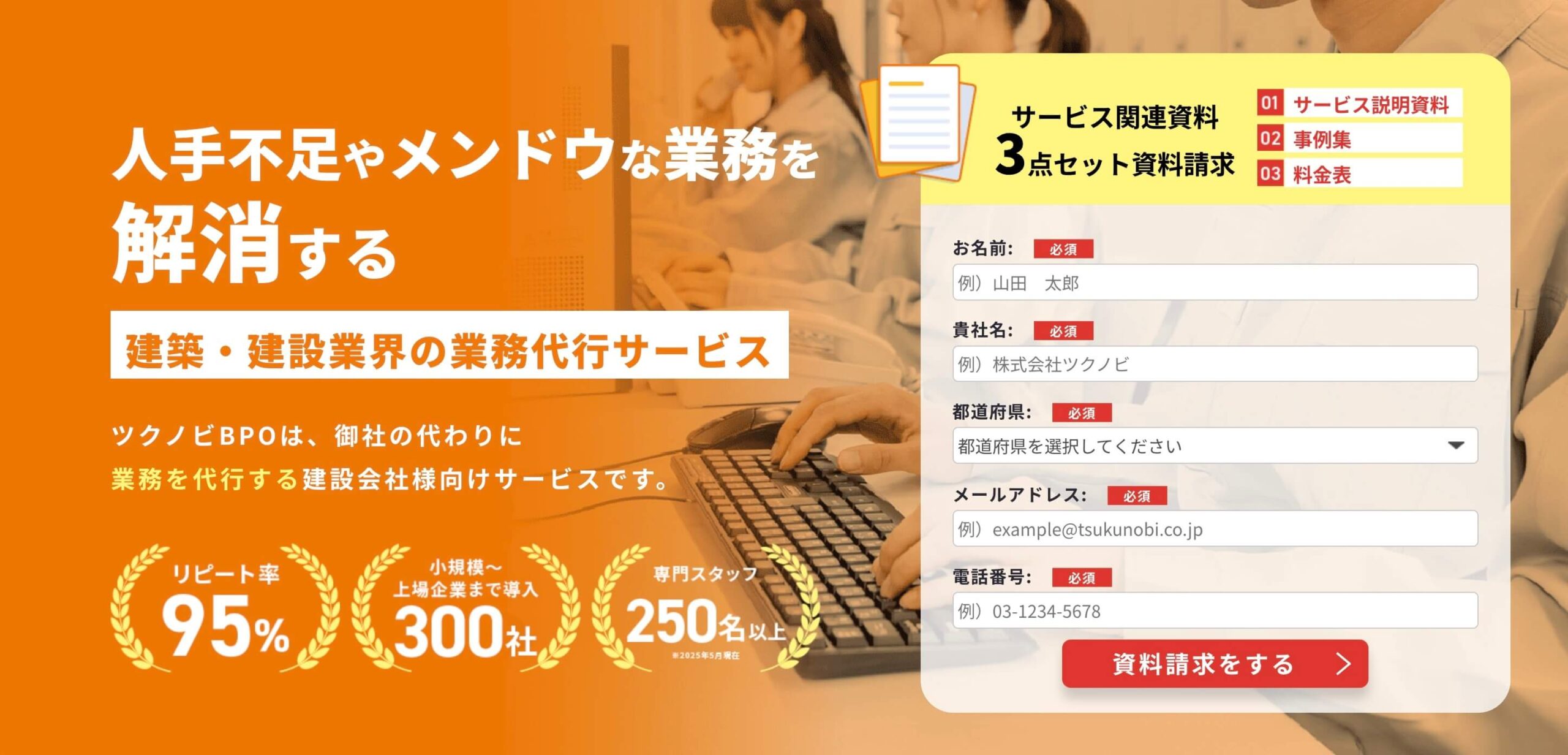
建設業の人手不足を解消するためには、アウトソーシングサービスの利用もおすすめです。
従業員のリソースがひっ迫している場合や、業務に対応できる人材が不足している場合などは、アウトソーシングサービスを活用すると、少ない工数で業務を実行できます。BPOサービスでは、専門的な知識を持っているスタッフが対応するため、さまざまな業務をスムーズに進められます。
弊社では、建設業の業務に対応している建設業特化のBPOサービス「ツクノビBPO」を提供しています。書類作成や図面の作成、積算業務など、幅広い業務を代行できます。ツクノビBPOでは、倍率200倍の選りすぐりの専任スタッフが対応いたします。
リソース不足を解消したい方は、ぜひこちらからお問い合わせください。
電気工事士は不足しているから仕事が取りやすい
電気は生活に必要不可欠で重要なものです。現在はインターネットやスマートフォンを取り扱う産業が発達し続けています。環境にやさしいエコ商品や電気自動車、太陽光発電などの設備の拡大など、電気工事に対するニーズは高いです。
また、建物の老朽化による改修工事や震災後の復旧、近年の自然災害の復旧なども行われているため電気工事の案件は受注が取りやすい傾向にあります。
さらに電気工事業界では、職人の人材不足も起きています。仕事はあるが人材がいないという現象です。電気工事士も人手不足によって仕事の依頼が増えるでしょう。
【まとめ】しっかり起業準備して営業活動をすれば独立も怖くない
いかがでしたか?電気工事士で独立すると、会社員時代以上の年収も夢ではありません。しかし、独立するには知識や経験を身につけておくだけではなく、営業力や資金なども必要になってきます。
今回紹介した内容を参考に事前の準備を入念に行い、電気工事士としての独立を成功させましょう!
※弊社の営業代行サービスツクノビセールスは、
【効果が出なければ全額返金プラン】を新たにスタートさせました!

※詳しくは👆👆👆のバナーをクリック!!