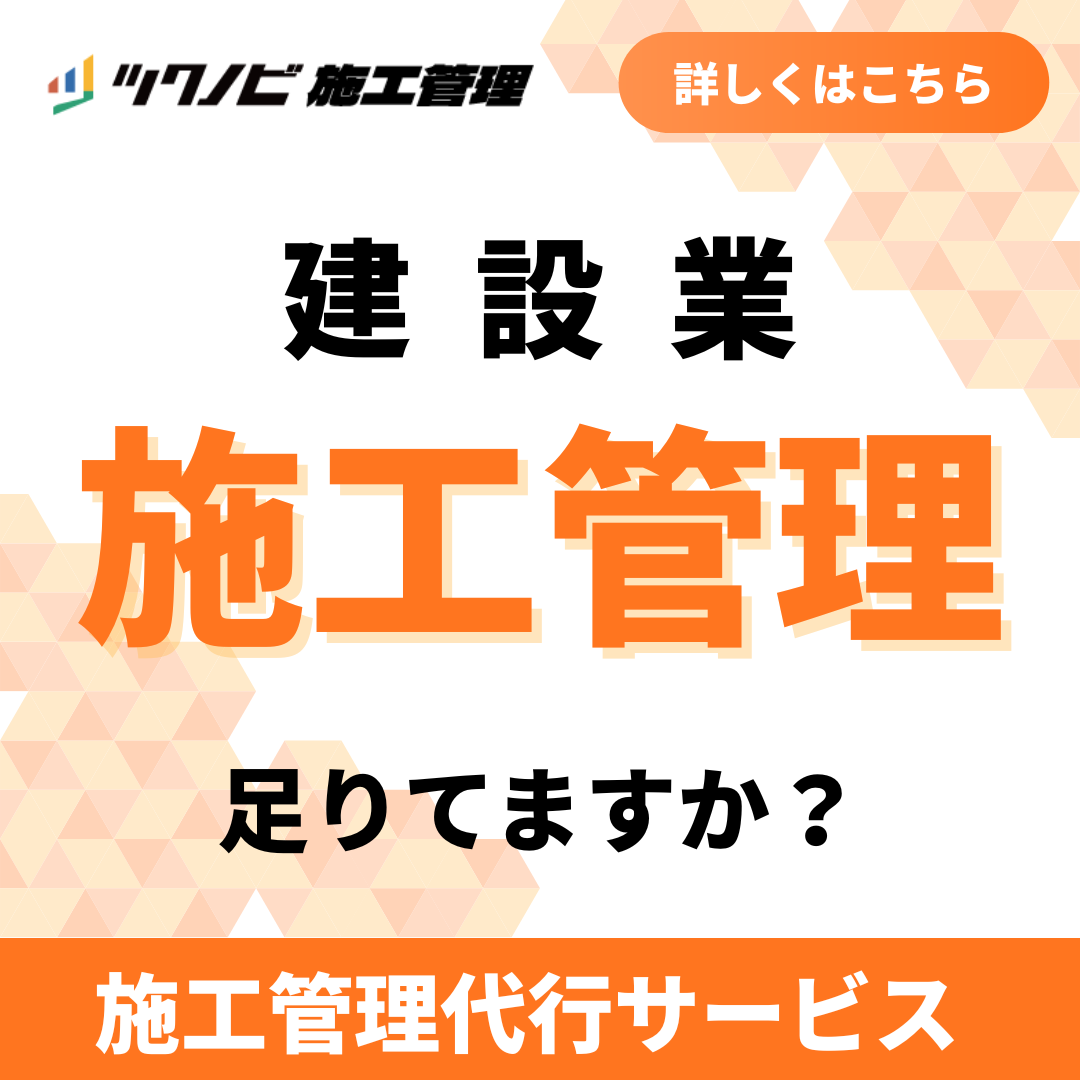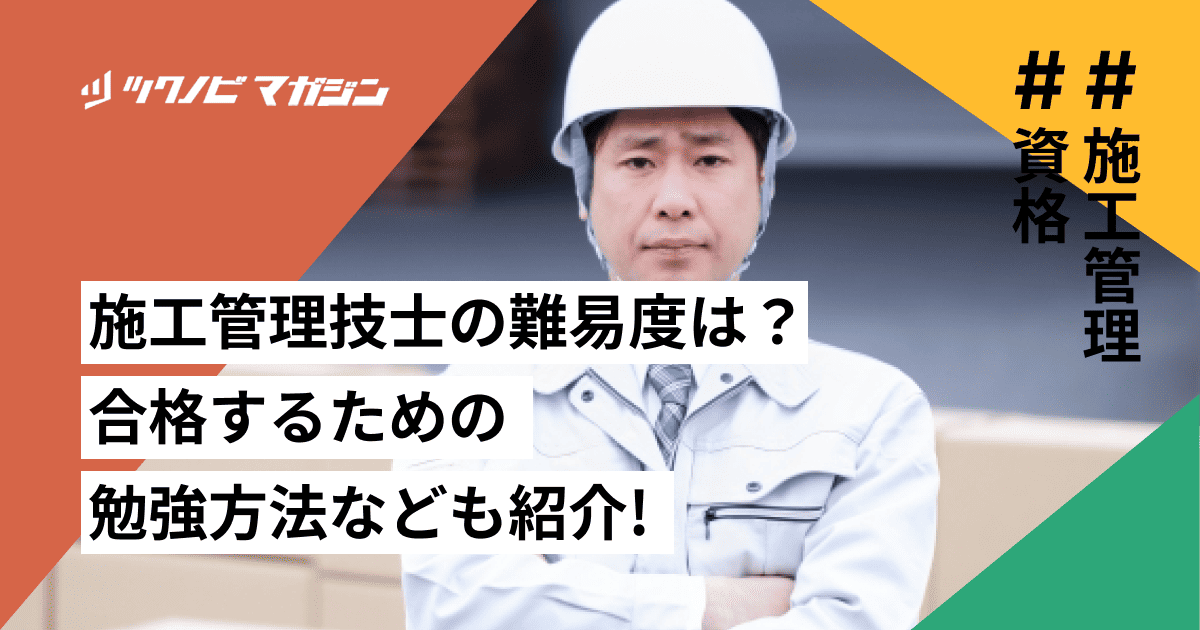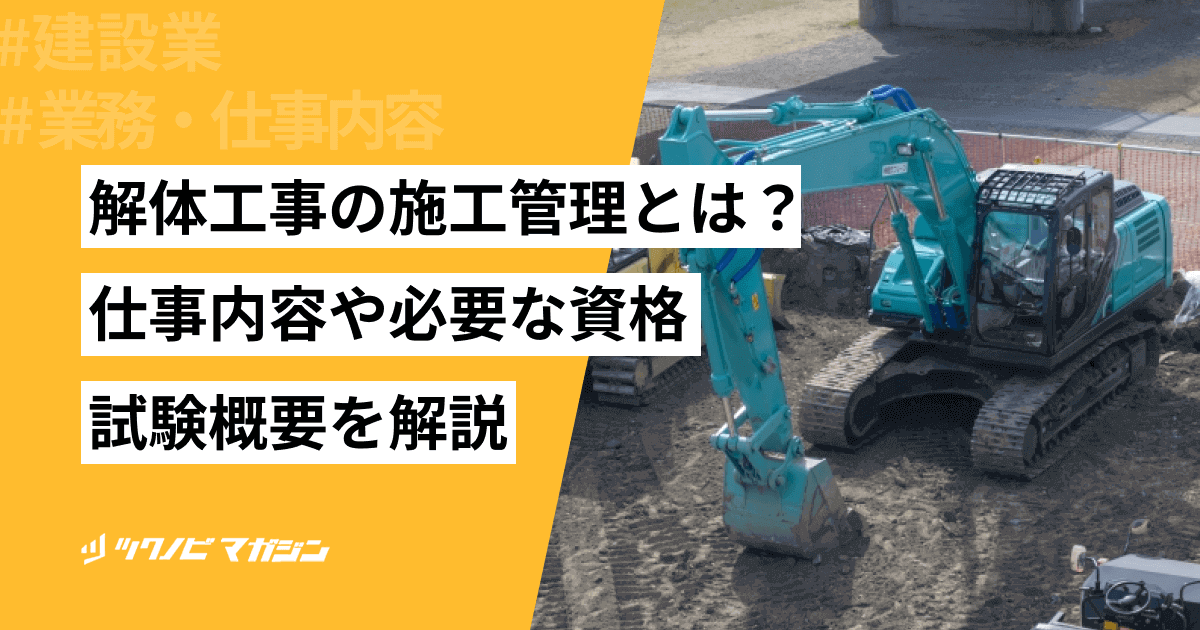※記事内に広告を含みます
施工管理の仕事は、工事の進捗管理だけでなく書類作成など覚えることが多いです。
- 施工管理士の仕事内容は?
- 施工管理士の仕事を早く覚える方法は?
- 施工管理士に求められるスキルは?
こんな疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか?
本記事では、施工管理士が初めに覚える仕事や具体的に仕事を覚える方法などを紹介します。また、施工管理士に求められるスキルも解説しているので、ぜひ参考にしてください。
施工管理の経験が豊富なプロ人材が御社の施工管理業務を代行いたします。施工管理の経験者をすぐに採用でき、施工管理人材の人手不足を解消できることで、受注できる案件の増加や退職率の低下など、様々なメリットがあります。詳細はぜひこちらからご確認ください。
施工管理の仕事で初めに覚えること
施工管理の仕事で初めに覚えることを5つ紹介します。
工程管理
工程管理とは、作業の予定を表した工程表のとおりに工事が進んでいるか確認・調整をする仕事のことです。建設現場では、複数の専門工事が同時並行で進んでおり、適切なスケジュール管理は欠かせません。工程表に基づいて工事の進捗を管理することで、工期の遅れを防ぎ適切なコストで建物は完成します。
工程表にはガントチャートが使われます。ガントチャートは、作業の開始から終了までを横棒で表し、工事の流れを一目でわかるようになるツールです。工程を可視化することで管理しやすくなっています。
工程管理は、現場の進捗状況を把握して、先のことを見通し判断する力が養われます。この能力は、施工管理だけでなく様々な業務にも役に立つでしょう。
原価管理
原価管理とは、見積から算出した予算内で工事を完了させるための仕事のことです。建設業は1つのプロジェクトの期間が長いため、人件費や材料費など様々なコストがかかります。原価管理を適切に行うことで、無駄な支出を防ぎ会社の利益を確保しつつ高品質な施工が実現します。
原価の計算で使われているのは、ガントチャートと資材のカタログです。ガントチャートは各工事の期間を横棒で示し、そこから必要な人数を割り出して人件費の計算に使います。
資材のカタログを使用するのは、使用する建材の材質や大きさなどから価格を比較するためです。これにより、適切な資材を選びコストを抑え、予算内に建材を調達します。ガントチャートと資材のカタログを使った原価計算は、工事費用の根拠を明確にし顧客が納得しやすい原価の証拠としても役立ちます。
原価管理は、建設におけるコストの流れを把握する力だけでなく、顧客と交渉する力も鍛えられます。工事の見積を適切な根拠を示しながら説明する必要があるため、論理的な思考力も身に付くでしょう。
安全管理
安全管理とは、工事現場で起こる労働災害を防ぐために対策をする仕事のことです。建設現場では、高所作業や重量物の荷揚げなど、一歩間違えば人命に関わる危険が潜んでいます。危険を排除することで、作業員の安全が確保されつつ事故を防ぐことができ顧客からの信頼につながります。結果、今後の仕事に良い影響を与えるでしょう。
安全管理に大切なのは、危険なことが起こらないように対策、もしくは立ち入りを禁止することです。例えば、資材を搬入・搬出するために床に大きな穴が開いている場合は、人が開口部に近づかないようにバリケードを設置します。
安全管理は、周囲の状況から危険を察知する危機管理能力やリスクを回避する力が身に付きます。このような能力は、日常生活でもリスクを予測し冷静に対応する力として活かせるでしょう。
品質管理
品質管理とは、建設業において設計図面や仕様書の基準を満たしているか確認する仕事のことです。建物は使用する建材や工法によって安全性が左右されるため、品質が低ければ重大な事故につながります。適切な品質の管理を行うことで、施工不良を未然に防ぎ高品質な建物を顧客に提供できます。
品質管理の仕事で特に多いのが、施工後の品質確認です。例えば配管同士をつなげる溶接工事では、施工管理士が溶接部分の強度を確認するために、作業員は水を使った耐圧試験を行います。
品質管理は、細部にまで注意する観察力や瞬時に判断する決断力を身に付けられます。特に決断力は、情報が更新されるスピードが早い現代において重要な能力でしょう。
環境管理
環境管理とは、建設工事によって周辺の環境に与える影響を最小限にする対策を行う仕事のことです。建設工事は、騒音の発生や粉塵が飛散するなど周囲に様々な影響を与えます。これらの影響を抑えることで周辺住民や自然環境への負担を減らし、安全でスムーズに工事ができます。
環境管理で大事なのは、周辺への影響を減らすことです。騒音対策では、騒音が出る時間帯を設定し周辺住民の理解を得るのと防音シートの設置をします。また粉塵対策は、風で飛ばされる砂は定期的に水をかけ固めることで周囲に飛散しないようにします。
環境管理の仕事をこなすことで、リスクから対策を講じる力が身に付くでしょう。環境に関する知識は建設業だけではなく様々な業界でも役に立ちます。
施工管理の仕事で覚える書類
施工管理の仕事は、建設するための管理だけでなく工事に関わる書類作成もあります。施工管理技士が覚える書類について3つ紹介します。
工事の契約に関係する書類
工事の契約に関係する書類は主に、発注者と下請けとの間で交わされる契約内容を明記したものです。建設工事では契約内容に基づいて工事を進めるため、適切な契約はトラブルの防止にもつながります。
施工管理に関わる書類は、工事請負契約書や見積書などがあります。
工事の契約書は金額に関わる内容が多いため、記載ミスがないよう細かい部分までチェックしましょう。また、施工内容が書かれているため、施工範囲を明確にする重要な書類です。
工事の予定・計画に関係する書類
工事をする期間や、作業を進めるうえで必要な内容を記した書類を指します。高品質な建物を建造するには工事計画は必要不可欠であり、発注者や下請け会社との打ち合わせに使われる書類です。
施工管理者が作るのは施工計画書や工程表などです。施工計画書は、工事の進め方や工事期間などを具体的かつ現実的に示した書類で発注者に提出します。工程表は、下請け会社の工事期間を説明するのに使われます。
工事の記録に関係する書類
工事の記録に関係する書類は、工事の実績や品質を顧客に証明するものです。これらの書類は、施工管理者が作業の進捗を把握し、適切な工程管理を行うのにも活用されます。
工事の記録で特に重要なのが施工状況の写真です。計画した工法で工事が行われたことや建材が適切に使われたことを顧客に証明できます。施工管理者は工事写真を効率的に撮影できるよう記録書類の内容を把握しましょう。
施工管理の仕事で覚える用語
施工管理の仕事は、業務の幅が広いため覚える用語は多いです。まずは施工管理の仕事で最初に覚えておきたい用語を7つ解説します。
施工計画
施工計画は、建設工事を円滑かつ安全に進めるために必要な計画を指します。主に建設する際に必要な工事期間や施工方法などを決めます。
施工計画書
施工計画書とは、建設工事を円滑に進めるために必要な計画を全てまとめた書類のことです。施工計画書は工事の成功に欠かせない書類であり発注者に提出します。
元請け
元請けは、発注者から直接工事を請け負い、全体の管理を担う会社を指します。施工管理者はその元請けとして、工事を統括します。
下請け
下請けとは、元請けから一部の工事を受注した業者のことです。職人さんと呼ばれる専門の工事をしている方達が所属している工事会社を指します。
孫請け
孫請けとは、下請け会社が請け負った仕事をまた別の会社に依頼して請け負う会社のことです。下請け会社の人間だけでは工事期間に間に合わないなどの理由で契約する場合が多いです。
実行予算
実行予算は、実際に工事で必要だと思われる金額を算出した金額を指します。会社の利益を出しつつ効率よく工事を進めるための指標です。
KY活動
KY活動のKYとは危険予知の略語であり、現場に潜む危険を予知して対策する活動のことです。また、下請け会社と危険箇所の情報を共有して安全を確保する動きともいえます。
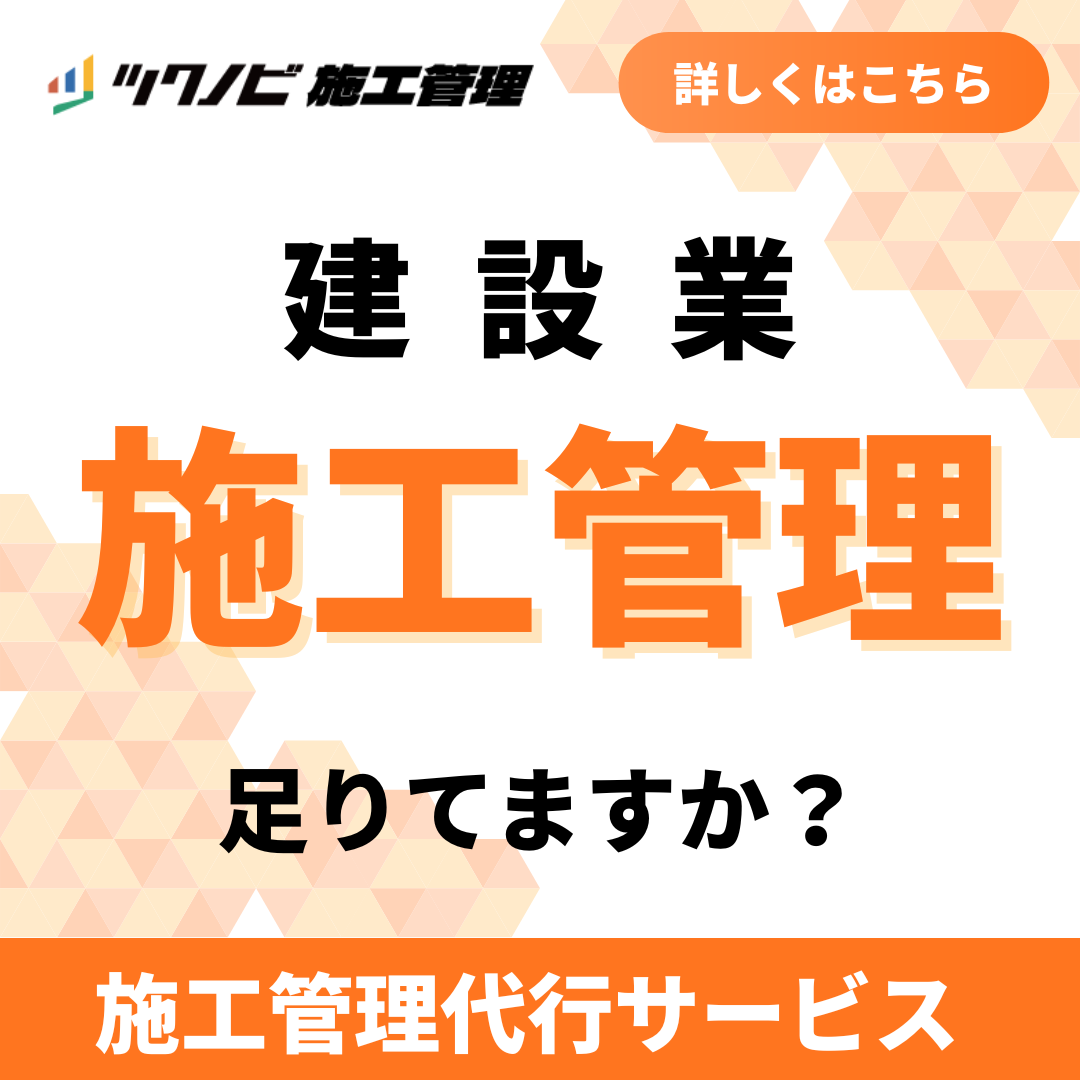
施工管理技士が仕事を覚える方法
施工管理技士の仕事を早く覚える方法を3つ紹介します。
現場をイメージする
まずは設計図面を元に、完成後の建物をイメージします。建物全体の構造を把握することで、工事の手順に間違いがないかを判断できます。
しかし、施工管理技士としての経験が浅いうちは、完成した建物を想像するのは難しいです。その場合は、先輩が設計図面を見てどのような判断をしているのかを観察し考え方を学ぶことから始めましょう。
実際の現場と設計図面を照らし合わせながら理解を深めることが、施工管理技士として成長する1歩目です。
メモなどで記録をとる
毎日の仕事内容を時系列ごとにメモなどで記録をとりましょう。あとで見返したときに「その仕事がなぜ必要なのか?」「なぜその工事手順なのか?」など客観的に考えられます。さらに、疑問点をメモしておけば、後から先輩や上司に質問する際の材料にもなります。
施工管理の主な仕事は工事の管理です。そのため、工事全体を把握する能力が求められます。メモをするときも内容だけでなく理由を考えることで、早く仕事を覚えられるでしょう。また、トラブルが発生した際にメモを見返すことで、過去の経験から適切な対応ができます。
積極的に質問する
施工管理士の仕事は専門的な知識が求められるため、分からないことは放置せず積極的に質問しましょう。知っている方に教えてもらうことで、注意すべきポイントなど具体的なことまで詳しくなります。また質問を通じて、自分では気づかなかった仕事に対する考え方を知ることができます。
質問をすることは自分と相手のことを知る絶好の機会です。施工管理士はコミュニケーション能力が必要となるため、質問する行為は目上の方とのコミュニケーションの練習にもなるでしょう。さらに、現場の作業員と積極的に会話することで、現場の状況を正確に把握できます。
施工管理技士が覚えること以外に求められるスキル
施工管理技士が仕事で覚えること以外に求められるスキルを紹介します。
コミュニケーションスキル
施工管理技士は、発注者や作業員など様々な方達とコミュニケーションをして仕事を進めます。相手とのコミュニケーションが上手くいかないと、事故や工事のやり直しだけでなく発注者との交渉トラブルにもつながります。
先輩がどのようなコミュニケーションをしているのか、理由を考えながら参考にしていきましょう。
リーダーシップスキル
施工管理技士は、工事全体を把握し、作業員をまとめるため適切な指示を出す役割を担っています。作業員をまとめるには、リーダーシップスキルは不可欠です。
しかし、初めからリーダーシップスキルを備えている人は多くありません。まずは自分が従いたいと思う理想のリーダーを思い浮かべ、そのリーダーはどういった行動をするのかを考えてみましょう。もし失敗しても、明確な理由を持って行動したので、すぐに改善につなげ成長できます。
臨機応変に対応するスキル
建設現場では、資材が予定時間に到着しないなどの予期せぬトラブルが発生します。こうしたトラブルを解決し被害を最小限に抑えるには、臨機応変に対応するスキルが求められます。
トラブルが発生した際は、まず現状を正しく把握し冷静に対処しましょう。適切な対応は、2次的なトラブルを防ぎ工事は円滑に進みます。こうした経験を積み重ねることで、ベテランの施工管理技士へと成長していきます。
施工管理の人手不足を解消したいならツクノビ施工管理がおすすめ
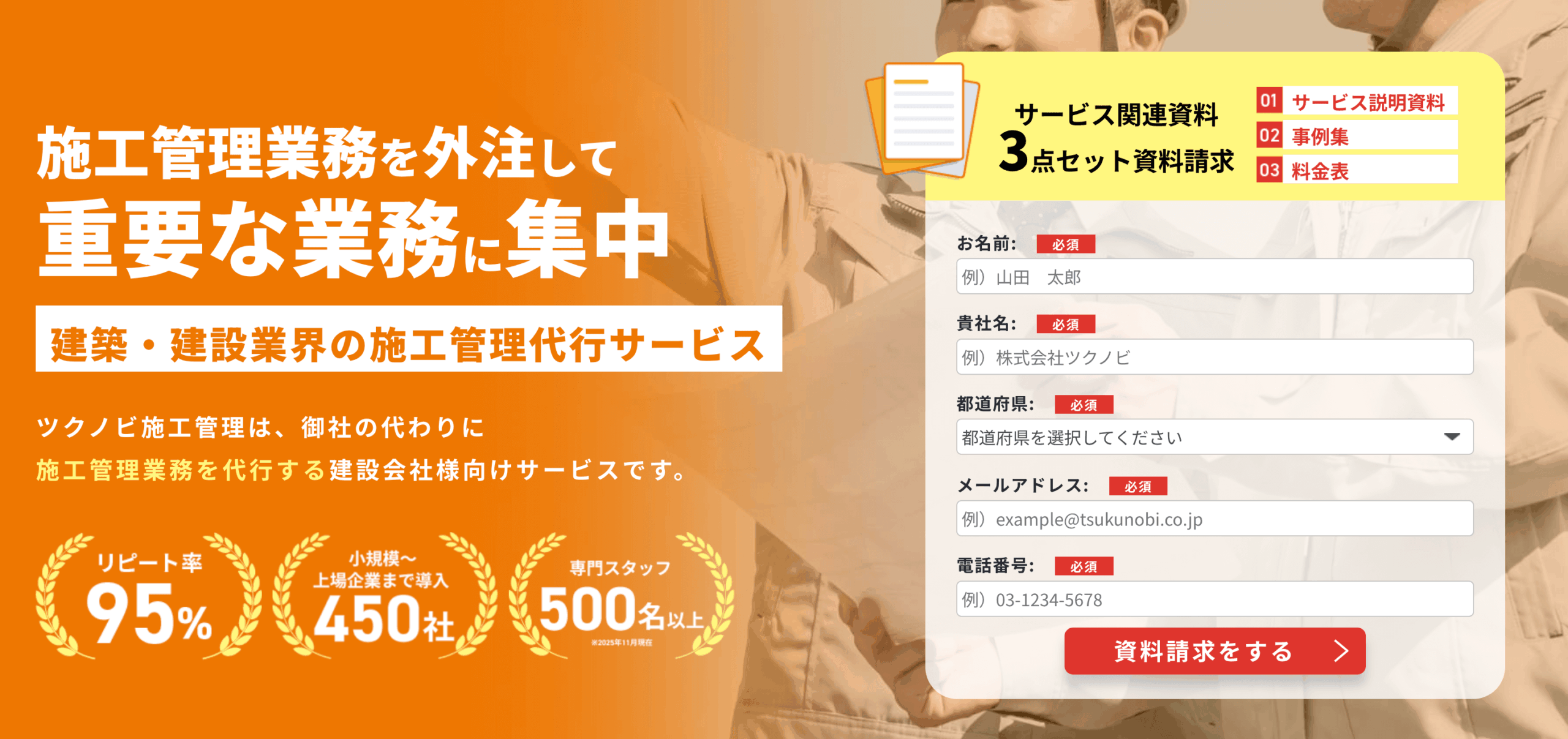
施工管理の人手不足で業務がスムーズに進まない場合や、施工管理人材を確保したい場合は、建設業特化の業務代行サービス「ツクノビ施工管理」の利用がおすすめです。
「ツクノビ施工管理」では、施工管理の経験が豊富なプロ人材が御社の業務を代行いたします。施工管理のリソースがひっ迫している場合や、業務に対応できる人材が不足している場合、施工管理人材の採用、教育のコストをかけられない場合などは、アウトソーシングサービスを活用すると、少ない工数で業務を実行できます。
施工管理業務の人手不足を解消したい方はぜひこちらからお問い合わせください。
ー【まとめ】施工管理の仕事で覚えることは広範囲に渡る!1つずつ確実に覚えよう
施工管理士が初めに覚えることは、管理するべき内容とその理由です。仕事の意義を知ることで、理解度が深まり広範囲の業務を覚えられるでしょう。
しかし、施工管理の仕事は覚えることが多いので、成長を実感できるまで時間がかかります。成果が見えてなくても焦らず、1つずつ確実に仕事を覚えることが大切です。継続的に知識を身に付けることで、自信をもって仕事ができるようになるでしょう。
施工管理技士の難易度や2級建築施工管理技士の難易度・施工管理の勉強アプリおすすめ15選についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
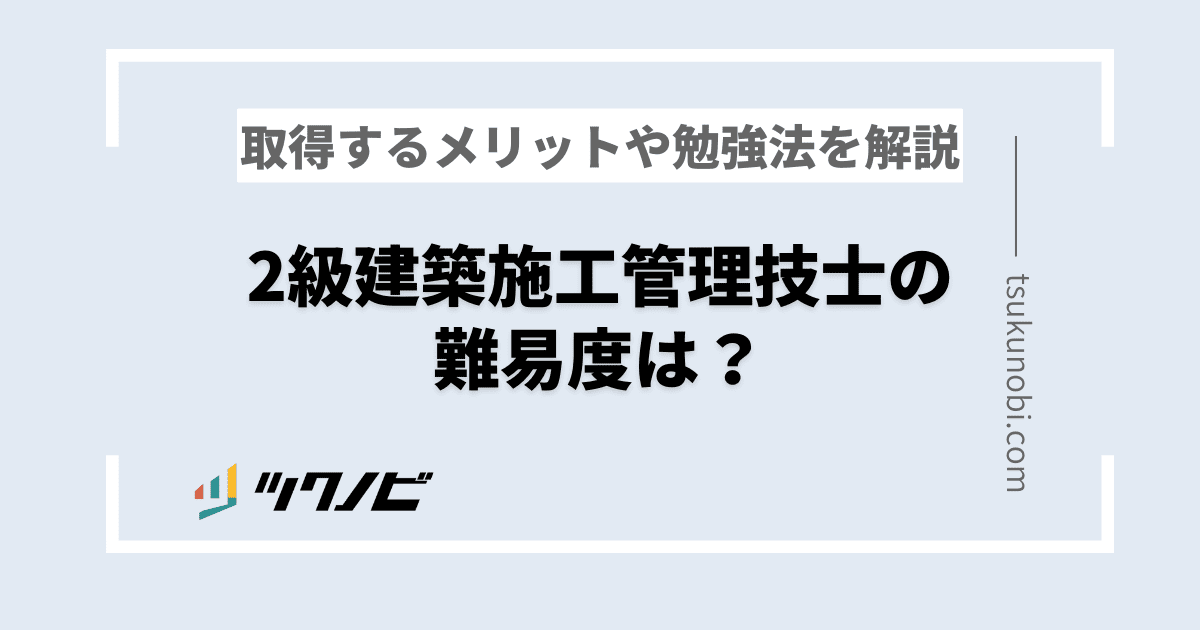 2級建築施工管理技士の難易度は?取得するメリットや勉強法を解説
2級建築施工管理技士の難易度は?取得するメリットや勉強法を解説
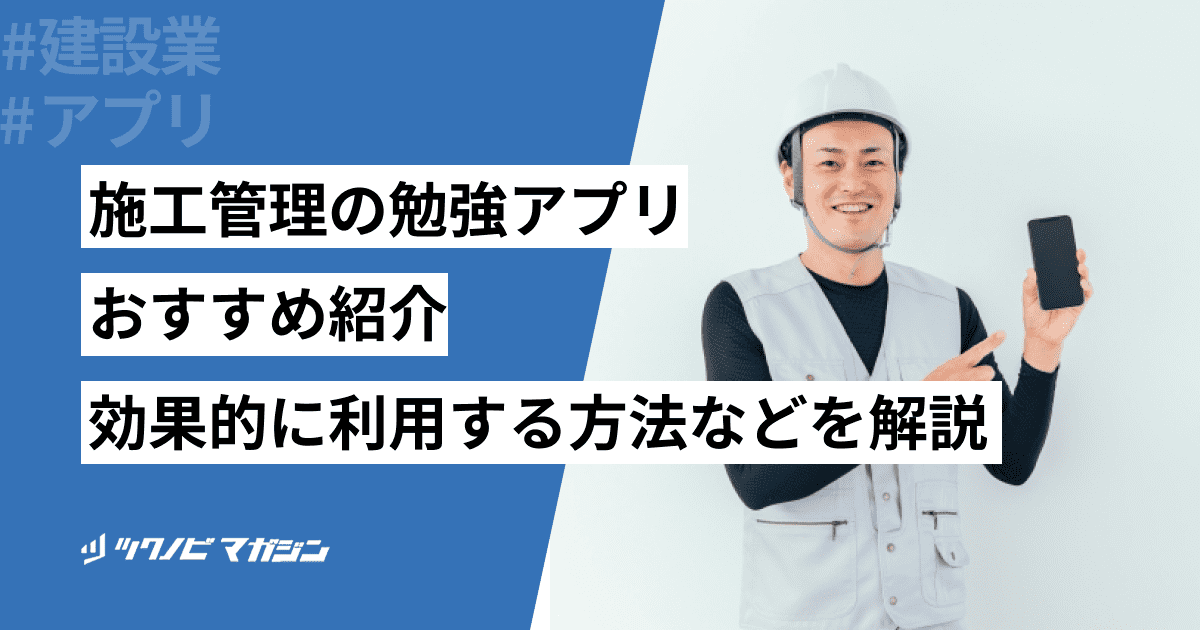 施工管理の勉強アプリおすすめ15選!効果的に利用する方法などを解説
施工管理の勉強アプリおすすめ15選!効果的に利用する方法などを解説