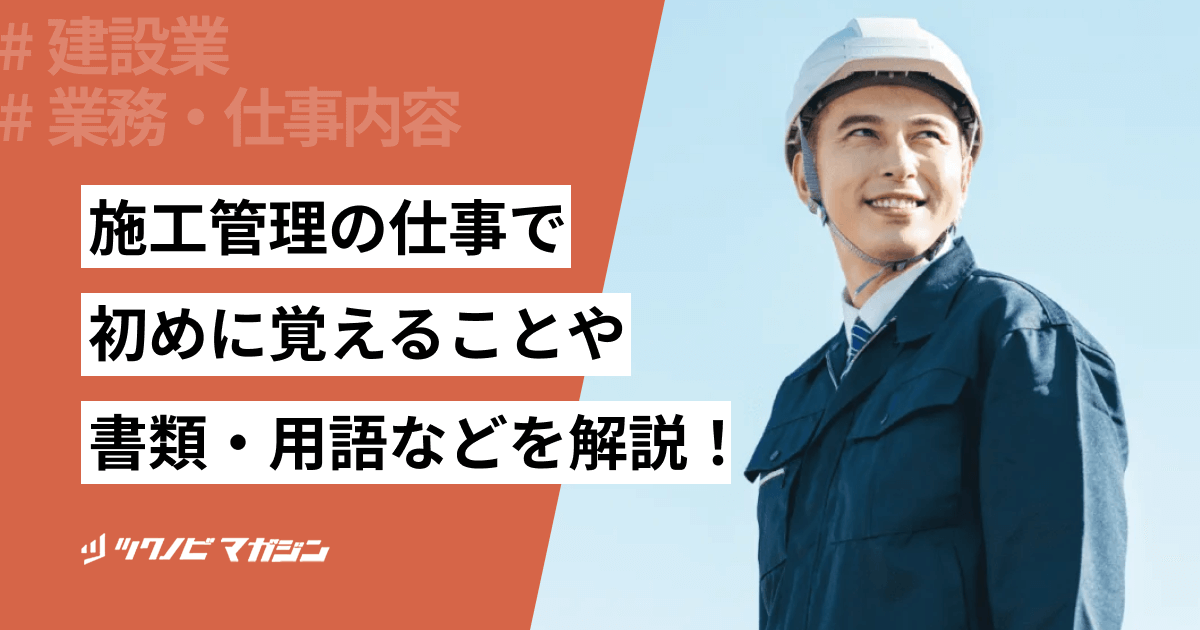※記事内に広告を含みます
解体工事の施工管理とは、建物を安全に壊す際に計画から完了までの工程を管理する仕事のことです。
- 解体工事の施工管理とは?
- 解体工事施工技士の資格をとるには?
- 解体工事施工技士の注意点は?
このような疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか?
この記事では、解体工事の施工管理の仕事について詳しく解説します。また、解体工事施工技士の資格についても紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
解体工事の施工管理とは
解体工事の施工管理の概要と仕事内容について紹介します。
解体工事の施工管理の概要
解体工事の施工管理とは、建物を安全に壊す際に計画から完了までの工程を管理する仕事のことです。解体工事の施工管理をするには、解体工事施工技士の資格が必要です。
解体工事施工技士とは、500万円未満の解体工事を行うための解体工事業の登録や技術管理者になるために必要な資格のことです。
近年では、建物の老朽化や再開発に伴う解体工事の依頼が増えているため、需要が高い職種となっています。
解体工事施工技士の仕事内容
解体工事施工技士の仕事内容は、主に以下のとおりです。
- 解体する建物の現場調査
- 解体工事の見積書作成
- 解体工事の施工管理
- 周辺の環境対策
- 廃棄物処理対策
建物を解体する全ての工程に関わるだけでなく、環境面も考慮する仕事です。
解体工事の施工管理に必要な資格が作られた背景
解体工事の施工管理に必要な資格が作られた背景には、日本の建物の寿命が関わっています。日本の建物の寿命は30年から50年といわれており、高度経済成長期に建てられた建物の多くが寿命を迎えています。
しかし、高度経済成長期の建物には、現在では人体に影響があるため使用が禁止されている建材が使われていることがあります。周辺住民への環境面の配慮から解体する際にも専門的な知識を必要とするようになり、解体に必要な専門的な知識を有している証明として、解体工事施工技士の資格が作られました。
解体工事の施工管理に必要な資格を取得するメリット
解体工事の施工管理に必要な資格を取得するメリットを2つ紹介します。
昇進や転職する際に役立つ
解体工事施工技士は、解体工事をする際に必要な知識を有している証明になるため昇進や転職する際に役立つでしょう。解体工事を管理できる人材は希少であり、企業は有望な人材を求めています。
解体工事施工技士の試験に合格するには、長時間の勉強は必須です。企業は資格取得者をスキルアップに前向きな人材と判断するため、昇進させたり採用基準の1つにしたりするでしょう。
活躍できる場所が広がる
インバウンドの需要が高まり外国人観光客を誘致するため再開発する動きが各地で進んでいます。再開発するには既存の建物を解体する必要があるため、解体工事施工技士の活躍できる場所は今後ますます広がるでしょう。また、高度経済成長期に建てられた建物は寿命を迎えており、解体する建物はこれからもっと増えていきます。
解体工事を管理できる解体工事施工技士の資格保有者の需要は高まり、長期に働ける職種といえるでしょう。
解体工事施工技士の資格試験の概要
解体工事施工技士の資格を取得するための試験について解説します。
受検資格
解体工事施工技士を取得するには、学歴と職務経験によって受験資格が異なります。
- 大学(指定学科を卒業した者) 卒業後1年以上の実務経験
- 大学(指定学科以外を卒業した者) 卒業後1年6カ月以上の実務経験
- 短期大学、高等専門学校、専門学校(2年制) 指定学科を卒業した者 卒業後2年以上の実務経験
- 短期大学、高等専門学校、専門学校(2年制) 指定学科以外を卒業した者 卒業後3年以上の実務経験
- 高等学校、中等教育学校、専門学校(1年制) 指定学科を卒業した者 卒業後3年以上の実務経験
- 高等学校、中等教育学校、専門学校(1年制) 指定学科以外を卒業した者 卒業後4年6カ月以上の実務経験
- 上記以外の者 8年以上の実務経験
指定学科は、施工技術検定規則に規定されています。また、実務経験は解体工事に関わるものだけに限ります。
試験内容
解体工事施工技士の試験内容は、四肢択一式(50問)試験時間90分と記述式(5問)試験時間120分の構成です。
四肢択一式の問題は、解体工事に関する基礎から工事の管理など基本から応用まで広い範囲から出題されます。
記述式の問題は、解体工事の施工計画など実務に近い内容が出題されます。
申込方法
解体工事施工技士の試験に申し込むには、一次申請と二次申請を行います。
一次申請は、パソコンからインターネット上で必要な情報を入力し、支払いの手続きをします。
二次申請は、一次申請で入力した情報を印刷して、写真の貼付と必要な書類を添付して郵送します。
一次申請はスマートフォンからの入力には対応していません。また、添付する書類には解体工事の実務経験を証明する書類と経験年数によっては卒業証明書が必要です。
受験料
受験料は税込16500円ですが、支払い方法によっては手数料がかかります。
- インターネット申込 16,500円<クレジット決済>
- インターネット申込 17,000円<コンビニ決済>
コンビニ決済は手数料で500円支払います。
合格率・難易度
令和6年に実施した試験の合格率は全国平均で63.5%であり、令和5年の合格率は56.2%です。合格率は50%を超えていますが、出題範囲は広いため簡単に取得できる資格ではありません。合格を目指して、無理なく計画的に勉強していきましょう。
解体工事施工技士の注意点
解体工事施工技士の注意点は、500万円以上の解体工事を受注できないことです。500万円を超える解体工事を請け負う際は、建設業許可を取得する必要があります。
解体工事施工技士は、500万円未満の解体工事の技術管理者になれる資格です。解体工事の金額が500万円以上の工事は受注しないようにしましょう。違反した場合は罰則が科されます。
施工管理で年収を上げるならツクノビワークがおすすめ
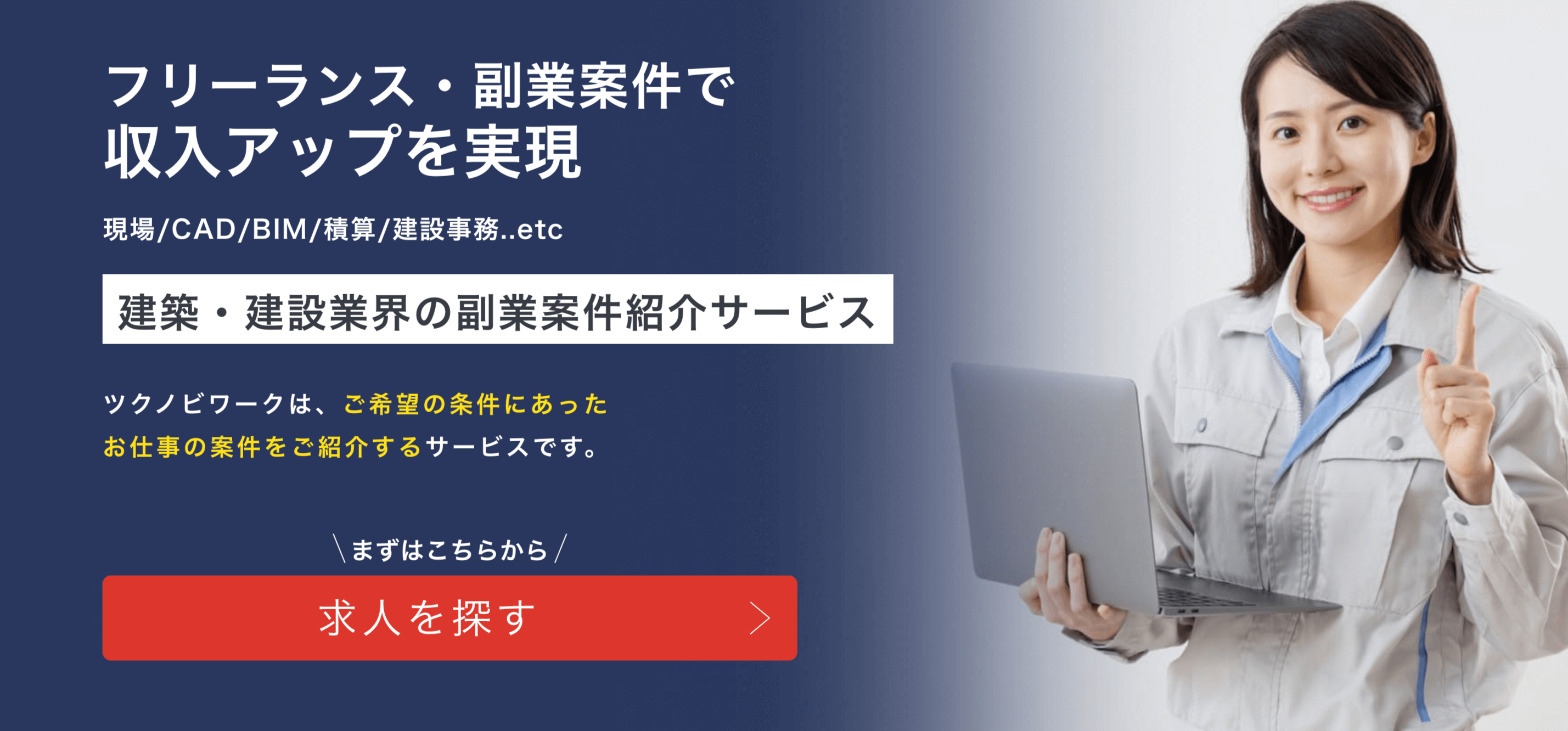
施工管理で年収を上げたい方には、建設業特化のフリーランス・副業案件マッチングサービス「ツクノビワーク」の活用がおすすめです。
様々な条件の案件を取り揃えているため、希望に合った案件を紹介可能です。週1~5日の施工管理案件の中から希望の案件をマッチングいたします。大手企業の案件から、即ご活躍いただける中小の企業まで、幅広い案件をご用意しています。
スキマ時間で稼ぎたい方や年収を上げたい方はぜひこちらから詳細をご確認ください。
【まとめ】解体工事の施工管理に必要な資格を取得しキャリアアップを目指そう!
解体工事の施工管理とは、建物を安全に壊す際に計画から完了までの工程を管理する仕事のことです。解体工事は再開発や建物の老朽化により需要が高まっており、解体工事施工技士の資格保有者は重宝されるでしょう。
建設工事だけでなく解体工事の知識を保有している人材は業界でも貴重な存在です。自身のキャリアアップを目指すなら解体工事施工技士の資格を取得しましょう。
空調設備施工管理士の仕事内容や施工管理からの転職におすすめ異業種10選についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
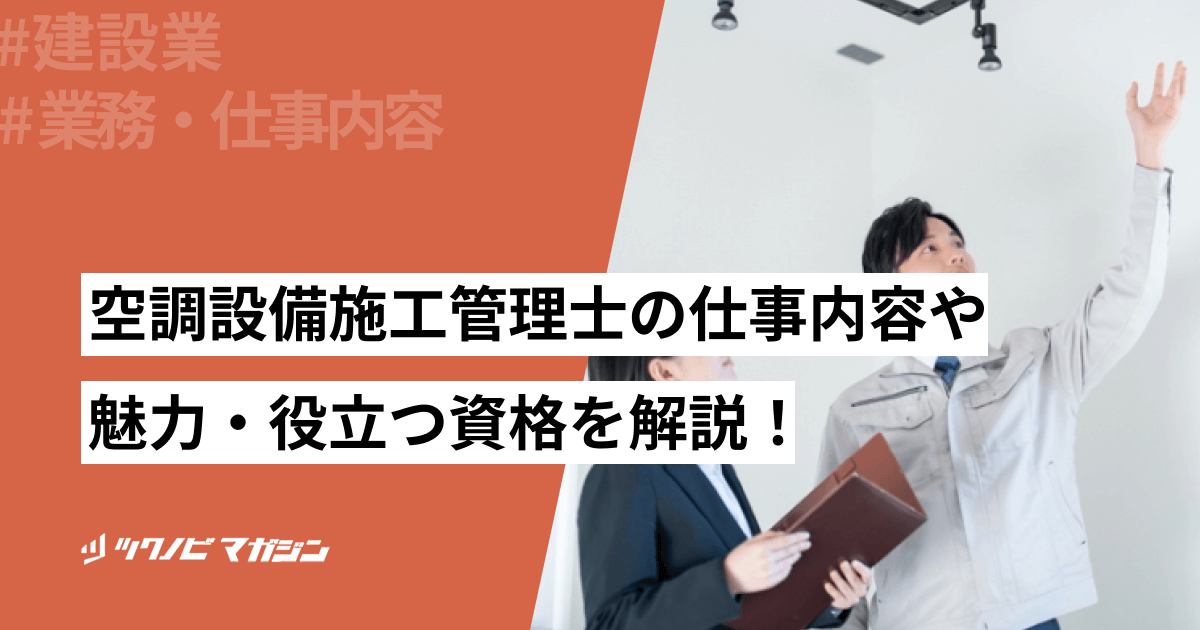 空調設備施工管理士の仕事内容や魅力・役立つ資格などを解説!
空調設備施工管理士の仕事内容や魅力・役立つ資格などを解説!
 施工管理からの転職におすすめ異業種10選!役立つスキルも解説
施工管理からの転職におすすめ異業種10選!役立つスキルも解説