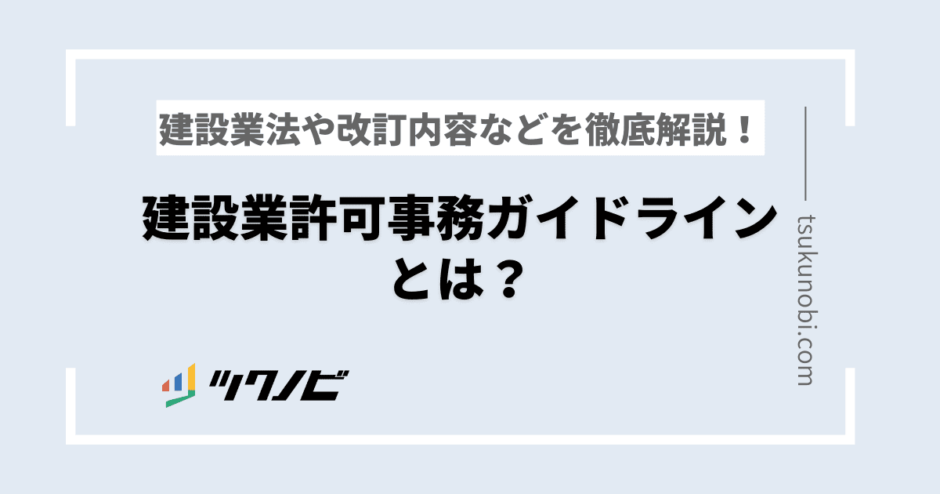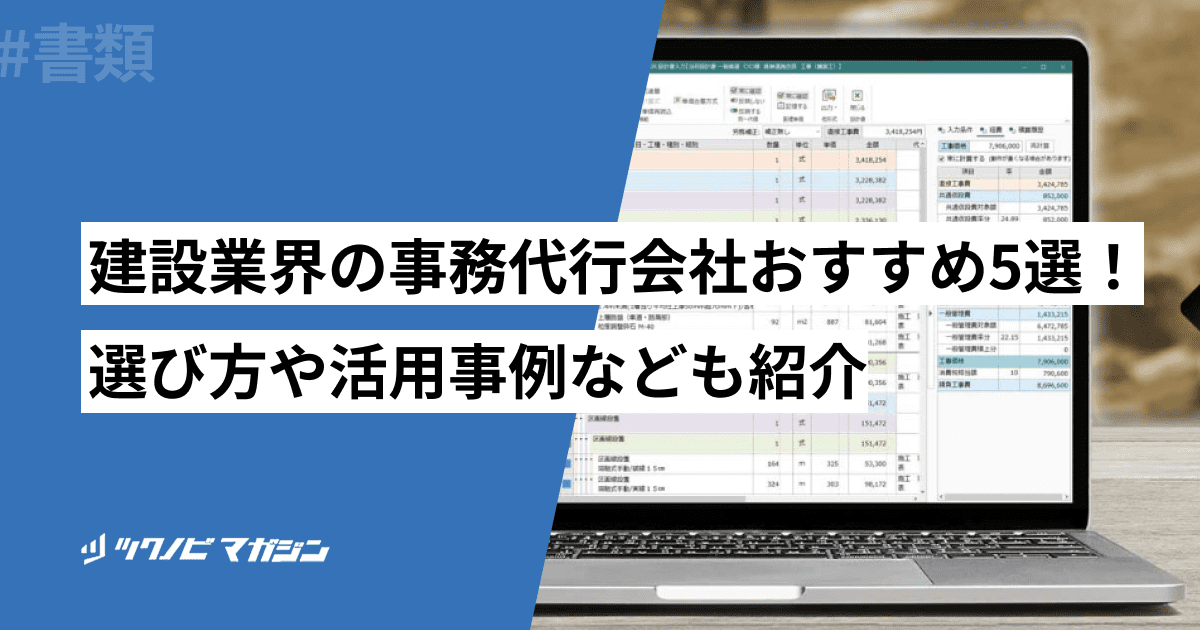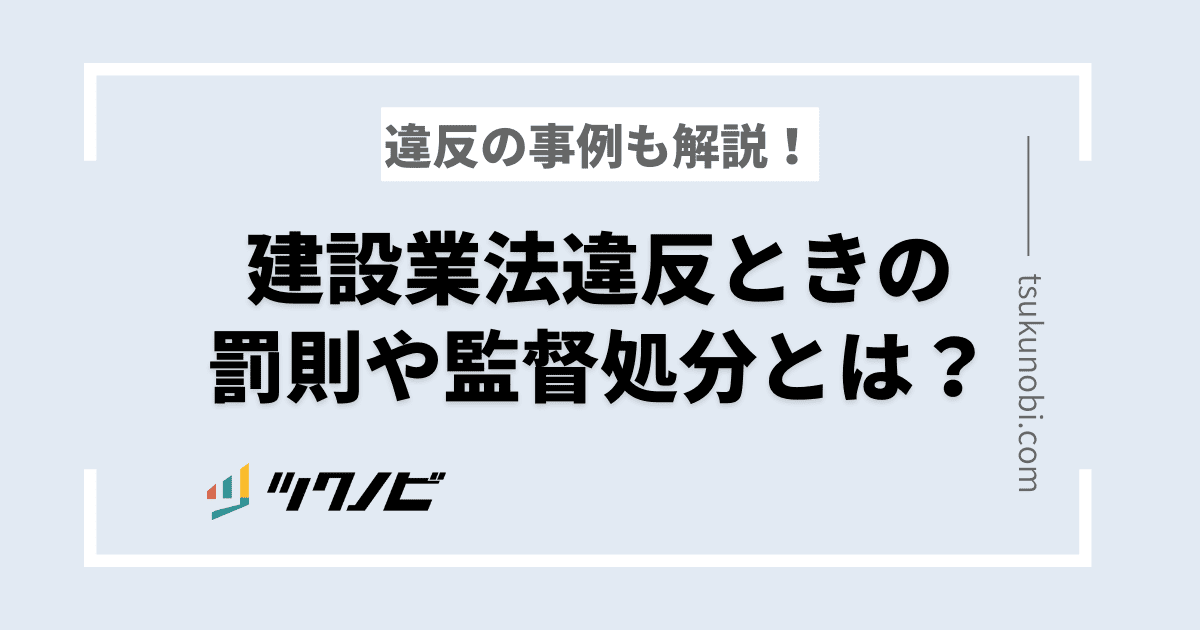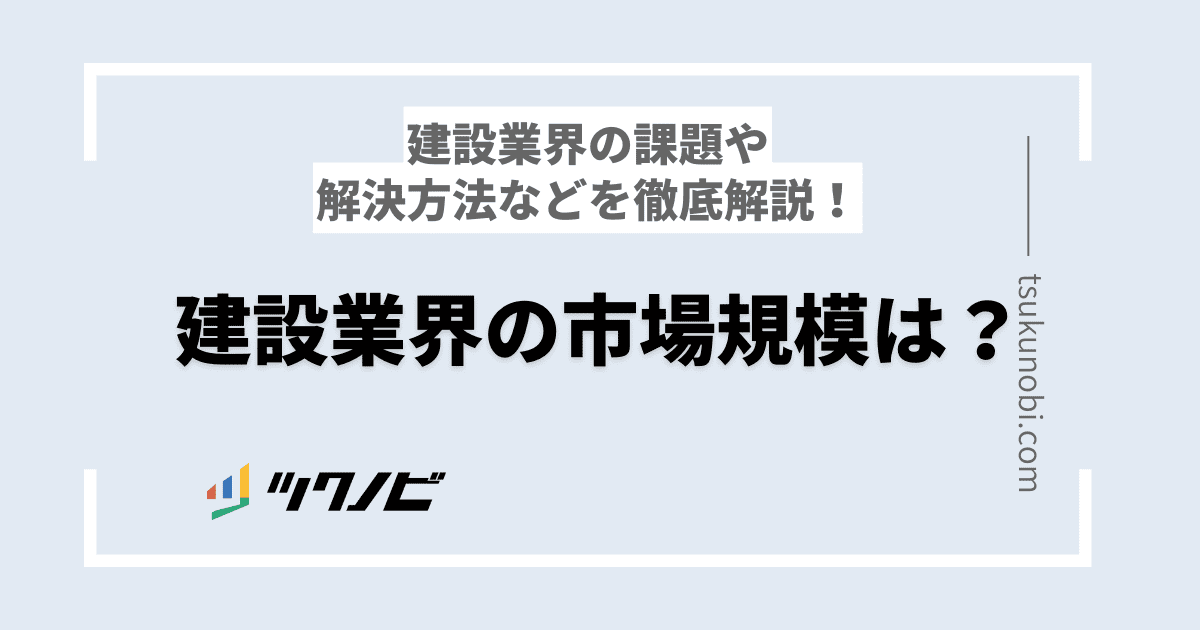※記事内に広告を含みます
建設業を開業し、運営するうえで欠かせないのが「建設業許可事務ガイドライン」。建設業に関わる法律の内容が記載されています。とはいえ、どういうものかいまいちピンとこない方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、そんな方のためにガイドラインに記載されている内容を解説します。
ツクノビ事務は、建設業の事務業務をプロが代行する建設業特化のアウトソーシングサービスです。
事務作業や書類作成を採用倍率200倍を通過した専門スタッフが代行いたします。現場での事務業務にかかる時間を90%削減し、受注できる案件の増加や退職率の低下につながった事例もあります。詳細はぜひこちらからご確認ください。
建設業許可事務ガイドラインとは?
建設業許可事務ガイドラインとは、許可事務についてのガイドラインです。建設業許可取得にあたってぜひ確認していただきたい資料です。
建設業は、建設業法や建設業法施行規則など、さまざまな法令に従って判断されます。法令を守りながら手続きをするには、専用の知識が必要です。建設業許可事務ガイドラインには、これらの法律を守りながら手続きするための方法が記載されています。
ガイドラインは法の改定などにより内容が変化するため、ただ資料を手元において作業すればよいものではありません。必要に応じて新しい内容を入手し、理解したうえで手続きを行うことが大切です。
建設業許可事務ガイドラインの使い方
建設業許可事務ガイドラインがどのようなものか分かっても、実際の業務での使い道が分からない方もいらっしゃるでしょう。業務上では、申請書や必要書類の確認や不明点をチェックするために使われます。
自社が行う工事や施工に関する手続きをする際、ガイドラインを確認に記載されたポイントをチェックしながら作業を進めます。
なお、建設業においてチェックすべきガイドラインは、建設業許可事務ガイドラインだけではありません。このほかのガイドラインも同様に確認しておく必要があります。
どれも法律の改定に合わせて作り直されるため、この内容をチェックするためにも使われます。
建設業許可事務ガイドラインの改訂内容
建設業許可事務ガイドラインに掲載されている内容は、実に膨大です。不備なく手続きを行うには、最近改定されたものをピックアップして覚えておく必要があります。次は、最近改定されたものの内容をそれぞれ解説します。
建設業許可の「経営事務の管理責任者」に関する内容
許可を受けるためには経営事務の管理責任者が必要ですが、この管理責任者になるための要件が変更されました。従来の条件を撤廃したため、新たに管理責任者を指定するには、以下の条件を満たさなくてはなりません。
| 条件 | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 適正な経営能力を有し、右記の条件を満たしている | 常勤役員のうち1名が以下いずれかに該当する |
|
| 常勤役員などのうち1名右記の条件を満たすものがいる | 建設業の財務管理・労務管理または業務管理のいずれかを建設業の役員などやその次の地位で5年以上の経験を有する者 | |
| 上記の条件を満たしたうえで、右記条件に該当する直接補佐するものをそれぞれ直接補佐として配置している |
|
|
| 社会保険に加入している | 社会保険並びに労働保険などに適切な加入を行っている |
従来は許可を受けたい業種により必要な経験年数が決まっていましたが、これが廃止され上記の新しい要件に変更されました。また、大きな変更点として、社会保険や労働保険の加入が加えられています。
認可手続きの新設
相続や事業譲渡は、法人・個人事業主に関わらず発生します。建設業も例外ではありません。しかし、これまでは許可までの引継ぎはできないため、新たに申請を取得する必要がありました。
改定により、事業継承や相続で建設業許可も引継ぎができるようになりました。方法は承継方法により異なるため、引継ぎ業務を行う際は注意しましょう。
| 引継ぎの内容 | 手続き方法 |
|---|---|
| 事業譲渡・合併・分割による承継 | 元の事業主と引受先事業主が許可行政庁へ事前に許可申請を行う
申請が下りたら各承継の効力が発揮する日において許可を受けた地位が承継される |
| 相続による承継 | 建設業者の死亡により相続が発生した日から30日以内に相続人による認可申請が必要になる
この期間内の認可申請日から認可が下りる日までは相続人に対して許可をしたこととみなす |
なお、承継による許可は手続きを行った日から起算して5年間が有効期限です。承継方法により違いはありません。
テレワークの常勤対応
常勤役員・専任技術者・令3条使用人は、今まで本店または営業所に出社しないと常勤として認められませんでした。しかし、働き方やライフスタイルの変化を受けた影響から、条件を満たせばテレワークでも常勤扱いになるよう改定されました。条件は以下のような環境が求められます。
テレワークの定義は以下の定義とされています。
営業所等の勤務を要する場所以外の場所で、ICTの活用により、営業所等で職務に従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ、当該所定の時間中において常時連絡を取ることが可能な環境下においてその職務に従事することをいう。
建設業許可事務ガイドラインを見るときのポイント
建設業許可事務ガイドラインは、法律に基づいて作成された資料です。チェックする際は、ただ見るだけでなく建設業法もあわせてチェックしなくてはなりません。ガイドラインを見るときのポイントを、建設業法ごとに解説します。
建設業法「第2条」
建設工事は、工事の内容・必要とする知識や技術に応じて工事の種類が決められています。建設許可を得るには、種類に応じた許可の申請が必要です。
許可申請を提出するときは、施工に必要な許可はどれか把握したうえで手続きを進めましょう。許可は複数取得できるため、業務に必要なものを取得してください。
建設業法「第3条」
建設業許可について記載されています。それぞれのポイントを以下の表にまとめたので、チェックしておきましょう。
| チェックポイント | 内容 |
|---|---|
| 許可者について | 許可者は国土交通大臣もしくは都道府県知事の許可に分かれる
|
| 建設業許可について | 建築業許可は第2条の工事の業種ごとに、以下のどちらかの区分の許可を受けなければいけない
※発注者から直接請け負う工事については、一般・特定に関わらず請負金額の制限はありません。 |
| 更新について | 建設許可の有効期限は許可があった日から5年間であり、更新申請の提出期限は有効期限の30日前となっているので注意しましょう。 |
一般建設業と特定建設業の違いについてはこちらの記事で詳しく紹介しておりますので合わせてご確認ください。
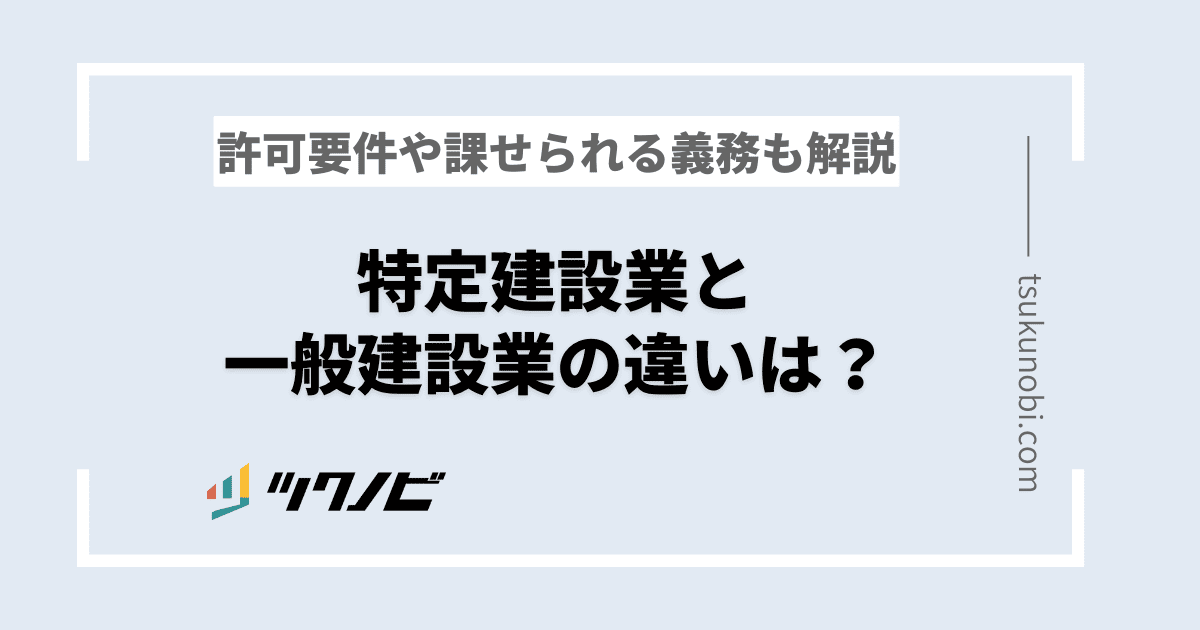 特定建設業と一般建設業の違いは?許可要件や課せられる義務も解説
特定建設業と一般建設業の違いは?許可要件や課せられる義務も解説
建設業法「第4条」
建設業法「第4条」では、許可を受けた業種の工事を請け負う場合、その工事に附帯する他業種の工事も請け負うことができるという内容を記載しています。
「附帯工事」とは主たる建設工事を完成させるために発生するものであるため、附帯工事のみ独立して発生することはありません。具体例としては、外壁工事において、塗装工事が必要となった場合、その塗装工事は「附帯工事」として認められます。
建設業法「第5条・第6条」
建設業法第5条では、国土交通省令が定める建設業許可の申請書に必要な事項を規定しています。申請書に添付する書類については、第6条が規定しているため、忘れずにチェックしておきましょう。
許可申請を申請者が取り下げしたい場合、許可申請取り下げ願書を提出しなくてはなりません。願書のフォーマットは任意書式です。申請先の国土交通省や各都道府県に問い合わせしましょう。
願書は郵送などを受け付けていない場合もあります。フォーマットだけでなく提出方法も忘れずに調べてください。なお、取り下げる申請にかかった手数料などは戻りません。この点にも注意が必要です。
まれに、申請しても建設業許可が下りない場合があります。この場合も申請者に通知が行くため、受取記録が残る形になります。不服の場合はそれぞれ以下の期限内であれば、請求や訴訟が可能です。
- 通知到着日翌日から3か月以内:国土交通大臣に審査請求
- 到着した日の翌日から6か月以内:国を被告として取消訴求
どちらの場合も、正当な理由がある場合は実施できません。そのため、めったに使われることはないでしょう。
建設業法「第7条」
建築業許可は、申請すればだれでも取れるわけではありません。許可を得るには、以下の条件を満たす必要があります。
- 経営業務管理責任者が1名以上いること
- 各営業所に条件に該当する専任技術者が配置されていること
- 法人の場合はその法人の役員などが、個人の場合は申請者などが請負契約において不正や不誠実な行為を行う恐れがない者
- 請負契約を履行するために必要な財産的基盤もしくは金銭的信用を有している者(一般建設業と特定建設業で条件が異なる)
許可申請をする前に、上記の条件をきちんと満たしているか確認してから作業に移りましょう。
建設業法「第8条」
建設業許可は、第7条の条件を満たしていても、欠格事由に該当する場合は許可が下りません。事由は14項目あります。国土交通省ウェブサイトで確認できるため、第7条と合わせて確認しておきましょう。
建設業許可の欠格要件についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
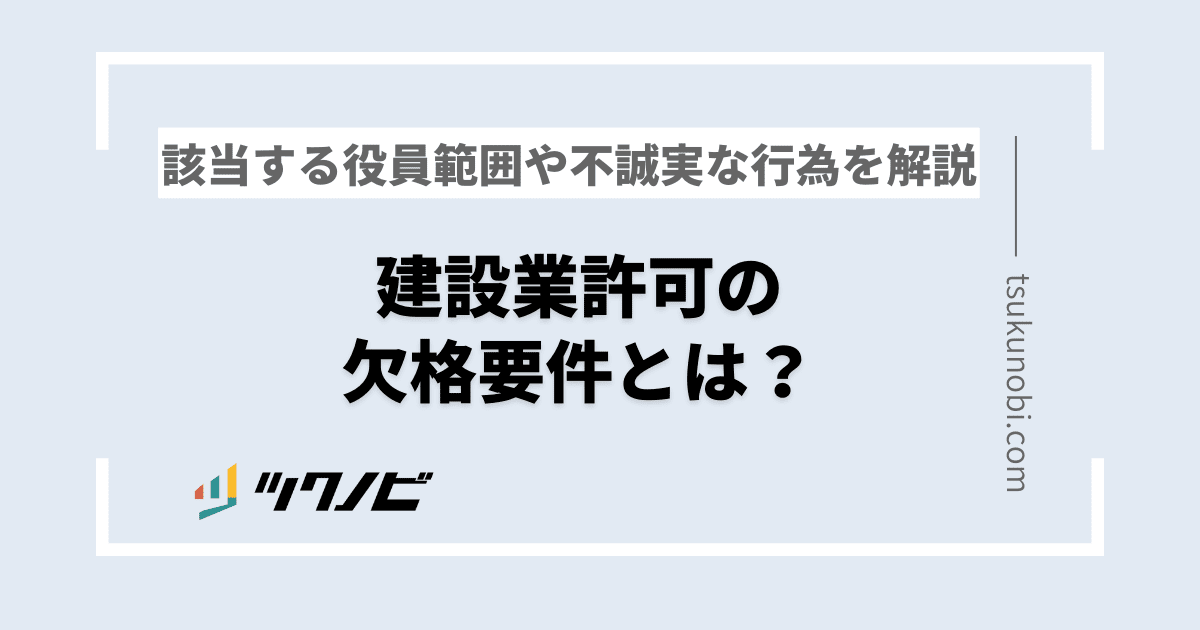 建設業許可の欠格要件とは?該当する役員範囲や不誠実な行為を解説
建設業許可の欠格要件とは?該当する役員範囲や不誠実な行為を解説
建設業法「第9条」
すでに受けていた建設業許可を変更しなくてはならない場合に関する内容が記載されています。許可換えが必要になる内容は、以下の通りです。
- 国土交通大臣許可を受けた業者の営業所がひとつの都道府県になった場合:都道府県知事許可に変更
- 都道府県知事許可を受けた業者の営業所がふたつ以上の都道府県になった場合:国土交通大臣許可に変更
- 都道府県知事許可を受けった業者の営業所が異なる都道府県に移った場合:移転先の都道府県知事の許可に変更
営業所の設置や移転の際は、許可申請の変更が必要か調べておきましょう。また、許可変更が必要な場合、忘れず手続きしてください。
建設業法「第10条・第11条」
建設業許可申請には、登録免許税もしくは許可手数料のいずれかを納めなくてはなりません。書類だけでなく、税や手数料を支払う費用も忘れずに用意しましょう。
また、許可申請書や添付書類に変更があった場合、許可申請行政庁に変更届を提出しなくてはなりません。変更事由により提出期限が異なります。早いものだと2週間以内で手続きする必要があるため、少しでも変化があった場合は必要な手続きやその期間を調べておきましょう。
建設業法「第12条」
第12条には廃業に関する内容が記載されています。以下の状態に該当する場合は、廃業届を提出しましょう。
- 許可を受けた法人または個人がいなくなる場合
- 許可を受けた業種について廃業する場合
それぞれ手続きが異なるため、混同しないように注意してください。廃業する際は、どちらに該当するか調べたうえで手続きに取りかかりましょう。
【まとめ】建設業許可事務ガイドラインは建設業許可に必要なマニュアル!
建設業許可事務ガイドラインは、業務を開始し、運営していくうえで必要な情報が記載されています。こまめに確認し、改定があれば新しい内容を入手しておきましょう。ガイドラインが必要なときにすぐ取り出せるよう、分かりやすいところに収納しておくことも大切です。
建設業許可申請の流れに建設業でおすすめの事務代行会社についてはこの記事でより詳しく解説しています。
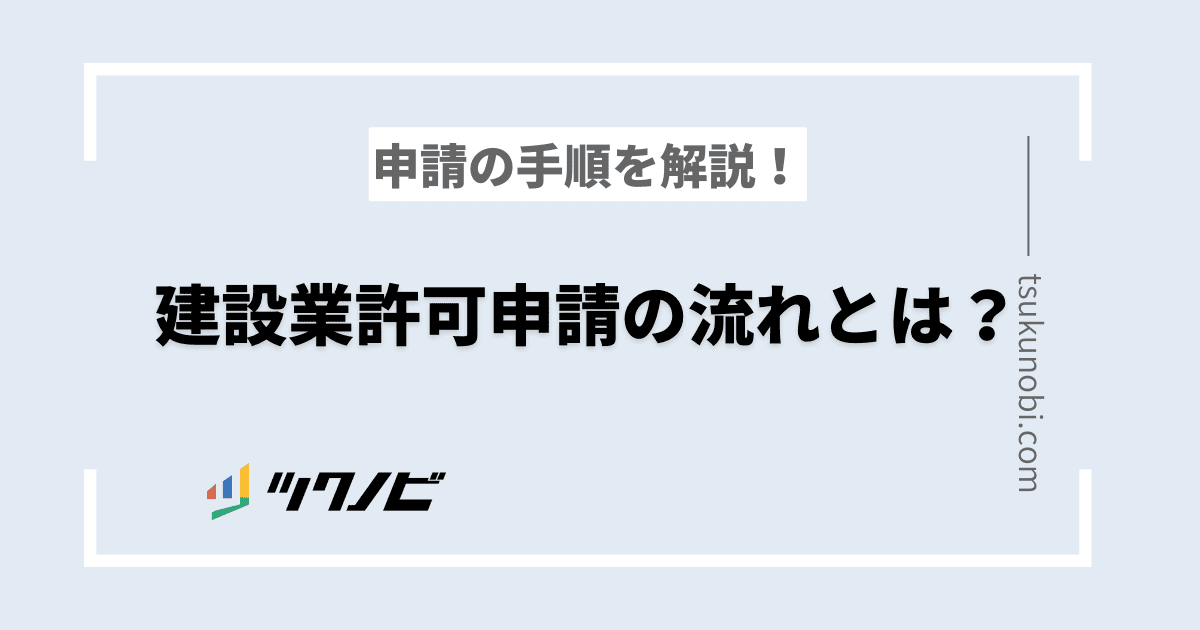 建設業許可申請の流れとは?必要な理由や申請の手順を完全解説!
建設業許可申請の流れとは?必要な理由や申請の手順を完全解説!
※弊社の営業代行サービスツクノビセールスは、
【効果が出なければ全額返金プラン】を新たにスタートさせました!  ※詳しくは👆👆👆のバナーをクリック!!
※詳しくは👆👆👆のバナーをクリック!!