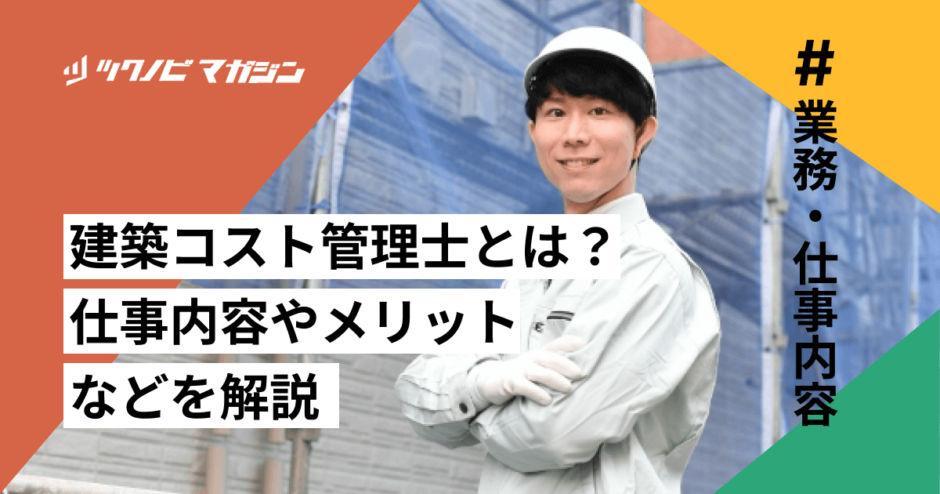※記事内に広告を含みます
建築プロジェクト全体のコストマネジメントができる人材は、多くの企業で求められています。建築コスト管理士は、建築物の構想から保全、解体まで考慮してコストを管理する専門資格です。
積算だけでなく発注・調達戦略、環境配慮、ITなどの幅広い知識が求められる建築コスト管理士の資格取得には、労力がかかりますが多くのメリットがあります。本記事では、建築コスト管理士の仕事内容、試験の概要、資格を取得するメリットなどを解説します。
建築コスト管理士とは
建築コスト管理士は、建築のプロジェクト全体のコスト管理を担う専門資格です。公益社団法人日本建築積算協会が試験を実施し、資格を認定します。同じく公益社団法人日本建築積算協会が認定する建築積算士よりも、幅広い知識が求められます。
建築コスト管理士の資格を取得することで、重要なプロジェクト管理の業務に就けるでしょう。建築コスト管理士について以下の項目ごとに解説します。
- 建築コスト管理士の資格が生まれた理由
- 仕事内容
- 求められる知識
- 建築積算士との違い
建築コスト管理士の資格が生まれた理由
1980年代頃から、積算業務だけでコストを算出することが問題視されてきました。適正なコストを導き出すために、1990年代頃から総合建設会社で組織的なコスト管理が進められます。徐々に設計の初期段階からコストを管理することの重要性が広まり、新しい資格の創設が検討されました。
検討の結果、2005年に建築コスト管理士認定事業が創設されました。近年は、毎年200人以上が建築コスト管理士資格の受験をしています。
仕事内容
建築に関わるコストを総合的に管理することが建築コスト管理士の主な業務内容です。建築コスト管理士は、企画や構想といった初期段階から、完成後の維持や保全、解体まで考慮してコストを算出します。環境や法令に配慮することも必要です。
また、場合によっては、算出したコストを発注者や設計者などの関係者に報告することも求められます。算出コストの内訳だけでなく、根拠、透明性、確実性なども説明できるように準備しなければなりません。
求められる知識
建築コスト管理士に求められる知識は多岐に渡ります。建築業特有の積算の知識だけでなく、分析手法、受発注、調達、LCC(ライフサイクルコスト)、建築に関わる法律などの知識も必要です。
場合によっては、環境やITに関する知識も求められるでしょう。また、知識を身に付けるために情報を収集し、コスト管理に適切に落とし込む能力が求められます。様々な分野の知識が必要であるため、実務経験を積みながら勉強することが大切です。
建築積算士との違い
建築コスト管理士と建築積算士のどちらも、資格を認定している団体は公益社団法人日本建築積算協会です。建築積算士も、建築コスト管理士と同様に、積算業務をします。
ただし、建築積算士は建築過程の積算を担当する一方で、建築コスト管理士は企画・構想〜維持・保全のライフサイクル全体のコストを管理します。建築コスト管理士は、建築管理士より広範囲な分野の知識が必要です。建築コスト管理士の資格は、建築積算士の上位資格であるといえるでしょう。
建築コスト管理士試験の概要
建築コスト管理試験について、以下の項目ごとに概要を解説します。これから受検を検討している方はぜひチェックにしてください。
- 受検資格
- 科目・出題範囲
- 受験手数料
- 日程
- 試験会場
受験資格
建築コスト管理士資格を受験するためには、以下の要件のいずれかを満たす必要があります。
建築積算士の称号を取得後、更新登録を1回以上行った方
建築関連業務を5年以上経験した方
一級建築士に合格し登録した方
科目・出題範囲
建築コスト管理士の試験では主に以下の知識が問われます。
- コスト情報収集・分析
- 広範囲な市場価格
- 発注戦略
- 調達戦略
- フィジビリティースダディー
- 積算技法
- 施工技術・工期算定
- LCC・VE及びFM・PM・CM概要
- 環境配慮
- 建築関連法規
- IT活用
新☆建築コスト管理士ガイドブックの第1章~第4章、新☆建築積算士ガイドブックの第6章~第8章、第10章から出題されます。新☆建築コスト管理士ガイドブックおよび新☆建築積算士ガイドブックは、公益社団法人日本建築積算協会から購入できます。
受験手数料
受験手数料は29,700円(税込)です。学科試験の免除により短文試験のみ受験する場合の受験手数料は16,500円(税込)です。
日程
2025年度の試験日程はまだ公開されていません。例年、10月下旬に試験が実施されます。参考までに、2024年度の試験日程を以下に紹介します。
- 試験日:2024年10月27日(日)
- 学科試験時刻:12:50~15:20(2時間30分)
- 短文記述試験時刻:15:40~17:40(2時間)
- 合格者発表日時:2024年12月16日(月)10時頃に公益社団法人日本建築積算協会Webサイトで受験番号を公開
試験会場
例年、試験会場は全国9都市9会場の中から選べます。2025年度の試験会場は未発表のため、2024年度の試験会場を紹介します。
- 札幌:かでる2.7(北海道立道民活動センター)会議室
- 仙台:仙都会舘ビル会議室
- 東京TOC有明コンベンションホール
- 名古屋:TKP名古屋栄カンファレンスセンター
- 大阪:大阪府建築健保会館
- 広島:広島工業大学広島校舎
- 福岡:博多バスターミナル9F貸会議室
- 鹿児島:ポリテクセンター鹿児島
- 沖縄:沖縄ガス(株)
建築コスト管理士試験の免除制度
過去に学科試験の合格基準点を超えた人は、次年度以降2年間に渡り学科試験が免除されます。
建築コスト管理士試験の合格率・難易度
年度によってばらつきがありますが、建築コスト管理士試験の合格率は60%前後です。2021~2024年度の合格率は以下のとおりです。
- 2024年度:実受験者数359名、合格者数146名、合格率40.7%
- 2023年度:実受験者数292名、合格者数160名、合格率54.8%
- 2022年度:実受験者数288名、合格者数138名、合格率47.9%
- 2021年度:実受験者数221名、合格者数140名、合格率63.3%
建築コスト管理士試験の勉強方法
建築コスト管理士の試験案内に記載されているように、新☆建築コスト管理士ガイドブックおよび新☆建築積算士ガイドブックから出題されます。2つのガイドブックの出題範囲を網羅的に勉強しましょう。
また、過去問題の解答と解説が公益社団法人日本建築積算協会Webサイトに掲載されています。過去問を解いて、傾向を確認してください。特に短文記述試験の独学は難しいかもしれませんが、一度は自分で解答を作成してみましょう。
建築コスト管理士の資格を取得するメリット
建築コスト管理士の資格を取得するメリットは主に以下の3つです。
- 給料アップにつながる可能性がある
- 重要な役割を担う仕事を担当できる
- キャリアアップにつながる
それぞれの内容を解説します。
給料アップにつながる可能性がある
建築コスト管理士の資格を取得することで、給料アップにつながる可能性があります。会社によっては、資格を取得した人に手当を支給するケースがあります。自社の制度や規約を改めて見て、建築コスト管理士の取得によって手当がもらえるか確認してみましょう。
また、後述するように、建築コスト管理士を取得することで重要な役割の仕事を担当したりキャリアアップしたりできるかもしれません。昇給・昇格や高待遇の会社への転職などによって給与が上がるでしょう。
重要な役割を担う仕事を担当できる
重要な役割を担う仕事を担当できることも建築コスト管理士の資格を取得するメリットの1つです。企画や構想といった初期段階から、完成後の維持や保全、解体まで考慮してコストを算出することは、会社の利益を左右する重要な仕事です。
特定の工程に詳しい人はいても、すべての工程をまとめて全体のコストを算出できる人材はほとんどいないでしょう。建築コスト管理士の資格を取得することで、会社で重用されるかもしれません。
キャリアアップにつながる
キャリアアップにつながることも、建築コスト管理士の資格を取得するメリットに挙げられます。建築コスト管理士の仕事は工程全体を見渡してコストマネジメントすることなので、プロジェクトリーダーとして社内で昇格・昇給できる可能性があります。
また、在籍していると公共工事の入札審査で加点されるケースがあるため、建築コスト管理士を探している企業は多くあります。現在勤めている会社よりも好待遇で転職できるかもしれません。
建築コスト管理士の資格を活用できる場所
建築コスト管理士の資格を活用できる場面がいくつかあります。公益社団法人日本建築積算協会によると、以下のように活用できます。
- RICS(英国王立チャータード・サベイヤー協会)の正会員(MRICS)として、「Chartered Quantity Surveyor」称号を取得できる
- 公共建築設計者情報システム(PUBDIS)における技術者情報の指定対象となる
- 沖縄県では建設工事入札参加資格審査および測量及び建設コンサルタント等業務入札参加資格審査において、主観項目(技術者)で2点の加点評価がされる
- 地方自治体等で、設計業務あるいはコストマネジメント業務プロポーザル等の資格要件として、点数が付与されることがある
建築コスト管理士に向いている人
建設会社や設計事務所のコスト管理責任者、積算事務所のプロジェクト責任者のように、総合的にコスト管理をしなければならない地位の人は、建築コスト管理士の資格が役立つでしょう。建築積算士の資格を保有しているのであれば、コスト管理担当者にも建築コスト管理士の資格の取得をおすすめします。
資格を取得することで責任者へのキャリアアップにつながります。官公庁のように発注する側のコスト管理担当者・責任者も、建築コスト管理士の資格取得を検討しましょう。
施工管理における原価管理の役割や原価管理のメリットなどについてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
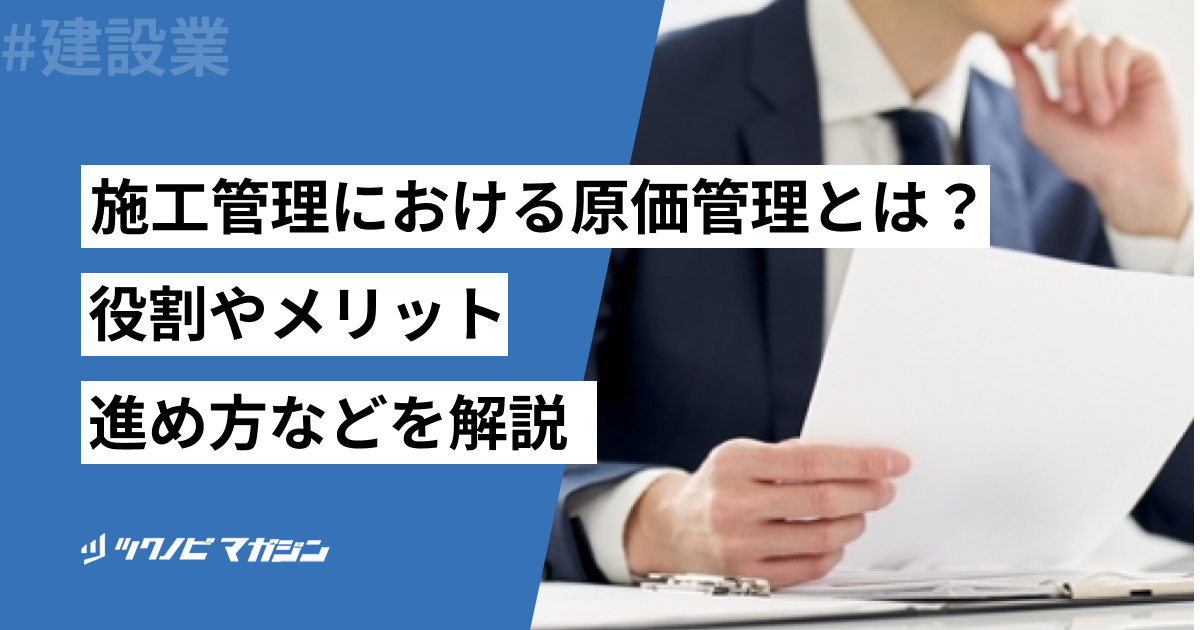 施工管理における原価管理とは?役割やメリット・進め方などを解説
施工管理における原価管理とは?役割やメリット・進め方などを解説
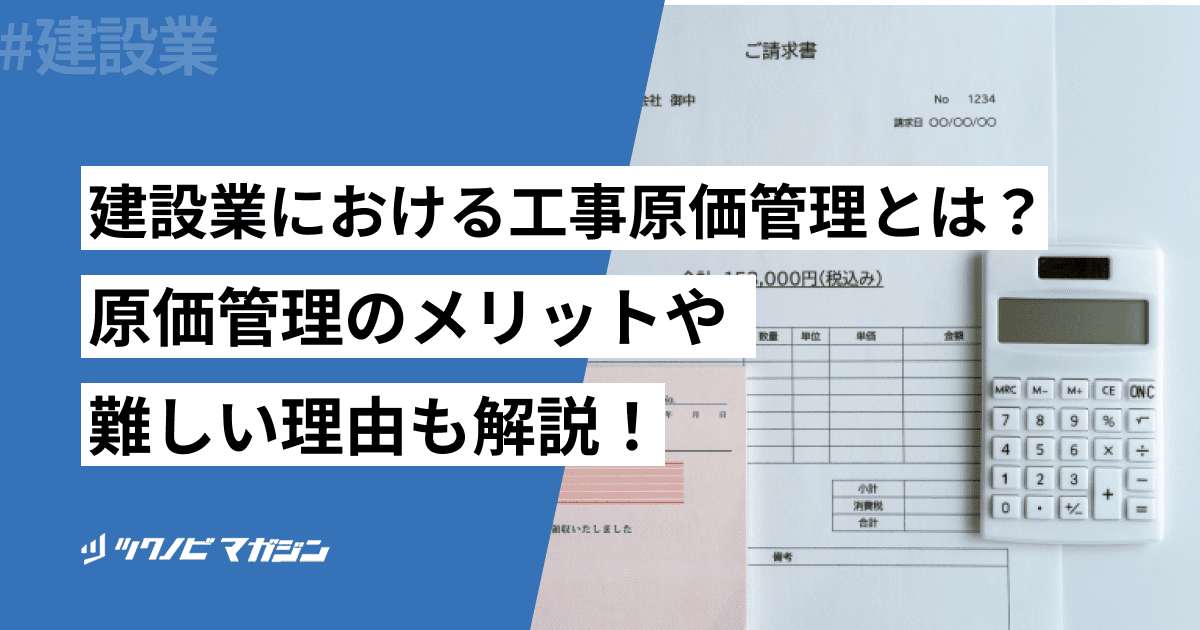 建設業における工事原価管理とは?原価管理のメリットや難しい理由も解説!
建設業における工事原価管理とは?原価管理のメリットや難しい理由も解説!
【まとめ】建築コスト管理士は幅広い知識が求められる!資格を取得してキャリアアップを目指そう
建築コスト管理士の仕事内容、試験の概要、資格を取得するメリットなどを解説しました。企画や構想といった初期段階から、完成後の維持や保全、解体まで考慮してコストを算出することが建築コスト管理士の主な業務です。
建築コスト管理士には、積算だけでなく発注・調達戦略、環境配慮、ITなどの幅広い知識が求められます。資格を取得すれば、建築プロジェクト全体のコストマネジメントができる人材として企業で重用されるでしょう。ぜひ本記事を参考に、建築コスト管理士資格の取得を検討してみましょう。