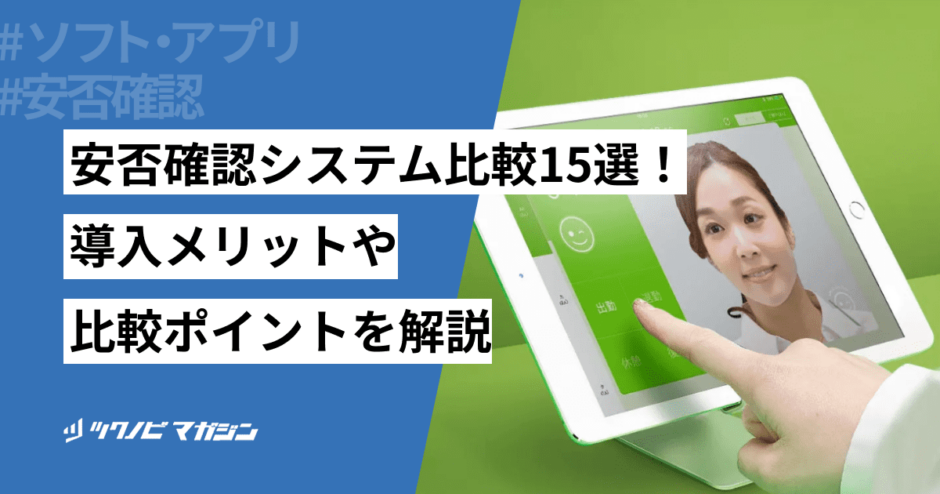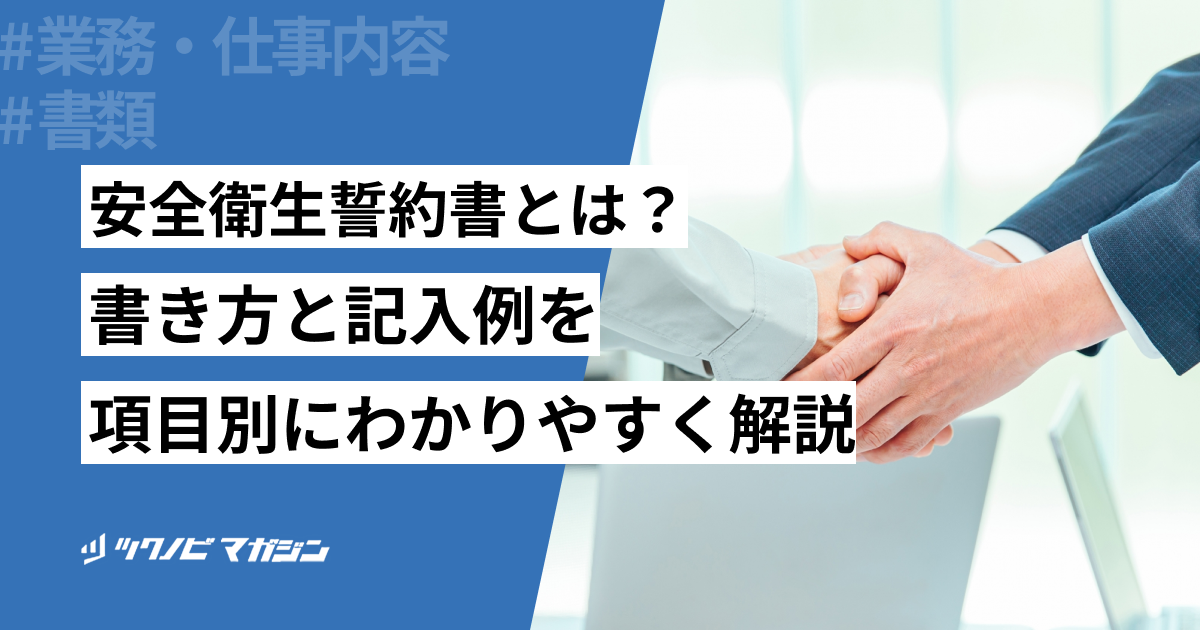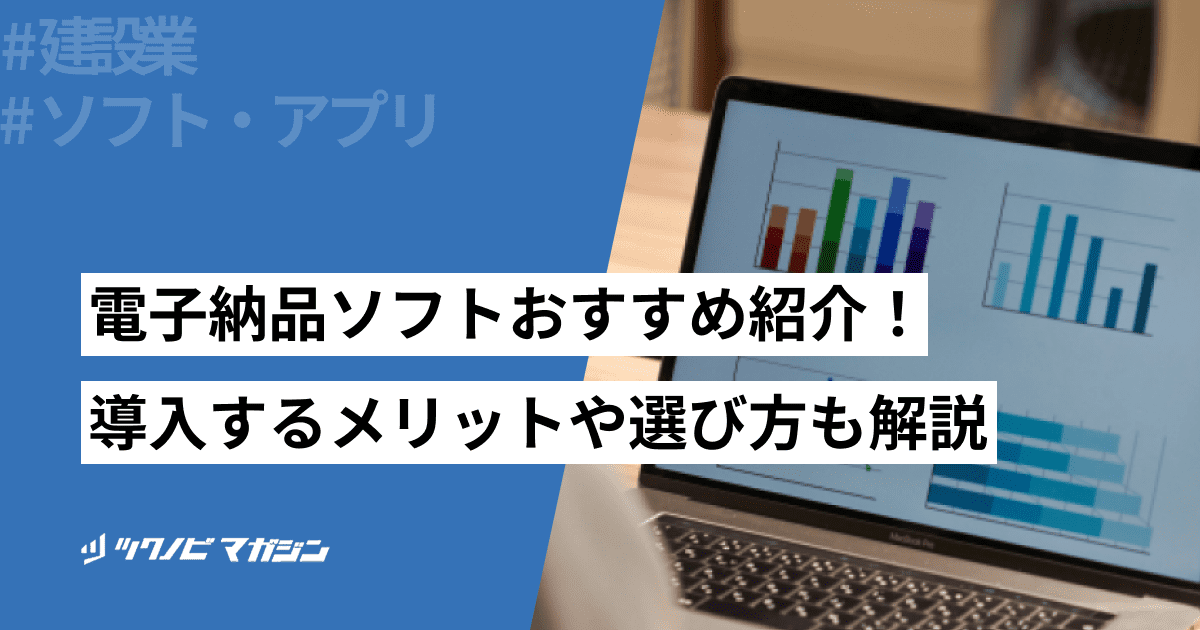※記事内に広告を含みます
災害時に従業員の安全をすばやく確認するための安否確認システムの需要は、大地震のリスクが懸念される中ますます高まっています。しかし、数多くの安否確認システムがリリースされているため、どれを選べばよいか分からないという方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回はおすすめの安否確認システムを15種類ピックアップし、それぞれの特徴を解説していきます。導入を検討している方はぜひご覧ください。
ツクノビBPOは、時間のかかる建設業業務を低コストで代行する建設業特化のアウトソーシングサービスです。
CADを活用した工事図面作成や事務作業、書類作成、積算、経理労務などまで幅広い業務に対応しています。詳細はぜひこちらからご確認ください。
安否確認システムとは
安否確認システムとは、地震などの災害時に自社の従業員に安否確認メールを送信し、返信状況を自動集計することで効率的に安否を確認するためのシステムです。また、工場やサプライヤーの被災状況を確認する機能も搭載しているものもあります。
従来は1人ひとりに安全や状況確認のメールを送信していましたが、手間がかかるうえ電波の混雑などでスムーズにいかないケースが多く見受けられました。安否確認システムを導入することでそれらのトラブルを回避し、災害後の企業の初動を迅速化する効果が期待できます。
安否確認システムの必要性
安否確認システムは、災害後に企業がスムーズに事業を再開するためにとても重要です。なぜなら従業員が現場で稼働可能な状況にいなければ、事業継続性を確認できないからです。
実際に事業所や工場を複数保有する従業員が300名以上の大手企業の7割が安否確認システムを導入しています。
安否確認システムを導入するメリット
安否確認システムを導入することで、どのようなメリットが得られるのでしょうか。代表的なものを以下で3つ紹介しましょう。
- 正確に安否確認できる
- 普段の情報集約に活用できる
- コンプライアンスの強化につながる
正確に安否確認できる
気象庁のデータに連動して自動で安否確認メールを一斉送信する機能などを搭載しているため、確実に安否を確認できるというメリットがあります。また、返信がない場合、定期的な間隔で何度もメールを送る機能を搭載しているシステムもあるため、ネット回線が混雑している際も復旧後迅速に確認ができます。
さらに、従業員の家族が被害を受けており、通常通り勤務することが難しい状態も想定されるでしょう。そのような状況を把握するため、従業員の家族の安否確認を行えるシステムも提供されています。
普段の情報集約に活用できる
安否確認システムは、災害時のみにしか活用できないものではありません。例えば、イベントを行う際に一斉送信機能や集計機能を用いて出欠の確認が行えます。また、社内の満足度や意見を問うアンケートも容易にできるのも魅力です。
このように、情報収集や集計を行なうツールとして、日常的に利用できるという汎用性の高さも安否確認システムを導入する大きなメリットと言えるでしょう。
コンプライアンスの強化につながる
システムを利用しない場合、従業員個人の電話番号やメールアドレスに直接連絡することになります。そうなると、情報漏洩のリスクがあるだけでなく、企業に個人情報を必要以上に教えることを拒む従業員も出てくる可能性が考えられます。
しかし、個人で情報を入力する安否確認システムを使えば個人情報が企業に知られることはありません。また、情報は高度なセキュリティ対策がされたサーバーで管理されるため、漏洩のリスクも軽減されます。
安否確認システムを導入するデメリット
安否確認システムを導入することで、メリットだけでなくデメリットも当然発生します。想定されるデメリットは以下の3つです。
- コストがかかる
- 通信インフラに依存する
- 定期的に情報の更新が必要
コストがかかる
システムを導入する際には、コストが発生することを考慮しなければなりません。システムの登録料や初期投資費用がかかるものもあります。また、月額料や年会費などのランニングコストに加えて、通信費用もかかるでしょう。
これらのコストが経営に影響しないかどうかを、考慮して導入するか否かを慎重に決める必要があります。
通信インフラに依存する
安否確認システムはネット回線があってはじめて機能するものなので、通信インフラ自体が機能しない状態では役割を果たせないというデメリットもあります。大地震をはじめとする災害時には、ネット回線が混雑してつながらないケースも想定されるので、そのようなリスクも考慮しなければなりません。
定期的に情報の更新が必要
安否確認システムは、従業員の住所や連絡先が正しく登録されていなければ機能しません。そのため、もし従業員が住居を移した場合や、電話番号を変更した場合は、その都度システムの情報を更新するというタスクが発生します。
もし従業員に登録をゆだねている場合、確実に更新するようなシステムを構築していないと非常時に安否確認が取れないというリスクが考えられます。
安否確認システムの主な機能
安否確認システムは様々な企業が提供していますが、それぞれのシステムがほぼ搭載している代表的な機能は以下の3つです。
- 自動送信・再配信
- グループ設定
- 模擬訓練
自動送信・再配信
自動送信機能は有事の際に災害情報にあわせて電子メールシステムを利用し、自動的に従業員に安否確認メールを送る機能です。再配信機能は安否の返信のない従業員に、一定の間隔でメールを送信する機能です。返信が確認できるまで送信され続けられるため、一定の期間を超えても返信が来ない際には迅速に次のステップに移行できます。
グループ設定
登録した従業員の情報を、グループに分けられる機能です。例えば、部署や役職、拠点など様々なグループに分別できます。この機能があると、全国に拠点がある企業では被災地に絞って安否確認ができるため、効率的に対象者にのみ連絡をとれるというメリットがあります。
また、グループ単位の会話も可能なため、災害後の対応について話し合いがスムーズになるという効果も期待できます。
模擬訓練
多くの安否確認システムには、模擬訓練機能が搭載されています。模擬訓練機能は、災害を想定して通常時に実際に安否確認メールを一斉送信します。従業員から返信がされるかを確認することで登録情報に誤りがないかが確認でき、実際の災害時に正常に機能するかをチェックするという意図があります。模擬訓練を行うことで、災害時もシステムを信頼して利用できます。
安否確認システムの比較ポイント
安否確認システムを比較する際には、以下の5つのポイントをチェックしましょう。
- 操作性
- 自動配信機能
- 通信手段
- セキュリティ対策
- 動作実績
操作性
操作性や画面の見やすさはとても重要です。なぜなら災害時は、パニック状態に陥る人も多く、判断能力がにぶることも予想されるからです。たとえ日常と異なる非常事態であっても使えるようなシンプルな操作性であることはとても大切なのです。
また、システムを全従業員に正確に操作してもらうために、操作マニュアルや、研修やコールセンターなどを導入しているシステムを選ぶのも良いでしょう。継続的に研修や訓練を行い、システムに慣れて非常時にも使いこなすことが何よりも重要です。
自動配信機能
震度や災害の条件、地域などに応じて、自動配信できるシステムだとよりスムーズに安否確認が取れます。ひと言に自動配信機能と言っても、「災害データを精査してから配信するシステム」、「気象庁のデータに連動して配信するシステム」「災害データ受信後、一定の時間が経ってから配信するシステム」など様々な種類があるので、自社のニーズに応じて選択しましょう。
通信手段
対応しているデバイスや通信手段の種類もチェックしましょう。例えば、現在では携帯のメール機能よりも、LINEなどのSNSツールやアプリを使って連絡する人が増えました。電話やPCメールアドレスだけでなく、これらのツールとも連携が取れるシステムを利用したほうが、従業員の目にも止まりやすく返信スピードが早くなる可能性が期待できます。
セキュリティ対策
従業員の個人情報を守るために、セキュリティ対策が万全なシステムを選びましょう。暗号化や復号化が施された通信を利用している、SSLサーバーや、海外や多拠点にサーバーを置くなどの対策を取っているシステムだと、サーバーが被害を被るリスクはぐっと少なくなります。
動作実績
災害時にきちんと機能していたかを確認するために、過去の動作実績も確認しましょう。システムのホームページで導入実績をチェックするのはもちろん、口コミサイトなどもチェックするとより安心です。新潟中越地震や能登半島地震など、近年の災害時の情報を見るとより正確に把握できます。
安否確認システム15選を比較
安否確認システムを選ぶ際には、操作性や通信手段や機能と併せて、セキュリティや動作実績などを確認すると導入後のミスマッチを防げます。しかし、実際にシステムを選ぼうとしても余りにも多く、目移りしてしまう人も多いでしょう。そこで、数ある安否確認システムの中でも特におすすめのものを、特徴と共に15個紹介します。
Biz安否確認
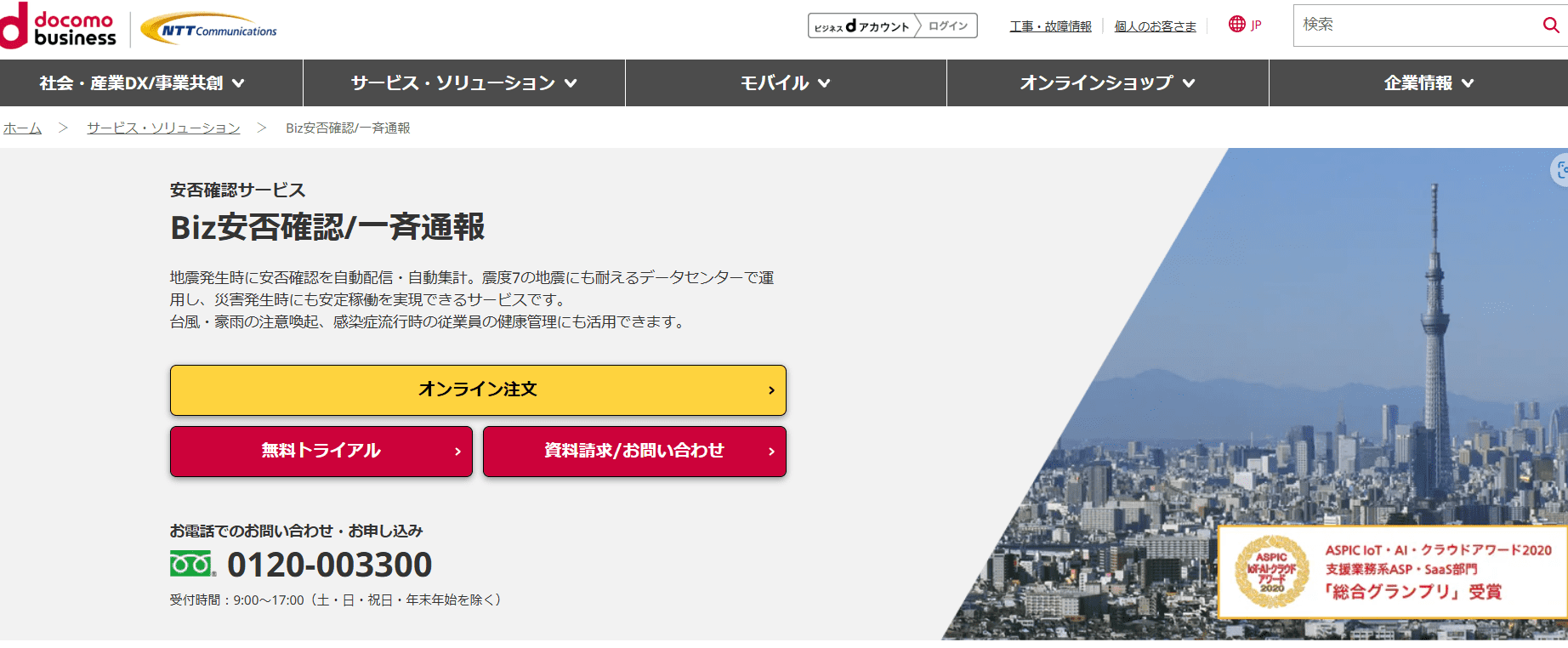
引用元:https://www.ntt.com/business/services/application/risk_management/anpi.html
Biz安否確認は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が提供する安否確認システムです。震度7の地震でも耐える強健なデータセンターで、従業員の安否確認メールを自動送信、自動集計します。震度を設定すれば、設定した震度以上の地震が発生した際にメールが自動的に送信され、未回答の従業員には再送信機能も利用できます。スマホアプリ・メール・電話と複数の通信手段に対応しているのも安心できるポイントです。
エマージェンシーコール
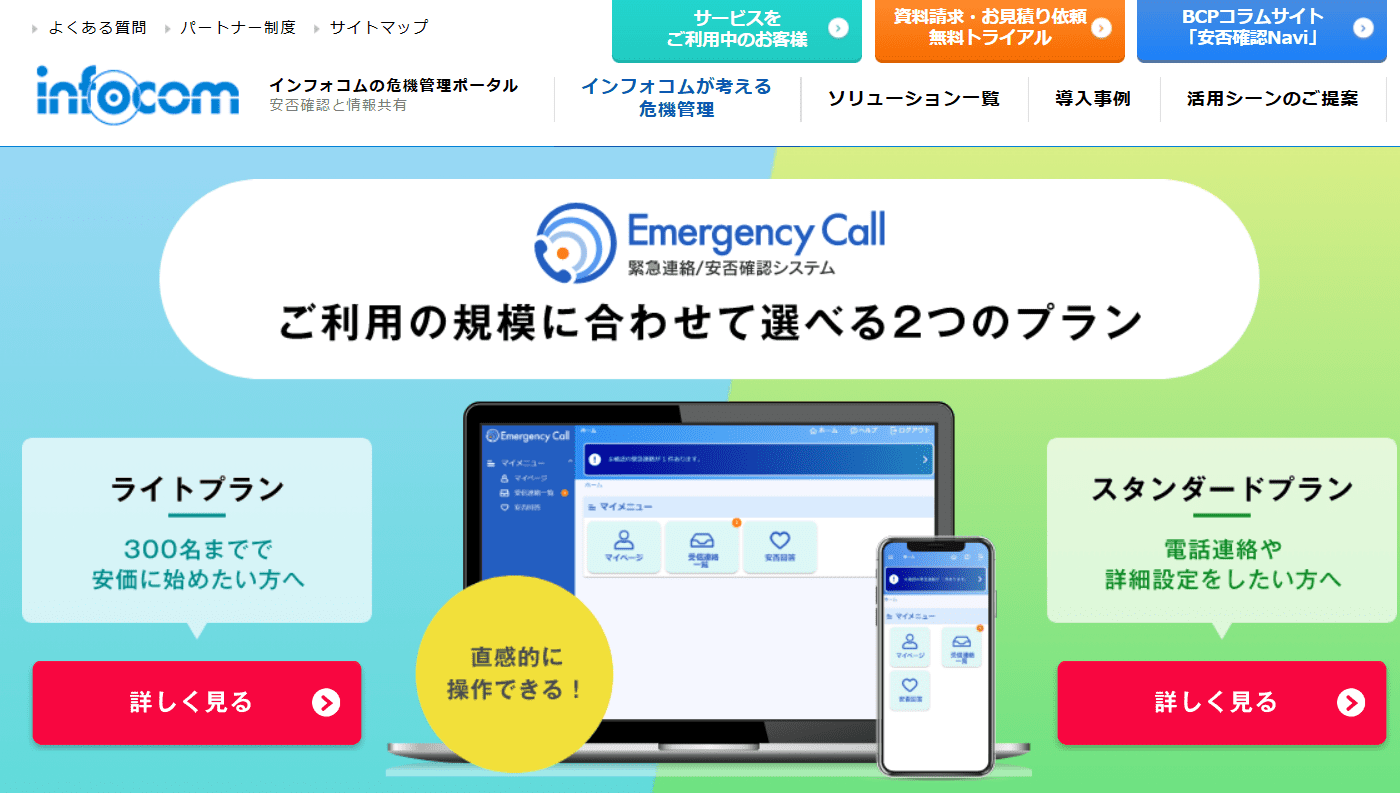
引用元:https://www.infocom-sb.jp/emc/
エマージェンシーコールは、インフォコム株式会社が運営する安否確認システムで、東日本大震災や熊本地震発生時にも安定稼働した実績があります。
回答率100%を目指した独自のシステムが好評で、自動送信・再送信、自動集計機能以外にも、未登録者をワンクリックで抽出できる機能も搭載しています。また、メールやアプリや電話番号以外にもFAXや固定電話にも対応しているのも魅力の1つです。関西と関東の2拠点のサーバーを同時稼働しているため、安定した稼働が期待できます。旭グループホールディングス株式会社やイオン株式会社などの大手企業の導入実績があるのも信頼感を与えます。
安否確認サービス2

引用元:https://www.anpikakunin.com/
安否確認サービス2はトヨクモ株式会社が運営する、3000社以上の導入実績がある安否確認システムです。まず、初期費用0円で契約できるのに関わらず、最低利用期間がないことが大きな魅力として挙げられます。また、外部システムと連携し、面倒なユーザー・部署の登録作業を簡略化できます。災害時は気象庁の情報と連動してメールを一斉送信、アプリや電話番号だけでなく連携すればLINEでも情報を受け取れるのです。再送信機能やリアルタイム集計機能も搭載している、代表的な安否確認システムの1つです。
ALSOK安否確認サービス

引用元:https://www.alsok.co.jp/corporate/service/safety_confirm.html
ALSOK安否確認サービスはアルソックが運営する安否確認システムで、直感的に操作できる分かりやすい画面が特徴です。複数拠点のサーバーで管理しており、東日本大震災や熊本地震でも安定稼働した実績があります。また、安否確認連絡の自動配信後、家族の安否確認は従業員と家族間のみ共有できるという配慮も魅力です。メールだけでなく、アプリの配信しており、またGPS機能と連携し写真や音声の添付も可能。従業員の安全に寄り添った大手ならではの充実したサービスが人気を集めています。
ANPiS

引用元:https://sol.kepco.jp/anpis/
ANPiSは関西電力が運営する安否確認システムで、初期費用無料、さらに従業員数に応じた最低月6000円〜という安価な料金でお得に利用できるのが特徴です。気象庁の情報と自動で連携した自動送信機能や再配信機能など主要な機能は備えており、オプションでLINEと連携もできます。手動で家族にも安否確認ができ、通常時もアンケートや出欠確認などにフレキシブルに利用できるのも魅力です。なるべくコストを抑えたい方におすすめのシステムの1つです。
安否コール

引用元:https://www.anpi-system.net/
安否コールは株式会社アドテクニカが運営する安否確認システムで、1,200者以上の導入実績があります。自動メール配信は震度1~7の間で設定でき、アプリによる プッシュ通知やスマートウォッチにも対応しています。また、GPSマップ機能や自動集計機能、家族間安否確認機能も搭載しており、災害時に利用できる掲示板があるのも魅力です。また、サーバーは国内の3箇所で運用されており、金融機関と同様のトップクラスのセキュリティレベルを維持しています。従業員数や機能に応じて多様なプランがあるだけでなく、無料トライアルもあるので様々な企業のニーズに応えられます。
セコム安否確認サービス

引用元:https://www.secom.co.jp/business/saigai/anpi/anpi.html
セコム安否確認サービスはセコム株式会社が運営する契約社数8,950社にも上る大手の安否確認システムです。中小企業向けのシンプルな機能の「セコム安否確認サービス スマート」と、中〜大規模の企業向けの豊富な機能の「セコム安否確認サービス」の2つがあり、どちらかを選択できるようになっています。
24時間365日体制のトラストオペレーションセンターが、人の目で災害情報を入手して誤報チェックなどを行ってから管理者に連絡をするのが最大の特徴です。一斉送信はメールやアプリだけでなく、オプションでLINEとも連携できます。また、万が一一斉送信メールが来なくても、自主報告できるのも魅力です。データは複数拠点のサーバーでバックアップされており、災害時も安定した稼働が期待できます。
らくらく連絡網

引用元:https://www.ra9.jp/lp/emergency/
らくらく連絡網は、登録者700万人の安否確認のメーリングリストを作成できる、無料で利用できる安否確認システムです。メールで登録する簡単ステップで、メーリングリストを簡単作成。自動送信機能はありませんが、アプリ版、WEB版の双方が簡単な操作性で利用でき、既読やコメントも一目で把握できます。公告のない有料版も、100名までなら月額5500円で利用できます。出来るだけコストを抑え、安否確認を行いたい方におすすめです。
ANPIC

ANPICは、株式会社アバンセシステムが運用する、産学連携で開発された低価格で利用できる安否確認システムです。直感的でシンプルなデザインにこだわりながらも、初回のユーザー登録を無料で代行する、無料の説明会を行うなどの手厚いサポートが魅力です。また、既存の人事や総務のシステムとデータ連携すると、登録作業の手間を軽減できます。自動メール送信機能の安否アック人はLINEと専用アプリの双方で確認でき、さらに収集した安否情報をデータ化し、報告書作成をすることもできます。サーバーはアメリカにあるため、災害時も影響は受けません。
オクレンジャー

オクレンジャーは株式会社パスカルが提供する安否確認システムで、使いやすい基本機能と豊富なオプション機能が好評です。気象庁の情報と連動して安否確認メールは自動送信され、従業員はアプリとメール双方で確認できます。解答結果は自動集計できるだけでなくグラフとしてデータ化も可能です。また、ストレスチェックや13言語に対応した翻訳機能、河川洪水予報や熱中症アラートなどの多様なオプション機能も有料で付けられます。多彩な機能をカスタマイズしたい方にお勧めのシステムです。
安否確認bot for LINE WORKS

安否確認bot for LINE WORKSはLINE WORKS・LINEアプリ内で全て完結できる安否確認システムです。気象庁と連携し自動送信される安否確認配信はラインで確認・返信でき、管理者にはBOTが自動的に回答状況を集計して通知してくれます。従業員の回答は、BOTが送る安否確認の選択肢を選ぶだけという簡単な操作性と、1IDあたり月額220円で利用できる価格設定も魅力です。安否質問設定は10個まで自由に設定でき、安否確認場所は従業員ごとに10個まで設定可能というカスタマイズ性も好評です。
安否LifeMail
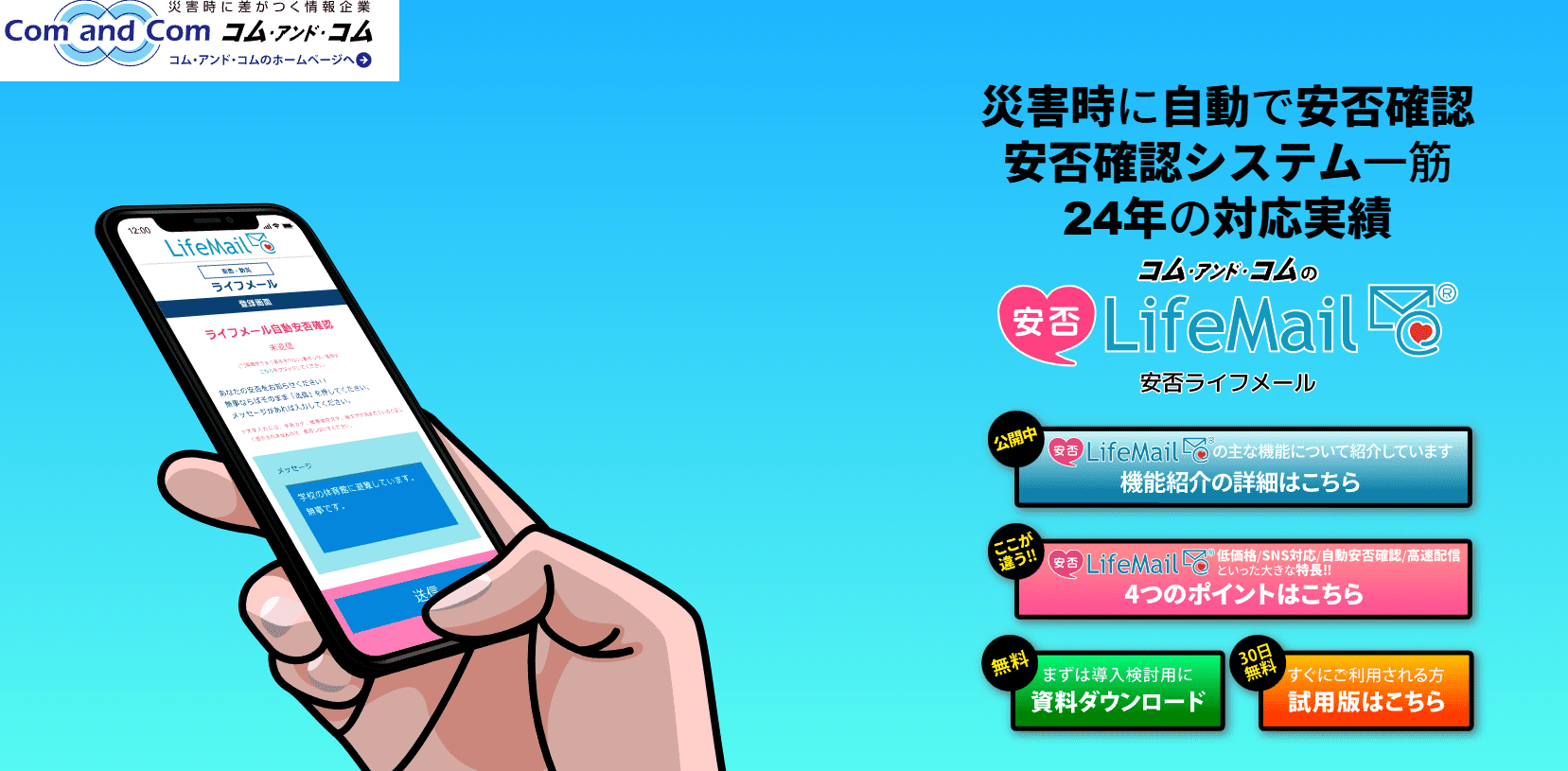
引用元:https://www.project-com.com/lifemail/index.html
安否LifeMailは株式会社コムアンドコムが提供する24年の実績がある安否確認システムのパイオニアともいえる存在です。気象庁の発表と連動して自動でメールを送信、LINEやGPSメールなど複数の媒体で確認できます。返信者への再送がワンクリックでできる手動再送機能や、自動集計機能、訓練メール機能などの多彩な機能を、初期費用150,000円、月額利用料1人当たり80円〜という低価格で利用できます。
大手企業、地方自治体、医療機関などで約200万人以上に利用されてきた、信頼と実績のあるシステムです。
バーズ安否確認

引用元:https://www.birds.co.jp/anpiplus/
バーズ安否確認は、株式会社バーズ情報科学研究所が提供する安否確認クラウドサービスです。通常時は連絡網としても利用でき、初期費用は不要で、必要なのは50人までは月額1,250円、100人までは月額2,500円というシンプルで安価な価格設定が好評です。パソコン、スマホ、ガラケーなど多様なデバイスに対応しており、有事・緊急事態に利用できる情報交換の場となるホワイトボード機能も搭載。安否確認メールの自動送信機能を搭載しており、有料オプションでLINEとの連携や家族向けの安否確認メールも利用できます。
バンソウ緊急SMS

バンソウ緊急SMSは株式会社fonfunが提供するSMS(ショートメッセージ)を利用した安否確認システムです。地震を感知し設定震度以上でアンケートのURLを搭載したSMSを自動送信します。必要なのは電話番号だけであるのに関わらず、自動集計機能や登録者をCSVで一括登録できる機能、送るメッセージに登録するテンプレート一覧など多彩な機能を搭載しています。
管理者画面からはURL未開封者や未回答者、送信エラー数などが一目で確認できるようになっているのも魅力です。アプリのダウンロードが不要なため、従業員が入れ替わっても管理しやすいというメリットがあります。
Safetylink24

引用元:https://www.safetylink24.jp/
特徴
Safetylink24(セーフティリンク24)は、株式会社イーネットソリューションズが提供する導入企業900社以上の安否確認システムです。気象庁発表データと連動しメールは自動送信され、返信がなければ自動リトライ機能で再送されます。CSVユーザー一括管理機能やメール配信結果レポートで管理者の負担も軽減されます。能従業員1人に対して、6人までの家族登録が可能で家族間でのみ安否確認連絡が取れるのも魅力です。能登沖地震、東日本大震災、熊本地震などの災害時に安定稼働した実績があり、分かりやすい料金体系も好評です。
安否確認システムを導入するときの注意点
安否確認システムを導入する際には、人気のものを選べばよいというわけではありません。自社にマッチしたシステムを導入し快適に利用するために、以下の3点に注意しましょう。
- 個人情報の管理方法を確認する
- 社内研修と訓練を実施する
- 予備の通信手段も検討する
個人情報の管理方法を確認する
安否確認システムを稼働するためには、従業員に個人情報を提供してもらわなければなりません。管理を徹底し漏洩を防ぐのはもちろん、従業員の理解を得て合意を得たうえで登録してもらうように心がけましょう。個人情報の取り扱いについても、情報収集時にしっかり説明しておくことで後のトラブル発生のリスクを軽減できます。
社内研修と訓練を実施する
社内研修や模擬訓練を行うなどして、災害時を想定したシミュレーションを定期的に行いましょう。普段システムに触れる機会を設けることで、パニックになりがちな災害時にも迅速にシステムに入力できるようになります。
予備の通信手段も検討する
安否確認システムが繋がらないリスクを想定し、予備の通信手段を検討するのも大切です。例えば、緊急時のみNTTから提供される災害伝言ダイヤル(171)や災害用伝言サービスの存在を周知しておくのも良いでしょう。しかし、これらは家族・親戚・友人との安否確認を目的としたものなので、最終手段として積極的には利用しないようにしてください。
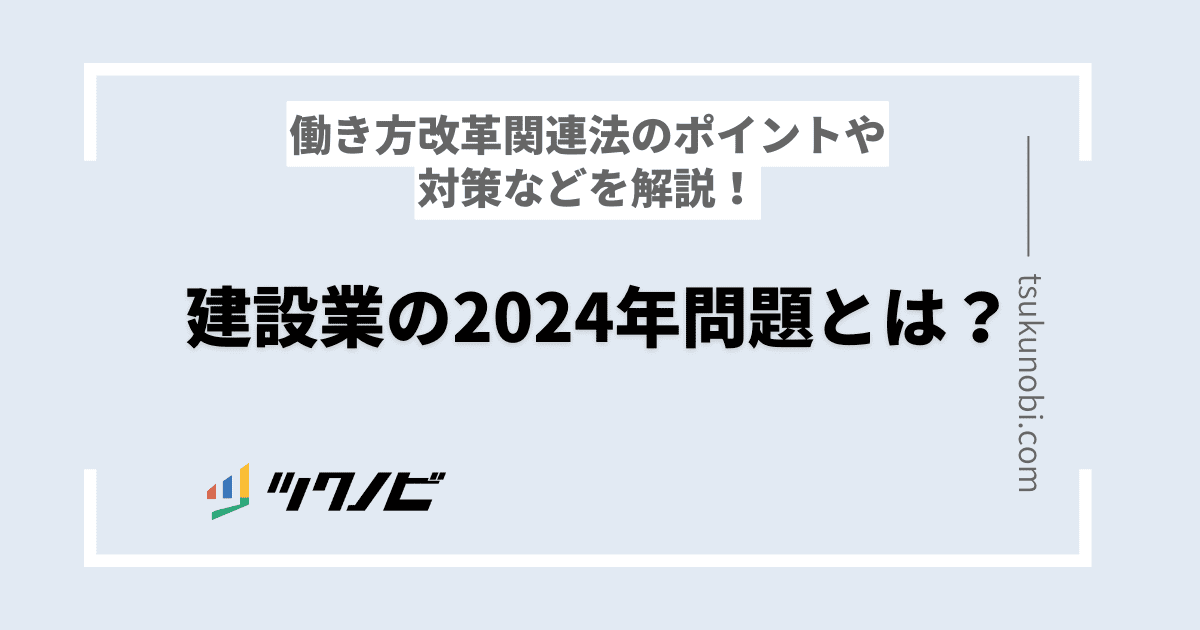 建設業の2024年問題とは?ポイントや対策をわかりやすく解説!
建設業の2024年問題とは?ポイントや対策をわかりやすく解説!
【まとめ】安否確認システムは比較ポイントを参考に自社にとってバランスのよいものを選ぼう!
安否確認システムは様々なものが提供されており、価格や機能も多岐にわたります。比較ポイントを参考に、自社に本当に必要な機能は何かを見極め、人気や価格に惑わされずにマッチするシステムを選んでください。導入後も、テストメールや研修を行い、災害時に正しく機能するような体制を作る努力も大切です。災害時の体制を整え、初動態勢を整えられる環境を整備しましょう。
※弊社の営業代行サービスであるツクノビセールスでは、
【効果が出なければ全額返金プラン】を新たにスタートさせました!

※詳しくは👆👆👆のバナーをクリック!!