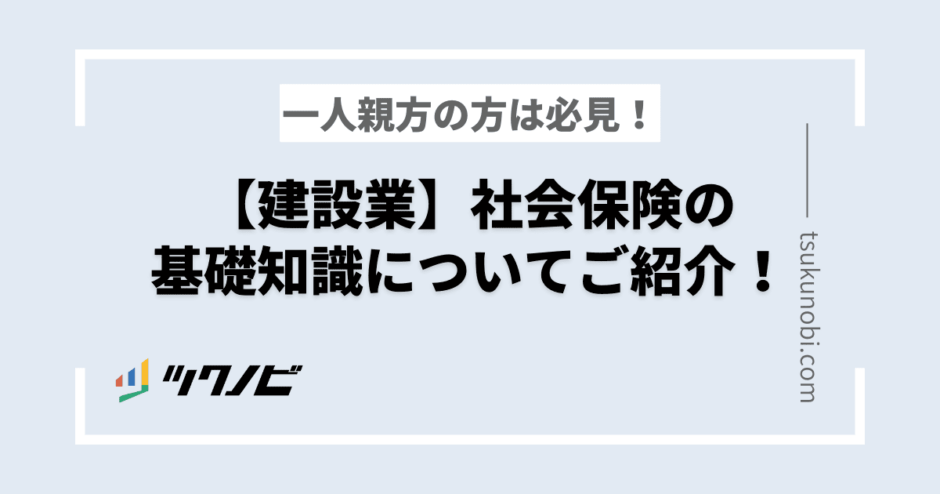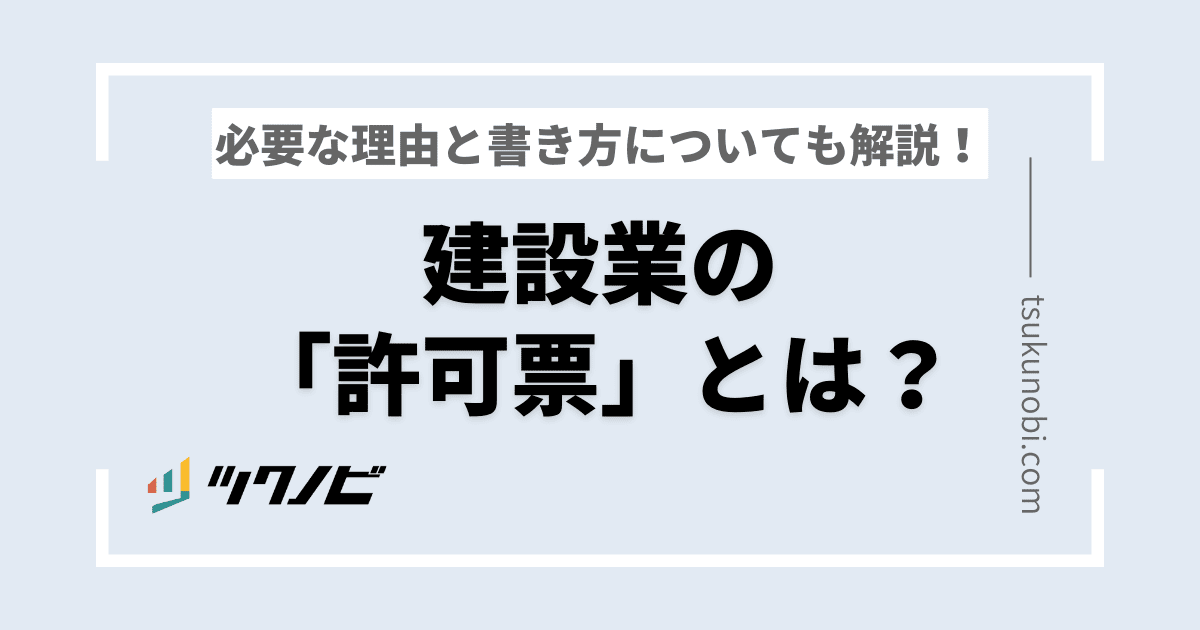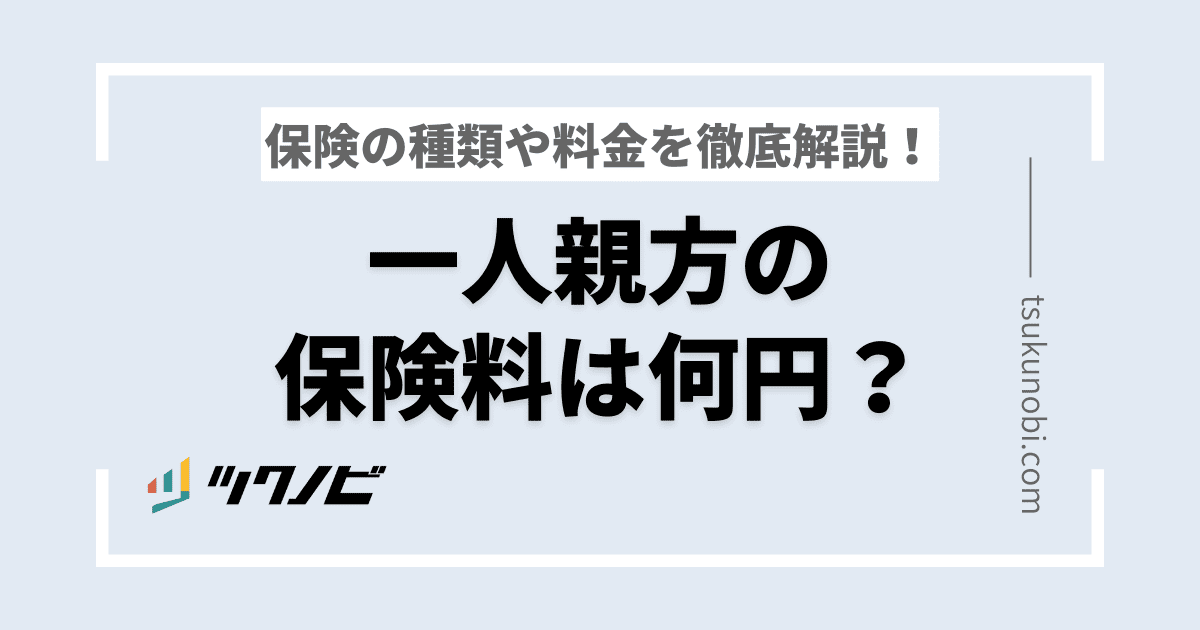※記事内に広告を含みます
一人親方のなかでは社会保険に加入すべきかどうか迷うかたもいるでしょう。
そこで今回は社会保険や各保険の説明、加入条件、リスクやメリット・デメリットを説明していきます。
「保険」は、業務に直接かかわるものではありませんが、万一の事態発生の時に頼りになるものです。ぜひ参考にしてみてください。
社会保険のことなら「社会保険労務士法人TSC」がおすすめ
社会保険労務士法人TSCは1年間無料でサービス利用できる社労士です。そのため「お試しで社労士に依頼したい」という方にもおすすめです。社会保険や労務関係の業務を丸ごと委託できるだけでなく、助成金の相談もできます。
一人親方であれば知っておきたい社会保険の種類
本来、社会保険とは、「健康保険」「年金保険」「介護保険」「労働保険(労災保険、雇用保険)」をいいます。この記事では特に、
- 業務外でけがや病気をした時のための「健康保険」
- 業務中に怪我などをした時のための「労災保険」
- 若いときに掛け金を支払い、高齢になったらもらう老齢年金や障害年金や遺族年金もある「年金保険」
以上の3つに焦点を当てて説明します。
市町村国保・国保組合
日本は健康保険に関して「国民皆保険制度」を採用しており、何らかの健康保険に加入する必要があります。
通常個人事業主は、「国民健康保険(市町村国保)」に加入します。国保は(市町村別ですから)「地域保険」とも称します。これに対し、サラリーマンの健康保険などは「職域保険」に分類されます。
そして国保にも職域保険があり、同業者で構成される組合員による「国民健康保険組合」が組織されている場合があります。これには建設業国保をはじめとして、医師国保、税理士国保など、100以上の団体があります。
したがって建設業一人親方は、市町村国保にするか業界団体国保にするか、決定する必要があります。
労災保険(特別加入)
次は労災(労働者災害補償保険)です。業務中に怪我をした場合に、保険金が支払われます。
労災はそもそも従業員(労働者)のための保険です。経営者である一人親方は対象外ですが、労災には「特別加入」という制度があり、一人親方でも加入できます。
建設業の現場作業は、怪我をするリスクが高いので、一人親方といえども労災加入の必要性も高いと思われます。加入にあたっては、すでに特別加入を承認されている業界団体を通じ申込をします。
一人親方向け労災保険のお申し込みはこちらから
国民年金
「国民皆年金制度」により、20歳以上であれば年金加入は義務です。さらに、自営業者については「国民年金」加入一択になります。
少し詳しく説明すると、20歳以上60歳未満の自営業者で、日本国内に住所を有する者は「第1号被保険者」と呼ばれる「強制被保険者」となります。たとえば脱サラして自営業者になった場合は、自分自身で14日以内に市町村窓口へ届け出る必要があります。
建設業の社会保険の加入基準の基本知識
立場(法人、従業員のいる個人事業主、一人親方)の違いに、各保険の加入基準を加味して判断する必要があります。また、従業員数による違いが生じる場合もあります。それぞれみていきましょう。
法人経営の場合は加入が必須
まずは法人経営の場合です。それぞれ、健康保険、労災、年金に分けて説明します。
- 健康保険について
法人は、強制適用事業所となります。通常大企業は「自社や業界団体の健康保険組合」に、中小企業は「協会けんぽ」に加入します。厚生年金保険と併せ、保険料の半額が会社負担になります。 - 労災保険について
労働者を一人でも雇用している場合は、加入義務が生じます。ちなみに労働者とは、事業に使用され、かつ賃金が支払われる者です。 - 年金保険について
先ほど健康保険のところで触れましたが、厚生年金保険に加入必須です。
個人事業主の場合は所属人数による
次は、個人事業主が従業員を雇用している場合です。
- 健康保険について
健康保険の適用事業所に関しては、三つの場合に分類されています。①法人は先ほど述べたように「強制」、②法定16業種は従業員数により判断、③16業種以外は「任意」と定められています。土木、建築、電気などはすべて法定16業種なので、従業員数により判断されます。具体的には、常時5人以上の従業員を使用する場合は強制適用です。 - 労災について
加入の例外があるのは農林水産業のみなので、建設業では労働者が一人でもいたら加入必須です。また経営者は通常加入はできず、特別加入の手続きが必要です。 - 年金について
この場合厚生年金となり、健康保険の基準と同一です。具体的には、法定16業種なので、常時5人以上の従業員を使用する場合は強制適用です。
(注)任意適用事業所には、適用事業所になる方法が準備されています。
一人親方の場合は任意
最後は一人親方の場合です。従業員はおらず、自分だけで営業しているケースです。
- 健康保険について
健康保険は市町村国保、または国保組合に加入することになります。ちなみに保険料は、国保組合の方が安価なケースが多いようです。 - 労災について
必須ではありません。先ほど述べたように、特別加入の方法があります。 - 年金ついて
国民年金に加入します。市町村への手続きが必要です。
一人親方が社会保険未加入で発生する3つのリスク
ここまでの説明で、社会保険には「強制適用」「任意適用」、労災保険には「特別加入」などの違いがあることが分かりました。では、「強制適用」の規則に違反したらどうなるのでしょうか。また、「任意」の場合でも、加入した方が良いケースや加入すべきケースはないのでしょうか。
一人親方の場合について、順にみていきます。
罰金・追微金の発生
まずは、一人親方が加入すべき国民健康保険に加入しない場合です。市町村国保、または国保組合への加入は義務なので、加入の手続きを怠ると罰金を科されるケースがあります。
市町村ごとに若干の差異があるようですが、財産差し押さえのうえ10万円以下の過料、などの罰則が課せられます。また、支払いが延滞した期間に応じ「延滞金」も徴求されます。
国民年金保険料の支払い遅延の場合は、国から請求を受けた市町村が、督促のうえ差し押さえ等の処分を行います。支払い遅延には、14.6%の延滞金が課されます。
仕事の受注が減少する
一定以上の大きな工事(500万円以上の規模)を行うための資格に「建設業許可」というものがあり、都道府県知事の認可を受ける必要があります。この許可を受けるのに、社会保険の加入が2020年から実質義務化されています。
さらにそういう風潮を受け建設業界では、公共工事においては社会保険への加入が条件にされる、民間工事でも元請けが社会保険加入をチェックする等、実質的に社会保険加入が仕事受注の条件になってきています。加えて、国土交通省でも「社会保険未加入業者は現場への入場を認めるべきではない」と通達しており、今後、社会保険未加入への風当たりは、ますます強くなることは確実です。
大きな事故や怪我に合っても自己責任
大きな怪我や事故にあった場合、まず必要なのは、業務外であれば市町村国保か国保組合への加入、業務中であれば労災保険への特別加入です。これらの加入がなされずに怪我などをした場合、医療機関に支払う代金は10割負担になります(国保は3割負担)。
また、業務中の労災事故に関していえば、怪我で病院を受診した場合の医療保障はもとより、障害を得たときの障害年金や、死亡した場合の遺族年金が支給されます。
(注)一人親方が建設現場で働く場合でも、たとえば「毎日、元請けから詳細で具体的な指示を受けて働いている」場合は、元請けの従業員として社会保険に加入する義務が発生するケースがあります。確認が必要です。
【保険別】一人親方の社会保険加入方法
それでは、一人親方が実際に社会保険に加入する場合の、具体的な手続きをみていきます。これまで説明してきた「国民年金」「国民健康保険」「労災保険」に加え、「国民年金基金」「小規模企業共済」というこの記事では初めて出てきた制度の加入方法も説明しています。
国民年金の場合
先ほども述べましたが、サラリーマンを辞めて一人親方になった場合、国民年金では「第1号被保険者」となり、自分自身で市町村長に対し「資格取得届」を提出しなくてはなりません。そしてこの届は、事実が発生した日から14日以内に提出する必要があります。
国民健康保険の場合
一人親方が健康保険制度に加入する際のパターンは、全部で4つです。
- 国民健康保険に加入する(前年度の所得が高額な場合は、負担する保険料も高くなります。 )
- 健康保険の任意継続をする(ポイントは以下の2つです。)
・退職日の翌日から20日以内に申請する
・任意継続の保険期間は、最長2年間まで - 健康保険の扶養家族に入る(家族の扶養に入るには、年間の収入が130万円未満である必要があります。年間収入は、被扶養者に該当または認定された日以降の年間見込み収入額です。)
- 健康保険組合に加入する(業種や事業、地域別に組織されている団体 です。)
国民年金基金の場合
国民年金基金とは、国民年金の第1号被保険者がゆとりある老後を送ることができるように、受給する国民年金に上乗せして受け取ることを目的として作られました。ひと言でいうと、「国民年金の上乗せ」です。国保組合と同様、地域型と職能型の2種類があります。建設業の場合は、「全国国民年金基金(旧:日本建築業国民年金基金)」が選択肢になります。加入方法は、年金手帳と銀行通帳を準備し、webから申し込みします。
(注)国民年金保険料を納めていない方は、対象外です。
小規模企業共済の場合
小規模企業共済は、一人親方や小規模企業の経営者などが、事業を辞めるときに退職金代わりの金銭を受け取るための制度です。国の機関である中小機構が運営しており、一人親方などの掛け金により運営されています。また、掛け金は全額「所得控除対象」なので、節税効果は大きいです。
申し込みには、申込書に確定申告書の写し(ない場合は「開業届」)、預金口座振替届出書を添付し、取引先の金融機関に申し込みます。申し込みから約40日後に、小規模企業共済手帳が郵送されます。
労災保険の場合
一人親方が労災保険に加入する場合は、先ほど述べたように特別加入制度を使います。
労災保険への特別加入をする場合、個人ではなく団体で手続きを行います。具体的には、地域の特別加入団体に申し込むことにより、「団体が事業主、加入希望者が労働者」とみなして労災保険適用が行われます。なお特別加入団体は、都道府県労働局長の承認が必要です。
また例外的ではありますが、既存の特別加入団体を利用せず、自分で新しく団体を作るという方法もあります。
おすすめの労災保険は「一人親方労災保険組合」
一人親方向け労災保険で一番おすすめなのは、業界No.1の加入者で実績豊富な一人親方労災保険組合の労災保険です。主な特徴は、以下の通りです。
- 全国の加入組合数は90,000人と業界トップクラス
- 月額組合費が500円と業界最安値
- 組合員様限定の優待サービスが多数
| 入会費 | 1,000円(初回のみ) |
|---|---|
| 組合費 | 500円/月 |
一人親方労災保険組合ではレストランやカラオケ、映画館など全国で20万ヵ所以上の施設のクーポンや割引などが適用される組合員様限定の優待サービスや友達紹介割引もあります。
一人親方が社会保険に加入する2つのメリット
一部の社会保険への加入は「義務」なわけですが、加入に対するメリットも存在します。どのようなメリットがあるのかを確認することにより、自分が加入すべきかどうかの判断材料にもなります。では、順にみていきます。
怪我をしても医療保障が受けられる
健康保険(業務外)と労災保険(業務中)の怪我などをした場合の保障のケースです。業務中と業務外、いずれにしても怪我をした場合は病院に行きますが、適切な保険に入っていないと医療費は全額自己負担になってしまいます。健康保険加入時の3割自己負担、労災保険加入時の全額保険適用と比べて個人の負担感は非常に大きいです。
収入が途絶えることがない
先ほどは医療保障の話をしました。それ以外にも、一人親方が怪我などにより業務が不能となることは、一切の収入が途絶えることを意味します。こうした場合でも、保険に加入していれば休業中の保障も受けられるほか、障害が残った場合の障害年金制度や、死亡した場合の遺族年金制度もあります。このように、怪我などをした場合でも最低限の生活や、または残された家族に対する補償も準備されています。
また国民年金にも、障害年金や遺族年金の制度があります。
一人親方が社会保険に加入する際に知っておきたい2つのこと
この章では、社会保険に加入することを決断した場合の注意点を説明します。あとから「こんなはずじゃなかった」とならないように、事前にチェックしておきましょう。
保険料の負担は個人で行う
「保険料の負担は個人で‥」と聞いて、当たり前じゃないかと思うかもしれませんが、実は当たり前じゃないケースもあるのです。
たとえば法人や、5人以上雇用の個人事業主の場合は、健康保険料(と厚生年金保険料)は原則として事業主と従業員が折半、労災保険料は全額事業主負担となっています。
これに対し一人親方の場合は、健康保険料(市町村国保または国保組合)、労災の特別加入とも個人負担となります。
保険料を経費にすることはできない
「保険料を経費にすることはできない」というのは、確かにその通りなのですが、今回説明したすべての保険料は確定申告時の「所得控除」の対象になるので心配する必要はありません。
一人親方の納税額は、以下のように計算します。
- 事業収入-仕入額および経費=事業所得
- 事業所得-所得控除=課税所得額
- 課税所得額×税率=納税額
そして、この記事で説明したすべての保険料(小規模企業共済の掛け金を除く)は、所得控除の中の「社会保険料控除」に算入され、小規模企業共済掛金は同じく「小規模企業共済等掛金控除」に算入されて控除されますから、実質的には経費と同様です。
社会保険のことなら「社会保険労務士法人TSC」がおすすめ
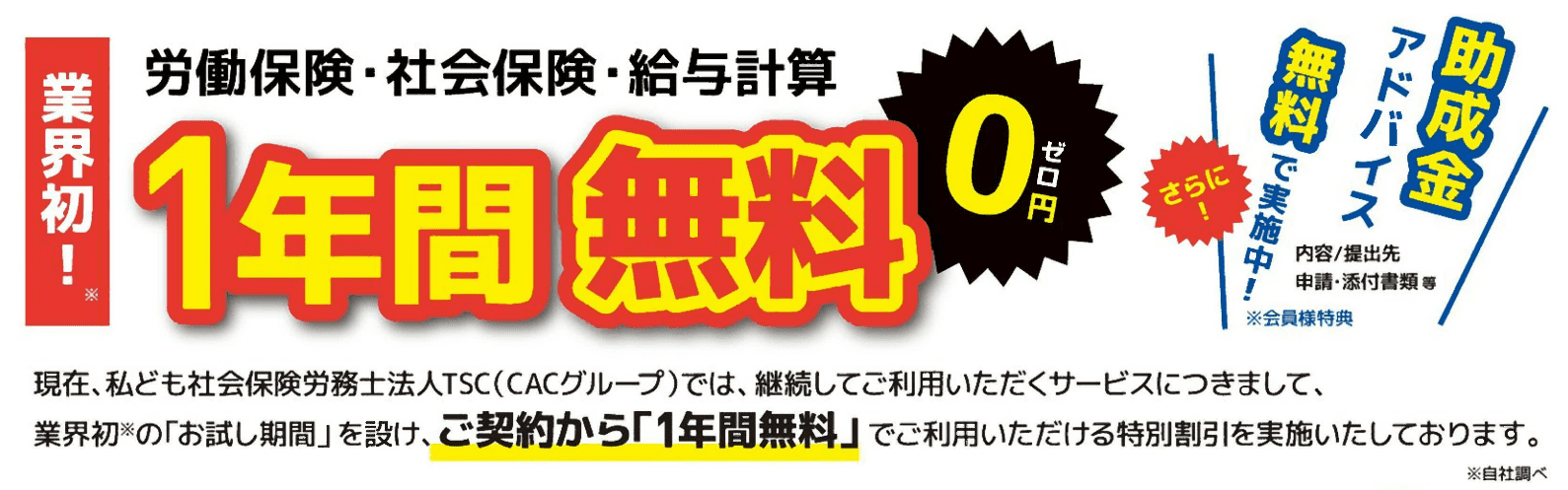 社会保険労務士法人TSCは1年間無料でサービス利用できる社労士です。そのため「お試しで社労士に依頼したい」という方にもおすすめです。社会保険や労務関係の業務を丸ごと委託できるだけでなく、助成金の相談もできます。全国に拠点があるため、エリアを問わずどんな企業様でも使いやすいのが特徴です。
社会保険労務士法人TSCは1年間無料でサービス利用できる社労士です。そのため「お試しで社労士に依頼したい」という方にもおすすめです。社会保険や労務関係の業務を丸ごと委託できるだけでなく、助成金の相談もできます。全国に拠点があるため、エリアを問わずどんな企業様でも使いやすいのが特徴です。
建設業における一人親方は社会保険について確認しておこう
ここまで、「一人親方の社会保険」というテーマで説明してきましたが、ご理解いただけましたでしょうか。税金や社会保険用語はそもそも難しいうえに、しっかりと定義づけしないと「同じ用語で実は別な説明をしている」というケースもありますから、注意が必要です。
今回の記事では、社会保険とひとくくりにしないで、各保険ごとに分解して説明したつもりです。文中でも触れましたが、保険加入が非常に有益なケースもありますから、十分吟味してご自身に必要なものに加入していただきたいと思います。
一人親方におすすめのクレジットカード5選!カード利用のメリットや申し込み時の注意点を解説!の記事はこちら
 一人親方におすすめのクレジットカード5選!カード利用のメリットや申し込み時の注意点を解説!
一人親方におすすめのクレジットカード5選!カード利用のメリットや申し込み時の注意点を解説!
今後建設業の一人親方はどうなる?方向性やインボイス制度についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
 今後建設業の一人親方はどうなる?方向性やインボイス制度についても
今後建設業の一人親方はどうなる?方向性やインボイス制度についても
※ちなみに弊社では、建築建設業界特化の
無料ホームページ制作代行を新たにスタートさせました! 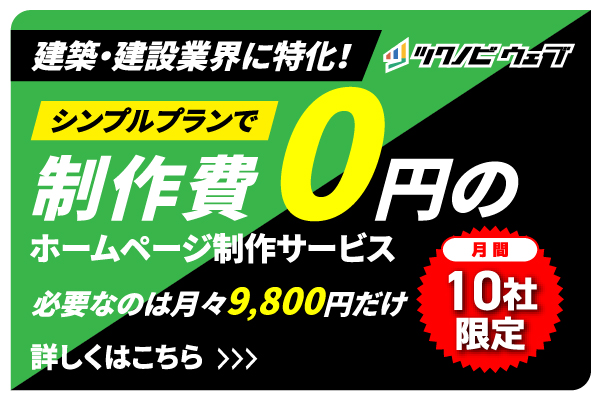 ※詳しくは👆👆👆のバナーをクリック!!
※詳しくは👆👆👆のバナーをクリック!!