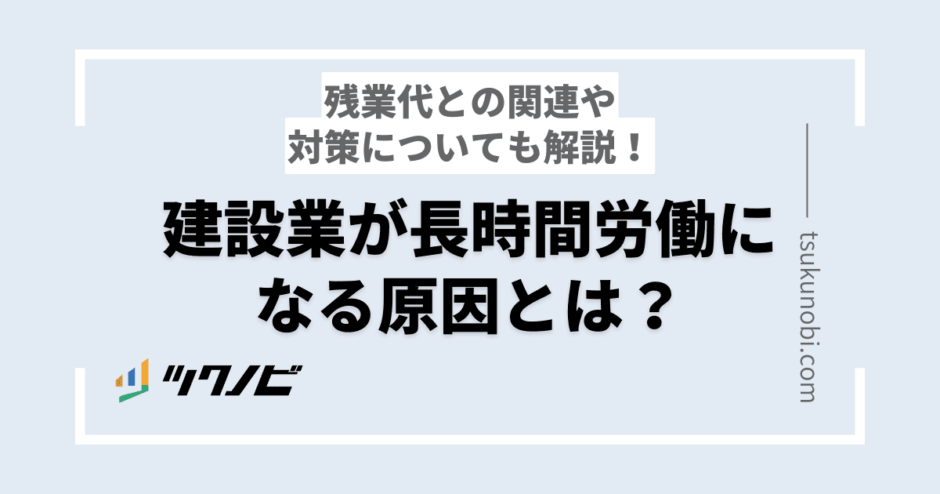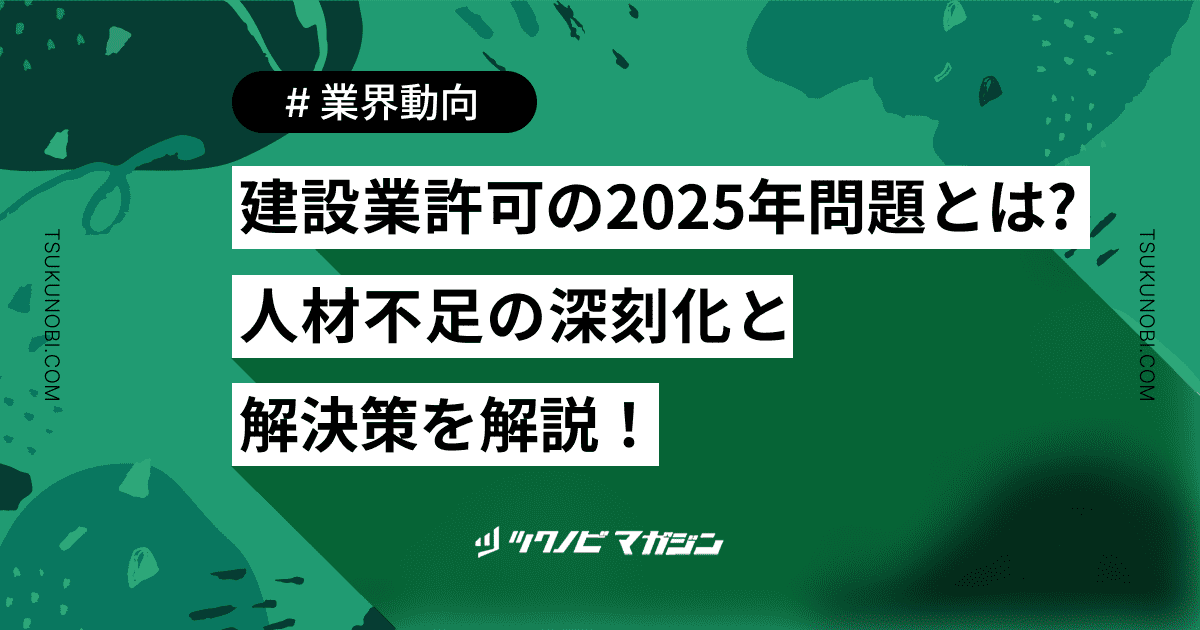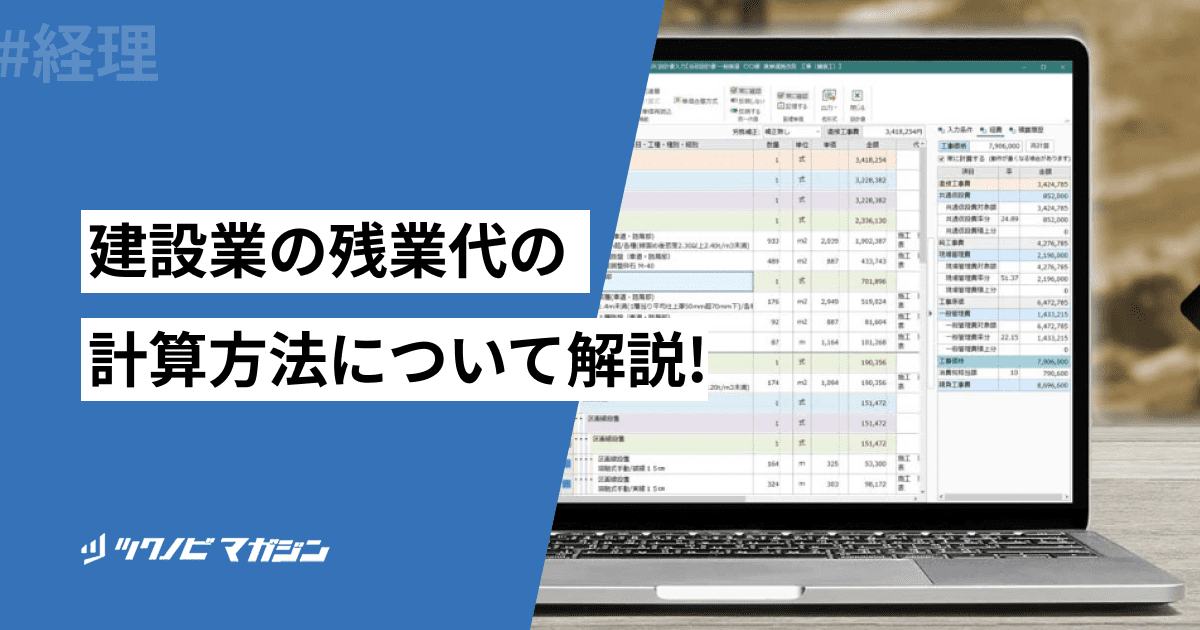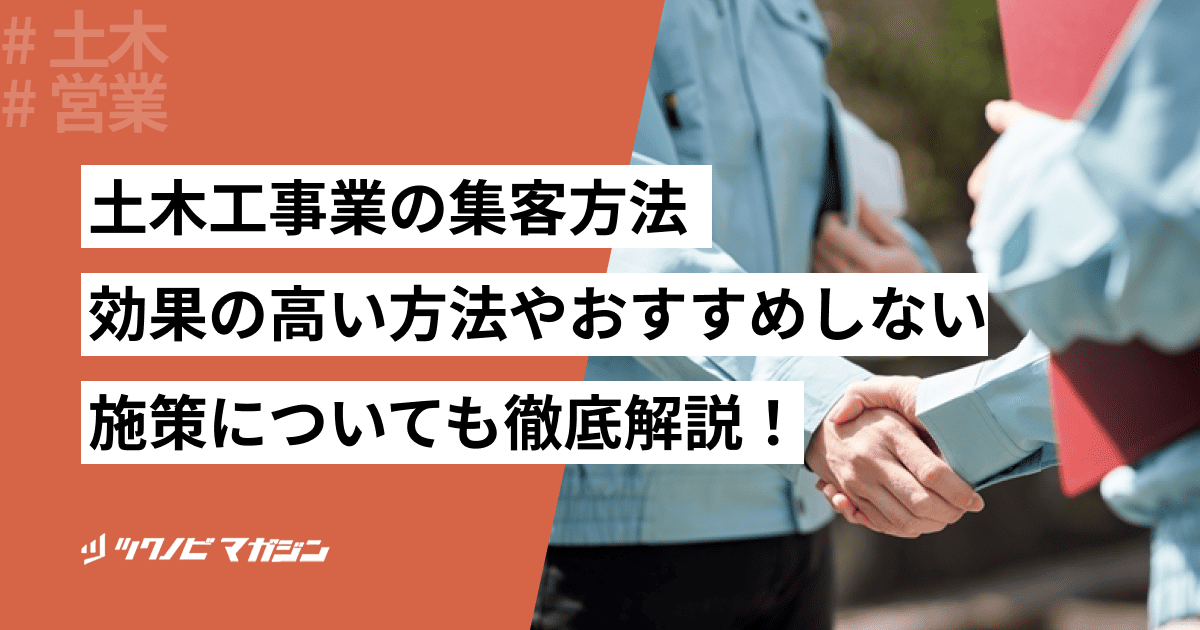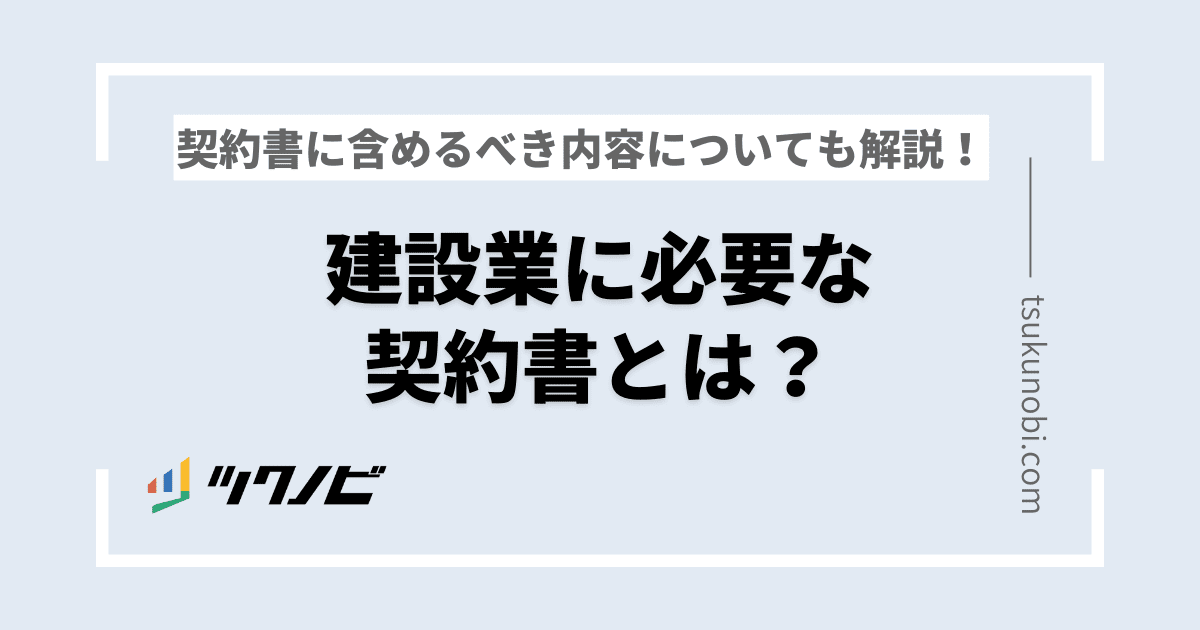※記事内に広告を含みます
「建設業はなぜ長時間労働が多いの?」
「長時間労働を改善したい!」
などと考えていませんか。
いきなり長時間労働を改善しようとしても、原因がわからなければ難しいですよね。
建設業の長時間労働は、休みが少ないことや人手不足の深刻化、工期の厳しさなど、様々な原因があります。長時間労働は残業代問題にも関連しており、原因を理解しきちんと対策するべきでしょう。
そこでこの記事では、以下の内容を解説します。
- 建設業の長時間労働が多い原因
- 建設業の長時間労働に対する「残業代」の問題点
- 建設業の長時間労働に対する対策
長時間労働の改善は、建設業の働き方改革につながるため、ぜひ最後までご覧ください。
建設業の長時間労働が多い原因
建設業の長時間労働が多くなる原因はいくつかあります。具体的にはどのようなことが原因で、長時間労働につながるのでしょうか。ここでは、建設業の長時間労働が多い原因を解説します。
原因1:休みが少ない
建設業はほかの産業と比べて、週休2日制の導入が遅れており、休日があまりありません。
2020年は、建設業全体で技術者のおよそ4割が、4週4休以下で働いています。
しかし、2015年は4週4休以下で働く人が、およそ7割でした。
それに比べれば、週休2日制の導入が建設業でも着実に進んでいるといえるでしょう。
原因2:人手不足が深刻化している
人手不足の深刻化も、建設業の長時間労働が多い原因の一つです。
建設業の平均就業者数
| 2018年 | 505万人 |
| 2019年 | 500万人 |
| 2020年 | 494万人 |
| 2021年 | 485万人 |
| 2022年 | 479万人 |
参考元:労働力調査(基本集計) 2024年(令和6年)平均結果|総務省
上記表を見ると、建設業の就業者数は、年々減少しています。
さらに建設業は、ベテランといわれる55歳以上の方が多数活躍中です。
2020年の建設業で働く人の割合は、55歳以上がおよそ36%、29歳以下がおよそ12%と、55歳以上がかなりの割合を占めています。
今後、ベテランの方々が退職するのに対して、10代や20代の若手はさらに不足していくでしょう。
人手不足が続けば、一人あたりの仕事量がおのずと増えてしまいます。
そして、仕事を終わらせるために残業をする悪循環に陥ってしまうのです。
原因3:工期が厳しい
次に、建設業の長時間労働が多い原因として、工期の厳しさがあります。
建設業は、主に工事の受注で成り立つ業界なので、工期の厳守が基本です。
工期を破れば会社の信用がなくなり、工事を発注されなくなる恐れがあります。
しかし、工期の厳守が必要ななか、建設工事は必ず計画通りに進むとは限りません。
悪天候で工事ができなかったり工事内容が変更になったりなど、想定外の事態で残業をしなければならないことがあります。
また、建設業は決算前や新年度前の12〜3月が繁忙期です。
短期間で数多くの工事をこなすために、残業が必要なこともあるでしょう。
原因4:36協定の残業上限が適用されない
建設業はほかの産業に比べて、人手不足や長時間労働の問題が深刻なことから、現在「36協定」の残業上限が適用されていません。
「36協定」とは、会社が労働者に法定労働時間(原則1日8時間、週40時間)を超えて残業させるために、締結・届け出をする労使協定のことです。
そして、その残業にも上限(原則月45時間、年360時間)が設けられています。(特別条項付きの場合は年720時間、複数月平均80時間、月100時間未満)
36協定の残業上限が適用されない建設業は、上限なしの残業が可能。
それにともない長時間労働が増えています。
ただし、建設業も2024年4月1日から36協定の残業上限が適用されます。(災害の復旧・復興の事業は除く)
建設業は、遅くても残業上限の適用前までに、長時間労働を改善するべきでしょう。
2024年4月からの残業規制にともない、建設業の従業員の給料が減る可能性があります。こちらの記事では、2024年問題で給料が減る可能性について解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
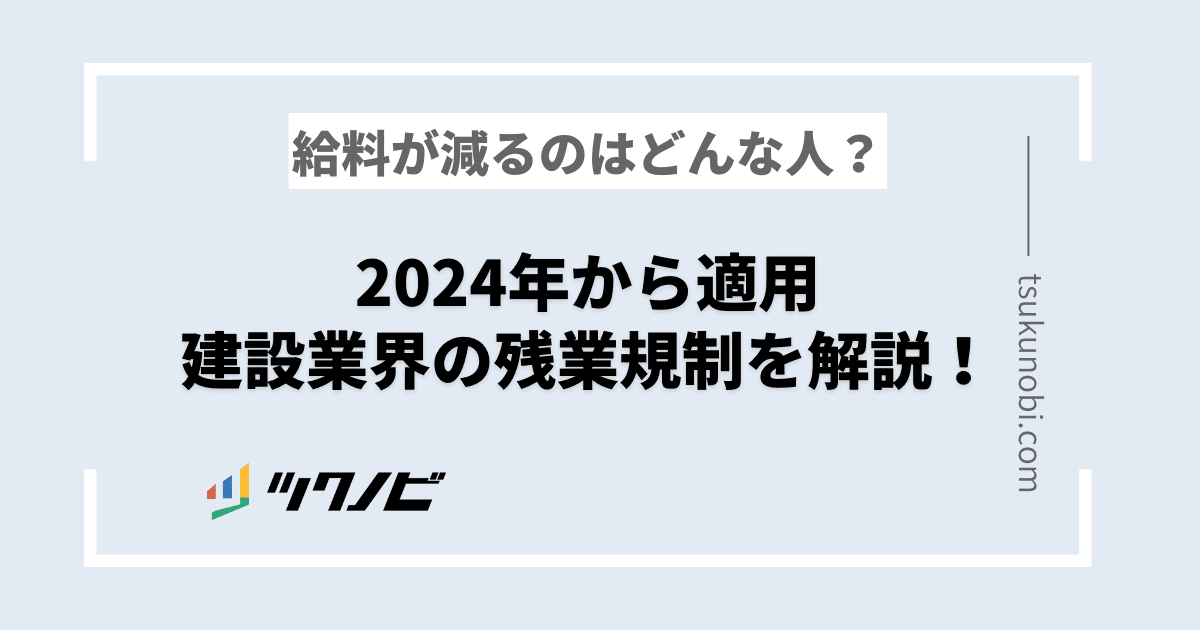 建設業界の残業規制(2024年問題)で給料が減る?給料が減る人の特徴も解説!
建設業界の残業規制(2024年問題)で給料が減る?給料が減る人の特徴も解説!
建設業の長時間労働に対する対策
建設業の長時間労働は、上手に対策することで改善できます。ここでは、建設業の長時間労働に対する対策を解説します。
対策1:工期設定を見直す
長時間労働の改善には、工期設定の見直しが大切です。
2020年10月に施行された改正建設業法では、著しく短い工期による工事の発注・受注を禁止しています。
発注者は、建設工事で働く人の休日や資材・機材の調達期間、天候などを考慮し、無理のない工期を提示しなければなりません。
受注者も、短期工事をアピールして無理に工事を受注しないよう注意するべきでしょう。
また、施工内容が不明確だと、工事のやり直しや計画変更で長時間労働につながる恐れがあります。
施工前の現場調査や打ち合わせを入念に行い、施工内容を明確にしておきましょう。
対策2:業務を外注する
業務の外注は、建設業の長時間労働を軽減する有効な方法です。
外注を活用すれば業務量を分散でき、社員の負担を減らせます。特に専門性が高い業務や単純作業を委託すれば、限られた人員を主要業務に集中させられます。
また、外注先の技術や設備を活用すると、工期短縮や品質向上も可能です。さらに、繁忙期だけ外注を増やす体制を整えれば、人件費の変動リスクを抑えつつ生産性を高められます。
業務を外注すると、社員のワークライフバランス改善にもつながります。
対策3:週休2日制を導入する
週休2日制導入は、建設業の長時間労働削減に直結します。
週2日の休暇を確保すれば労働時間を抑えられ、心身の疲労回復も可能です。休養による集中力の維持は、作業効率や安全性の向上にもつながります。
また、働きやすい環境は若手や女性の採用にも有利で、人手不足の緩和に効果的です。導入時は現場工程や契約条件を調整し、無理のないスケジュールを組みましょう。
さらに、取引先や元請けと連携して工期を見直すことで、制度の定着と離職率低下が期待できます。
対策4:施工管理システムを導入する
最後に、長時間労働の対策として、施工管理システムの導入があります。
施工管理システムを導入すれば、スマートフォンやタブレットを使って、日報や現場全体の進捗を会社に戻ることなく確認できます。
また、現場の写真をリアルタイムで共有可能です。
管理部門とのやりとりもスムーズに行えるでしょう。
施工管理システムの導入は、現場の技術者や管理者の手間が減り、業務の効率化や長時間労働・休日出勤の防止につながります。
対策5:給与設計を見直す
給与設計の見直しは、建設業の長時間労働改善に効果的です。残業時間に依存する給与体系では、労働時間が増えやすくなります。
基本給の引き上げや成果・技能に応じた評価制度を導入すれば、時間ではなく成果で報われる仕組みを構築できます。
さらに、インセンティブや資格手当を設ければ、労働意欲の向上が期待できます。固定残業代制度の見直しや実労働時間に応じた支給を徹底することで、不要な残業の抑制にもつながります。
対策6:デジタル技術を導入する
デジタル技術導入は、建設業の業務効率化と長時間労働削減に直結します。
BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)やドローン測量を活用すれば、現場作業や図面管理の効率が向上します。
さらに、クラウド型施工管理ツールを導入すれば、進捗や資材状況をリアルタイムで共有でき、移動や確認の時間を削減が可能です。
事務作業の短縮と現場の意思決定の迅速化が実現します。加えて、AIによる工程予測や安全管理システムを活用することで、無駄な作業やトラブルを未然に防げます。
デジタル技術を導入すると、労働時間を抑えながら生産性を高められます。
建設業の人手不足解消ならツクノビBPOがおすすめ
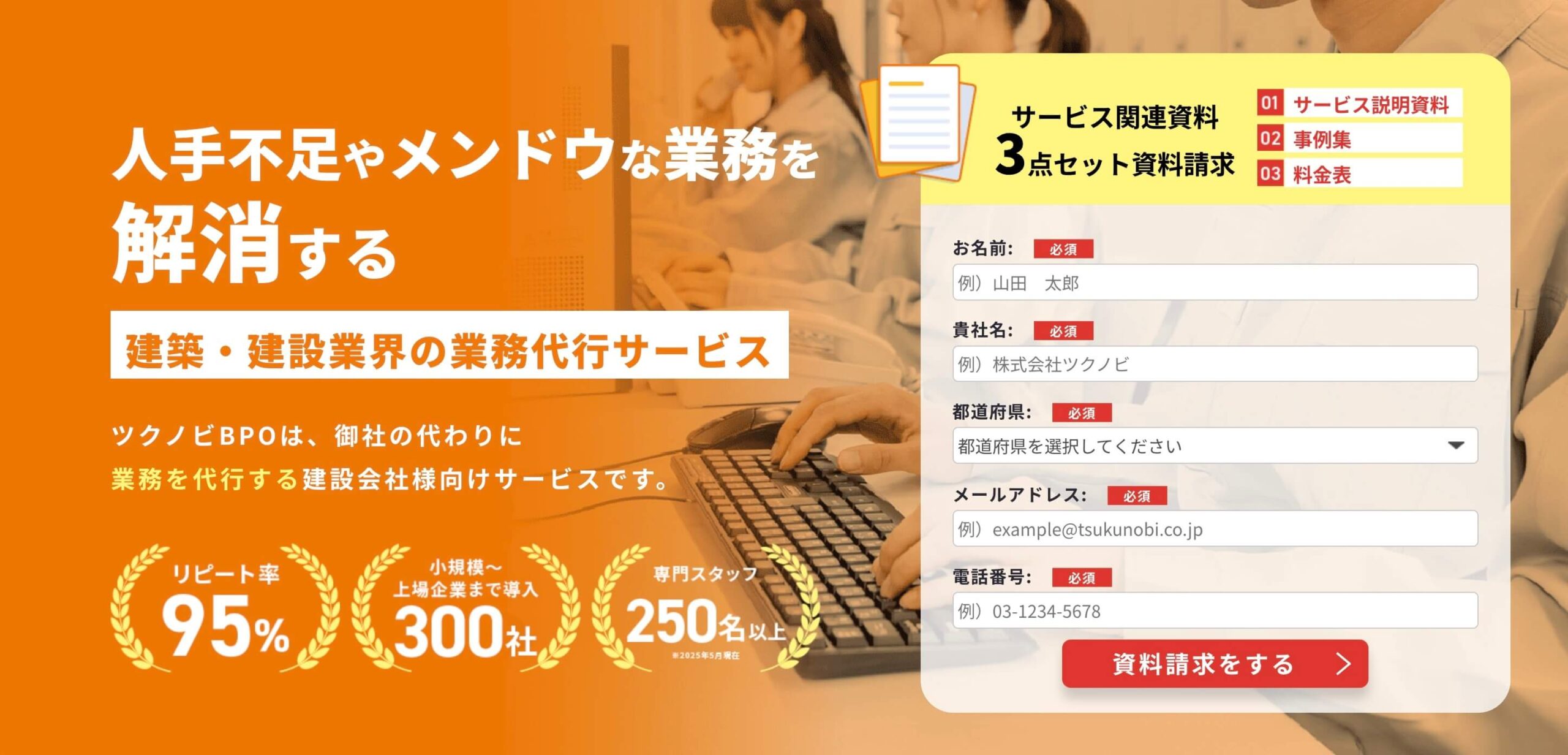
建設業の人手不足を解消するためには、アウトソーシングサービスの利用もおすすめです。
従業員のリソースがひっ迫している場合や、業務に対応できる人材が不足している場合などは、アウトソーシングサービスを活用すると、少ない工数で業務を実行できます。BPOサービスでは、専門的な知識を持っているスタッフが対応するため、さまざまな業務をスムーズに進められます。
弊社では、建設業の業務に対応している建設業特化のBPOサービス「ツクノビBPO」を提供しています。書類作成や図面の作成、積算業務など、幅広い業務を代行できます。ツクノビBPOでは、倍率200倍の選りすぐりの専任スタッフが対応いたします。
リソース不足を解消したい方は、ぜひこちらからお問い合わせください。
建設業の長時間労働を改善する時間外労働の上限規制とは
建設業の長時間労働を改善するには、時間外労働の上限規制を正しく理解し、遵守しましょう。
この制度は過剰な労働時間を抑え、労働者の健康と安全を守るために設けられています。2024年から適用された上限の具体的内容や違反時の罰則について、以下で詳しく解説します。
2024年から適用された時間外労働の上限規則
2024年から建設業にも時間外労働の上限規制が適用され、原則は月45時間以内、年360時間以内です。
繁忙期などでこの枠を超える場合は、労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)を締結し、労働基準監督署長へ届け出ることで特別条項を利用できます。
特別条項の適用時でも、年間720時間以内、2〜6ヶ月平均80時間以内、月100時間未満(休日労働含む)、月45時間超は年6回までといった条件が課されます。
災害復旧や復興の場合は、2〜6ヶ月平均80時間以内や月100時間未満の条件は適用除外です。
時間外労働の上限規制に違反した際の罰則
時間外労働の上限規制に違反すると、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
長時間労働が常態化すると従業員の健康リスクが高まり、労働環境への不満も蓄積します。
その結果、離職率の上昇や採用難につながる恐れがあります。
さらに、法令違反は企業の社会的評価を損ない、取引先や顧客からの信頼を失う要因にもなります。そのため、企業は規制遵守の体制を整え、適切な労務管理と働き方改革を着実に進めることが重要です。
【まとめ】建設業が長時間になる原因は工期設定や人手不足による!対策についても要チェック!
建設業の長時間労働は、厳しい工期設定や深刻な人手不足などが原因です。
さらに、36協定の残業上限に関する間違った解釈などが、残業代が支払われない問題にもつながっています。
36協定の残業上限は、2024年4月1日から建設業にも適用されるため、長時間労働は早急に改善するべきでしょう。
長時間労働は、工期設定の見直しや施工管理システムの導入で改善が期待できます。
ぜひ、長時間労働を改善して、建設業の働き方改革を目指してみてください。
建設業の2025年問題や建設業の残業代の計算方法についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。