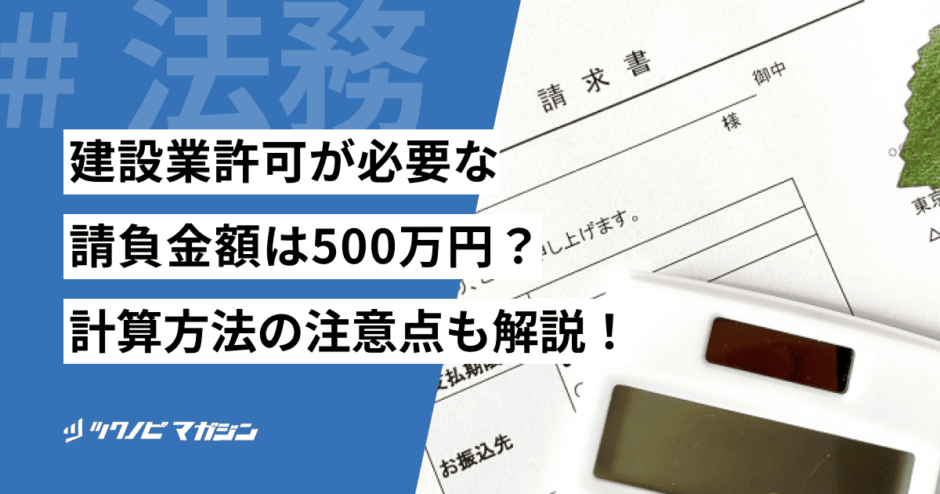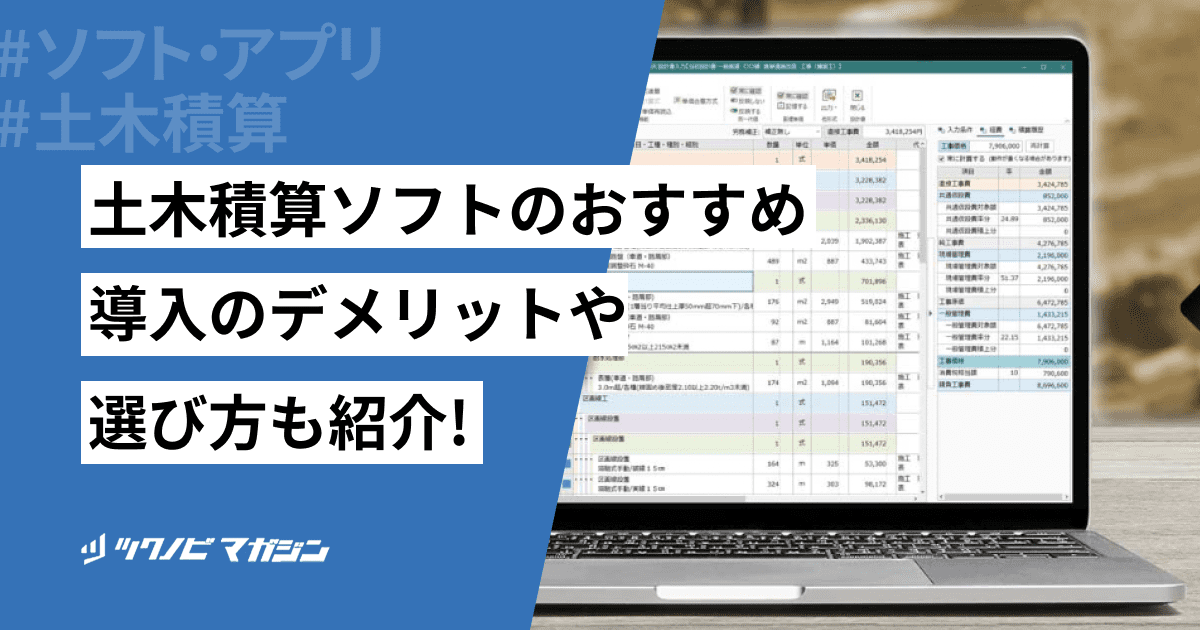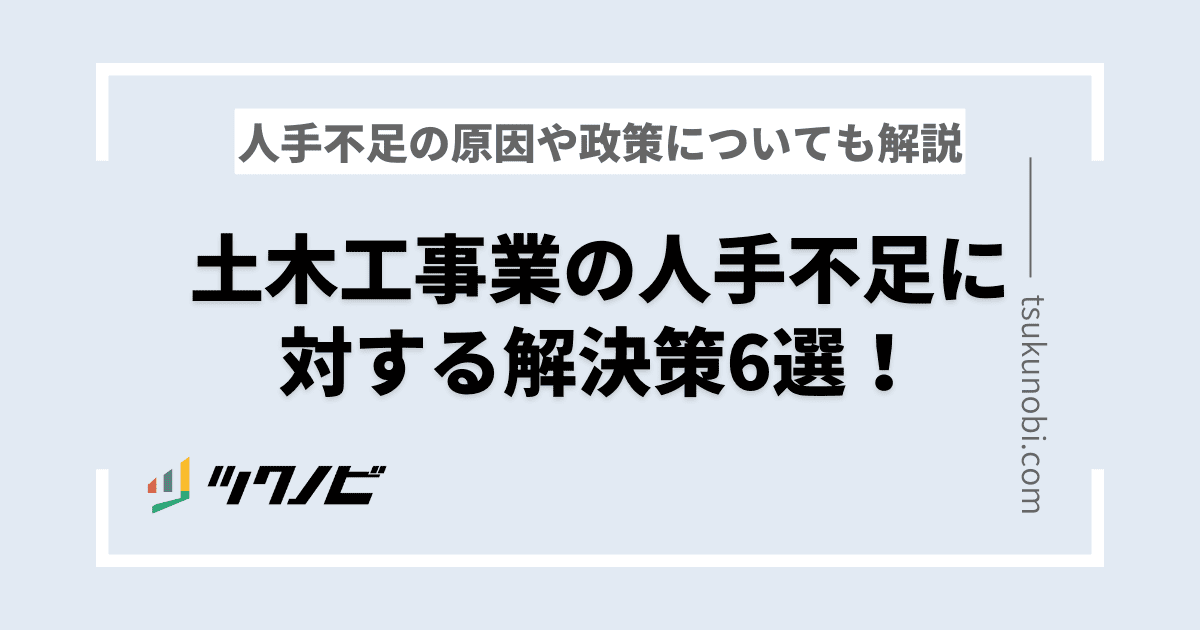※記事内に広告を含みます
建設業許可が必要となる工事の請負金額をご存知でしょうか?「請負金額が500万円以上の場合は必要」というざっくりとした知識は持っている方も多いかと思います。
一方、自分の専門工事は500万円基準に該当するのか?消費税や材料代は含まれるのか?など細かい基準までは知らないという方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、建設業許可が必要になる基準と建設業許可を受けるために必要なことについて解説します。
建設業許可なしで工事を行なった際のペナルティやペナルティを受けないための注意点についてもまとめたので、これから建設業許可を取得しようと考えている方はぜひ参考にしてください。
建設業許可に関する基礎知識
建設業を営む者は「建設業許可」を受けなくてはならないと法律で定められています。ただし、すべての工事に必要というわけではありません。
「軽微な建設工事」のみを請け負う場合、建設業許可が無くても工事を請け負うことができます。この章では、建設業許可が必要なケースと不要なケースについて解説します。
参照: 「建設業法」
この記事では、建設業許可の詳細についてより詳しく解説しています。
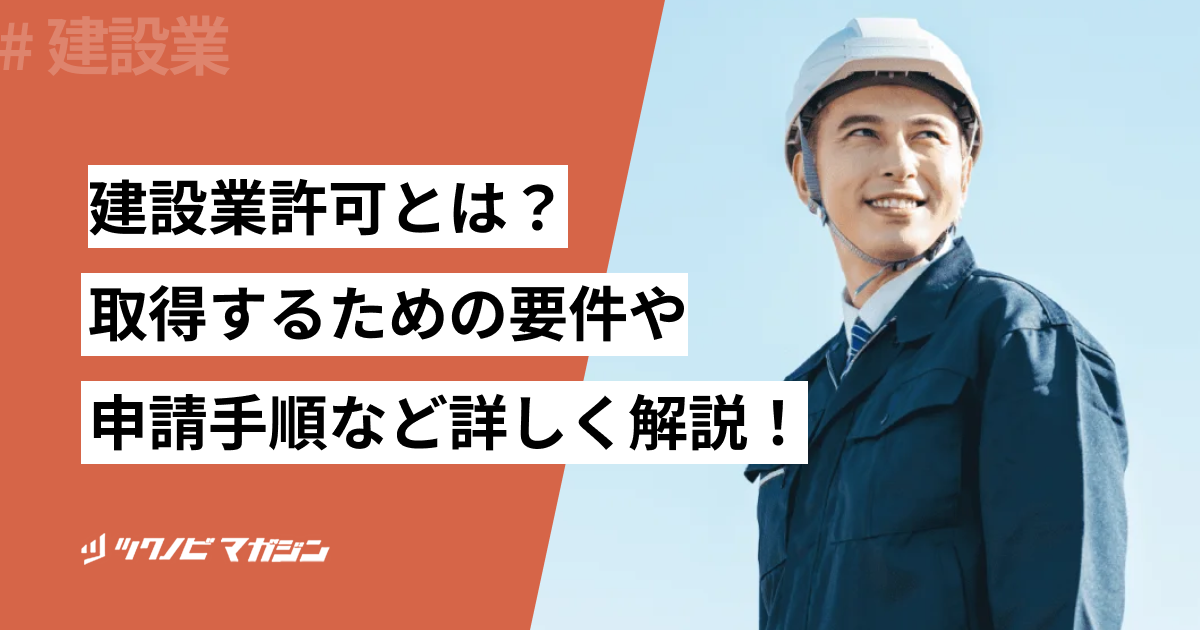 建設業許可とは?取得するための要件や申請手順などを詳しく解説
建設業許可とは?取得するための要件や申請手順などを詳しく解説
軽微な建設工事とは
軽微な建設工事の場合、建設業許可を受ける必要はありませんが、そもそも、軽微な建設工事とはどのような工事のことを指すのでしょうか?
軽微な建設工事は、以下の2つの場合に分けて定義づけされます。
- 建築一式工事の場合
- 建築一式工事以外の場合
それぞれの場合における軽微な建設工事の定義について解説します。
参照: 「国土交通省 建設業の許可」
建築一式工事の場合
建設一式工事の場合、以下の2つが軽微な建設工事と定められています。
- 1工事あたりの請負金額が1,500万円未満の工事
- 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事(延べ面積の2分の1以上が居住用であること)
建設一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもと、建築物を建設する工事のことです。具体的には、建築確認(建物や地盤が建築基準法や各市町村の条例などに適合しているか工事前に確認する行為)を必要とする新築工事や増改築、大規模建築工事のことなどを指します。
建築一式工事以外の場合
建築一式工事以外の場合、以下の場合が軽微な建設工事と定められています。
- 1工事あたりの請負金額が500万円未満の工事
請負金額が500万円未満の場合は、建設業許可が必要ないという結論となります。ただし、請負金額を計算する際にはいくつか注意点があります。
請負金額を計算する際の注意点については後ほど解説します。
建設業許可を受けるには500万円以上の財産的基礎が必要
建設業許可は申請すればどの会社でも通るというわけではありません。建設業許可を申請する直近の「事業年度決算書」を基に審査され、財産的基礎の有無によって判断されます。
財産要件の基準となる500万円の計算方法は【資産-負債】です。財産的基礎が500万円以上なければ審査の対象外となるため、申請前に確認しておきましょう。
財産的基礎の確認をするには、貸借対照表の右側に記載されている「純資産の部」をチェックしてください。純資産の部の金額が500万円以上であれば、建設業許可の申請要件に当てはまっていると覚えておきましょう。
また、以下の場合も財産的基礎があると認められます。
- 500万円以上の資金調達能力を有すること
- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
請負金額を計算するときの注意点
建設業許可を受けないで500万円以上の工事をおこなった場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。
では、500万円未満の工事なら絶対にペナルティを受けないのかと問われると、そうとは限りません。そこでこの章では、建築業法に違反してペナルティを受けないための注意点を詳しく解説します。
請負契約は分割せずに合算する
正当な理由が無い限り、1件の契約を分割して2件以上にしてしまうと建設業法にひっかかりペナルティを受けます。
たとえば、600万円の工事を請け負ったのに、契約を分割して300万円の工事を2件請け負ったことにしてしまう。これはアウトです。
建設業法施行令(第一条の二第2項)では、契約を分割して請け負う際は各契約の合算を請負金額とする、となっているため、上記の例のように契約を分割することはできません。
また、下記のようなケースは、軽微な建設工事に該当しないため注意が必要です。
- 工期が長く断続的に500万円未満の工事を3件請け負ったが、合計すると500万円以上になる場合
- 複数の工種がある契約で、それぞれの請負金額は500万円未満だが、合計すると500万円以上になる場合
- 雑工事など断続的に500万円未満の小さな工事を5件請け負ったが、合計すると500万円以上になる場合
なお、建設業法の許可を免れるためではないということを十分に証明できる場合に限り、正当な理由として契約を分割することが認められます。
請負金額には材料費・運送費も含める
請負金額には材料費・運送費も含める必要があります。たとえば元請け業者から材料を無償提供される場合もありますが、請負金額は材料費も含めて計算するよう定められています。工事を請け負う際は、材料費及び運送賃を含めた金額で建設業許可が必要かどうかを判断してください。
請負金額には消費税も含める
消費税についても同様です。建設業許可の請負金額は、消費税を含んだ金額のことを指します。消費税は含まないものと間違った解釈をして工事を請け負った場合、建設業法にひっかかりペナルティの対象となります。
建設業許可なしで500万円以上の工事を行った際のペナルティ
もし建設業の許可なしで工事をおこなった場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。建設業法の中でも重い罰則となっています。
また、建設業許可を受けている元請け業者が、無許可の下請け業者に500万円以上の工事を発注して、下請け業者が受注した場合には、下請け業者は建設業法に違反したとして罰金などのペナルティを受けることがあります。
【まとめ】500万円以上の請負契約には建設業許可が必要!法令を遵守して操業しよう
500万円以上の工事を請け負うには、建設業許可を取得する必要があります。もし、無許可で工事をおこなった場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられるため注意が必要です。
都道府県知事許可の一般申請の場合、申請手数料として9万円前後かかります。しかし、間違った認識でペナルティをくらうことや500万円未満の軽微な工事しか請け負えないことを考えたら、それほど大きな支出ではないと言えるでしょう。
建設業許可を受けて、事業拡大や自社の信頼性アップにつなげてみてはいかがでしょうか。