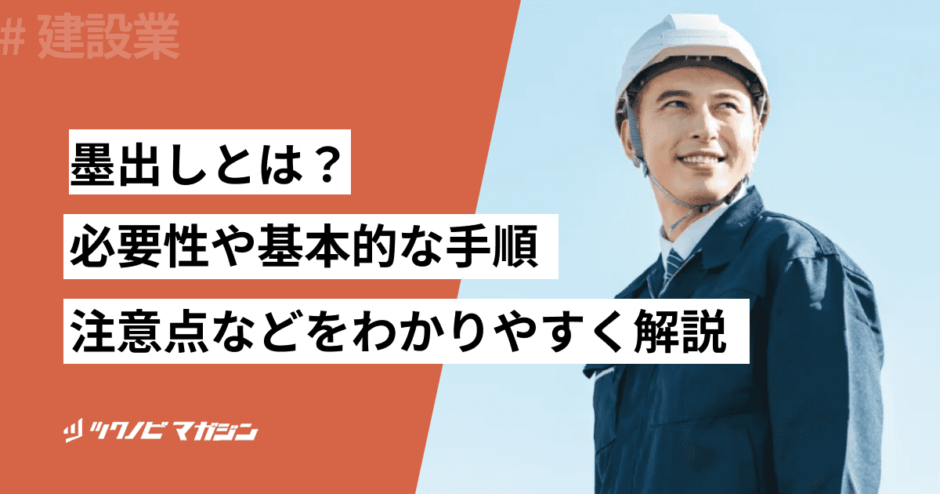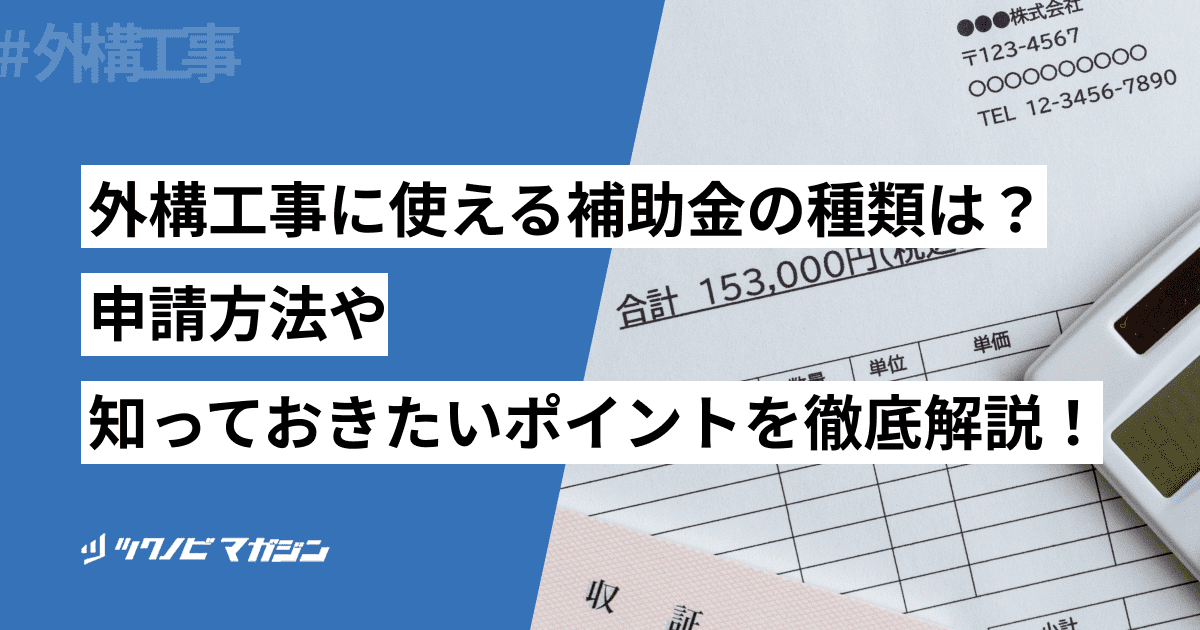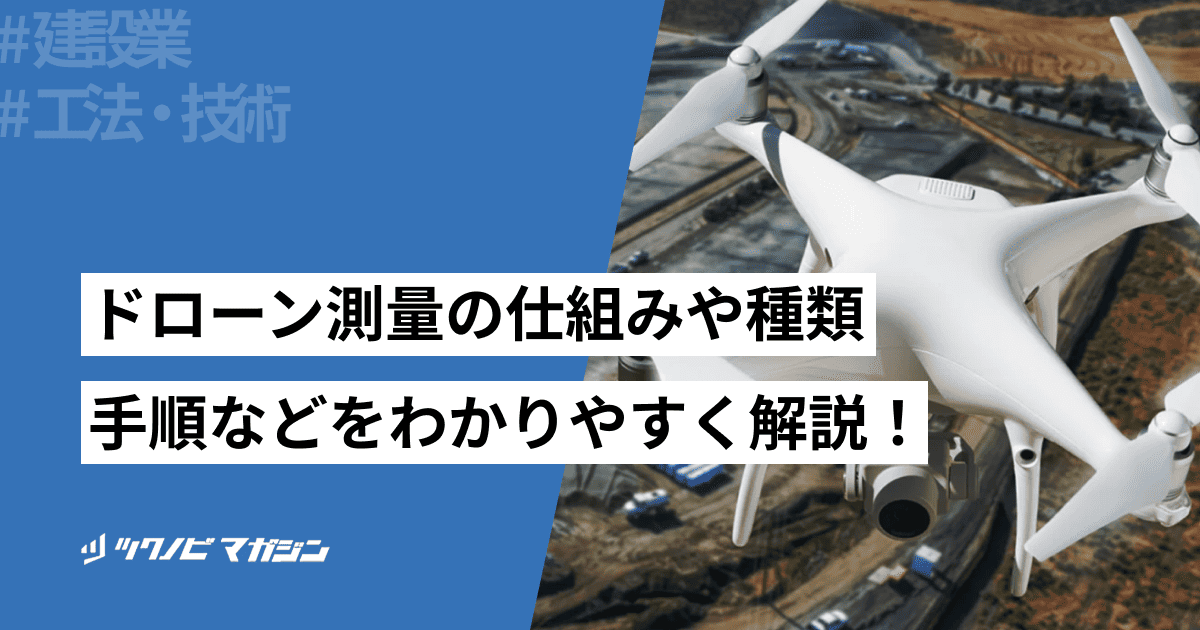※記事内に広告を含みます
建築や土木工事では、様々な作業を行います。そのなかでも必ずといっていいほど行われる特殊な作業が、墨出しです。
建造物を作る際重要な役割を果たす墨出しですが、そもそもなぜ行われるのか理解していない方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は、墨出しに関する基本的な知識をまとめました。
墨出しの目的から具体的なやり方・必要な道具などを解説しています。作業の重要性を理解したい方はもちろん、より効率的に作業したい方にも役立つヒントを盛り込みました。興味を持たれた方は、ぜひご覧ください。
墨出しとは
墨出しとはなぜ必要なのでしょうか。作業内容や必要性を解説するので、作業の意味を再確認しましょう。
墨出しは工事に必要な線や印をつける作業
墨出しとは建築や土木工事の際に、施工図の情報を現場に反映させる作業です。以下の建材や構造物に作業中必要な水平位置や中心位置を記入します。
- 木材をはじめとした建材
- 壁や柱
- 床や天井
これらの位置を正確かつ安全に把握・施工するには、設計図の内容を正確に反映しなくてはなりません。工事の内容や種類を問わず行われるのは、このためです。
墨出しの必要性
建築や土木工事は、必要な建材を設計図通りの位置に移動・設置したうえで施工します。少しでもずれると、正しい建造物は作れません。また、施工内容によっては、ほんの少しのずれが大きな事故を引き起こす恐れもあります。
これを避けるためには設計図通りの施工が必要ですが、1回1回設計図を見ながらの作業は非常に非効率です。また、複数の作業員で異なる作業を同時に進行させるには、明確な基準を設けなくてはなりません。
その都度設計図を確認しなくても、建材や構造体などに施工に必要な情報を分かりやすく記入すれば効率的に改善できます。このことから、墨出しは建造物の品質を保ち、効率的かつ安全に施工するのに欠かせない作業であるといえます。
基本的な専門用語の意味
墨出しに使う墨には様々な種類があります。工事において何度も使われるうえに様々な所に記入される関係から、状況に応じて名前が付けられています。ここでは主に活用されているものを解説しますので、覚えておきましょう。
親墨
最初に打つ墨です。柱や壁の位置を示すのが目的で、施工図にかかれた通り芯を親墨とします。一般的には、このあと解説する陸墨や芯墨が親墨として扱われます。
子墨
躯体工事や仕上げ工事で使われる墨です。親墨を基準にし、柱や壁・健具や金物などの位置を示します。
陸墨
現場各階の水平を表す墨で、基準となる高さを示します。主に床の高さを示す際に使われる墨です。陸墨より上に打つ墨を上り墨・下に打つ墨を下がり墨といいます。
芯墨・心墨・真墨
柱や壁の中心を指す墨で、組立の精度を向上させる目的で打ちます。複数の名前がありますが、どれも同じ意味です。
逃げ墨・返り墨
障害物などがあると、墨出しが必要なのにできない箇所が発生します。このとき、該当の個所から少し離れた場所に示すのが、逃げ墨または返り墨です。一定の距離に打たれることが多く、以下のような形で示されます。
- ヨリ1,000(1m)
- 500返り(50cm)
墨は必ずしも該当箇所のみ打たれるわけではないことも覚えておきましょう。
墨出しの手順
墨の種類を把握したら、次は作業手順を身につけましょう。墨出しの手順について解説します。
基本的な手順
墨出しは基本的に、行政が定める共通仕様書や特記仕様書に従って行います。これは公共・民間工事ともに変わりません。基本のやり方は、以下の流れの通りです。
| 墨出しの手順 | 作業内容 |
| 1.親墨出し |
|
| 2.型枠用小墨出し | 躯体コンクリートの位置表示 |
| 3.型枠建込中の墨出し | 以下の墨出し
|
| 4.鉄骨アンカーボルト |
|
| 5.躯体工事中におけるそのほかの墨出し |
|
| 6.仕上基準墨出し |
|
| 7.仕上げ細部墨出し |
|
| 8.設備関連墨出し |
|
これらの作業は、基本的に2人1組で行います。片方が墨を吸わせた綿が入った墨壺をもち、もう片方が綿に通して墨で染めた糸の先端をもって墨を出す形で作業します。
1人で作業する場合
墨出しは基本的に複数人で行います。しかし、作業員の人数が足りない場合などは、1人で行わなくてはなりません。このような場合、片方の作業員がもっていた糸の先端を、自分の足や釘で固定しながら行います。
ちなみに、レーザーラインをもとに墨出しができるレーザー墨出しと呼ばれる機器があれば、水平や高さを測りながら作業できます。導入しておけば効率的な作業が可能です。墨出し作業にかかる業務上のコストを削減したい場合は、導入をおすすめします。
墨出し作業で使用する道具
墨出し作業では、専用の道具を使いながら行います。墨出しで使用する道具の特徴や仕組みもあわせて覚えておきましょう。
専門道具
専門的な道具としては、以下の道具があげられます。
| 名称 | 機能 |
| 墨壺 | 墨を含んだ綿が入った壺と伸びる糸で構成されている道具
墨が染みた糸をはじいて壁や柱に線を引く |
| 糸巻き | 作業に使う糸を巻き付けておく道具 |
| 下げ振り | 糸に重りをぶら下げて垂直を確認する道具 |
| 墨差し | 墨汁を含ませ線を引くヘラ状の道具 |
| レーザー墨出し | 本体にレーザー光を出す機能が搭載された墨壺
レーザーラインをもとに線を引く部分を示しながらできるため、効率的かつ正確に墨出しができる |
| チョークライン | 墨壺同様、壁や柱に基準線を引く道具
墨ではなく粉チョークを使うため、あとで消せる |
一見同じような使い方をする道具でも、それぞれ特徴が異なります。利用する際は道具ごとに異なる使い方や特徴をおさえておきましょう。
おすすめは「VOICE 5ライン グリーンレーザー墨出し器」
VOICE 5ライン グリーンレーザー墨出し器は、楽天ランキング4冠獲得しているレーザー墨出し器です。レーザー墨出し器は高額なものだと10万円以上するのが一般的です。しかし、この製品は4万円程度でかつ性能も高いのが特徴です。
一般的な道具
墨出しでは一般的な道具も使いながら作業します。
- 図面や特記事項の書かれた資料
- 測量機
- 水平器
- 差し金
- レベル
- ほうき
- カッター
- スケーラー
- スケールまたはメジャー
- ヘッドライト
- 建築用筆記具
- 養生に使うシートやテープ
効率的に作業するためにも、専門的な道具と一緒にこれらの道具も用意したうえで取りかかりましょう。
墨出し作業をするときの注意点
墨出しは建築物の品質や作業の効率・安全を守るために欠かせない作業です。ただ作業するのではなく、以下の注意点を意識しながら行う必要があります。墨出し作業時の注意点も、欠かさずおさえておきましょう。
線はわかりやすく引く
分かりにくい線は施工中の作業員のミスややり直し・読み取りにかかる時間のロスなど、様々な問題を招く要因です。作業中は、パッと見てわかりやすい線を引くよう意識しましょう。
分かりやすい栓を引くためには、道具をきれいな状態で管理し、正しく使うことが大切です。普段から道具の手入れや使い方を復習しておきましょう。
修正は速やかに行う
墨出しは正確性の求められる作業です。ミスをしてしまった場合は、速やかに修正しましょう。間違った線には大きくバツ印を入れてください。併せて正しい線にもマル印をつけておきましょう。
ミスをそのままにしておくと、ほかの作業でもミスを招いてしまいます。最悪の場合、すべての工程でミスが発生する事態になりかねないため、ミスの修正は迅速かつ正確に行いましょう。
工事する場所以外に汚れや傷をつけない
墨出しは汚れや傷が発生する作業でもあります。余計な汚れや傷は、作業の被効率化や事故を引き起こす要因です。作業が必要な箇所以外に傷や汚れがつく場合は、事前にシートやテープなどで養生しましょう。
 レーザー墨出し器おすすめランキング15選!選び方なども解説
レーザー墨出し器おすすめランキング15選!選び方なども解説
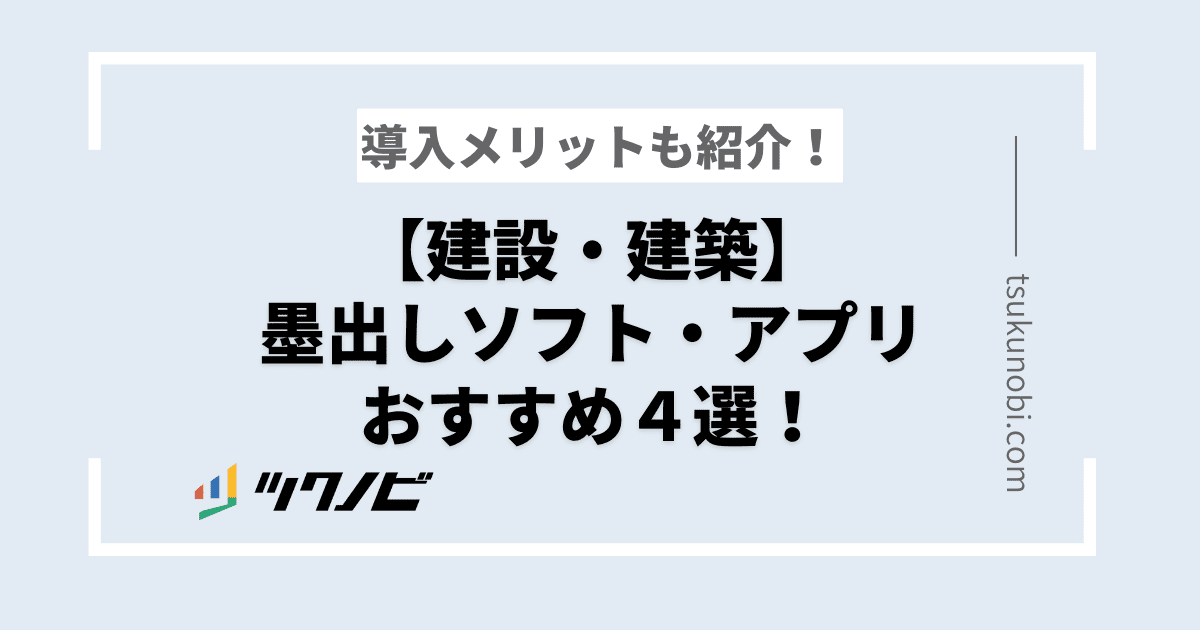 【建設・建築】墨出しソフト・アプリおすすめ4選!導入メリットも紹介!
【建設・建築】墨出しソフト・アプリおすすめ4選!導入メリットも紹介!
建設業の人手不足解消ならツクノビBPOがおすすめ
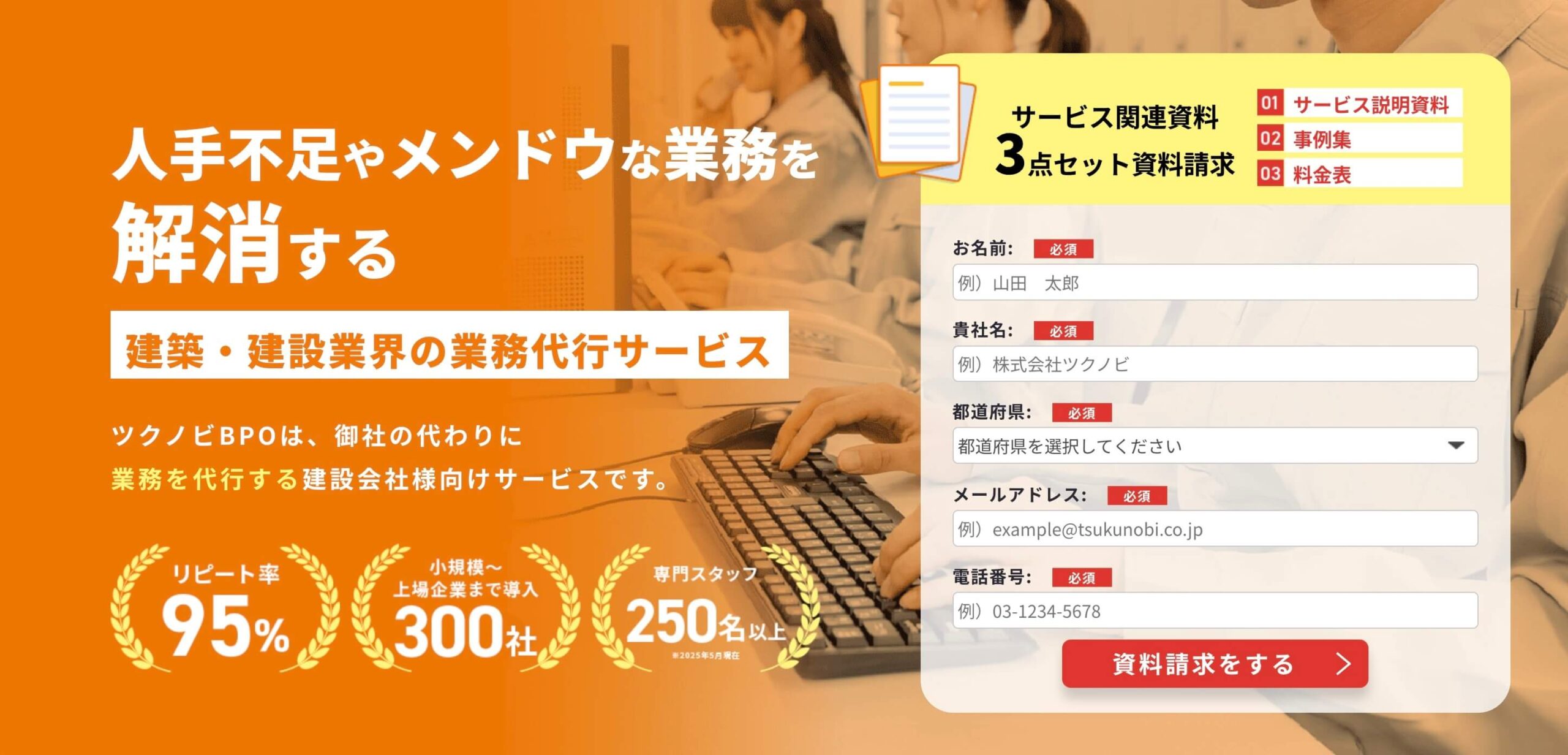
建設業の人手不足を解消するためには、アウトソーシングサービスの利用もおすすめです。
従業員のリソースがひっ迫している場合や、業務に対応できる人材が不足している場合などは、アウトソーシングサービスを活用すると、少ない工数で業務を実行できます。BPOサービスでは、専門的な知識を持っているスタッフが対応するため、さまざまな業務をスムーズに進められます。
弊社では、建設業の業務に対応している建設業特化のBPOサービス「ツクノビBPO」を提供しています。書類作成や図面の作成、積算業務など、幅広い業務を代行できます。ツクノビBPOでは、倍率200倍の選りすぐりの専任スタッフが対応いたします。
リソース不足を解消したい方は、ぜひこちらからお問い合わせください。
【まとめ】墨出しは工事に必要な基準線を書き出す作業!正確に行おう
墨出しは建造物の品質を守り、作業を効率的かつ安全に進めるために欠かせない作業です。作業中は正確性を意識しながら取りかかりましょう。また、よりスムーズに作業を進めたいなら、便利な道具の導入もおすすめです。
ただ作業するのではなく、より正確に、効率的に行うにはどうすればいいかをよく考えながら取り組みましょう。
※弊社の営業代行サービスであるツクノビセールスでは、
【効果が出なければ全額返金プラン】を新たにスタートさせました!

※詳しくは👆👆👆のバナーをクリック!!