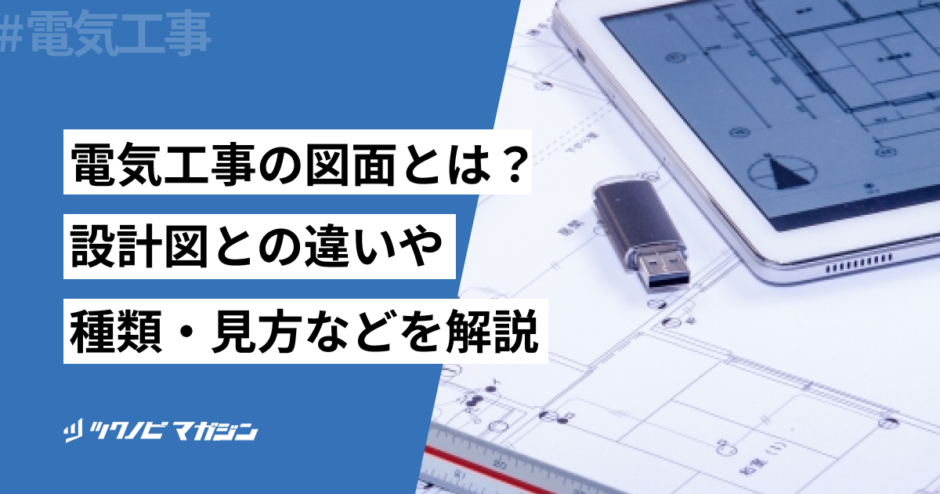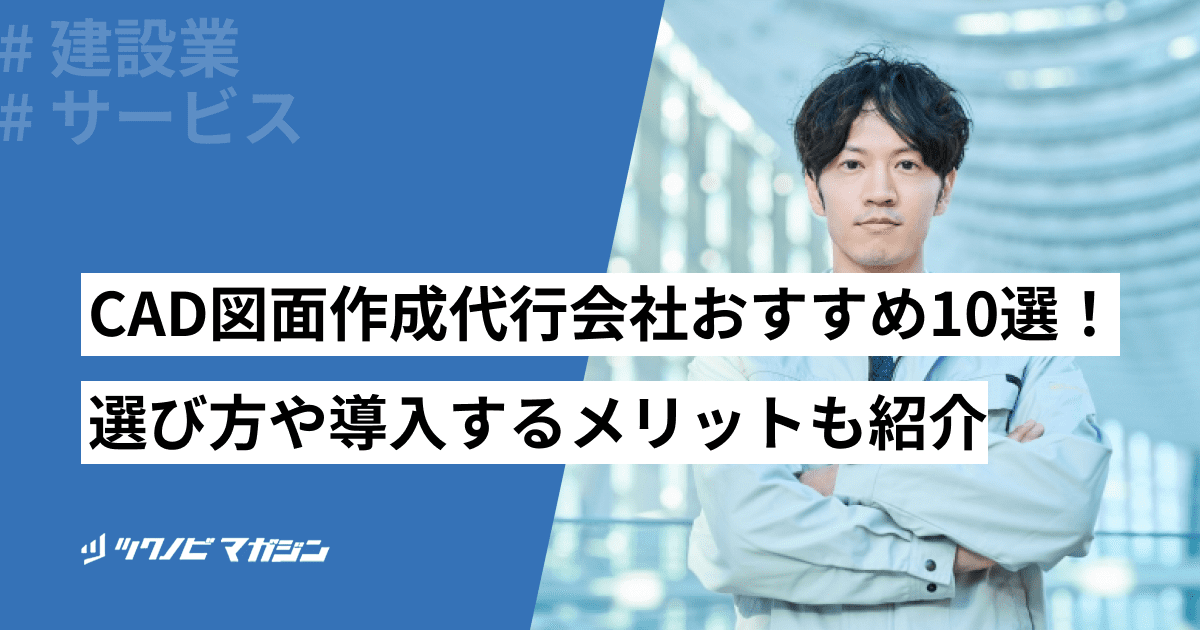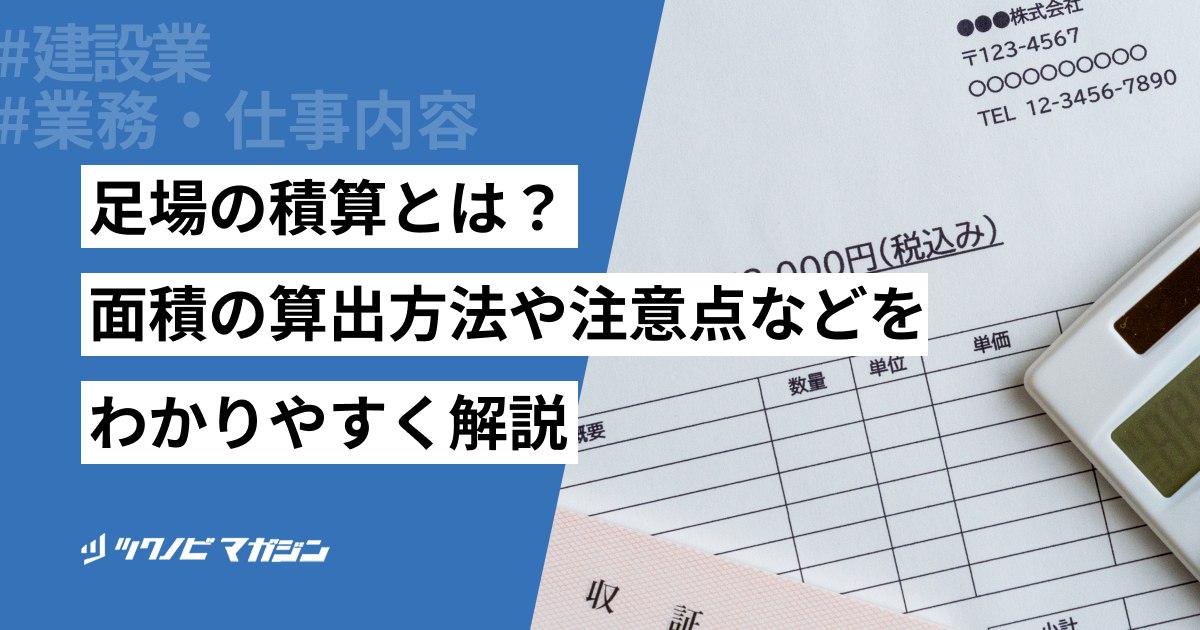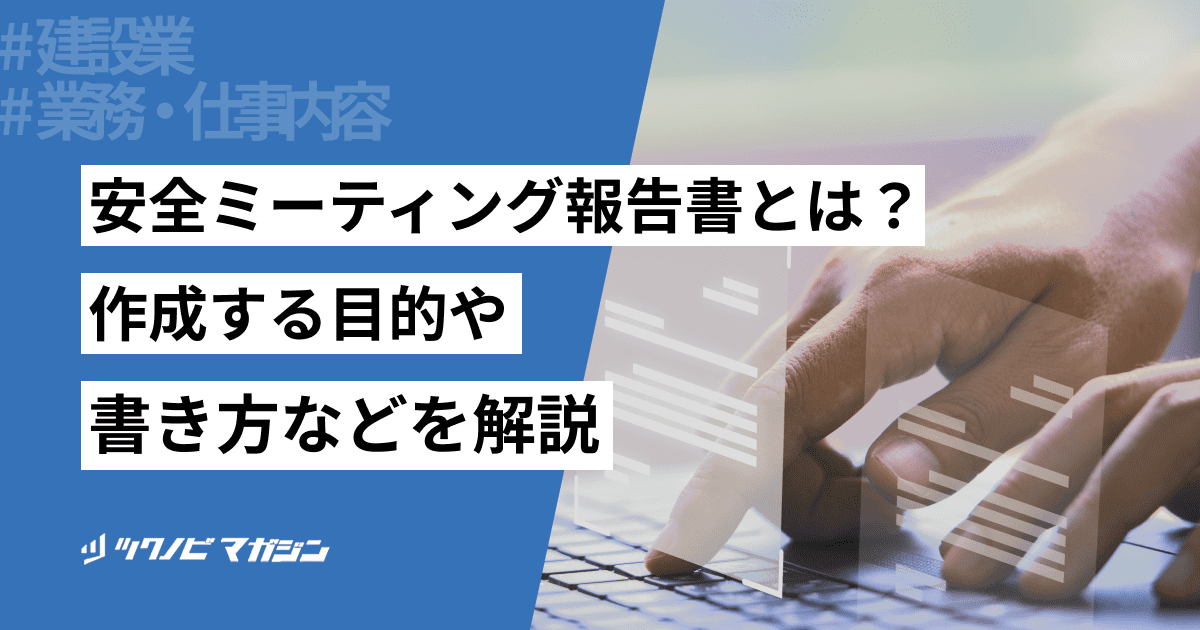※記事内に広告を含みます
建設工事において、電気工事図面は欠かせないものの1つです。しかし、電気工事の図面と言っても、どのようなものかイメージしづらい方も多いのではないでしょうか。
そこで今回の記事では、電気工事の図面について詳しく解説します。設計図と電気工事図面の違いや、種類・見方・使い方などもそれぞれ解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
ツクノビCADは、図面作成、トレース業務を低コストで代行する建設業特化のアウトソーシングサービスです。
施工図や仮説計画図、設備図、パース図の作成などまで、幅広い業務に対応しています。詳細はぜひこちらからご確認ください。
電気工事の図面とは
電気工事図面は
- 電気設備設計図
- 電気設備施工図
の2種類があります。どちらも電気工事には欠かせないもので、それぞれ使用するシーンが異なります。それぞれ詳しくご紹介します。
電気工事に図面が必要な理由
電気工事において、図面は必要不可欠です。電気工事図面には、建物のどこで電気が使われるのか・配線や設備はどうなっているのかが記載されているからです。
建物にはエアコンや換気扇・コンセントなど、様々な電気器具が設置されますが、配線はどれも壁や天井に潜んでいるため確認できません。それらを確認するために、電気工事の図面を使用し、保管しておく必要があります。
電気設備設計図との違い
電気設備設計図は、建物の電気回路が記載されている図面です。
- 建物の大きさ、広さ
- コンセント、スイッチなどの位置
- 電気部品の数
などが記載されています。
電気設備設計図は全て専用の記号で描かれているため、設計図を見る方は回路記号の知識が必要です。また、のちのメンテナンスの際にも設計図が必要になるため、保存しておくのがおすすめです。
電気設備施工図との違い
電気設備施工図は、
- 施工方法
- 施工工事のスケジュール
などが記載されます。電気設備設計図には電気機器関連の細かい情報が記載されていますが、施工方法や工事の段取りはありません。施工図と合わせて使いながら、電気工事を進めていきます。
電気施工図は回路記号を用いて書かれています。書き取りや読み取りを行う方は、電気回路記号の知識を持ち応用できなければなりません。
電気工事の図面の種類
電気工事の図面は4種類あります。
- 単線接続図
- 複線接続図
- 内部接続図
- 屋内配線図
の4つです。それぞれ用途が異なるので、電気設備の工事を行う際は使い分けが重要です。
単線接続図
単線接続図では、電気機器や設備の接続情報を1本の線で表しています。本来であれば電気回線は往路・復路の2本を用いますが、単線接続図はあえて単線を用いているのが特徴です。
単線接続図を見ると、外部から引き込んだ電気がどこに流れているのかがわかります。分電盤から各部屋への経路や、それぞれの電気機器の容量なども把握できます。
複線接続図
複線接続図は、電気機器同士がどのようにつながっているのかを細かく記載した図面です。単線接続図に対し、実際の配線本数をそのまま記載しているため、電気回路の詳細を確認する際に欠かせません。
ただし、複線接続図の記載も簡易的な部分があります。ジョイントボックスや照明器具・スイッチなどの設置場所は記載されていません。接続方法の確認と配線工事の際に用いるものになります。
内部接続図
内部接続図は、単線接続図・複線接続図よりも詳細を記載した図面です。配電盤・分電盤・制御盤の内部の配線や接続を記載しています。配電盤内部は機器の配置や接続が複雑なため、内部接続図で電線の行先を確認しましょう。
また、内部接続図はレストランや工場の工事などでも欠かせないものです。キッチンに設置する大型冷蔵庫や、モーターの配線を確認するときに使用します。配線ミスによる事故や機械の故障を防ぐために重要です。
屋内配線図
屋内配線図は、別名電気設備図とも呼ばれています。建物に設置する電気設備の位置を表す図面です。主に設置するコンセントや換気扇・スイッチ・遮断器などの位置を記載しています。
他の図面と同様に、記号を用いて照明やスイッチの位置が書かれています。また、配線図を作成する人によっては、配線を記載していない場合もあるため、参考にする際は注意しましょう。
電気工事の図面の見方
電気工事の図面を見て作業するには、見方のポイントが2つあります。
- 図面に使われている記号を理解する
- 電気の流れを読み取る
の2つです。
それぞれ詳しく解説しますので、図面を見る際の参考にしてください。
図面に使われている記号を理解する
電気工事の図面には、たくさんの記号が使用されています。記号を全て暗記した上で図面を見ることが理想ですが、似たような記号も多いため難しいです。はじめは使用頻度の高い図記号から覚えましょう。
例えば、配線記号・電動の記号など、床や天井に隠れた配線を把握する際に欠かせないものは使用頻度が高いです。各部屋についている照明器具関連のものも必ず表記されていますので、覚えておきましょう。
配管配線の図記号
配管配線は、おもに配線の位置や状態を示しています。
- 天井隠ぺい配線
- 床隠ぺい配線
- 露出配線
- 立上り
- 素通し
など、壁や天井に隠れている配線も含めて表示します。
工事の内容によっては、図面内に電線の種類も記載しなければならない場合があります。
- IV:600Vビニル絶縁電線
- HIV:600V二種ビニル絶縁電線
- IC:600V架橋ポリエチレン絶縁電線
- OW:屋外用ビニル絶縁電線
- VCT:600Vキャプタイヤケーブル
- VCTF:300Vキャプタイヤケーブル
- CV:600Vまたは高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
- CVT:600Vまたは高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(3本のより線)
電線を配置する際は、感電などの事故を防ぐために銅管で保護します。銅管の種類についても図面に記載しなければいけないため、以下のような記号を使用します。
- E:鋼製電線管(ねじなし電線管)
- PF:合成樹脂製可とう電線管(PF管)
- CD:合成樹脂製可とう電線管(CD管)
- F2:2種金属製可とう電線管
- MM2:2主金属線樋
- MM1:1主金属線樋
- VE:硬質塩化ビニル電線管(VE管)
照明の図記号
電気図面では、照明も記載しなければなりません。代表的な照明器具は以下になります。
- ペンダントライト
- シーリングライト
- ダウンライト
- スポットライト
- 壁付け、天井付け、LED蛍光灯
スイッチの図記号
スイッチの図記号は、主に黒丸で表記されます。リモコンスイッチやパイロットスイッチなど、特殊なスイッチの場合は、黒字に添字で表記します。
コンセントの図記号
コンセントの記号はわかりやすいものが多いです。天井コンセントを基準に、添字や黒塗り部分でコンセントの違いを表記しています。
機器・器具の図記号
そのほか、遮断機やモーターブレーカーなども、全て記号が決まっています。特に換気扇や文電気はよく使用される記号なので、覚えておきましょう。
電気の流れを読み取る
電気工事の図面を見る際は、電気の流れを読み取ることを意識しましょう。電気工事の図面では、電気の流れは「左から右」という決まりがあります。
ごく稀に右から左の電気の流れを掲載している場合がありますが、特記事項が必ずあります。記号と合わせて電気の流れを読み取り、スムーズに工事を行いましょう。
電気工事の図面の見方を習得するコツ
続いて電気工事の図面の見方を習得するコツを解説します。下記の3つのコツを確認してみましょう。
- 配線のルートや配線図のシンボルを正しく理解する
- 学習ツールを活用する
- プロのテクニックを学ぶ
配線のルートや配線図のシンボルを正しく理解する
電気工事の図面の見方を習得するために、まずは図面の構成要素を理解しましょう。電気工事の図面では、配線のルートや配線図の尺度などが様々な記号で表現されています。
図面特有の専門用語や記号の意味を理解することが、電気工事の図面を読み取るための第一歩です。
学習ツールを活用する
電気工事の図面の見方を習得するために、学習ツールを活用してみましょう。学習ツールには様々なものがありますが、オンラインの学習コースなどを受講することで、効率よく図面の見方を学習できます。
また、図面ソフトを用いて実際に自分で図面を作成してみることで、実践的に図面の見方を習得できます。
プロのテクニックを学ぶ
電気工事の図面の見方を習得するために、実際にプロが使用しているテクニックをまねてみましょう。
プロが図面を読む方法はいくつかありますが、先に配線の全体図を把握する方法がもっとも一般的です。最初から細部を読まず、配線の大枠を把握した後に細部の記号を読むと全体の配線を簡単に掴めます。
電気図面が役立つ3つの場面
続いて電気図面が役立つ3つの場面を紹介します。下記の3つのシチュエーションをチェックしてみましょう。
設備工事をスムーズに行える
電気図面は工事のときのみに役立つわけではありません。電気図面があることで、建物全体の電気設備を把握することができます。
電気図面を見ることで、施設のどこにどのような電気設備があるかが一目でわかるため、工事のみならず様々なケースで活用できます。
トラブルに迅速に対応できる
電気図面を見ることで電気関連の様々なトラブルに迅速に対応可能です。停電や漏電など様々な電気トラブルの際に、電気図面の有無は大きく影響します。電気図面がない場合は、トラブルの対応に手間取り、復旧に多くの時間を要します。
情報を見える化できる
電気図面があることで情報を見える化できます。施設の電気設備に問題が生じた際に、設備担当者が不在の場合は、工事業者は電気図面をもとに対応します。
電気図面があることで、情報共有がスムーズになり効率よく作業ができます。
電気工事の1人工の単価や電気工事の回路図作成に使えるフリーソフトおすすめ6選についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
 電気工事の1人工の単価は?計算方法や上げるときの注意点などを解説
電気工事の1人工の単価は?計算方法や上げるときの注意点などを解説
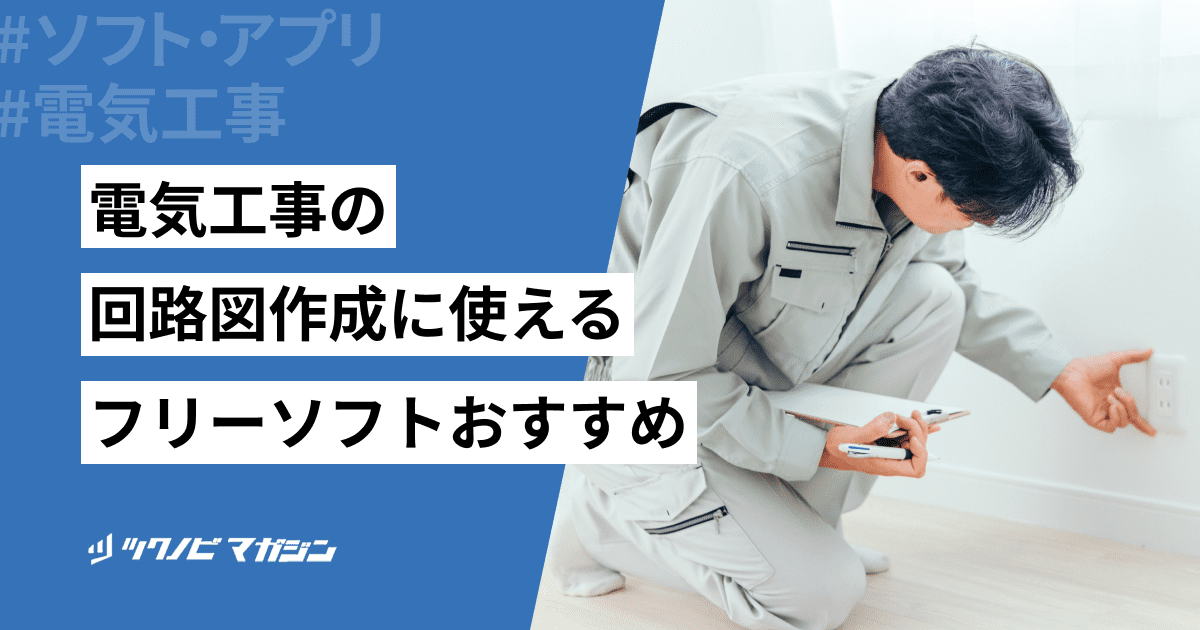 電気工事の回路図作成に使えるフリーソフトおすすめ7選!選び方も紹介
電気工事の回路図作成に使えるフリーソフトおすすめ7選!選び方も紹介
電気図面の作成はアウトソーシングもおすすめ
電気図面の作成業務は、建設業の経験が豊富なプロへのアウトソーシングもおすすめです。弊社では、建設業に特化したアウトソーシングサービス「ツクノビBPO」を提供しています。
図面の作成や修正、印刷、製本、デジタル化などの対応が可能です。また、建設業での各種事務作業や採用業務まで、幅広く対応しています。
図面作成業務をアウトソーシングして効率化したい方は、ぜひこちらからお問い合わせください。
【まとめ】電気工事の図面の基本を理解して作業をスムーズに進めよう!
電気工事の図面について、記号や使い方・種類などをご紹介してきました。電気工事の図面は複雑でわかりづらいものですが、記号や見方を覚えて使用すれば、工事が円滑に進みトラブルも減ります。正しい図面の見方や使い方を覚え、電気工事に生かしてみてください。
CAD図面作成代行会社おすすめ10選や単線接続図についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
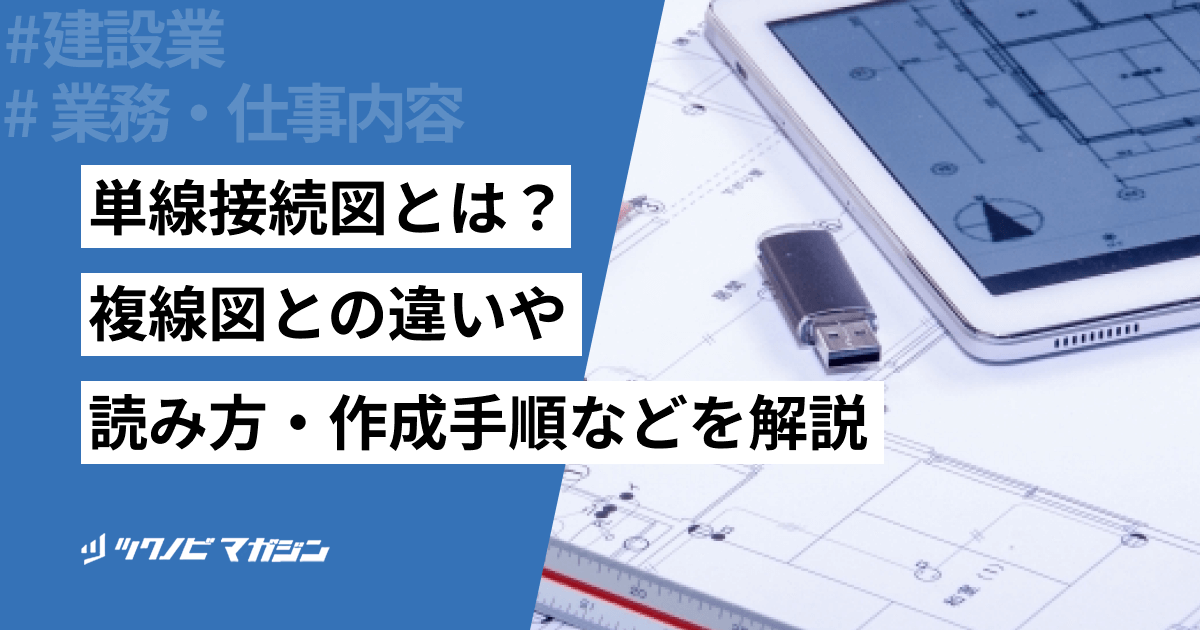 単線接続図とは?複線図との違いや読み方・作成手順などを解説
単線接続図とは?複線図との違いや読み方・作成手順などを解説
※弊社の営業代行サービスであるツクノビセールスでは、
【効果が出なければ全額返金プラン】を新たにスタートさせました!

※詳しくは👆👆👆のバナーをクリック!!