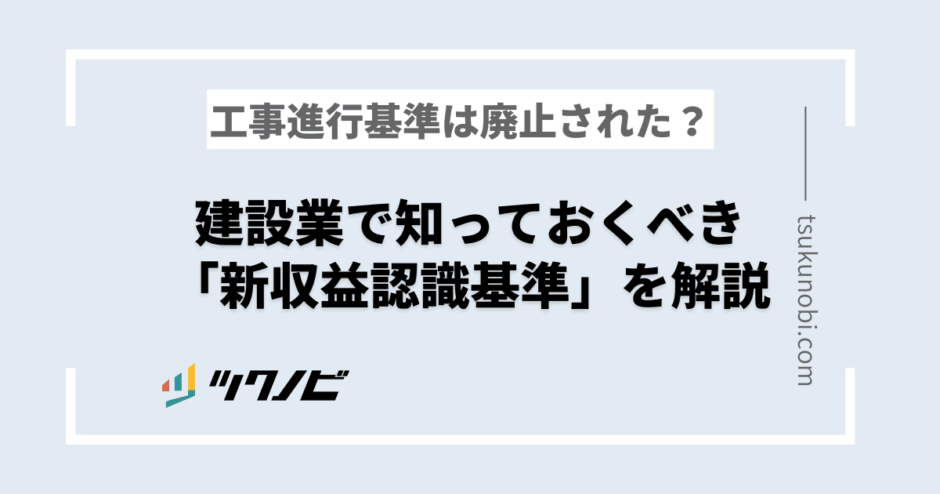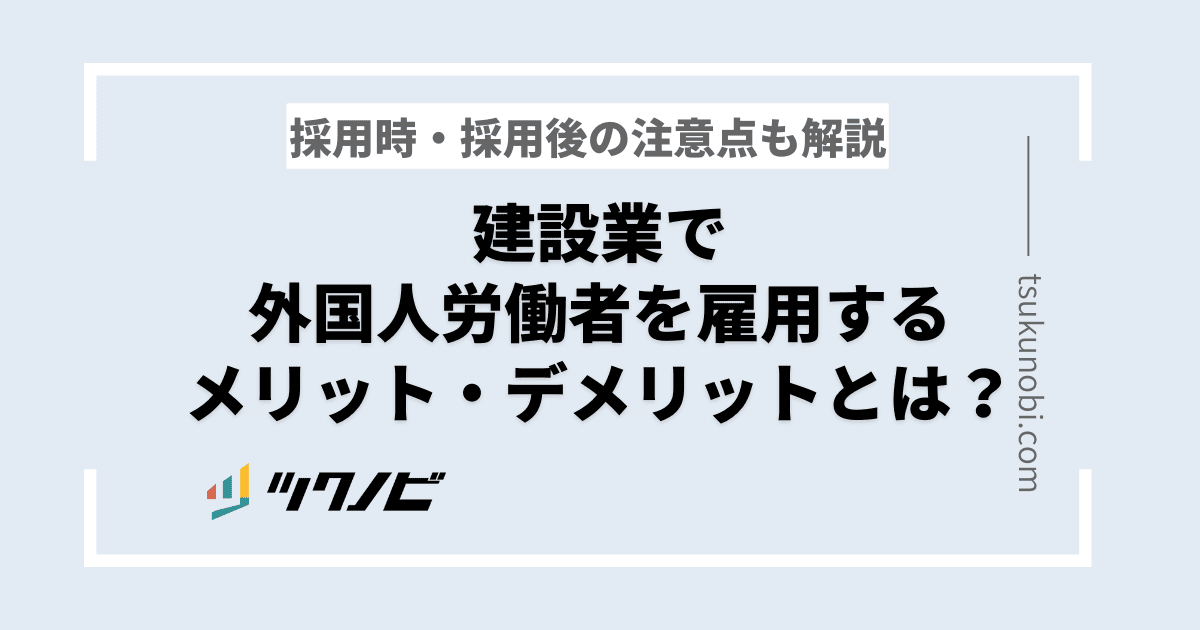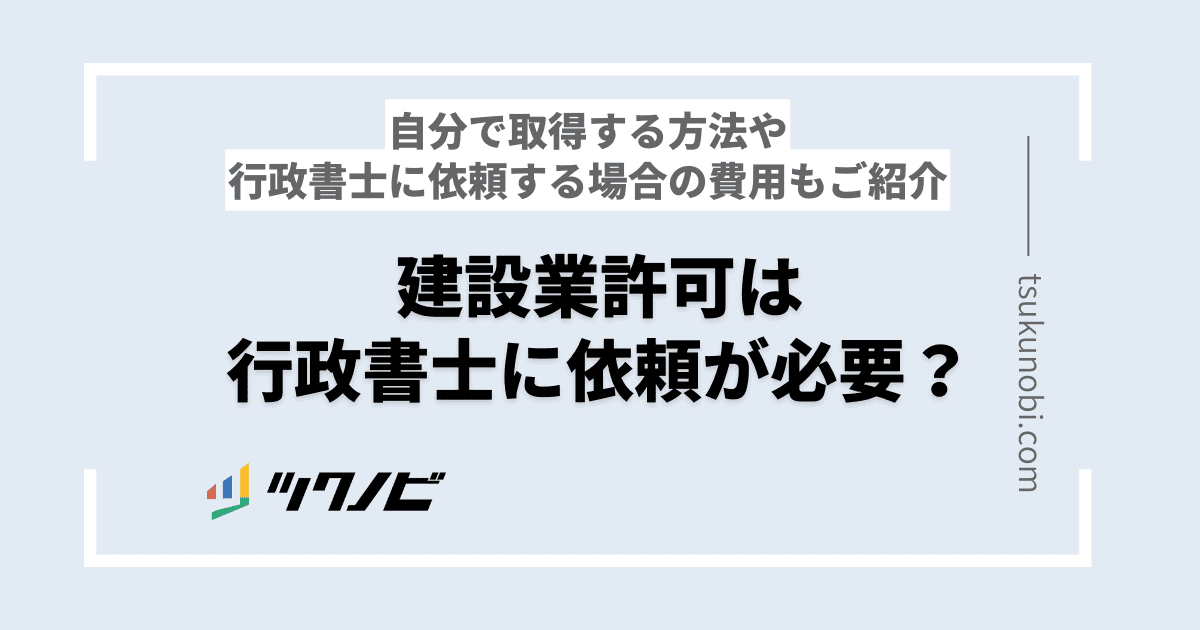※記事内に広告を含みます
工事進捗基準の廃止を受けて、新しい基準ではどのように計上すればよいのか分からないと感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
工事進捗基準はそれ自体は廃止されましたが、実際は新しい基準のなかに引き継がれる形で実施されています。そのため、混同して考えてしまう方も多いです。
今回は、工事進捗基準が現状どうなっているのかを取り上げつつ、新しい基準である新収益認識基準について解説します。
工事進行基準は廃止された?
建設業界では従来の工事の進行具合を基準として会計処理を行う「工事進行基準」にて、会計処理を行ってきました。しかし、工事進行基準は「新収益認識基準準90項」により、廃止が明記されています。
工事進行基準は「なぜ廃止されるのか」「いつ廃止されたのか」といった疑問について、ここから詳しく解説していきます。
工事進行基準はなぜ廃止された?
工事進行基準が廃止された背景には、国際的な動きがあります。従来の会計ルールでは、企業会計原則により定める程度にとどまっていたため、企業ごとに計上基準の判断がバラバラでした。
様々なビジネスモデルが現れるなか、国際的にも会計基準を統一しようという動きが高まり、2018年に「新収益認識基準」が開発されたのです。
日本もこの流れを受け、会計基準を高品質かつ国際的整合性のあるものへ移行する動きとなりました。そして、新収益認識基準の導入に伴い、工事進行基準が廃止されることとなったのです。
工事進行基準はいつ廃止された?
工事進行基準は2021年4月に廃止されました。今後は工事進行基準に代わり、国際会計基準と基本的にほぼ同じである「新収益認識基準」が適用されます。
しかし、工事進捗基準の処理自体は新収益認識基準に引き継がれる形で残っています。これまで工事の売上高は工事収益総額にその期の工事進捗度をかけることで求められていました。新収益認識基準では、履行義務、つまり顧客との間で提供を約束した成果物やサービスに応じて、収益を認識します。
従来の工事進行基準のように一定期間にわたり履行義務が充足される場合の処理方法は、新収益認識基準「収益認識に関する会計基準44項」に記載されています。
収益を計算する際は、履行義務の充足に係る進捗度を見積もり、当該進捗度に基づき収益を一定期間にわたり認識するとあるため、工事進捗基準の処理自体はこれからも行っていかなくてはなりません。
新収益認識基準とは?
もう少し新基準について学んでいきましょう。新収益認識基準は、売上に対する認識や財務諸表上どのように反映するのかを定める新しい基準です。そして、新収益認識基準では対象となる契約があらかじめ決められています。したがって、以下6つの取引は対象外となります。
- 「金融商品会計基準」の範囲に含まれる金融商品に係る取引
- リース会計基準の範囲に含まれるリース取引
- 保険法における定義を満たす保険契約
- 同業他社との交換取引
- 金融商品の組成または取得において受け取る手数料
- 不動産流動化実務方針の対象となる不動産の譲渡
対象となる取引は、顧客との契約から発生する収益に関係する会計上の処理やその開示だけです。金融商品やリースが関わる取引は対象外となります。対象となる物とそうでないものをきちんと理解しておきましょう。
工事契約基準と新収益認識基準の違い
工事契約基準と新収益認識基準は、細かい部分に違いがあります。混同を避けるためにも、それぞれの違いを把握しておきましょう。以下の図はそれぞれの違いをまとめたものです。
| 工事契約基準 | 新収益認識基準 | |
|---|---|---|
| 判定基準 | 工事契約について以下3つを合理的に見積もれるか
|
履行義務について以下どちらに該当するか
|
| 判定内容 |
|
|
| 収益認識 |
|
|
図にある「収益認識基準38項」の条件は、以下3つです。
- 履行と同時に顧客が便益を受け、消費する場合
- 履行による資産の創出・増加につれて、顧客が資産を支配する場合
- 創出した資産がほかに転用できず、かつ履行済み部分に対する対価の支払いを受ける権利がある場合
これらに該当するかどうかで収益の判定が変わるため、ご注意ください。
新収益認識基準の5段階ステップ
次は新収益認識基準の処理を確認していきましょう。新収益認識基準の処理は、5段階のステップで処理していきます。それぞれの作業内容について解説します。
1.契約の識別
契約の識別とは、当事者間の契約として認められているものを収益として認める考え方です。新収益認識基準では、契約書を交わしていないいわゆる口頭で交わした契約や、取引慣行によるものもその一部として認められますが、建設業は書面で契約を結ぶのが一般的です。
実務において書面で契約と承認を行い、顧客の信用調査などを行ったうえで対価を回収できるかを判断します。受注の流れでこの段階はクリアしているといえるでしょう。
2.履行業務の識別
新収益認識基準には、対象外となる取引があります。契約上、対象外となる物が含まれている可能性もあるため、処理を行う取引をピックアップし、把握しておかなくてはなりません。
契約のうち、製品の提供とその保守サービスがひとつになった契約の場合は、ふたつの履行義務があると把握します。ひとつの契約に複数の取引が含まれていることも珍しくないため、契約内容をよく確認しておきましょう。
3.取引価格の計上
契約の履行義務を把握したら、取引価格の計上に移ります。これは、取引の金額がいくらになるかを確認する作業です。契約の取引価格、つまりいくらで利益を認識するかを把握します。
4.取引価格の配分
計上が終わったら契約に含まれる履行義務ごとに、取引価格を分配していきます。それぞれの履行義務を、独立して販売する場合の価格を基準として考えて配分しましょう。
5.収益の認識
最後に、売上を計上するタイミングを決定します。履行義務ごとに計上するパターンは異なるため、注意しましょう。たとえば、キッチンをリフォームした場合、以下の履行義務が発生します。
- 設置するキッチンなどの価格
- リフォーム工事の施工に係る価格
- 保障制度に係る価格
このうち、上ふたつは新収益認識基準でいうところの一時点で充足される履行義務に該当します。保証制度は年単位で履行義務が続くため、一定の期間にわたり充足される履行義務です。
上ふたつはそれぞれの価格が一定のタイミングで計上されますが、保障制度は年数で配分した取引金額を割り、計上していきます。なお、どちらになるかの判断は決まっています。一定の期間にわたり充足される履行義務として認められるには、条件があるためご注意ください。
新ルールの原価回収基準とは
新収益認識基準には、新しいルールが追加されています。新ルールの原価回収基準の内容もおさえておきましょう。原価回収基準は、履行義務を充足する際に発生する費用のうち、回収が見込まれる費用の金額を収益として認識する方法です。
新収益認識基準は、仕組み上一定期間にわたって充足される履行義務における進捗度を合理的に見積もれません。しかし、発生する費用の回収が見込める場合は、進捗度を合理的に見積もれるまで、原価回収基準により処理できます。
建設業のプロ人材を採用したいならツクノビBPOがおすすめ
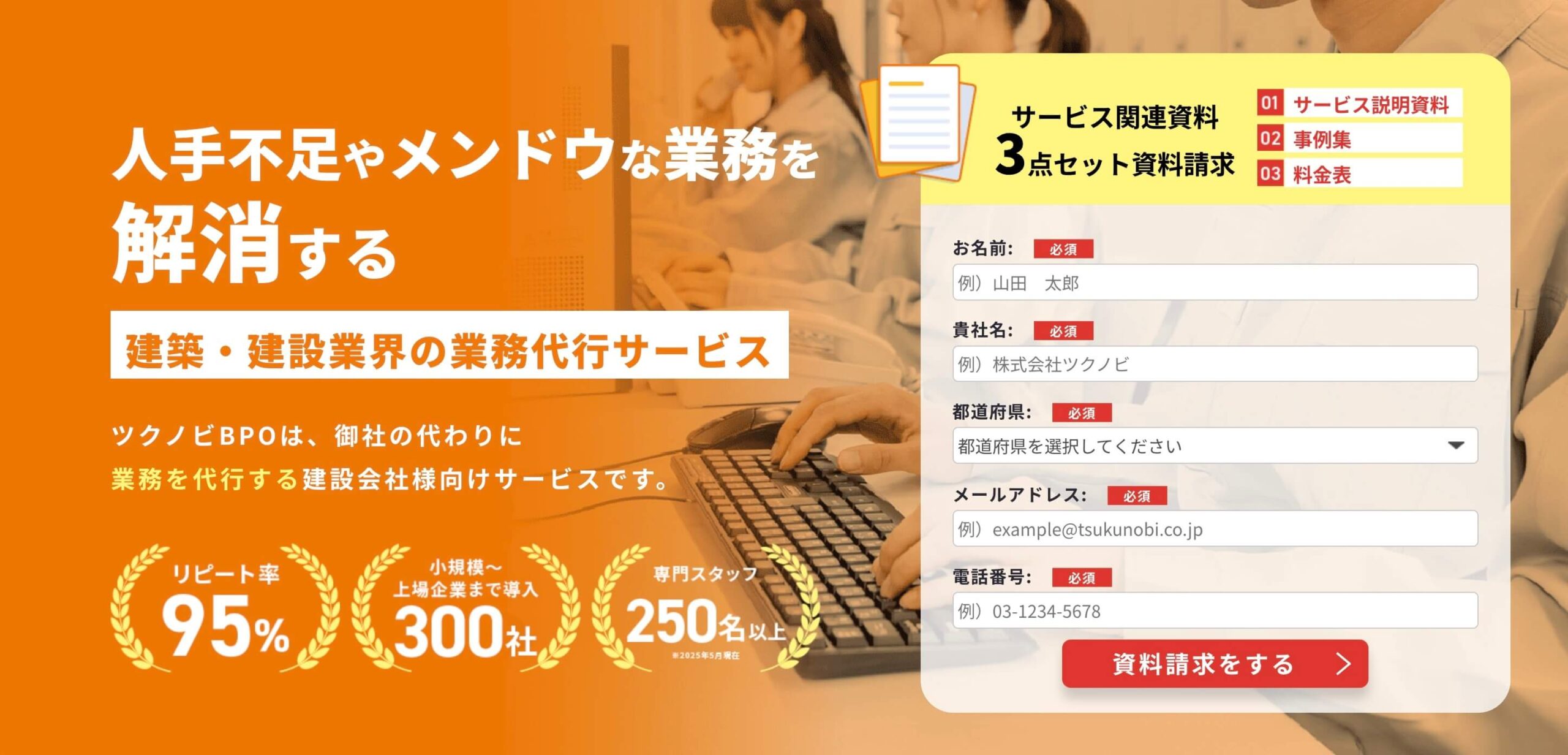
対応したことのない業務が発生した場合や業務に対応できる人材が不足している場合は建設業のプロ人材を活用することがおすすめです。
建設業特化の業務代行サービス「ツクノビBPO」は、建設業の経験が豊富なプロ人材が御社の業務を代行するサービスです。採用倍率200倍を乗り越えた選りすぐりのプロ人材を採用しているため、安心して業務を依頼できるでしょう。
対応可能な業務は施工管理や建設業事務、書類作成、各種申請業務、CAD図面作成、積算など多岐にわたります。業務をただ代行するだけでなく、作業効率が高い方法のご提案や業務マニュアル作成などで御社の作業効率の向上に貢献いたします。
業務の品質を上げたい方やこれまで対応できなかった業務にも対応していきたい方、作業効率を上げたい方などはぜひこちらから詳細をご確認ください。
【まとめ】工事進行基準は新収益認識基準の導入によって廃止されている!ルールをしっかり覚えよう
工事進行基準自体は廃止されていますが、処理自体は新ルールである新収益認識基準に引き継がれています。変更点はこのほかにもあるうえに、新ルールである原価回収基準もあるため、混同しないようにしましょう。新しい処理のルールとステップをきちんと理解して、正しい方法で処理してください。
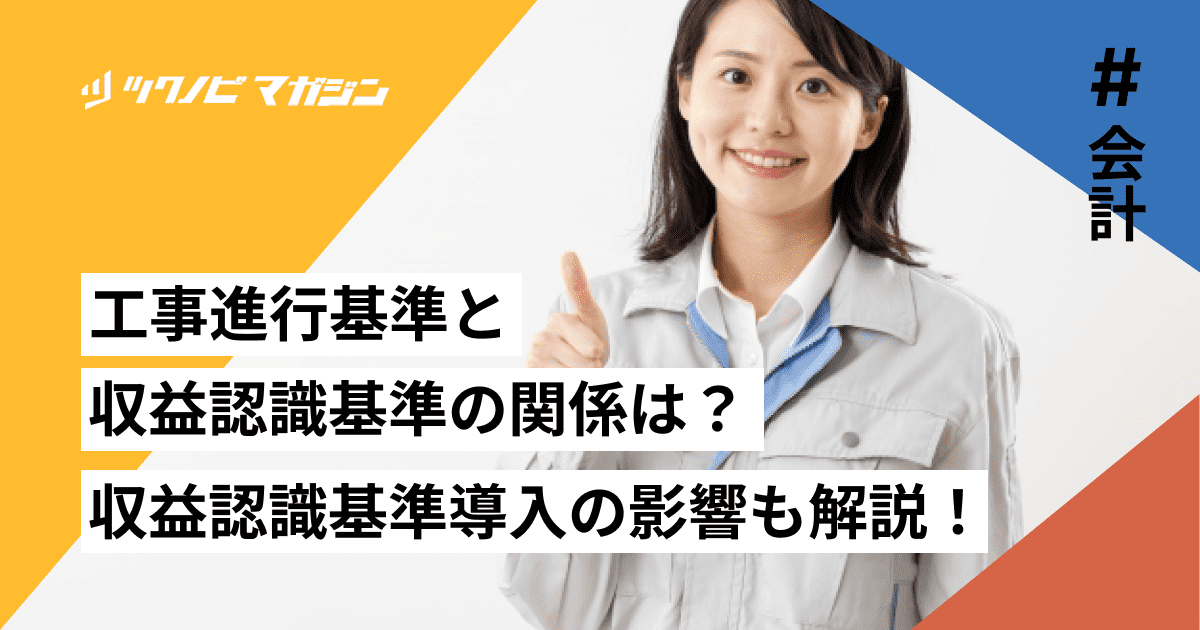 工事進行基準と収益認識基準の関係は?収益認識基準が導入されたことによる影響についても解説
工事進行基準と収益認識基準の関係は?収益認識基準が導入されたことによる影響についても解説
※弊社の営業代行サービスツクノビセールスは、
【効果が出なければ全額返金プラン】を新たにスタートさせました!

※詳しくは👆👆👆のバナーをクリック!!