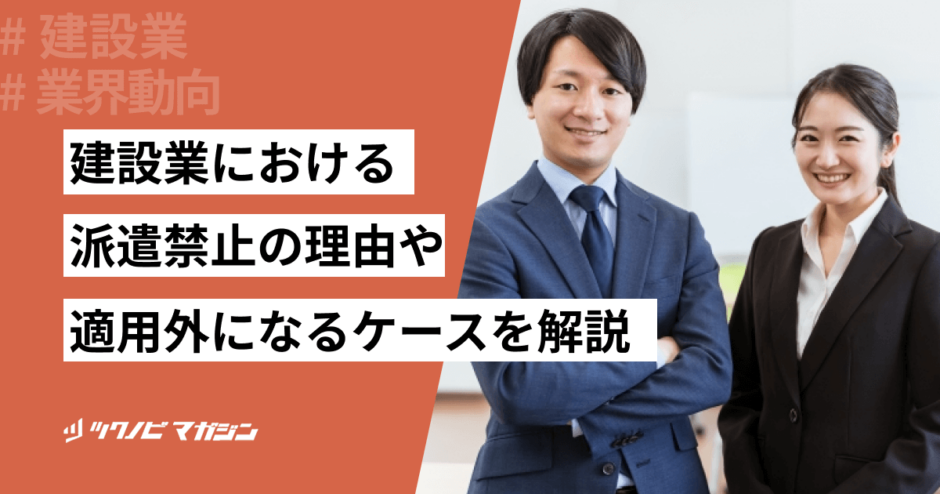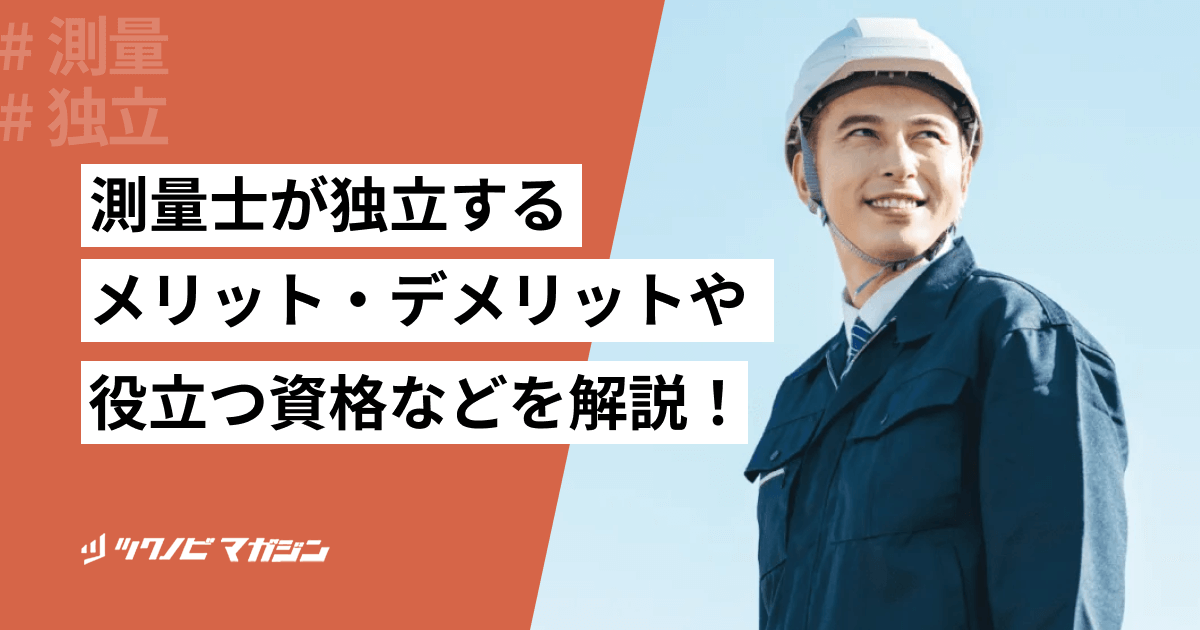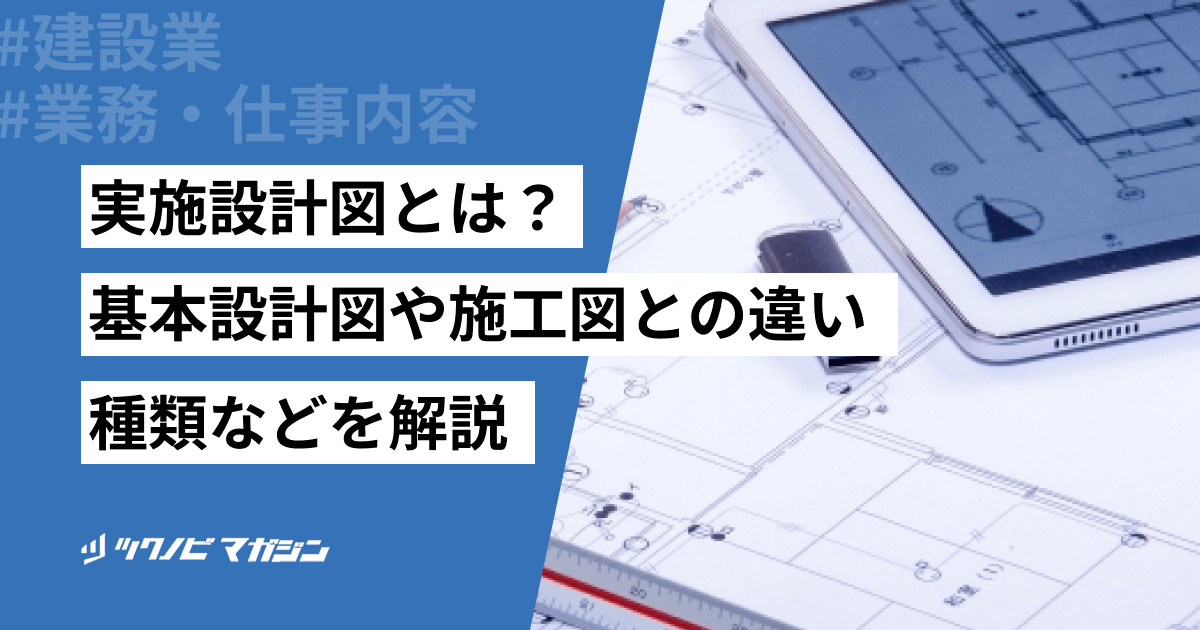※記事内に広告を含みます
建設業界には、雇用形態や労働環境において独自の法規性が存在しています。その中でも、建設業における労働者派遣の禁止は、多くの方にとって理解が難しい部分かもしれません。
建設業における労働者派遣の禁止は、なぜ必要とされているのでしょうか?
本記事では、派遣禁止の背景にある法的根拠やその意図、さらにこの規制がもたらす影響についてわかりやすく解説します。
建設業界で働く方はもちろん、労働法に関心のある方もぜひご覧ください。
派遣とは
建設業の労働者派遣がなぜ禁止されているかを説明する前に、派遣がどのような業務形態化について、以下の2つに分けて説明します。
- 派遣の概要
- 請負との違い
派遣の概要
派遣とは、派遣会社が自社で雇用した労働者を、別の企業に派遣し就業させる雇用形態のことです。
労働者は雇用契約を派遣会社と締結しているため、勤務先ではなく派遣会社から給与の支払いや福利厚生などを受けます。
しかし、実際の就労の指揮は雇用先から受けるので、労働者が派遣として働く際には雇用関係と就労環境が分離するという特徴があります。
派遣会社との雇用契約は、派遣先企業の決定と共に派遣期間や給与などの雇用契約を締結する一般的な「登録型派遣」と、派遣会社と期間を定めずに契約をする「常用型派遣」の2種類があります。
請負との違い
建設業の短期労働というと、請負労働者を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
請負は「成果物の納品」を目的に請負事業者と発注者が契約を結びます。
そして、労働者は請負事業主と雇用契約を締結し、請負事業主の指揮管理のもとで就労し、給与支払いも受けます。
派遣の目的が派遣先企業での就労であり、責任の所在が派遣企業であるのに対し、請負は仕事の完成を目的としており、責任の所在が請負事業主であるという違いがあります。
建設業における派遣禁止の理由
前述したように建設業では、請負労働は許可されていますが派遣労働は禁止されています。
なぜ、派遣労働のみ禁止されているのでしょうか。その理由について、以下の2つに分けて解説します。
- 労働者の安全を確保するため
- 不安定な雇用を防止するため
労働者の安全を確保するため
建設業で派遣労働が禁止されている大きな理由の1つに、労働者の安全性への配慮が挙げられます。
建設業で派遣労働が禁止されている一番の理由は、労働者の安全性の確保のためです。
建設業の現場は、高所での作業やチェーンソーや重機など危険な工具を使用する機会が多く、怪我や事故のリスクが高いという特徴があることから、指揮系統を統一化することで安全管理を徹底しています。
しかし、派遣会社の指揮命令下で勤務する派遣作業員が業務に参加すると、指揮系統が不明瞭になり、怪我のリスクが高まると考えられます。
また、事故が発生した場合も責任の所在が不明瞭になるため、労働者本人が不利益を被るリスクが懸念されていることなども挙げられます。
不安定な雇用を防止するため
建設業が派遣を禁止するもう1つの理由に、不安定な雇用を防止するという目的が挙げられます。
建設業は受注生産なので、景気の影響を受けやすく需要が安定しないという特徴があります。
そのため、閑散期になると仕事がなくなり、雇用した派遣労働者の契約を解除するいわゆる「派遣切り」をしなければならなくなる懸念が出てきます。
こうした職人の雇用の安定とキャリア育成が十分にできないリスクが考えられるという背景から、派遣労働は禁止されているのです。
建設業における派遣禁止の業務
派遣労働者の就労環境の確保と権利の保護を目的として定められた、「労働者派遣法」という法律があります。
労働者派遣法において建設業において労働者派遣の適用とならない業務は以下のように定められています。
- 土木
- 建築その他工作物の建設
- 改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業またはこれらの作業の準備の作業に係る業務
つまり、建設・土木業における資材の運搬から組み立て、塗装や補修、工事や解体、撤去などのあらゆる現場に直接従事する作業において派遣労働者を雇用することは禁止されています。
建設業における派遣禁止が適用外になるケース
建設業の現場作業において派遣労働は禁止されていますが、例外となる業務もあります。
建設業で派遣労働が許可される業種とその理由について、以下の4つに分けて解説します。
- 建設業ではない業務を行う場合
- 技術指導を行う場合
- 安全衛生上の対応を急いで行う必要がある場合
- 全員が同じ時間に作業しなければならない場合
建設業ではない業務を行う場合
建設業の現場で就業する作業ではなく、デスクワーク作業であれば派遣労働者の雇用は許可されています。
しかし、無許可で雇用することは違法となるため、厚生大臣の許可を取得することが義務付けられています。
建設業で派遣労働者を雇用できる職種は、以下の3つです。
- 事務
- オペレーター
- 施工管理
事務
建設業を支えるバックオフィス業務は、事務作業として分類できます。
現場作業をスムーズに進行するために裏方で支える事務作業員は、建設業にとって非常に重要な存在ですが、経理や総務などのノウハウがあれば派遣作業員でも従事可能です。
事務作業員は具体的に、以下の業務を担当します。
- 契約書や見積書の作成
- 役所や元請けに提出する安全書類の作成
- 現場作業員の労務管理
- 予算管理や経費精算などの経理業務
- 来客対応や現場作業員のサポートなどの総務
オペレーター
建設業におけるオペレーターとは、特殊なソフトを用いて図面作成や3次元モデルを作る人員のことを指します。
建設業では図面作成や設計においてDX化が進んでおり、以下の3つのソフトを使用できる人材を派遣で雇用するケースがあります。
- CAD PC上で2D、3Dの設計や図面作成ができるソフト
- BIM 建物のの設計・施工・管理を3Dモデルを使用して表現するソフト
- CIM 3Dモデルを活用し土木構造物の形状や配置を可視化するソフト
施工管理
建設業の計画を立て、プロジェクトがスケジュール通り進行するように調整や監督を行うポジションを、施工管理と言い、派遣作業員の雇用が許可されています。
施工管理の主な業務は、以下の通りです。
- 工事の進捗管理
- 設計図通りに工事が行われているかの品質の管理
- 原価管理
- 検査や審査などの行政への対応
- 安全管理
このように、作業員への安全ルールの徹底や現場の巡回なども業務に含まれていますが、現場作業はたとえ軽作業であっても派遣社員には行えないので注意が必要です。
そのため、現場監督の派遣は違法になります。
技術指導を行う場合
現場作業であっても、初めて使用する重機の技術指導に関しては、派遣労働者の雇用禁止には該当しません。
一般的に、元請業者から下請け業者が指揮命令を受けることは禁じられています。
しかし、初めて使用する機器の指導は工事を安全に受けるために不可欠であるため例外とされているのです。
新しい機器でなくても、以前からレンタルしていた機器や設備に改修が加えられた場合も、同様に派遣労働者の就労が許可されます。
安全衛生上の対応を急いで行う必要がある場合
建設業に限らず、派遣労働者は基本的に派遣会社の指揮命令において労働することが義務付けられており、請負形式で現場の指揮命令の元で就労すると「偽装請負」となる恐れがあります。
しかし、災害や事故などの緊急時に限っては、現場の指示のもと行動、あるいは派遣労働者に指示を出しても違法にはなりません。
現場従業員の安全と生命の確保が最優先事項となるからです。
緊急性が去って安全性が去った後も指示命令を出していると、偽装請負と判断される可能性があるので注意しましょう。
建設業における派遣禁止に違反した場合の罰則
建設業では、デスクワークや緊急時、安全性の確保のための技術指導以外では派遣労働は禁止されています。
では、派遣労働を行った場合どのような罰則が科されるのでしょうか。
以下の2つに分けて解説します。
- 刑罰
- 行政処分
刑罰
建設業の現場で派遣労働法に違反する就労や偽装請負があった場合の罰則について、労働者派遣法の59条で「1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑」と定められています。
法人・個人事業主に関わらずこの罰則は同様に科されます。
また、両罰規定というものも第62条で定められており、違反行為があった場合該当の行為者だけでなく、その法人に対しても同様の罰金刑を科するとされています。
行政処分
派遣労働者の就労や偽装請負を行った場合、科されるのは刑罰だけではなく、行政処分を受けなければなりません。
建設業者が前述した刑罰を科された場合、建設業許可が取り消されることが、建設業法8条に定められています。
また、一度取り消された建設業許可は、5年間取得することができないので注意しましょう。
もし、刑罰に至らず建設業許可取り消しにならなかったとしても、営業停止処分などの行政処分が科される可能性があります。
建設業における派遣禁止に代わる制度
建設業では派遣労働は禁止されており、違反すると厳しい刑罰や行政処分が科されます。
しかし、人材不足を解消するために以下の派遣制度に代わる以下の2つの制度が導入されています。
- 建設業務有料紹介事業
- 建設業務労働者就業機会確保事業
建設業務有料紹介事業
建設業で求職者と求人企業をマッチングするための有料サービスを、「建設業有料紹介事業」と言います。
建設業有料紹介事業は、厚生労働省が定めた「職業安定法」に基づき許可を得た事業者のみが運営できる事業です。
事業者は求職者や求人企業から手数料を受け取り、職業を紹介します。
多くの場合採用が決定したら、成功報酬が支払われます。
建設業に特化しているため、専門性の高いスキルや資格を保有する人材を、企業ニーズに基づき紹介できるというメリットがあります。
紹介後は企業の直接雇用になるため、派遣労働には該当しません。
建設業務労働者就業機会確保事業
建設業で労働者の雇用促進や就業機会の確保のために、就業機会の提供を行う厚生労働省の許可を受けた事業主団体を「建設業務労働者就業機会確保事業」と言います。
まず、従業員を送出する事業主と受け入れる事業主が、就業機会確保契約を締結します。
そして、繁忙期など一時的に労働者を必要とするときに、送出先から受け入れ先の建設業務に従事させるよう、労働者を送り込むという制度です。
受け入れ先で労働している際も、送出先と労働者の雇用関係は維持されていますが、受け入れ事業主の指揮命令の元で働きます。
建設業務労働者就業機会確保事業ではこれらの就労支援だけでなく、労働者の技術向上のための技能講習や訓練プログラムなども行っています。
土木工事業の人手不足に対する解決策や電気工事士の人手不足にできる対策などについてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
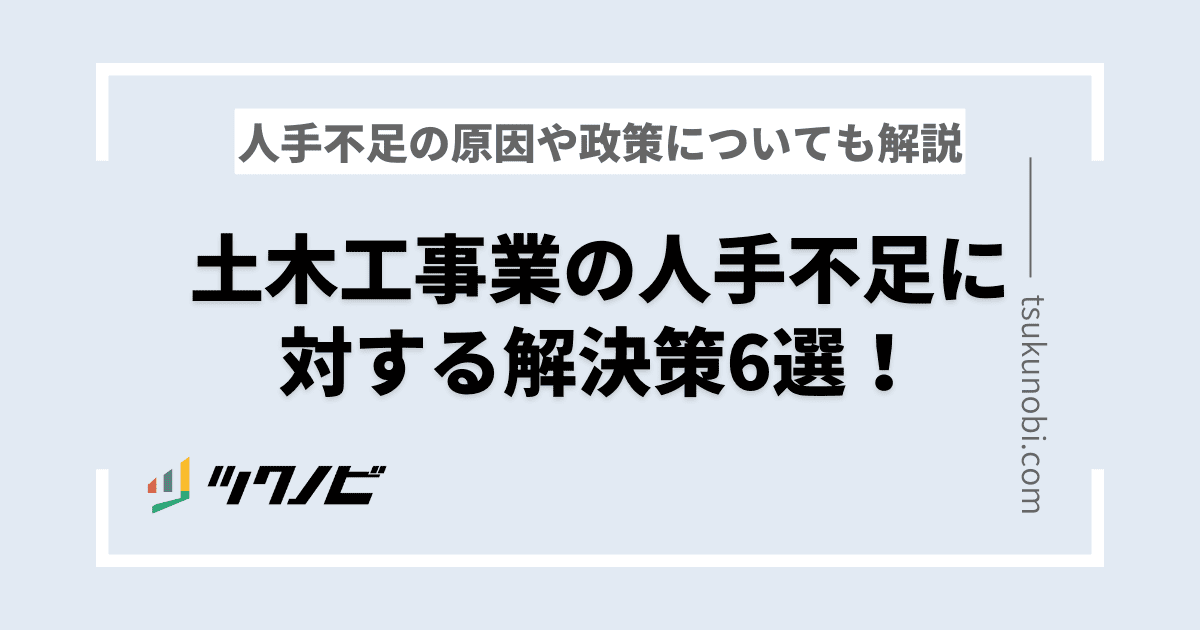 土木工事業の人手不足に対する解決策6選!理由についても解説
土木工事業の人手不足に対する解決策6選!理由についても解説
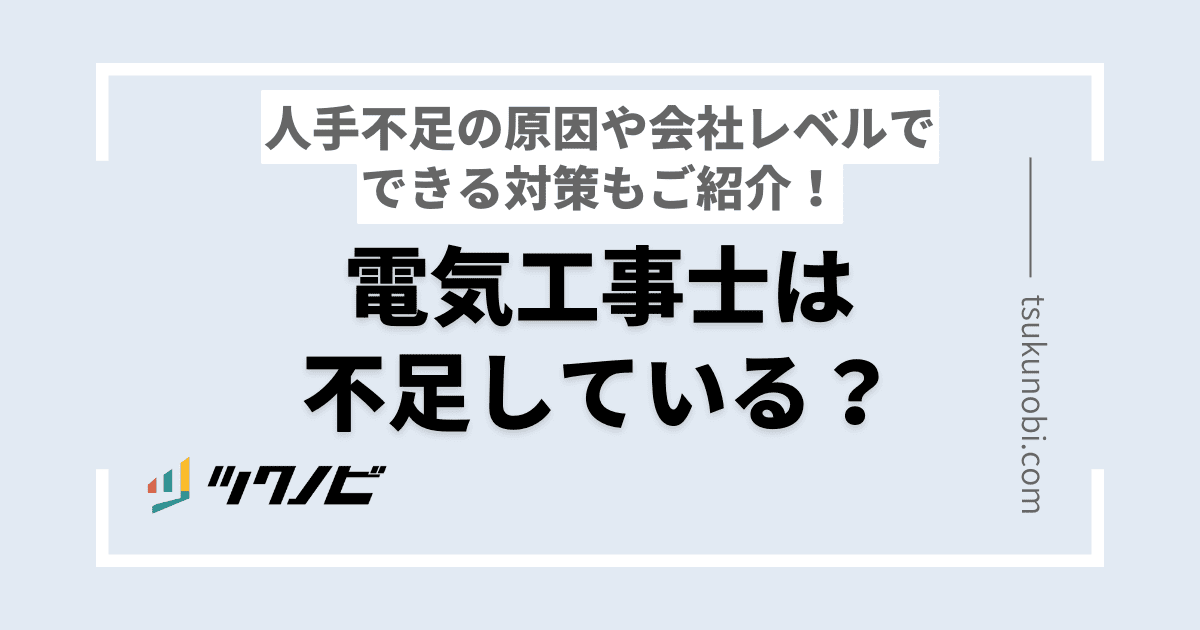 電気工事士の人手不足の原因は?対処法もご紹介!
電気工事士の人手不足の原因は?対処法もご紹介!
建設業の人手不足解消ならツクノビBPOがおすすめ
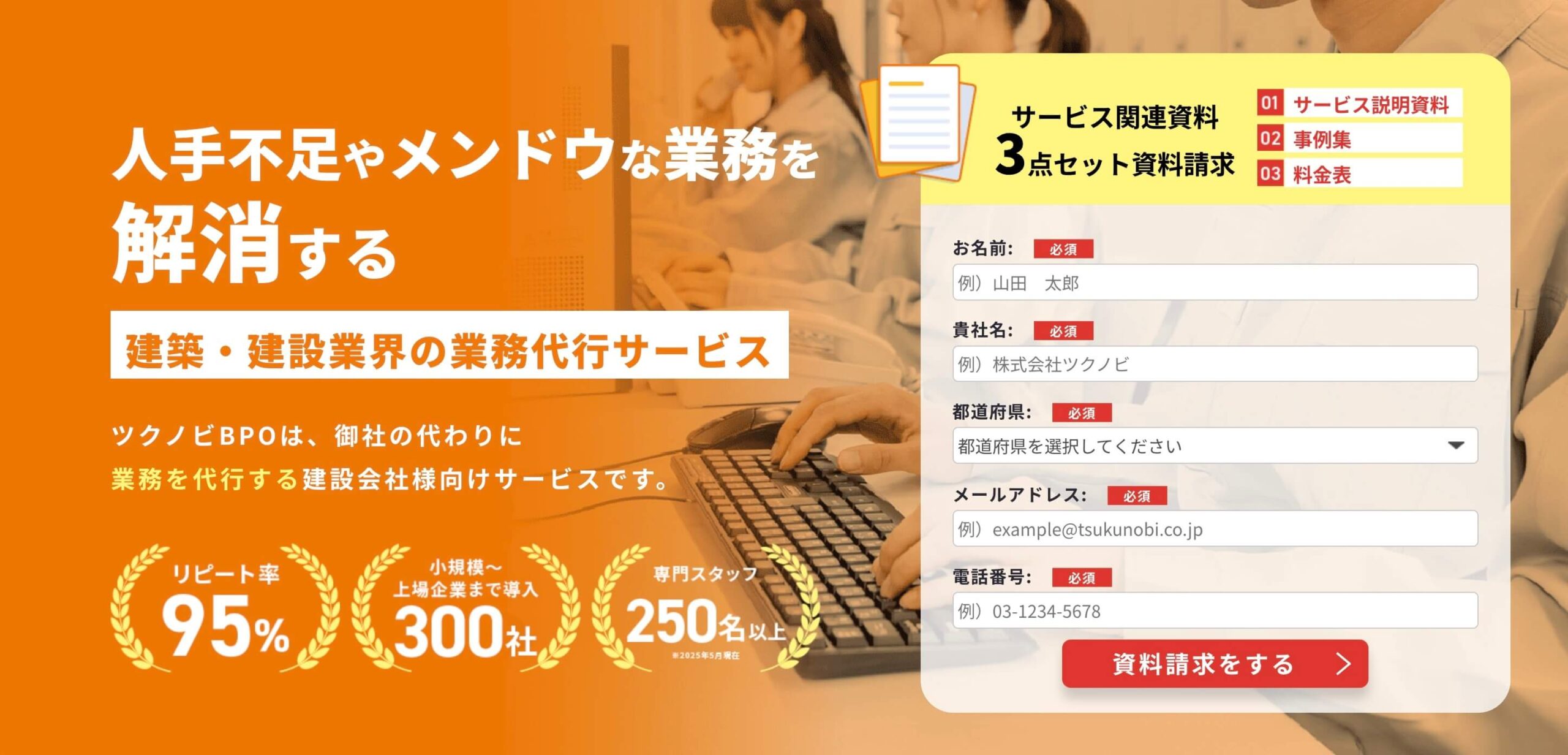
建設業の人手不足を解消するためには、アウトソーシングサービスの利用もおすすめです。
従業員のリソースがひっ迫している場合や、業務に対応できる人材が不足している場合などは、アウトソーシングサービスを活用すると、少ない工数で業務を実行できます。BPOサービスでは、専門的な知識を持っているスタッフが対応するため、さまざまな業務をスムーズに進められます。
弊社では、建設業の業務に対応している建設業特化のBPOサービス「ツクノビBPO」を提供しています。書類作成や図面の作成、積算業務など、幅広い業務を代行できます。ツクノビBPOでは、倍率200倍の選りすぐりの専任スタッフが対応いたします。
リソース不足を解消したい方は、ぜひこちらからお問い合わせください。
【まとめ】建設業における派遣禁止には理由がある!適用外の業務もあるため上手に取り入れよう
建設業で派遣労働者が禁止されているのは、安全性の確保と雇用の安定のためという2つの理由があります。
デスクワークや技術指導などの一部の例外を除き、もし違反した場合は、刑罰や建設業許可取り消しなどの厳しい処分が科されます。
しかし、建設業の人材不足を解消するために、派遣労働に代わる建設業務有料紹介事業や、建設業務労働者就業機会確保事業などの制度も設けられています。
繁忙期やにはこれらを利用して、法に違反することなく人材確保を行いましょう。
建設業界に強い人材派遣会社おすすめ10選についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
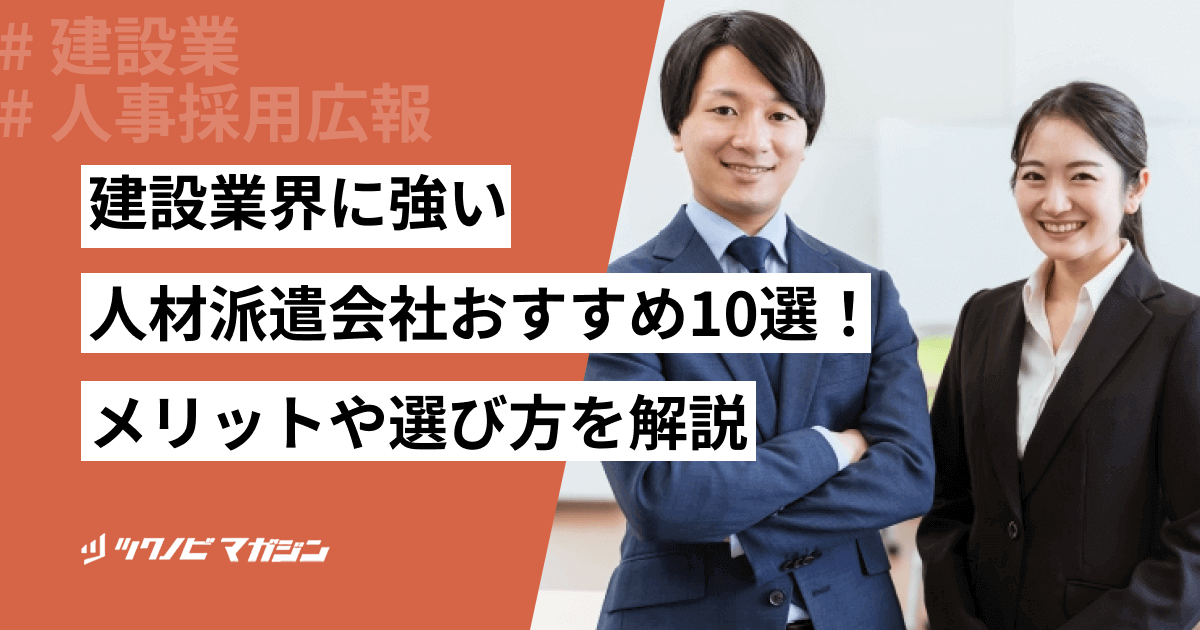 建設業界に強い人材派遣会社おすすめ11選!メリットや選び方を解説
建設業界に強い人材派遣会社おすすめ11選!メリットや選び方を解説