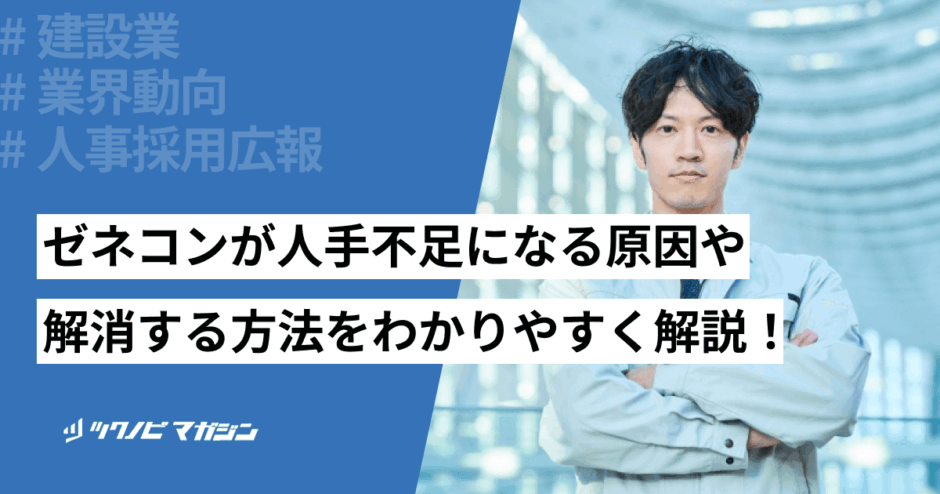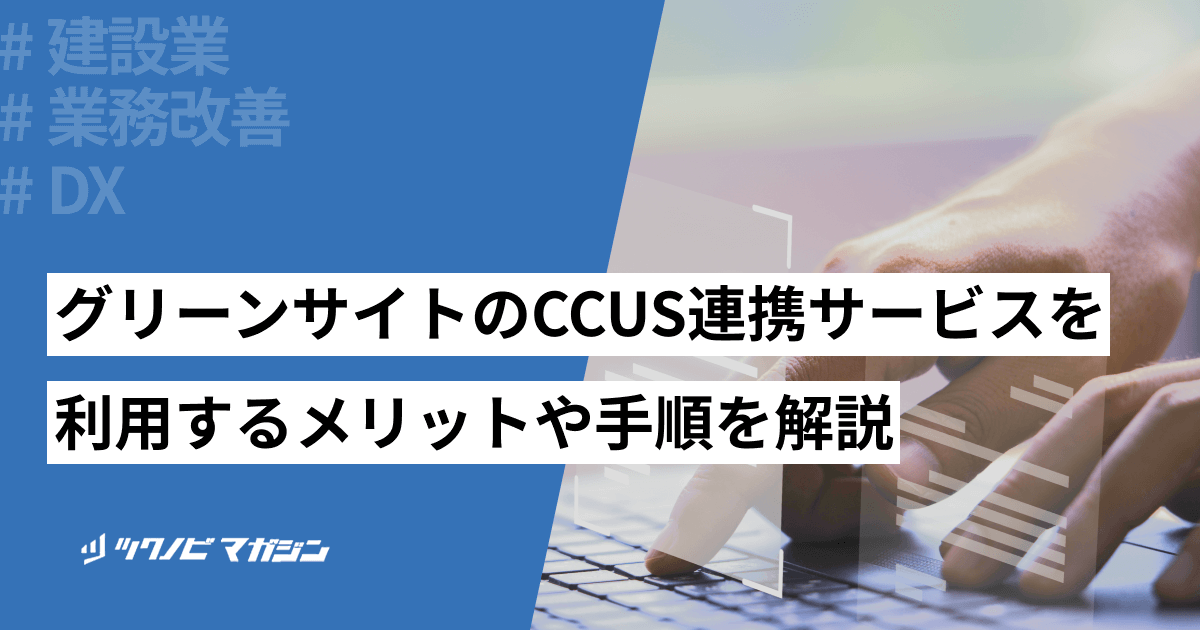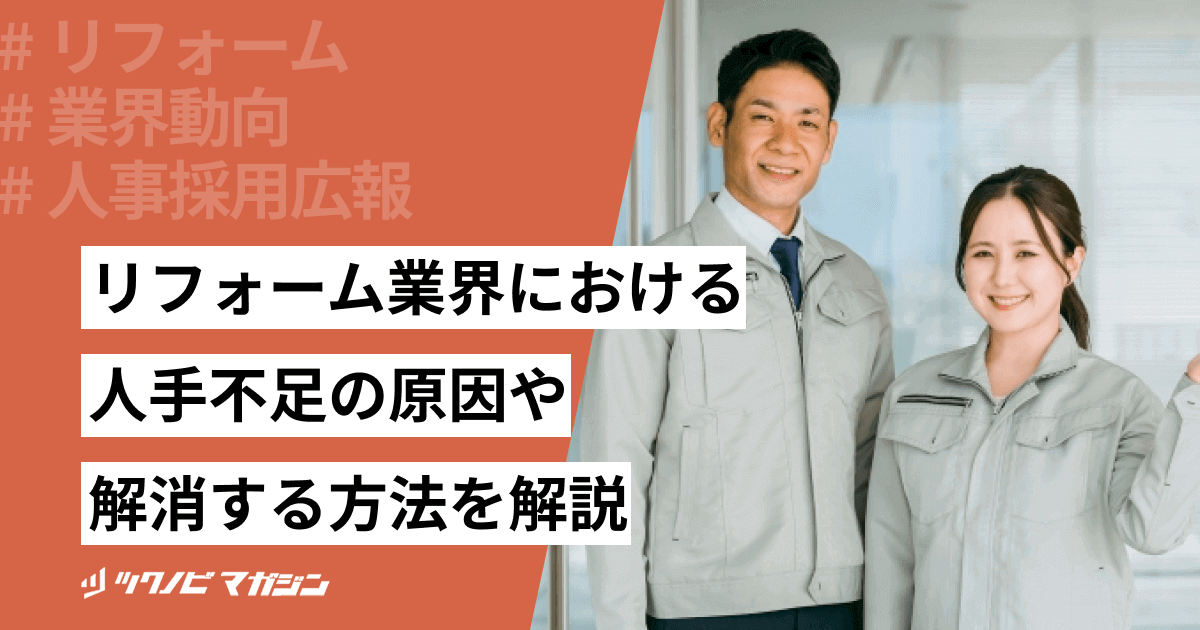※記事内に広告を含みます
「ゼネコン業界は人手不足が深刻なのか?」「若者が建設業界に入らない理由とは?」そんな疑問や不安をお持ちの人は多いです。
特に近年、建設業界は世界的に需要が高まっているにもかかわらず、慢性的な人手不足が問題視されています。その問題の中心に存在するのが、ゼネコンです。
今回は、ゼネコンの定義から現状、なぜ人手が足りないのか、そして将来の展望まで、分かりやすくご紹介します。建設業界に関心のある方、ゼネコンでの働き方を考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
ゼネコンとは
ゼネコンの人手不足について解説する前に、ゼネコンと建設業者の違いについて理解しておきましょう。
「ゼネコンの定義」と「スーパーゼネコンの定義」を簡単に紹介します。
ゼネコンの定義
ゼネコンとは、アパートやマンション、商業施設など、様々な建物の建設工事を手がける「総合建設業者」のことを指します。
単に工事を請け負うだけでなく、現場全体の施工管理や進行の調整、下請け業者への指示・監督といった役割を含めて、「総合建設業者」と言われるのです。
法律上、明確な定義があるわけではないですが、一般的には豊富な資金力を持ち、設計から施工までを自社で一貫して行える体制を備えている企業がゼネコンと認識されています。
中小の建設会社と、ゼネコンとの違いは、そのスケールと管理能力にあると言えるでしょう。
スーパーゼネコンの定義
スーパーゼネコンとは、ゼネコンの中でも特に規模が大きく、年間売上高が1兆円を超える企業グループを指します。
具体的には、鹿島建設、大成建設、竹中工務店、清水建設、大林組の5社です。
いずれも国内外の大型プロジェクトを多数手がけており、技術力・組織力ともに業界を牽引する存在です。
単に売上規模が大きいだけでなく、高度な設計・施工ノウハウを備え、超高層ビルや大規模インフラ整備などの複雑な工事に対応できる体制を整えている点が特徴です。なお、スーパーゼネコン各社は、建設だけでなく、売主(デベロッパー)として名を連ねることも少なくありません。
ゼネコンの現状
ゼネコンの現状を一言で表すと、「需要は高まっているのに人手不足が続いている」といういびつな状態です。
以下、ゼネコン業界の現状について、詳しく解説します。
需要は高まっている
近年、建設業界全体の需要は大きな増減こそ見られないものの、ゼネコンに関しては安定的に高い需要が続いています。
特に個人住宅の着工件数が減少する一方で、高速道路や橋梁といった社会インフラの老朽化対策が急務で、改修・更新工事へのニーズが高まっています。
また、2025年の大阪万博や2027年開業予定のリニア中央新幹線などの大型プロジェクトも、需要を下支えする要因となっています。
さらに、海外ではアジア諸国を中心に日本の高度な建設技術が注目されており、水道インフラや鉄道・道路整備、エネルギー関連施設の分野で技術輸出が期待されています。
ゼネコン・スーパーゼネコンの活躍の場は国内外ともに広がっており、今後も高い需要が継続する見通しです。
人手不足が課題となっている
需要が高まっている一方で、ゼネコン業界では深刻な人手不足が続いています。
その背景には、若者世代の建設業離れが影響しています。特に職人の高齢化が進み、若年層の就業者が減少している現状は、現場の持続性にとって大きな課題です。
建設業に対して「きつい」「危険」といったイメージが根強く、体力仕事や高所作業の多さが若者の敬遠につながっています。
実際、ゼネコン業界では29歳以下の就業者は減少し、55歳以上の割合が年々増加しています。
さらに、長時間労働などの労働条件も離職の要因となり、定着率が高くありません。
ゼネコンの人手不足は、今後、建設業界全体にも影響してくる大きな課題となっています。
ゼネコンが人手不足になる原因
ゼネコンが人手不足になる原因は、大きく分けて以下3つです。
- 入職者が少ない
- 若い技術者が少ない
- 労働環境の改善が進んでいない
それぞれ、順番に見ていきましょう。
入職者が少ない
ゼネコンをはじめとする建設業界では、入職者よりも退職者が多い状態が続いています。
特に若い世代の建設業離れは顕著で、職人の高齢化が進行していること自体が入職者の減少に拍車をかけています。
実際に、現場では身体を動かす仕事が多く、高所での作業や、工具を使った作業も含まれます。また、ゼネコン業界はいわゆる「3K」と呼ばれることもあり、男性社会のイメージも強いです。
さらに近年は働き方の多様化が進み、在宅勤務・テレワーク、そしてフリーランス志向が若年層に広がっていることも、建設業への入職を難しくしているのでしょう。
若い技術者が少ない
ゼネコンでは若い技術者が不足しています。建設業界全体で退職者が入職者を上回る傾向が続いており、世代交代が進まない現状があります。
このような状態では、なかなか労働者が「明るい将来」や「輝かしいキャリアステップ」を想像することができません。
若手技術者を育成し、若い世代が安心して働ける環境づくりができないと、ゼネコンの人手不足の解決は望めません。
労働環境の改善が進んでいない
ゼネコン業界では、長年にわたる労働環境の課題がいまだ解消されていないため、人材が集まりにくい側面があります。
実際に、建設現場では高所での作業や危険な工具を扱う作業も含まれ、心身ともに消耗しやすいです。
また、業界全体における長時間労働も問題です。建設業の年間総労働時間は他業種よりも長く、週休二日制が一般化する中で、週に1日しか休めないという職場も残されているのが現状です。
2024年からの残業規制強化によって是正が進んでいるものの、ネガティブなイメージは排除されていません。
加えて、日給月給制による収入の不安定さや、低さも問題です。スーパーゼネコンを別として、資格制度などのキャリア支援や福利厚生が整っていない企業が多く、若者離れに拍車をかけています。
ITやAIによる業務効率化の必要性は叫ばれているものの、現場の改革はまだまだこれからです。
ゼネコンが人手不足を解消する方法
ゼネコン業界が人手不足を解消するため、特に以下4つの方法が注目されています。
- 働き方改革を進める
- 省人化を図る
- 外国人を雇用する
- 派遣社員を活用する
順番に、詳しく解説していきます。
働き方改革を進める
ゼネコン業界の人手不足を解消するためには、働き方改革が不可欠です。具体的には、まず適切な工期設定が重要です。予期せぬトラブルや悪天候を考慮した余裕のある工期を設定することで、残業や休日出勤を抑制できます。
また、週休二日制の導入も必須です。現状では週休1日制の企業もありますが、完全週休二日制への移行によって労働時間の短縮とワークライフバランスの改善が期待できます。
さらに、現場作業員の技術を適切に評価し、給与水準を改善することも重要です。加えて、資格制度の整備によるキャリアアップ支援は、若手人材の定着に効果的です。これらの施策を総合的に実施することで、業界全体の働き方改革につながります。
省人化を図る
人手不足解消の2つ目の方法は、省人化です。その中心となるのが、ITツールと先進技術の導入です。
具体的には、タブレットを活用した現場状況の共有により、報告業務の効率化と遠隔管理が可能になります。また、BIMやCIMを導入することで、設計から施工までの情報共有が円滑化され、作業効率が向上します。
さらに、ドローンやAI、ロボット技術の活用も進んでいます。タワークレーンや重機の遠隔操作、現場巡視ロボットや自動清掃ロボットなど、様々な技術が実用化されています。
これらの新技術は、今後さらに普及が進み、ゼネコン業界の働き方、人材の在り方を大きく変革すると期待されています。
外国人を雇用する
建設業界の人手不足対策として、外国人労働者の受け入れも加速しています。
特に2019年に導入された特定技能制度により、最長10年間の就労が可能となり、建設分野では特定技能2号取得で無期限在留も認められています。
受け入れにあたっては、業務面だけでなく文化や習慣への理解を深める体制が重要です。企業は事前研修やセミナーを実施し、日常的なコミュニケーションをサポートすることで、スムーズな職場環境を整備します。
また、技能実習制度も併用され、技術習得と母国への還元を目指した人材育成も進められています。外国人労働者の活用は、建設業界の発展と人手不足解消に不可欠となっています。
派遣社員を活用する
ゼネコン業界の人手不足対策として、派遣社員の活用も有効です。
大手ゼネコンでは全従業員11万6,600人のうち、2万1,500人(16.3%)が派遣社員として働いており、この高い割合は人手不足や残業規制の影響によるものと言われています。
派遣社員の活用により、柔軟な人員配置と急な人手不足への対応が可能になります。また、派遣から正社員への転籍も増加しており、長期的な人材確保にも貢献しています。
一方で、短期的な人員確保に頼りすぎると、技術継承や人材育成に課題が生じる可能性があります。そのため、派遣社員への教育体制の整備も重要となっています。
正社員に切り替える
ゼネコン業界では、派遣社員の活用を進める一方で、派遣社員の正社員転籍も積極的に進めています。
この動きは、安定した人材確保を目指す企業側と、雇用の安定を求める働く側の双方にとって、魅力的な選択肢となっています。
実際、派遣から正社員への転換数は増加傾向にあり、正社員全体に占める転籍者の割合が20%を超えるケースも報告されています。
短期的な人手不足対策だけでなく、長期的な人材確保の有効な手段として、今後さらに重要性を増すと考えられています。
建設業の人手不足解消ならツクノビBPOがおすすめ
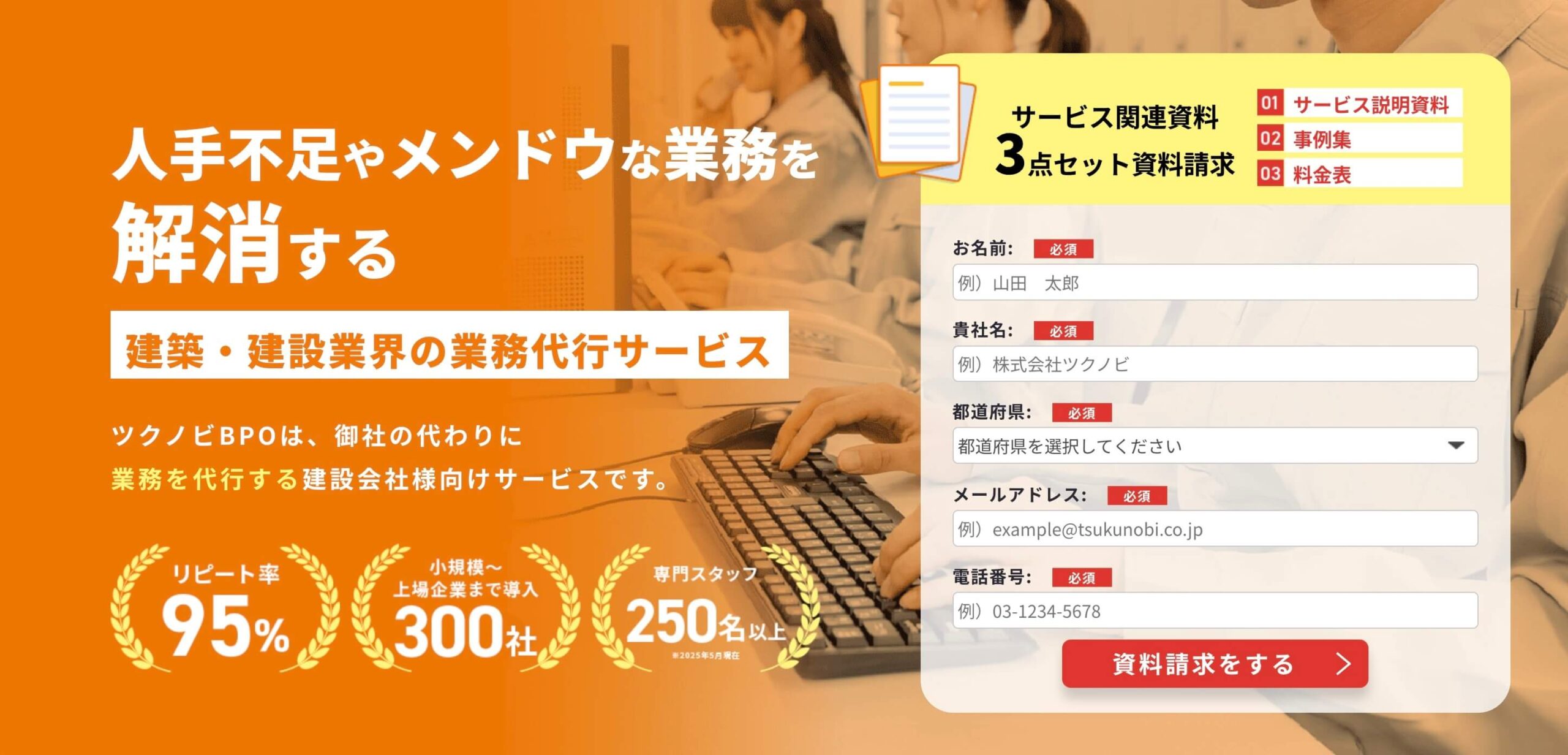
建設業の人手不足を解消するためには、アウトソーシングサービスの利用もおすすめです。
従業員のリソースがひっ迫している場合や、業務に対応できる人材が不足している場合などは、アウトソーシングサービスを活用すると、少ない工数で業務を実行できます。BPOサービスでは、専門的な知識を持っているスタッフが対応するため、さまざまな業務をスムーズに進められます。
弊社では、建設業の業務に対応している建設業特化のBPOサービス「ツクノビBPO」を提供しています。書類作成や図面の作成、積算業務など、幅広い業務を代行できます。ツクノビBPOでは、倍率200倍の選りすぐりの専任スタッフが対応いたします。
リソース不足を解消したい方は、ぜひこちらからお問い合わせください。
【まとめ】ゼネコンは人手不足が課題!省人化や外国人雇用などで対策しよう
今回の記事では、ゼネコンの定義や役割、そして建設需要の高まりとそれに伴う人手不足の現状、そしてその背景や今後の展望について解説してきました。
現在、ゼネコン業界は若手人材の減少や、職人の高齢化といった課題に直面しています。
その一方で、働き方改革の推進、省人化技術の導入、さらには外国人労働者や派遣社員の活用といった多様な対策が進められており、人手不足解消に向けた動きも広がりつつあります。
人材の不足は確かに大きな課題ですが、それを乗り越えることでゼネコン業界全体がより持続可能な方向へと進む変革のタイミングでもあります。今後のゼネコン業界に、注目です。
ゼネコンの残業時間が全業界の平均より長い理由やゼネコンのDXへの取り組みについてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
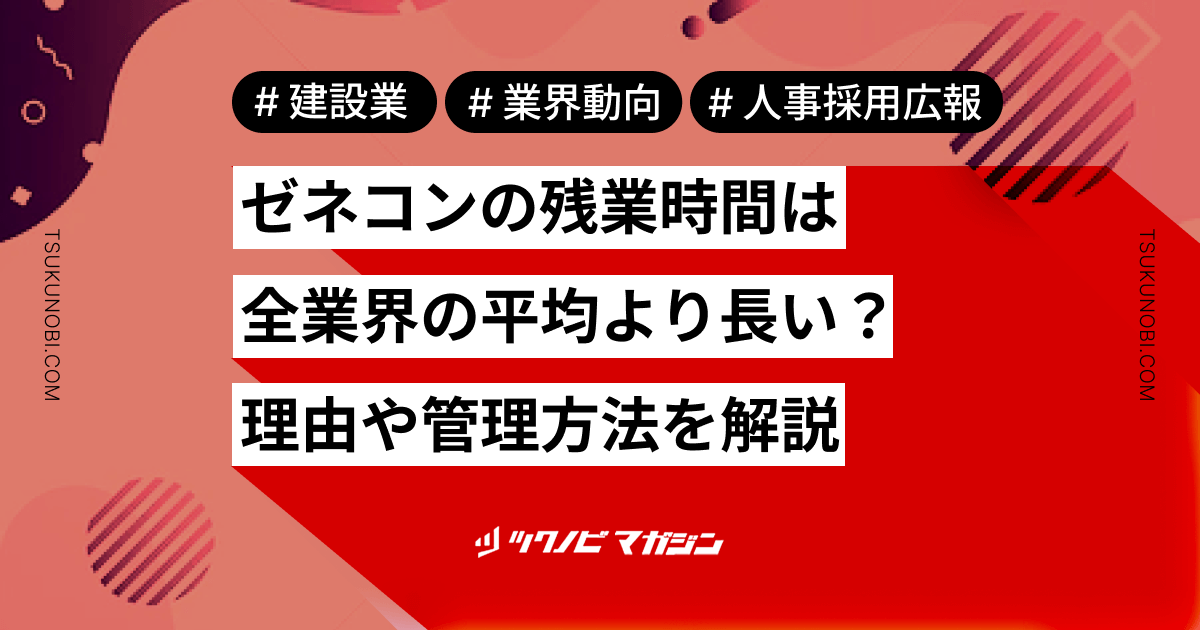 ゼネコンの残業時間は全業界の平均より長い?理由や管理方法を解説
ゼネコンの残業時間は全業界の平均より長い?理由や管理方法を解説
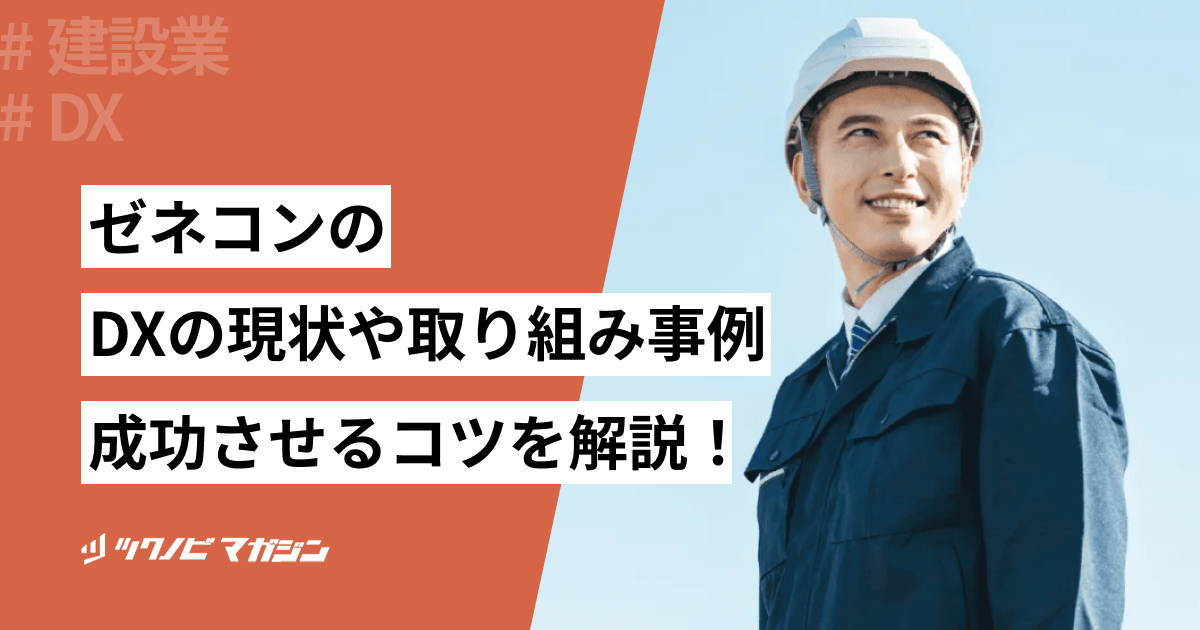 ゼネコンのDXの現状や取り組み事例・成功させるコツを解説!
ゼネコンのDXの現状や取り組み事例・成功させるコツを解説!
建設事務の人手不足の現状についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
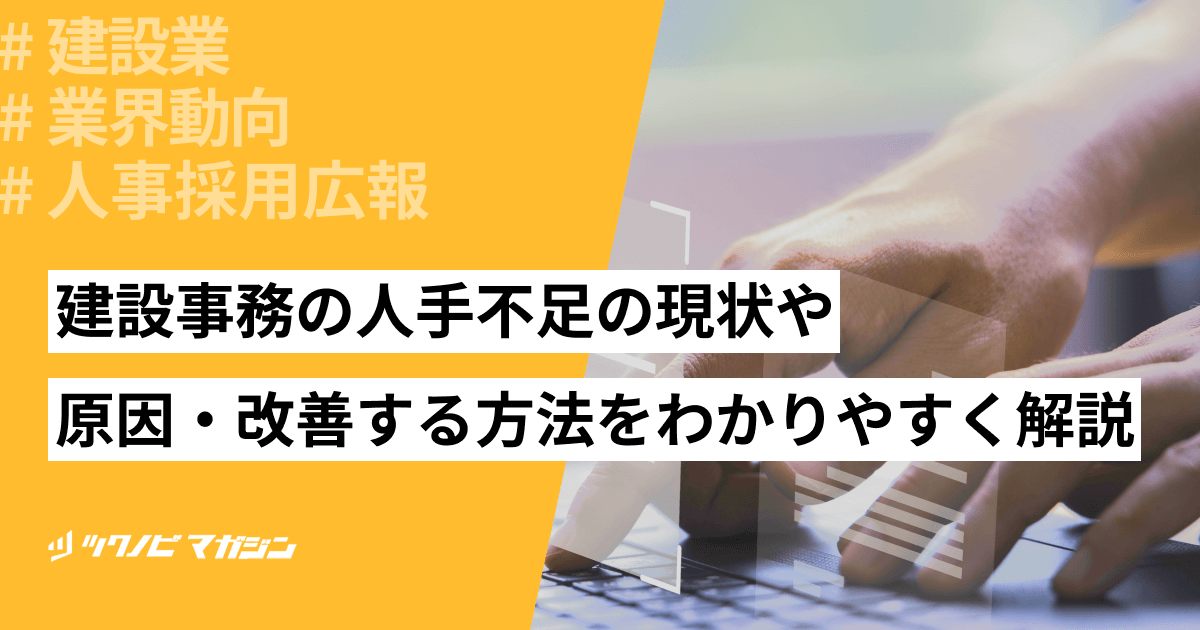 建設事務の人手不足の現状や原因・改善する方法をわかりやすく解説
建設事務の人手不足の現状や原因・改善する方法をわかりやすく解説