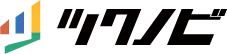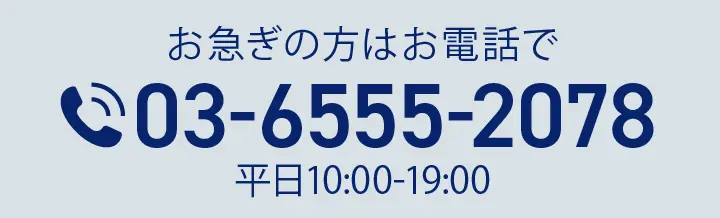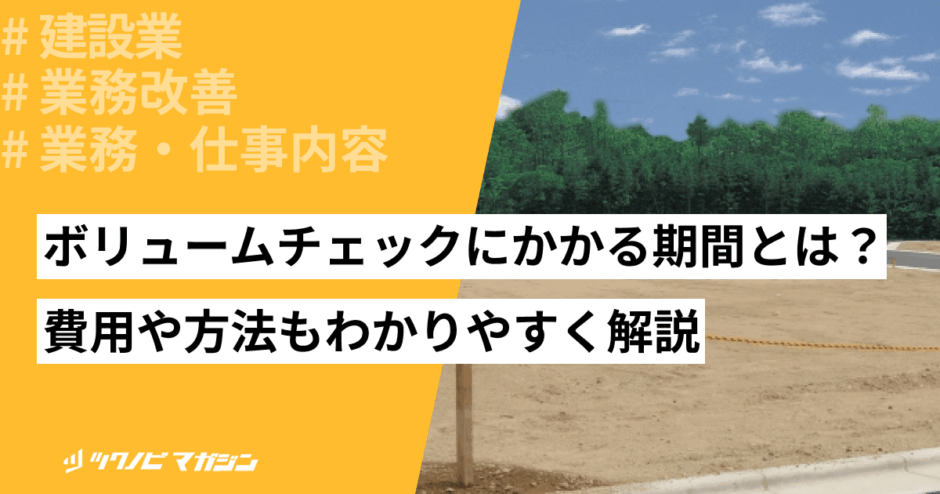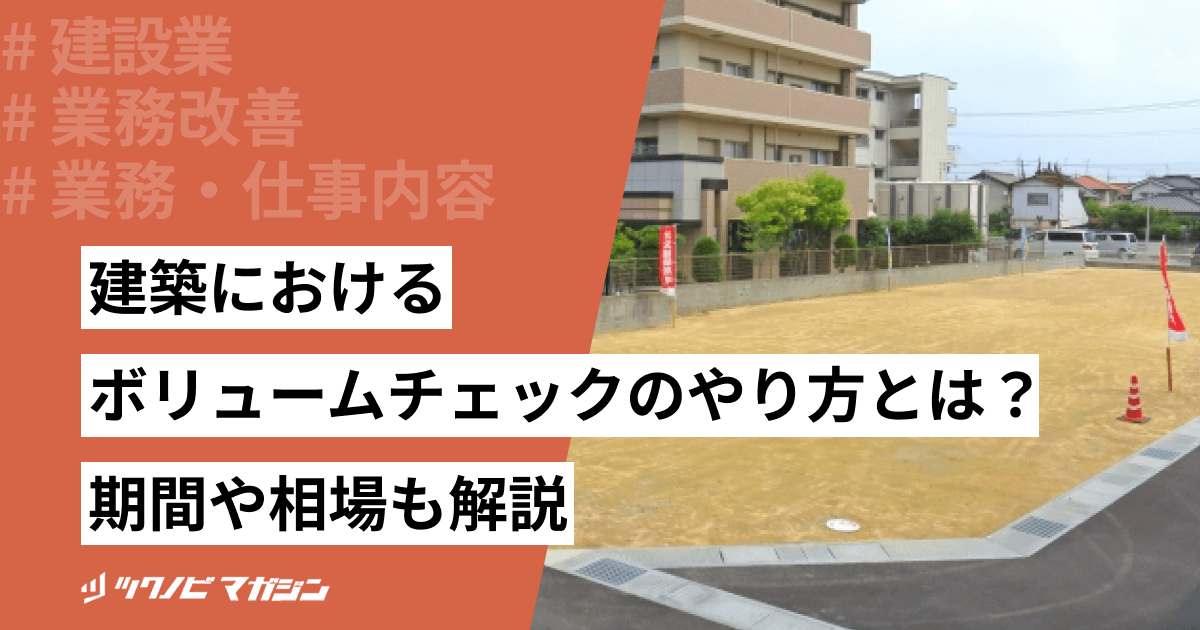※記事内に広告を含みます
ボリュームチェックは、建築計画の初期段階で重要な工程です。建築面積や容積率をもとに、建てられる建物の規模を計算します。慣れないと難しい作業のため、どのくらいの期間や費用がかかるのか、わからず作業を進められないと悩む人も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、ボリュームチェックの期間・費用と方法をわかりやすく解説します。実務で使える要点を整理しましたので、ぜひ最後までご覧ください。
施工管理の経験が豊富なプロ人材が御社の施工管理業務を代行いたします。施工管理の経験者をすぐに採用でき、施工管理人材の人手不足を解消できることで、受注できる案件の増加や退職率の低下など、様々なメリットがあります。詳細はぜひこちらからご確認ください。
ボリュームチェックとは
ここでは、ボリュームチェックの概要と目的を整理して解説します。建築物のボリュームの計算は建築計画において重要な工程ですが、概要や目的を正しく理解しなければ、必要な計算ができません。
そのため、「ボリュームチェックとは何か」「何のために行うのか」を把握することで、建築計画をより具体的に立案しやすくなります。これから解説する内容を理解して、効率的な建築計画の立案に活用してみてください。
ボリュームチェックの概要
ボリュームチェックとは、敷地条件や法的制限をもとに、建築可能なボリューム(容積)を試算する作業です。建ぺい率・容積率・斜線制限などを踏まえて、「この敷地にどのくらいの大きさの建物が建つのか」を可視化します。
これまでは知識と経験のある設計士などが計算していました。しかし、近年はAIや専用ソフトも普及しています。AIツールを使えば、短時間で建物計画の立案が可能です。
ボリュームチェックの目的
ボリュームチェックの主な目的は、大きく分けて以下の3つがあります。
- 法規制内で最大限の建築計画を検討
- 事業性の試算
- 設計・施工段階のトラブルを防止
特にマンションや商業施設など規模が大きい案件では、建物のボリューム計算の精度が事業収支の成否を左右します。
また、建築主が「どこまで建てられるか」を早期に把握できるため、土地購入や企画段階の意思決定にも欠かせません。
建築物のボリューム計算は、建築計画の初期段階で大きな役割を果たします。
ボリュームチェックにかかる期間
近年はAIや専用ソフトの登場により、建物のボリューム計算に必要な期間も短縮されました。
しかし、慣れた人でも簡単に計算できるものではありません。そのため、計算にどれくらいの時間がかかるかを把握しておかないと、建築計画の進行に悪い影響を及ぼす恐れがあります。
そこで、ここでは、ボリュームチェックの期間と必要な下準備を解説します。ボリュームの計算に取り組む前に、必要なことを把握して、適切に作業に取り掛かることを心がけてみてください。
一般的にかかる期間
ボリュームチェックの期間は、建物の規模・用途・情報量によって異なりますが、一般的には2〜7営業日ほどが目安です。
戸建てなどの小規模な建築物であれば、図面・法規確認やボリュームモデル作成などで2〜3日ほどです。共同住宅や事務所などの中規模な建築物の場合、条件整理や配置案・簡易パースの作成などで3〜5日程度必要です。
商業施設や複合施設などの大規模な建築物の場合、詳細検証や複数案の比較、報告書作成などで5〜7日ほどかかります。
早ければ1日で概算チェックを出すことも可能ですが、法的制限や周辺環境の確認を含めると、数日程度は必要です。
スムーズに行うための共有資料や情報
ボリュームチェックを効率的に進めるためには、以下の資料を事前に共有しておくことが重要です。
- 敷地図・測量図(正確な寸法・方位・高低差がわかるもの)
- 用途地域・建ぺい率・容積率の情報
- 接道条件・建築制限(斜線・日影などの情報)
- 希望する建物規模・階数・用途
これらが揃っていないと、再確認や修正作業が発生して期間が延びる場合があります。AIアプリや無料ソフトを使う場合でも、正確な敷地情報を入力しないと誤差の原因となるため注意が必要です。
ボリュームチェックにかかる費用
ボリュームチェックの費用は、依頼先や使用ツールによって異なります。一般的な相場を表にまとめましたので、以下をご覧ください。
| 方法 | 費用目安 |
| 設計事務所に依頼 | 5万〜20万円程度 |
| 不動産会社・デベロッパーに依頼 | 無料〜10万円程度 |
| AI・無料ソフトを利用 | 無料〜数万円程度 |
設計事務所に依頼する場合、基本的に有料です。不動産会社やデベロッパーは土地販売の付帯サービスとして、建築物のボリューム計算をしてくれる場合があります。AIや無料ソフトを使えば、自社で簡易的にボリュームの計算が可能です。
ただし、正式な設計や申請を見据える場合は、設計事務所に正式依頼して精度を確認することが重要です。
ボリュームチェックを行っている企業と選び方
建物のボリュームの計算は、建築計画の精度を左右する重要な工程です。依頼先を選ぶ際は、法規に精通した企業かどうかを見極めなければいけません。ボリュームチェックの主な依頼先は以下の3つです。
- 一級建築士事務所
- 不動産会社
- ハウスメーカー・工務店
ここでは、それぞれの依頼先の特徴と選ぶ際のポイントを解説します。依頼先ごとの違いと選び方を把握して、適切な企業へ依頼するための知識を身につけましょう。
企業
ボリュームチェックを依頼できる企業は多岐にわたりますが、重要なのは精度と法令対応力です。例えば、一級建築士事務所は法規的観点からの検証に強く、不動産会社は土地活用視点からの提案が得意です。
ハウスメーカーや工務店は、建築コストを踏まえた現実的なボリューム提案を行えます。目的が「土地開発」か「住宅建築」かによって、最適な依頼先を選ぶことが重要です。
ここから解説する3つの企業の違いを理解し、建築目的に応じた依頼先を見つける参考にしてみてください。
一級建築士事務所
一級建築士事務所は、法令遵守と設計精度の高さで最も信頼性が高い依頼先です。一級建築士事務所のボリュームチェックでは、建ぺい率や容積率、高さ制限などを厳密に確認します。そのうえで、建築可能なボリュームを提示する点が特徴です。
また、配置計画や用途地域の制約も踏まえ、将来的な申請や設計段階にもスムーズに移行できます。費用は5〜20万円程度かかることもありますが、精度重視のプロジェクトでは最適な選択肢です。
不動産会社
不動産会社によるボリュームチェックは、多くの場合、土地活用や事業性の検証を目的としています。土地販売や開発提案の一環として、無料で簡易ボリュームを提示することも珍しくありません。
不動産会社では、建物配置や容積率を概算で算出し、建築可能な建物を可視化します。
ただし、詳細な設計には対応できないため、後から設計事務所での再確認がおすすめです。不動産会社によるボリュームの計算は、建築計画の初期に、建築物のイメージを作る際に最適です。
ハウスメーカー・工務店
ハウスメーカーや工務店は、実際の施工コストやプラン提案を重視したボリュームチェックを行います。
自社の設計基準をもとに、建築可能な面積を算出し、具体的なプランや見積もりを提示するのが特徴です。建築に直結する提案が得られるため、実施設計を前提とした相談に向いています。
ただし、法規確認は簡易的なことが多く、複雑な敷地では建築士のチェックを併用すると安心です。具体的なプランが明確になれば、厳密なボリュームチェックが可能なため、1社で計算が完結できる場合もあります。
選び方
ボリュームチェックの依頼先を選ぶ際は、目的・精度・対応スピードの3点で比較することが重要です。事業性を重視するなら不動産会社、法的根拠を重視するなら設計事務所、施工費を意識するなら工務店をおすすめします。
また、AIソフトを併用して初期段階の方向性を早期に把握し、詳細検証を専門家に任せるハイブリッド型も有効です。依頼時には、過去実績や提案スピード、報告書の内容もチェックする必要があります。
ボリュームチェックの目的を念頭に置いて、依頼先を選んでみてください。
ボリュームチェックを行う方法
ここからは、ボリュームチェックの方法を具体的に解説します。建築物のボリュームを計算する際は、まず「敷地条件」と「法的制限」を正確に把握することが重要です。具体的には「容積率の確認・計算」と「建築制限(高さ・斜線・日影)」などを順に検討します。
これらを整理することで、建築可能な延床面積を試算でき、実現性の高い設計計画を立てられます。最近ではAIやBIMソフトを活用して自動計算する方法も普及し、短期間で精度の高い計算が可能です。
容積率を把握・計算する
ボリュームチェックの第一歩は、容積率の把握と計算です。容積率とは、敷地面積に対する建物の延床面積の割合を示す指標で、建物のボリュームを決定づけます。都市計画区域や用途地域ごとに上限が異なり、土地の利用効率や建築規模を左右します。
容積率を正しく理解しておくことで、計画段階から無理のない設計や事業計画の立案が可能です。ここでは、容積率の確認と計算の方法を解説します。
容積率の確認方法
容積率の上限は、市区町村の都市計画図や役所の建築指導課で確認できます。また、自治体の公式サイトでも「用途地域」「建ぺい率」「容積率」が公開されていることが多く、オンラインでの確認も可能です。
敷地が複数の用途地域にまたがる場合や、前面道路の幅員によって制限を受けるケースもあります。このため、現地確認と公的資料の照合を行うことが正確なボリューム算出につながります。
必要に応じて自治体に確認し、法令違反にならないようにボリュームチェックを行うことが重要です。
容積率の計算方法
続いては、容積率の計算方法を解説します。容積率の基本式は以下のとおりです。
容積率(%)=(延床面積 ÷ 敷地面積)× 100
例えば、敷地面積200㎡・延床面積300㎡の場合、容積率は150%となります。ただし、車庫や地下室など一部の用途は容積率に算入されないため、建築基準法第52条を参照して判断することが重要です。
また、土地の前面道路の幅員によっては、上限が変動する場合もあります。そのため、設計段階では必ず法令チェックを行いましょう。
土地に関する制限を確認する
容積率以外にも、建築物の形状や高さを制限する法的規制が存在します。代表的なものが高さ制限や斜線制限、日影規制です。これらは周辺環境や採光・通風を確保する目的で定められています。
ボリュームチェックでは、これらの制限を踏まえて建物の高さや位置を調整することが求められます。誤った計算は、後に建築確認の不適合につながるため注意が必要です。ここでは、高さや斜線に関する制限と日影規制を詳しく解説します。
高さや斜線制限
高さ制限とは、建物の最高高さを用途地域ごとに制限する基準です。
斜線制限には「道路斜線」「隣地斜線」「北側斜線」などがあり、周囲への日照や圧迫感を防ぐ目的で設定されています。ボリュームチェック時には、これらの制限を図面上で立体的に検証し、どこまでの高さ・形状が許容されるかを確認します。
BIMやCADを用いれば、制限を可視化して迅速に調整することが可能です。高さや斜線制限に適合していない場合、後からトラブルになる恐れがあるため、必ず遵守しなければいけません。
日影規制
日影規制とは、建物が敷地外に作る影の時間や面積を制限する制度です。主に中高層住宅地域や商業地域で適用され、冬至日を基準に日影時間を算出します。
一定時間以上の影を他人の敷地に落とすことは認められないため、ボリュームや高さの調整が必要になります。ボリュームチェックの段階で日影シミュレーションを行うことで、建築確認後の修正リスクを最小限に抑えられます。
日影規制も遵守しなければトラブルの元となるため、注意が必要です。
ボリュームチェックを行う際に役立つ資格
ボリュームチェックには、建築法規や都市計画に関する知識が求められます。代表的な資格として、以下が挙げられます。
- 一級・二級建築士
- 宅地建物取引士
- 建築積算士
特に一級建築士は、法的制限を踏まえた設計判断ができ、高精度なボリューム提案を行ううえで不可欠な存在です。
近年はAIやBIMソフトを扱う、BIM利用技術者の資格も重視されています。概算レベルのボリュームチェックであれば、無料ソフトで資格がない人でも計算が可能です。
ボリュームチェックを行う際の注意点
ボリュームチェックをする場合、容積率を意識し過ぎないことが良い場合があります。
特に集合住宅や商業施設などの中規模以上の建築物の場合、土地活用と需要のバランスを意識することが重要です。なぜなら、容積率をフルに消化しても、需要がなければ無駄に建築費用をかけるだけになる恐れがあるからです。
また、需要・日照・通風の条件によっては、容積率の最大化が最適解とは限りません。こうしたことから、土地活用の計画とニーズのバランスと周辺環境を意識することが大切です。
建設業の人手不足解消ならツクノビBPOがおすすめ
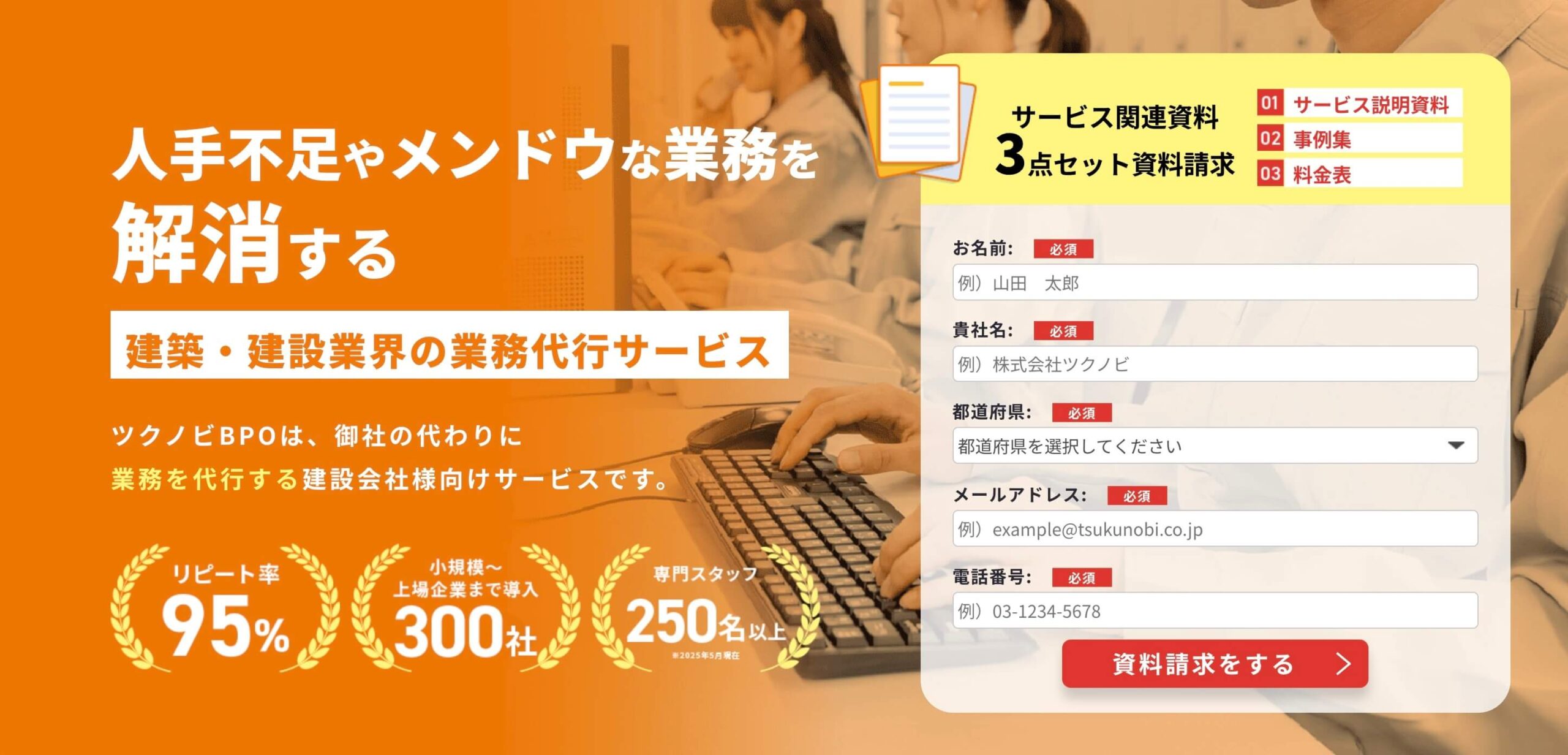
建設業の人手不足を解消するためには、アウトソーシングサービスの利用もおすすめです。
従業員のリソースがひっ迫している場合や、業務に対応できる人材が不足している場合などは、アウトソーシングサービスを活用すると、少ない工数で業務を実行できます。BPOサービスでは、専門的な知識を持っているスタッフが対応するため、さまざまな業務をスムーズに進められます。
弊社では、建設業の業務に対応している建設業特化のBPOサービス「ツクノビBPO」を提供しています。書類作成や図面の作成、積算業務など、幅広い業務を代行できます。ツクノビBPOでは、倍率200倍の選りすぐりの専任スタッフが対応いたします。
リソース不足を解消したい方は、ぜひこちらからお問い合わせください。
【まとめ】ボリュームチェックにかかる期間を把握しスムーズにプロジェクトを進めよう!
この記事では、ボリュームチェックの概要や必要な期間や費用を解説しました。
建築物のボリューム計算は、建築計画の方向性を決める重要なステップです。期間は一般的に2〜7営業日、費用は依頼先によって異なりますが、精度を重視するなら設計事務所・スピード重視ならAI活用が効果的です。
容積率や高さ制限を正確に把握し、事前に必要情報を整理すれば、設計・申請がスムーズに進行します。早期段階での正確なボリュームの把握が、コスト削減とプロジェクト成功のカギです。効率的なボリュームチェックで、土地活用に最適な建築計画を立てましょう。