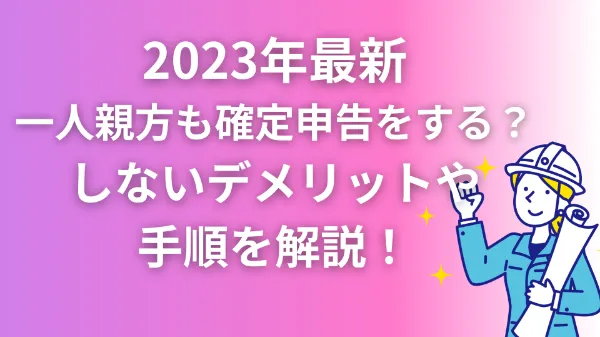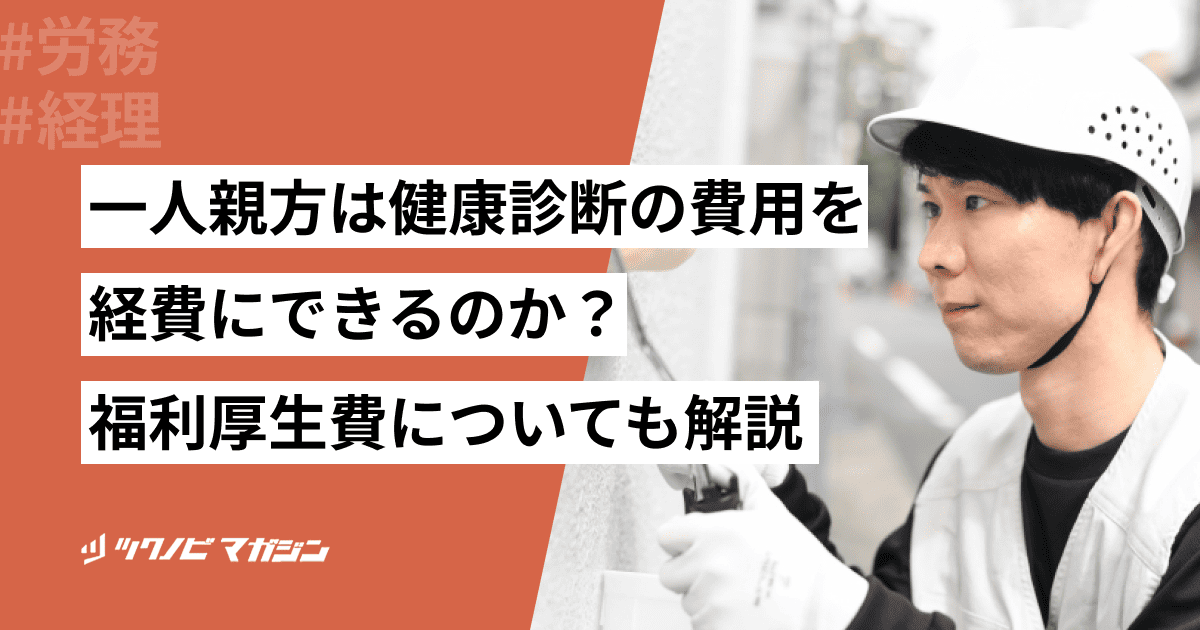※記事内に広告を含みます
一人親方とは、労働者を雇用せず事業を行う方、いわゆる個人事業主のことを指します。
親方という響きから、土木・建設関係の事業で働いている方を思い浮かべる方も少なくないかと思いますが、ドライバーや漁業従事者、廃棄物処理業に関わる方や、労働者を雇っている方でも年間で雇う日数が100日未満の場合は一人親方と呼ばれます。
今回は一人親方をされている方の確定申告のメリット、デメリットとその手順について解説したいと思います。
領収書の保存や経費の計算、帳簿付け、確定申告まで簡単にできるのが一人親方向け経理アプリのTaxnap(タックスナップ)です!
無料で利用ができることから、2023年にリリースしてすぐに5万ユーザー突破しました!
一人親方も確定申告をする必要がある!
会社勤めの経験のある方なら、今まで年末調整が行われていたと思います。しかし、一人親方になった方は会社勤めではなくなるため年末調整が行われません。このため、確定申告を行って、自分自身で納税をする必要が出てきます。
一人親方が行う確定申告の種類
確定申告を行う必要性は理解できたでしょうか。以下では、一人親方が行う確定申告の種類について紹介します。
青色申告
青色申告は、会計帳簿に記帳した日々の取引を、記帳に基づいて申告をすることで、所得計算などで税務上有利な取り扱いが受けられる制度です。青色申告を行う場合、事前に税務署へ開業届と青色申告承認申請書を提出する必要があります。
青色申告を行う最大のメリットは「青色申告特別控除」を受けられることです。最高65万年の控除を受けられます。その他のメリットは、以下の通りです。
- 家族への給与を必要経費として計上できる
- 純損失の赤字を3年間繰り越せる
- 減価償却の特例を受けられる
青色申告は、白色申告に比べて多くの節税が可能です。
白色申告
青色申告の対象外となる方や複式簿記による記帳をしていない場合は、白色申告で確定申告を行うことになります。白色申告する場合は、簿記などの専門知識が不要です。簡単に確定申告が行えます。
しかし、青色申告に比べてメリットが少ないです。そのため、特別な理由がなければ一人親方の場合、青色申告を行うことがおすすめです。
一人親方が確定申告をする手順
確定申告はどのような手順で行えばよいのでしょうか。ここからは、一人親方が確定申告をする手順について詳しく解説します。
白色確定申告と青色確定申告のどちらかを選ぶ
では確定申告をどのような手順でしていけばいいのでしょうか。
確定申告には「白色確定申告」と「青色確定申告」の2種類があります。
- 白色確定申告とは
単式簿記と呼ばれるとてもシンプルな記帳で行える確定申告のことをいいます。所得の控除を受けることができません。
- 青色確定申告とは
「青色申告承認申請書」という書類が必要になります。単式簿記とは違い、複雑な複式簿記が求められます。
白色確定申告より難しいですが、難しいかわりに毎年の取得から決まった金額の控除を受けることができます。
まずは、どちらを選んだほうが自身にとってメリットが大きいかを確認し、自身に合ったやり方を選びましょう。
所得金額を計算する
確定申告の方法が決まれば次に行うのは実際申告する際に必要な計算です。
式は「所得金額=収入−経費」となります。
例えば、一人親方の売上が年間500万だとすると、仕事に必要な材料費などに150万かかった場合、「500万−150万=350万」ということになります。
課税所得金額を計算する
では次に、取得金額から「所得控除」を差し引いて課税所得金額を求めていきましょう。
計算式は「課税所得金額=所得金額−所得控除」になります。
所得控除とは、条件に合わせて所得の合計金額から一定の金額を差し引くことができる制度のことを言います。
所得控除ができる費用としては、医療費、社会保険料、生命保険料、地震保険料、ひとり親控除、障害者控除、配偶者控除などが挙げられます。
控除できる金額はその人の各種費用によって異なります。保険料や医療費の控除額が知りたい場合は年末に送られてくる書類で確認ができるため、送られてきた場合は大切に保管しておきましょう。
税額を計算する
課税所得金額を求めることができたら、税額所得税の税額を計算していきます。所得税の税率は課税所得金額によって決められているため、金額が大きいほど税率も高くなっていきます。
税額の計算式は「所得税額=課税所得金額×所得税率−税額控除」となります。税率と税額控除の金額はホームページで確認することができるため、税額を計算する際は確認を忘れないようにしましょう。
税務署に必要書類を提出する
ここまで計算できたら、必要な書類に記入を済ませて税務署に確定申告書を提出します。確定申告の期間は原則2月中旬から3月15日です。管轄の税務署に必要な書類を提出します。
確定申告に必要な書類は、白色確定申告と青色確定申告で異なるため注意しましょう。
【白色確定申告で必要なもの】
- 確定申告書B
収入や取得金額、計算した税額を記載する。
- 収支内訳書
収入や原価、人件費や家賃等の費用を計算し、所得を記入する。
- 各種控除関係の書類
が必要となってきます。
対して青色確定申告で必要なものはまた違いますので、こちらも記載させていただきます。
【青色確定申告で必要なもの】
- 確定申告書B
- 各種控除関係の書類
- 青色申告決算書
になります。
また、収入と経費を記載する「損益計算書」、「損益計算書の内訳」、資産や負債の状況を記載する「貸借対照表」を合計4枚作成する必要もあります。
もし、こちらの書類を自分で用意するのが難しい場合は収入と支出を入力すれば自動的に必要な金額を計算してくれる会計ソフトを利用するのをおすすめします。
白色確定申告であれば、無料で使えるソフトも多いので、会計ソフトを是非活用してみてください。
領収書の保存や経費の計算、帳簿付け、確定申告まで簡単にできるのが一人親方向け経理アプリのTaxnap(タックスナップ)です!
無料で利用ができることから、2023年にリリースしてすぐに5万ユーザー突破しました!
一人親方が確定申告をしないデメリット
一人親方が確定申告しないと無申告加算税や延滞税のペナルティが発生するだけでなく、各種サービスが受けられなくなるというデメリットがあります。以下詳しく紹介します。
建設業許可の取得ができない
建設工事の請け負いやその他建設業務に当たって、建築物を完成させるためには公共や民間など関係なく、建設業法第三条に基づき、建設業の許可が必ず必要となります。
ちなみに、工事1件の請負料金が1500万円以下の工事や面積150平方センチメートル未満の木造住宅工事のような建設工事を主にする場合は許可を受けなくても工事が可能です。
しかし、大きい仕事を考えている建設業者には必要不可欠となってくるのです。
では、建設業の許可を貰うためにはどうすればいいのでしょうか。それには条件があります。
役員の一人に「経営業務の管理責任者としての経験が5年以上あるもの」というものが必要です。
ですが仮に一人親方が5年以上経験がある、というのであれば許可を貰うことが出来るのですが、その経験を証明するものが確定申告書になるのです。
仕事の腕前が認められているのに、確定申告をしないと仕事を請け負うこともできなくなります。
無申告加算税が発生する
確定申告をしないといけない期間が過ぎてから申告したり、期間内に申告しなかった場合は無申告加算税というものが発生します。
納付すべき金額が50万までなら15%、50万を超える場合は20%を上乗せされます。
ただし、税務署からの調査を受ける前に自主的に期間後に申告をすれば無申告課税が5%にまで減ります。
また、期間のあとに申告した場合であっても、その申告が法定申告期限から一ヶ月以内に自主的に行われている等いくつかの条件を満たすと、無申告加算税が課せられない場合もあります。
延滞税が発生する
定められている期限内に納税をしなかった場合、原則法延納期限の次の日から納付するまでの日数に応じて、利息と同じようなものの延滞税がかかってくることになります。
因みに、延滞税の割合は年度によって異なるため、国税庁のホームページを見て確認しましょう。
各種サービスが受けられなくなる
例えば住宅ローンを組みたいと考えていたり、子供を保育園に入園させたいと思っていたりするとき、手続きが必要になってきますよね。
その手続きを行うためには所得を証明しなければなりません。
一人親方が取得を証明するには、課税証明書、納税証明書、確定申告の写し、計3つの書類が必要となってきます。
この書類の名称を見てもらえれば分かりますが、納税していることを証明する書類ばかりになります。
逆に言えば、この書類が用意できなければ先程挙げたサービスを受けることができなくなります。そのため、しっかり確定申告は行うようにしましょう。
一人親方が確定申告で経費計上できるもの
一人親方の確定申告で重要なことは、必要な経費をきちんと収入から差し引いて、正しい利益を算出することです。
適正な範囲で経費を計算すれば、大幅な節税をすることも可能になってきます。しっかりと経費を計算する事が大切です。
ここからは、一人親方が確定申告の金額を計算した際にかかる経費について紹介していきたいと思います。
基本的に事業に関する費用は経費に換算されます。ただし、所得税や住民税、交通反則金等は経費として認められません。
そして、ボールペンやコピー用紙等の消耗品、仕事に使う携帯電話やネット代等も仕事と直接結びついているものなので、経費として計算することが可能です。
経費である証拠を残しておくためにも、必ず領収書や取引先の企業名が記載してあるものは記録として残しておきましょう。
領収書の保存や経費の計算、帳簿付け、確定申告まで簡単にできるのが一人親方向け経理アプリのTaxnap(タックスナップ)です!
無料で利用ができることから、2023年にリリースしてすぐに5万ユーザー突破しました!
一人親方が確定申告をする際の注意点
一人親方が確定申告をする際に注意することが2つあります。
それをひとつずつ紹介したいと思います。
「外注費」と「給与」の違いを確認しておく
一人親方が確定申告で経費を計算する際に気をつけたいのが、誰かに仕事を手伝ってもらったときに支払う報酬です。
その報酬が「外注費」にあたるか、「給与」にあたるかによって課せられる税金が異なるため、正しく判断をして計算をする必要があります。
- 「外注費」
一時的な請負契約であるため、源泉徴収がなく、社会保険の加入義務もありません。
- 「給与」
長期にわたって雇用をしている場合は雇用契約となり、源泉徴収や社会保険の加入義務があります。
このように給与の方が課せられる税金の金額が多くなります。節税の為に無理やり外注費として計算しても税務調査が行われれば高確率で不正が見つかってしまいます。そのため、外注費と給与の違いをしっかりとわかったうえで区別し計算することが大事です。
日頃から取引をこまめに記帳する
日ごろから日々のすべての取引を請求書や領収書、通帳などから帳簿と呼ばれるものに記入しなければなりません
この帳簿に記入する作業は大変な作業ですが、現在は様々な会計ソフトが出ているので、会計ソフトを使用し帳簿付けをすることをお勧めします。
初めは会計ソフトを使用する際、難しいかもしれませんが、慣れると記入が簡単になるのでぜひ活用してみて下さい。
業種によって主帳簿と補助簿とあるのですが、こちらでは補助簿の種類を細かく記載したいと思います。
- 帳簿の名前概要
- 現金出納表
現金での取引を日付と発生順に記録する帳簿の事。
- 預金出納表
銀行預金での取引を日付と発生順に記録する帳簿の事。
- 経費帳
必要経費に関する取引をまとめた帳簿の事。
- 売上表
売り上げに関する取引をまとめた帳簿の事。
- 買掛表
材料費の支払いが後日になる取引をまとめた帳簿の事。
- 売掛表
売り上げの回収が後日になる取引をまとめた帳簿の事。
- 固定資産台表
減価償却する固定資産をまとめたもの。
棚卸を行い資産状況を正確に把握する
一人親方が正確な利益を確定するためには、「棚卸し」という作業が重要になってきます。
棚卸しとは、簡単に説明すると在庫管理をする仕事となります。今ある在庫を把握して正しい利益や経費を算出することが目的です。
在庫として残っている材料は棚卸資産と呼ばれ、経費から除外しなければなりません。実際に棚卸をして売上純利益を計算する際は以下の計算式を使用しましょう。
「売上純利益=売上ー(棚卸資産)」となります。
年末時点で残っている材料は、税金対策のために経費として計算ができません。「仕掛け品」と呼ばれる棚卸資産として計算する必要があるため、十分注意しましょう。
確定申告の期間を把握し、余裕を持って書類を準備する
では、確定申告をする準備ができれば、確定申告ができる期間を把握しなければなりません。申告対象期間は1月1日から12月31日までの一年間になります。
その一年間分を翌年2月16日から3月15日の間に管轄税務署へ申告し、納税をしなければなりません。
年度によって期間が変動することは無いので、余裕を持って必要書類などを準備しておきましょう。
確定申告の手間を省くなら
「仕訳や勘定科目と言われてもよく分からない」「確定申告はめんどくさい」そう思って、確定申告せずにいると、後から多額の遅延税を払わなくてはいけなくなります。
そうなる前に、どうしても確定申告が面倒だと感じる場合は税理士に申告業務を依頼しましょう。
税理士は確定申告の書類作成ができるだけでなく、節税方法のアドバイスをくれたり、将来法人化する際の融資の相談などもできます。
税理士といってもたくさんの事務所があるので、自分に合った税理士が分からない場合は税理士ドットコム![]() を使うのがおすすめです。
を使うのがおすすめです。
税理士ドットコム![]() は自分にあった税理士を見つけてくれる完全無料のサービスです。
は自分にあった税理士を見つけてくれる完全無料のサービスです。
まずは税理士ドットコムに無料登録して、自分にあった税理士を探してみると良いでしょう。
税理士はコストが高すぎる、、という方は確定申告が手軽にできるアプリの活用もおすすめです。
領収書の保存や経費の計算、帳簿付け、確定申告まで簡単にできるのが一人親方向け経理アプリのTaxnap(タックスナップ)です!
無料で利用ができることから、2023年にリリースしてすぐに5万ユーザー突破しました!
 建設業に強い税理士おすすめ15選!選び方や依頼するメリットも紹介!
建設業に強い税理士おすすめ15選!選び方や依頼するメリットも紹介!
【まとめ】一人親方も忘れずに確定申告をしておこう!
いかがだったでしょうか?
一人親方でも確定申告をする大事さが少しでも理解していただけたでしょうか?
この記事を参考にしていただき、一人親方の役に立てたら幸いです。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
※弊社の営業代行サービスであるツクノビセールスでは、
【効果が出なければ全額返金プラン】を新たにスタートさせました!

※詳しくは👆👆👆のバナーをクリック!!