※記事内に広告を含みます
施工管理技士は、建設プロジェクトの現場で重要な役割を担っています。しかし、厳しい労働環境や人間関係などの理由から、早期に離職するケースが少なくありません。そのため、なかなか人材が定着せずに困っている建設会社もあります。
本記事では、施工管理技士がすぐに辞める主な原因と、転職を成功させるためのポイントについて解説します。これからこれから施工管理技士を目指す方や、現在従事している方にとって、有益な情報となるでしょう。
施工管理の経験が豊富なプロ人材が御社の施工管理業務を代行いたします。施工管理の経験者をすぐに採用でき、施工管理人材の人手不足を解消できることで、受注できる案件の増加や退職率の低下など、様々なメリットがあります。詳細はぜひこちらからご確認ください。
施工管理技士がすぐに辞める原因
なぜ、施工管理技士がすぐに辞めてしまうのか、ここではその理由を分析していきましょう。施工管理技士が早期に離職する主な原因を詳しく紐解くことで、取り組むべき課題が見えてくるはずです。
休日が少ないため
施工管理技士がすぐに辞めてしまう理由の1つに、休日の少なさが挙げられます。施工管理の仕事は、プロジェクトの進行状況に応じて勤務時間が長くなりがちで、休日も十分に確保できないことは珍しくありません。
特に工期が迫っている場合や、天候不良によるスケジュール調整が必要な際には、休日出勤が求められることもあります。このような状況が続くと、プライベートの時間が減少し心身の疲労が蓄積され、結果的に離職を考える要因となります。
体力的にきついため
施工管理技士が辞める理由として、体力的にハードという面もあります。施工管理技士は、現場での監督業務や打ち合わせ、書類作成など多岐にわたる業務を担当します。現場での業務は屋外での作業が多く、天候や季節に左右されるため、体力的な負担が大きい仕事です。
また、長時間の立ち仕事や移動も多く、膨大な量の事務作業もこなさなければいけません。こうした多岐にわたる業務が体力的な疲労を引き起こし、離職の一因となることがあります。
給料と仕事量が見合わないため
施工管理技士の業務は多岐にわたり、責任も大きいにもかかわらず、給与がそれに見合わないと感じる方も少なくありません。そのため、退職する人も多くいます。特に、残業や休日出勤が多い場合、時給換算すると低く感じる人も少なくありません。
仕事量と給料のアンバランスが続くと、モチベーションの低下や不満が募り、離職を検討する要因となります。
人間関係が難しいため
施工管理技士が仕事を辞めてしまう理由として、職場内の人間関係もあります。
施工管理技士は、職人や他のスタッフ、発注者など多くの人々と関わりながら業務を進めます。業務を進めるためとはいえ、性格や仕事の進め方などの面で相性の悪い人と一緒に仕事をすることも珍しくありません。
現場では、年齢や経験が異なる多様な人々とのコミュニケーションが求められ、時には意見の衝突やトラブルが発生することもあります。これらの人間関係のストレスが原因で、離職を考える方もいます。
責任が重いため
施工管理技士は、プロジェクトの進行や安全管理、品質管理など多くの責任を負う仕事です。そのため、責任の重さに耐えかねて辞める人もいます。
特に、大規模なプロジェクトや厳しい納期の案件では、プレッシャーが大きく精神的な負担となることは珍しくありません。
このような重責が続くと、ストレスが蓄積し、離職を検討する要因となります。こうした原因を踏まえ、施工管理技士として長く働くためには、労働環境の改善や適切なサポート体制の整備が重要です。
施工管理技士がすぐ辞めてしまうときの対処法
施工管理技士がすぐに辞めてしまう要因には、過酷な労働環境や人間関係の負担など複数の背景があります。
離職を防ぐためには、現場で改善策を講じて働きやすさを高めることが不可欠です。
ここでは、施工管理技士がすぐ辞めてしまうときの対処法について、詳しく解説します。
労働環境を見直す
施工管理技士がすぐ辞めてしまうときの対処法は、労働環境を見直すことです。
長時間労働や休日不足は離職の大きな要因であり、改善には就業時間の管理や休日制度の整備が欠かせません。
例えば、現場の進捗管理を適切に行い、計画的に休暇を確保できる仕組みを導入することが有効です。
ITツールを活用して書類作成や報告業務を効率化すれば、残業時間の削減につながります。
さらに、現場設備の安全性を高める取り組みも労働環境改善の一環です。
環境を整備すると、施工管理技士のモチベーションを維持し、定着率の向上につなげられます。
アウトソーシングを活用する
施工管理技士がすぐ辞めてしまうときの対処法は、アウトソーシングを活用することです。
施工管理の業務は多岐にわたり、業務過多が離職の要因となるケースがあります。
外部の専門会社に一部業務を委託すれば担当者の負担を軽減でき、効率的に仕事を進められます。
例えば、事務処理や図面作成、積算業務は外注化が有効であり、技士は本来の管理業務に専念できるのです。
さらに、繁忙期や人員不足の場面でも柔軟に対応できるため、現場全体の安定化につながります。
アウトソーシングを適切に導入することは離職防止策として有効であり、施工管理の質を維持しながら働きやすい環境を実現する方法です。
コミュニケーションを活性化させる
施工管理技士がすぐ辞めてしまうときの対処法は、コミュニケーションを活性化させることです。
現場では多職種の人々と協力する必要があり、意思疎通が不足するとストレスや人間関係の悪化を招きます。
定期的にミーティングや情報共有の場を設ければ、問題を早期に発見し解決につなげられます。
加えて、相談しやすい雰囲気をつくることも重要で、上司が意見を受け止める姿勢を示せば部下の不安を軽減できます。
コミュニケーションツールを活用して、現場内外で円滑に情報交換を行うことも有効です。
風通しの良い職場は離職率を下げる効果があり、働きやすい環境づくりに直結します。
教育・研修制度を充実させる
施工管理技士がすぐ辞めてしまうときの対処法は、教育・研修制度を充実させることです。
未経験者や若手が成長の見通しを持てなければ、不安から早期離職につながります。
そのため、入社時研修やOJT制度を整え、業務知識やスキルを段階的に習得できる環境を提供することが重要です。
さらに、資格取得支援や外部セミナーの受講制度を導入すれば、自己成長を実感しやすくなります。
経験を積むごとに、責任ある業務を任せる仕組みも有効です。
教育や研修の充実はキャリア形成を後押しし、施工管理技士が長期的に活躍できる基盤となります。
結果として、組織全体の人材定着率を高める効果が期待できます。
適切な評価制度を導入する
施工管理技士がすぐ辞めてしまうときの対処法は、適切な評価制度を導入することです。
努力や成果が正当に評価されない環境ではモチベーションが低下し、離職につながります。
そのため、業務内容に応じた明確な評価基準を設定し、昇給や昇格に反映させることが重要です。
例えば、現場の安全管理や工程管理の成果、チームワークへの貢献度を評価項目に含めれば公平性が高まります。
さらに、定期的なフィードバック面談を行い、改善点や成果を丁寧に伝えることで社員の成長意欲を引き出せます。
適切な評価制度は働きがいを高め、施工管理技士が長く活躍し続けるための要因となるでしょう。
施工管理の人手不足を解消したいならツクノビ施工管理がおすすめ
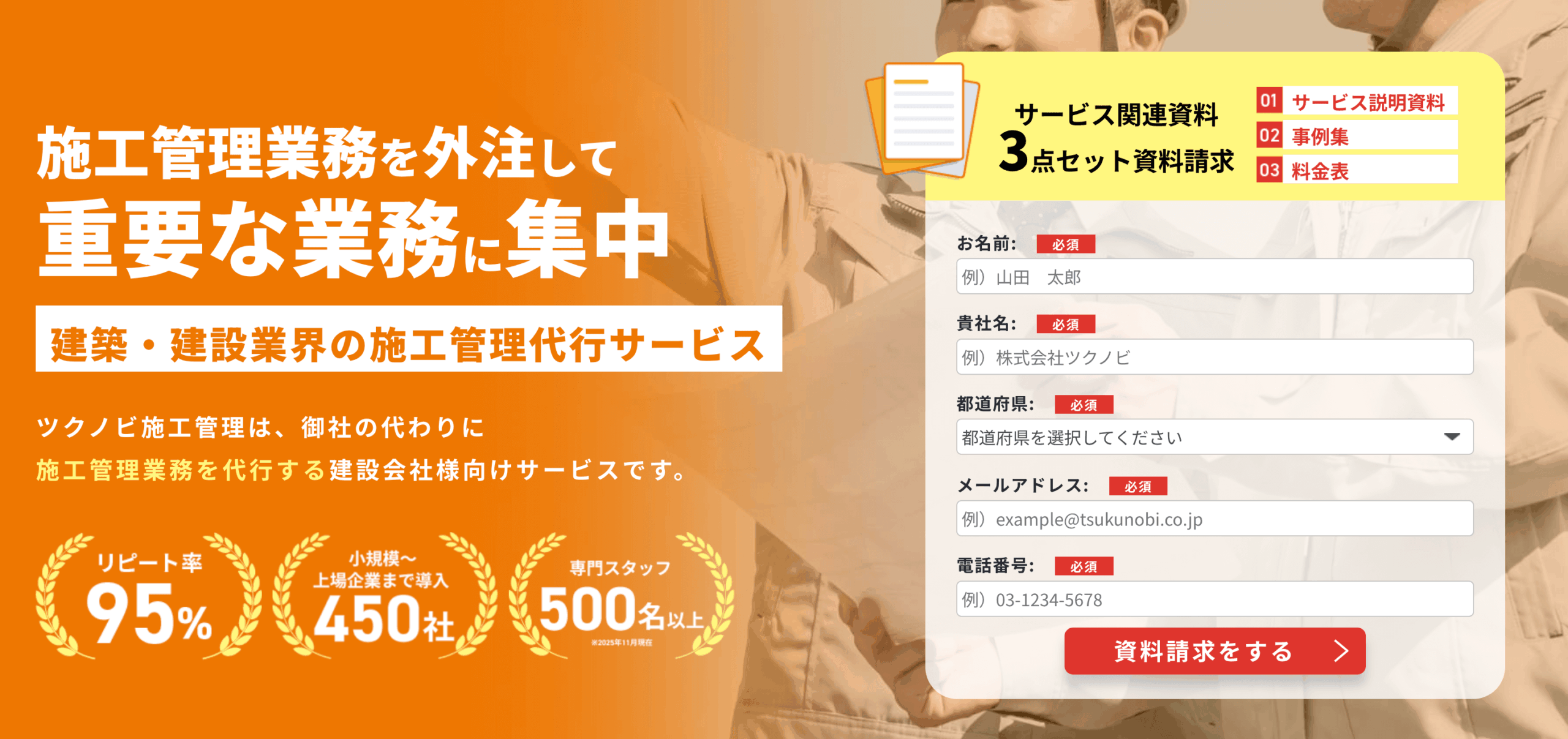
施工管理の人手不足で業務がスムーズに進まない場合や、施工管理人材を確保したい場合は、建設業特化の業務代行サービス「ツクノビ施工管理」の利用がおすすめです。
「ツクノビ施工管理」では、施工管理の経験が豊富なプロ人材が御社の業務を代行いたします。施工管理のリソースがひっ迫している場合や、業務に対応できる人材が不足している場合、施工管理人材の採用、教育のコストをかけられない場合などは、アウトソーシングサービスを活用すると、少ない工数で業務を実行できます。
施工管理業務の人手不足を解消したい方はぜひこちらからお問い合わせください。
施工管理技士がすぐに辞めるべきサイン
施工管理技士の仕事が厳しいと感じても、すぐに辞めるべきか悩む人は多いでしょう。しかし、無理を続けることで健康やキャリアに悪影響を及ぼす可能性があります。特に、以下のような状況に当てはまる場合は、早めに退職を検討するのが賢明です。
- 体調不良が続いている
- パワハラやモラハラが横行している
- 挑戦したい職種が見つかる
こうした条件に当てはまるか、身体的・精神的な負担が限界に達していないか、自分の状況を冷静に見直しましょう。
体調不良が続いている
慢性的な疲労や睡眠不足、頭痛や胃痛などの体調不良が続く場合は、退職を考えましょう。なぜなら、施工管理の仕事は長時間労働が常態化しており、身体への負担が大きくなっているためです。
特に、現場のストレスやプレッシャーが原因で体調を崩している場合は、体調の変化に注意しましょう。そのまま無理に続けると、うつ病や過労による深刻な健康被害につながる可能性があるからです。
健康は何よりも大切です。体調不良が続くなら、退職を含めた選択肢を考えましょう。
パワハラやモラハラが横行している
上司や同僚からの暴言や過度な叱責、無理な労働を強いるような環境は、心身の健康に悪影響を及ぼします。過度な指導や叱責は、場合によってはパワハラやモラハラに該当します。こうしたことが原因で心理的に負担を感じる人は、辞めることも考えましょう。
パワハラやモラハラに長期間耐え続けることで精神的に追い詰められ、最悪の場合は適応障害やうつ病に発展する可能性があります。パワハラ・モラハラが改善される見込みがない場合は、すぐに辞める判断をしても良いでしょう。
挑戦したい職種が見つかる
仕事をする中で「別の仕事に挑戦したい」と思うこともあります。例えば、建設業界の中でもデスクワークが中心の職種に移行したい、あるいはまったく異なる業界に興味を持つこともあります。そうした場合は、思い切って辞めることも選択肢の1つです。
仕事を続けながら転職活動を進めることも可能ですが、時間的な制約が大きいため、簡単ではありません。そのため、思い切って退職することで、新たなキャリアに集中しやすくなるメリットもあります。
施工管理技士がすぐ辞めるメリット
ここでは、施工管理技士が早めに退職することで得られるメリットについて解説します。
施工管理技士のように精神的・身体的な負担が大きい環境に身を置くことは、プラスにはなりません。これから紹介する辞めるメリットを把握し、自分の状況と照らし合わせて辞めることも検討してみてください。
ストレスが減少する
施工管理技士を辞める大きなメリットとして、ストレスの減少が挙げられます。施工管理の仕事は、多くの責任を伴い長時間労働や厳しい人間関係が避けられないことが多い職業です。そのため、ストレスが慢性化し、心身の健康に悪影響を及ぼす人もいます。
そこで、すぐに辞めることで精神的な負担が軽減され、心の余裕を取り戻すことにつながるでしょう。ストレスから解放されることで、次のキャリアについて前向きに考えられるでしょう。
ワークライフバランスがとりやすくなる
施工管理技士を辞めることで、仕事とプライベートのバランスをとりやすくなる点もメリットです。施工管理の仕事では休日出勤や残業で、プライベートの時間を確保することが難しいケースが少なくありません。
しかし、転職することで、プライベートを充実させられる可能性があります。
例えば、年間休日がしっかりと確保されていたり有給休暇を取得しやすかったりする企業であれば、ワークライフバランスがとりやすくなります。仕事とプライベートのバランスを重視した働き方を目指すのであれば、早めの転職も1つの選択肢です。
自分に合う仕事を見つけられる
施工管理技士として働いていても、「施工管理は向いていないかもしれない」と感じる人も多いでしょう。そうしたネガティブなモチベーションで働き続けることは、将来的なキャリアにとってもマイナスです。
施工管理の仕事は、技術的な知識やコミュニケーション能力が求められるため、人によって向き不向きがあります。早めに辞めて自分に合う仕事を探せば、新しい環境で活躍するチャンスが広がります。適性に合った職場を見つけることで、より充実したキャリアを築けるでしょう。
施工管理技士がすぐに辞めるデメリット
施工管理技士の仕事をすぐに辞めたいと考えることは珍しくありません。しかし、短期間で退職することにはデメリットも存在します。
施工管理技士がすぐに辞めるデメリットが存在する理由は、転職市場では「長く続けられる人材」が評価されやすく、早期離職がマイナスに働く可能性があるためです。
これから解説するデメリットを頭に入れて、辞める前に自分にとって本当に最適な選択なのかを慎重に考えましょう。
継続力がないと評価される可能性がある
短期間で退職すると、「この人は忍耐力がなく、すぐに辞めてしまうのではないか」と採用担当者に思われる可能性があります。施工管理の仕事は、長期間のプロジェクトを担当することが多く、安定して働ける人材が求められます。
特に、前職を1年未満で退職していると「またすぐ辞めるかもしれない」と警戒されることも少なくありません。そうなると転職が難しくなることもあります。短期離職を避けることがベストですが、やむを得ない場合は、面接でしっかりと理由を説明することが大切です。
スキルや経験が浅いと評価される
施工管理の仕事は、経験を積むことでスキルが向上し、市場価値が高まる職種です。
しかし、短期間で辞めてしまうと、十分な経験やスキルを身につける前に転職することになります。その結果、新しい職場で即戦力として認められず、希望する給与や待遇を得られない可能性も少なくありません。
また、施工管理技士としての就業期間が短いと経験が少ないと判断され、キャリアアップの機会が限られることもあります。転職時には、今までの業務で培ったスキルをアピールすることが重要です。
施工管理技士がすぐに辞めても転職を成功させる方法
「すぐに辞めたら転職が不利になるのでは?」と不安に思うかもしれません。しかし、適切な準備を行い戦略を持って転職活動を進めれば、短期離職のデメリットを最小限に抑え理想の職場を見つけられます。
ここでは、施工管理技士が早期離職後に転職を成功させる方法を紹介します。
前向きな退職理由を伝える
転職活動では、前職をすぐに辞めた理由を必ず聞かれます。その際、人間関係や業務の過酷さなどネガティブと受け取られる理由をそのまま伝えると、採用担当者にマイナスの印象を与えます。
代わりに、スキルの向上やワークライフバランスの改善など前向きな理由を伝えることで、採用を前向きに検討してくれることもあります。企業側が納得できる理由を準備し、面接で自信を持って話せるようにしておきましょう。
今後のキャリアを明確にする
転職活動では、「今後どのようなキャリアを築きたいか」を明確にすることが大切です。施工管理の仕事を続ける場合は、「どのような現場で働きたいのか」「どの資格を取得する予定なのか」などを具体的に説明できるようにしておきましょう。
別の職種に転職する場合は、その仕事を選んだ理由やこれまで培ってきたスキルをどのように活かせるかを論理的に説明できるように準備しておきましょう。そうすることで、採用される可能性が高まります。
転職サポートサービスを活用する
施工管理技士として転職を成功させるためには、転職エージェントや求人サイトを活用するのも有効な手段です。施工管理に特化した転職サイトを利用することで、業界の動向や企業の内部事情を知り、自分に合った職場を見つけやすくなります。
転職エージェントを利用すれば、履歴書や職務経歴書の添削、面接対策などのサポートを受けられます。そうすれば、転職成功率が向上するでしょう。短期離職後の転職では、できるだけ多くの情報を集め、慎重に企業を選ぶことが重要です。
【まとめ】施工管理技士がすぐに辞める際はキャリアを明確にすることが大切!
施工管理技士がすぐに辞めることには、メリットとデメリットの両面があります。そのため、辞めるかどうかを決める際には、自分のキャリアや健康を考慮し慎重に判断することが重要です。
早期離職後の転職を成功させるためには、前向きな退職理由を用意し、今後のキャリアプランを明確にしましょう。
施工管理技士としてのキャリアに悩んでいる方は、一人で抱え込まず、転職の専門家に相談するのも一つの方法です。自分にとって最適な選択を見つけ、より良い働き方を実現してください。
施工管理の人手不足は当たり前といわれる理由や施工管理士を新卒1年目で辞める理由・ブラックといわれる理由についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
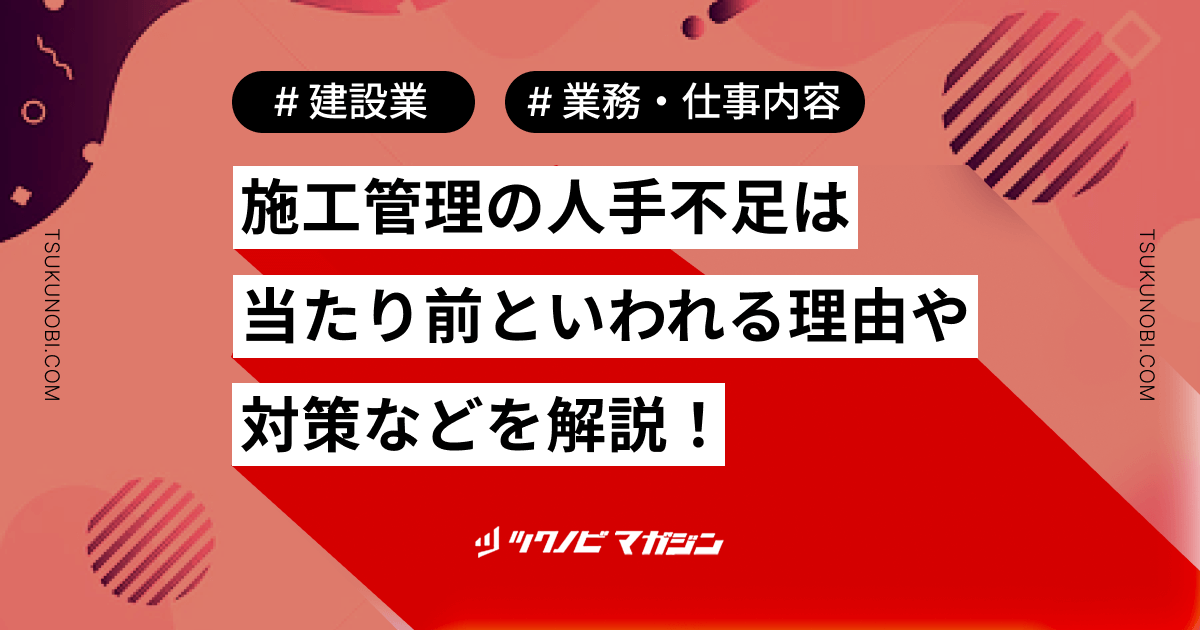 施工管理の人手不足は当たり前といわれる6つの理由や対策を解説!
施工管理の人手不足は当たり前といわれる6つの理由や対策を解説!
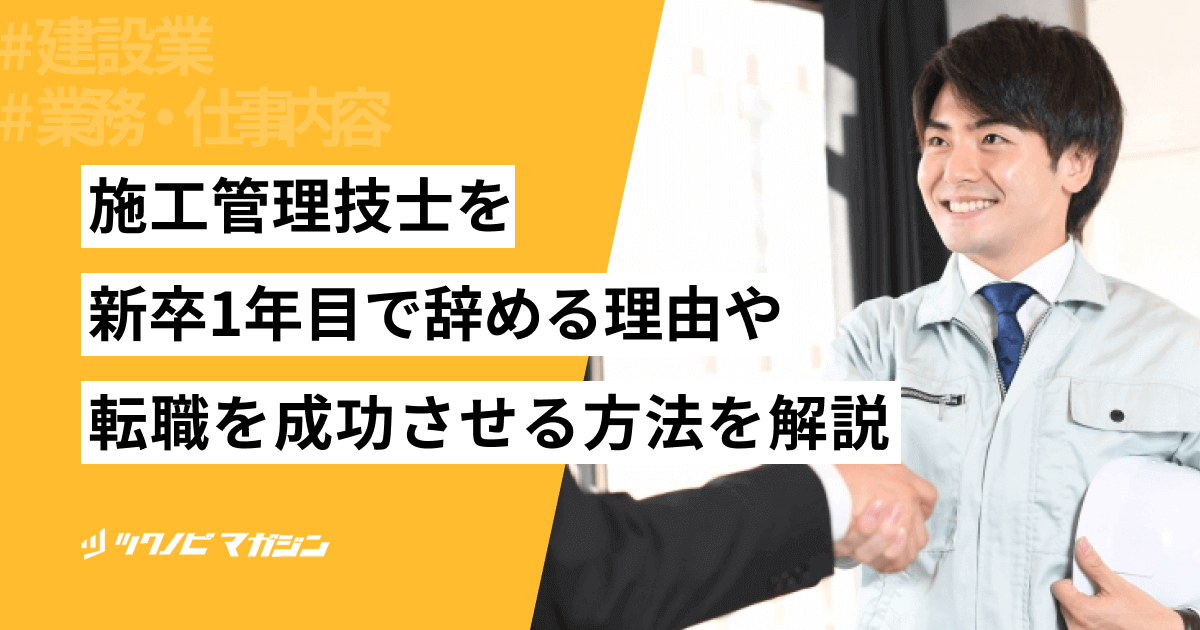 施工管理技士を新卒1年目で辞める理由や転職を成功させる方法を解説
施工管理技士を新卒1年目で辞める理由や転職を成功させる方法を解説
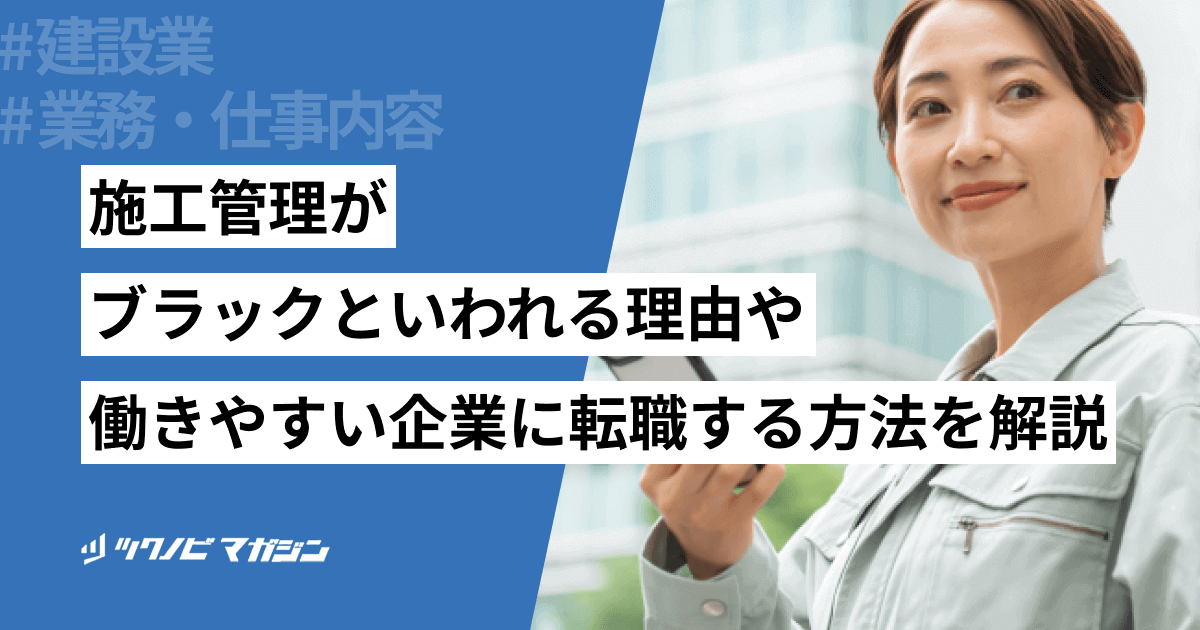 施工管理がブラックといわれる理由や働きやすい企業に転職する方法を解説
施工管理がブラックといわれる理由や働きやすい企業に転職する方法を解説



