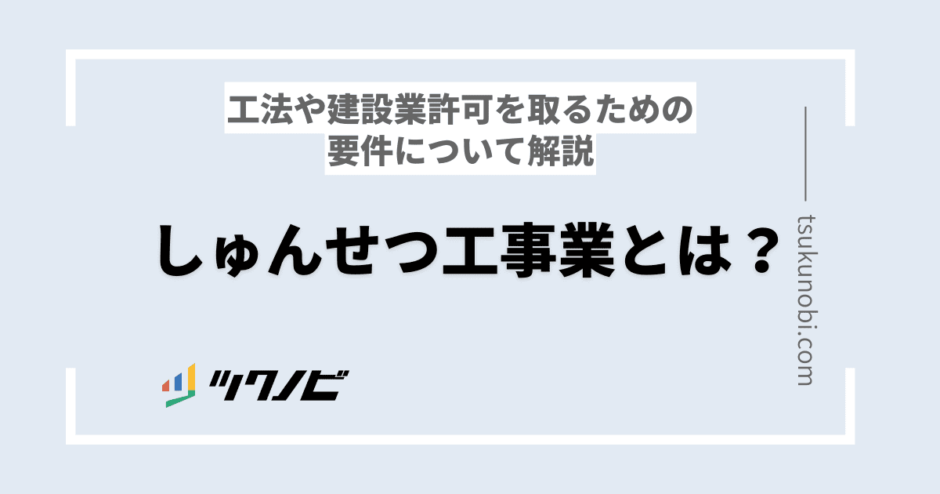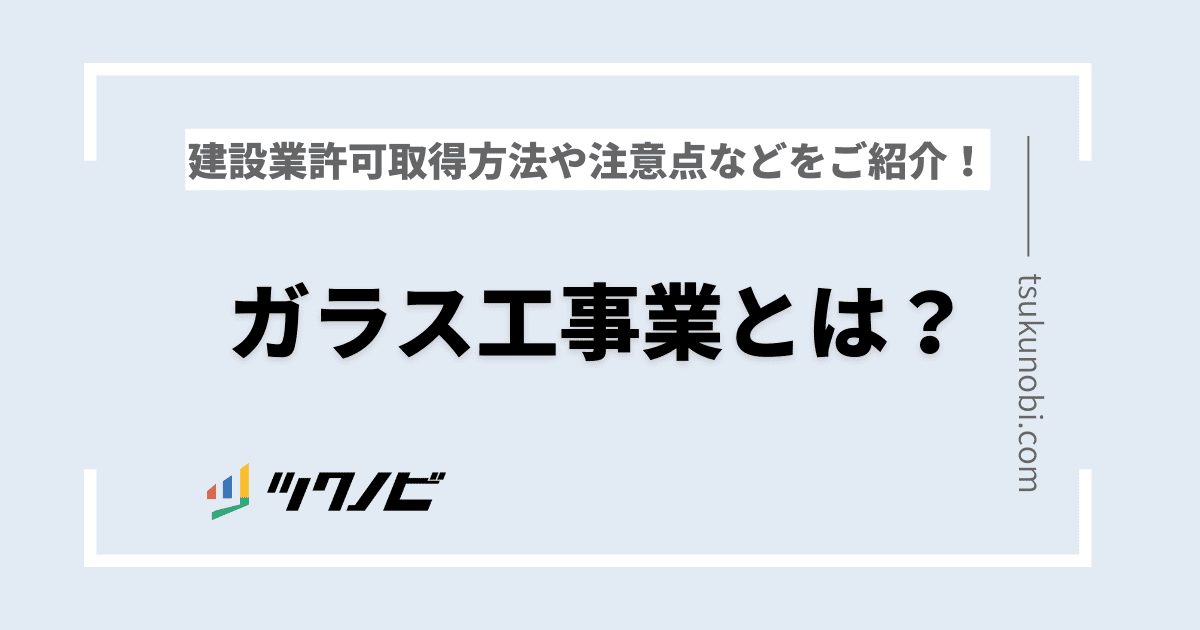※記事内に広告を含みます
しゅんせつ工事業の許可を取得する場合、どのような要件やメリットがあるのでしょうか?
「どのようにして許可をとればいいの?」「必要な費用ってどのくらい?」とお悩みの方も多いでしょう。
本記事ではしゅんせつ工事業許可に必要な要件と、申請手続きの窓口や費用、そして建設業許可を取得するメリットなどを解説します。しゅんせつ工事業の許可を検討している方はぜひ参考にしてください。
しゅんせつ工事業とは?
しゅんせつ工事とは、海や港湾・河川などの底面の土砂をすくいとる土木工事のことです。昨今は船が大型化しており、より十分な水深が必要とされています。したがってしゅんせつ工事は、船が安全に運航するために重要な役割を担っているのです。
また、しゅんせつ工事業を行う際は、公共工事・民間工事問わず建設業許可(しゅんせつ工事許可)が必要です。しゅんせつ工事の「ポンプ浚渫」と「グラブ浚渫」の2つの工法を下記で解説します。
工法1:ポンプ浚渫
ポンプ浚渫とは土砂だけでなく海水も一緒にすくいとる工法です。底面に土砂を吸い込む装置を置き、ストローで吸い上げるようにして行います。広い範囲の土砂を大量にすくいとることができるので、海でのしゅんせつ工事に適しています。大型のポンプ浚渫船を使用するため、コスト負担が大きいのが特徴です。
工法2:グラブ浚渫
グラブ浚渫とは、底面の土砂をグラブバケットでつかみ取る工法です。グラブ浚渫はポンプ浚渫のような大型の装置を必要としないため、港・壁岸のような狭い場所でも作業可能です。ロープの長さを調節すれば、深い底面での作業も可能になります。また、作業場所が深くなってもつかみ取る力は弱くなりません。
しゅんせつ工事業の建設業許可が必要なケース
しゅんせつ工事業において建設業許可が必要なのは、500万円以上のしゅんせつ工事を請負う際です。元請け業者として合計4,000万円以上の発注をする場合は特定建設業許可が必要になるので間違えないようにしましょう。
ここでの注意点は、一式工事業の建設業許可があってもしゅんせつ工事は金額の制限があるということです。
しゅんせつ工事業の建設業許可に必要な5つの条件
しゅんせつ工事業の建設業許可に必要な条件は下記の5つです。
- 経営業務の管理責任者
- 専任技術者の配置
- 財産的基礎
- 誠実性
- 欠格要因に該当しない
専任技術者の配置と財産的基礎においては、一般建設業・特定建設業どちらも詳しく解説していきます。ぜひ参考にしてください。
1.経営業務の管理責任者
しゅんせつ工事業の建設業許可を取得するためには、建設業を営む会社の役員、もしくは個人事業主として経験業務の管理責任者の経験が5年以上あることが必須です。つまり、建設業で作業員として働いた経験はカウントされません。
法人であれば役員・個人であれば個人事業主か支配人として登記されている方が対象です。
また、経営補佐の経験が6年以上ある方がいる場合も対象となるケースもありますが、可能性は非常に低いと認識しましょう。
2.専任技術者がいること
専任技術者とは、一つの事業所の専属として従事する人のことを指します。常勤である必要があり、他の事業所と兼用で業務することはできません。各事業所への配置が義務付けられている、重要なポジションです。
専任技術者の要件は一般建設業と特定建設業で異なるので以下詳しく解説していきます。
一般建設業で取得する場合
一般建設業で取得する場合の要件は下記のとおりです。
- しゅんせつ工事業の実務経験が10年以上ある
- 指定学科卒業としゅんせつ工事の実務経験(大学は3年以上、それ以外は5年以上)
- 該当の国家資格を有すること
10年以上の実務経験を証明するために必要な書類は建設業許可を保有しているかしていないかで異なります。書類を下記で確認しましょう。
| 建設業許可を保有している会社 |
|
| 建設業許可を保有していない会社 |
|
指定学科とは土木工学・機械工学のことを指し、中等教育学校・高等学校・専修学校を卒業した場合は5年以上の実務経験、高等専門学校・大学を卒業した場合は3年以上の実務経験が必要です。上記と同様、証明するためには建設業許可を保有しているかしていないかで異なります。
| 建設業許可を保有している会社 |
|
| 建設業許可を保有していない会社 |
|
該当する国家資格は下記のとおりです。
- 一級土木施工管理技士
- 二級土木施工管理技士(土木)
- 技術士法の建設・総合技術監理(建設)
- 技術士法の建設・鋼構造及びコンクリート・総合技術監理(建設 鋼構及びコンクリート)
- 技術士法の水産「水産土木」総合技術監理(水産「水産土木」)
特定建設業で取得する場合
特定建設業で取得する場合の要件は下記のとおりです。
- 上記の一般建設業の要件1、2のいずれかに該当し、4,500万円以上の工事での2年以上の指導監督的な実務経験
- 該当の国家資格を有する
特定建設業で取得する場合は下記の国家資格が必要です。
- 一級土木施工管理技士
- 技術士法の建設・総合技術監理(建設)
- 技術士法の建設・鋼構造及びコンクリート・総合技術監理(建設 鋼構及びコンクリート)
- 技術士法の水産「水産土木」総合技術監理(水産「水産土木」)
- 一級建築施工管理技士
3.財産的基礎
建設工事を遂行するにあたっては、ある程度の資金力が求められます。資材や機械器具等の購入・人材確保・営業活動などや、工事を請け負うことができる資金を保持していることが、建設業許可の要件です。特定建設業の許可を受ける場合は、一般建設業よりもさらなる資金力があることが求められます。以下それぞれの場合の財産的基礎の条件を解説します。
一般建設業の場合
一般建設業の場合は下記のいずれかに該当する必要があります。
- 自己資本が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること
自己資本の概要は建設業者が法人か個人かで異なります。法人の場合は賃借対照表「純資産の部」の純資産合計額のことです。個人の場合は期首資本金・事業主借勘定・事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に、負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額を指します。
資金調達能力の証明は、取引金融機関が発行する預金残高証明書で行います。
建設業許可を取得したいけど、500万円の資本金がたりなくて困っている、、という方はこちらもぜひ参考にしてみてください。
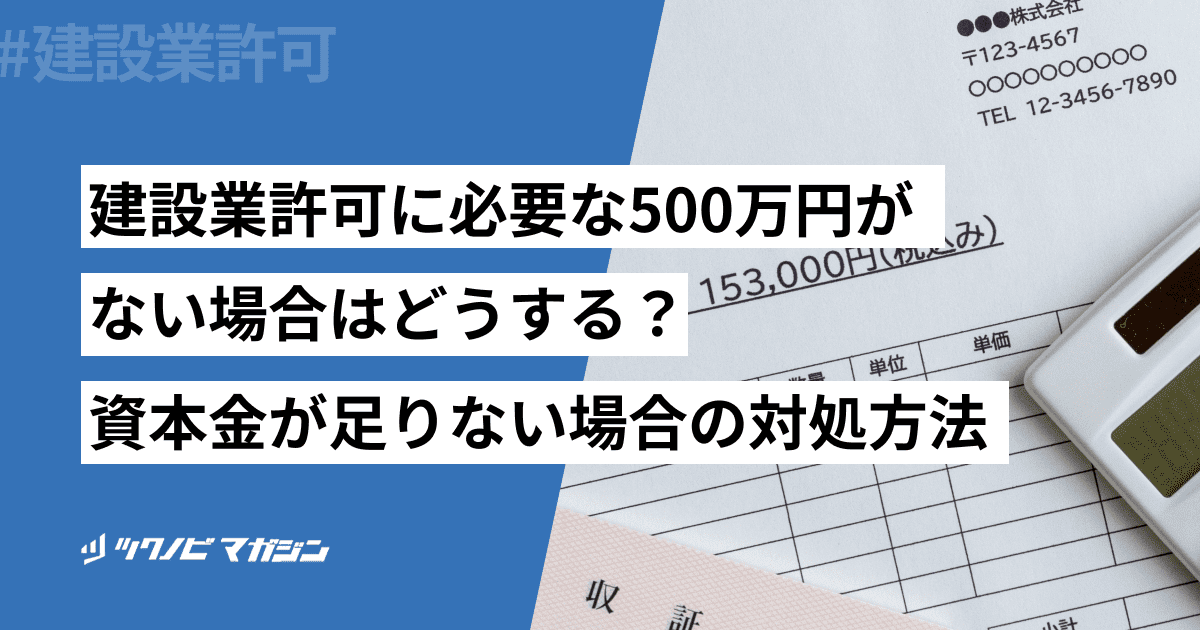 建設業許可に必要な500万円がない場合はどうする?資本金が足りない場合の対処方法をご紹介!
建設業許可に必要な500万円がない場合はどうする?資本金が足りない場合の対処方法をご紹介!
特定建設業の場合
特定建設業の場合は下記のすべてに該当する必要があります。
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること
4.誠実性
建設業許可を得るためには誠実性も重要です。請負契約の締結や履行の際に不正・不誠実な行為をしている場合や、する可能性が高いと判断された場合は許可の取得はできません。個人事業主や事業所の役員・所長などの上役の方達は誠実性が求められることを覚えておきましょう。
5.欠格要件に該当しない
建設業の許可を得るためには欠格要件に該当しないことも条件の1つです。個人事業主、法人は役員と令3条使用人(支店長・営業所長など)は、下記の事項に1つでも該当した場合、許可を得ることはできません。
- 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
- 不正の手段で許可をい受けた、または営業停止処分に違反したことで許可を取り消され、取り消しになった日から5年を経過しない者
- 2の取り消し処分にかかる通知があった日から当該処分があった日までの間に廃業の届出をした者で当該届出の日から5年を通過しない者
- 2の取り消し処分にかかる通知があった日以前60日以内に、3の廃業の届出をした法人の役員等もしくは令3条使用人、または届出をした個人の令3条使用人で、当該届出の日から5年を経過しない者
- 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が通過しない者
- 営業の禁止を命ぜられ、その禁止の期間が通過しない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(※禁固以上とは死刑・懲役・禁固が該当します)
- 一定の法律に違反したことfr罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を通過しない者
- 申請者が未成年者で、その法定代理人が上記に該当する者
- 法人でその役員等、または令3条使用人が上記に該当する者
- 個人でその支配人または令3条使用人が上記に該当する者
- 暴力団員等にその事業活動を支配されている者
6.社会保険への加入
社会保険への加入が、2020年10月に建設業許可の要件に新たに追加されました。新規・更新を問わず、今後建設業許可の申請をする際は社会保険へ加入していなければ受理されなくなります。少なからずまだ社会保険に加入していない事業所もあるでしょう。加入していなくても許可の取り消しにはなりませんが、更新はできなくなるので注意が必要です。今後のことを考え、なるべく早いうちに社会保険への加入をおすすめします。
しゅんせつ工事業の建設業許可に必要な申請手続き
しゅんせつ工事業の建設業許可の申請手続きは各都道府県で窓口が異なります。申請の際に必要なものは申請書類と申請手数料です。
各都道府県ごとの窓口は下記のとおりです。
| 都道府県 | 窓口 | 都道府県 | 窓口 |
| 北海道 | 建設部建設政策局建設管理課 | 滋賀県 | 土木交通部監理課 |
| 青森県 | 県土整備部監理課 | 京都府 | 建設交通部指導検査課 |
| 岩手県 | 県土整備部建設技術振興課 | 大阪府 | 住宅まちづくり部建築振興課 |
| 宮城県 | 土木部事業管理課 | 兵庫県 | 県土整備部県土企画局総務課建設業室 |
| 秋田県 | 建設部建設政策課 | 奈良県 | 県土マネジメント部建設業・契約管理課 |
| 山形県 | 県土整備部建設企画課 | 和歌山県 | 県土整備部県土整備政策局技術調査課 |
| 福島県 | 土木部技術管理課建設産業室 | 鳥取県 | 県土整備部県土総務課 |
| 茨城県 | 土木部監理課 | 島根県 | 土木部土木総務課建設産業対策室 |
| 栃木県 | 県土整備部監理課 | 岡山県 | 土木部監理課建設業班 |
| 群馬県 | 県土整備部建設企画課 | 広島県 | 土木建築局建設産業課建設業グループ |
| 埼玉県 | 県土整備部建設管理課 | 山口県 | 土木建築部監理課建設業班 |
| 千葉県 | 県土整備部建設・不動産業課建設業班 | 徳島県 | 県土整備部建設管理課 |
| 東京都 | 都市整備局市街地建築部建設業課 | 香川県 | 土木部土木監理課契約・建設業グループ |
| 神奈川県 | 県土整備局事業管理部建設業課 | 愛媛県 | 土木部土木管理局土木管理課 |
| 新潟県 | 土木部監理課建設業室 | 高知県 | 土木部土木政策課 |
| 山梨県 | 県土整備部県土整備総務課建設業対策室 | 福岡県 | 建築都市部建築指導課 |
| 長野県 | 建設部建設政策課建設業係 | 佐賀県 | 県土整備部建設・技術課 |
| 富山県 | 土木建設技術企画課 | 長崎県 | 土木部監理課 |
| 石川県 | 土木部監理課建設業振興グループ | 熊本県 | 土木部監理課 |
| 岐阜県 | 県土整備部技術検査課 | 大分県 | 土木建築部土木建築企画課 |
| 静岡県 | 交通基盤部建設業課 | 宮崎県 | 県土整備部管理課 |
| 愛知県 | 都市整備局都市基盤部都市総務課 | 鹿児島県 | 土木部監理課 |
| 三重県 | 県土整備部建設業課 | 沖縄県 | 土木建築部技術・建設業課 |
| 福井県 | 土木部土木管理課 | ー | ー |
しゅんせつ工事業の建設業許可にかかる費用相場
上記でも触れましたが、しゅんせつ工事業の建設業許可の申請の際は手数料がかかります。新規でしゅんせつ工事業の許可を受けたい場合の手数料は9万円、大臣許可の場合は15万円。しゅんせつ工事業の許可を追加・更新する場合は5万円、大臣許可の場合も5万円必要です。申請時の手数料は下記を参考にしてください。
| 申請の種類 | 知事許可 | 大臣許可 |
| 新規 | 9万円 | 15万円 |
| 許可換え新規 | 9万円 | 15万円 |
| 般・特新規 | 9万円 | 15万円 |
| 業種追加 | 5万円 | 5万円 |
| 更新 | 5万円 | 5万円 |
しゅんせつ工事業建設業許可取得のメリット
しゅんせつ工事業の建設業許可を取得するメリットは主に3つあります。
- 500万円以上の大規模な工事を請け負うことができる
- 公共工事の入札に参加ができる
- 発注業者や銀行などからの信頼性が上がる
しゅんせつ工事の建設業許可を取得すると、信頼性が上がり仕事の幅も増えます。労力と費用がかかりますが、その分以上の見返りはあるといえるでしょう。
【まとめ】しゅんせつ工事業の建設業許可には条件があるがメリットも大きい
しゅんせつ工事業の建設業許可取得には、クリアしなければならない条件が大きく6つあります。しかし、取得すれば大きなメリットもあります。
また、必要書類や窓口などは、申請する区分や都道府県で異なります。ぜひ本記事を参考にして、しゅんせつ工事業許可の申請手続きに役立てください。
※弊社の営業代行サービスツクノビセールスは、
【効果が出なければ全額返金プラン】を新たにスタートさせました!

※詳しくは👆👆👆のバナーをクリック!!