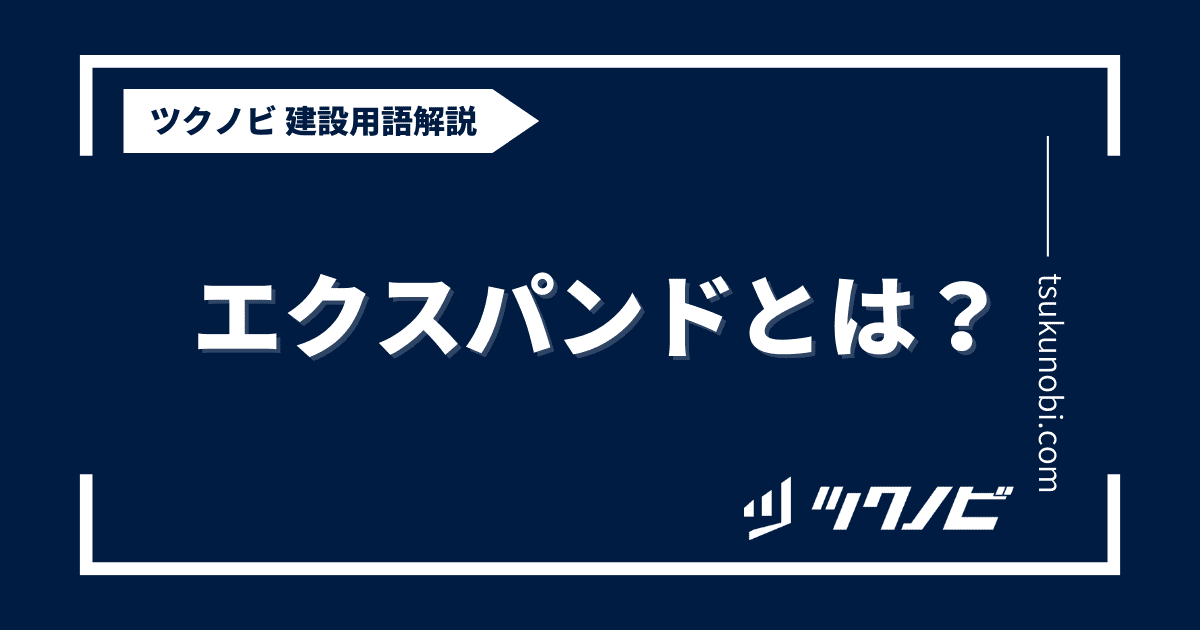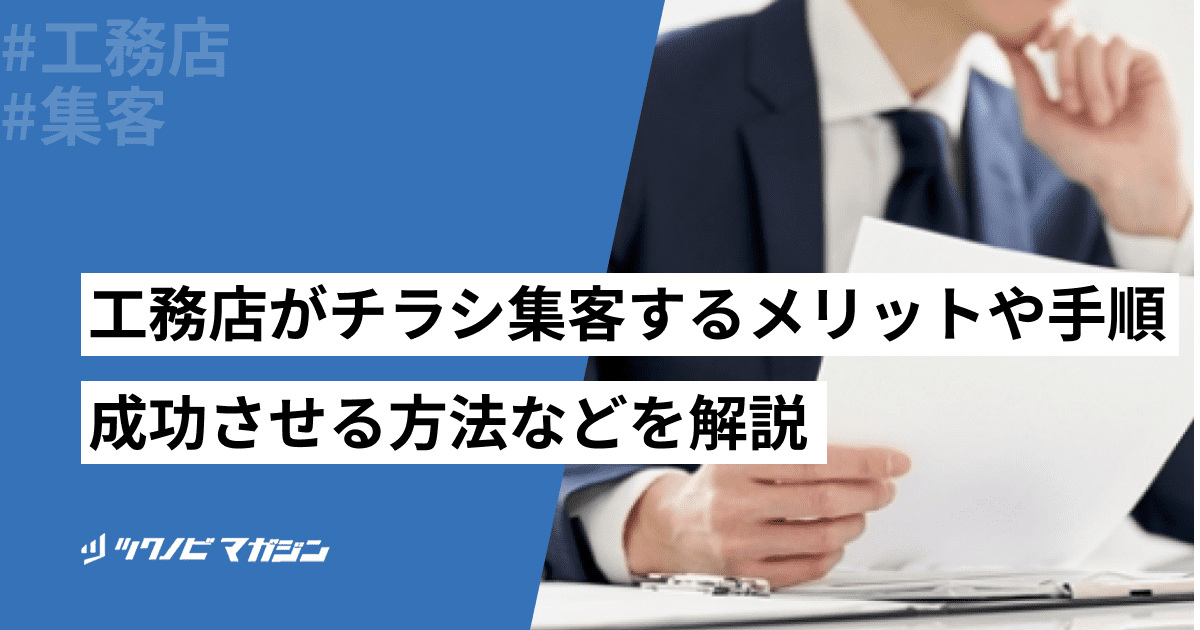※記事内に広告を含みます
業務中のけがや病気の際の保険給付を行う労災保険は、ほかの業界と同様に建設業でも加入が義務付けられています。しかし、建設業の労災保険は仕組みが複雑です。今回は建設業の労災保険の特徴や計算方法など、基本的な情報について徹底解説します。労災保険に苦手意識をお持ちの方は、ぜひご覧ください。
ツクノビ事務は、建設業の事務業務を低コストで代行する建設業特化のアウトソーシングサービスです。
建設業の複雑な事務作業や書類作成、写真データ整理などまで、幅広い業務に対応しています。詳細はぜひこちらからご確認ください。
建設業の労災保険の特徴
一般的な企業の労災保険と、建設業における労災保険はどのような点で異なるのでしょうか。建設業における労災保険の特徴を、以下の3つに分けて解説します。
- 現場労災は元請け企業が加入する
- 現場労災以外の保険は各企業が加入する
- 一人親方や個人事業主は特別加入制度に加入する
現場労災は元請け企業が加入する
建設業の現場労災は元請け企業が加入するという特徴があります。建設業は1次請け、2次請け…と何次もの下請け企業で行われており、元請け企業は下請け企業に対して使用者責任があります。
そのため、元請けを1つの工事の事業主と定義し、下請け企業の労災保険の加入から保険金給付までの一連の手続きの義務を負っているのです。
現場労災以外の保険は各企業が加入する
作業現場で従事しない事務職や営業職の労災保険は各企業で加入しなければなりません。一般的にこれらは事務所労災と呼ばれており、元請け・下請けにかかわらず各企業で加入手続きを行います。現場監督の労災保険は、こちらに該当しません。
一人親方や個人事業主は特別加入制度に加入する
労災保険は企業が労働者に対して補償する保険なので、雇用主を持たない一人親方や個人事業主は対象ではありません。しかし、危険を伴う建設業では、一人親方のための労災保険特別加入制度が用意されています。常時労働者を使用しないで事業を行っている場合、あるいは労働者を雇用しているが、雇用期間が年間100日間に満たない場合はこの特別加入制度を利用できます。
一人親方におすすめの労災保険は「一人親方労災保険組合」
一人親方の場合、万が一に備えて労災保険に入る必要があります。一人親方向け労災保険で一番おすすめなのは、業界No.1の加入者で実績豊富な一人親方労災保険組合の労災保険です。主な特徴は、以下の通りです。
- 全国の加入組合数は90,000人と業界トップクラス
- 月額組合費が500円と業界最安値
- 組合員様限定の優待サービスが多数
| 入会費 | 1,000円(初回のみ) |
|---|---|
| 組合費 | 500円/月 |
一人親方労災保険組合ではレストランやカラオケ、映画館など全国で20万ヵ所以上の施設のクーポンや割引などが適用される組合員様限定の優待サービスや友達紹介割引もあります
建設業の労災の種類
建設業の労災の種類について、以下の2つに分けて説明します。
- 建設業は有期事業
- 建設業は二元適用事業
建設業は有期事業
有期事業とは終わりが予定されている事業のことを指します。建設工事はプロジェクトの終了時期が定められているので、有期事業に該当します。有期事業は「一括有期事業」と「単独有期事業」の2つに分類されています。
一括有期事業
建設業で、2つ以上の下請けを一括して1つの事業とみなしている元請けのみを事業主として取り扱っています。以下の点を満たす事業を「一括有機事業」と言います。
- それぞれの企業の行う事業が同一(建設業)
- 元請け(事業主)が同一
- 工事の請負金額が1億9,000万円未満
- 概算の保険料が160万円未満
単独有期事業
上記に該当しない有期事業は、「単独有期事業」と言います。工事規模でいうと、請負金額が1億8千万円以上、あるいは概算の保険料が160万円以上の工事です。この場合、工事ごとに保険が成立します。
建設業は二元適用事業
労災保険用保険の加入手続きを一括して行うものを「一元適用事業」、個別に行うものを「二元適用事業」と言います。建設業は、以下の理由から二元適用事業に該当するといわれています。
- 事業ごとに労災保険に加入する(現場の労災保険は除く)
- 現場の労災保険に加入するため、下請けの現場労働者は各企業の労災保険に加入していない
建設業の労災保険料の計算方法
建設業における労災保険料は「請負金額×労務費率×労災保険率」の計算式で計算します。これらの比率は厚生労働省によって定められており、事業の種類によって異なるため確認しなければなりません。
また、年度ごとに発表されるため、前年度とは異なる可能性も考えられます。厚生労働省のホームページの「労災保険料率表」に記載があるので、計算するたびに必ず確認しましょう。
※参考:労災保険率表(令和6年4月1日施行)
建設業の労災保険の手続き
労災保険の加入手続きは複雑ではないかと考える方も多いのではないでしょうか。建設業において労災保険に加入する際に発生する手続きを、以下の4つのケースに分けて説明します。
- 工事開始時の手続き
- 工事が分割・追加発注された際の手続き
- 工事が延期・短縮した際の手続き
- 工事が終了した際の手続き
工事開始時の手続き
工事を開始する際は、以下の2つの手順で手続きを行いましょう。
- 保険関係成立届を提出する
- 労災保険関係成立票を見えるところに掲示する
1.保険関係成立届を提出する
労働基準監督署に雇用者と加入者の保険関係の成立を知らせる書類が、「保険関係成立届」です。事業が成立した日の翌日から10日以内に、所轄の労働基準監督署に提出しましょう。
提出したらその事業所の「労働保険番号」が控えと共に返却されるので、工事終了まで保管しておきましょう。
2.労災保険関係成立票を見えるところに掲示する
労災保険関係成立表には、保険関係の成立日や労働保険番号が、事業の期間や事業者氏名、発注者の情報とともに記載されています。
建設業許可証などと共に工事期間中見えるところに掲示することが義務付けられています。
工事が分割・追加発注された際の手続き
大規模なプロジェクトでは、工事が1次、2次と分割発注されることも珍しくありません。この場合はまず1次工事の分だけ保険の手続きを行い、2次発注が確定になったタイミングで労働基準監督署に「労働保険・名称、所在地等変更届」を提出します。
また、工事の追加発注を受けた場合も同様に手続きを行います。
その際に労災保険料の額が2倍を超えて増加し、かつ追加で申し込んだ概算保険料の額と最初に申告した概算保険料との差額が13万円以上の場合、「増加概算保険料申告書と請負金額内訳書(乙)」を30日以内に提出しなければなりません。
工事が延期・短縮した際の手続き
悪天候や資材の遅れなどのトラブルにより工期が延長、あるいは何らかの理由で短縮した際は、労働基準監督署に「労働保険・名称、所在地等変更届」を提出しましょう。
工事が終了した際の手続き
工事が終了したら、まず労災保険の確定保険料を計算します。その後、最初に計算・納付した概算保険料との差額を精算し、必要であれば差額を納付するか、還付請求しましょう。
建設業の雇用保険加入は義務?適用除外や保険料率についても解説の記事はこちら
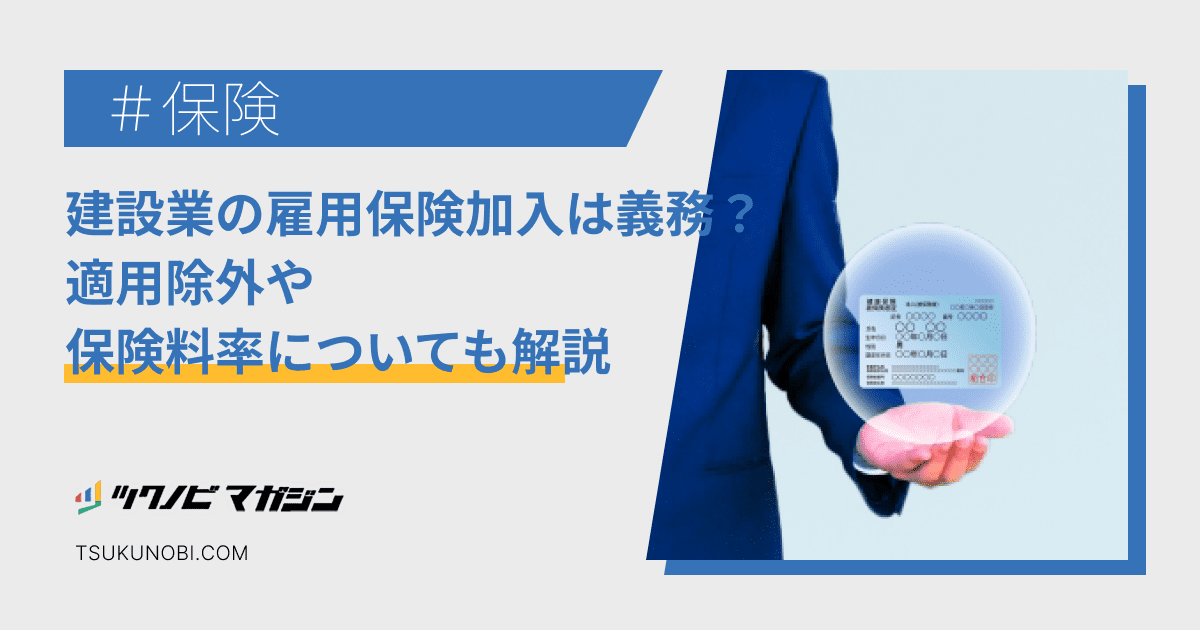 建設業の雇用保険加入は義務?適用除外や保険料率についても解説
建設業の雇用保険加入は義務?適用除外や保険料率についても解説
建設現場の安全対策12選!想定される事故と原因なども解説の記事はこちら
 建設現場の安全対策13選!想定される事故と原因なども解説
建設現場の安全対策13選!想定される事故と原因なども解説
【まとめ】建設業の労災保険は一般とは異なる!特徴についてよく理解しよう
建設業における労災保険は、元請けが下請けの分もまとめて加入手続きを行う、一人親方や個人事業主は特別加入制度を利用するなどの一般企業にはない特徴があります。
また、労災保険料率や労務費率も事業ごとに異なるので、チェックしなければなりません。工期が変更になった手続きも理解しておくと良いでしょう。労災保険の概要を正しく理解し、適切な加入手続きや請求を行い安全な労働環境を整えましょう。
労災保険加入証明書が必要となる場面や受け取る方法についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
※弊社の営業代行サービスであるツクノビセールスでは、
【効果が出なければ全額返金プラン】を新たにスタートさせました!

※詳しくは👆👆👆のバナーをクリック!!