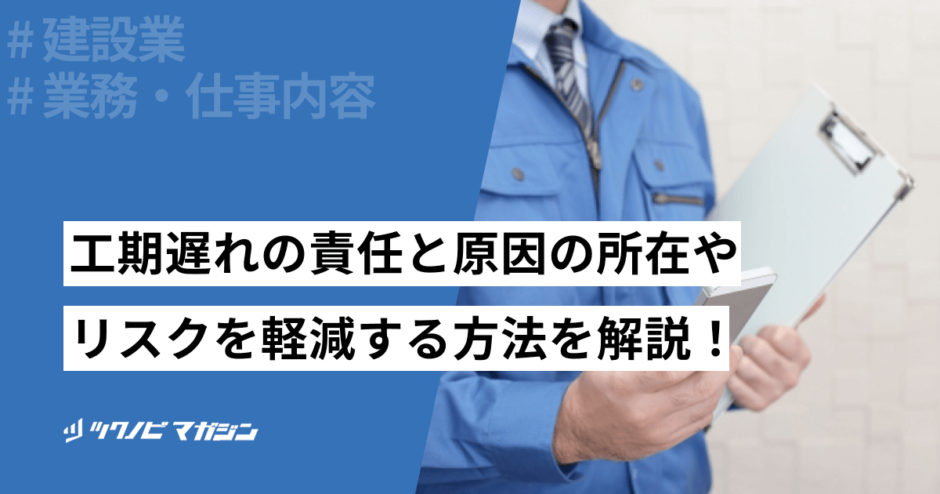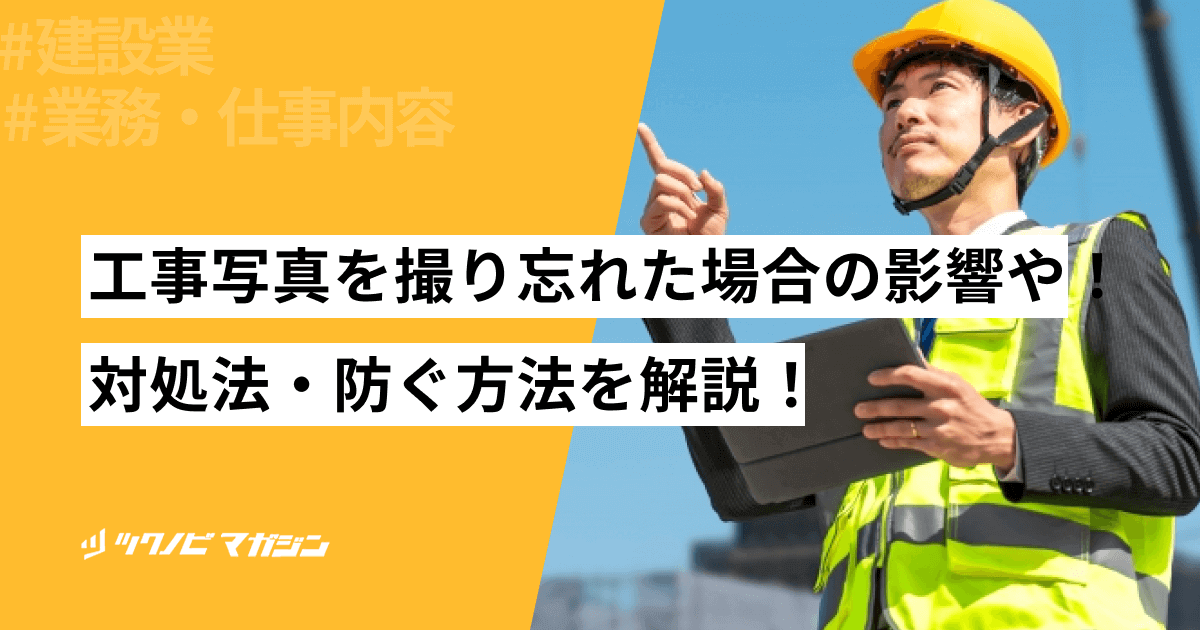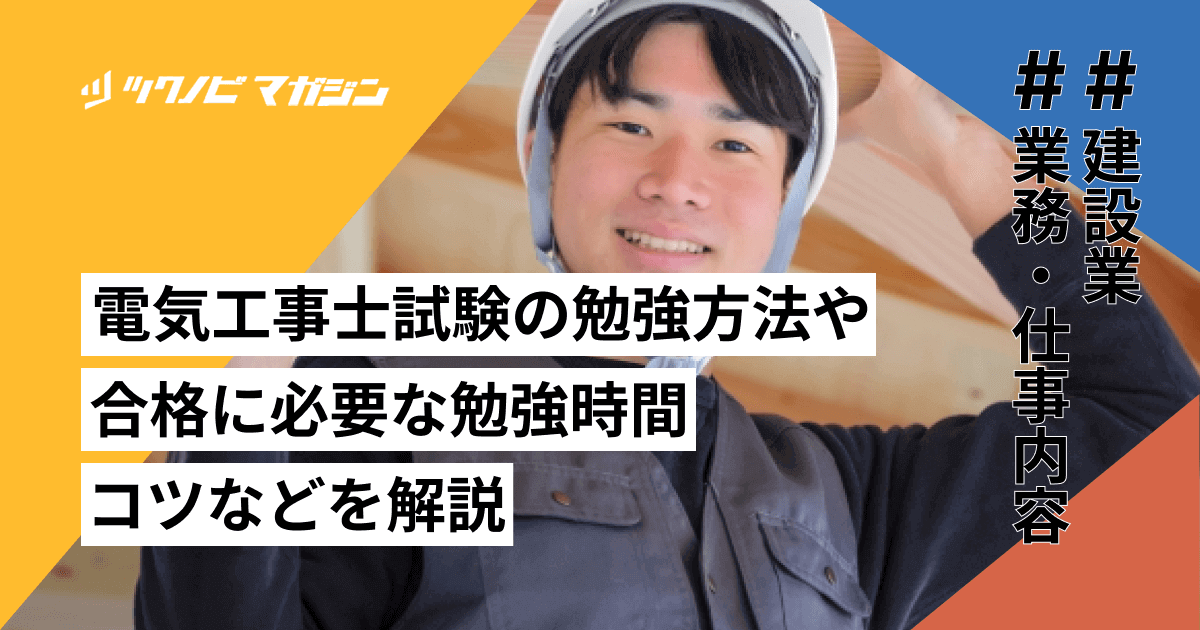※記事内に広告を含みます
建設業界において、工期遅れはしばしば発生する問題として挙げられます。施主と施工業者の双方にとって、避けたい課題の中でも特に重要なものの1つであると言えるでしょう。
工期遅れの原因は多岐にわたり、様々な要因が絡み合うため、遅延の責任がどこにあるのかを明確にすることが非常に重要です。
そこで、今回は工期遅れに関する基本的な知識に加え、工期遅れに伴うリスクとその回避策について具体的に紹介します。
工期遅れとは
工期遅れとはどのタイミングで遅れることをさすのでしょうか。はじめに、基本知識として工期の定義と工期遅れを判断するタイミングについて説明します。
工期の基本
工期とは、工事が開始されてから完了するまでの期間を言います。契約時や計画段階で具体的な日程が設定され、工事の開始日と終了日も含まれます。
例えば、「2025年4月1日着工、2026年12月31日竣工」のような形で明確に定められることが一般的です。
工期は契約における重要な条件の1つであり、各工程の期間を考慮しながら設定します。契約の締結前に、施主と施工業者が協議を行い双方が合意のうえで決定する必要があり、一方的に決められるものではありません。
工期は、資材の手配や人員の配置などを効率的に管理するうえで重要であり、コスト管理とも密接に関連しています。工事がスムーズに進められるように、プロジェクトの規模やリスクを考慮し、現実的なスケジュールを設定する必要があります。
一般的な工期遅れ
工期遅れとは、工事完了予定日までに工事が完了しない状態を言います。これは、プロジェクトが計画どおりに進んでいないことを意味し、引渡日までに建物や施設などの完成が間に合わない場合に発生します。
工期遅れの判断基準はプロジェクトの規模や内容によって異なりますが、一般的に「軽微な遅れ」「要調整の遅れ」「重大な遅れ」といった段階に分類されます。遅れの程度に応じて対応策や補償の範囲が変わるため、適切な管理と迅速な対応をしなければなりません。特に重大な遅れが発生した場合は、契約内容の見直しや損害賠償が伴う可能性があります。
工期遅れの責任と原因の所在
工事の進捗が予定より遅れると、追加費用の発生や契約トラブルにつながる可能性があります。しかし、工期遅れの責任が施工業者にあるとは限りませんので、まずはその原因がどこにあるのかを明確にしましょう。
ここからは、工期遅れの責任を「施工業者」「施主」「どちらにもない」という3パターンに分けて説明します。
施工業者に責任がある場合
施工業者の管理体制や業務遂行に問題がある場合、工期の遅延につながることがあります。特に「人手不足」と「人的ミス」は、施工業者側に責任が生じる代表的な原因です。
それぞれの要因について詳しく説明します。
人手不足が原因
施工業者が作業員を十分に確保できない場合、工事の進捗が遅れ、結果的に工期に影響を及ぼします。例えば、作業員の急な退職や病欠、繁忙期による人員不足などが重なると、予定通りの作業が困難になります。また、専門技術者の確保が難しく特定の工程が遅延するケースもあります。
さらに、施工管理者が不足すると、少数の施工管理者が複数の現場を担当することになり、1人当たりの業務が増えます。その結果、工程の進捗確認や資材調達、協力会社との調整が滞ることで工期の遅延リスクが高まります。
人的ミスが原因
現場での人的ミスも工期遅れの大きな要因です。
具体的なケースとして、施工手順の不徹底による効率の低下や修正作業の発生、現場での情報共有不足による指示の誤りなどがあり、これらが積み重なることで工期が遅延します。また、安全管理が徹底されていないことで事故が発生し、一時的に工事がストップすることもあります。
契約書には、こうした人的ミスによる工期遅れの責任を明確にする条項が設けられることが一般的です。施工業者が工期を遵守できなかった場合は、遅延損害金が発生し、損害賠償責任を負う可能性があります。
施主に責任と原因がある場合
施主の意思決定や資金面の問題が、工事進行に支障をきたす場合があります。特に、「工事の追加」と「工事代金の滞納」は、工期遅れを引き起こす主な原因の1つとして挙げられます。
それぞれについて詳しく説明します。
工事の追加
施主が工事内容の変更や追加工事を希望した場合、工期が延びることがあります。当初の契約に含まれていない追加工事は、資材の再手配や設計の修正が必要となるため、施工スケジュールに遅れが生じる原因となります。
変更内容によっては、役所への申請手続きが必要になることもあり、承認が下りるまで工事が進められないケースもあります。追加工事に関する契約書や見積書が作成されていない場合、後々報酬の支払いやその他のトラブルが発生し、工期遅れを引き起こすこともあります。
工事代金の滞納
建設工事の請負契約において、支払いのタイミングは契約内容や工事の規模によって異なりますが、一般的に「着工時の前払い(着手金)」「中間払い」「完成時の残金払い」があります。
着工時や中間時に工事代金の支払いが遅れると、資材の調達や作業員の確保が困難になり、工事に取り掛かれずに工期遅れが生じます。施主の資金計画が十分でない場合、途中で資金ショートを起こし、工事が一時停止することも考えられます。
施工業者・施主のどちらにも責任と原因がない場合
工期遅れは、必ずしも施工業者や施主の責任によるものとは限りません。
特に、施工現場の状況を大きく左右する自然災害や資材不足などによって、工事の進行が妨げられるケースがあります。こうした事態は予測が難しく、どちらの当事者にも直接的な責任を問えません。
これらの要因について説明します。
自然災害
自然災害が発生すると、台風や地震などによって施工現場で作業員の安全確保が難しくなることから、工事を続行できなくなる場合があります。施工済みの構造物に損害が発生した場合には復旧作業が必要になり、工期が延びる原因となります。
契約書には、自然災害による遅延について責任を問わない旨が記載されていることが一般的ですので、この条項によって施工業者は損害賠償を請求されることはありません。
資材不足
資材不足は外的要因によって引き起こされることが多く、施工業者・施主の管理能力や意図とは無関係に発生します。
需要の急増によって特定の資材が市場で不足し、これが原因で必要な資材が調達できず、工事が遅延することがあります。資材価格の高騰で調達計画が変更されるケースもあり、十分な在庫を確保できない場合もあります。
また、自然災害で資材供給元が被害を受けると、特定の地域で生産される木材や金属製品が不足し、必要な資材を手に入れられなくなる可能性もあります。
これらの要因で工期が遅れることはしばしばありますが、このような外的要因に対して責任が追及されることはありません。
工期遅れにより発生する責任
工期遅れは、契約上の重要な問題として施主と施工業者の双方に大きく影響します。工期遅れで施主が損害を被った場合、施工業者はその責任を負うことになります。契約内容によっては、損害賠償の支払い、追加費用の負担、さらには契約解除を受け入れなければならないケースもあります。
ここからは、それぞれの責任について詳しく説明します。
損害賠償を支払う責任
工期遅れによって施主に損害が生じた場合、施工業者は契約内容に基づいて損害賠償を支払う責任を負うことがあります。例えば、工事の完成が遅れたことで施主の業務開始が遅れたり、テナントが入居できずに賃料収入を得られなくなったりした場合、その損失額が損害賠償として請求される可能性があります。
ただし、遅延が不可抗力や施主側の指示によるものである場合には、この責任は基本的に免除されます。
損害賠償の計算方法
損害賠償の金額は、契約書や法令に基づいて算出されます。契約時に定められた遅延損害金の計算方法がある場合には、その方法が順守されます。
一般的に、遅延損害金は「請負代金×年率×遅延日数/365」で計算されます。
具体的な計算例は、以下のとおりです。
計算例:
工事請負代金が5,000万円、遅延日数が15日の場合(年率10%)
50,000,000 × 0.1 × (15 / 365) = 205,479円
なお、年率は標準約款の違約金10%で算出した金額です。
出典:国土交通省「民間建設工事標準請負契約約款 p27」
追加費用を支払う責任
工期遅れによって発生する追加費用の負担も、施工業者が責任を問われるケースの1つです。
例えば、遅延によって現場の維持管理費用が増加したり、追加の人件費が膨らんだりすることがあります。工程の遅れを取り戻すために夜間工事や休日作業を実施する場合、これにかかるコストも施工業者の負担となる可能性があります。
また、工期が延びることで重機や設備のレンタル費用、仮設物(仮囲いや足場など)の維持にかかる仮設費用も発生します。
契約解除の受け入れ責任
工期遅れが著しく、施主の業務に重大な支障を及ぼす場合、契約の解除を求められることがあります。契約書に「工期遅延が一定期間を超えた場合、施主は契約を解除できる」といった条項が含まれている場合、施工業者はこれを受け入れざるを得ません。
契約解除に至ると施工業者は多くの責任を負うことになりますが、民法634条2号に基づき出来高に応じた請負代金の請求ができます。しかし、未完成部分に対する損害賠償と相殺されることもあります。
出典:内閣府「民法の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 44 号) 新旧対照条文(抄) p4」
工期遅れによるリスクを軽減する方法
工期遅れは施工業者にとって大きなリスクとなるため、事前に適切な対策を行っておくことが不可欠です。
ここからは、リスクを最小限に抑えるための3つの方法について詳しく説明します。
不測の事態については文章に残す
不測の事態に備え、契約書や協議記録を文章として残しておくことが大切です。特に、自然災害、資材不足、施主からの設計変更など、施工業者の責任ではない事由による遅延については、契約時点で不可抗力条項を盛り込み後々のトラブルを防ぎます。
工事の進捗状況や発生した問題を定期的に文書化し施主と共有することで、万が一の際に責任の所在を明確にする証拠となります。変更指示や追加工事に関する合意内容の文書化も、誤解や紛争を回避することが可能です。
人員を確保する
工期遅れのリスクを軽減するためには、プロジェクト開始前に、必要な人員数や役割を明確にし、適切なタイミングで専門技術者や作業員を配置することで進捗を滞らせないようにします。
突発的な欠員や予期せぬトラブルに備え代替要員を確保しておくことで、作業の遅れを最小限に抑えられます。プロジェクトが長期に及ぶ場合には、作業員の定着率を高めるために労働環境を改善することも大事です。
保険を活用する
万が一の損害に備えて保険に加入することも選択肢の1つです。工事関連の保険に加入しておけば、資材や設備の損害、施工中の事故、さらには第三者への損害が発生した際の経済的負担を軽減できます。
ただし、保険ごとに補償範囲や条件は異なるため、プロジェクトに最適なものを慎重に選定する必要があります。契約内容を十分に確認し、想定されるリスクに対応できる保険を選ぶことをおすすめします。
建設業の業務効率化ならアウトソーシングサービスがおすすめ
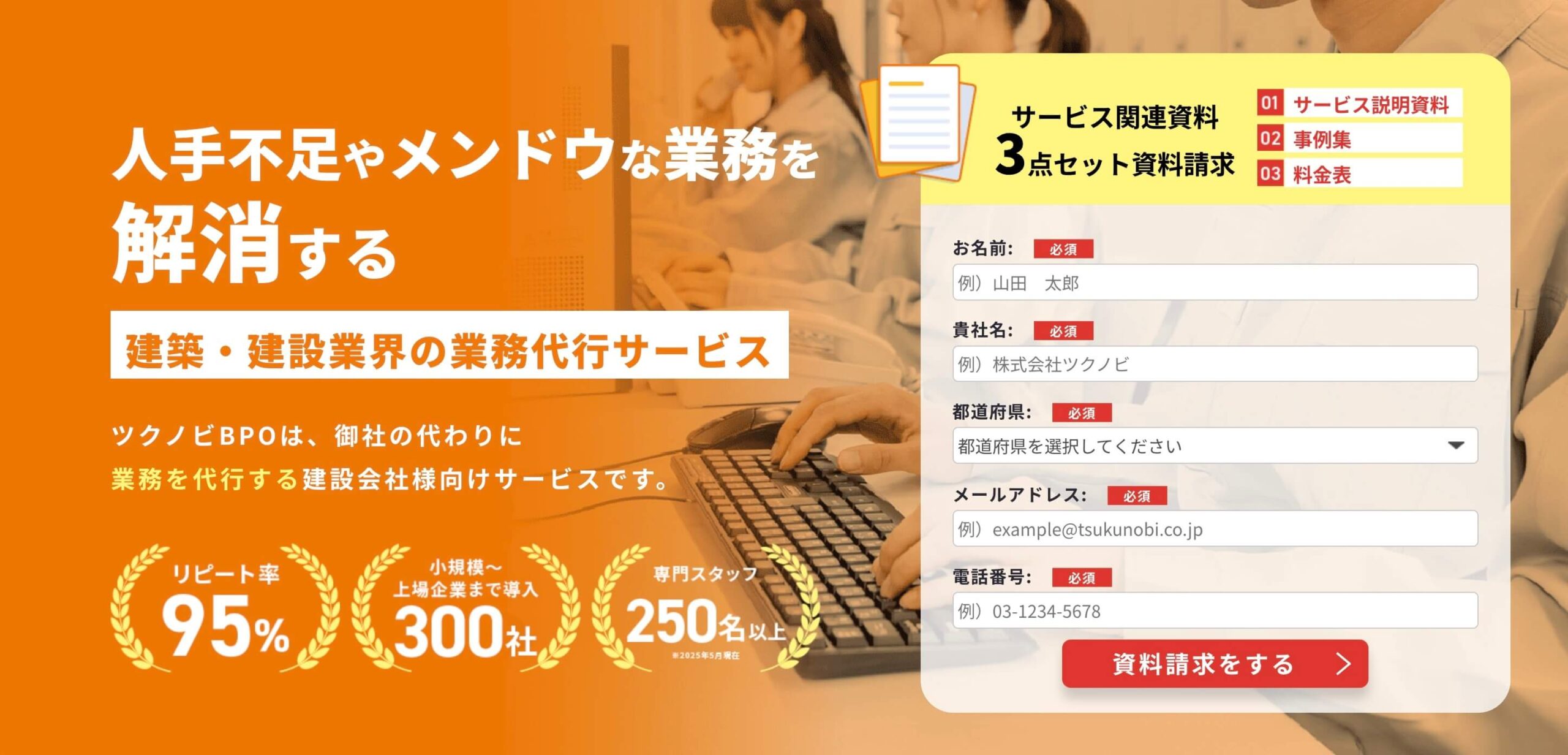
建設業で業務効率化を進めるには、アウトソーシングサービスの利用もおすすめです。従業員のリソースがひっ迫している場合や、業務に対応できる人材が不足している場合などは、アウトソーシングサービスを活用すると、少ない工数で業務を実行できます。
BPOサービスでは、専門的な知識を持っているスタッフが対応するため、さまざまな業務をスムーズに進められます。
弊社では、建設業の業務に対応している建設業特化のBPOサービス「ツクノビBPO」を提供しています。書類作成や図面の作成、積算業務など、幅広い業務を代行できます。ツクノビ事務では、倍率200倍の選りすぐりの専任スタッフが対応いたします。
業務を行うなかで作業効率が高い方法のご提案や業務マニュアル作成を行うため、業務効率の向上も図れます。
建設業業務の業務効率化でリソース不足を解消したい方は、ぜひこちらからお問い合わせください。
【まとめ】工期遅れは原因によって責任を負う側が異なる!速やかな情報共有が大切
工期遅れとは、工事が計画どおりに進まずにプロジェクトが遅延していることを言います。引渡日までに完成が間に合わないことで、その責任が追及されることになります。
工期遅れの責任は、その原因によって異なります。施工業者が原因となる場合、人手不足や人的ミスが影響することがありますが、施主による工事の追加や代金の滞納もまた遅延の原因となり得ます。さらに、自然災害や資材不足など両者に責任がない場合もあります。
工期遅れにより発生するリスクとしては、損害賠償や追加費用、契約解除などがあり、これらには明確な責任を伴います。そのため、不測の事態に備えて契約書の明記や適切な人員確保、保険の活用といった対策を行い、リスクを軽減することが重要です。
工期遅れを未然に防ぐために、情報共有を迅速に行い双方で綿密なコミュニケーションを取るようにしましょう。
公共工事の工期が間に合わない理由や工期延長の理由についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
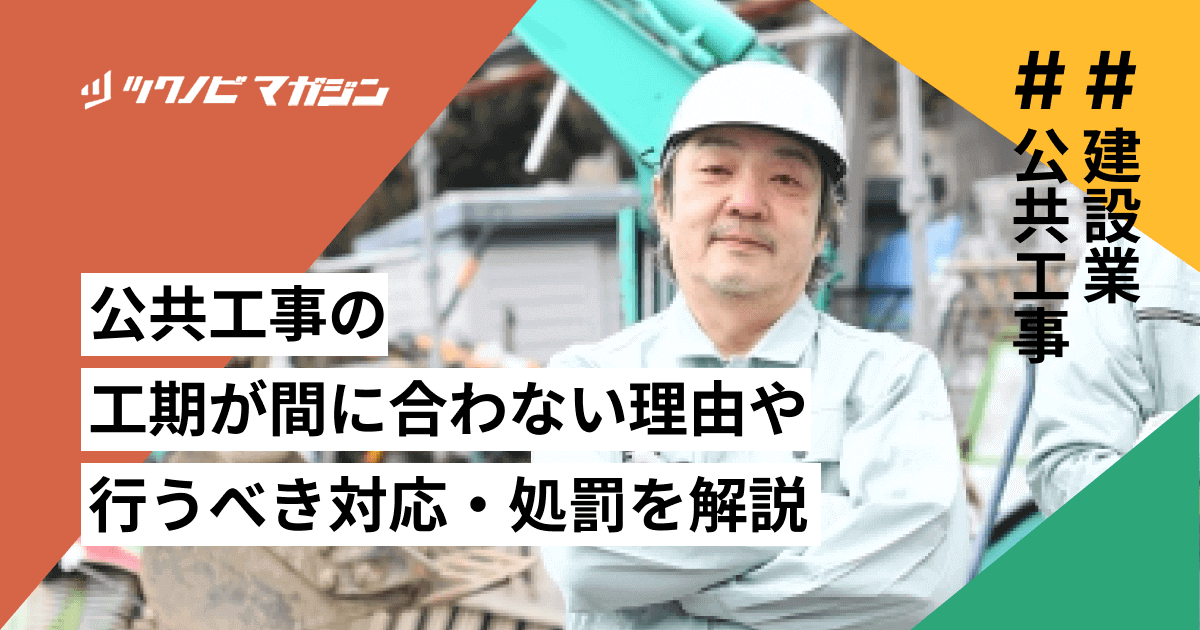 公共工事の工期が間に合わない4つの理由や取るべき対応・処罰を解説
公共工事の工期が間に合わない4つの理由や取るべき対応・処罰を解説
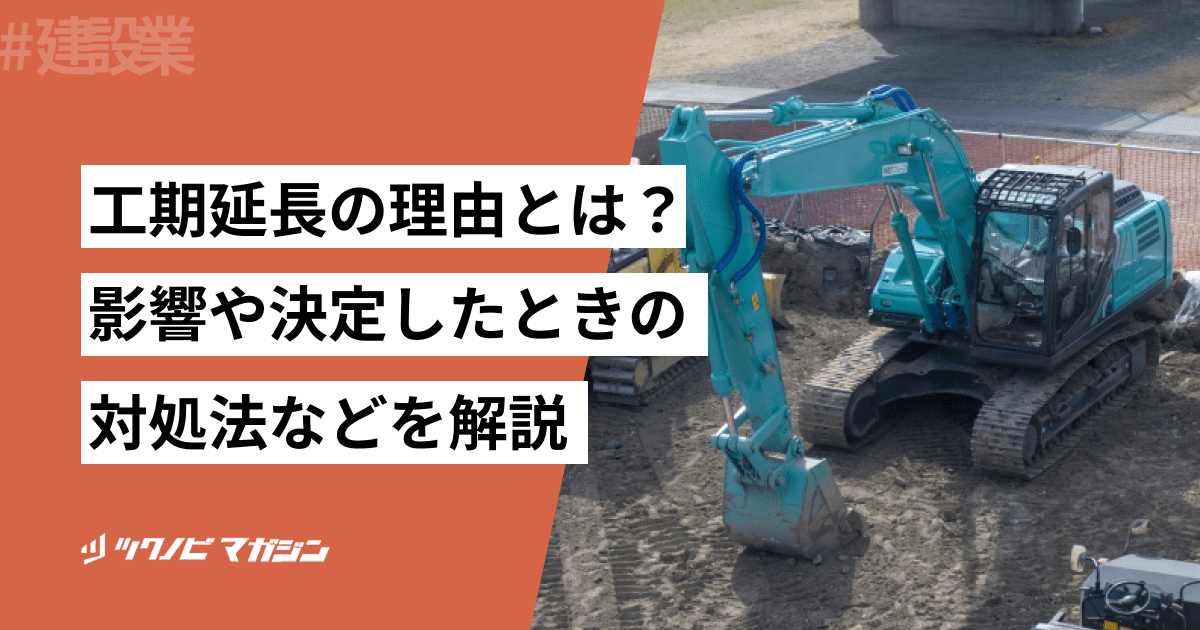 工期延長の理由とは?影響や決定したときの対処法などを解説
工期延長の理由とは?影響や決定したときの対処法などを解説