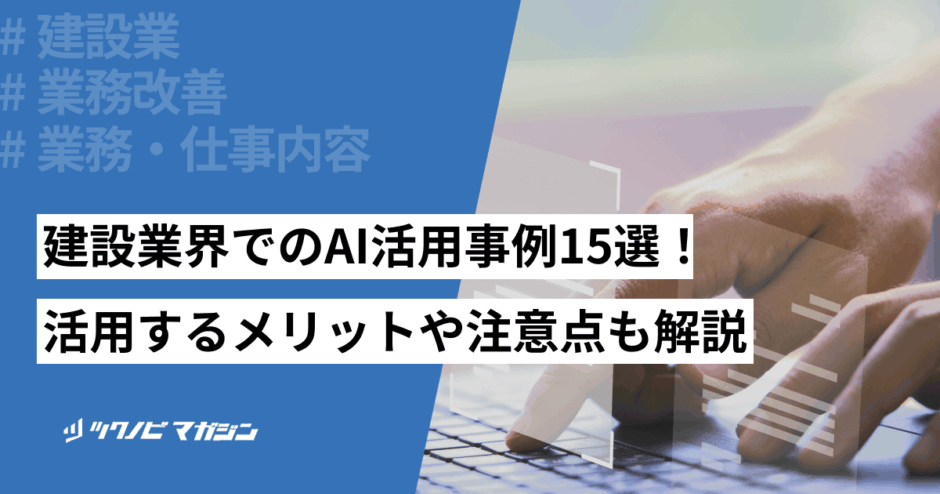※記事内に広告を含みます
昨今の日本では人口が毎年減少しているため、すべての業界で労働者不足の問題が深刻化しており、建設業界も例外なく該当しています。
政府は外国人労働者の規制緩和などにより労働力を確保する政策を実施していますが、問題の根本的な解決までには至っていません。
建設業界は「危険、汚い、きつい」という3Kの労働環境であるため、若い世代から魅力的に感じておらず建設業離れが起こっていることも人手不足の要因としてあります。
そのような中、建設業界でもAI技術を活用し今まで抱えていた課題解決に向けた取り組みが資金力のある企業を中心として活発になってきています。
また、工事現場でAI技術の活用をしたいけどよくわからない、導入に高額な費用も必要であるため事前に多くの事例を知りたいと悩んでいる担当者も多いのではないでしょうか。
今回は建設業界において抱えている課題解決のため、AI技術をすでに活用している企業の取り組みを15事例について紹介します。
AI技術を活用するためのメリットと注意点も記載していますので、ぜひ参考にしていただき自社へAIを導入するきっかけにしてください。
ツクノビAI研修は、AIの活用で業務を効率化する建設業特化の生成AI研修サービスです。御社の状況に合わせて最適なAI活用を支援いたします。
AIを活用して業務を効率化することで、時間外労働の削減、コスト削減につながります。詳細はぜひこちらからご確認ください。
建設業界の課題
近年において建設業界は様々な課題を抱えていますが、ここでは主に3つの課題について解説します。建設業の課題を把握することで、AIを活用する際のヒントとなるでしょう。
働き手が不足している
建設業界が抱える課題の1つ目は、業界内で働く人数が不足していることです。
国土交通省が発表した「建設業を巡る現状と課題」より、建設業就業者数は平成9年平均で685万人をピークとして減少の傾向にあります。
令和4年の平均で就業者数は479万人まで下がり、ピーク時から約30%も減少してしまいました。
また、建設業の働き手が不足する原因は、人口減少の中、さらに若年層において建設業を希望する人が少ないためです。
年代別の建設業就業者の割合において、55歳以上が35.9%を占める一方、29歳以下はたった11.7%しか就業していません。
そのため、人手不足によっておこる建築工程の遅延や、技術の継承者が不足することによる品質の低下が大きな問題となっています。
働く時間が長い
年間の総実労働時間が他業界よりも大幅に長いことも、建設業界が長い期間ずっと向きあってきた課題です。
国土交通省が作成した「産業別年間実労働時間」の表によれば、令和3年度において建設業は他業界と比べ年間で90時間も長いことがわかっています。
そして、年間の実労働時間の減少幅を20 年前と比較しても、建設業は50時間しか減少しておらず、全業界の減少幅である90時間との差は明確です。
建設業界の働く時間が長くなる理由のほとんどは工事現場でのトラブルなどによる建築工程の遅延に対応するためです。
実際、4週6休程度しか休めない方が多く、他業種では常識と考えられている週休2日の勤務体系が業界として機能していません。
ケガや事故などのリスクがある
3つ目に解説する建設業の課題は、作業中に起こるケガや事故などのリスクが他の業種より高いということです。
実は、建設業における死亡事故は昭和44年の2492人から比べると、約50年間で大幅に減少し令和3年では288人となります。
また、建設業の休業4日以上の死傷災害の発生件数も下がっており、現場におけるケガや事故などのリスクは昭和時代から減っていることは間違いありません。
ただ、令和3年において、全産業の死亡災害の件数(867人)から建設業の件数(288人)を割合でみると33%も占めており、全産業の中でもっとも高い数値です。
建設業界の死亡災害は、絶対数としては確実に減少しているものの、他の業界と比べるとまだまだ死亡災害の高い産業であることがいえるでしょう。
この事実も建設業で働くリスクと認識されているので、より安全かつ安心して働ける現場の労働環境へ改善する必要があります。
参考:建設業における安全衛生をめぐる現状について|厚生労働省 国土交通省
建設業界でのAI活用事例15選
建設業界の課題を解決するべく、15の企業が取り組んでいるAI活用の事例を紹介します。
それぞれの事例を参考にしていただきまして、ぜひ、AI技術の導入によって自社の悩みや課題の解決に向けて役立ててください。
鹿島建設株式会社
鹿島建設株式会社はAI inside株式会社と共同開発して、新しい資機材管理システムを導入しました。
この新しい資機材管理システムは、AI技術とドローンの組み合わせによるシステムです。
ドローンが空から撮影した動画をAIが分析し3Dモデルに表示することで、資機材管理業務にかかる時間の削減に成功しています。
システムの成果は、約2時間を要していた業務をたった30分で終わらせ、時間の削減率はなんと約75%です。
また、ドローンを導入しているため、高所や狭所などに出向くことがなく、労働環境の改善にも効果があります。
大成建設株式会社
自動運転する建設機械(以下、自動建機)を、複数台まとめて協調運転を制御するシステム「T-iCraft」を開発したのが、大成建設株式会社になります。
「T-iCraft」の役割は、自動で作業しているそれぞれの建機の位置や工事の進捗を監視しながら、自動建機を制御し協調運転することです。
また、国が「国土強靭化に関する施策のデジタル化」の中で掲げている無人化施工技術を向上させ、建設機械の自律運転、走行技術の確立にも貢献しています。
清水建設株式会社
AI技術を活用しガス圧接継手の外観検査システムをNTTコムウェア株式会社と共同開発しトライアル導入したのは、清水建設株式会社です。
このシステムは、検査員が目視にておこなっていた目視検査を、スマートフォンなどで撮影した鉄筋継手の画像を画像認識AIによって検査します。
鉄筋継手の目視検査では1カ所につき5分程度かかっていましたが、画像認識AIによる検査ではたった20秒から30秒で完了し効率的に検査をおこなえます。
また、専用アプリに鉄筋サイズを事前に入力し、継手部を撮影するだけで検査ができるという使い勝手の良さも注目されているAI技術です。
株式会社竹中工務店
株式会社竹中工務店が開発したAI技術は、ドローンを利用して外壁タイルの浮きや欠けを判定する「スマートタイルセイバー」です。
法律上、外壁タイルは竣工した10年後の時点で浮きや欠けの有無を必ず調査しなければなりません。
これまで実施していた外壁タイルの打診検査や赤外線検査では、時間と費用がかかる上、高所作業のため危険性も高く効率的ではありませんでした。
スマートタイルセイバーは、ドローンを使用しているため高所や人が入りにくい場所でも安全に調査が可能です。
また、赤外線にて調査した結果をAIが判定するため、人によって調査結果のばらつきが生じにくく、品質の改善も見込めます。
株式会社大林組
スマートビルマネジメントシステムである「WellnessBOX」を開発した企業は株式会社大林組です。
「WellnessBOX」はIoT、AI技術を活用しオフィスや病院などで働く人にとってより快適で健康的な職場環境にするためのシステムになります。
また、職場環境を改善することで、人口減少で働き手が不足している中でも優れた人材の確保や、従業員の生産性を向上させることが目的です。
このシステムはIoT技術を活用し、建物の各設備で集めた建物利用者一人ひとりが感じる快適性や位置情報、建物内外の情報などをクラウドへ集約させます。
集約した情報はAI技術を用いて分析し、従業員のそれぞれが最も快適と感じる職場環境の提供を実現しました。
株式会社安藤・間
株式会社安藤・間は、建設業特化大規模言語モデル「AKARI Construction LLM」を開発中です。
ChatGPTなどの従来のLMMはテキストを送信しサービスを利用するため、使用方法によっては自社の重要な情報が学習に利用される恐れがありました。
「AKARI Construction LLM」を活用すれば、AI学習において自社で培ったノウハウや顧客データの情報漏洩リスクを押さえつつ業務への利用が可能になります。
株式会社小松製作所
現場の人材不足問題をかかえる土木・建設業界を救うために、株式会社小松製作所が取り組んでいることがICT建機などによるスマートコンストラクションです。
スマートコンストラクションは、建設プロセスにおけるすべてのデータをICTで有機的に繋ぐことで、効率的で生産性の高い現場を目指しています。
また、今まで時間と労力を費やしてきた現場検査や、建機に自動運転機能を付けるなどをデジタル化すれば、人材不足の状況の中でも施工品質の確保ができます。
東洋建設株式会社
東洋建設株式会社は富士通株式会社とともに「AI Loading Navi」というAI技術を活用して土運船への積み込みの管理を支援するシステムの開発に成功しています。
「AI Loading Navi」はグラブ浚渫中に撮影した土砂・水面・壁の画像をリアルタイムにAI処理し識別した後、自動判断で積込位置の状態をオペレーターに伝える支援システムです。
このシステムを導入したことで、確認作業にかかる時間を短縮し、積込作業の待機時間の削減が可能になりました。
また、オペレーターと情報共有によって、現場への指示が的確になり、作業員の業務効率の向上、危険エリアへ行く回数も減るため職場の安全性が高まります。
ギリア株式会社
AI技術によってプラント保全に関する業務の生産性を向上させ、点検品質を高いレベルで平準化することを実現している企業がギリア株式会社です。
ギリア株式会社は、プラント配管の腐食点検を自動化するシステムにおいて数多くの導入実績があります。
この技術は、錆こぶや板金の欠損、保温材の露出など、配管に関わる様々な異常を高精度で検出可能です。
AI技術による統一したチェックや検出ができるため、作業員それぞれの経験則によるばらついた判断とならないメリットがあります。
西松建設株式会社
西松建設株式会社は、物価変動の影響を見込んだ適正な建設コストを算出するため、経済予測AIプラットフォームサービス「xenoBrain」を導入しました。
「xenoBrain」の魅力は、企業実績、業界市場規模、万単位の統計データなど、おおくの経済情報の予測を提供できる点です。
AIによる予測が必ず当たるとは言えませんが、AI技術により数多くのデータベースから導き出されるため、人が予測するよりも当たる確率が高くなります。
「xenoBrain」が導いた予測により建材上昇を見越した金額設定や、価格が上昇する前の発注など建設コスト適正化に向けた判断材料としても大いに活用できます。
株式会社 fantasista
「造成くんベータ版」というAIアプリケーションを株式会社 fantasistaの不動産DX事業部は株式会社AVILENの支援を受け開発に成功しました。
造成くんは、土地情報を入力するだけで、搭載されたAI技術によって最適な区画割り、造成に伴う土量、造成工事費の概算を短時間で提示できるシステムです。
今までは外部の専門業者に頼るため時間も費用も掛かっていましたが、「造成くんベータ版」の開発によりたった20秒で業務が完了します。
用地購入に対する意思決定や造成工事の概算費用など事業を成功させるための採算をいち早くイメージでき、ライバル会社より進んだ対応が可能です。
オングリットホールディングス株式会社
橋梁点検調書の作成における作業効率を上げるため、オングリットホールディングス株式会社は「マルッと図面化」というAI画像システムを開発しました。
「マルッと図面化」は、打音点検でチョーキングした写真画像をアップロードするだけで、説明用の損傷図をCADデータ化します。
全国の橋梁数はおおよそ70万橋もあり、その中で建設後50年に達する橋梁の数は2013年で約71,000橋でしたが、2033年にはなんと約267,000橋と予測されてます。
今後、調査が必要な橋梁の数は増え続けるため、従業員の作業について生産性の効率化は急務な課題です。
「マルッと図面化」のシステムを導入すれば、手間のかかるCAD作成業務への負担軽減を実現し人材不足の解消にも繋がる期待があります。
株式会社CONOC
株式会社CONOCは、2021年にAI技術を活用したCONOC業務管理クラウドをリリースしました。
CONOC業務管理クラウドは、過去の見積データを機械学習することで、即時に一定レベルの見積を提示できるAI見積もりシステムです。
2023年には約300社以上の建設関係の企業が導入した実績があります。
また、工事見積もり作成の業務を属人化できるため、今までかかっていた人材コストを大幅に削減できます。
株式会社アドバンスト・メディア
会議で必要となる議事録作成のAI化を実現したのが、株式会社アドバンスト・メディアのAI議事録作成システム「VoXT One(ボクストワン)」になります。
「VoXT One(ボクストワン)」は、AI音声認識AmiVoiceを搭載した「ScribeAssist」と「ProVoXT」を一元化し、利用者が使いやすい設定に対応ができるシステムです。
さらに、GPTー4oや音声入力ソリューションなど多彩な機能を活用し、手間がかかっていた議事録の作成業務の効率化に貢献しています。
株式会社FRONTEO
建設現場における安全性を高めるため、株式会社FRONTEOは危険予知運動を支援するAIシステムを開発しました。
そのAIシステムの名称は、KIBIT WordSonar for AccidentViewといい、なんと40万件以上の事故事例を機械学習し、現場における危険予知運動を支援します。
想定可能なリスクの検知から予測がつきにくい事故発生の可能性も提示できる機能が搭載されています。
建設業における労働災害の発生を抑制し安全で安心できる工事現場の実現に向け、これからもシステムの導入が増え続けるのではないしょうか。
建設業界にAIを導入するメリット
様々な建設会社がAI技術を利用したシステムを積極的に現場へ導入する理由は、建設業界が抱えている問題を解決できるメリットがあるためです。
建設業界においてAIを導入するメリットを3つ解説していきます。
人手不足の解消につながる
建設業界にAI技術を導入することで、少子化による人口減少、現場技術者の高齢化による工事現場における人手不足の問題を解消するメリットがあります。
現場で今まで人が実施してきた単純作業はAI技術を活用することで、作業時間の短縮が可能です。
1つひとつの作業について効率があがるため、技術者ひとりで対応できる工事範囲が広くなり人手不足の解消に繋がります。
様々な工事にAI技術が搭載されたシステムを導入すれば、現場での過酷な労働環境も改善され、建設業に若い人材があつまることも期待できます。
ベテラン職人の技術継承がしやすくなる
AIを活用してベテラン職人の動きを映像解析すれば、その技術を容易に再現できるようになります。映像解析から得られたデータを教材として蓄積・活用することで、ベテラン職人が引退したあとでも新人作業員の育成に役立ちます。
建設業界では、若者の不足が深刻化しており、ベテラン職人の技術やノウハウの継承が難しい状況です。そのため、引退前に、どのように技術やノウハウを次世代へ引き継ぐかが課題となっています。
しかし、AIを活用してベテラン職人の技術やノウハウを新人の育成教材にすることで、次世代への技術継承がしやすくなるでしょう。
事故などを未然に防げる
AIに今までに工事中に起きてしまった事故の事例を学ばせれば、事前に危険予知するため現場において事故が再発することを未然に防げます。
危険な場所の作業も技術者が工事するのではなく、ロボットやドローンを使えば事故が発生する確率を大幅に下げられます。
また、建設業で発生する事故は、墜落や転落、機械の倒壊、工具の誤操作による大ケガなどがあり、人生が一変するような重大な事故が多いのも事実です。
AI技術を活用し過去の事例から事故の発生が高い危険な作業を予測し対策すれば、技術者にとって安心で安全な現場環境となります。
品質の確保・改善が期待できる
建設業にAI技術を導入するメリットの4つ目は、現場での作業に安定した品質の確保や改善が期待できることです。
人による現場作業はベテランと若手の技術者によるスキルの違いや、意図しないヒューマンエラーによって品質にばらつきが出ます。
また、病気、ケガや精神の不調などによる体調面の良し悪しが、作業の精度に影響を及ぼしかねません。
AIによる現場での作業は求めるレベルの品質を確保したり、安定した品質へ改善したりが可能です。
ただし、AIによる作業でもエラーが完全になくせませんし、学習している情報にない作業は対応が困難になります。
単純な作業箇所はAIに任せ、技術者は複雑であったり重要であったりする作業箇所に集中するような作業を分担することが理想です。
コスト削減につながる
AIを活用することで、建設資材を効率的に利用でき、コスト削減につながります。AIは過去の膨大なデータを分析して、建設プロジェクトに必要な材料を適切に判断します。
さらに、市場価格の変動などを分析することで、将来的な単価予測も可能です。AIの導入により、建設プロジェクトに必要な資材の無駄を減らせるため、コストの最適化を図れます。
また、最適な作業工程の立案による工期短縮によって、少人数でもプロジェクトをスムーズに進められるため、人件費の削減も可能です。
建設業界で活躍するAI技術
建設業においてAI技術が搭載されたシステムは開発されているもの複数あり、現場に導入した上で一定の成果を上げています。
現在、建設業界ですでに活躍している代表的なAI技術を紹介します。
BIM/CIM
BIMとはBuilding Information Modelingの頭文字をとった略名で、建築物におけるすべての情報を3Dモデルを用いて一元で管理・共有できるシステムです。
建物が建つ前の敷地条件の調査結果から基本設計、実施設計、現場施工、そして、完工後の維持管理や更新まですべての過程において情報が集約できます。
施工管理の業務では、BIMの導入は建築物を3Dモデルとして可視化できるため、図面情報の素早い理解に効果的です。
二次元の図面では見落としてしまうような工事個所も、3Dイメージにて漏れが少なく品質の向上も見込めます。
CIMとはConstruction Information Modelingの頭文字をとった略語です。
BIMは建物工事である一方、CIMは道路、橋、電力などといった土木工事に特化したシステムになります。
IoT
IoTは、Internet of Thingsの頭文字をとった略語となり、建設業にも導入されている代表的なAI技術の1つです。
IoTの仕組みは、「モノ」に組み込まれたセンサーで、「モノ」自体がインターネットを繋げ、「モノ」の相互間においてそれぞれの情報を共有するシステムです。
建設業では現場を効率的に管理するために導入しており、資材や機器の管理や工事の進捗状況の把握などで活用されてます。
インターネット上でリアルタイムに様々な情報が共有できるため、現場管理におけるリモート化ができるでしょう。
現場監督が工事しているエリアに出向く回数も減り、生産効率の向上、時間管理の改善、工事費用の削減に効果があるAI技術です。
ロボット・ドローン
AI技術によるロボットやドローンなども建設現場において生産性を上げるため導入され、たいへん活躍しています。
それぞれの工程における作業用のロボットも開発、検証、改善と技術が進歩していますので、工事現場においてますます実用が増えてくるでしょう。
また、建設業のイメージである「危険・汚い・きつい」と言われる作業をロボットが代行する事例も増え、業界の労働環境のイメージ改善にも繋がっています。
また、ドローンにおいても、人が立ち入り危険な土地における空からの測量や、高層建物のメンテナンス時の調査などに対して大きな成果があります。
建設業界でAIを活用する際の注意点
建設業の課題の多くを解決できるAI技術ですが、導入する際に気をつけるべきポイントがあります。
それは「AIが提供する情報の真偽がわからない」と「現場でしかわからない情報もたくさんある」ということです。
AIによって提供される情報は多くのデータから導き出されるため高精度でありますが、その情報をそのまま信じることはとても危険な判断になります。
元のデータが間違っていたり不足していたりする場合、AIは私たちに誤った情報を提供してしまいます。
Web上の情報が常に最新であるとは言えませんし、各行政が独自に設定した法令がすべてアップされているとは限りません。
AI技術を活用して情報を収集する場合においても、技術者による情報の再確は実施する必要があります。
建設業界でAIを活用する今後の可能性
建設業界では、さらにAIの活用が広がると考えられています。すでに、建築デザインでは過去のデータをもとに、条件に合う設計案を自動で生成する事例が見られます。今後はAIを活用したソフトウェアの導入が一層進むでしょう。
また、工程管理ではリアルタイムで進捗や品質を監視できます。問題が発生した際は、原因や対策の分析に加え、スケジュールの自動修正も可能です。
さらに、ドローンで撮影した赤外線画像から外観の検査を行うなど、AIの活用の幅がより広がることが期待されています。
建設業の人手不足解消ならツクノビBPOがおすすめ
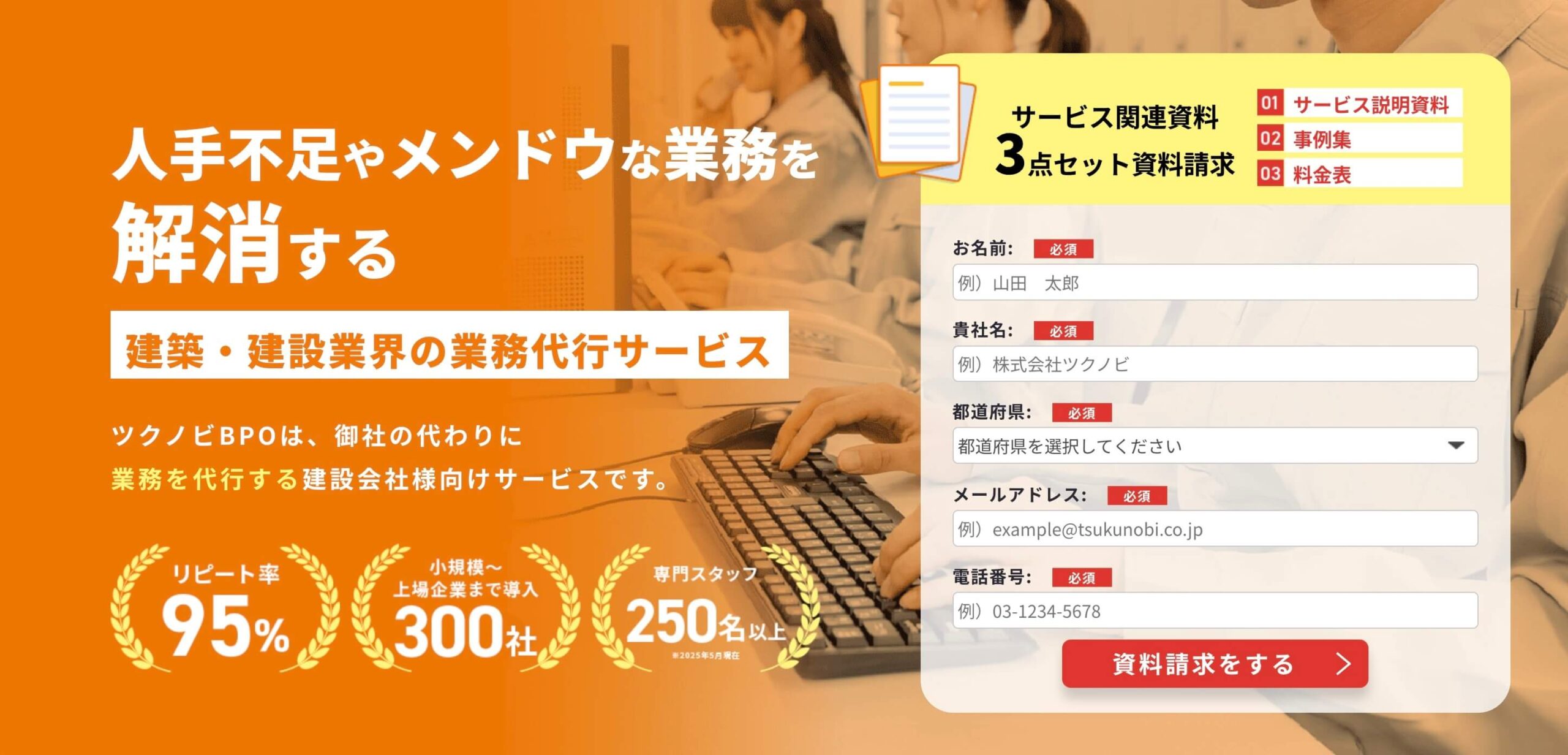
建設業の人手不足を解消するためには、アウトソーシングサービスの利用もおすすめです。
従業員のリソースがひっ迫している場合や、業務に対応できる人材が不足している場合などは、アウトソーシングサービスを活用すると、少ない工数で業務を実行できます。BPOサービスでは、専門的な知識を持っているスタッフが対応するため、さまざまな業務をスムーズに進められます。
弊社では、建設業の業務に対応している建設業特化のBPOサービス「ツクノビBPO」を提供しています。書類作成や図面の作成、積算業務など、幅広い業務を代行できます。ツクノビBPOでは、倍率200倍の選りすぐりの専任スタッフが対応いたします。
リソース不足を解消したい方は、ぜひこちらからお問い合わせください。
【まとめ】建設業界でのAI活用事例を参考に自社の課題を解決に取り組もう!
建設業のAI活用事例で様々な企業が業界の課題に対し、AI技術を駆使して解決に向けた取り組みをしていることが理解していただけたましたでしょうか。
AI技術の産業自体がまだまだ未成熟の業界でもあるため、技術発展は止まりません。
建設現場に導入されたAI技術が搭載されたシステムは、その効果を検証するとともにシステムの改善が繰り返されており進歩しています。
そして、今後の日本は人口減少の流れが止まる気配がなく、性能の高い多くのAI技術によって現場の単純作業や施工監理することが当たり前となるでしょう。
ぜひ、自社が悩んでいる課題をAI技術によって取り組み、安心・安全な労働環境を整えた生産性の高い現場を実現してください。
建設業における労務管理のAI活用方法や建設業界における生成AIの活用事例・建設業のAI導入事例についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
 建設業における労務管理のAI活用方法やメリットなどを解説!
建設業における労務管理のAI活用方法やメリットなどを解説!
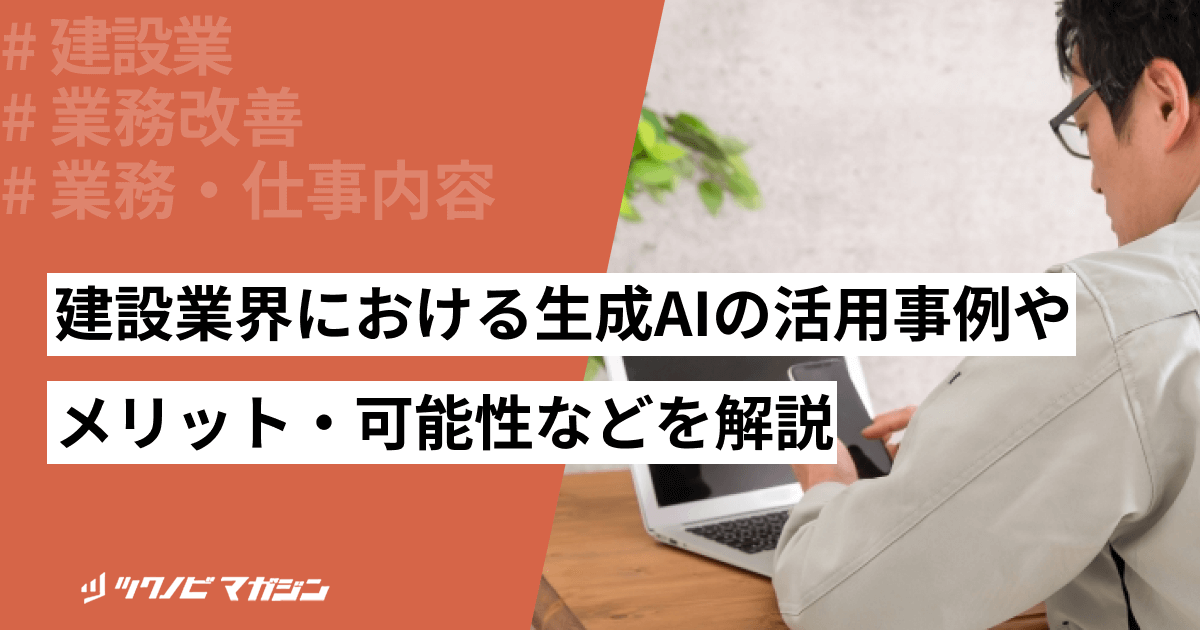 建設業界における生成AIの活用事例やメリット・可能性などを解説
建設業界における生成AIの活用事例やメリット・可能性などを解説
 建設業のAI導入事例やメリット・今後の可能性などを解説!
建設業のAI導入事例やメリット・今後の可能性などを解説!
建設業の事務作業にAIを活用する方法や建設業の書類作成にAIを活用する方法する方法についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
 建設業の事務作業にAIを活用する方法やメリットを解説!事例も紹介
建設業の事務作業にAIを活用する方法やメリットを解説!事例も紹介
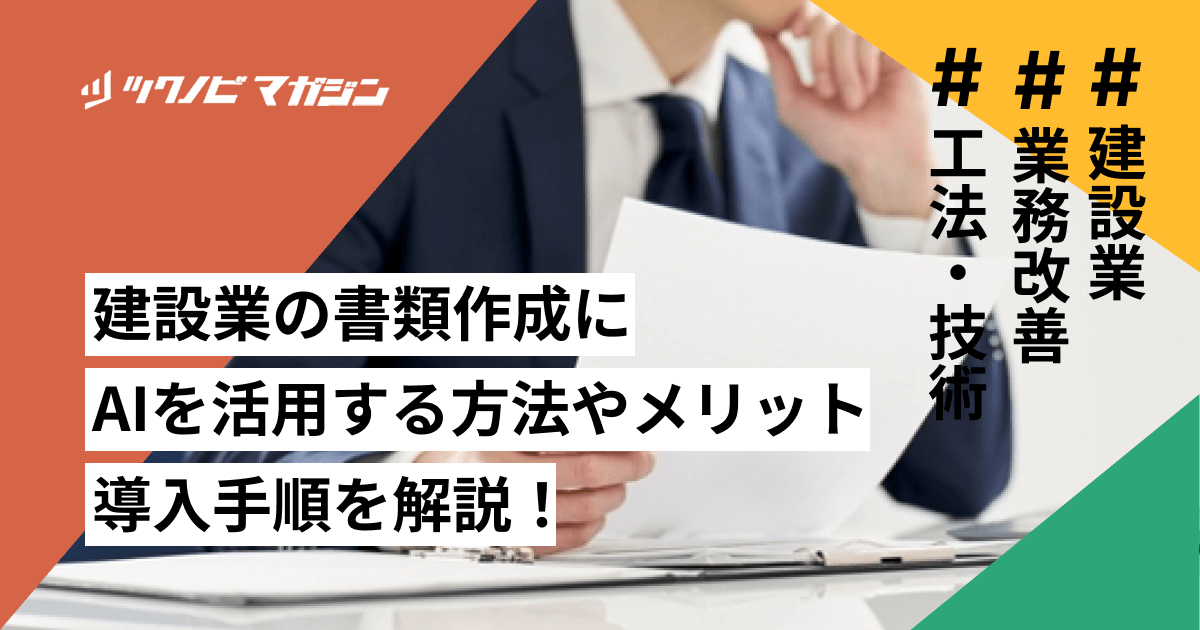 建設業の書類作成にAIを活用する方法やメリット・導入手順を解説!
建設業の書類作成にAIを活用する方法やメリット・導入手順を解説!