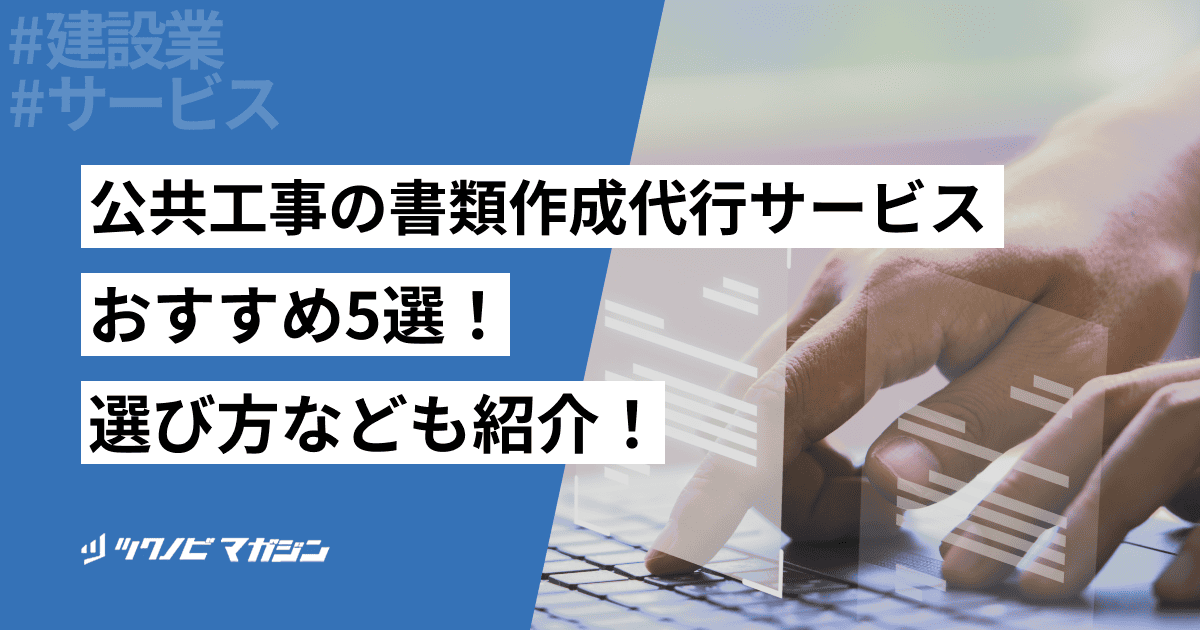※記事内に広告を含みます
多くの業者が関わる工事では特に「施工体制台帳」が重要です。施工体制台帳を適切に作成・管理することで、工事の品質や作業者の安全を守れます。
記入方法や項目を十分に把握し、漏れやミスのないように作成することが大切です。本記事では、施工体制台帳の作成目的、必要な工事、各記入項目の詳細、記入の注意点などを解説します。
施工体制台帳とは
工事の体制に関連する情報をまとめた台帳を「施工体制台帳」と呼びます。工事に参加する元請業者と下請業者の構造や関係性、作業員の保険加入の有無や雇用関係といった情報などが詳細に記載されています。
建設業法によって作成するよう義務づけられた、重要な書類です。施工体制台帳の作成目的、必要な工事、作成者、保存期間を以下で解説します。
施工体制台帳の作成目的
施工体制台帳を作成する目的に、工事現場の体制を十分に把握することが挙げられます。元請業者が施工体制を把握することで、施工品質や現場の安全を保ち、工期の遅れを減らせるでしょう。
予期せぬトラブルが発生しても、工事業者や作業員の情報を把握していれば、迅速に対応できます。また、施工体制の管理によって、建設業法違反である一括下請負や不適格業者の参入も防げるでしょう。
施工体制台帳の作成者
発注者から建設工事を直接的に請け負った建設業者(元請業者)が施工体制台帳を作成します。施工体制台帳には、元請業者が直接契約した一次下請業者だけでなく、二次以下の下請業者を網羅して記載しなければなりません。
ただし、発注者から特別な要望がない限り、資材業者、警備業者、運搬業者といった関連業者の情報の記載は不要です。
施工管理台帳との違い
施工管理台帳との違いは、記載内容と利用場面が大きく異なることです。
施工体制台帳は元請と下請の組織体制を示す書類で、一次下請までの会社情報や現場責任者、配置技術者など「誰が工事に関わるか」を明確にします。公共工事では提出が義務であり、発注者が適切な体制で工事が行われているかを確認する目的があります。
施工管理台帳は品質や安全、工程などの管理内容をまとめた書類で、工事をどのように進めたかを記録するものです。写真や検査記録、工程表など実務の管理状況を整理するため、現場での運営に直結する書類です。
施工体制台帳は「体制の証明」、施工管理台帳は「管理の記録」という役割を持ち、どちらも工事を適切に進めるためには欠かせません。
施工体制台帳の作成が必要な工事
施工体制台帳の作成が必要な工事には、条件があります。公共工事と民間工事によって、その条件は異なります。施工体制台帳の作成が必要な工事について、きちんと理解しておくと安心です。
公共工事
施工体制台帳の作成が必要な公共工事の条件は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条によって定められています。
「公共工事発注者から2015年4月1日以降に直接建設工事を請け負った建設業者が当該工事に関して下請契約を締結した場合」です。
公共工事の場合、施工体制台帳を発注者に提出することも必要です。発注者へ提出する施工体制台帳は「写し」で問題ありません。
民間工事
施工体制台帳の作成が必要な民間工事の条件は、建設業法第24条の8にて定められています。
「発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が当該工事に関して締結した下請金額の総額が、5,000万円(建築一式工事の場合8,000万円)以上となる場合」です。
また、民間工事の場合、施工体制台帳を発注者に提出する義務はありません。しかし、発注者から請求された際は、閲覧できるようにしておく必要があります。
施工体制台帳を作成する重要性
施工体制台帳は、施工品質や現場の安全を確保するため、作成・管理が義務付けられている重要な書類です。
しかし、作成する必要性は理解しているものの、作成にかかる時間と労力を十分に注げない場合もあるでしょう。実際、どの程度の建設業者が施工体制台帳を作成しているか、気になる現場管理担当者の方もいるのではないでしょうか。
また、施工体制台帳を作成しない場合は、どのようなリスクがあるのでしょうか。ここでは、施工体制台帳を作成する重要性を解説します。
施工体制台帳の作成状況
国土交通省の調査によると、2024年における施工体制台帳の作成状況は92.6%でした。これは、前年の2023年(91.9%)と比較しても高い水準で施工体制台帳の作成義務が遵守されており、作成義務が建設業界に浸透していることが伺えます。
施工体制台帳の作成率が高い水準を維持している背景としては、行政の指導や周知が継続的に行われていることが考えられます。今後も適切な作成・管理が求められるでしょう。
参考:令和6年度下請取引等実態調査の結果について|国土交通省
施工体制台帳を作成しない場合のリスク
施工体制台帳を作成しない場合や事実に反する情報を記載した場合は、建設業法違反となり、以下のような罰則を受ける可能性があります。
- 監督行政庁からの指示処分
- 営業停止命令
- 入札資格の制限
- 刑事罰
施工体制台帳を作成しないことや事実と異なる情報を記載することは、重大な違反行為です。厳しい処分だけではなく、企業の信頼や経営に関わります。
施工体制台帳は、現場の管理だけでなく、法令遵守や企業信用といった観点からも重要な書類です。作成しない場合や事実に反する情報を記載するリスクを理解し、正しい施工体制台帳を作成しましょう。
施工体制台帳の作成義務についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
施工体制台帳の左側部分の書き方
![]()
施工体制台帳に定められた様式はありませんが、記載すべき項目は法令で決められています。実際の項目ごとに施工体制台帳の記載内容を解説します。
作成日
作成日は施工体制台帳の左側上部に記載する日付で、台帳をいつ作成したかを示す項目です。契約日や工事開始日とは意味が異なり、実際に台帳を整えた日を記入する点が大切です。
また、後から確認した際に作成のタイミングが分かるよう工事ごとに日付を残しておきましょう。保存や保管の管理基準にもなるため、修正日とは明確に区別する必要があります。
会社名・事業者ID/事業所名・現場ID
![]()
会社名・事業者ID、事業所名、現場IDは施工体制台帳の基本情報であり、正確に記載する必要があります。
会社名は元請と下請の正式名称を記入し、事業者IDは建設業許可やCCUSで管理される識別番号を用いると発注者が事業者を特定しやすくなります。事業所名は工事を担当する拠点を示し、本社と異なる場合は必ず明記しましょう。
また、工事を行う現場名も正式名称で記入し、CCUS加入企業は現場IDも併記します。これらの情報は工事体制の透明性を高め、適切な管理が行われているかを発注者が確認するための重要な項目です。
建設業の許可
元請業者が有している建設業の許可をすべて記入してください。業種、許可番号、許可年月日それぞれを記入しましょう。特定建設業許可と一般建設業許可に分けて記入します。
工事名称及び工事内容
![]()
請け負った工事の名称、内容を記入します。工事内容として、建造物の構造、延べ面積、数量などを記入してください。
発注者名及び住所
発注者の名称および住所を記入します。
工期
発注者と締結した契約に基づいて、工期を記入します。工事開始日を「自」の欄に、工事終了日を「至」の欄に記入してください。
契約日
契約日は元請と発注者、または下請間で工事請負契約を結んだ日を記載します。
施工体制台帳の作成日とは異なり、契約が正式に成立したタイミングを示す重要な項目です。また、工期や契約内容の確認にも関わるため契約書に記載された日付をそのまま正確に記入します。
不一致があると確認作業に支障が出るため、注意が必要です。
契約営業所
元請業者に支店や営業所がある場合、工事現場の近隣の支店・営業所が施工を担当するケースがあります。
支店・営業所が施工する場合、形式上、本部と支店・営業所が下請契約を結びます。契約営業所欄に、本部(元請)と支店・営業所(下請)の関係を記入してください。
【例】
元請契約:○○株式会社本社
下請契約:○○建設株式会社中部支社
発注者の監督員名/権限及び意見申出方法
![]()
発注者が定めた監督員の氏名を記入します。契約時に定めた権限と意見申出方法も記入してください。
権限及び意見申出方法欄には、「契約書記載のとおり」、「契約書第○条記載の内容」などと記入します。具体的な内容を記入しなくても構いません。
監督員名/権限及び意見申出方法
発注者ではなく、元請業者側の監督員の氏名を記入してください。権限及び意見申出方法欄には、「契約書記載のとおり」、「契約書第○条記載の内容」などと記入します。
現場代理人名/権限及び意見申出方法
元請会社側が選任した現場代理人の氏名を記入します。権限及び意見申出方法欄には、「契約書記載のとおり」、「契約書第○条記載の内容」などと記入します。
監理技術者/主任技術者名
![]()
監理技術者または主任技術者の氏名を記入してください。建設業許可を有する業者が工事をする際、主任技術者を配置しなければなりません。
発注者が直接請け負った特定建設業者が、下請契約の合計金額が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる場合、主任技術者ではなく監理技術者を配置する必要があります。
資格内容
資格内容には、現場に配置する技術者が保有する資格名を正確に記載します。
例えば、1級・2級施工管理技士や工種ごとに必要な資格など、工事内容に応じた資格を明示します。また、資格は配置技術者の適格性を示す重要な情報であり、発注者が必ず確認する項目です。
資格名と区分、取得状況を誤りなく記入することが欠かせません。
監理技術者補佐名/資格内容
![]()
監理技術者補佐の氏名と有する資格を記入します。監理技術者が複数の現場を兼任するならば、監理技術者補佐を配置してください。
専門技術者名/資格内容/担当工事内容
専門技術者の氏名、有する資格、担当工事の内容を記入します。自社で施工する専門工事がある場合、主任技術者の資格を有する専門技術者を配置しなければなりません。
現場ごと、担当する業種ごとに配置が必要です。専門技術者を確保・配置できない場合、附帯工事の建設業許可を受けた業者に施工を請け負ってもらう必要があります。
ただし、附帯工事が500万円未満の軽微な工事である場合は、専門技術者を配置することは不要です。
一号特定技能外国人の従事状況(有無)
一号特定技能外国人が工事に従事しているかどうかを記入してください。一号特定技能とは、特定産業分野に関する知識や技能を持つ外国人向けの在留資格です。
外国人技能実習生の従事状況(有無)
外国人技能実習生が工事に従事しているかどうかを記入します。
保険加入の有無
![]()
健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入状況を記入します。各保険について「加入」、「未加入」、「適用除外」の中から選択することが一般的です。
健康保険、厚生年金保険の欄には事業所整理記号と整理番号を記入します。雇用保険の欄には労働保険番号を記入します。
事業所整理記号等
事業所整理記号等は、企業内部で現場や事業所を識別するための管理番号を記載する欄です。
社会保険や労働保険の手続きで使う整理番号を示す場合もあり、事業所ごとの情報を正しく区分する目的があります。また、発注者が事業所を特定しやすくなるため社内で使用している正式な番号を記入します。
他の記号と混同しないよう、正確に記載しましょう。
施工体制台帳の下請負人に関する事項の書き方
下請負人に関する事項欄には、一次請負業者の情報を記入してください。元請業者と一次請負業者が締結した契約内容に基づいて記入します。下請負人に関する事項欄に特有の記入項目は以下のとおりです。
- 安全衛生責任者名
一次下請業者が選んだ安全衛生責任者の氏名を記入します。 - 安全衛生推進者名
現場従事者の安全と衛生を維持する安全衛生推進者の氏名を記入します。 - 雇用管理責任者名
現場の労務管理を担当する雇用管理責任者の氏名を記入します。
施工体制台帳の書き方や安全書類の共通マニュアル・書き方についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
施工体制台帳を効率よく作成する方法
施工体制台帳を効率よく作成するには、作業を標準化し手間を減らす工夫が大切です。フォーマットの活用や、作成に慣れた担当者や専門業者への外注は大幅な時短につながります。
ここでは、施工体制台帳を効率よく作成する方法について、詳しく解説します。
フォーマットを活用する
施工体制台帳を効率よく作成する方法は、既定のフォーマットを活用することが効果的です。
フォーマットは記入欄が整理されているため、必要な情報を漏れなくまとめやすくなります。また、国土交通省や自治体が公開する書式を使えば公共工事で求められる項目をそのまま反映でき、確認作業の手間も抑えられます。
社内で共通フォーマットを用意しておくと、担当者が変わっても一定の品質で作成でき、属人化も防ぎやすくなります。
さらに、Excel版やクラウド型のテンプレートを利用すると過去の台帳を複製して更新するだけで作成できるため、複数現場を抱える企業でも効率よく作業を進められます。
このように、フォーマットの活用は、時短と正確性の両方を実現しやすい方法です。
作成経験を持っている人に外注する
施工体制台帳を効率よく作成する方法として、作成経験を持つ専門家へ外注することも有効です。
施工体制台帳は元請と下請の構成や配置技術者の資格、社会保険の加入状況など多くの情報を正確に整理する必要があります。初めて担当する場合は時間がかかりやすく記載漏れや形式の誤りも起こりやすいため注意が必要です。
経験者へ外注すれば、必要な情報をヒアリングしたうえで適切な様式に沿って迅速に作成してもらえます。公共工事で求められる基準にも対応しやすく、提出期限が迫っている場合も準備を進めやすくなります。
また、繁忙期や担当者不在時のサポートとしても活用でき、社内の負担を抑える手段としても効果的です。
建設業の安全書類作成代行サービスや施工体制台帳の作成を外注するメリットについてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
施工計画書をスムーズに作成したいなら作成代行がおすすめ
施工計画書の作成に対応できる人材が不足している場合には、施工計画書の作成経験が豊富なプロ人材を活用することがおすすめです。
建設業特化の施工計画書作成代行サービス「施工計画書作成代行byツクノビ事務」は、建設業の経験が豊富なプロ人材が御社の業務を代行するサービスです。施工計画書、仮設計画図の作成や図面作成など、御社が必要としている業務を代行可能で、これまでにさまざまな企業の施工計画書作成実績があります。
経験豊富なプロ人材が業務を代行するため、業務依頼と業務実施のやりとりがスムーズに進むでしょう。自社での新規採用をすることなく、業務を進められることで、書類作成や付随業務対応までのタイムラグの短縮や対応できる人材を採用できないリスクの軽減につながります。
業務の品質を上げたい方やこれまで対応できなかった業務にも対応していきたい方、作業効率を上げたい方などはぜひこちらから詳細をご確認ください。
施工体制台帳の注意点
施工体制台帳の準備や作成、保管する際は様々な注意が必要です。施工体制台帳に関する注意点を把握しておくことで、スムーズに作成や管理を行えるでしょう。ここでは、施工体制台帳に関する注意点について解説します。
法令遵守を徹底する
施工体制台帳を作成する際は、法令遵守を徹底する必要があります。前述したとおり、使用する様式に決まりはありません。しかし、記載項目は建設業法施行規則により定められています。
自社で様式を用意する際は、記載項目をよく確認するなど、法令遵守を徹底することが大切です。
また、公共工事の場合は、発注者からの指示に応じて追加項目を記載しましょう。
記入漏れがないか確認する
施工体制台帳の記載項目は、すべて正確に記入する必要があります。建設業法施行規則で定められた記載項目に記入漏れや不備があった場合、発注者から指摘を受ける可能性があります。
最悪の場合は営業停止処分や入札資格の制限など、厳しい罰則が科される場合もあるため、十分に注意が必要です。
施工体制台帳を作成する際は、正確な情報を漏れなく記入することを心がけましょう。
添付書類のつけ忘れに注意する
施工体制台帳を提出する際は、添付書類のつけ忘れに注意しましょう。施工体制台帳は、本紙に加え、前述した添付書類で構成されています。提出する前に添付書類をつけ忘れていないか、しっかり確認しましょう。事前にチェック項目をまとめておくのがおすすめです。
また、発注先にてチェックリストがある場合、チェックリストに沿って確認するのもよいでしょう。特に、元請業者は、下請業者が作成した書類にも注意を払う必要があります。書類内容に抜けや漏れ、添付書類のつけ忘れがないかなど、しっかり確認しましょう。
施工体制台帳に必要な添付書類
施工体制台帳には、作成する書類に加えて必要な添付書類があります。施工体制台帳に必要な添付書類は、以下のとおりです。
- 工事担当技術者台帳
- 発注者との契約書の写し
- 下請負人との契約書の写し(注文・請書及び基本契約書又は基本契約約款等の写し)
- 配置技術者(監理技術者等)が資格を有することを証する書面(専任を要する監理技術者の場合、監理技術者証の写しに限る)
- 配置技術者(監理技術者等)が資格を有することを証する書面(専任を要する監理技術者の場合、監理技術者証の写しに限る)
- 専門技術者等を置いた場合は資格を証明できるものの写し(国家資格等の技術検定合格証明等の写し)
- 配置技術者(監理技術者等)の雇用関係を証明できるものの写し(健康保険証等の写し)
- 再下請通知書(二次以下の下請業者がいる場合)
- 再下請業者との契約書の写し
また、どの書類も大事な個人情報・企業情報なので、情報漏洩のないよう取り扱いに注意しましょう。情報が漏洩すると、関係業者が不利益を被るだけでなく、自社の信頼が失われる恐れもあります。
保存期間を遵守する
前述のとおり、施工体制台帳は5年間の保存期間が定められています。その期間は施工体制台帳を適切に保管しなければなりません。保存期間が経過する前に、誤って破棄しないよう注意しましょう。
また、関係者が必要に応じて閲覧できるよう、わかりやすい場所に保管する必要があります。現場事務所や社内共有フォルダなど、手近な場所を選びましょう。
施工体制台帳は電子データでの保存が可能です。管理の手間や紛失のリスクを防止するため、デジタル化を活用するなど、スムーズに保存・管理を行いましょう。
最新情報に更新する
施工体制台帳は、常に最新の情報に更新する必要があります。工事の進行に伴い、下請負人や技能者が変更した場合、施工体制台帳を更新しなければなりません。更新が遅れた場合、施工体制台帳の信頼性が失われ、法律違反になる可能性があります。
そのため、現場の状況に合わせてすべての変更を遅れることなく反映させましょう。また、更新作業は正確に行う必要があります。記載されている情報に誤りがあると、現場に混乱を招く可能性があるためです。
効率的に更新できるシステムを導入するなど、自社に合う方法で負担を軽減しながら、慎重に確認作業を行いましょう。
【まとめ】施工体制台帳は特定の工事に関する情報をまとめた書類!正確に作成しよう
施工体制台帳の作成目的、必要な工事、各記入項目の詳細、記入の注意点などを解説しました。工事の遅れやトラブル、不適格業者の参入などを防ぐためにも、施工体制台帳を適切に作成・管理することが大切です。
記入漏れや記入ミスだけでなく、添付書類のつけ忘れにも注意しましょう。個人情報や他社の機密情報を扱うので、情報漏洩対策も重要です。ぜひ本記事を参考に、正確な施工体制台帳を作成し、工事の適切な管理を実現しましょう。
安全書類の作成がめんどくさい理由についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
※弊社の営業代行サービスであるツクノビセールスでは、
【効果が出なければ全額返金プラン】を新たにスタートさせました!
![]()
※詳しくは👆👆👆のバナーをクリック!!